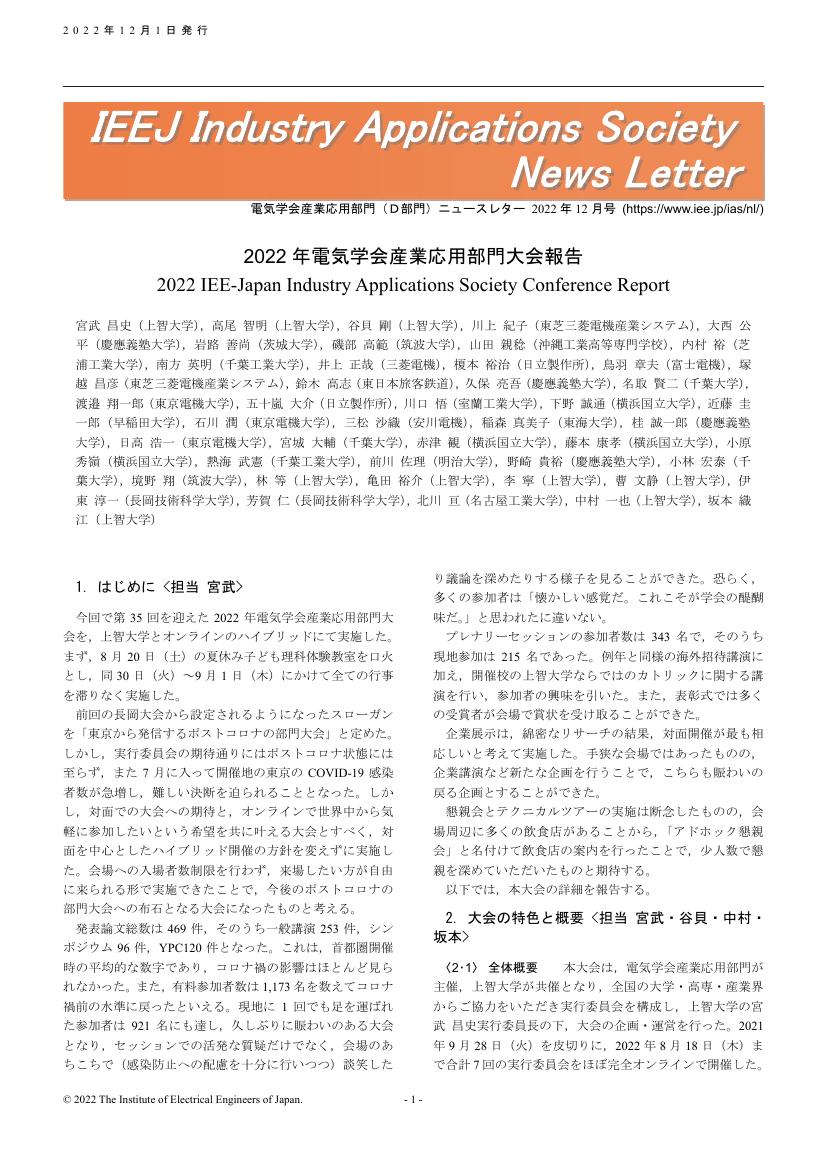4 0 0 0 OA 地球化学的・鉱物学的調査から推定した倶多楽火山登別地熱地域の熱水系
- 著者
- 高橋 良 鈴木 隆広 大森 一人
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 火山 (ISSN:04534360)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.4, pp.453-469, 2022-12-31 (Released:2023-01-30)
- 参考文献数
- 49
In active geothermal areas, subsurface high-temperature thermal waters occasionally cause phreatic (hydrothermal) eruptions without any direct input of mass and energy from magma. So, understanding subsurface hydrothermal systems is critical to improving mitigation strategies for such hazards. The Noboribetsu geothermal area in Kuttara volcano, southwestern Hokkaido, has had repeated phreatic eruptions through the Holocene. In this study, to reveal the hydrothermal system beneath this geothermal area, we investigate (1) the chemical and isotopic compositions of thermal waters and fumarolic gases and (2) the characteristics of hydrothermally altered rocks in phreatic ejecta and around thermal water discharge areas. The chemical and isotopic features of the thermal waters indicate that the hydrothermal activity in this area is attributable to a deep thermal water with a Cl concentration of approximately 12,000 mg/L and a temperature>220 °C. The hydrothermally altered pyroclastic rocks in the phreatic ejecta often include vesicles filled with smectite, chlorite, and Ca-zeolite, implying that a low-permeability clay cap consisting of these minerals exists in the subsurface and impedes the ascent of the deep thermal water. The deep thermal water ascends partly to the shallow subsurface, causing separation of the vapor phase containing CO2 and H2S due to boiling, and the liquid phase discharges as neutral NaCl-type waters. In addition, absorption of the separated vapor phase by groundwater, with oxidation of H2S, leads to the formation of steam-heated acid-sulfate waters, which cause acid leaching and alunite precipitation in the shallow subsurface. The Hiyoriyama fumaroles are derived from the vapor separated from the deep thermal water at 140 °C. Phreatic (hydrothermal) eruptions in the Noboribetsu geothermal area are assumed to have occurred due to rapid formation of a vapor phase caused by a sudden pressure drop of the deep thermal water. Because such eruptions are likely to occur in this area in the future, we should perform efficient monitoring using the constructed model of the hydrothermal system.
4 0 0 0 OA 集中治療における日本独自治療の国内認可試験
- 著者
- 小尾口 邦彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.163-169, 2023-05-01 (Released:2023-05-01)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 1
日本の集中治療領域では国際的に承認されていない独自の薬剤や医療機器があり,時にガラパゴス化と呼ばれる。2000年以後に認可された独自治療の国内認可試験と公開審査議事録を検討した。シベレスタットは,国内第Ⅲ相試験で有効性を示せなかったが,追加の単 一群試験の人工呼吸器離脱日数が最初の第Ⅲ相試験やARDS network試験を上回り,認可された。シベレスタットの国際試験は,中間解析の180日死亡率において対照群よりも劣ったため,早期中止された。トロンボモジュリンは国内第Ⅲ相試験のDIC離脱率においてヘパリンに対して非劣性を示し,認可された。トロンボモジュリンは,国際試験の28日死亡率において対照群に対して優位性を示せず,海外において認可されていない。AN69ST膜を用いた血液濾過器は,敗血症を対象として単一群試験が行われ,28日生存率がAPACHEⅡスコアによる予測生存率に比して著しく高かったため,敗血症の保険適用を得た。日本の医薬品や医療機器の臨床試験において,死亡率よりも代用指標や単一群試験結果が重視されて認可されることがある。
4 0 0 0 OA 車室内のTVOC値と“におい”および健康リスクに関する考察
- 著者
- 達 晃一
- 出版者
- 公益社団法人におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.9-15, 2019-01-25 (Released:2021-11-03)
- 参考文献数
- 14
健康志向の高まりを受けて,近年では空気質への関心も高くなってきている.住宅屋内で発生する揮発性有機化合物(以下VOCと呼ぶ)は,建材や材料などの対策が進み,対策前と比較して大幅に改善されている.自動車においても,住宅同様に,内装材や,車室内に使用されている材料の対策が進み,車室内VOC濃度は低減している.しかし,車室内環境は,住宅環境よりも容積が小さく,温度も高くなるため空気質環境としては厳しい環境となっている.そこで,空気質の指標となっている総揮発性有機化合物(以下TVOCと呼ぶ)と“におい”に着目して車室内空気質に対する評価法の考察を行った.
4 0 0 0 OA 多精巣症の1例
- 著者
- 水流 輝彦 影山 進 成田 充弘 岡田 裕作
- 出版者
- 一般社団法人 日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科学会雑誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.6, pp.738-741, 2010 (Released:2012-03-16)
- 参考文献数
- 11
28歳,男性.左陰嚢内無痛性小腫瘤を主訴に受診.身体所見では左精巣上体尾部に無痛性腫瘤を触知し,精巣・精管は正常であった.超音波検査にて精巣実質と等信号の内部均一な径16mmの球状の腫瘤を認めた.左精巣上体腫瘍の診断で陰嚢切開を行った.腫瘍は精巣上体尾部近傍に位置し,精巣白膜のような白い膜で覆われていた.術中迅速標本では悪性変化を認めない精巣組織であり,多精巣症と診断された.精巣上体,精管との交通がなかったため余剰精巣は摘除された. 多精巣症は比較的まれな先天奇形であり,文献的には海外も含めると100例以上の報告がある.余剰精巣の手術摘除の適応に関しては一定の見解はない.陰嚢内に余剰精巣が存在する場合は術中の生検所見で異形成を認めた際は摘除が推奨される.余剰精巣が温存された際は慎重に定期的な診察と超音波検査が必要である.しかし,陰嚢外に存在する余剰精巣は悪性化の危険性が高くなるため摘除が必要である.
4 0 0 0 OA 幼児期における運動能力の性差
- 著者
- 久保 温子 平尾 文 入部 健次郎 松林 宏美
- 出版者
- 公益社団法人 佐賀県理学療法士会
- 雑誌
- 理学療法さが (ISSN:21889325)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.31-34, 2015-02-28 (Released:2020-05-01)
- 参考文献数
- 20
4 0 0 0 OA 二重性を設える -セルトーの日常的実践論からゴフマンの共在研究へ-
- 著者
- 草柳 千早
- 出版者
- 早稲田大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 早稲田大学大学院文学研究科紀要 (ISSN:24327344)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, pp.109-123, 2023-03-15
4 0 0 0 OA 2022年電気学会産業応用部門大会報告
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌D(産業応用部門誌) (ISSN:09136339)
- 巻号頁・発行日
- vol.142, no.12, pp.NL12_1-NL12_10, 2022-12-01 (Released:2022-12-01)
4 0 0 0 OA スポーツにおけるイップスのアセスメント・症状・対処
- 著者
- 柄木田 健太 田中 美吏 稲田 愛子
- 出版者
- 日本スポーツ心理学会
- 雑誌
- スポーツ心理学研究 (ISSN:03887014)
- 巻号頁・発行日
- pp.2021-2103, (Released:2021-11-13)
- 参考文献数
- 73
Many athletes suffer from yips, which is defined as “a psycho-neuromuscular movement disorder, which affects sports in which fine motor precision skills (Clarke et al., 2015, p. 156).” Yips is one reason for significant performance decrements in sports. Several case studies, surveys, and experimental studies have been conducted to clarify this phenomenon. These studies can increase the understanding of yips and help athletes, coaches, and practitioners improve this problem during practice and competitions. Therefore, we reviewed 62 articles published from 1981 to 2021 reporting assessment, symptoms, and treatments of yips in sports. As a result, we identified four types of assessments: (1) self-assessments, (2) observations by others, (3) kinematic and physiological assessments using motion capture and electromyography, and (4) responding to assessment scales. The studies were also categorized in terms of symptoms, as psychological (e.g., anxiety, attention, and personality) and physio-behavioral (e.g., kinematics, muscular activity, and brain activity). The studies on yips treatment could be classified into imagery techniques, pharmacotherapy, and other psychological skills. Furthermore, specific studies indicated post-traumatic psychological growth through yips experiences. The implications of these studies for future research on yips are discussed based on this review.
4 0 0 0 OA 日本における『うつ』の医療化 北中淳子 著『うつの医療人類学』(日本評論社、2014年)
- 著者
- 山田 陽子
- 出版者
- 日本保健医療社会学会
- 雑誌
- 保健医療社会学論集 (ISSN:13430203)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.82-91, 2017-07-31 (Released:2019-02-26)
- 参考文献数
- 4
4 0 0 0 OA 妊娠期の葉酸サプリメント摂取と児の喘息発症リスクとの関連
- 著者
- 金高 有里 小林 道 土肥 聡 荻原 重俊
- 出版者
- 一般社団法人 日本DOHaD学会
- 雑誌
- DOHaD研究 (ISSN:21872562)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.69-75, 2021 (Released:2021-12-02)
【目的】我が国では、胎児の神経管閉鎖障害のリスク低減のために、妊娠を計画している女性、妊娠の可能性がある女性及び妊娠初期の妊婦は、通常の食品から摂取する葉酸以外に、サプリメントや食品中に添加される葉酸(狭義の葉酸)を400 ㎍/日摂取することが望ましいとされている。受胎期に重要な葉酸サプリメントの摂取が普及する一方で、海外において母親の葉酸過剰摂取による児の喘息発症のリスクが報告されている。そこで本研究では日本における妊娠期の葉酸サプリメントの摂取と児の喘息発症リスクとの関連を検討した。 【方法】2014年7月から8月に、北海道札幌市、石狩市の計17か所の保育所に通う児童の保護者589人を対象に、児の性別と月齢、児の喘息の有無と発作頻度、児のRSウイルス罹患状況、両親の喘息の有無と発作頻度、両親の喫煙歴、妊娠前および妊娠20週まで(妊娠前半期)と 21 週以降(妊娠後半期)のサプリメントによる葉酸摂取状況について自記式質問紙調査を行った。解析対象は、児の性別、児の月齢、喘息の有無、妊娠期の葉酸サプリメント摂取の有無について欠損が無かった305人(51.8%)とした。 【結果】多重ロジスティック回帰分析の結果、葉酸サプリメント非摂取群と比較した摂取群の喘息有症の調整オッズ比は、4.54(95%CI: 1.20-17.30)であった。 【考察】本研究では、妊娠期の葉酸サプリメント摂取と喘息の罹患に正の関連が見られた。妊娠期に葉酸サプリメント摂取が無かった群と比較して、葉酸サプリメントを摂取していた群で喘息の有症率が高かった。葉酸摂取を否定するものではないが、本研究の結果から、葉酸サプリメントの摂取は、児の喘息発症のリスクであることが示された。
4 0 0 0 OA イソヒヨドリのハビタットとその空間構造―内陸都市への進出―
- 著者
- 鳥居 憲親 江崎 保男
- 出版者
- 公益財団法人 山階鳥類研究所
- 雑誌
- 山階鳥類学雑誌 (ISSN:13485032)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.15-24, 2014-09-30 (Released:2016-09-30)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1 2
イソヒヨドリは,国内ではもともと,崖や岩のある海岸に生息し繁殖するが,近年になって内陸の都市での繁殖が確認されるようになった。そこで,2011年5月から2012年12月までの20ヶ月間,海岸から20 km離れた内陸部に位置する兵庫県三田市のニュータウンでセンサスと行動観察を行なった。本種は調査地に周年生息する留鳥であったが,特に高層建築物が密集する地区に多く出現し,オスのなわばりもこの地区に偏って存在していた。オスは高い場所において高確率でさえずり,隣接オスとのなわばり闘争においては,隣接者よりも高い場所でさえずろうとした。イソヒヨドリのオスは高層建築物をソングポストとして利用し,高い位置からさえずることによって,なわばりの形成と防衛を行なっていると考えられる。また,本種は高層建築物に隣接した草地の地表面で,地表性の小動物をとっていた。したがって,都市においては高層建築物と草地のセットこそが,イソヒヨドリの好適なハビタットを形成しており,本種のハビタットに必要な空間構造は,高さを生み出す崖地形と,これに隣接し地表性動物が豊富に存在するオープングラウンドのセットであることが示唆される。また,人が創り出した崖地形としての高層建築物と芝生などのオープングラウンドのセットを巧みに利用することにより,本種は都市への進出を果たしたのだと考えられる。
4 0 0 0 OA 自由意志と神経科学—リベットによる実験とそのさまざまな解釈—
- 著者
- 鈴木 秀憲
- 出版者
- 科学基礎論学会
- 雑誌
- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.27-42, 2012-09-30 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 41
In 1980s, Benjamin Libet and his colleagues conducted a series of experiments on voluntary acts. Its result is that certain brain potential (RP) precedes conscious will, which has excited much discussion about the existence and nature of free will. This paper shows that this result admits various interpretations about RP, conscious will, and their relation, depending on philosophical assumptions concerning free will and the relation between mind and brain. I also argue that the process of deliberation, rather than the momentary decision, should be the focus of investigation in order to elucidate the role of conscious will and the nature of free will.
4 0 0 0 OA 科学教育研究における科学的な研究方法論に関する一考察
- 著者
- 齊藤 智樹 熊野 善介
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.9, pp.51-56, 2015 (Released:2018-04-07)
- 参考文献数
- 19
著者らは,科学教育研究における科学的な研究方法論についての研究の手始めとして,NRC(National Research Council, 2002)が示した科学的原則や研究デザイン(計画)の原則を示し,それがいわゆる自然科学と何ら変わらないことを示した.同様に,混合研究法(Creswell・Plano Clark, 2007)にまつわる哲学から,量的な検討や質的な検討のどちらを採用しているかといった方法論が,研究を科学的なものにしている訳ではないことを指摘し,プラグマティズムの基礎となる可謬主義から,現代的教育課題とその実践的・実証的研究との関連性を述べた.また,アクション・リサーチ(Action Research)とデザイン研究(Design-based Research)の比較から,これらを理論的枠組みと捉え,議論可能な文法を持った方法を構築し,その方法論を議論していくという,これからの科学的な教育研究の方向性について考察した.
4 0 0 0 OA 新宿御苑におけるクールアイランドと冷気のにじみ出し現象
- 著者
- 成田 健一 三上 岳彦 菅原 広史 本條 毅 木村 圭司 桑田 直也
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:13479555)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.6, pp.403-420_1, 2004-05-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 33 30
新宿御苑を対象に夜間の冷気の「にじみ出し現象」の把握を主眼とした微気象観測を夏季約7日間連続して行った.緑地の境界に多数の超音波風速温度計を配置し,気流の直接測定から「にじみ出し現象」の把握を試みた.その結果,晴天かつ静穏な夜間,全地点でほぼ同時に緑地から流出する方向への風向の変化と約1°Cの急激な気温低下が観測された.にじみ出しの平均風速は0.1~0.3 m/sで,にじみ出し出現時にはクールアイランド強度が大きくなる.このときの気温断面分布には流出した冷気の先端に明確なクリフが現れ,その位置は緑地境界から80~90 mであった.このような夜間の冷気の生成に寄与しているのは樹林地よりも芝生面で,芝生面は表面温度も樹冠より低い.芝生面の顕熱流束は夜間負となるが,にじみ出し出現夜はほぼゼロとなる.すなわち,クールアイランド強度の大小と大気を冷却する効果の大小は,別のものと考えるのが妥当である.
4 0 0 0 OA 林泉首夏のあそひ
- 著者
- 香蝶楼豊国,一陽斎豊国
- 出版者
- 中〔仁〕・中仁
- 雑誌
- 豊國錦繪
- 著者
- Yuya ASHITOMI Tsuneo KONTA Fuyuhiko MOTOI Masahumi WATANABE Takamasa KAYAMA Yoshiyuki UENO
- 出版者
- Center for Academic Publications Japan
- 雑誌
- Journal of Nutritional Science and Vitaminology (ISSN:03014800)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.4, pp.270-275, 2022-08-31 (Released:2022-08-31)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 1
The element magnesium (Mg) is involved in various metabolic reactions within the human body, and its deficiency is considered a risk factor for several diseases. In this study, we investigated the relationship between serum Mg levels and mortality in a community-based population. We prospectively assessed the association between serum Mg levels at enrollment and all-cause mortality in 1,314 participants who underwent a community health examination. The mean serum Mg level was 2.4 (±0.2) mg/dL. Patients with serum Mg levels ≤2.3 mg/dL constituted the low Mg group, while those with serum Mg ≥2.4 mg/dL constituted the high Mg group. Ninety-three (7.1%) patients died during the 10-y follow-up period. Kaplan-Meier analysis revealed that all-cause mortality was significantly higher in the low Mg group (log-rank p<0.05). Cox proportional hazards analysis revealed a significant association in the unadjusted model (hazard ratio [HR] 1.72, 95% confidence intervals [CI] 1.14–2.58, p<0.01) and in the fully adjusted model (HR 1.73, 95% CI 1.09–2.76, p<0.05). This association was particularly strong in males (HR 2.08, 95% CI 1.19–3.63, p<0.05). Low serum Mg levels were significantly associated with the risk of all-cause mortality among males in a community-based Japanese population.
4 0 0 0 OA 日本文化団体年鑑
- 著者
- 日本文化中央聯盟 編
- 出版者
- 日本文化中央聯盟
- 巻号頁・発行日
- vol.昭和18年版, 1943