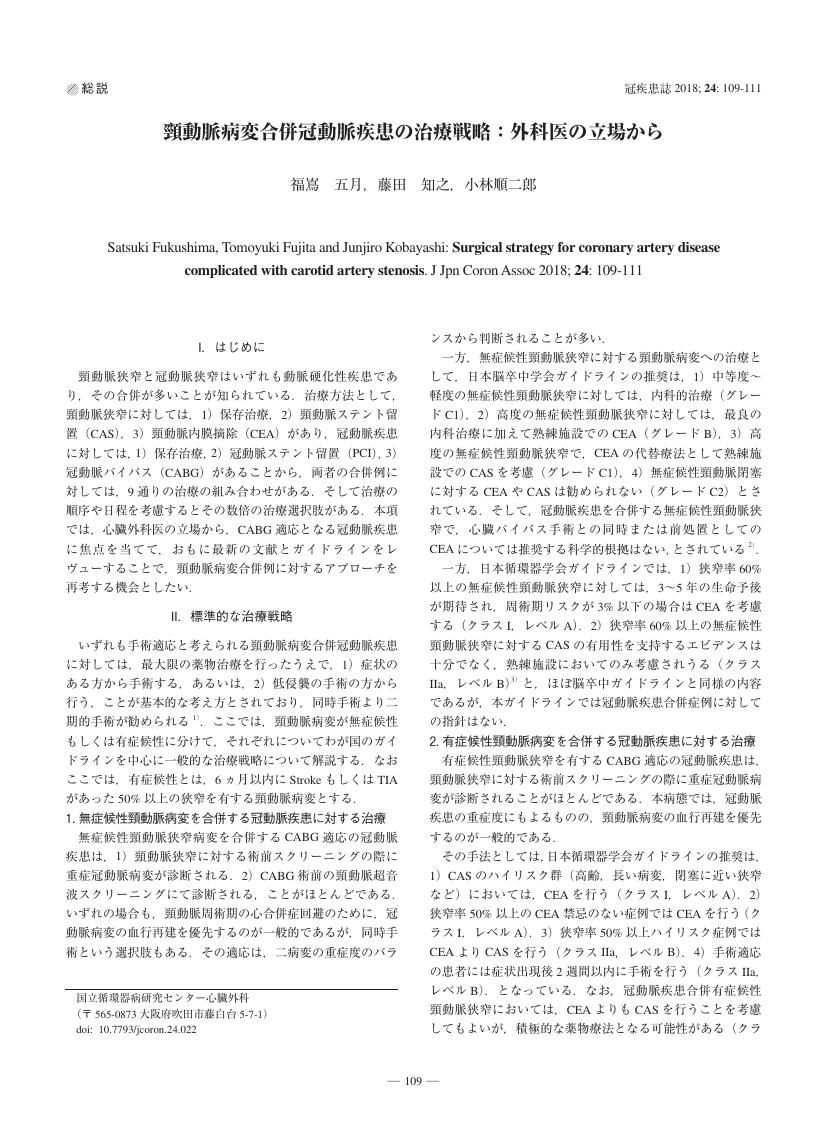2 0 0 0 OA ソウシチョウの間接効果によるウグイスの繁殖成功の低下
- 著者
- 江口 和洋 天野 一葉
- 出版者
- 日本鳥学会
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.3-10, 2008-05-01 (Released:2008-05-21)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 5 4
高密度のソウシチョウの巣の存在にともなうウグイスの巣への捕食の増大という間接効果を検証するために,えびの高原(鹿児島県,宮崎県)において,ソウシチョウの巣の除去実験を行った.調査は2002年と2003年の繁殖期に,ソウシチョウの巣を繰り返し除去し,除去を行わない対照区との間で,ウグイスの巣に依存する期間の生存確率を比較した.除去の結果,2002年は巣密度の低くなった除去区では対照区より全期間生存確率は有意に高かった.2003年はウグイスの営巣数が大きく減少したため,ソウシチョウの巣を除去したにもかかわらず両地区の巣密度差が小さく,生存確率に有意差が生じなかった.本研究の結果はソウシチョウの高密度な巣の存在がウグイスの偶発的な捕食の増加を引き起こし,ウグイスの低い繁殖成功をもたらしたことを示唆している.
2 0 0 0 OA 10歳時に初めて高度難聴を指摘できた人工内耳手術症例
- 著者
- 杉本 賢文 曾根 三千彦 大竹 宏直 寺西 正明 杉浦 淳子 吉田 忠雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本聴覚医学会
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.218-223, 2016-08-30 (Released:2017-03-18)
- 参考文献数
- 12
要旨: 10歳時に初めて高度難聴を指摘できた人工内耳手術症例を経験したので報告する。 5歳時より難聴を疑わせる症状を呈していたが, 耳鼻咽喉科診療所や総合病院耳鼻咽喉科にて複数回純音聴力検査を受けても難聴は指摘されなかった。 当院初診時の純音聴力検査による聴力レベル (4分法) は右 98.8dB, 左 92.5dB と 500Hz 以上の中高音域にて高度な難聴を認めたが, 右耳の 125, 250Hz では 30~40dB の残存聴力を有していた。 初診10ヶ月後には, 補聴器装用効果不十分のため, 左耳へ人工内耳植込術を実施した。 10歳まで高度難聴を把握できなかった要因としては, 難聴が徐々に進行した可能性, 低音域に残存聴力が存在したこと, 不十分な聴力評価により繰り返し難聴を否定されてきたことなどが考えられた。 小児の聴力検査を行う際は, 他覚的聴覚検査の併用も考慮し, 慎重に診断を行うべきである。
2 0 0 0 OA Dynamic Pricing of Luxury Fashion Products
- 著者
- Takao FURUKAWA Mariko NAKAZAWA Chikako MIURA Sakiho KAI Kaoru MORI
- 出版者
- Japan Society of Kansei Engineering
- 雑誌
- International Journal of Affective Engineering (ISSN:21875413)
- 巻号頁・発行日
- pp.IJAE-D-19-00009, (Released:2019-12-13)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 2
To reveal the actual situation of luxury fashion products in the online market, this study sheds light on dynamic pricing observed from the difference between regular and selling prices. Regular price distributions indicated the prestige of luxury fashion brands, with traditional French and Italian brands appearing in a higher rank. Two emerging luxury brands also had a higher social status. This result suggests that the mobility of creative talents allows emerging brands to inherit the brand equity of traditional and prestigious brands. This paper also analyzed dynamic pricing strategy in luxury fashion products by category. The results revealed 67.4% of dresses were discounted with the large markdown ratio even for online luxury fashion stores, however, 69.1% of bags were sold at regular price. A time fluctuation model of product value to interpret the dynamic pricing difference between dresses and bags are also discussed.
2 0 0 0 OA 呼吸困難の発生メカニズム
- 著者
- 西野 卓
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.12, pp.936-940, 2017-12-18 (Released:2018-01-10)
- 参考文献数
- 18
呼吸困難は異常な呼吸感覚であり,呼吸困難の発生には呼吸調節系で重要な役割を果たしているいくつかの感覚受容器が大きく関与している.受容器からの情報は延髄,視床を経由し,体性感覚野や大脳辺縁系に収束する.現段階で最も有力な呼吸困難の発生機序は,中枢-末梢ミスマッチ説あるいは出力-再入力ミスマッチ説と呼ばれている説であり,これらは中枢からの運動出力と神経受容器からの求心性入力に乖離あるいはミスマッチが存在する場合に呼吸困難感が発生するという説である.この説において,中枢からの運動出力は逆行性に大脳皮質感覚受容野に伝えられ,求心性入力には呼吸調節系に存在するすべての受容器からの入力が含まれる.
2 0 0 0 OA アルカリホスファターゼ(ALP)と血液型
- 著者
- 田中 榮司
- 出版者
- 信州医学会
- 雑誌
- 信州医学雑誌 (ISSN:00373826)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.6, pp.400, 2006-12-10 (Released:2014-06-09)
2 0 0 0 OA プリコンセプションから科学的概念への変容過程
- 著者
- 春日 彩花 土田 宣明
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.2, pp.184-198, 2016 (Released:2016-08-08)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2 2
本研究の目的は, 大学(院)生が力学のプリコンセプションをどの程度有しているかを明らかにし, プリコンセプションから科学的概念への変容過程を検討することである。対象者67名に中学校で学習する力学課題を提示したところ, 多くの者が, 学校で教えられる「科学的概念」と不一致の概念を所持していることが確認された。この結果をもとに, Hashweh(1986)の概念変容モデルに沿って教材を作成し, 全問正答者を除く52名に提示した。概念の変容が比較的容易な課題(課題1)では, 提示された新情報と自分の考えを関連付けて整理する(関連付け)ことで, 科学的概念へ変容し得ることがわかった。一方, プリコンセプションが強固で概念の変容が難しい課題(課題2, 3, 4)では, 新情報に対して疑問を示す(懐疑)ことで受容しなかったり, 新情報を自分の考えと関連付けることでプリコンセプションの不整合には気付いたものの(関連付け), 新情報をそのまま取り入れず再解釈して, プリコンセプションを部分的に変化させたりした可能性が示された。また, 提示された「科学的概念」が他の現象も統一的に説明できることに注目しなかったために, 変容には至らなかった可能性も考えられた。
2 0 0 0 OA 頸動脈病変合併冠動脈疾患の治療戦略
- 著者
- 福嶌 五月 藤田 知之 小林 順二郎
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本冠疾患学会
- 雑誌
- 日本冠疾患学会雑誌 (ISSN:13417703)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.109-111, 2018 (Released:2018-06-25)
- 参考文献数
- 9
2 0 0 0 OA 音楽療法の現状
- 著者
- 板東 浩
- 出版者
- 日本補完代替医療学会
- 雑誌
- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.27-36, 2008 (Released:2008-03-12)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1 1
現在,補完代替医療 (CAM) の一つとして音楽療法 (music therapy, MT) が注目されている.同療法には広義でレクリエーションなどを主とする音楽健康法と,狭義で治療の視点を有する狭義の音楽療法がある.セッションにより単に良くなったという判断は不十分で,何らかの評価法で改善したというエビデンスや効果の判定が必要となる.音楽を聴取する受容的音楽療法と,カラオケなどの歌唱や楽器演奏などを行う能動的音楽療法に大別される.対象者としては,小児や精神疾患患者,高齢者,認知症などがあり,本邦では高齢者対象の場合が多く,ニードが高い.高齢者では認知レベルや QOL, ADL の変化を評価し,療法の効果を判定すべきである.近年 MT と他の CAM との併用が行われ,行政の見地からも,展開する余地が残されている.今後は CAM の中で MT の重要性が増し,evidence-based MT ならびに narrative-based MT の両者で研究の発展が望まれる.
- 著者
- 古川 宇一
- 出版者
- 一般社団法人 日本特殊教育学会
- 雑誌
- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.34-46, 1978-03-15 (Released:2017-07-28)
- 被引用文献数
- 1 1
中部太平洋岸の小漁村における成人知的遅滞者の生活状況の特徴とその社会的背景について検討した。資料は知的遅滞者の家族・職場関係者、村人との面接資料、および関係事務所の文献資料である。世帯数371、カツオ・マグロ遠洋漁業を主産業とするこの村では、男子知的遅滞者は1人前に働きうる存在であり、就業し家庭を持っているものが多い。女子の場合、結婚するか、さもなくば次世代の家族に扶養されている。村人の態度は受容的であり、知的遅滞が問題になることは比較的少い。このような知的遅滞者の生活状況を支える社会的背景として、地域社会の主産業である漁業の技術的単純性、職場適応への良い教育環境、職場・地域社会における強い血縁的紐帯、漁業利益配分における古い平等原則の残存、世帯間の生活様式の類似性、家計収入面での利害の共有性、古くからのつきあいの緊密性、しつかりした家制度の残存などの要因が考えられた。
2 0 0 0 OA 生活習慣病における運動療法の役割
- 著者
- 森谷 敏夫
- 出版者
- The Japanese Association of Rehabilitation Medicine
- 雑誌
- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.7, pp.430-435, 2003-07-18 (Released:2009-10-28)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 3 1
2 0 0 0 OA G-59 コールセンターの室内環境が知的生産性に与える影響
- 著者
- 小林 弘造 北村 規明 田辺 新一 西原 直枝 清田 修 岡 卓史
- 出版者
- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会
- 雑誌
- 空気調和・衛生工学会大会 学術講演論文集 平成17年 (ISSN:18803806)
- 巻号頁・発行日
- pp.2053-2056, 2005-07-25 (Released:2017-08-31)
The field study for 134 days, concerning indoor environment quality and productivity of call-center workers, was conducted. Call data of total 13,169 workers was analyzed. The rate of response to calls was adopted as an index to evaluate the worker performance. Worker performance decreased by 2.1 % when the average indoor air temperature rose at 1.0℃. The possibility of the improving productivity under thermal comfortable environment was suggested.
2 0 0 0 OA 音の気柱共鳴とエネルギー保存則
- 著者
- 内川 英雄 浜崎 修
- 出版者
- 日本物理教育学会
- 雑誌
- 物理教育 (ISSN:03856992)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.3, pp.188-191, 1978-08-20 (Released:2017-02-03)
高等学校で,従来行なわれてきた音の気柱共鳴実験では,音源と気柱とのCoupling(結合)にはふれられなかった.鳴っている音叉に気柱共鳴管を近づけると,音が大きくなるかわりに,音叉の振動が早く減衰することを知る,手軽な実験方法がなかったからである.そこで,音叉に二個の半導体ひずみゲージを取付け,ブリッジ回路による出力電圧を,シンクロスコープまたはデジタルテスターで読み取り,音叉の振幅が1/2になるまでの時間(半減期)を測定した.音叉と気柱の相互作用を強める工夫をすれば,非常に大きな音を生じ,半減期も1/5以下にすることができた.音叉のかわりにスピーカーを使用した場合,共鳴管の有無による音の大小と,スピーカーの消費電力とは必ずしも対応しない.しかし,消費電力からジュール熱を差し引いた値は,音の大小に対応し,定性的にはエネルギー保存則を保証している.以上の二実験を大学の物理演習で実施し,エネルギー保存則の意味を再確認した.
2 0 0 0 OA 特別講演「高等教育を取り巻く最近の状況について-工学教育への期待-」
- 著者
- 黄地 吉隆
- 出版者
- 公益社団法人 日本工学教育協会
- 雑誌
- 工学教育 (ISSN:13412167)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.6, pp.6_28-6_35, 2019 (Released:2019-12-05)
2 0 0 0 OA 遺伝子組み換え食品の品質と安全性
- 著者
- 橋本 渉 小澤 祥子 門間 敬子 村田 幸作
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.4, pp.321-326, 1998-11-20 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 16
2 0 0 0 OA 原子力発電所立地地域における廃炉後の地域再生支援の課題
- 著者
- 乾 康代
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.1156-1162, 2017-10-25 (Released:2017-10-25)
- 参考文献数
- 26
イギリス,福井県,新潟県における原発立地地域への支援状況を明らかにした。イギリスとの比較から,立地自治体にとって,廃炉決定過程における立地自治体の権限が確保されること,原子力事業者との廃炉協定が法定化されること,地域再生のための経済的支援が保証されること,原子力事業者の経済支援が重要であること,これらを包括した立地地域再生支援が法定化されることが重要であることを指摘した。
2 0 0 0 OA ローラーを用いた上肢トレーニングが脳卒中片麻痺患者の肩関節運動に及ぼす影響
- 著者
- 長田 悠路 本島 直之
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- pp.11199, (Released:2016-11-22)
- 参考文献数
- 21
【目的】本研究の目的は片麻痺患者に対するローラーを用いた上肢トレーニングの効果を検討することである。【方法】三次元動作解析装置を用い,片麻痺患者7 名のローラー運動20 回後,40 回後,60 回後で上肢最大挙上時の麻痺側肩関節屈曲角度の変化を分析した。その後同様に,片麻痺患者21 名のローラー運動20 回の即時的効果,経時的効果(1日20 回を2 週間)を上肢挙上動作の違いと肩の痛みの変化の違いから分析した。【結果】20 回のローラー運動直後に即時的な肩関節屈曲角度の改善が見られた。経時的な分析では,肩関節屈曲角度の改善が得られ(p<0.05),肩関節の痛みも改善する傾向を示した。【結論】ローラー運動は即時的に麻痺側上肢挙上運動時の肩関節屈曲角度を増大させ,従来のリハビリテーションと併用することでさらに肩関節痛の軽減効果が期待できることが示唆された。
- 著者
- Kazuhisa Kodama Tomohiro Sakamoto Toru Kubota Hideyuki Takimura Hiroshi Hongo Hiromichi Chikashima Yoshiyuki Shibasaki Toru Yada Koichi Node Takeo Nakayama Koichi Nakao
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Reports (ISSN:24340790)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.12, pp.582-592, 2019-12-10 (Released:2019-12-10)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2
Background:Clinical studies on heart failure (HF) using diagnosis procedure combination (DPC) databases have attracted attention recently, but data obtained from such databases may lack important information essential for determining the severity of HF.Methods and Results:Using a HF database that collates DPC data and electronic medical records from 3 hospitals in Japan, we investigated factors contributing to prolonged hospitalization and in-hospital death, based on clinical characteristics and data obtained early during hospitalization in 2,750 Japanese patients with HF hospitalized between 2011 and 2015. Mean age was 77.0±13.0 years; 55.3% (n=1,520) were men, and 39.1% (n=759) had left ventricular ejection fraction <40%. In-hospital mortality was 6.0% (n=164) and mean length of stay for patients who were discharged alive was 18.2±13.7 days (median, 15 days). Factors contributing to in-hospital death were advanced age, higher New York Heart Association (NYHA) class, low albumin and sodium, and high creatinine and C-reactive protein (CRP). Factors contributing to prolonged hospitalization were higher NYHA class, low Barthel index, low albumin, and high B-type natriuretic peptide, lactate dehydrogenase, and CRP.Conclusions:We have constructed a database of HF hospitalized patients in acute care hospitals in Japan. This approach may be helpful to address clinical parameters of HF patients in any acute care hospital in Japan.
- 著者
- 成瀬 厚
- 出版者
- 地理科学学会
- 雑誌
- 地理科学 (ISSN:02864886)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.292-293, 2004-10-28 (Released:2017-04-15)
2 0 0 0 OA インターネット時代における統制語彙の意義と役割(<特集>統制語彙・シソーラスの現在)
- 著者
- 岸田 和明
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.62-67, 2007-02-01 (Released:2017-05-09)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2
本稿では,シソーラスや件名標目表をはじめとする統制語彙に関して,その基本的な機能や限界を整理した上で,インターネットが高度に発達し,サーチエンジンが広く普及した現在における統制語彙の意義と役割について議論する。具体的には,再現率向上および精度向上のための装置としての統制語彙の機能を確認した上で,検索実験や種々の実証研究等で明らかになっている,その限界について述べる。次に,その点を踏まえ,専門的データベースの検索におけるその意義,ウェブなどの全文検索におけるその意義,複数根拠を提供するための表現としての意義について議論する。さらに,今後の可能性として,シソーラスの自動構築や索引語の自動付与,オントロジやフォークソノミーとの関連についても触れる。
2 0 0 0 OA Coupled Drive of the Multi-DOF Robot
- 著者
- Shigeo HIROSE Mikio SATO
- 出版者
- The Robotics Society of Japan
- 雑誌
- Journal of the Robotics Society of Japan (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.128-135, 1989-04-15 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 2 11
ロボットの機能性向上のためには多自由度化することが不可欠である.しかし, 在来のアクチュエータの出力重量比は著しく制限されている.単純な多自由度化はロボット重量の過大な増加を招く.そのため機能性を十分発揮し得る軽量で現実的なロボット, 特にこれから必要とされてゆく自律移動ロボットを実現してゆくためには, 従来とはまったく異なる新しい設計手法が必要とされる.本研究は, 多自由度化と同時に軽量化も計る新しいロボット設計手法を提案する.提案する設計手法は, ロボットに装備する複数の自由度を使用頻度の高い作動状態において出来る限り相互に干渉させ, 共同駆動させようとするものであり「干渉駆動」と呼ぶ.干渉駆動によれば, 多自由度的な機能を発揮するために複数のアクチュエータが装備されていたとしても, 各アクチュエータが装備すべき出力容量は低く抑えられる.よってロボット本体の重量も軽減できる.従来, 制御性の観点からはロボットの駆動系は出来る限り非干渉化すべきであるとされてきた.提案する干渉駆動は, 逆に出来る限り干渉化させるべきであることをハードの立場から主張している.干渉駆動の評価関数として, 装備すべき全出力パワーに対する作業のためのパワーの比である「駆動率ηc」を導入する.干渉駆動の考え方に基づくロボットの機構設計および制御法を検討するため, 4足で壁面を垂直上方に吸着歩行するロボットを想定しシミュレーション実験を行う.実験は準静的な運動を対象とし, 歩行ロボットの機構や歩行姿勢が与えられたとき, その駆動率を最大化する歩行を線形画法によって誘導している.この実験により, 干渉駆動の考え方の導入がロボットの軽量/高速化設計に有効であることを明らかにしている.