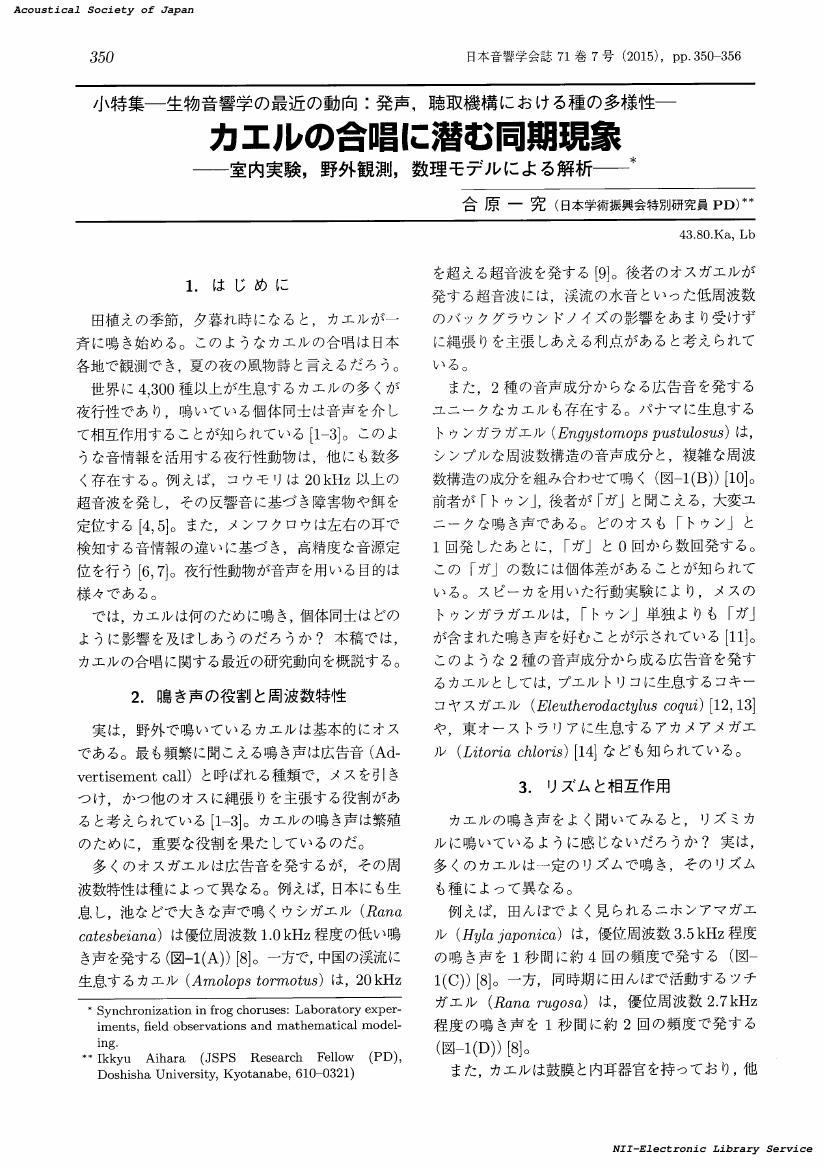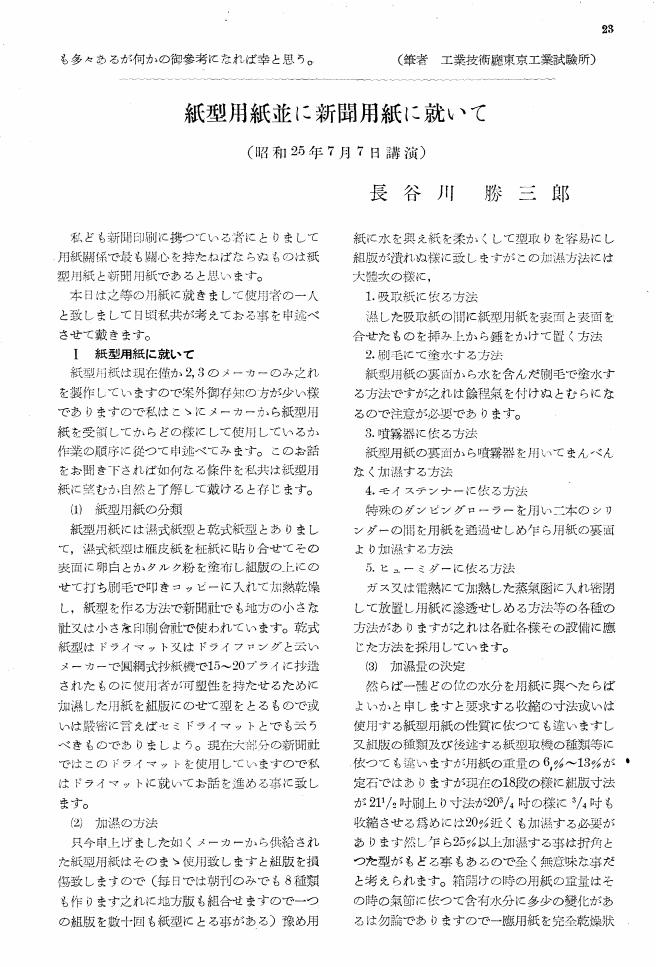- 著者
- 松浦 滉明 坂井 直樹
- 出版者
- 日本結晶学会
- 雑誌
- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.219-221, 2021-08-31 (Released:2021-09-02)
- 参考文献数
- 6
Automated data collection by the ZOO system has realized effective data collection for protein structure determination at SPring-8. Using the ZOO system, it is now available to collect diffraction data from hundreds of single crystals within a day. In order to analyze crystal structures using the huge amount of data, we have been developing an automated structure analysis pipeline. Furthermore, we have applied the highly efficient data collection systems of SPring-8 to high-throughput ligand screening using protein crystals.Here we report our recent developments on the automated structure analysis pipeline NABE system and the ligand screening pipeline using an acoustic liquid handler ECHO.
4 0 0 0 OA 日本における女性大臣
- 著者
- 岩本 美砂子 Iwamoto Misako
- 出版者
- 三重大学法律経済学会
- 雑誌
- 三重大学法経論叢 = The Journal of law and economics (ISSN:02897156)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.1-40, 2021-03-20
4 0 0 0 OA 理系は非宗教的か? : JGSS-2002の分析
- 著者
- 寺沢 重法
- 出版者
- 藤女子大学
- 雑誌
- 藤女子大学人間生活学部紀要 (ISSN:21874689)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.13-28, 2015-03-31
Objective: To examine whether respondents majoring in natural science (rikei) in higher education(under graduate and graduate university) are non-religious. Methods: Data from the 2008 ]apanese General Social Surveys (JGSS・2008) is analyzed. Dependent variables are 1) religious affiliation,2) devotion,a nd 3) confidence in religious organizations. Independent variable is whether respondents majoring in natural science (rikei) or human-social science (bunkei) in higher education. After cross-tabulation analyses,mu ltinominallogit analyses and ordered logit analyses are conducted with the net effects of various socio-demographic and educational variables. Results: Respondents majoring in natural science are not significant1y less religious than those who majored in human-social science in higher education, even though controlling various control variables. Conclusions: The widely accepted idea that those who majored in natural science in higher education are non-religious is partially rejected.
4 0 0 0 OA 麻酔の歴史 全身麻酔の始まり
- 著者
- 吉見 誠一
- 出版者
- 高知赤十字病院図書室運営委員会
- 雑誌
- 高知赤十字病院医学雑誌 = Medical Journal of Kochi Red Cross Hospital (ISSN:09197427)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.65-66, 2016-03-31
- 著者
- 茂木 伸之 鈴木 一弥 山本 崇之 岸 一晃 浅田 晴之
- 出版者
- 公益財団法人大原記念労働科学研究所
- 雑誌
- 労働科学 (ISSN:0022443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.2, pp.27-38, 2018 (Released:2019-12-10)
- 参考文献数
- 21
近年,長時間の座位姿勢の継続による健康リスク対策として,立位姿勢で作業を挿入する方法(sit-stand workstation)が提案されている。本研究は立位姿勢を挿入する適切な時間範囲を導くために,2時間のコンピュータ(文章入力)作業を(1)10分立位と50分座位の繰り返し,(2)40分立位と20分座位の繰り返し,(3)座位条件で比較した。測定項目は下腿周囲長,主観的疲労感,身体違和感,反応時間課題であった。その結果,10分立位条件は有効であった。一方,40分の立位姿勢の継続は下肢の負担が生じる条件となった。立位姿勢の適切な挿入時間は10分から30分になった。作業パフォーマンスは男性の10分立位条件の姿勢転換後にリフレッシュ効果が示唆された。(図6 表1)
4 0 0 0 OA 人力飛行機
- 著者
- 木村 秀政 内藤 晃
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.360, pp.15-22, 1984-01-05 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 10
4 0 0 0 OA ソ連の千島列島、樺太の占領過程──北方領土不法占領の背景──
- 著者
- 三浦 信行
- 出版者
- 国士舘大学日本政教研究所
- 雑誌
- 日本政教研究所紀要 (ISSN:03859169)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, 1981-02
4 0 0 0 OA 加熱によらない殺菌技術
- 著者
- 伊藤 均
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.72-77, 1991-01-15 (Released:2010-01-20)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 1
- 著者
- 合原 一究
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.7, pp.350-356, 2015-07-01 (Released:2017-06-02)
4 0 0 0 OA 島崎藤村「ある女の生涯」における信仰 ――森田正馬の〈患者〉認識との比較を中心に――
- 著者
- 栗原 悠
- 出版者
- 日本近代文学会
- 雑誌
- 日本近代文学 (ISSN:05493749)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, pp.112-127, 2019-11-15 (Released:2020-11-15)
本稿は島崎藤村「ある女の生涯」において主人公おげんが晩年を過ごした「根岸の病院」において精神病〈患者〉として亡くなったという点に注目した。そこで、まず舞台のモデルとなった根岸病院の院長・森田正馬の言説を整理し、森田が特に〈患者〉たちの土着的な因習や信仰を精神医学の症例として読み替えていったことを指摘した。また、そこには当時の社会における宗教への脅威に合理的な説明を与えることで科学としての精神医学を確立したいというねらいがあり、テクストにおいて周囲の人々がおげんの御霊さまへの帰依を病の兆候として入院を仕向けるのはかような論理を内包したものだったとし、語りがもたらすおげんと周囲の認識の不一致によってそうした問題が批判的に捉えられていることを論じた。
4 0 0 0 OA 赤外線ビデオカメラによる光体の撮影研究(<特集>第36回日本超心理学会大会)
- 著者
- 小林 信正
- 出版者
- 日本超心理学会
- 雑誌
- 超心理学研究 (ISSN:1343926X)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1-2, pp.23-27, 2003-12-04 (Released:2017-08-09)
近年、デジタル・ビデオカメラの開発により撮影機器性能が著しく向上し、特に肉眼では見えない領域、即ち紫外線や赤外線領域まで簡便にビデオカメラで撮影することが可能になった。そこで紫外線カメラ、赤外線カメラやサーモグラフィー等の特殊カメラを用い超常現象が頻発する各所を撮影した結果、不可視の光体が浮遊、移動している状態を近赤外線ビデオカメラで捕捉することができた。この発光体はアメリカではオーブ(ORB=球体の意)と呼び、霊体の可能性が高いと話題になっている。各種の撮影実験では、光体は近赤外線領域(700nm〜800nm)で捉えられ、ノーマルカメラでも時々写ることがあり、発光状態によっては可視光(400nm700nm)の内680nm〜700nm付近でも撮影可能であり、超常現象との関連性が高いと思われる。この特質は、球状のガス体で室内外の空間を浮遊移動し、壁やガラス板までも貫通、磁場との共鳴性を持ち、ラップ現象の原因であると考えられる。今後の課題として、より精度の高い撮影機器や物理的測定機器を用い、かつ様々な条件下で観測実験を試み、その正体を究明して行きたい。諸兄のご意見、ご批判、ご指導を賜えれば幸いである。
4 0 0 0 OA 戦後の風水害の復元(1) : 枕崎台風
- 著者
- 河田恵昭
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 京都大学防災研究所年報
- 巻号頁・発行日
- vol.35(B-2), 1992
- 著者
- 鎌倉遊馬
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- vol.(月刊版. 292-2), 2022-08
4 0 0 0 OA 紙型用紙並に新聞用紙に就いて
- 著者
- 長谷川 勝三郎
- 出版者
- 紙パルプ技術協会
- 雑誌
- パルプ紙工業雜誌 (ISSN:18844731)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.5, pp.23-29, 1950-10-20 (Released:2010-02-10)
4 0 0 0 OA 科学とジェンダー
- 著者
- 都河 明子
- 出版者
- 国立大学法人 東京医科歯科大学教養部
- 雑誌
- 東京医科歯科大学教養部研究紀要 (ISSN:03863492)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.95-108, 2004 (Released:2018-07-06)
- 著者
- NAKAMURA Shingo KUSAKA Hiroyuki SATO Ryogo SATO Takuto
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- pp.2022-030, (Released:2022-04-08)
- 被引用文献数
- 4
This study assesses heatstroke risk in the near future (2031-2050) under RCP8.5 scenario. The developed model is based on a generalized linear model with the number of ambulance transport due to heatstroke (hereafter the patients with heatstroke) as the explained variable and the daily maximum temperature or Wet-Bulb Globe Temperature (WBGT) as the explanatory variable. With the model based on the daily maximum temperature, we performed the projection of the patients with heatstroke in case of considering only climate change (Case 1), climate change and population dynamics (Case 2), and climate change, population dynamics, and long-term heat acclimatization (Case 3). In Case 2, the number of patients with heatstroke in the near future will be 2.3 times higher than that in the baseline period (1981-2000) on average nationwide. The number of future patients with heatstroke in Case 2 is about 10 % larger than that in Case 1 on average nationwide despite of population decline. This is due to the increase in the number of elderly people from the baseline period to the near future. However, there were 21 prefectures where the number of patients in Case 2 is smaller compared to Case 1. Comparing the results from Cases 1 and 3 reveals that the number of patients with heatstroke could be reduced by about 60 % nationwide by acquiring heat tolerance and changing lifestyles. Notably, given the lifestyle changes represented by the widespread use of air conditioners, the number of patients with heatstroke in the near future was lower than that of the baseline period in some areas. In other words, lifestyle changes can be an important adaptation to the risk of heatstroke emergency. All of the above results were also confirmed in the prediction model with WBGT as the explanatory variable.
- 著者
- 河島 伸子
- 出版者
- Japan Association for Cultural Economics
- 雑誌
- 文化経済学 (ISSN:13441442)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.80, 2000-03-31 (Released:2009-12-08)
4 0 0 0 OA 酸・塩基の硬さ・軟らかさ(講座:反応はなぜ起こるのか)
- 著者
- 眞鍋 敬
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.8, pp.400-401, 2008-08-20 (Released:2017-06-30)
- 参考文献数
- 4
酸と塩基(ルイス酸とルイス塩基)の親和性の傾向を理解しやすくする概念として,硬い酸・塩基および軟らかい酸・塩基という考え方が導入されている。一般に,硬い酸は硬い塩基と高い親和性を持ち,逆に軟らかい酸は軟らかい塩基と高い親和性を持つ。この考え方は,酸と塩基の熱力学的な親和性の理解だけでなく,反応速度の理解にも役立つものである。