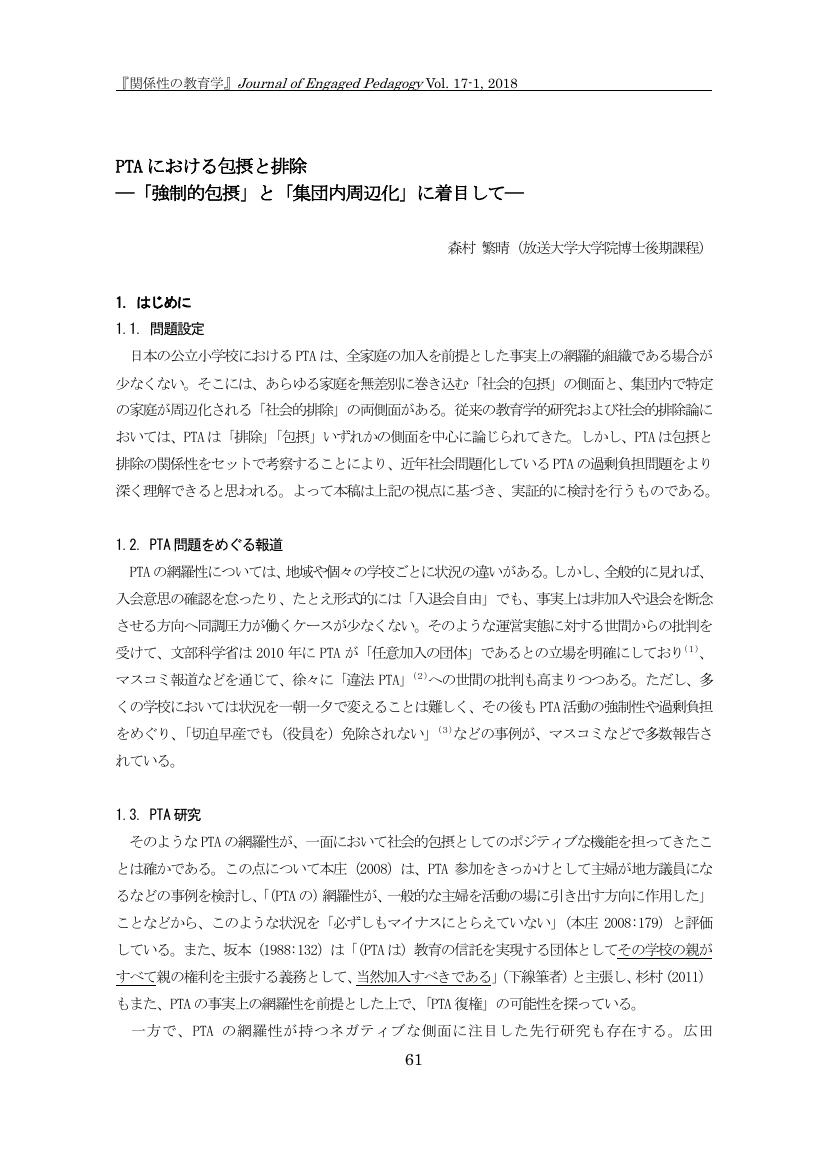3 0 0 0 OA インターネットを支える 通信インフラ
- 著者
- 樋口 雅文
- 出版者
- 一般社団法人 電気設備学会
- 雑誌
- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.8, pp.622-627, 2010-08-10 (Released:2014-08-01)
- 参考文献数
- 3
3 0 0 0 OA マイクロコーンによる疼痛緩和の神経性機序
- 著者
- 堀田 晴美
- 出版者
- 公益財団法人 国際全人医療研究所
- 雑誌
- 全人的医療 (ISSN:13417150)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.39-45, 2014-12-25 (Released:2019-04-09)
- 参考文献数
- 16
侵害刺激で誘発される自律神経反応は,慢性痛を増悪させる要因の一つである.従って,その制御は臨床的に重要である.我々は,軽い皮膚タッチが熱侵害刺激による心血管反射を抑制し得ることをヒトと動物で見出した.その効果は,規則正しく配列した微小突起を持つマイクロコーンによるタッチで生じる.同一素材の平坦な円盤では効果がない.微小突起の有無は,触覚や体性感覚皮質の代謝,触知覚に重要な皮膚Aβ求心性線維の活動には影響しない.しかし,前帯状皮質の代謝や,皮膚低閾値Aδ及びC求心性線維の活動は,微小突起有の方でより高い.熱刺激による心血管反射を抑制するマイクロコーンの作用は,脊髄へのオピオイド受容体遮断薬の局所投与で消失する.以上より,マイクロコーンによる皮膚の低閾値Aδ及びC線維の興奮が脊髄のオピオイド系を賦活して脊髄での侵害受容伝達を抑制し,心臓交感神経反射を抑えると考えられる.
3 0 0 0 OA 精神疾患の血液メタボローム解析研究:うつ病から社会的ひきこもりまで
- 著者
- 加藤 隆弘 松島 敏夫 瀬戸山 大樹
- 出版者
- 日本生物学的精神医学会
- 雑誌
- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.7-12, 2023 (Released:2023-03-25)
- 参考文献数
- 30
うつ病など精神疾患をもつ患者が発症初期から精神医療機関を受診することはまれであり,適切な精神医療の導入は遅れがちである。他方,こうした患者は身体症状のために身体科を受診していることがまれではない。しかるに,筆者らは精神科以外でも実施可能な採血による血液バイオマーカーの開発が,精神疾患の早期発見・早期介入につながることを期待して,血液を用いた精神疾患の客観的バイオマーカー開発を進めている。本稿では,血液メタボローム解析について概説し,うつ病やひきこもりに関連した研究の成果を紹介する。筆者らはこれまで抑うつ重症度と3ヒドロキシ酪酸,自殺とキヌレニン経路代謝物,ひきこもりとアシルカルニチン/アルギニンとの関連を萌芽的に見いだしてきた。こうした研究の発展により精神疾患を採血で客観的に生物学的に評価できるシステムが構築されることで,精神疾患の早期発見・早期介入の実現に加えて精神疾患への偏見解消が期待される。
- 著者
- 杉井 健 Takeshi Sugii
- 出版者
- 熊本大学文学部
- 雑誌
- ドローンによる空撮写真を用いた熊本県球磨郡錦町四ツ塚古墳群の測量調査 : その成果、手順、課題
- 巻号頁・発行日
- 2023-03-31
本書は、科学研究費補助金基盤研究B(2021-2024, 21H00596)および基盤研究A(2020-2024, 20H00019)の助成を受けて実施した四ツ塚古墳群の3次元測量調査についてまとめたものである。
3 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1918年03月19日, 1918-03-19
3 0 0 0 OA 市民科学,医学・臨床研究への市民参画と当事者研究の相互関係を考える
3 0 0 0 OA PTAにおける包摂と排除 「強制的包摂」と「集団内周辺化」に着目して
- 著者
- 森村 繁晴
- 出版者
- 関係性の教育学会
- 雑誌
- 関係性の教育学 (ISSN:13490206)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.61-72, 2018-06-03 (Released:2022-09-22)
3 0 0 0 OA 排ガス(おなら)臭を主訴とする自己臭症に過敏性腸症候群が高率に併発する
- 著者
- 小林 伸行 濱川 文彦 金澤 嘉昭 廣松 矩子 高野 正博
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.12, pp.1380-1385, 2015-12-01 (Released:2017-08-01)
- 被引用文献数
- 3
目的:排ガス(おなら)臭を主訴とする自己臭症の患者における腹部症状を質問紙を用いて調べた.対象と方法:当院心療内科を初診したおなら臭を主訴とした自己臭症患者47名(男性20名,女性27名,平均年齢27.7±12.4歳,以下,自己臭群)と健常者82名(男性48名,女性34名,平均年齢37.3±9.7歳,以下,対照群)を対象とした.当科初診時にRomeIII診断基準に基づいて作成した問診票を用い腹部症状を調査した.結果:過敏性腸症候群(IBS)の診断基準を満たしたのは,自己臭群25名(53%),対照群17名(21%)と自己臭群で有意に高頻度であった(p<0.001).自己臭症とIBSを併存するものは対照群のIBSと比較していきみ,排便困難感,残便感の頻度が高かった(すべてp<0.001).自己臭患者の中でIBS患者と非IBS患者を比べると排便困難感がIBSで高頻度であった(p<0.05).結論:おなら臭を主訴とする自己臭症には高頻度でIBSを併存していた.今後,下部消化管の機能異常の解明により自己臭症の病態理解を促進すると考えられる.
3 0 0 0 OA 暴力と映画的真実 : 真利子哲也監督インタビュー
- 著者
- 堅田 諒 黄 也
- 出版者
- 北海道大学大学院文学研究院 映像・現代文化論研究室
- 雑誌
- 層 : 映像と表現
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.4-21, 2022-03-24
3 0 0 0 OA 眼窩底に埋伏歯を有する濾胞性歯嚢胞の 2 症例
- 著者
- Mizuki Asako Hitomi Matsunaga Kazumasa Oka Shuji Ueda
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.15, pp.2397, 2022-08-01 (Released:2022-08-01)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 3
3 0 0 0 OA Laugier-Hunziker-Baran症候群の1例
- 著者
- 金生 茉莉 藤田 康平 池浦 一裕 加藤 伸 小高 利絵 高森 康次 中川 種昭 角田 和之
- 出版者
- 日本口腔内科学会
- 雑誌
- 日本口腔内科学会雑誌 (ISSN:21866147)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.41-45, 2018 (Released:2019-06-30)
- 参考文献数
- 14
Laugier-Hunziker-Baran症候群(LHB)は,口腔,指趾の色素沈着と爪甲色素線条を特徴とし,全身症状を伴わない後天性疾患である。今回,経過観察中に症状推移の観察が可能であったLHB症候群の1例を経験した。71歳女性で初診時,下唇,頬粘膜に黒褐色色素斑があった。4年経過時に粘膜色素斑の増悪と指趾,爪甲色素線条が発生した。全身検索の結果LHBの診断となった。口腔粘膜色素斑の診断には全身疾患の精査と慎重な経過観察が重要である。
3 0 0 0 OA はじめての音声信号処理とサウンドプログラミング
- 著者
- 青木 直史
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.4, pp.230-238, 2017-04-01 (Released:2017-10-01)
- 参考文献数
- 7
- 著者
- WANG Chung-Chieh CHEN George Tai-Jen NGAI Chi-Hong TSUBOKI Kazuhisa
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- pp.2018-051, (Released:2018-07-31)
- 被引用文献数
- 5
There exists a minor, secondary early-morning peak in mei-yu rainfall climatology along the western coast of Taiwan, and this work investigates one such event on 8 June 2012 in southwestern Taiwan under weak synoptic conditions through both observational analysis and numerical modeling, with the main focus on the triggering mechanism of the convection. Observations show that the convection developed offshore around midnight near the leading edge of a moderate low-level southwesterly wind surge of 15-20 kts, and intensified and moved onshore to produce rainfall. The cold outflow from precipitation also led to new cell development at the backside, and the rain thus lasted for several hours till about 0700 LST. Numerical simulation using a cloud-resolving model at a grid size of 0.5 km successfully reproduced the event development with close agreement with the observations, once a time delay in the arrival of the southwesterly wind surge in initial/boundary conditions (from global analyses) is corrected. Aided by two sensitivity tests, the model results indicate that the convection breaks out between two advancing boundaries, one from the onshore surge of the prevailing southwesterly wind and the other from the offshore land/mountain breeze, when they move to about 40 km from each other. Also, both boundaries are required, as either one alone does not provide sufficient forcing to initiate deep convection in the model. These findings on the initiation of offshore convection in the mei-yu season, interestingly, are qualitatively similar to some cases in Florida with two approaching sea breeze fronts (in daytime over land).
3 0 0 0 OA 博物図譜でたどる明治の科学系博物館資料(科学史入門)
- 著者
- 原田 紀子
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- 科学史研究 (ISSN:21887535)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.231, pp.161-164, 2004 (Released:2021-08-12)
- 著者
- 上田 由紀美
- 出版者
- 人間文化研究機構国文学研究資料館
- 雑誌
- 国文学研究資料館調査研究報告 = Report on Investigation and Research (ISSN:24352047)
- 巻号頁・発行日
- no.43, pp.81-91, 2023-03-31
3 0 0 0 OA 不条理な「2」が友達同士の「2」に解きほぐされる : 今泉力哉監督『街の上で』
- 著者
- 阿部 嘉昭
- 出版者
- 北海道大学大学院文学研究院 映像・現代文化論研究室
- 雑誌
- 層 : 映像と表現
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.72-93, 2023-03-22
3 0 0 0 OA 「記録」から「文学」へ : 伊藤整『裁判』の作られ方
- 著者
- 尾形 大
- 出版者
- 山梨大学教育学部
- 雑誌
- 山梨大学教育学部紀要 (ISSN:24330418)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.v1-14, 2023-02-21
一九五〇年に小山書店から刊行されたD・H・ロレンスの長編小説『チャタレイ夫人の恋人』の訳書が、同年六月に刑法第百七十五条「猥褻文書販売罪」の廉で摘発された。翻訳者・伊藤整と小山書店社長の小山久二郎が起訴され、一九五一年五月の第一回公判から一九五七年三月の最高裁判決まで約七年におよぶチャタレイ事件が幕を開けた。突如裁判の当事者になった伊藤は、東京地裁での第一審の内容を小説『裁判』としてまとめた。この『裁判』は、初出稿と初刊本で大きく加筆修正と増補がなされている。これら二つのテクストの間の異同に加えて、伊藤が執筆時に資料として利用した速記録(『「チャタレイ夫人の恋人」に関する公判ノート』)が存在する。これらの比較・分析をとおして、伊藤が「体験」および「記録」をどのように「文学」に作り変えたのか、その方法と意図を考察し、『裁判』の意義を検討した。
3 0 0 0 OA もう一度ラートブルフを読み直す
- 著者
- 足立 英彦
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, pp.157-166,229, 2004-10-20 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 17
Gustav Radbruch (1878-1949) presented his famous formula under the direct influence of 12 years of National Socialism. It reads: “Where there is not even an attempt at justice, where equality, the core of justice, is deliberately betrayed in the issuance of positive law, then the statute is not merely ‘false law’; it completely lacks the very nature of law.” Many scholars claim that this proposition differs from the legal philosophy expressed in his earlier works. I will argue that his legal philosophy has commonly been misinterpreted in such a way that it is apparently inconsistent with this proposition, and that when correctly interpreted, it supports the proposition. The reinterpretation presented in this paper is based on two arguments. The first concerns Radbruch's concept of law. Many scholars believe that Radbruch developed his concept of law with reference to Heinrich Rickert's “value-reference”, according to which any false statute is acknowledged as “law”. However, I will argue that Radbruch developed this concept under the guidance of Emil Lask's teleological principle. The second argument concerns Radbruch's theory about the purposes of law, and his closely interrelated notion of relativism. I will present a manuscript that Radbruch wrote for his lecture at the University of Kiel in 1919 (Gustav Radbruch. Rechtsphilosophische Tagesfragen [Current Questions of Legal Philosophy]. Ed. Hidehiko Adachi and Nils Teifke. Nomos-Verlag: Baden-Baden 2004). In this manuscript, Radbruch gave preference to what he called the “transpersonal view”, in which personality values and collective values (i. e., the values of nations) are subservient to work values. However, he added to this the argument that personalities and nations are at the same time the precondition of any true community of work. In addition, relativism, from which standpoint he developed his theory before 1919, is critically described in this paper. Pursuant to this, I will maintain that his legal philosophy after 1919 should be reinterpreted as non-relativistic and that, as argued in his proposition, any statute that completely denies one of three given values is non-law.
- 著者
- 藤井 広重 Hiroshige FUJII
- 雑誌
- 宇都宮大学国際学部研究論集 = Journal of the Faculty of International Studies, Utsunomiya University (ISSN:13420364)
- 巻号頁・発行日
- no.45, pp.95-106, 2018-02-01