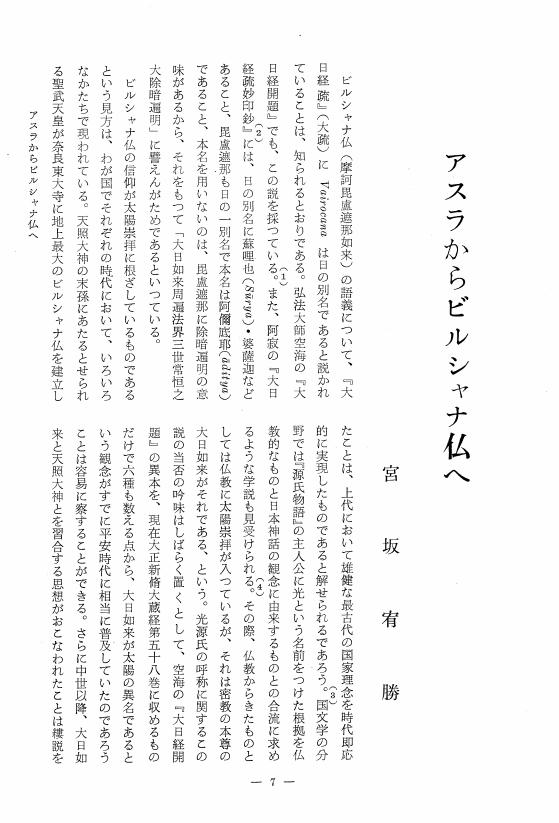3 0 0 0 OA レセプトデータを用いた薬剤師の職能評価
- 著者
- 池谷 怜
- 出版者
- 日本社会薬学会
- 雑誌
- 社会薬学 (ISSN:09110585)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.143-147, 2021-12-10 (Released:2022-02-08)
- 参考文献数
- 8
3 0 0 0 OA 御雇外国人アップジョンズ : 下総牧羊場における緬羊飼育
- 著者
- 角山 幸洋
- 出版者
- 關西大学經済學會
- 雑誌
- 關西大學經済論集 (ISSN:04497554)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2-4, pp.793-826, 1986-11-04
3 0 0 0 OA 意勢固世身見立十二直
- 著者
- 香蝶楼豊国 画
- 巻号頁・発行日
- vol.1, 1800
- 著者
- 林 健太郎
- 雑誌
- 北星学園大学社会福祉学部北星論集 = Hokusei Review, the School of Social Welfare (ISSN:13426958)
- 巻号頁・発行日
- no.58, pp.103-120, 2021-03-15
3 0 0 0 OA 第20回 臨床不整脈研究会 逆Coumel現象を認めた房室回帰性頻拍の1例
- 著者
- 杉 直樹 清水 昭彦 上山 剛 吉賀 康裕 沢 映良 鈴木 慎介 大野 誠 大宮 俊秀 吉田 雅昭 松崎 益徳
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.Supplement4, pp.34-40, 2008-11-30 (Released:2013-05-24)
- 参考文献数
- 4
症例は32歳,男性.主訴は動悸.心電図で左脚ブロック型のwide QRS tachycardiaを指摘された.電気生理学的検査ではHRAからの期外刺激法にてnarrow QRS tachycardiaが誘発され,心房最早期興奮部位は僧帽弁輪後壁で,心房早期捕捉現象がみられることからAVRTと診断した.RVAからの期外刺激法では臨床的に認められたwide QRS tachycardiaが誘発された.同頻拍はすぐにnarrow QRStachycardiaへと変化し,AH間隔およびVA間隔の延長により頻拍周期は延長した.最終的に副伝導路への2回の通電によりwide QRS tachycardiaおよびnarrow QRS tachycardiaはともに誘発不能となった.一般にAVRT中に副伝導路と同側の脚ブロックとなった場合頻拍周期は延長を認めるが(Coumel現象),本症例では房室伝導路および副伝導路の特性のために脚ブロックにより逆に頻拍周期は短縮したと考えられた.
3 0 0 0 OA P. L. バーガーによる社会学の意義論
- 著者
- 池田 直樹
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.56-71, 2018 (Released:2019-06-30)
- 参考文献数
- 40
本稿はP. L. バーガーの社会学論, とりわけ社会学のメタレベルにおける意義に関する彼の議論を取り上げ考察する. バーガーが社会学論を展開した1960年代以降のアメリカにおいては, ‹社会学と政治›の関係をめぐって盛んにこの種の社会学論が論じられていた. バーガーももちろんこういった状況を自覚しながらそれに取り組んでいた. だが同時に彼においては‹社会学と信仰›というもう1つの問題系列も存在した. 時系列的にはこちらの系列に‹社会学と政治›問題が重ねられてくる.これを踏まえて本稿ではバーガーの社会学論を‹社会学と信仰›, ‹社会学と政治›という2つの問題系列の交点において捉える. 本稿はバーガー自身の言葉を借りてこの問題を, 「科学と倫理の問題」として考える. それによって, 従来はともすればバーガーが保守化したのかどうかということのみが焦点化されてきた, 彼における‹社会学と政治›問題に異なる光を当てることができる. それはつまり彼の社会学を‹社会学・政治・宗教›というより包括的な問題連関において捉え直すということである.こうした問題設定によってわれわれは, バーガーの思想全体への概略的見通しを得ることができるだろう. さらに上記の枠組みにおいて彼を捉え直すことは, 意味概念をはじめとする彼の社会学説の再検討のためだけでなく, アメリカ社会学全体の思想的性格を問うための手がかりの1つとなるとも思われる.
3 0 0 0 OA 産業衛生における化学物質過敏症の現状と課題
- 著者
- 加藤 貴彦
- 出版者
- 一般社団法人 室内環境学会
- 雑誌
- 室内環境 (ISSN:18820395)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.217-223, 2019 (Released:2019-08-01)
- 参考文献数
- 13
化学物質過敏症は, 環境不耐症ともいわれ, 低濃度の化学物質に曝露に関係した多臓器にわたる非特異的な症状をもつ病態として定義されている。本論文では, 産業衛生における化学物質過敏症の現状に関し, 1) 最近12年間の3社における質問紙(Quick Environment Exposure Sensitivity Inventory (QEESI))を用いた化学物質過敏症の頻度推移 2) 化学物質に関する法律と労働災害の認定 3) 労働現場で発生した化学物質過敏症に関する裁判判例 の3点について解説した。
3 0 0 0 OA アスラからビルシャナ仏へ
- 著者
- 宮坂 宥勝
- 出版者
- 密教研究会
- 雑誌
- 密教文化 (ISSN:02869837)
- 巻号頁・発行日
- vol.1960, no.47, pp.7-23, 1960-08-25 (Released:2010-03-12)
- 著者
- 松村 亜矢子 石井 成郎 尾方 寿好 鈴木 裕利 竹林 正樹
- 出版者
- 日本健康支援学会
- 雑誌
- 健康支援 (ISSN:13450174)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.191-198, 2022-09-01 (Released:2022-12-13)
- 参考文献数
- 26
BACKGROUND:Enjoyment, realization of benefi ts, and interaction with peers are important factors in continuing exercise. Although rhythm synchro exercise is designed to incorporate nudges into the program to elicit enjoyment, the enjoyment felt by participants in response to the rhythm synchro exercise program and the effects of implementing the program have not been verifi ed. OBJECTIVE:This study aimed to subjective changes felt by participants of performing rhythm synchro exercise and the factors that promote enjoyment. METHODS:Thirteen elderly people, who participated in a rhythm synchro exercise class for three months, were interviewed individually to determine the factors promoting enjoyment and subjective changes through the class. RESULTS:A categorical analysis of the interview content showed that enjoyment was promoted by four factors: program component, psychological factors, social factors, and environmental factors. Subjective changes were summarized by six factors: psychological changes, physical changes, environmental adaptation, social changes, cognitive changes, and changes in daily life. CONCLUSION:The results suggested that rhythm synchro exercise incorporating nudges may be a program with respect to fun and exercise continuation.
3 0 0 0 OA 円頓戒の根本問題
- 著者
- 恵谷 隆戒
- 出版者
- 大谷大学佛教学会
- 雑誌
- 佛教学セミナー = BUDDHIST SEMINAR (ISSN:02871556)
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.74-85, 1972-05-30
3 0 0 0 OA 天竜川河口右岸の浜松五島海岸で進む集中的な侵食の実態
- 著者
- 三波 俊郎 宇多 高明 石川 仁憲 大井戸 志朗 遠藤 和正 佐藤 純一郎
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集B2(海岸工学) (ISSN:18842399)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.I_646-I_650, 2013 (Released:2013-11-12)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1 2
On the Hamamatsu-goto coast located west of the Tenryu River mouth, beach has been eroded severely in recent years, resulting in the exposure of the seawall protecting the sewage facility. Now urgent measures are required to prevent the damage to the seawall. In particular, large-scale offshore troughs have developed in this area, resulting in strong wave action to the seawall. Erosion around the Tenryu River mouth was investigated using aerial photographs, NMB and bottom sounding data along with the grain size analysis of seabed materials.
3 0 0 0 OA 緑茶の疲労回復効果
- 著者
- 渡邉 映理 木村 真理 今西 二郎
- 出版者
- 日本補完代替医療学会
- 雑誌
- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.9-16, 2013 (Released:2013-04-13)
- 参考文献数
- 13
目的:心理,生理,免疫指標等により,緑茶飲用効果を包括的に評価すること. 方法:試験デザインは無作為化クロスオーバー試験とした.対象者は,パソコンによる疲労負荷作業を 120 分間実施した後,抽出した緑茶または水を飲用した.試験開始時,疲労負荷作業後,緑茶または蒸留水飲用 30 分後の 3 回で,採血,事象関連電位測定,質問紙記入を実施し,比較した.心拍測定を行い,HF, LF/HF 値の平均を算出した. 結果:疲労状態の時に緑茶を飲用すると,飲用 30 分で,副交感神経が優位になり,注意力が改善され,NK 活性が一時的に上がり,自覚的な疲労,特に精神疲労が回復するという効果が示唆された. 考察:本研究によって緑茶の疲労回復効果を心理,生理,免疫指標により包括的に示すことができた.このことから,緑茶は,疲労回復に有用な飲料と考えられる.
3 0 0 0 OA 高齢者の嚥下障害
- 著者
- 藤谷 順子
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.234-241, 2018-03-16 (Released:2018-04-20)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 2
3 0 0 0 OA 単純閉凸曲線の長さについて
- 著者
- 西 晃央 瀧川 真也 菊池 泰樹 Muhammad Iqbal
- 出版者
- 佐賀大学文化教育学部
- 雑誌
- 佐賀大学文化教育学部研究論文集 / 佐賀大学文化教育学部 (ISSN:13479601)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.21-26, 2011-08
3 0 0 0 OA 調理食品での腸管出血性大腸菌O157:H7をはじめとする食中毒菌に対する食酢の抗菌作用
- 著者
- 円谷 悦造 浅井 美都 太田 美智男
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会
- 雑誌
- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.101-106, 1998-04-10 (Released:2009-12-10)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 1
食酢を用いた調理における, 食中毒原因菌であるEscherichia coli O157: H7 NGY-10, Salmonella Enteritidis IID 604, Vibrio parahaemolyticus IFO 12711および Staphylococcus aureus IFO 3060の挙動を調べ, 食酢が細菌性食中毒の予防に有効か否かを検証した。食酢を調味に使用する調理食品では, 食酢使用量の多い, 酢漬け類, 紅白なます, サワードリンク等では, E. coli O157: H7 NGY-10に対する殺菌効果が, 食酢使用量の比較的少ない, 酢の物類, すし飯等では静菌効果が確認された。食酢を調味には使用しないが, 刺身類や茹で蛸を食酢に短時間浸漬すると, 供試菌株に対する静菌効果ないしは殺菌効果が発現し, 保存性が高まった。炊飯前に, 食味に影響しない量の食酢を添加すると, 冷却後の米飯に供試菌株を接種しても静菌された。冷凍魚介類を食酢希釈液中で解凍すると, その後の穏和な加熱でも, 供試菌株が殺菌され, 保存性が高まった。また, ハンバーグステーキに食酢を適量添加して焼くと, 中心温度が65℃という不十分な加熱でも, 供試菌株が殺菌され, 保存性が高まった。以上の結果より, 調理の場面での食酢の細菌性食中毒防止効果が確認された。
3 0 0 0 もうひとつの福祉レジーム?:イタリアの研究動向から
- 著者
- 小谷 眞男
- 出版者
- Japan Welfare Sociology Association
- 雑誌
- 福祉社会学研究 (ISSN:13493337)
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, no.2, pp.91-105, 2005
本稿は,1990年代以降のイタリアにおける福祉政策研究の動向を,エスピン=アンデルセンの「福祉レジーム類型論」との関係で,3つの大きな流れに整理して紹介する.<BR>独自の4類型論(1993年)を構築した行政学者フェッレーラは,「福祉国家の南欧モデル」を模索した末,もうひとつの4類型論(1998年)を提案する.そこでは,イタリアないし南欧諸国に共通する特徴として,とくにクライエンテリズムが強調されている.家族社会学者サラチェーノとその後継者ナルディーニは,イタリアないし地中海諸国について「家族主義」という分析視点が重要であることを指摘し,ジェンダーと世代から構成される"親族連帯モデル"を比較史的に論証する.以上の諸研究は,互いに相補的な関係にあり,また国際的な研究動向とも密に連動している.これに対して,カトリック社会学者ドナーティらは,「補完性」の原理という教会の社会教説に即した多元的協働モデルの福祉社会論を構築し,イタリアの福祉政策や実践を多角的に点検する作業を精力的に進めている.<BR>総じて"国家性の欠如"という表現に集約される特質を有するイタリアの福祉が,比較福祉研究の素材としてどのような意味を持ちうるかについての若干の私見が,最後に示唆される
3 0 0 0 OA 日本語会話文における比較表現の分析
- 著者
- 友清 睦子 鈴木 雅実
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告自然言語処理(NL)
- 巻号頁・発行日
- vol.1991, no.67(1991-NL-084), pp.151-158, 1991-07-18
The primary goal of this paper is a statistical investigation of the comparative form of Japanese Spoken Language using appropriable data from the ATR spoken language corpus. The analysis includes the choice of comparative phrase markers as well as more general comparative form phenomena. In addition the paper also examines the semantics of the Japanese comparative form and compares them with those of the English and French comparative forms. Also considered are the problems of describing the comparative form in a dictionary oriented J-E MT telephone conversation task. Finally some examples of description following the markers of the Japanese comparative form are shown.
3 0 0 0 IR 成年後見制度における福祉の視点について
- 著者
- 渡部 朗子
- 出版者
- 千葉大学大学院社会文化科学研究科
- 雑誌
- 千葉大学社会文化科学研究科研究プロジェクト報告書 (ISSN:18817165)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.31-47,
千葉大学社会文化科学研究科研究プロジェクト報告書第21集『高齢化社会における家族問題と消費者問題の比較法的研究』所収
- 著者
- 木梨 雅子
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.5, pp.234-244, 1998
The purpose of this study is to investigate the negotiations between the Tokugawa shogunate and the 'Sumo-kaisho'(an organization of sumo wrestlers and referees)regarding the arrangements for the 'Joran-sumo match in the Kansei era', which was beld in the presence of the Shogun in 1791, and to clarify the principles underlying the arguments for and against the appointment of Zenzaemon Yoshida XIX to the top of the sumo party concerned. The archives used for this study were selected from the National Diet Library, and were written down by the Tokugawa shogunate for the record. The 'Joran-sumo match in the Kansei era' was the first one held in the Edo period, so the Tokugawa shogunate was unsure how to hold this momentous event. Therefore he appointed the Sumo-kaisho to arrange the Joran-sumo match for him. The Sumo-kaisho had been organized under Zenzaemon Yoshida XIX, who had asserted that he had been the chief of the sumo party for generations all throughout Japan, and that the Sumo-kaisho had been his apprentice. Therefore, the Sumo-kaisho required that the Tokugawa shogunate appoint Zenzaemon Yoshida XIX to the 'sumo-shiki'(a sumo ceremony)for the Joran-sumo match since both the Sumo-kaisho and the Tokugawa shogunate recognized that the 'sumo-shiki' was essential for the Joran-sumo match. However the Tokugawa shogunate refused, and instead appointed Shonosuke Kimura VII, deciding that Zenzaemon Yoshida XIX was the chief only in name. Accordingly Shonosuke Kimura VII was made the head organizer of the Sumo-kaisho based on the fact that Shonosuke Kimura VII had had several experiences as substantial organizer, whereas Zenzaemon Yoshida XIX had no practical experience. Furthermore, his background was very suspicious. However, the Sumo-kaisho had been united behind Zenzaemon Yoshida XIX and his background, so if they allowed his background to questioned, it would show a lack of unity to the Sumo-kaisho's part. Therefore, the Sumo-kaisho insisted on appointing Zenzaemon Yoshida XIX to do the 'sumo-shiki'. In the end, the Tokugawa shogunate appointed Zenzaemon yoshida XIX to do the 'sumo-shiki' and his questionable background was overlooked. As a result, the 'Joran-sumo match in the Kansei era 'proved to be an important factor in the Sumo-kaisho's effort to gain authority as the leading organization in sumo.