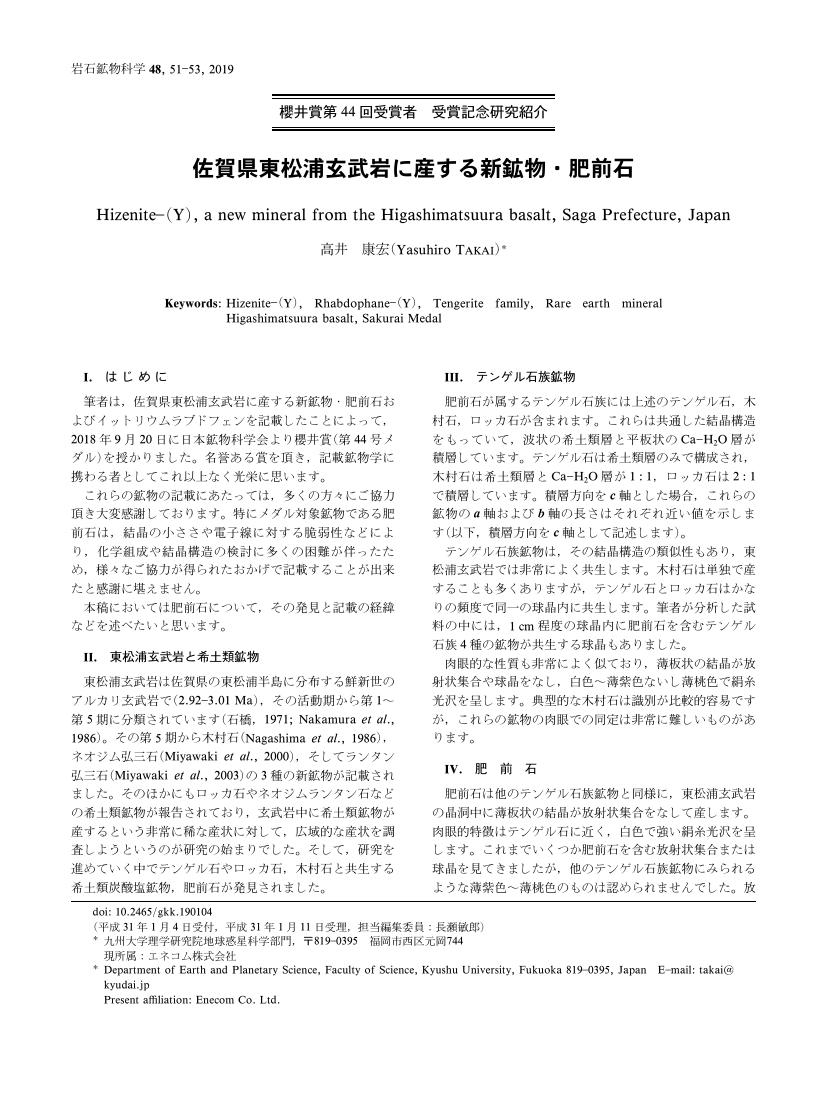2 0 0 0 OA 龍膽寺雄の挑戦 : 「放浪時代」を中心に
- 著者
- 小倉 斉
- 出版者
- 愛知淑徳大学大学院文化創造研究科
- 雑誌
- 愛知淑徳大学大学院文化創造研究科紀要 (ISSN:21884633)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.1-24, 2021-03-25
Pages also numbered 84-61
2 0 0 0 OA サーベイ・フィードバックを活用した若年教員の人材育成
- 著者
- 高瀬 浩介
- 出版者
- 日本学校改善学会
- 雑誌
- 学校改善研究紀要 (ISSN:24365009)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.120-129, 2023-03-31 (Released:2023-04-24)
2 0 0 0 OA 心理アセスメント学への回帰IX : 知能検査・発達検査の正しい解釈
- 著者
- 緒方 康介
- 雑誌
- 大阪大谷大学紀要 = Bulletin of Osaka Ohtani University (ISSN:18821235)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.1-10, 2020-02-20
2 0 0 0 OA 援助要請の諸相と陥穽 ―中谷・岡田論文と永井論文へのコメント―
- 著者
- 橋本 剛
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.497-502, 2020 (Released:2022-02-05)
- 参考文献数
- 7
2 0 0 0 OA 辞書に見る「版」と「刷」の表示
- 著者
- 境田 稔信
- 出版者
- 日本出版学会
- 雑誌
- 出版研究 (ISSN:03853659)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.157-179, 1995-03-31 (Released:2020-03-31)
2 0 0 0 OA Impact of Diabetic Retinopathy on Aortic Valve Calcification in Patients With Type 2 Diabetes
- 著者
- Takaomi Kasuga Asako Sato Tetsuya Babazono
- 出版者
- Society of Tokyo Women's Medical University
- 雑誌
- Tokyo Women's Medical University Journal (ISSN:24326186)
- 巻号頁・発行日
- pp.2022015, (Released:2023-04-27)
- 参考文献数
- 30
Background: Aortic valve calcification (AVC) has a strong association with cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetics (T2D). The objective of this study was to determine the prevalence and risk factors for AVC in Japanese T2D.Methods: We conducted a cross-sectional study of 193 consecutive T2D with estimated glomerular filtration rate (eGFR) ≥ 60 mL/min/1.73 m2 and without overt heart disease (110 men, mean age 61 years). AVC was determined as bright echoes > 1 mm on at least one cusp of the aortic valve by echocardiography.Results: Eighty-two (42%) diabetic patients had AVC, 9 patients had aortic valve stenosis, and 25 had regurgitation. Patients with AVC were older (67 vs. 55 years), with longer diabetic duration (15 vs. 11 years), lower HbA1c (9.1 vs. 10.0%), higher presence of diabetic retinopathy (66 vs. 47%), lower BMI (24 vs. 26 kg/m2), and lower eGFR (82.1 vs. 90.4 mL/min/1.73 m2) (p < 0.01) than patients without AVC. By logistic regression analysis, older age (p < 0.001) and presence of diabetic retinopathy (p < 0.05) were independent risk factors for AVC in T2D.Conclusions: The prevalence of AVC was 42% in Japanese T2D. Diabetic retinopathy associates with presence of AVC.
- 著者
- 永井 智
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.477-496, 2020 (Released:2022-02-05)
- 参考文献数
- 153
This article reviewed three help-seeking issues in counseling and in clinical psychology research: (1) help-seeking processes, (2) facilitation of help-seeking, and (3) help-seeking and adjustment. Based on a review of previous literature about help-seeking processes and the facilitation of help-seeking, the importance of integrating perspectives that combine theoretical models of help-seeking, factors influencing help-seeking, programs facilitating help-seeking, and clinical practice was indicated. With regard to help-seeking and adjustment, help-seeking may not always serve an adaptive function and practices that aim to facilitate help-seeking have several considerations. Finally, the conclusion of this article is that future studies should consider the impact of sociocultural factors on help-seeking.
- 著者
- 松崎 丈
- 出版者
- 宮城教育大学
- 雑誌
- 宮城教育大学紀要 = BULLETIN OF MIYAGI UNIVERSITY OF EDUCATION (ISSN:13461621)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.111-124, 2023-03-31
本研究では、ろう重複障害教育担当教員における実践的見識を明らかにすることを目的に、ろう重複障害のある子どもたちに対する教育実践を20年以上経験した教員3名にインタビュー調査を行った。質的データ分析の結果、8件の概念的カテゴリー(ろう重複障害教育の孤立無援化、長期化している構造的な諸問題、ろう重複障害教育担当教員同士で同僚性を形成、家族と協働でろう重複障害児のキャリア教育を考える、コミュニケーションの実践的見識の蓄積、専門家が導入するオンサイト研修、ろう重複障害児とのコミュニケーション実践の質的向上、同僚性に基づいた研修や環境の変革)が生成された。これら概念的カテゴリー同士の関係から、今後のろう重複障害教育において個々の教員の実践的見識を形成するために必要と考えられる事柄を考察した。
2 0 0 0 OA 模倣と行為の理解に関する最近の研究の紹介:ミラーシステム,サル,乳児の模倣
- 著者
- 川合 伸幸
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.155-160, 2007 (Released:2008-12-15)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 2
「ミラーニューロン」の発見から10年が経過した.その間,「模倣」の重要性の再認識とともに,心理学の諸領域(発達,比較認知)や神経科学のみならず,工学(ロボティックス,人工知能),言語学などにも大きな影響を与え,「ミラーニューロン」という言葉が一人歩きしている感さえある.「ミラーニューロン」が模倣に関連していることは広く知られているが,実はかならずしも正確に理解されていないように思われる.たとえば,ミラーニューロンはサルで見つかったが,サルは決して模倣をしない.チンパンジーの模倣でさえ非常に限定的である.サルのミラーニューロンは,模倣にどのように関わり,何をしているのだろうか? そこで,ミラーニューロンを発見した著者の1人がそれ以降の研究をまとめ展望を述べた論文を紹介し,ミラーシステムとはどのようなものであるのかを確認する.結論をいえば,ミラーシステムは模倣に関わっているが,その一義的な働きは,他者の「行為を理解」することである.著者らは,模倣はコミュニケーションや学習メカニズムの一部としてのみ必要とされると考えている.ここでは読みやすくするために,図を補いオリジナルの論文とは多少異なる説の分け方をした.2番目の論文は,サルはこれまでのレパートリーにない新たな行動が要求されるいわゆる運動模倣をしないが,認知的なルールをコピーする認知模倣は可能であることを示している.模倣には,「行為レベルの模倣」と「プログラムレベルの模倣」があり,この論文では,サルはプログラムレベルの模倣が可能であることを示している.3番目の論文は,行為が行われた状況ではそれらのどちらのレベルの模倣が合理的であるか,という推論を14ヶ月齢の赤ちゃんが行うことを示している.つまり,大人のモデルが行った目的指向的な行動が,その目的を達成するための合理性があるかを推論し,そう判断される場合には同じやり方の行為で模倣するが,そうでなければ(すでに行動レパートリーになっている)より簡単なやり方の模倣で目的を達成することを示している.これらの論文を,図などを補足しつつ簡単に紹介したい.
2 0 0 0 OA こぼればなし : 東京ディズニーランドと地盤基礎(<特集>関東の土質と基礎)
- 著者
- 大川 大地
- 出版者
- 日本聖書学研究所
- 雑誌
- 聖書学論集 (ISSN:27581519)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.117-154, 2022 (Released:2022-09-08)
2 0 0 0 OA 乳酸発酵プロセスにおける反応・分離条件の探索
- 著者
- 野崎 俊哉 片桐 誠之 入谷 英司
- 出版者
- 公益社団法人 化学工学会
- 雑誌
- 化学工学会 研究発表講演要旨集 化学工学会第38回秋季大会
- 巻号頁・発行日
- pp.252, 2006 (Released:2007-02-09)
2 0 0 0 OA 乳酸菌を利用した発酵ソーセージの製造に関する基礎的研究
- 著者
- 加藤 丈雄 蟹江 和茂 志賀 一三 佐藤 泰
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.11-17, 1985 (Released:2008-11-21)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 5 3
(1) スターター乳酸菌としてLactobacillus plantarum-4 (ST)(LP-4)とPediococcus cerevisiae-1 (Pc-1)を使用して,試験ソーセージを調製し,発酵中の乳酸菌数,ブドウ球菌数と保水性の変化を追跡した. (2) 試験ソーセージ中で増殖できるLp-4およびPc-1の最大数は2×108~5×108 cells/gであった. (3) Lp-4, Pc-1はブドウ球菌の生育阻害効果を示し,とくにLp-4は107cells/g接種, 37°C, 20時間培養で99.99%以上の生育照害効果を示した. Pc-1の阻害効果はLp-4に比べ小さかったが, 0.4%ソルビン酸カリウムの添加で強化することができた. (4) 試験ソーセージのpHは乳酸菌接種量の増加に伴って低下し,また保水性はpHの低下に伴って減少した107cells/g接種では,培養6時間後にpH 5.3,保水性は約73%となった. (5) ブドウ球菌の抑制と保水性の維持の点から,基本的発酵条件としては,乳酸菌107cells/g接種, 37°C培養が適当であった.また,ソルビン酸カリウムの添加も一つの有効な手段と考えられた.
2 0 0 0 OA 清朝の乳茶儀礼
- 著者
- 祁 玫
- 出版者
- 東京学芸大学国語国文学会
- 雑誌
- 学芸国語国文学 (ISSN:03879135)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.160-174, 2018 (Released:2018-10-12)
2 0 0 0 中枢神経の障害にともなう皮質脊髄路の再編
- 著者
- 井上 貴博 上野 将紀
- 出版者
- 日本神経心理学会
- 雑誌
- 神経心理学 (ISSN:09111085)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.30-39, 2023-03-25 (Released:2023-04-25)
- 参考文献数
- 41
皮質脊髄路は随意運動の制御に重要な役割を果たしており,脳卒中や脊髄損傷などで損傷を受けると重篤な運動障害が引き起こされる.一方で,脳や脊髄には可塑性があり,失われた機能は時間を経て回復あるいは増悪するなどしばしば変容することが知られる.近年の研究成果から,こうした機能の変容は,障害をのがれた回路網の代償的なはたらきや再編に起因することが明らかとなりつつある.本総説では,げっ歯類の基礎研究から明らかになってきた皮質脊髄路の構造や機能,障害パターンに応じた再編様式について概説し,中枢神経障害後の回路再編と機能回復を促進しうる有望な治療アプローチと今後の課題について述べていく.
2 0 0 0 OA 義務教育における無償制の発展過程
- 著者
- 伊藤 秀夫 松井 一麿 下村 哲夫 角替 弘志 沢井 昭男 桑原 敏明
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.196-208, 1962-09-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 86
2 0 0 0 佐賀県東松浦玄武岩に産する新鉱物・肥前石
- 著者
- 高井 康宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉱物科学会
- 雑誌
- 岩石鉱物科学 (ISSN:1345630X)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.51-53, 2019 (Released:2019-03-28)
- 参考文献数
- 8
2 0 0 0 OA 幼児の集団社会的スキル訓練 : 訓練前の特徴に焦点をあてた効果の検討(実践研究)
- 著者
- 岡村 寿代 金山 元春 佐藤 正二 佐藤 容子
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.3, pp.233-243, 2009-09-30 (Released:2019-04-06)
- 被引用文献数
- 2
本研究では、集団社会的スキル訓練を78名(男子43名、女子35名)の幼児に実施し、その効果を検討した。その際、訓練前の社会的スキルの程度によって社会的スキルの高群、中群、低群の3群に分類し、どのような特徴をもつ幼児に訓練効果がみられるかの検討を行った。3つの標的スキル(上手に聞く、仲間入り、あたたかい言葉かけ)を訓練するために、6〜8セッションからなる集団社会的スキル訓練が行われた。訓練は、教示、モデリング、行動リハーサル、フィードバック、強化からなるコーチング法の手続きに従って行われた。自由遊び場面へのスキルの般化を促進するために、教室でのスキル訓練と自由遊び場面でのスキル訓練を交互に繰り返す訓練プログラムを計画した。その結果、自然な自由遊び場面での行動観察のデータによれば、社会的スキル低群と中群において協調的行動の増加が認められた。また、担任教師による社会的スキル評定によれば、社会的スキル低群において、社会的スキル領域総得点および社会的働きかけスキル得点の増加が見いだされた。これらの結果から、本研究で実施された集団SSTは、社会的スキル低群だけではなく、すでに社会的スキルを獲得している中群にも有効であったことが示された。
2 0 0 0 OA 高齢者のリハビリテーション
- 著者
- 草野 修輔
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.175-181, 2004 (Released:2004-08-30)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 5 2
厚生労働省老健局の私的諮問機関である「高齢者リハビリテーション(以下,リハ)研究会」から『高齢者リハのあるべき方向』と題された中間報告書が発表された。その中で,高齢者リハにおいては高齢者の状態像に応じた適切なアプローチが必要であるとし,リハモデルとして,(1) 脳卒中モデル,(2) 廃用症候群モデル,(3) 痴呆高齢者モデル,を提唱している。上記提言に基づいて,総論として,高齢者の疾患の特徴,加齢に伴う生理的変化,高齢者のリハ対象疾患について述べ,各論として脳卒中モデルに関して急性期脳卒中のリハについて,廃用症候群モデルに関して廃用症候群の病態について,痴呆高齢者モデルに関して,最近の痴呆の診断・治療について述べる。
2 0 0 0 OA 自然災害後の被災地周辺観光地への観光手控え行動に関する研究
- 著者
- 高野 佑 目黒 公郎
- 出版者
- 東京大学生産技術研究所
- 雑誌
- 生産研究 (ISSN:0037105X)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.4, pp.421-423, 2010-07-01 (Released:2010-11-25)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
観光地周辺で自然災害が発生すると,被害のなかった地域でも観光客数が減少することがある.本研究ではこのような現象を「観光手控え」と呼び,事例分析及び意識調査を行った.その結果,県外の観光客には安全・復興に関する記事はほとんど提供されておらず,安全状況を確認せずに「危険そう」との認識から観光手控え行動が発生しており,その傾向は男性よりも女性の方が強いことが分かった.また,観光客側は通常通りの観光活動が効果的な支援として求められていることをあまり認識していないことも明らかになった.その対策として,安全性の明確な提示や,支援としての観光活動の重要性の周知について具体的な方法を構築する必要性を提案した.[本要旨はPDFには含まれない]