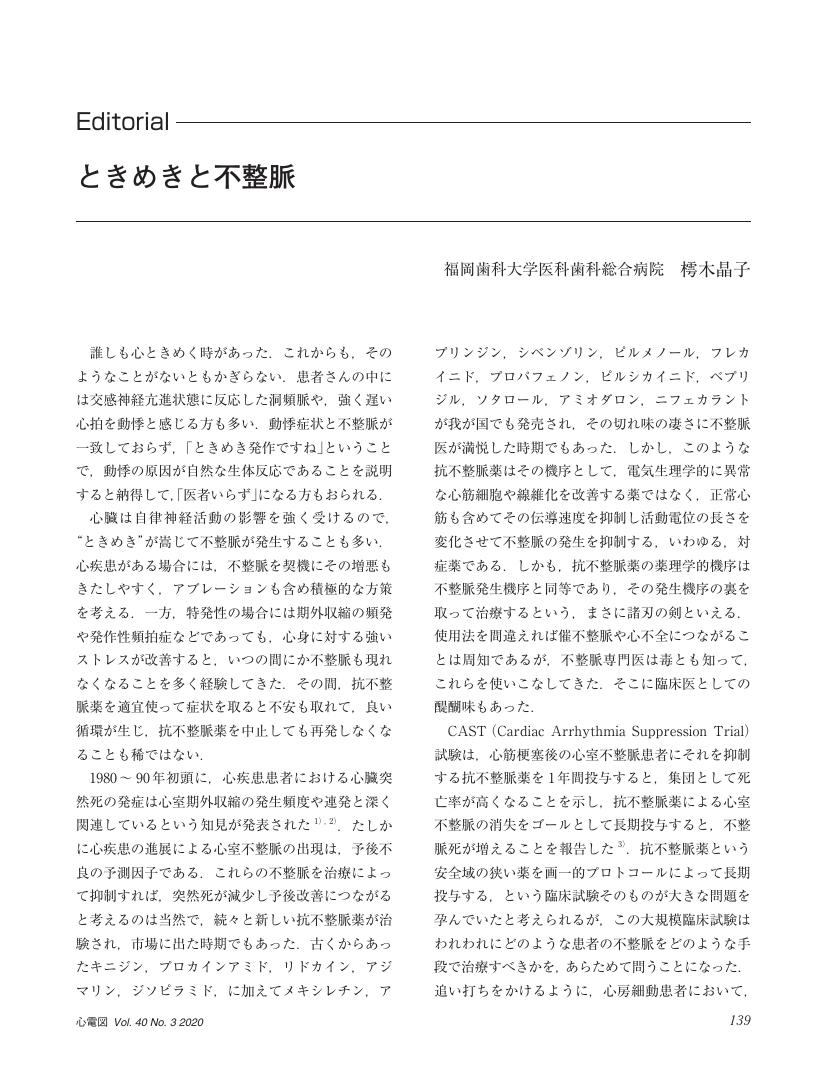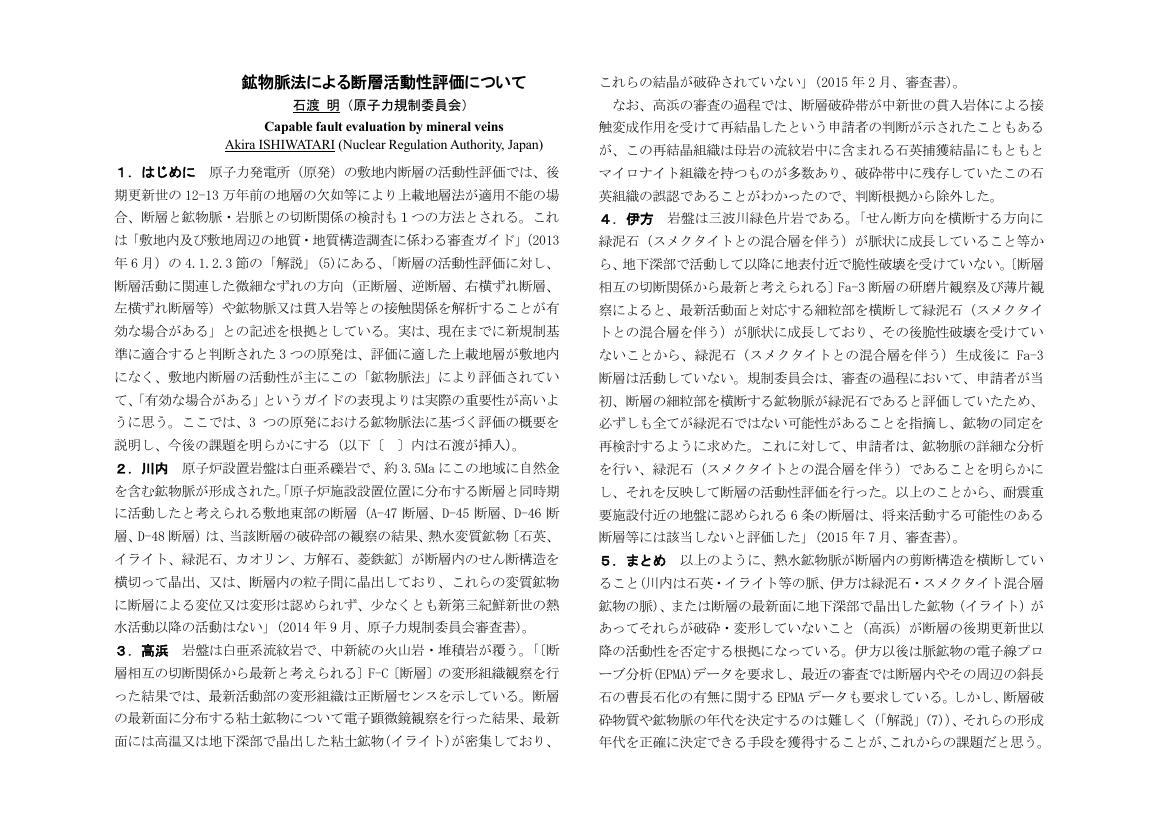2 0 0 0 OA 視覚障害者の鉄道事故について-二つの事故例から
- 著者
- 森 すぐる
- 出版者
- 交通権学会
- 雑誌
- 交通権 (ISSN:09125744)
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, no.31, pp.68-75, 2014 (Released:2017-04-10)
2 0 0 0 OA 「かいもちひ」考 ―『徒然草』注釈書を中心に―
- 著者
- 久保田 一弘
- 出版者
- 東洋大学大学院
- 雑誌
- 東洋大学大学院紀要 (ISSN:02890445)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.1-13, 2017
2 0 0 0 OA 地域における給与の官民格差に関する統計分析 : なぜ,地方では公務員人気が高いのか
2 0 0 0 OA <史料紹介>森林助宛の二通の書簡 : 花山院忠長の津軽滞在をめぐって
- 著者
- 本田 伸
- 出版者
- 弘前大学國史研究会
- 雑誌
- 弘前大学國史研究 (ISSN:02874318)
- 巻号頁・発行日
- no.123, pp.35-40, 2007-10-30
2 0 0 0 OA イノシシの鋭い牙による攻撃で生じた開放性気胸の1例
- 著者
- 岩﨑 安博 川嶋 秀治 柴田 尚明 田中 真生 中島 強 國立 晃成 置塩 裕子 中田 朋紀 米満 尚史 上田 健太郎 加藤 正哉
- 出版者
- 一般社団法人 日本外傷学会
- 雑誌
- 日本外傷学会雑誌 (ISSN:13406264)
- 巻号頁・発行日
- pp.37.3_01, (Released:2023-02-15)
- 参考文献数
- 13
症例は50代の男性. 罠にかかったイノシシを捕獲しようとした際に, イノシシに胸部に突進された. さらに転倒後両下肢を複数回咬まれた. 救急隊により開放性気胸と判断されドクターヘリが要請された. 現場で胸腔ドレナージを実施した. 両下肢にも多発切創を認め圧迫止血を行い病院へ搬送した. 第4病日に胸腔ドレーンを抜去し, 第28病日に退院となった. イノシシの犬歯は非常に鋭く大きく, それによる外傷は単なる咬傷でなく, 深部に達する刺創, 切創となり致死的な外傷を来たしうる. また攻撃性が強く多発外傷ともなりうる. イノシシによる外傷を診療する場合には, これらの特徴を踏まえて重症外傷の可能性も念頭に置いて対応する必要がある.
- 著者
- 青木 純一
- 出版者
- 日本教育政策学会
- 雑誌
- 日本教育政策学会年報 (ISSN:24241474)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.40-52, 2011-07-15 (Released:2017-11-18)
The purpose of the article is to show that the special zones for structural reform in the field of education have been unsuccessful in making good use of the local government initiatives and their distinguishing features. The information the government had disclosed intentionally, leading to poor initiatives of local governments, gave birth to a substantial number of special zones. Most of them, however, proposed fairly similar ideas without fully taking into account their defining features. Some local governments, for example, have had their incentives to provide the measures for regional revitalization and the countermeasures against declining birthrate and depopulation. It could be concluded that the government and the local governments have only exploited the zones for achieving their respective aims.
2 0 0 0 IR 知的障碍福祉における意思決定支援を捉える視座
- 著者
- 中島 由宇
- 出版者
- 東海大学文化社会学部
- 雑誌
- 東海大学紀要文化社会学部 (ISSN:24344710)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.51-74, 2021-09
2 0 0 0 OA ときめきと不整脈
- 著者
- 樗木 晶子
- 出版者
- 一般社団法人 日本不整脈心電学会
- 雑誌
- 心電図 (ISSN:02851660)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, pp.139-140, 2020-10-30 (Released:2020-11-19)
- 参考文献数
- 4
- 著者
- 村上 純一
- 出版者
- 東京都立大学教育学研究室
- 雑誌
- 教育科学研究 (ISSN:02897121)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.49-58, 1989-07-01
2 0 0 0 OA 日本近世初期における渡来朝鮮人の研究: 加賀藩を中心に
- 著者
- 鶴園 裕 笠井 純一 中野 節子 片倉 穣 Tsuruzono Yutaka Kasai Junichi Nakano Setsuko Katakura Minoru
- 出版者
- 金沢大学教養部
- 雑誌
- 平成2(1990)年度 科学研究費補助金 一般研究(B) 研究成果報告書 = 1990 Fiscal Year Final Research Report
- 巻号頁・発行日
- 1991-03-01
1.研究状況の把握 加賀藩はじめ諸藩における「渡来朝鮮人」の研究状況、史料の残存状況を調査・検討し、「日本近世初期渡来朝鮮人一覧稿」を作成した(研究成果報告書に収録)。 2.史料の調査・翻刻 (1)「家伝」の研究及び翻刻を行なった(報告書に収録)。(2)如鉄に関する(1)以外の史料の翻刻を行なった(報告書に収録)。(3)加賀藩における渡来朝鮮人の研究をすすめ、その成果を「加賀藩における渡来朝鮮人」としてまとめた(報告書に収録)。(4)九州地域他の「渡来朝鮮人」関係史料の調査を続行したが、目下整理中である。 3.加賀藩初期『侍塚』の分析 『加賀藩初期の侍帳』(石川県図書館協会)に収録された藩士の石高・役職等を全てパソコンに入力し、家臣団中における「渡来朝鮮人」如鉄の位置づけを明らかにした(報告書に収録)。 4.比較史的研究 東南アジアにおける「渡来朝鮮人」の研究を行ない、その存在形態を明らかにした(報告書に収録)。 5.研究会を月一回のペ-スで開き、研究成果の報告と問題点の整理を行なって、課題の追究に努めた。 6.総括と報告書の作成 上記の研究諸成に立脚し、総論「近世初期渡来朝鮮人冶究序説」をまとめ、諸成果とともに、研究成果報告書『日本近世初期における渡来朝鮮人の研究ー加賀藩を中心にー』に載録して刊行した。 5. Discussion Meeting were held once a month and members of the study team reported on their progress and problems. This helped to facilitate the individual research of team members. 6. Summary and Publication of the Research We summarized the findings of all the members of the study team and this is reported under the heading "Introduction to the Research on the Koreans brought to Japan in the Early Pre-Modern Period". The publication of this research also included the various reports mentioned above. 1. Literature Review Related to This Area of Research We reviewed and examined existing research and documents relating to these Koreans in the Kaga and the other clans and compiled a name list. This name list included such variables as could be determined, example age, rank etc. (Included in this report) 2. The Review and Rewriting of Documents (1) We reviewed and rewrote "Autobiography of Kim Jotetsu". (Included in this report) (2) We rewrote documents related directly to Jotetsu besides 2 (1) above. (Included in this report) (3) We reviewed and researched the history of these koreans in the Kaga clan and the result of this research is reported under the heading "The Koreans in the Kaga Clan". (Included in this report) (4) We expanded this study and included the Koreans brought to the Kyusyu area and other areas and are at the moment finalizing the details. 3. Analysis of the "Soldier's List" of the Early Kaga Clan With the help a personal computer, we analyzed the "Soldier's List" and was able to trace Jotetsu's movement and rise in rank in the Kaga clan. (Included in this report) 4. Comparative Study We also did a comparative study by researching this area in some South-Asian countries and endeavored to clarify the situation of the Koreans at that time. (Included in this report) 5. Discussion Meeting were held once a month and members of the study team reported on their progress and problems. This helped to facilitate the individual research of team members. 6. Summary and Publication of the Research We summarized the findings of all the members of the study team and this is reported under the heading "Introduction to the Research on the Koreans brought to Japan in the Early Pre-Modern Period". The publication of this research also included the various reports mentioned above.
2 0 0 0 OA スケジュール履歴効果の刺激性制御 : 教示と弁別性スケジュール制御の影響
- 著者
- 大河内 浩人
- 出版者
- 一般社団法人 日本行動分析学会
- 雑誌
- 行動分析学研究 (ISSN:09138013)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.118-129, 1997-03-20 (Released:2017-06-28)
17名の大学生を、最少教示-標準FI群、最少教示-修正FI群、正教示-標準FI群、正教示-修正FI群の4群のいずれかにランダムにふりわけ、多元定比率低反応率分化強化(mult FRDRL)スケジュールの後に多元定間隔定間隔強化(mult FIFI)スケジュールを行った。最少教示条件の被験者には反応率に関する教示をしなかった。正教示条件の被験者には、FR成分のときにすばやく反応する、DRL成分のときに間隔をあけて反応するように教示した。標準F1条件の被験者には、mult FIFIで、一定量の強化子を与えたのに対し、修正F1条件の被験者には、インタバル中に自発された反応数に応じて強化量を変えた。Mult FR DRLでは、全被験者がFR成分で高率、DRL成分で低率の反応を示した。最少教示-標準FI群の4名中3名のmult FIFIでは、かつてFRスケジュールと相関のあった刺激下での反応率がDRLと相関のあった刺激下でのそれよりも高かった。このような履歴効果の刺激性制御は、最少教示条件より正教示条件で顕著だった。教示の効果は、反応量と強化量の相関の影響を受けなかった。教示性制御に影響すると考えられる変数について論じた。
2 0 0 0 IR 古代の神々と光
- 著者
- 三宅 和朗
- 出版者
- 三田史学会
- 雑誌
- 史学 (ISSN:03869334)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.4, pp.379-410, 2007-03
論文
2 0 0 0 IR 知的障害者福祉研究における研究の視点 : 先行研究の批判的検討と障害者福祉研究との関連
- 著者
- 船本 淑恵
- 出版者
- 大阪大谷大学志学会
- 雑誌
- 大阪大谷大学紀要 = Bulletin of Osaka Ohtani University (ISSN:18821235)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.121-133, 2021-02
2 0 0 0 OA 鉱物脈法による断層活動性評価について
- 著者
- 石渡 明
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 第123年学術大会(2016東京・桜上水) (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- pp.325, 2016 (Released:2017-04-25)
2 0 0 0 20世紀前半のシベリア・ロシア極東における植民都市と地図作製
- 著者
- 米家 志乃布
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, pp.95, 2010
本報告では、モスクワ・サンクトペテルブルク・イルクーツクでの史料調査をもとに、シベリア・ロシア極東における植民都市の建設の状況、各都市を対象とした都市地図を概観し、シベリア・ロシア極東における20世紀前半の近代都市地図の特徴について考察することを目的とする。 モスクワのロシア国立図書館(РГБ)の地図室には、ロシア各地の地図が地域別に分類されており、最近のものまで各種揃っている。そこで、1900年代前半を中心に、当該期において東シベリアの中心都市であったイルクーツク、ロシア極東の主要な植民都市であるウラジオストク・ハバロフスク・ブラゴベシチェンスクで出版された地図を、地図室内の目録で検索して閲覧・撮影した。また、サンクトペテルブルクのロシア国民図書館(РНБ)の地図室においても地図を閲覧した。ここではモスクワと同様の地図が複数確認された。しかし、地図の撮影は許されておらず、閲覧のみであった。イルクーツク大学付属学術図書館も地図の撮影は禁止、閲覧のみであった。帝政時代におけるイルクーツクの都市計画図や都市図など多くの地図資料の所蔵が確認できた。 地図の発行主体は、帝政期においては「市参事会」の発行であるケースが多かった。つまり、都市行政を担う役割の組織が、都市地図も発行していた。しかし、実際の測量、土地の区画設定や各土地の価格などの実質の土地管理は軍が行っていたと思われる。都市地図内部に軍事区域が描かれている場合と描かいていない場合があるものの、特に極東の3都市(ウラジオストク、ハバロフスク、ブラゴベシチェンスク)をみる場合、ロシアにとって「東方を征服する」ための軍事拠点であることが地図作製のコンテクストを考えるうえで重要である。軍の外部に公表しても構わない情報のみ、印刷地図として発行され、一般の市民(移民など)に公表されていたと推測できる。1922年の日本軍のシベリア撤退以後は、ソ連政府の管轄のもとで都市の復興を行う必要からも、さまざまな整備が急速に行われたことが予想できる。そのなかで、都市地図が一般向けに作製され、発行されたのであろう。1920年代頃の作製である都市地図は、いずれも地図の周囲に広告が掲載されていることに特徴がある。しかし、帝政末期のように、軍事施設の記載や中心部をとりまく周囲の開発地域の記載はなくなり、その部分を覆い隠すように各種広告が存在することが特徴である。東シベリア総督府があったイルクーツクは、極東の3都市に比べて、20世紀初頭においてはすでに都市内部のさまざまな施設の建設がすすんでいた植民都市であり、同時期の極東の都市地図に比べると、都市地図としても大型であり、中心部の周囲にある建設・開発可能地域の情報が詳細である。しかし、基本的には都市地図の作成状況は極東と同様である。 ロシアで作製された大縮尺の地域図を考えるうえでは常に描かれていない情報、隠されている情報を推測する必要がある。地図史研究でいう「沈黙」の論理を考えていくことが重要であろう。帝政末期~ソ連初期における各地域の軍事施設に関する情報は、軍事史文書館など別機関での史料調査を今後の課題としたい。
2 0 0 0 OA 小泉文夫の音楽教育論から学ぶもの ―音楽教育の理念と実際の再検討―
2 0 0 0 OA "I" 見聞録 : Haskellナイト
2 0 0 0 OA 古代の一日と「ぬばたまの夜」(後篇)
- 著者
- 近藤 信義
- 出版者
- 立正大学
- 雑誌
- 立正大学文学部研究紀要 (ISSN:09114378)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.51-85, 1989-03-20
- 著者
- Nozomi Yamamoto Yuji Tanno Yoichi Tanaka Daiki Hira Tomohiro Terada Yoshiro Saito Yuya Yokozawa
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.511-516, 2023-03-01 (Released:2023-03-01)
- 参考文献数
- 27
Pharmacogenetics (PGx) enhances personalized care, often reducing medical costs, and improving patients’ QOL. Unlike single variant analysis, multiplex PGx panel tests can result in applying comprehensive PGx-guided medication to maximize drug efficacy and minimize adverse reactions. Among PGx genes, drug-metabolizing enzymes and drug transporters have significant roles in the efficacy and safety of various pharmacotherapies. In this study, a genotyping panel has been developed for the Japanese population called PGx_JPN panel comprising 36 variants in 14 genes for drug-metabolizing enzymes and drug transporters using a mass spectrometry-based genotyping method, in which all the variants could be analyzed in two wells for multiplex analysis. The verification test exhibited good concordance with the results analyzed using the other standard genotyping methods (microarray, TaqMan assay, or another mass spectrometry-based commercial kit). However, copy number variations such as CYP2D6*5 could not apply to this system. In this study, we demonstrated that the mass spectrometry-based multiplex method could be useful for in the simultaneous genotyping of more than 30 variants, which are essential among the Japanese population in two wells, except for copy number variations. Further study is needed to assess our panel to demonstrate the clinical use of pharmacogenomics for precision medicine in the Japanese population.
- 著者
- 山崎 元一
- 出版者
- 東洋文庫
- 雑誌
- 東洋学報 = The Toyo Gakuho
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.4, pp.483-490, 1972-03