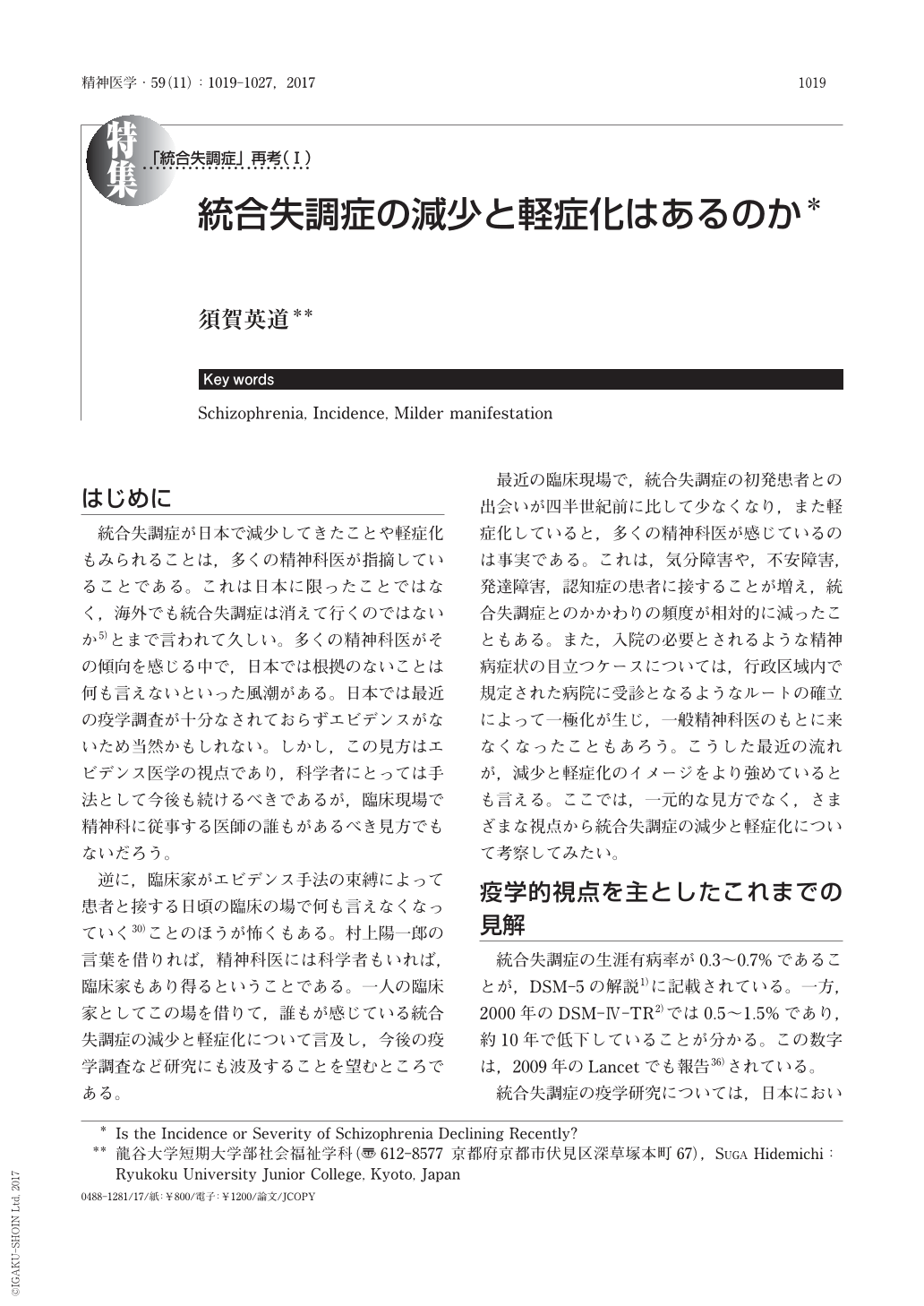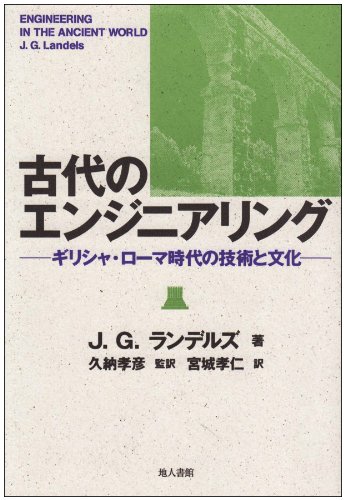2 0 0 0 OA ベトナム北部華人の移住と社会的ネットワーク 広東系/客家系家族を事例として
- 著者
- 河合 洋尚 呉 雲霞
- 出版者
- 国立大学法人 大阪大学グローバルイニシアティブ機構
- 雑誌
- アジア太平洋論叢 (ISSN:13466224)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.171-184, 2022 (Released:2022-03-26)
Most Chinese in northern Vietnam emigrated overseas, primarily because of the Chinese Exclusion Movement in the late 1970s. This paper is based on fieldwork in northern Vietnam and Overseas Chinese State Farms, investigating six households with a northern Vietnamese background: Four Cantonese Chinese in Haiphong and two Hakka Ngai in overseas Chinese farms. It reports on the migration of Chinese from northern Vietnam and the global networks they formed in the places they migrated to, analyzing why some Chinese chose to remain in northern Vietnam and the motivations of those Chinese who left northern Vietnam to maintain communication with the land they left.
- 著者
- 楊 海英
- 出版者
- 国立民族学博物館
- 雑誌
- 国立民族学博物館研究報告. 別冊 (ISSN:0288190X)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.135-212, 1999
別冊 ユーラシア遊牧社会の歴史と現在
- 著者
- Linda MARUSIC Atsushi IWAI
- 出版者
- The Society of Socio-Informatics
- 雑誌
- Journal of Socio-Informatics (ISSN:18829171)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.53-68, 2009-09-30 (Released:2017-02-04)
In this paper we present the problems in developing the learning environment of Japanese as a foreign language in a small European country with its own language, and suggest a method of improvement. The Republic of Slovenia, an EU member state with a population of approximately 2 million, geographically and culturally distant from Japan, is taken as an example. Not only is the number of Japanologists in Slovenia quite small, the small number of potential purchasers results in higher prices for books, leading to difficulties in publishing Japanese language related materials. In this paper, construction of a learning support environment based on an information system incorporating Web 2.0 elements is proposed as the means of improvement: centralizing the existing resources on a single, academically credible website based on the Slovene language and focused on Japanese language learning, and inviting participation from not only Slovene students and scholars, but also Japanese students willing to support foreign students in learning the Japanese language.
2 0 0 0 OA ペリオスチンを基軸とした新規の肺線維化機序の解明とその制御
IPFは肺組織における不可逆的な線維化を特徴とする疾患であり、既存治療薬の効果は充分でなく、新しい治療薬の開発が急務である。我々は、ペリオスチンが線維化に重要なサイトカイン TGF-bにより誘導されると共に、ペリオスチンとTGF-bシグナル間にクロストークが存在し、肺線維化機序において重要な役割を持つと考えるに至った。本研究では、クロストークを阻害するインテグリン阻害剤 (CP4715)を同定し、間質性肺炎モデルマウスへ投与した結果、クロストークシグナルを阻害し、肺線維化に対して軽減効果を示した。これらから、ペリオスチン/TGF-bのクロストークの阻害がIPFの新たな治療戦略として期待される。
2 0 0 0 OA チャングーのスポーツ変容化 エクストリームスポーツの要素に注目して
- 出版者
- 日本スポーツ人類学会
- 雑誌
- スポーツ人類學研究 (ISSN:13454358)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, no.23, pp.1-20, 2021-12-31 (Released:2023-01-10)
A study on the transformation of traditional Taiwanese sport: On the elements of "Extreme Sport" in Yilan Toucheng Qianggu The "Toucheng Qianggu Folk Culture Festival" is conducted as an annual local event in Toucheng, Yilan County, in the North-East of Taiwan. Qianggu takes place in July according to the lunar calendar (August in the solar calendar) during the period called chugen-setsu (Zhongyuanjie) and is said to have been introduced from Fujian Province in China about 200 years ago. A characteristic of Qianggu is the incorporation of competitive elements such as scrambling for a flag, attached to a high pole about 20 meters above the ground. Qianggu was originally considered a religious and cultural activity. While previous studies did point out that Qianggu was a sport, the element of participants "enjoying the extreme thrill" through taking part in a competition high above the ground only recently gained attention. This element of thrill can be regarded as a characteristic of "Extreme Sport" which is a new genre differing from traditional competitive sports. Extreme Sports as an aspect of "extreme thrill" are portrayed in the media as sports involving danger popular among young people. The aim of this paper is to discuss the transformation of Qianggu into a sport, especially focusing on its similarities with elements of extreme sports, while considering its traits as a traditional sport with underlying values and innovative aspects.
2 0 0 0 OA 急性感音難聴をきたし脳脊髄液減少症が原因と考えられた2症例
- 著者
- 古田 厚子 小林 一女
- 出版者
- 一般社団法人 日本聴覚医学会
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.5, pp.491-492, 2014-10-30 (Released:2015-04-10)
2 0 0 0 IR 教科「日本語」と日本語教育との接面―連携の可能性を探るために―
東京都世田谷区と新潟県新発田市の公立小中学校では、構造改革特区認定による自治体独自の教科「日本語」が全児童生徒への必修科目となっている。一方、日本語教育では、非母語話者だけではなく、母語話者に対する関与と貢献の必要が昨今主張されている。小論では、二者の連携の可能性を探るための基礎研究として、日本語教育が母語話者に貢献しようとする理由としての3つの視点から、教科「日本語」の教科書のなかにその接面があるかどうかを検討した。その結果、(1)両者の共通点は随所で見いだせ、特にメディア・リテラシーに関しては教科「日本語」から学ぶべき点が多いこと、(2)「多言語・多文化共生を目指す教育」に関する内容は、教科「日本語」に補われるべき点として日本語教育の視点から指摘しえること、が明らかとなった。
2 0 0 0 OA 「寿岳日記2」向学心探求心全開の東北大学時代
- 著者
- 遠藤 織枝
- 出版者
- 現代日本語研究会
- 雑誌
- ことば (ISSN:03894878)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.180-197, 2022-12-31 (Released:2022-12-31)
- 参考文献数
- 5
東北大学入学から卒業までの寿岳章子の暮らしと思惟を、当時章子が家郷に送った手紙と日記から読み取る。1年生の章子は、大学の講義も演習も語学授業もすべてに興味を抱き、貪欲に学んだ。戦争末期の2年生は学徒動員で明け暮れた。最終学年の3年生は多くの古典文献を読み、室町時代の助詞をテーマに自他ともに認める質の高い卒論を書き上げた。この時期は「女は無知」、「目立たないコツコツした仕事が女の学問にふさわしい」などと言っていて、当時の女性劣位の思想からまだ解放されていない。
2 0 0 0 IR 知的障害のある夫婦の子育て支援に関する研究―「親性獲得」の支援プロセスに着目して―
- 著者
- 西村 明子
- 出版者
- RIKKYO UNIVERSITY(立教大学)
- 巻号頁・発行日
- 2021
元資料の権利情報 : CC BY-NC-ND
2 0 0 0 OA 音響計測とキャリブレーション
- 著者
- 森川 昌登
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.6, pp.351-356, 2020-06-01 (Released:2020-12-01)
- 参考文献数
- 9
2 0 0 0 統合失調症の減少と軽症化はあるのか
- 著者
- 須賀 英道
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 精神医学 (ISSN:04881281)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.11, pp.1019-1027, 2017-11-15
はじめに 統合失調症が日本で減少してきたことや軽症化もみられることは,多くの精神科医が指摘していることである。これは日本に限ったことではなく,海外でも統合失調症は消えて行くのではないか5)とまで言われて久しい。多くの精神科医がその傾向を感じる中で,日本では根拠のないことは何も言えないといった風潮がある。日本では最近の疫学調査が十分なされておらずエビデンスがないため当然かもしれない。しかし,この見方はエビデンス医学の視点であり,科学者にとっては手法として今後も続けるべきであるが,臨床現場で精神科に従事する医師の誰もがあるべき見方でもないだろう。 逆に,臨床家がエビデンス手法の束縛によって患者と接する日頃の臨床の場で何も言えなくなっていく30)ことのほうが怖くもある。村上陽一郎の言葉を借りれば,精神科医には科学者もいれば,臨床家もあり得るということである。一人の臨床家としてこの場を借りて,誰もが感じている統合失調症の減少と軽症化について言及し,今後の疫学調査など研究にも波及することを望むところである。 最近の臨床現場で,統合失調症の初発患者との出会いが四半世紀前に比して少なくなり,また軽症化していると,多くの精神科医が感じているのは事実である。これは,気分障害や,不安障害,発達障害,認知症の患者に接することが増え,統合失調症とのかかわりの頻度が相対的に減ったこともある。また,入院の必要とされるような精神病症状の目立つケースについては,行政区域内で規定された病院に受診となるようなルートの確立によって一極化が生じ,一般精神科医のもとに来なくなったこともあろう。こうした最近の流れが,減少と軽症化のイメージをより強めているとも言える。ここでは,一元的な見方でなく,さまざまな視点から統合失調症の減少と軽症化について考察してみたい。
2 0 0 0 OA 薬禍の風霜——薬害のない世界を求めて——
- 著者
- 増山 ゆかり
- 出版者
- 日本保健医療社会学会
- 雑誌
- 保健医療社会学論集 (ISSN:13430203)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.12-17, 2017-01-31 (Released:2018-07-31)
1957年にドイツでサリドマイド剤を含む医薬品が開発され、副作用がない夢の新薬と持てはやされ翌年の1958年には日本でも医薬品として承認されました。この医薬品の副作用によって、多くの人々の命が奪われた事件が「薬害サリドマイド事件」です。多くの消費者は、企業が示す安全性や有効性のエビデンスに国が保証し、それを製品化したのだから偽薬でも飲まされない限り、重篤な副作用は起きないと思っているのではないでしょうか。しかし、承認時におこなう治験や臨床試験だけで、すべての副作用を把握できるわけではありません。実際には、市場に出て初めて医薬品という商品は価値を問われるのです。何が起きたのか知る間もなく亡くなった人や、何の落ち度もない人が自分のせいだと苦しむ無念さは、今もこの国の何処かで哀しみを湛えているでしょう。副作用に科学的根拠を求めれば、被害の蓄積を待つということしかないのです。被害が何をもたらしたのか知り、それを教訓にする責任が社会にはあると思います。
2 0 0 0 OA 商品化したメディアの不調
- 著者
- 岩澤 聡
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.10, pp.691-693, 2012 (Released:2012-01-01)
- 参考文献数
- 1
- 著者
- 森田哲至
- 出版者
- 日本橋学館大学
- 雑誌
- 日本橋学研究 (ISSN:18829147)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.35-51, 2012-03-31
明治末期から大正初期に日本橋高等女学校で学んだ天野喜久代は、昭和初期に日本最初の女性ジャズ歌手となった。彼女は同校を卒業する前に、帝国劇場の洋劇部に研修生として入り、イタリア人で振付師兼演出家のローシーや世界的に有名になったプリマドンナ三浦環から、オペラ女優となるための声楽・舞踏・演技の指導を受けた。ところが、帝劇オペラの奥行成績は不振を極め、洋劇部は数年で解散となってしまった。演技をする場を失った天野は、脚本家、演出家兼俳優の伊庭孝と作曲家の佐々紅肇に出会った。彼らは一般大衆に理解されるオペラを創作することによって時代を切り開く先端的芸術運動を試みており、天野はその二人から影響を受け、浅草でオペラ女優として活躍する。彼女はモダン化される大都市東京で大衆の心を捉えようと、舞台だけでなくお伽歌劇のレコードにも挑戦し、先駆的な活動を続けた。彼女は、この時に培った能力で、昭和初期には日本最初の女性ジャズ歌手としてラジオやレコードに登場し、昭和歌謡にモダンな旋律とリズムを提供する役割を果した。本稿では前編として、大正期における彼女のオペラとお伽歌劇での活動の軌跡を迫ってみた。
- 著者
- Kiyoshi Toko
- 出版者
- Japanese Society for Food Science and Technology
- 雑誌
- Food Science and Technology Research (ISSN:13446606)
- 巻号頁・発行日
- pp.FSTR-D-22-00195, (Released:2023-01-06)
- 被引用文献数
- 1
The first taste sensor was developed 30 years ago, and its use has become widespread in the food and pharmaceutical industries. Numerous efforts have been made to improve taste sensor technology since that time. Now, over 600 taste sensors are used around the world to quantify and visualize the taste of food. In this article, we first explain the mechanisms underlying the operation of taste sensors and how they respond to the five basic sensations of taste. A taste map of beers that presents their taste in a visual manner will be introduced as a typical application of the taste sensors used in the food industry. We then discuss the ability of the taste sensor to detect taste interactions, such as bitterness-suppressing effects as well as attempts to produce tasty low-calorie foods. Recent attempts to visualize personal preferences and the dynamic changes in the taste of food during chewing using the taste sensor are also explained. The environment surrounding taste sensors and the taste sensors themselves have progressed considerably, with new food services appearing constantly. We are entering an era where we can increase our enjoyment of eating.
2 0 0 0 OA DPP-4阻害薬関連水疱性類天疱瘡の発症機序の解明
自己免疫疾患の発症誘因は、未だ大部分が未解明である。水疱性類天疱瘡 (BP) は最も頻度の高い自己免疫性水疱症であるが、近年、2型糖尿病治療薬であるDPP-4阻害薬を服用中にBPが生じることが知られるようになってきた。本研究では、DPP-4阻害薬関連BPにおける自己抗体産生機序を明らかにする。本症ではHLA-DQB1*03:01保有者が多いことに着目し、同HLAを持つ健常人におけるBP180反応性T細胞の有無を解析する。また、DPP-4阻害薬がTリンパ球に及ぼす影響を、細胞培養や制御性T細胞欠損マウスの実験で明らかにする。本研究により免疫自己寛容破綻の機序を解明し、自己免疫疾患の本質に迫る。
2 0 0 0 OA インターネット接触が職業におけるジェンダー・ステレオタイプに及ぼす影響
- 著者
- 小川 眞理絵 和田 正人
- 出版者
- 東京学芸大学教育実践研究推進本部
- 雑誌
- 東京学芸大学紀要. 総合教育科学系 (ISSN:24349356)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, pp.517-527, 2021-02-26
2 0 0 0 古代のエンジニアリング : ギリシャ・ローマ時代の技術と文化
- 著者
- J.G.ランデルズ著 宮城孝仁訳
- 出版者
- 地人書館
- 巻号頁・発行日
- 1995
2 0 0 0 OA 現代民話に見る他界観分析―「よみがえり」から見る他界と現世の境界―
- 著者
- 佐﨑 愛
- 出版者
- 東北大学大学院文学研究科宗教学研究室
- 雑誌
- 東北宗教学 = Tohoku Journal of Religious Studies (ISSN:18810187)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.149-182, 2016-12-31
2 0 0 0 OA 人工ふ化放流河川におけるサケ野生魚の割合推定
- 著者
- 森田 健太郎 高橋 悟 大熊 一正 永沢 亨
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.2, pp.206-213, 2013 (Released:2013-03-22)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 9 26 3
サケ資源はほとんどが放流魚で維持されていると考えられているが,これまで野生魚(自然産卵由来)の寄与率は調べられていない。本研究では,耳石温度標識による大量放流が行われている北海道の 8 河川において,サケ野生魚の割合を推定した。ウライで捕獲されたサケに占める野生魚の割合は,調査河川全体で計算すると 28.3±1.2%,放流魚の全数が標識されている河川に限定すると 15.9±0.6% と推定された。野生魚の割合は河川や年級群によって大きく変動したが(0~50%),野生魚も十分に資源に貢献しうると考えられた。