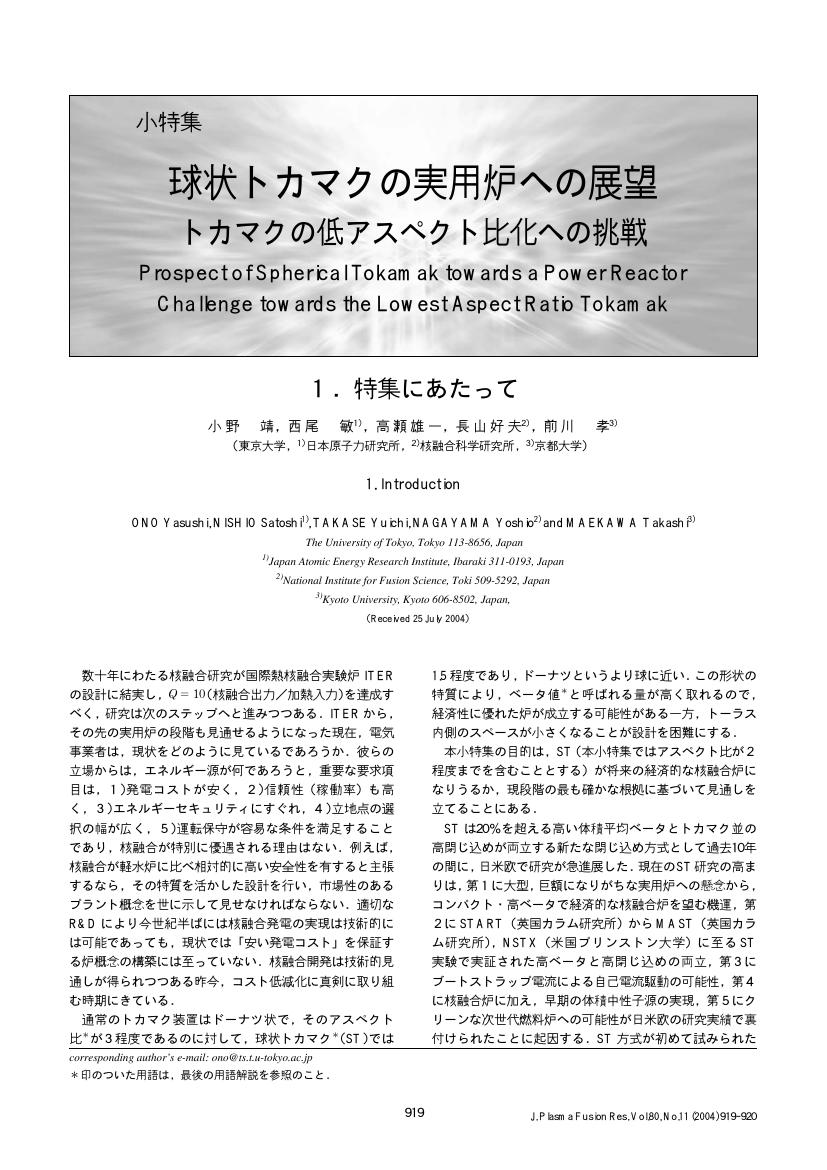2 0 0 0 IR 明治初期の大村藩の藩制改革 (岡本悳也教授 退職記念号)
- 著者
- 長野 暹
- 出版者
- 熊本学園大学経済学会
- 雑誌
- 熊本学園大学経済論集 (ISSN:13410202)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.145-170, 2016-03
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1391, pp.28-31, 2007-05-14
東欧が薄型テレビの工場建設ラッシュに沸き、西欧に向かう大動脈はトラックで溢れ返っている。未開拓の地を求める企業の進出は加速し、その先にはロシア、中東、アフリカの新市場も視野に入る。 ロンドンの家電販売店が立ち並ぶトッテナムコート・ロード。
2 0 0 0 OA 独裁国家における中下級エリートの「ゲーミング」としての選挙不正
- 著者
- 豊田 紳
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.88-100, 2018 (Released:2021-07-16)
- 参考文献数
- 36
非民主主義体制(=独裁体制)の政治過程は,秘密のベールに覆われている。そのため,その選挙,殊に選挙不正については,不明な部分が多い。本稿の目的は,独裁体制の選挙不正に新たな光を当てることを通じて,その政治過程の理解に貢献することである。具体的には次の2つを主張する。第1に,独裁体制における選挙不正には,独裁体制内の中下級エリートが独裁者に対して,自らの得票率を誇示するための「ゲーミング」として行うものが存在する。第2に,野党が競争選挙に参加し,監視するようになると,ゲーミングとしての選挙不正は起きづらくなる。2000年の民主化以降,様々なアーカイブ資料やデータが利用可能となったかつての独裁国家メキシコを分析し,これらの仮説の妥当性を検証した。
2 0 0 0 OA 核兵器なき世界に向けて グローバル・ゼロ軍縮会議
- 著者
- 遠藤 哲也
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3, pp.160-163, 2009 (Released:2019-06-17)
- 参考文献数
- 4
核兵器廃絶論は,古くから唯一の被爆国である日本,非同盟諸国,北欧,カナダ,豪,ニュージーランド等の非核兵器国から主張されてきたが,近年,米国から,それもかつて米国の核戦略に直接関与した元政府高官から主張されるようになったことは注目に値する。その議論は以前の核廃絶論が,一般的,情緒的であったのに比べ,冷戦終えん,9.11事件後の安全保障環境の変化を踏まえた核戦略論に基づくもので,かつ廃絶に至る具体的な道筋を提案している。それとともに,廃絶への過程に横たわる多くの政治的,技術的困難を指摘している。世界が核廃絶の途に踏み出すには,まずは米国の決断が必要なこと,核なき世界が米国にとっても世界の安全保障にとっても望ましいことを強論している。この軍縮会議はそういった議論の流れの一つである。
- 著者
- 加藤 愛美 福留 奈美
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.32, 2021
<p>【目的】明治時代以降、西洋文化のひとつとして伝来したイタリア料理は、現在、外食だけでなく中食、家庭内食への浸透が進む。本研究は、外来の食文化の受容と普及のプロセスをとらえる研究の一環として、イタリア料理のパスタに着目し、日本の現代食生活において身近に利用されるパスタの種類と調理法の実態をとらえることを目的とする。</p><p>【方法】首都圏の小売店の販売状況を調査し、取り扱い上位のパスタの種類を特定した。また、家庭内食への影響や実態を反映する食情報のひとつとして、NHK『きょうの料理』アーカイブスに収録されたイタリア料理の中のパスタ料理と、レシピサービス『クックパッド』でパスタの種類別に検索した人気上位50品のパスタ料理を抽出し、使用食材とソース分類について集計・分析した。</p><p>【結果】大型スーパーから都市型の小規模スーパー、輸入食品を多く取り扱う酒類量販店等計20店舗の内、11店舗以上で販売されるパスタは12種類あった(2021年5月現在)。NHK『きょうの料理』のイタリア料理レシピ336品中にパスタ料理は95品あり1/3弱を占めた。『クックパッド』のパスタ料理レシピ(パスタ16種類、計800品)において、ニンニク、トマトが4割前後のレシピで使用されているのに対し、和風食材・調味料の利用はきのこ類と醤油の利用が1割前後あるものの、ネギ、海苔、大葉、明太子・たらこ等は3%前後の使用率だった。ソース分類については、マカロニ等のショートパスタでマヨネーズによるサラダの利用が、カッペリーニ等細めのロングパスタでトマトのソースが、フェットチーネやラザニア等いくつかの種類でトマトとクリームの両方を使うソースの利用が特徴的にみられた。</p>
2 0 0 0 将棋における状態空間数の上下界
- 著者
- 都 勇志 木谷 裕紀 小野 廣隆
- 雑誌
- 研究報告ゲーム情報学(GI) (ISSN:21888736)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022-GI-47, no.14, pp.1-7, 2022-03-11
ゲームの難易比較や AI ベンチマークの妥当性評価などのため,二人零和有限確定完全情報ゲームの「複雑さ」の計量が様々な形で研究されている.代表的な「複雑さ」の尺度の一つが状態空間数であり,これは初期局面から到達可能な局面数として定義されている.本研究では将棋の状態空間数の見積もりを行う.禁則ルールの多さなどから将棋の厳密な状態空間数を測ることは容易ではないが,2008 年の篠田の研究により 4.65×1062 と 9.14×1069 の間の値を取ることがわかっている.本研究では将棋の状態空間数のより正確な評価を行い,2.45×1064 と 6.78×1069 の間の値を取ることを示す.上界値の評価については持ち駒が少ないほど局面のパターンが増えることに注目した計量方法を提案する.下界については,篠田により提案された駒配置のテンプレートを改良し,これに基づく解析を行う.また将棋から派生したゲームである 5 五将棋についても状態空間数が 13 桁から 20 桁の間であることを示す.
2 0 0 0 OA 皇紀二千六百年記念行事と飯田下伊那
- 著者
- 齊藤 俊江
- 出版者
- 飯田市歴史研究所
- 雑誌
- 飯田市歴史研究所年報 (ISSN:13486721)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.118-130, 2019 (Released:2022-03-12)
2 0 0 0 OA 環太平洋連帯構想 : 大平外交とアジア太平洋地域秩序の模索
- 著者
- 田 凱
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.75-107, 2007-12-21
申請者らは、幹細胞が多いとされるヒト歯髄にも全能細胞(Muse細胞)[間葉系マーカー(CD20, CD105, CD90 陽性とES細胞マーカー (SSEA-3) 陽性)が存在することを発見した。そこで、歯髄由来のMuse細胞を天蓋培養して胚様体を形成させ、これを還流培養して3胚葉性の胚子様構造物を育てる。ここから中枢神経の原基を採取し初代培養する。このなかには中枢神経を構成する細胞がone set存在しているはずである。本研究は、胚子様構造体から中枢神経原基を採取し、脳梗塞やパーキンソン病の患者に自家移植できれば、感染、免疫、倫理の問題もなく極めて安全性の高い治療を開発できると考えた。
2 0 0 0 OA 飯田下伊那の少年農兵隊 戦争末期の食糧増産隊
- 著者
- 原 英章
- 出版者
- 飯田市歴史研究所
- 雑誌
- 飯田市歴史研究所年報 (ISSN:13486721)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.131-156, 2019 (Released:2022-03-12)
2 0 0 0 OA 黙示録,ユートピア,遺産 エルンスト・ブロッホにおける「(第三の)ライヒ」論
- 著者
- 吉田 治代
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文学 (ISSN:24331511)
- 巻号頁・発行日
- vol.154, pp.82-102, 2017-03-25 (Released:2018-03-31)
Ernst Blochs Utopie mit ihrem ‚religiös-marxistischen‘ Impetus ist im späten 20. Jahrhundert in Verruf geraten. Entsprechend der berühmten Interpretation von Karl Löwith, dass das Dritte Evangelium von Joachim von Fiore sowohl als die Dritte Internationale wie auch als das nationalsozialistische „Dritte Reich“ erscheine, haben Kritiker wie K. Vondung und N. Bolz Blochs Geist der Utopie mit dem „apokalyptischen Geist“ und somit dem „philosophischen Extremismus“ identifiziert und – genauso wie Nationalismus / Faschismus – mitverantwortlich für die Katastrophen des 20. Jahrhunderts gemacht. Dass es sich hier um eine voreilige Kritik handelte, lässt Siegfried Kracauers Einschätzung des Blochschen Denkens erkennen. Auch er fand zwar in Blochs Büchern Geist der Utopie (1918) und Thomas Münzer (1921) zunächst das Manifest eines „religiösen Kommunismus“ und kritisierte, dass Bloch die politische Utopie der klassenlosen Gesellschaft mit der apokalyptisch-eschatologischen Erwartung verschränkt habe. Gegen Ende der 1920er Jahren hat Kracauer jedoch eine weitaus differenziertere Sicht entwickelt. Er sieht beim linken Philosophen einen konservativen Zug, indem dieser die Dinge nicht nur „entschleiern“, sondern auch „bewahren“ will. Damit trifft Kracauer genau das Motiv des Buches Erbschaft dieser Zeit (1935). „Zum utopischen Ende stürmen“ einerseits und andererseits „in der Welt verweilen“, „alles Gewollte, Gedachte und Geschaffene einsammeln“ – das gehört bei Bloch zusammen, und Kracauer nennt in den späteren Jahren Blochs Utopie „eine bewahrende“. (View PDF for the rest of the abstract.)
2 0 0 0 IR Jポップに見る男と女の言説 : 平成の若者の「こころもとなさ」(PART II)
- 著者
- 難波江 和英
- 出版者
- 神戸女学院大学
- 雑誌
- 女性学評論 (ISSN:09136630)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.121-142, 2002-03
This monograph is the second part of the ongoing trilogy study on discourses of heterosexual love in J-POP.This part consists of two chapters titled "Boredom and Stimulation"and"Mole>Female'&'The Weak/ The Weak'"respectively.The first chapter shows that Japanese youth are now so much inficted with boredom that they are willing to gain ready-made simulation from their love relationships in an attempt to find a way out.As proved through analysis, their boredom derives neither from the lack of stimulation nor from the excess of stimulation but from the constant saturation of srimulation.Now that they are wealthy enough to fill their basic needs for life, they wish to gain even stronger stimulation in the easiest way possible, like having a chat through a mobile phone and finfing a girl/boy friend.The second chapter shows that a majority of young people in Japan are now fascinated by having a girl/boy friend, for they believe in the myth of "Almighry Love."In this belief, both girls and boys find the most dominant discourse of love in that love makes them stronger.This suggests in effect that they start their love relationships with an assumption that both of the couple are "weak."As indicated in J-POP songs such as "sweetness"by MISIA, "B'coz I love yuo"by Hitomi Yaita, and"A Boy"by Yuzu, however, their real problem lies in their bind conceming heterosexual love : they are tied not only to the newly devised discourse of "the Weak vs.the Weak"but also to the outdated discourse of "Male>Female"that has been carried over by the generation of their parents.It is shown in conclusion that these young people are trying are trying yo diminish the fearful space distancung the couple in order to be "one" all the time and thus find no apace left to place themselves as someone.Thus their love relationships are filled with an unprecedented sense of uneasiness emerging from the failure of living alone, addiction to codependency, and the resignation of being someone, Remedial methods to cope with these issues will be clarified in the final third part of this serial study on deiscourses of heterosexual love in J-POP.
2 0 0 0 OA バングラディシュのサルフォレストにおける参加型林業の費用便益分析
- 著者
- エムディ アブデュルラ ラナ 野口 俊邦 エムディ アブデュス セレム
- 出版者
- 林業経済学会
- 雑誌
- 林業経済研究 (ISSN:02851598)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.54-61, 2006-03-01
This paper applies the cost-benefit analysis to the issue of participatory forest management (PFM) projects in Bangladesh. As economic incentive is the key factor to ensure farmers' willingness to continue in the PFM project, cost-benefit analysis of the project is very essential to understand the success of the project. To meet the objective of the study an interview-administered questionnaire survey was conducted on 146 purposively selected participated farmers whose plots were felled in 2003. The important findings of this study were (i) the PFM project was economically beneficial both for the farmers and for the government, (ii) the average amounts of farmers' share of benefit from the final felling were Tk. 37,260 in agroforestry system and Tk. 67,104 in woodlot forestry system, which were attractive amounts for a local poor households, (iii) the benefit-cost ratios were 3.54 for the agroforestry system and 2.45 for the woodlot forestry system, (iv) although the collection of total government revenues was higher from woodlot forest plots than from agroforestry plots, the benefit-cost ratio was higher in agroforestry plot than in woodlot forest plot, (v) the standard of living of 100% of the farmers had improved after receiving their share of benefits from final felling.
- 著者
- 篠木 涼
- 出版者
- 立命館大学人間科学研究所
- 雑誌
- 立命館人間科学研究 = 立命館人間科学研究 (ISSN:1346678X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.49-65, 2017-02
2 0 0 0 OA 球状トカマクの実用炉への展望 -トカマクの低アスペクト比化への挑戦- 1.特集にあたって
- 著者
- 小野 靖 西尾 敏 高瀬 雄一 長山 好夫 前川 孝
- 出版者
- 社団法人 プラズマ・核融合学会
- 雑誌
- プラズマ・核融合学会誌 (ISSN:09187928)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.11, pp.919-920, 2004 (Released:2005-07-14)
2 0 0 0 OA 「バグ捕獲・再捕獲法」を用いたソフトウェア信頼性保証について
- 著者
- 伊土 誠一
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.12, pp.2534-2542, 1993-12-15
ソフトウェアの聞発において・潜荏バグ数を精度よく推定できれぱ、効率のよい信頼性保証活動が可能となり、適切なソフトウェア聞放時期が決定できる。従来は、開発途中までのバグの発生数の経時変化を把握し、それをソフトウェア信頼度成長モデルにあてはめることにより、潜在バグ数を推定する方法が主に開発されてきた。この手法はデバグや試験のプロセス、横軸として何を採用するかが堆定精度こ大きく影響する。本論文では、バグ摘曲工程の途中のプロセスが潜在バグ数推定精度に影響を与えない特徴をもち、野生動物の頭数なぎを捧定する手段としてよく知られている「蒲獲・再捕獲法」をソフトウェアのバグ数推定に適用することを考える。それには、2つの間題を解決する必要がある。1つは、対象プログラムに埋め込んだバグをどのように選定するかである。これはバグ数の推走精度に大きく影響する。2番目は、バグ数推定のために埋め込むバグが発生することによるトラブルである。本来の品質保証作業の進捗に影響を与えないような工夫が必須である。本稿では、これらの課題を解決する「バグ摘獲・再捕獲法」を提案する。さらに、ここで提案した方法論とバグ捕獲・再捕獲法のために聞発したツールを、実際に商用に供する大規模ソフトウェアに適用した事例を紹介する。最後に、本方式とソフトウユア信頼度成長モデルとの推定精度の比較等の考察により、バグ捕獲・再捕獲法の有効性を示す。
2 0 0 0 個人間の贈与(みなし贈与を含む)と所得税法9条1項16号
- 著者
- 藤間 大順
- 出版者
- 日本税法学会 ; 1951-
- 雑誌
- 税法学 (ISSN:04948262)
- 巻号頁・発行日
- no.584, pp.187-206, 2020-11