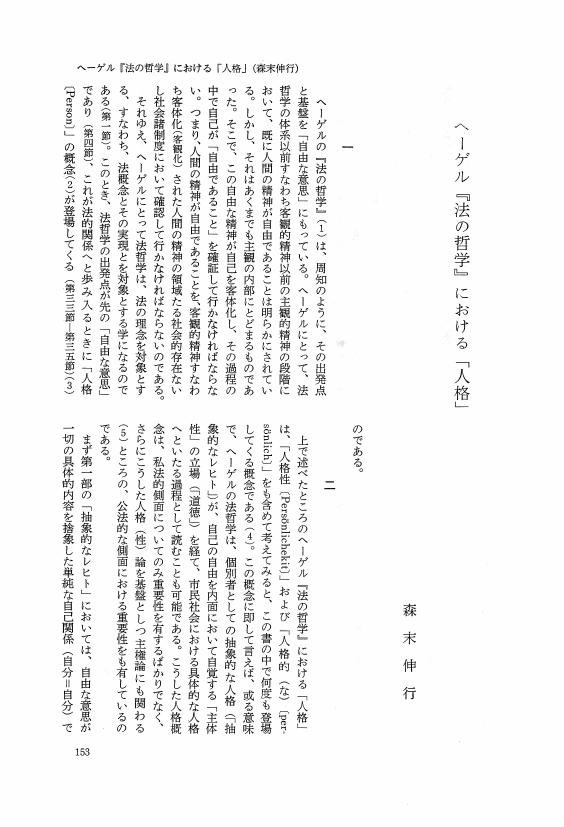- 著者
- Yuya KAWAMATA Akira EJIRI Kyohei MATSUZAKI Yuichi TAKASE Naoto TSUJII Takumi ONCHI Yoshihiko NAGASHIMA
- 出版者
- The Japan Society of Plasma Science and Nuclear Fusion Research
- 雑誌
- Plasma and Fusion Research (ISSN:18806821)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.1402072, 2019-04-11 (Released:2019-05-22)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 2
The stray light is a major problem in Thomson scattering (TS) measurements. The main cause of stray light is unnecessary divergence of the incident laser beam and an aperture is a standard component to reduce it. In order to improve the aperture configuration (including size, number and position in the laser injection tube), a peripheral beam profile monitor, consisting of a screen with a through hole for the laser beam and a CMOS camera, was developed. Instead of the actual laser injection tube a mock-up tube was used to measure the peripheral beam profiles under various aperture configurations. The configuration with four 15mm diameter apertures was chosen and installed on the TS system for the TST-2 spherical tokamak. The stray light was reduced to about 4% compared to the smaller diameter injection tube with no apertures. As a result, it became possible to make TS measurements in the electron density range above 1.0 × 1017 m−3.
2 0 0 0 IR 素朴心理学的な心の捉え方を救う方策としての道具主義
- 著者
- 杉左近 淳
- 出版者
- 東京都立大学哲学会
- 雑誌
- 哲学誌 (ISSN:02895056)
- 巻号頁・発行日
- no.45, pp.34-53, 2003
- 著者
- 森 聡太 長谷 和久 毛 新華
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.170-173, 2022-02-28 (Released:2022-02-28)
- 参考文献数
- 15
This study aimed to examine the relationship between the use of online games and the helping behavior of university students. First, we divided online games into two types, cooperative and competitive. We then examined the relationship between whether online games were used and helping behavior and the relationship between the time spent playing online games and helping behavior. The survey was conducted among 134 students at a private university in the Kansai region. The results of multiple regression analysis showed no significant relationship between game use and helping behavior scores regardless of the type of online game. Analyses focusing on the game usage time showed that the longer the usage time of competitive games, the significantly lower the helping behavior scores were. Still, no such relationship was found for cooperative games. The game usage time significantly correlated with helping behavior, and the relationship between the game usage time and helping behavior differed depending on the type of game used.
2 0 0 0 IR 日本列島の気候変動と大気・海洋の影響
- 著者
- 田上 善夫
- 出版者
- 富山大学人間発達科学部
- 雑誌
- 富山大学人間発達科学部紀要 (ISSN:1881316X)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.173-188, 2013
The climate variation involves phenomena which occur spatially and temporally from macro to micro scale.Especially, the one on the local scale is clear around the land surface. Therefore climate variation was analyzed mainly around the land surface, widely, synoptically, and locally. The climate variation in the Japanese Islands is affected by land and sea, and varies seasonally. Thus, seasonal variation around the land and sea surface was analyzed. The main results are as follows: 1) On the wide scale, the thermal state of the Eurasian Continent and the North Pacific changes to the contrary from winter to summer, and vice versa. Furthermore, the thermal state difference between the continent and the ocean is large in winter, but is small in summer. In addition, the phase of annual variation delays on the ocean. The climate variation is basically brought about by these, and it is influenced largely by the inter-annual shift of seasonal change. 2) On the meso-scale, the difference of the thermal state between the marginal sea,Yellow Sea, Sea of Japan, and Sea of Okhotsk, and the chains of islands and the peninsulas around the seas, becomes clear in spring and fall. Especially, from spring to early summer, the sea surface temperature of the marginal seas is remarkably cooler than the land surface temperature of surrounding areas. Therefore, meso-scale anticyclones are more likely to develop. In the warm current areas of the marginal seas, the difference of temperature between land and sea becomes remarkable in severe winter. And meso-scale cyclones develop. 3) On the local scale, the thermal states of the land and sea surfaces interchange between the night and the day. The difference of temperature between land and sea surfaces is small in hot summer, but it is large in severe winter. Therefore the reverse of thermal state between the night and the day is clear in hot summer, and the sea surface has a great influence on climate variation. On the other hand, the reverse is not clear in severe winter and the influence of the sea surface on climate variation is small.本年(2012),また一昨年(2010)年は,夏季に全国各地で猛暑日の出現がとくに多かった。全国17地点の平均による夏季(6-8月)気温は,2010年は1898年以降で第 1位であった(田中昌太郎・牛田信吾・萱場亙起,2012)。熊谷や多治見のほか,全国各地で同様に高温が出現する。その地球規模から局地的な要因の解析によれば,さまざまなスケールの要因が複合して影響している。たとえば,富山平野南部の昇温には山越え気流の影響が考えられる(田上善夫,2010a)。また,富山をはじめ,広域に昇温が現れるとき,暖気が涵養され,移流となる場合がみられる(田上善夫,2010b)。さらに,異常高温は,日本海側やオホーツク海沿岸などに現れる傾向があり,かつ日中に現れることが多いが,高温の出現には地域的な類似性がある(田上善夫,2011)。さらに,日によって全国最高気温の出現地点が変わるように,特定の地点のみがとくに高温となるわけではない。このことに示されるように,広域的な出現要因が基本にあるが,こうしたスケールでの大気の内部変動,総観規模での気団の出現が深く影響している。またこうした高温は,その出現前後の期間に比べた昇温としてみれば,暑夏のみならずどの季節にも出現する。むしろ夏季以外の季節では,顕著な昇温は地域的な差異が大きく,その出現過程は複雑である。従来の研究の場合,対象範囲が陸上に偏するか,あるいは広域の大気状態を対象にしているために,高層の状態が中心に解析されることが多かった。こうした気温にみられるような季節的に異なる大気状態の変動には,陸上のみならず,海上,また上層の状態が重要であるため,それらを含めての解析が必要となる。影響する現象のスケールとして,東アジアのようなおよそ2000kmのスケール,中部地方のようなおよそ200kmのスケール,富山平野のようなおよそ20kmのスケールに分けて考えることができ,それぞれについて解析を行う。
2 0 0 0 OA へーゲル『法の哲学』における「人格」
- 著者
- 森末 伸行
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1982, pp.153-159, 1983-10-10 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 28
2 0 0 0 OA 複雑ネットワーク科学の拡がり:パネル討論:ネットワーク科学の今後
- 著者
- 日比野 英彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本油化学会
- 雑誌
- オレオサイエンス (ISSN:13458949)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.11, pp.539-547, 2013 (Released:2016-02-01)
- 参考文献数
- 55
リン脂質(PL)は細胞やオルガネラの膜形成やシグナル伝達分子の機能を果たす重要な成分である。細胞間と細胞内のPL由来シグナル伝達分子は,PL分子種自身,ホスホリパーゼA(PLA1,2),ホスホリパーゼC(PLC),ホスホリパーゼD(PLD)による分解産物とそれらの代謝産物である。PL,特に特定のホスファチジルコリン(PC)分子種は核受容体に認識される。このPC分子種は転写因子を活性化し標的遺伝子を発現させ,脂質代謝を促進する。PLのPLA1,2による加水分解はリゾPL(LPL)と当モルの脂肪酸またはアラキドン酸(AA),エイコサペンタエン酸(EPA)とドコサヘキサエン酸(DHA)などを含む高度不飽和脂肪酸(PUFA)を産生する。LPLにはリゾPC(LPC)や免疫関連作用を示すリゾホスファチジルセリンなどが含まれ,PUFAからは,AAのカスケード領域が華々しく創生され,EPAはエイコサノイドとDHAはドコサノイドへの進展が観られる。PLのPLCによる加水分解はホスファチジルイノシトールが主な対象であり,プロテインキナーゼCを活性化するジアシルグリセロールと滑面小胞体からカルシウムイオンを放出させるイノシトール1,4,5-三リン酸を産生する。PLDによりPLの作用に関し,ホスホジエステラーゼ(PDE)機能による加水分解はたん白質を活性化するホスファチジン酸(PA)とコリン(Cho),セリン,エタノールアミンなどの塩基を産生する一方,塩基交換機能では中枢領域においてPCやホスファチジルエタノールアミンがホスファチジルセリン(PS)に転換され,そのPSが神経細胞膜のシグナル伝達に関与している。LPCをリゾPAとChoに加水分解する分泌型リゾPLDが細胞運動性刺激因子オータキシンであると同定された。新たに発見されたCho含有PL特異的PDEはLPCとグリセロホスホコリン(GPC)をホスホChoに分解してCho代謝を制御することが見出された。GPCはCho補給源として母乳に豊富に存在し,精液,睾丸,腎臓に存在が認められ,成長ホルモン分泌促進,肝機能障害改善などが知られ,腎臓や精巣での浸透圧調整作用との関係が深い。
2 0 0 0 OA 「科学教育研究」誌を研究成果発信の場に
- 著者
- 織田 揮準
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 科学教育研究 (ISSN:03864553)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.1-2, 1997-03-10 (Released:2017-06-30)
2 0 0 0 OA スピノザの存在論における必然性の問題 : 運命に対する人の態度を軸として
- 著者
- 富積 厚文
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.1, pp.157-181, 2013-06-30 (Released:2017-07-14)
本稿は運命に対する人の態度を軸として、スピノザ(Brauch de Spinoza, 1632-1677)の存在論における必然性の問題について考察するものである。そのためにまず、九鬼周造の学説を手がかりとして「運命」の現れ方を検討し、それが人間精神のうちにその他の考えを容れる余地を与えぬほど容易には逃れえない強烈な「表象」を抱かしめる「原因」であることを示す。次に、ライプニッツの行った対スピノザ批判を考察することを通し、「運命」の二つの顔を明らかにするとともに、人間たちは「運命」を自由に判断することができないとするスピノザの主張を確認する。そして最後に、これまでの成果を踏まえた上で、<運命の受容>に関する問題を検討する。ここでは現実的存在の基礎解析と表象としての時間の解明がなされる。結論として、スピノザの思想にそって「運命」について考えて行くと必然的に神の「恩寵」の問題に逢着することが示される。
- 著者
- 大橋 容一郎
- 出版者
- 上智大学
- 雑誌
- ソフィア : 西洋文化ならびに東西文化交流の研究 (ISSN:04896432)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.4, pp.86-88, 2010-09-15
2 0 0 0 牧草類の根の生長 : 2.根の首振り生長についての細胞学的検討
- 著者
- 広田 秀憲 中西 健
- 出版者
- 日本草地学会
- 雑誌
- 日本草地学会誌 (ISSN:04475933)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.161-169, 1976-10-25
トウモロコシ(品種ホワイトデント)の発芽種子を水耕して得た種子根の先端を採取し,パラフィン法によって10μづつの根の縦断および横断による連続切片の永久プレパラートをつくり,デラフィルドヘマトキシリン法又はゲンチアンバイオレット法によって根端組織内の核分裂像を調査した。得られた結果は次のとおりである。1)縦断切片の調査結果によると,細胞の新生から分裂を繰り返していたものが伸長を開始する位置は,表皮,皮層,中心柱の各組織によって左右がズレている。根端の細胞分裂も後部における細胞の伸長も非対称的な分布になっているが,これは根端の首振り生長を組織的な面から裏づけているものと考えられる。2)核分裂は根端から1,400μmの位置までみられる。分裂は表皮,皮層,中心柱の各々の組織に認められ,根端から510〜600μmの位置に核分裂の最大になる部位がある。3)連続横断切片の鏡検結果から分裂率(核分裂している細胞数×100/視野中の総細胞数)を求めた。これを180づつの2つの視野に分けて100μm毎に集計し,検討したところ,根端から1,400μmに至るまでに2つの視野の分裂率が6回逆転することがわかった。これは根端における核分裂像の偏在とその周期的な移動を示すものである。4)根端から7mmまでは細胞の長さが伸長し,125〜155μmになる。これは生長ホルモンの力の大きさを示すものである。また,伸長帯における細胞の長さは中心柱や皮層で長く,表皮細胞で短かい。5)根端の「曲げ」に反応する部位を知るため,まっすぐに伸びかけた種子根を逆さに立て,2日後に150〜160°彎曲した材料の縦断切片の顕微鏡写真を用いて,先端から10ヶずつの細胞の位置を直線で結んでみると,根が曲がるのは根端から1.5mmの位置であり,組織的にみると,曲がる外側の表皮,皮層の両組織の細胞の伸長が著しい。根の彎曲は分裂帯で反応するよりも伸長帯の外側の組織の細胞の伸長によって直接曲がると考えた方がよい。以上要するに,根端細胞の伸長開始部位の立体的なズレ,これを促がす核分裂像の立体的な偏在とその周期的な移動が根端の細胞の伸長開始部位の立体的なズレをもたらし,このズレは根の基部にいたるほど拡大する。根端の「曲げ」は分裂帯でなく伸長帯で刺戟を受けとめ,いつもまがりやすい状態にあるということができる。根の首振り生長は根自体のもつ内在的な生命活動の姿である。6)イタリアンライグラス,オーチャードグラス,チモシー,スーダングラス,バヒアグラス,アルファルファ,クリムソンクローバ,シロクローバの8種を用いて種子根の根端における核分裂を検討した結果,トウモロコシの種子根と同様に,分裂帯における核分裂像の立体的な偏りがみられ,これが根端の首振り生長に関係があるものと推論された。
- 著者
- 宮川 泰夫
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.51-66, 1992
- 被引用文献数
- 1
東アジアは, 国際政治経済構造の変革が, その国際工業配置体系の変容に如実に示されている地域である. とくに, 自動車産業の展開は, 戦前の日本フォード, 日本GMの生産停止と日本の国産車育成に始まり, 満州・中国への展開と, 国防経済体制の構築と密接に関連して始まった. 第二次大戦後の中国での自動車産業配置も, こうした国防経済体制配置と無縁ではなく, またその配置には, 長春第一汽車製造廠の配置にみられるように直接的には中ソの政治経済構造が, 間接的には戦前の日本の自動車工業配置が生かされている. 日華平和条約, 日韓基本条約の締結による国際工業配置体系の変容は, それぞれの国内の産業育成政策, 国防政策と関連して生じ, 内外の産業構造の変動と都市集積に左右された. 自動車工業の配置変動, 提携関係の変化は, こうした点を良く示している. この提携関係の変化は, 1972年の日中国交回復によって如実に示されはしたが, むしろ石油危機と変動相場制移行を契機とした自動車工業の内に典型的に示された日本工業の国際競争力強化や海外展開と深く関連して基本的には生じてきた. そして, 日米間の政治・経済構造の変革がその大枠を規定したが, 1975年の十堰の第二汽車製造廠設立に示される中ソの政治経済構造の変質もその国際工業配置体系には微妙に影響している. 1978年の中国経済開放政策は, 日本・香港・台湾を含む東アジアの工業配置を変質させ, 1985年からの台湾, 旧ソ連の変革, 88年のオリンピックを契機とした韓国の変質とあいまって, 自動車工業に典型的に表われているように東アジアに新たな錯綜した国際工業配置体系を欧・米をも巻きこんで形成しつつある.
- 著者
- 高橋 綾 宇田 恵
- 出版者
- 環境芸術学会
- 雑誌
- 環境芸術 : 環境芸術学会論文集 (ISSN:21854483)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.21-28, 2009-03-31
この「あかりアートプロジェクト」は、人の内面に響く力を持つ「あかり」をテーマにした作品を制作・展示することにより「人の心を癒す」という効果を病院という環境において得、ひいてはその環境に美術を根付かせるきっかけになれば、という考えから始まった。大学のある群馬県玉村町地域で唯一の内科系病院である角田病院に大学側から提案され、これまで、以下のように、その狙いの下に学生の作品の展示、そのツアー発表が行なわれて来た。・2006年「癒しのあかり展」学生作家(11名12作品)(開催期間:展覧会6月20日〜7月3日/ツアー6月24日) ・2007年「コミュニケーションから生まれたあかり展」学生作家(9名13作品)(開催期間:展覧会7月10日〜30日/ツアー7月28日)この企画の進行に伴い、学生の態度に主体的な変化が生まれただけでなく、健康診断に始まり、次いで病院側が広報誌のデザインを大学へ依頼したことから進展した当病院と大学とのアートを媒介にした共同関係は更に深まることとなった。病院側にも美術を受け入れる自然な姿勢が生み出されたが、この当企画の継続により、病院関係者の自分達の環境美化の可能性とその必然性に対する意識を更に深化させたいと考えている。
2 0 0 0 OA 胎内音刺激による新生児聴性反応の記録
- 著者
- 村本 多恵子 山根 仁一 田中 美郷 阿波野 安幸
- 出版者
- Japan Audiological Society
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.4, pp.244-249, 1991-08-31 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 14
泣いている新生児に胎内音をきかせると体動を停止して泣き止むことが知られている。 この反応を新生児の聴覚スクリーニングとして用いるため, 自動的に記録できる装置を開発し, 正常成熟新生児47例と, 周産期に異常の認められた新生児11例について反応を記録した。 反応の有無の判定は極めて容易であつた。 正常成熟新生児47例の胎内音をきかせた場合 (on記録) の反応出現率は46.3%, 胎内音をきかせない状態 (off記録) で偶然に体動を停止する率は24.2%で, 胎内音をきかせたほうが新生児が泣き止む確率が明らかに高かった。 個々の新生児についてみると, on記録の反応出現率がoff記録の見かけ上の反応出現率を下回ったのは, 47例中1例のみであった。 一方, 周産期に異常の認められた新生児では, 泣き続ける力が乏しいなため, off記録での体動停止の確率が高く, そのため, これらの新生児の聴覚のスクリーニングとしては十分に有効とはいえなかった。
2 0 0 0 OA 透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについての提言
- 著者
- 透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについての提言作成委員会
- 出版者
- 一般社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.4, pp.173-217, 2020 (Released:2020-05-21)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 3 13
2 0 0 0 イラン-イラク戦争における化学兵器使用の実態
- 著者
- 水谷 営三
- 出版者
- 日本中東学会
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.323-351, 1993-03-31
The extensive use of chemical weapons by Iraq both against Iranian soldiers and its own Kurdish population was one of the most hideous aspects of the Iran-Iraq War (1980-1988). Based on American and Japanese newspaper reporting, this study includes a detailed chronology of dates and places of the use of the chemical weapons by Iraq in the war. This is the first of its kind in Japanese. It is hoped that the chronology will serve as source material for further study of the Iran-Iraq War. It is also the strong wish of this author that the study will contribute, however tangentially, to the abolition of chemical weapons by highlighting their inhumane nature.
2 0 0 0 OA 木村駿吉の四元数理解と「万国四元法協会」の提案
- 著者
- 益田 すみ子
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- 科学史研究 (ISSN:21887535)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.287, pp.168-185, 2018 (Released:2021-01-24)
Shunkichi Kimura (1866-1938) studied quaternions during his stay in the U.S. from 1893 to 1896. In particular he deepened and widened his understanding of quaternions. Kimura was first introduced quaternions by one of Scottish teachers who were working in early Meiji Japan. These teachers were former students of Peter Guthrie Tait (1831-1901) at Edinburgh University. Tait had developed quaternions to apply to geometry and physics. One of his key ideas was that quaternions transform vectors as operators. Taitʼs students taught Japanese students, including Kimura, only Taitʼs style of quaternions aiming at application to physics and engineering. But in the U.S. Kimura found that quaternions were not only operators for transformation of vectors but also the expanded complex numbers. He recognized the need for more exchange between scientists interested in quaternions and allied systems of mathematics, and hoped promoting quaternions as pure mathematics. So he proposed for an “International Association for Promoting the study of Quaternions and Allied Systems of Mathematics” in 1895. His enthusiasm for quaternions as pure mathematics was his primary motive of this proposal. Because of difficulty of finding a president and secretaries, only in 1899, after Kimuraʼs return to Japan, was this association established by Scottish and Irish scientists and it remained active for fourteen years. Kimuraʼs proposal for this association also shows how productive he was during his three year study in the U. S.
2 0 0 0 OA 脳死状態と蘇生限界
- 著者
- 真船 えり
- 出版者
- 科学基礎論学会
- 雑誌
- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.85-90, 1996-03-31 (Released:2009-07-23)
- 参考文献数
- 33
2 0 0 0 大正初期における陸軍の政党観--田中義一を中心として
- 著者
- 坂野 潤治
- 出版者
- 錦正社
- 雑誌
- 軍事史学 (ISSN:03868877)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.4, pp.p54-62, 1976-03