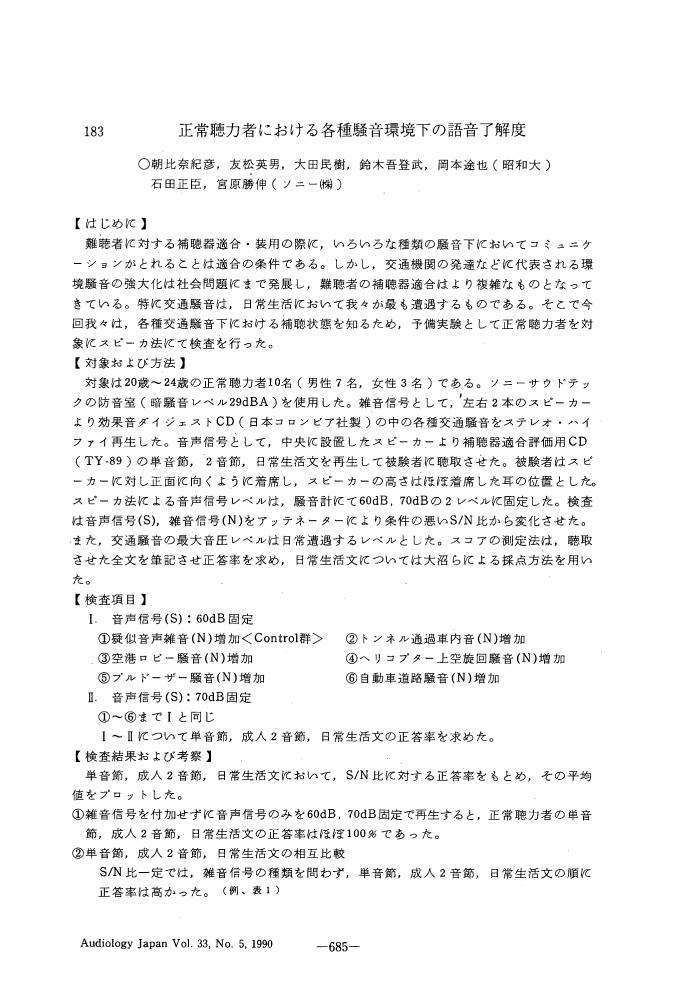1 0 0 0 OA 〈研究ノート〉社会空間の感性的質について
- 著者
- 宮原 浩二郎 Kojiro Miyahara
- 雑誌
- 関西学院大学社会学部紀要 (ISSN:04529456)
- 巻号頁・発行日
- no.126, pp.81-89, 2017-03-15
1 0 0 0 OA 三菱電機株式会社 デザイン研究所
- 著者
- 宮原 浩二
- 出版者
- 一般社団法人 システム制御情報学会
- 雑誌
- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.12, pp.548-549, 2016-12-15 (Released:2017-05-15)
- 著者
- 岡部 光 宮原 由美 山内 辰郎
- 出版者
- 天然有機化合物討論会
- 雑誌
- 天然有機化合物討論会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.95-102, 1981-09-10
An extensive survey for the triterpenoid constituents of Momordica charantia L. has been carried out in this laboratory, and so far, five glycosides (momordicosides A-E) of cucurbit-5-ene derivatives were isolated from the seeds, and their structures were determined. They are unique cucurbitacins being highly oxygenated only in the side chain and having no oxygen function at C_<11>. This study concerns the structure elucidation of two bitter glycosides, momordicosides K and L, and four non-bitter glycosides, momordicosides F_1, F_2, G and I isolated from the fruits. The structure of F_1 was proposed as 3-O-β-D-glucopyranoside of 5,19-epoxy-25-methoxy-5β-cucurbita-6,23-dien-3β-ol on the basis of PMR, CMR and CD spectral data and chemical conversion into a cucurbit-5-ene derivative. G is the corresponding β-D-allopyranoside. F_2 and I are the C_<25>-OH derivatives corresponding to G and F_1, respectively. K and L were determined as 7-O-β-D-glucopyranosides of 19-oxo-25-methoxy-cucurbita-5,23-diene-3β, 7β-diol and its C_<25>-OH derivative, respectively, on the basis of spectral data and chemical correlation with F_1-aglycone. F_1, F_2, G and I are the first cucurbitacins having 5β-cucurbitane nucleus found in nature, and K and L are noted as the new cucurbitacins having C_9-aldehyde and 7-O-β-D-glucopyranosyl groups. Among momordicosides, G and F_2 are the first triterpenoid glycosides having D-allose as a component sugar.
- 著者
- 木村 栄一 斧田 太公望 宮原 光夫 金沢 知博 新谷 博一 水野 康 早瀬 正二 高安 正夫 戸山 靖一 木村 登 奥村 英正
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.347-358, 1974
新しく開発された抗不整脈薬prajmalium(propylajmaline)の経口投与による効果を,群問比較による二重盲検法を用いてajmalineおよびinactiveplacebo のそれと比較した.1分間数個以上の期外収縮を有する78例に上記薬剤を1週間投与し,来院時における期外収縮数の減少度を目標として,3薬間の比較を行なったが,有意の差はえられなかった.しかし分析の結果,1分間10個以上の期外収縮を有する例を対象とするならば,prajmaliumがajmalineおよびinactiveplaceboより有効だという成績がえられるであろうとの推定がなされた.一方,主治医の評価による総合判断を用いた時には,3群間に有意の差のあること,さらにprajごnaliumがi捻activeplac¢boより有意の差をもってすぐれていることが知られた.また多変量解析により分析を行なうに,期外収縮数の消艮,心拍不整感およびめまいが主治医の総合判断に強く影響していることが知られた.なお,本剤は発作性心頻拍や発作性心房細動の予防にも有効であることが期待されるが,症例数が少ないため参考データとするに止めた.本剤の副作用として最も重大なのは肝機能障害の発生であるが,分析の結果,心胸比の大きな例でS-GOTの上昇をきたしやすいことがわかった,したがって心臓の大きなもの,始めからS-GOTや3GPTの高いものには,投薬にさいし注意することが必要である.
1 0 0 0 下位脳神経障害をきたした帯状庖疹の1例
- 著者
- 宮原 伸之 白根 誠 上田 勉
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 補冊 (ISSN:09121870)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.117, pp.126-129, 2006
Varicella-zoster virus often causes not only vesicles, but also facial and vestibular nerve paralysis (Ramsay Hunt syndrome). This syndrome can affect other cranial nerves. We report a case of unilateral palsy of the V, VII, IX, and X cranial nerves due to varicella-zoster virus infection.
1 0 0 0 OA 輝尽性蛍光材料を用いたコンピューテッド・ラジオグラフィー
- 著者
- 宮原 諄二 加藤 久豊
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.10, pp.884-890, 1984-10-10 (Released:2009-02-09)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 8
従来のレントゲン写真は(蛍光スクリーン/フィルム)システムでX線像を可視化したものである.このシステムに代る新しいデジタルラジオグラフィーシステムの開発が各国で進んでいる,輝尽性蛍光材料をX線像の検出とメモリーの二つの機能に用い,デジタル画像処理システムと組合せたコシピューテッドラジオグラフィーシステムもその一つであり,多くの臨床上の有用な効果が明らかになってきている.このシステムは,古くから知られている固体結晶中のカラーセンターとルミネッセンスを,最新のエレクトロニクスとコンピューター技術に結びつけ,古きものの中に新らしい血を注いだ「温故知新」の技術開発の一つの例としてあげられよう.
1 0 0 0 OA 林友春編近世中国教育史研究
- 著者
- 宮原 兎一
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.5, pp.51-53, 1958-10-30 (Released:2009-01-13)
1 0 0 0 OA 超音波定在波による液中気泡の制御とその応用
- 著者
- 梶山 智晴 富田 裕之 宮原 裕二
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌E(センサ・マイクロマシン部門誌) (ISSN:13418939)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, no.10, pp.464-469, 1999-10-01 (Released:2008-12-19)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1 1
We have developed a new method for cleaning flow-through cells by using microbubbles and ultrasonic (US) standing waves. A standing wave generated by US transducers at 1 MHz was used to trap microbubbles at node positions of the sound pressure. We were also able to control the microbubbles' positions spatially through frequency modulation. We found that these microbubbles were very effective for washing microbeads out of flow-through cells, particularly when frequency-modulated US irradiation was used. The proposed method promises to be very useful for cleaning the flow-through cells in small analytical instruments.
1 0 0 0 Diamond Mandala Matrixを用いて作成したWork Breakdown Structureが大学生の行うプロジェクトを成功に導く : 事例報告(<特集>プロジェクトの計画と評価)
- 著者
- 宮原 勅治 岸野 孝裕 稲葉 舞香 田邊 央樹 中西 淳 出原 雄太 横田 貴久
- 出版者
- プロジェクトマネジメント学会
- 雑誌
- プロジェクトマネジメント学会誌 (ISSN:1345031X)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.21-24, 2015-06-15
プロジェクトマネジメントにおいてWork Breakdown Structure(WBS)が極めて重要な役割を果たすことは周知であるが,大学生のようなプロジェクトマネジメントの初学者にとって,WBSを上手く作成することは容易なことではない.そこで,大学生のプロジェクトチームにWBSを作成させるためのトレーニングとして,仮想プロジェクトを用いたWBS作成の教育方法を開発した.すなわち,WBSを作成するツールとしてDiamond Mandala Matrix(DMM)を用いる方法である.このDMMを使って作業分解を行い,WBSを作成する手法は,大学生のようなプロジェクトマネジメントの初学者においても理解しやすく,実際の卒業研究プロジェクトにも使用することができ,学生にとって極めて有用なトレーニング方法となる.本稿では,大学生のプロジェクトチームに対し,DMMを用いて仮想プロジェクト(たこ焼き模擬店プロジェクト)のWBSを作成するトレーニングを行った後,実際の卒業研究プロジェクトにおいても同様にWBSを作成し,プロジェクトを完遂させた事例を報告する.
1 0 0 0 OA 臨床実習学生に質問行動の増加を促したことが能動的な行動変容へ与えた影響について
- 著者
- 由谷 仁 梶原 秀明 宮原 正文 中根 博
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.38 Suppl. No.2 (第46回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.GaOI2055, 2011 (Released:2011-05-26)
【目的】 情意領域の低下、特に「自発性のなさ」が問題となる臨床実習学生(以下、学生とする)の指導は、臨床実習指導者(以下、指導者とする)の心的負担を著しく増加させる。そこで、臨床実習を円滑に遂行するため、指導者にとって負担の少ない指導方法を確立させることは急務であるが、現状は各病院や各指導者の裁量次第で明確な方法は示されていない。当院では臨床実習の位置付けとして、平成21年より「受動的教育」から「能動的教育」へ行動変容させることを最重要課題とし、続いて国家試験の知識を習得することを目的として掲げている。辻下は、行動分析学的アプローチは有効な行動変容法であると述べており、学生に行動変容を促しつつ指導者に負担の少ない指導方法を模索してきた。 今回は、情意領域に問題があると指摘された学生に対し、行動分析学的アプローチを用いた「質問行動の増加」という介入を行い、その効果をシングルケースデザインにより検討し報告する。【方法】 対象は当院での臨床実習にて情意領域の低下が指摘された理学療法士学科最終学年、30代、男性、1名。方法は畑山らの報告を参考にし、実習期間をベースライン期(2週間)、介入期(4週間)、非介入期(2週間)に分け、まずベースライン期終了時にターゲット行動の明確化を図るため中間評価を行った。その際、特に低下がみられ問題とした「自発性のなさ」に対し、「質問行動の増加」をターゲット行動と設定した。 介入期は「質問行動の増加」のため、学生に自ら質問を行い、その内容を質問行動記録表に記載するよう指導した。また、質問のルールとして自分の考えを可能な限り述べることとした。先行刺激は、質問数に応じて臨床実習総合評価の情意領域に関して15回/週以上で「可」、30回/週以上で「良」にすること、質問に関して否定的なコメントはしないこと、必要以上に課題を出さないことを約束した。後続刺激は、質問行動が見られた直後に指導者側から賞賛することを徹底し、週末に学生と1週間分の質問内容を確認した。 非介入期では質問行動記録表への記載は継続させたが、後続刺激は与えなかった。調査内容は質問行動数(自分の考えを述べた質問数/全体の質問数)、臨床実習評価(当院独自、各項目4点満点で良好4点、普通3点、やや劣る2点、劣る1点)とした。なおベースライン期の質問行動数はデイリーノートより作成した。加えて最終週は3日間のみのデータ収集となった。【説明と同意】 学生には本報告の主旨、本データを報告以外に使用しないこと、未同意でも不利益を受けないことなどを実習終了時に説明し、紙面にて同意を得た。【結果】 1週間の平均質問行動数はベースライン期で0/0.5(0%)回、介入期で16.3/32.3(50.4%)回、非介入期で16.3/31.3(52.0%)回であり、介入期で増えた回数を非介入期でも維持できた。臨床実習評価による全領域の平均は、2週後2.6点、4週後2.4点、6週後2.5点、最終2.5点と若干の変化であった。そのうち、情意領域だけの平均は、2週後2.5点、4週後2.6点、6週後2.7点、最終2.8点と改善傾向はみられたが大幅な変化ではなかった。【考察】 ベースライン期ではほとんどなかった質問行動自体は、介入期より増加し非介入期でも継続してみられたため、質問行動自体の定着は図れたと考えられる。しかし、臨床実習評価の平均点数に大幅な変化がなかったことを考慮すると、当院で目的とした能動的な行動変容までは至らなかったと考えられる。これは質問行動数の結果より、先行刺激で与えた30回/週以上で「良」との質問数を若干超えた値が多く、質問行動数自体が目的となっていたためと考えた。臨床実習教育の手引き-第5版-によれば内発的動機づけには知的好奇心が必要で、その知的好奇心は環境に変化を起こせたという有能感あるいは達成感が動機づけに重要となると述べられている。今回、知的好奇心を促せなかったことが、能動的な行動変容まで至らなかった原因ではないかと思われた。今後は、知的好奇心を促すために、人の役に立つという視点で指導方法を模索し、能動的な行動変容を促す方法の確立に取り組んでゆきたい。【理学療法学研究としての意義】 臨床実習教育において自発性のなさが問題となる学生に対し、受動的から能動的への行動変容を起こさせる簡便かつ、有効な指導方法が確立出来れば大変有意義なことである。
1 0 0 0 OA 正常聴力者における各種騒音環境下の語音了解度
- 著者
- 朝比奈 紀彦 友松 英男 大田 民樹 鈴木 吾登武 岡本 途也 石田 正臣 宮原 勝伸
- 出版者
- 日本聴覚医学会
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.5, pp.685-686, 1990-10-15 (Released:2010-04-30)
1 0 0 0 OA 宇宙線生成核種・炭素14の超高精度分析による宇宙線異常増加イベントの年代決定
1 0 0 0 兵庫県におけるソデイカ釣り漁法の変遷
- 著者
- 宮原 一隆 武田 雷介
- 出版者
- 兵庫県立農林水産技術総合センター
- 雑誌
- 兵庫県立農林水産技術総合センター研究報告 水産編 (ISSN:13477757)
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.25-29, 2005-11
- 被引用文献数
- 1
兵庫県但馬地域におけるソデイカ釣り漁法について,漁法の開発過程と変遷を整理した。1960年代初期に,竹竿,30-60mの釣り糸,生鮮餌を用いた夜間の一本釣り漁業が地域的に開始された。1967年に,より効率的な漁獲を目的として延縄式と立縄式の諸漁法が導入された。その後,多くの試行錯誤を経て1960年代後期には日中操業の「樽流し立縄漁法」が確立された。漁具漁法の主要な改良は1980年代には完了していたため,1990年代以降のソデイカ来遊資源の高水準期を迎えるにあたり,漁獲努力の迅速かつ効率的な投入が可能になったと考えられた。これらの漁法は,日本海の各沿岸海域や,沖縄,鹿児島,東京(小笠原)の島嶼部でも広く導入されることとなった。
1 0 0 0 OA 牛腎石の超音波映像所見と剖検所見との関連
- 著者
- 山田 明夫 宮原 和郎 井上 千春 亀谷 勉
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.10, pp.709-713, 1988-10-20 (Released:2011-06-17)
- 参考文献数
- 14
著者らは先の報告で, 乳用経産牛の腎石の存在状況と組成を検索し, その96.4%の症例に腎石が存在し, 潜在性尿石症が高率に認められたことから, 牛尿石症に対する早期診断法の0確立の必要性を強く指摘した.今回は超音波検査による牛尿石症の早期診断の可能性を検討する目的で, 牛62例の腎臓78検体 (右腎62検体, 左腎16検体) での超音波映像所見と剖検所見との関連を検索した.超音波所見で78検体中52検体に腎石の存在が指摘され.腎石エコーの形状は, 3タイプに分類された.タイプI (5検体) は, 腎杯内に貝殻状の結石エコー (SE) とその後方にSEと同じ幅の音響陰影 (AS) が見られたもので, 剖検所見では全例とも腎杯を満たすように腎石が存在していた. タイプII (33検体) は, 5~10mmの斑状SEとその後方に明瞭な線状のASが観察されたもので, 剖検所見では全例とも腎杯内に10mm程度の腎石が単在または1.5mm程度の腎石が10数個集まって存在していた.タイプIII (14検体) は, 点状あるいは不明瞭なSEとその後方に細い線状のASが観察されたもので, 剖検所見では1検体を除いて, 米粒大の腎石が単在あるいは0.5mm程度の微細な腎石が集まって存在していた.超音波所見で腎石エコーの存在が指摘できなかった26検体中4検体は, 剖検所見で腎石が存在したが, 腎石の大きさはいずれも3.5mm以下であった.超音波縁による腎石の有無の的中率は93.6%で, 2~4mm程度の腎石が存在すれば, これを超音波所見で指摘できたことから, 超音波検査法は牛尿石症の早期診断法としてきわめて有用であると思われる.
- 著者
- 宮原 牧子
- 出版者
- 筑紫女学園大学
- 雑誌
- 筑紫女学園大学・筑紫女学園大学短期大学部紀要 (ISSN:1880845X)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.43-55, 2016
1 0 0 0 OA “輝き感”を発生させる物理要因の発見と検討
- 著者
- 石川 智治 三井 実 熊谷 隆富 日比野 靖 宮原 誠
- 出版者
- 日本感性工学会
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18828930)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.4, pp.1021-1024, 2009-03-31 (Released:2016-01-25)
- 参考文献数
- 7
We have found that the sense of brilliant observed from an image is deteriorated by a digital processing of granular noise reduction. By seven grade subjective assessment tests about “sense of brilliant” removing and adding isolated impulsive dots, “sense of brilliant” was deteriorated “-2”(reduction) and improved “+1”(addition). We have found the more than 5.4% isolated impulsive dots of total pixel greatly generated “sense of brilliant”.
1 0 0 0 PN-6 スペースライン フィール21の開発コンセプトにていて
- 著者
- 宮原 征人
- 出版者
- 一般社団法人日本歯科理工学会
- 雑誌
- 歯科材料・器械. Special issue, 日本歯科理工学会学術講演会講演集 (ISSN:02865858)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.22, pp.104-105, 1993-08-20
今回、紹介するユニット スペースラインフィール21は、人間の持つ固有感覚に基づき開発されたもので、開発コンセプトは、(1)Top Level Patient Relation Ship (2)Top Level SKill For Treatment (3)Top Level Infection Controlである。その結果、最もシンプルで容易な診療行為を行える新ユニットを開発したので紹介する。