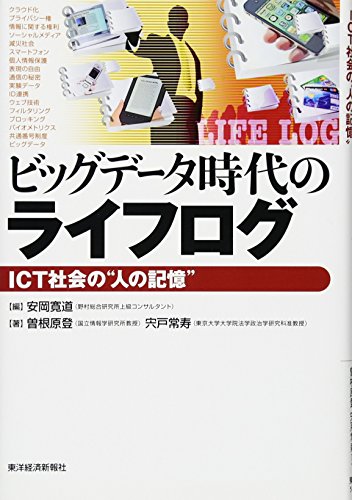5 0 0 0 OA 「情報」とはなにか 第4回 ■情報×実世界:情報とモノが溶け合う融合社会
- 著者
- 曽根原 登
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:13471597)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.6, pp.429-435, 2017-09-01 (Released:2017-09-01)
3 0 0 0 OA プレプリントへの長期署名付与および検証システムの構築
- 著者
- 山地 一禎 片岡 俊幸 行木 孝夫 曽根原 登
- 出版者
- 情報知識学会
- 雑誌
- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.3, pp.240-248, 2008 (Released:2008-11-15)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2 2
数学や物理学などの分野では,プレプリントの公開により研究成果の先取権が確保される.現在では,印刷物の出版と共に,電子ファイルをインターネット上で公開する方式が主流となっている.今後,電子ファイルのみの公開となった場合,プレプリントの存在と非改ざん性が担保される内容証明が重要になる.本研究では,ボーンディジタル時代におけるこうした問題に対して,電子署名とタイムスタンプから構成される長期署名を適用し,プレプリントをよりセキュアに流通できる学術コンテンツの内容証明システムを開発した.また,長期署名付きコンテンツを入手したユーザが手軽に内容検証をできるように,長期署名検証サーバの構築を行った.
3 0 0 0 学術機関のためのサーバ証明書発行フレームワーク
- 著者
- 島岡 政基 西村 健 古村 隆明 中村 素典 佐藤 周行 岡部 寿男 曽根原 登
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 B (ISSN:13444697)
- 巻号頁・発行日
- vol.J95-B, no.7, pp.871-882, 2012-07-01
通信の安全を確立するサーバ認証を適切に行うには,パブリック認証局から発行されたサーバ証明書が必要である.しかしながら,過去にはパブリック認証局から発行を受けることの重要性が正しく認識されてこなかったことがあり,更には商用のサーバ証明書は審査手続きが煩雑な上に学術機関の実態に沿っていないなどの課題もあったため,学術機関におけるサーバ証明書の普及は遅れていた.そこで筆者らは,学術機関のために最適化したサーバ証明書発行スキームと,証明書自動発行支援システムからなる学術機関のためのサーバ証明書発行フレームワークを提案した.国立情報学研究所による実証実験と本運用を通じて,同スキームにより高い身元確認レベルを確保しつつ審査手続きの学術機関最適化を,また同システムにより認証事業者の証明書発行業務を自動化するとともに各学術機関が必要な学内システムを用意した場合には学術機関側の工数削減も可能であることを実証した.
- 著者
- 曽根原 登 宮澤 一洋 奥村 貴史 北村 紗衣
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.5, pp.241-250, 2017-05-01 (Released:2017-05-01)
- 著者
- 原 直 笠井 昭範 阿部 匡伸 曽根原 登
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. LOIS, ライフインテリジェンスとオフィス情報システム (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.113, no.479, pp.29-34, 2014-02-28
本研究ではあらゆる環境音を対象とした集合知としての環境音データベース構築を目的とする.例えば,環境音の一つとして環境騒音問題を考えると,車や鉄道などの特徴的な音だけではなく,道や公園の賑わいのような生活雑音も考慮する必要がある.しかし,日常的かつ広範囲な音を少人数で収録することは容易ではない.そこで,クラウドソーシングによる収録を行うことで,環境音測定に必要な膨大な空間を覆うことを目指す. Android OSを搭載したスマートデバイスで動作するアプリケーションの試作を行い,さらに収録音の集積と閲覧のためのサーバシステムの試作を行った.また,スマートデバイス搭載のセンサ群の精度を検証するために,騒音レベルの校正と環境音収録実験を行った.実験では900分の環境音データを収録し,収録された騒音レベルと主観的な評価値の関係性を分析した.
- 著者
- 小林 哲郎 一藤 裕 曽根原 登
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 D (ISSN:18804535)
- 巻号頁・発行日
- vol.J95-D, no.4, pp.834-845, 2012-04-01
提供されたライフログの管理や匿名化に関する情報セキュリティ的研究が進む一方,ライフログ提供者の心理的抵抗や提供を促進するインセンティブや制度に関する研究は不足している.そこで本研究は,ライフログ提供を促進する有効な制度設計のための基礎的な知見を提供することを目的に,ライフログ調査研究への参加依頼を実験刺激として,収集するライフログの種類,金銭的謝礼の金額,対価として提供されるライフログ活用サービスを要因操作した無作為配置被験者実験を行った.その結果,コミュニケーション履歴を提供することへの心理的抵抗が最も強く,GPS位置情報を提供することへの心理的抵抗は比較的弱いことが明らかになった.また,金銭的謝礼はライフログ提供を促進するがその効果は非線形であることが示唆された.一方で,レコメンデーションサービスやライフログ可視化サービスはライフログの提供を促進するインセンティブとしての効果が見られなかった.これらの知見を総合することで,できるだけ潜在的提供者の心理的抵抗を緩和しながらライフログの提供を促進する方法について考察を行った.
2 0 0 0 大学間認証連携のためのキャンパスPKI共通仕様
- 著者
- 谷本 茂明 島岡 政基 片岡 俊幸 西村 健 山地 一禎 中村 素典 曽根原 登 岡部 寿男
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 B (ISSN:13444697)
- 巻号頁・発行日
- vol.J94-B, no.10, pp.1383-1388, 2011-10-01
全国大学共同電子認証基盤(UPKI)プロジェクトでは,大学間PKI連携及び構築コスト削減等を実現するキャンパスPKI共通仕様を新たに開発した.本仕様が,PKI連携とコスト削減を同時に満足し,キャンパスPKI普及促進に寄与することを示す.
2 0 0 0 OA 大学間連携のための全国共同認証基盤UPKIのアーキテクチャ設計
- 著者
- 島岡 政基 片岡 俊幸 谷本 茂明 西村 健 山地 一禎 中村 素典 曽根原 登 岡部 寿男
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 B (ISSN:13444697)
- 巻号頁・発行日
- vol.J94-B, no.10, pp.1246-1260, 2011-10-01
国立情報学研究所(NII)では,平成17年度より大学間連携のための全国共同電子認証基盤(UPKI)の構築を行ってきた.UPKIは,コンピュータや学術コンテンツ等を大学間で安全・安心かつ効果的に共有し活用するための基盤として,PKI(公開鍵認証基盤)を中軸に利用者や利用機関の認証とサービスの認可の機能を提供する.本論文では,学術機関における認証の必要性と制約,対象とするサービスの多様性,既存の各種認証基盤との整合性などを考慮して設計した3層(オープンドメイン層,キャンパス層及びグリッド層)のPKIからなるUPKIの基本アーキテクチャについて解説するとともに,設計方針に基づく各層の実装及び連携方法などについて述べる.
2 0 0 0 ウェアラブルコンピュータ用キーボード FingeRing
- 著者
- 福本 雅朗 平岩 明 曽根原 登
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌. A, 基礎・境界 (ISSN:09135707)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.2, pp.460-470, 1996-02-25
- 被引用文献数
- 22
将来の携帯情報環境には,「装着」するタイプの携帯機器が適している. 腕時計や眼鏡のような超小型のコンピュータを常時身につけておくことによって, 日常生活のあらゆる場面において, 欲しい情報に即座にアクセスすることができる. 本報告では, 装着使用を前提とした入出力インタフェースのありかたについて考察し, その一例として, 加速度センサを用いた指輪型キーボードであるFingeRing (フィンガリング) を提案する. FingeRingは, 大腿部や机の上など, あらゆる場所で即座にタイピングが可能であり, 立位若しくは歩行中の入力も可能である. 更に, FingeRingに適用されるシンボル生成方式として, 順序打鍵併用型の和音入力方式を提案し, 打鍵評価実験によって, 使用すべき指の組合せを抽出した. 鍵盤楽器の経験者では, 本方式によって, 200個/分を超える速度で52種のシンボルを入力することが可能である.
1 0 0 0 デジタル画像の半開示とその認知特性
- 著者
- 金子 利佳 釜江 尚彦 曽根原 登
- 出版者
- 一般社団法人 画像電子学会
- 雑誌
- 画像電子学会年次大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.33-34, 2006
デジタル画像をインターネットで販売するためには,画像の概略を見せ,購入の決断を促すことが大切である.本研究では,半開示された画像に対する人の認知特性について検討した.実験の結果,画像の同定成績は画像をスクランブル化する範囲の大きさに影響を受けることが示唆された.
1 0 0 0 OA 筋電操作ハンドの制御のための皮膚表面筋電信号のニューラルネットによる認識
- 著者
- 平岩 明 内田 典佳 下原 勝憲 曽根原 登
- 出版者
- The Society of Instrument and Control Engineers
- 雑誌
- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.216-224, 1994-02-28 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 8 15
The cybernetic interface through which users can communicate with computers “as we may think” is the dream of human-computer interactions. Aiming at interfaces where machines adapt themselves to users' intention instead of users' adaptation to machines, we have been applying a neural network to realize electromyographic (EMG)-controlled slave hand. This paper proposes that EMG patterns can be analyzed and classified by a neural network. Through experiments and simulations, it is shown that recognition of finger movement and joint angles in dynamic finger movement can be successfully accomplished.A 3-layred back-propagation network is used for finger action recognition from 1 or 2ch surface EMG. In the case of static fingers' motions recognition, 5 categories were classified by the neural network and the recognition rate was 86%. In the case of joint angles estimation in continuous finger motion, the root mean square error was under 25 degrees for 5 fingers 10 joints angles' estimations.Cyber Finger with 5 fingers 10 joint angles was realized to be controlled by 2ch surface EMG. The slave hand was controlled smoothly and voluntarily by a neural network.
1 0 0 0 セキュアデジタルシネマコンテンツ伝送の考察
- 著者
- 小池 真由美 小暮 拓世 藤井 寛 曽根原 登
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告オーディオビジュアル複合情報処理(AVM) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, no.23, pp.61-65, 2005-03-11
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
数あるセキュアコンテンツ伝送方式の中でデジタルシネマコンテンツは固有の課題を抱えている。2K/4Kレベルの2時間動画をファイル化してネットワーク転送する事は、経済性や信頼性の面であまり得策ではなく、ストリーム型やそれに準じた配信方式が当面多用されると思われる。一方、配給会社のセキュリティー政策の違いや上映シアターの端末等の多様性を考慮すれば、端末では、共通プラットホーム的なDRMの相互運用性を確保することが要求されよう。本稿では、デジタルシネマの配信を考慮したセキュアコンテンツ配信についてのDRM標準方式の実装検証とそこから浮上した技術課題について考察する。ISO/IEC, MPEG-2 system standard consist from stream configuration including MPEG-2 IPMP part. MPEG-2 system stream can transfer Digital Cinema Content securely by using MPEG-2 system IPMP function where PSI(Program Specific Information) portion. Originally this PSI can use for broadcast contents carriage however this PSI also can map IPMP standard for secure interoperable compatible DRM system.This paper describe the implementation study of this high level standard actually on the practical terminal and through this feasible study try to find out the necessary middle layer standard interface for practical application. Actual amendment proposal will be necessary for this purpose.
1 0 0 0 コンテンツ流通における不正利用防止技術
- 著者
- 廣田 啓一 曽根原 登
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会誌 (ISSN:09135693)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.10, pp.823-828, 2005-10-01
- 被引用文献数
- 8
近年, 個人によるコンテンツの不正利用として, 音楽や映画などのネット上での交換, 雑誌やコミック, アイドルの写真集などのインターネット上への無断公開など, 著作権を侵害する行為がカジュアル化し, 大きな問題となっている.本稿では, コンテンツ流通における不正利用防止技術の現状, 技術的な課題, 将来展望について解説する.
1 0 0 0 テキストインデキシング方法の提案
- 著者
- 沼田 秀穂 池田 佳代 釜江 尚彦 曽根原 登
- 出版者
- The Institute of Image Electronics Engineers of Japan
- 雑誌
- 画像電子学会年次大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- pp.101-102, 2006 (Released:2008-09-02)
本稿ではディジタル書籍、特許文書、学術文書、新聞社説などのディジタル文書を対 象に、自動的にキーワード付与を行うインデキシングの実用的な方法の提案を行う。 ディジタルコンテンツ流通の活性化において、多くのコンテンツの中から所望のコン テンツをいかに見つけることができるかが大きな課題である。現在、インターネット を利用したネット書店などでは、書籍のジャンル別分類での提示や、題名や著者名に よるキーワード検索の手法提供により書籍探索が可能となっているが、本提案により 容易なキーワード付与が可能となる。
1 0 0 0 ビッグデータ時代のライフログ : ICT社会の"人の記憶"
- 著者
- 安岡寛道編 曽根原登 宍戸常寿著
- 出版者
- 東洋経済新報社
- 巻号頁・発行日
- 2012
1 0 0 0 OA Webデータを用いた京都市のホテル業界に関する応用研究
- 著者
- 津田 博史 多田 舞 山本 俊樹 一藤 裕 曽根原 登 椿 広計
- 出版者
- 情報知識学会
- 雑誌
- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.4, pp.442-451, 2013-12-07 (Released:2014-02-07)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
本研究の目的は,地域観光の政策実行主体である自治体やホテルなどの宿泊施設事業者が,データに基づいた合理的な観光政策,事業経営を実施するための情報収集・データ解析理論,方法を研究することである.本研究では,Webサイトから収集したホテル空室データや観光情報を用いて,日次で宿泊施設の稼働率を推定し,また,宿泊施設であるホテルの人気の要因を分析した.今回の研究目的の1つ目として,京都市の観光政策の経済波及効果を捉えるために,京都市内のホテルの客室稼働率を推定することとした.2つ目の目的として,人気ホテルの要因を解明することとした.実証分析結果により,京都市内のホテルの客室稼働率,および,ホテルの人気の要因に関して新しい知見が得られた.
- 著者
- 阿部 剛仁 南 憲一 山室 雅司 曽根原 登
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告 (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.89, pp.41-47, 2004-09-02
- 被引用文献数
- 1
自由な利用や配布,改変が可能な草の根的コンテンツ(トランスフォーマティブ・コンテンツ)に着目し,それらコンテンツの利便性,信頼性を高めて流通を活性化するとともに,従来の商用コンテンツとの連携により,商用コンテンツ市場を含めたコンテンツ流通全体の活性化を促し,皆がより多くの益を得ることを目指す新しいコンテンツ流通フレームワークを提供するTEAM Digital Commonsについて述べる.また,Creative Commons Public Licenseを利用したコンテンツのメタデータ管理システムについて紹介する.
1 0 0 0 OA 科学的政策決定のための統計数理基盤整備とその有効性実証
- 著者
- 北川 源四郎 椿 広計 藤田 利治 津田 博史 西山 慶彦 川﨑 能典 佐藤 整尚 土屋 隆裕 久保田 貴文 藤田 晴啓 奥原 浩之 村上 政勝 片桐 英樹 宮本 道子 曽根原 登 冨田 誠 笛田 薫 蓮池 隆 宮原 孝夫 安藤 雅和
- 出版者
- 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構(新領域融合研究センター及びライフサイ
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2010-04-01
本研究では,科学的情報収集に基づく社会価値選択,価値を決定する構造モデル導出,価値のモデル上での最適化,最適化された価値の社会への還元からなる情報循環設計を科学的政策決定の統計数理科学的枠組みと位置づけ,政策の科学的決定に資する統計数理体系構築を目的とした.本研究を通じて,公的ミクロ情報分析統計基盤の確立,情報循環加速ツールの開発,時空間可視化ツールの開発を達成し,同成果を自殺予防対策研究,観光政策研究,産業環境政策研究に応用し,それぞれの政策立案に資する新たな知見を得るとともに,データに基づく政策を提言した.
大学では,全学的な図書館だけなく,キャンパス,学部,研究室など様々なレベルで図書が購入され共有されている.こうした利用形態を電子ブックの利用においても実現することは,その利用促進に向けての重要な鍵となる.電子ブックの閲覧方式には,ウェブブラウザを利用するサーバサイド方式と,コンテンツをダウンロードして利用するクライアント方式に大別できる.本研究では,後者のクライアント方式において,電子ブックの閲覧を所属レベルで制御可能な方法を提案した.所属情報には,学認において,大学の認証システムから送信される属性と,メンバー属性プロバイダから送信させる属性を利用した.この属性情報に基づいたクライアント証明書を発行し,電子ブックの PDF ファイルを暗号化するプラットフォームを構築した.PDF の標準仕様活用した DRM 機能により,特殊なアプリケーションを用意することなく,普段利用している PDF ビューアを用いて,電子ブックのセキュアなグループ閲覧を実現することに成功した.In universities, books are purchased and shared by the variety of organizations such as individual labs or departments, or the broader campus, in addition to the main campus library. Students and researchers benefit when the e-book platform allows access to materials for the right campus members from the right organizations. In general, there are two ways to read an e-book. One, the server side method, utilizes a web browser. The other, the client method, requires specific e-book reader applications. This study focuses on the latter client method and proposes a way to control e-book access depending on the different affiliation levels. The system developed in this study is based on the academic access management federation, GakuNin. Attributes from university IdP's and other GakuNin member attribute providers are employed as trusted user data. The PDF file that contains the e-book is encrypted using a client certificate, for which the corresponding private key is available only to users with the proper membership in the right campus organization. The system is entirely standards-based, so there is no need for modification of the client or installation of a new application.
- 著者
- 伊達 拓紀 安川 健太 馬場 健一 山岡 克式 曽根原 登
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. IN, 情報ネットワーク (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.628, pp.255-260, 2006-02-23
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
近年,ストリーム型通信の普及に伴い,IP網においても受付制御の必要性が高まっている.筆者らはこれまでに,新規到着フローを一時収容し,一定期間後に輻輳の有無を確認することにより受付制御を行う,パケット交換網ならではの受付制御方式,TACCS (Tentative Accommodating and Congestion Confirming Strategy)を提案している.TACCSでは,CDA (Congestion Detection Agent)から広告されるパケット損失情報を基にフロー収容可否決定を行うため,網内のボトルネックとなり得る箇所にCDAを配置する必要がある.しかし,コアノードへの機能追加なしで同等の性能が実現できれば,その導入コストを低く抑えられる上,TACCSのスケーラビリティの向上を実現することが可能である.そこで本稿では,CDAを配置せずに,エッジノードの連携のみで網内の輻輳に対する受付制御を実現する,Edge-based TACCSを提案する.計算機シミュレーションによる評価結果から,Edge-based TACCSは,コアノードの機能追加を必要としないにも関わらず,従来のTACCSに対して遜色ない性能を実現可能であることを示した.