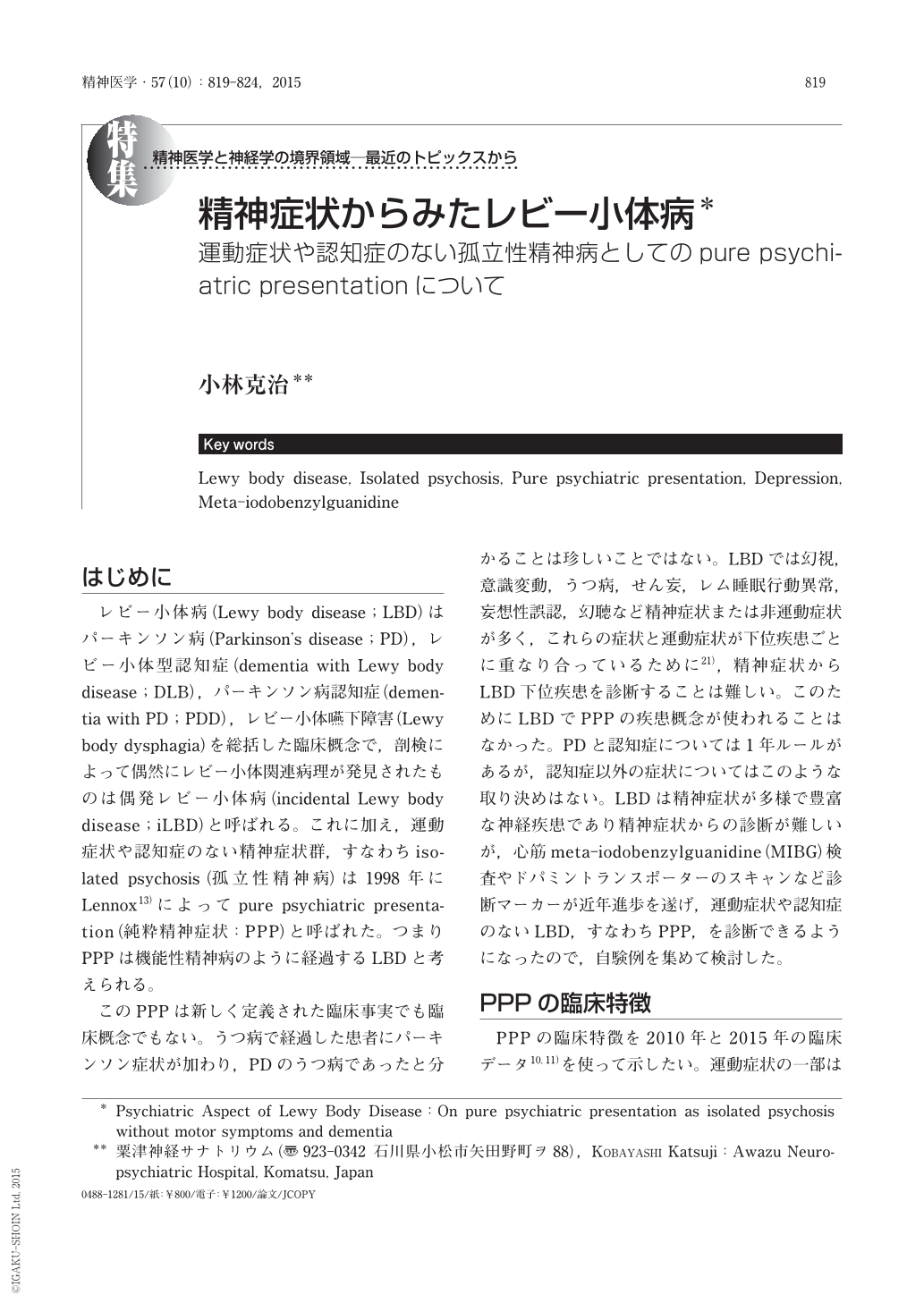1 0 0 0 OA ガス産生化膿性肝膿瘍を合併した糖尿病の1例
- 著者
- 上垣 正彦 高杉 佑一 杉江 広紀 辻 和之 林 憲雄 粂井 康孝 並木 正義
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.8, pp.683-689, 1992-08-30 (Released:2011-03-02)
- 参考文献数
- 15
ガス産生化膿性肝膿瘍を合併したNIDDMの1例を経験した. 症例は84歳, 男性. 嘔吐, 発熱で発症し, 当院に入院した. 高血糖, CRP陽性, 白血球増多, 胆道系酵素の上昇を認め, ただちにインスリン治療と抗生剤の投与を開始した. 腹部の超音波検査とCT像で少量のガス産生を伴う孤立性化膿性肝膿瘍 (CT上72×92mmのSOL) に特徴的な所見を認めたので抗生物質を変更し, ドレナージを行うことなく順調に治癒した. 肝動脈塞栓術後やエタノール局所注入療法後などにみられる医原性のガス産生症例を除外して集計すると, (非医原性) ガス産生化膿性肝膿瘍の本邦報告例は自験例を含め23例で, このうち糖尿病合併例が20例 (87%) と極めて高率である. 本症の報告例は少ないが, 糖尿病者に多い特徴があり, 早期の診断と治療効果判定には, 腹部超音波や腹部CTによる画像診断が有用と思われ報告した.
- 著者
- 栗林 克匡
- 雑誌
- 北星学園大学社会福祉学部北星論集 = Hokusei Review, the School of Social Welfare (ISSN:13426958)
- 巻号頁・発行日
- no.58, pp.19-26, 2021-03-15
1 0 0 0 OA 重力可変装置で火星表層の水の流れを解析する
- 著者
- 神野 佑介 永田 英 新居 優太郎 今林 潤 鷲見 香莉奈 若林 健流 岩築 美幸 松田 孟男 柏木 ハツヱ 佐古 佐世子 鴈金 舞 鄭 喆心 廣岡 陽子 森本 拓輝
- 雑誌
- JpGU-AGU Joint Meeting 2017
- 巻号頁・発行日
- 2017-05-10
アトウッドの滑車を利用して加速度をコントロールすれば,月や火星の重力もつくれると考え,重力可変装置を製作した.下降するおもりの側を実験カプセルとして内部の重力を計測した.0.5秒の短い時間ではあるが,火星,月,エンセラダスの表面重力を作ることができた.すでに実働している微小重力発生装置と連携すれば0Gから1Gの任意の重力を生み出すことができる.さらに,上昇するおもりの側を実験カプセルとすれば,約1.5Gまでの重力をつくりだせると考えられる. この装置で作った火星表面重力を用いて,火星での水の振る舞いを観察した.その結果,火星上の水は,地球上での挙動とかなり異なることがわかった.火星重力下での水は,粘性が大きくなったような動きを示した.映像から解析した火星の水の粘性は地球の水と比べて約2.4倍であった. 簡単な原理で目的とする天体の重力を実現することができた.今後の太陽系探査で,さまざまな天体環境での予備実験に重要な役割を果たすと考えられる.
1 0 0 0 カイコの性決定の分子機構
- 著者
- 嶋田 透 鈴木 雅京 大林 富美 船隈 俊介 小池 淑子
- 出版者
- 日本比較内分泌学会
- 雑誌
- 日本比較内分泌学会ニュース = Newsletter of Japan Society for Comparative Endocrinology (ISSN:09139044)
- 巻号頁・発行日
- no.111, pp.39-46, 2003-12-01
1 0 0 0 OA 交叉率と突然変異率を自動調整する改良遺伝的アルゴリズム
- 著者
- 王 超陽 賈 墨林 陳 奎廷 馬場 孝明
- 出版者
- 電気・情報関係学会九州支部連合大会委員会
- 雑誌
- 電気関係学会九州支部連合大会講演論文集 平成24年度電気関係学会九州支部連合大会(第65回連合大会)講演論文集
- 巻号頁・発行日
- pp.349, 2012-09-14 (Released:2014-12-17)
近年、最適問題を高速に解く方法の一つに、遺伝的アルゴリズムは提案されてから、多くの応用分野において幅広く使われている。しかし、この手法は収束速度が遅いという問題がある。これを解決するため、本研究ではパラメータを自動調整する手法を用いた改良遺伝的アルゴリズムを提案する。この改良遺伝的アルゴリズムは、交叉率と突然変異率のパラメータを自動調整させることにより、収束速度を上げるという新しい手法である。さらに、例として一般的な遺伝的アルゴリズムとこの改良遺伝的アルゴリズムで実現したそれぞれのFIRフィルタを比較し、提案手法による結果がより良いことを示す。
- 著者
- 工藤 紗希 小島 慎一郎 佐久間 博子 町田 明子 杉本 諭 丸谷 康平 伊勢崎 嘉則 室岡 修 大隈 統 加藤 美香 小林 正宏 三品 礼子
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.E3P2246, 2009
【目的】<BR> 近年では在院日数の短縮化に伴い、介護老人保健施設(老健)を経て在宅復帰されるケースが増加している.一方在宅復帰した者の中には、機能低下により在宅生活が困難となり、施設入所となることも多い.従って通所者の在宅生活の継続、入所者の在宅復帰を目標とした際に、在宅生活に必要なADL能力及びバランス能力を把握することは、理学療法を進める上で重要であると考えられる.本研究の目的は、通所・入所者のADL自立度の違いを明らかにし、その違いをバランス能力に焦点を当てて分析することである.<BR>【対象と方法】<BR> 対象は通所リハサービス利用者及び老健施設入所者のうち本研究に同意の得られた高齢者247名(男性75名、女性172名、平均年齢79.1±8.8歳)で、通所者188名、入所者59名であった.疾患の内訳は、脳血管疾患95名、神経疾患20名、整形疾患87名、内部障害27名、その他18名であった.ADL自立度の評価にはFIMの運動項目を、バランス能力の評価にはBerg Balance Scale(BBS)を用いた.なおFIM下位項目のうちの階段昇降は、運動能力の違いに関わらず使用している者が少ないため、階段を除く12項目の合計(FIM12項目合計点)及び各下位項目の素点を用いた.BBSは合計点及び14の下位項目を用いた.分析方法は、まず通所者と入所者のFIM12項目合計点及び下位12項目の得点の違いをMann-Whitney検定を用いて分析し、有意差のみられた下位項目の分布と臨床的意味合いをもとに、各下位項目を良好・不良の2段階に分類した.次に抽出されたFIM下位項目を独立変数、利用状況(通所・入所)を従属変数として、Stepwise法による判別分析を行った.更に判別分析により最終選択された下位項目を従属変数、BBS下位項目を独立変数とし、Stepwise法による重回帰分析を行い、バランス能力との関連について分析した.<BR>【結果および考察】<BR>FIM12項目合計点の中央値は通所者78点、入所者61点、BBSは通所者44点、入所者27点であった.Mann-Whitney検定の結果、FIM12項目合計点、FIM下位12項目のうち食事と移動を除く10項目に有意差がみられ、判別分析ではトイレ動作と浴槽への移乗が最終選択された.この2項目が良好と判断される境界点は、トイレ動作は6点、浴槽への移乗は5点であった.重回帰分析によるBBS下位項目との分析では、トイレ動作では着座、リーチ、起立、浴槽への移乗では一回転、リーチ、タンデム立位、車いすへの移乗が最終選択された.以上より、在宅復帰の可否にはトイレ動作が修正自立、浴槽への移乗が見守りで可能であることが関連し、このような動作の獲得には、着座、起立、リーチ、一回転、タンデム立位、移乗動作のようなバランス能力の向上が重要であることが示唆された.
- 著者
- 古田 朋子 鵤 心治 小林 剛士
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.605, pp.135-142, 2006
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
The purpose of this paper is to investigated the fact of technical standards for developments exceeded, to secure the minimal standards of town area. Result is as follows. Ranging small-scale development connected to roads of weak condition in the loose regulated area, which causes a condition of maze-like street. And we showed that technical standards in the City Planning Act are not enough to accumulate an ideal living environment. It is necessary to revise the technical standards or to guide developer development by local governments.
1 0 0 0 OA エモティコンによる感情認知
- 著者
- 竹原 卓真 栗林 克匡
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第5回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.123, 2007 (Released:2007-10-01)
日常生活では、高頻度で電子メールが送受信されている。電子メールには、顔文字や絵文字など、エモティコンと呼ばれるオブジェクトがしばしば付加されるが、本研究では、それらエモティコンを付加した場合に、電子メールの感情情報がどのように認識されるのかを検証した。その結果、喜び感情については先行研究と同様に、顔文字を付加しない条件よりも、付加した条件のほうが喜び感情の認知が促進された。また、悲しみ、怒り、恐怖、嫌悪の4つのネガティブ感情を表現する電子メールに、対応する顔文字を付加しても、当該感情の認知が促進されることはなかった。中性感情と位置付けられる驚きについては、喜び感情とほぼ同様の結果が示された。他方、感情表出している静止した絵文字を付加した場合、顔文字よりも視覚的情報量が多いため、当初は感情認知が促進されると推測したが、結果的に感情認知が促進される感情と、促進されない感情が存在した。
1 0 0 0 OA 治療困難な不法滞在患者の治療方針 ~AIDS患者の1例を経験して~
- 著者
- 長谷川 浩一 林 真人 川口 健司 田代 晴彦 森川 篤憲 岡野 宏 川上 恵基 村田 哲也
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会学術総会抄録集 第56回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)
- 巻号頁・発行日
- pp.29, 2007 (Released:2007-12-01)
(症例)患者はインドネシア国籍の29歳男性で、平成19年1月17日に頭痛を主訴に当院外来を受診。頭部単純CTで左側頭葉に低吸収域を呈する脳病変を認めた。しかしながら不法滞在者であると判明し、それ以上の精査治療は母国で行うべきと初診医が判断し、即時の帰国を勧めた。しかしながら、症状は徐々に悪化し発熱と意識障害をきたしたため、1月21日に当院救急外来を受診し内科入院となった。入院時、口腔内カンジダ症を認め、抗HIV抗体が陽性であった。髄液検査では異常を認めなかったが、AIDSによる脳トキソプラズマ症が最も疑われ、ST合剤とクリンダマイシンの投与を開始した。治療により解熱しCRPも9.0から0.5に低下したが、意識状態の改善はあまり認められず、到底旅客機で帰国できる状態ではなかった。2月1日に局所麻酔下で定位的に病変部位の生検術を施行し、病理組織にて脳トキソプラズマ症の確定診断が得られたため、2月8日に三重大学附属病院血液内科に転院した。その後、ピリメサミンを用いた積極的な治療により旅客機で帰国できる状態にまで回復した。 (当院での対応)不法滞在のため保険には未加入で、治療費は自費のため金銭的な援助をインドネシア大使館にも相談したが、予算がないため金銭的な援助は不可能との返事であった。また、当院はAIDS拠点病院に指定されていないため、県内のAIDS拠点2病院への転院も考慮したが困難であった。三重大学附属病院のみHIV感染により何らかの合併症を発症している事が確認されていれば、何とか受け入れ可能であるが、少なくとも脳の生検でAIDS以外の脳病変を否定する事が前提条件であった。HIVに対する手術器具の消毒法もHCV等と同じであるが、HIV感染患者の手術は当院では初めてであり手術室等からの反対もあったが、転院のためには他に手段はなく、当院でやむなく生検術を施行した。 (考察)不法滞在患者でなく金銭的に問題なければ、大学病院以外のAIDS拠点病院への転院も可能であったと思われるが、研究機関でもある大学病院しか受け入れは許可してもらえなかった。鈴鹿市は外国人の割合が高いので、不法滞在の外国人も多いと予想されるが、これは全国的な問題と考えられる。不法滞在者であるからといって人道的に治療を拒否する事はできず、行わなければならない。その様な場合、どこからか金銭的な援助を得て、なんとか治療を行える方法はないのであろうか。また、外来受診の翌日に名古屋の入国管理局から連絡があり、すぐに帰国させる様に伝えたが、手続き上少なくとも1週間以上かかり、結局その間に症状が悪化し帰国できなくなってしまった。不法滞在ではあるが、この様な緊急事態の場合、入国管理局はもっと早く帰国の手続きをとる事はできないのであろうか。この患者は治療により帰国できる状態にまで回復したが、回復しなかった場合は二度と自国の土を踏む事はできなかったと考えられた。
1 0 0 0 越境ヘイズ災害のための危険予告情報:レジーム変化と長期記憶性
- 著者
- 小林 潔司 JAAFAR Mohamed Nazari Bin 尾形 誠一郎 塚井 誠人
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.478-497, 2007
インドネシアのスマトラ島の森林火災は,周辺各国における日常的サービスの中断,呼吸器系疾患の多発等の深刻なヘイズ(煙害)災害をもたらしている.マレーシア政府は,大気中の汚染物質量をリアルタイムに観測し,ヘイズ警報を発令するシステムを開発している.ヘイズ警報を発令(解除)するためには,衛星情報と地上観測データに基づいて,将来時刻における大気汚染物質の滞留量を迅速に予測するような統計的予測モデルが有用である.本研究では,レジーム変化(regime switching)と長期記憶性を考慮した統計的時空間モデルを定式化するとともに,ヘイズ災害に関する危機管理情報を作成するための方法論を提案する.さらに,マレーシア半島部を対象としたケーススタディにより,本研究で提案した方法論の有効性を実証的に検証する.
1 0 0 0 OA 愛知県渥美半島のイシガメに寄生するカメキララマダニ
- 著者
- 矢部 隆 林 文男
- 出版者
- The Acarological Society of Japan
- 雑誌
- 日本ダニ学会誌 (ISSN:09181067)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.47-50, 1998-05-25 (Released:2011-02-23)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 2 3
A total of 655 larvae, 329 nymphs and 26 adults(5 males and 21 females)of the ticks, Amblyomma geoemydae, were collected from the Japanese pond turtles, Mauremys japonica, captured in the small impoundment of the Ayu River, Doda, the Atsumi Peninsula, Aichi Prefecture, central Japan. This is the first distributional record of A. geoemydae from Japan excluding the Nansei Islands. In this study site, all stages of ticks were generally found on the hosts during the period from late April to early November. In winter, however, the hosts could not be examined because they overwinter under water of the impoundment.
1 0 0 0 死者とともに生きる : ボードリヤール『象徴交換と死』を読み直す
1 0 0 0 OA 開心術時の自己血回収法におけるセルセーバーとヘモコンセントレーターの比較検討
- 著者
- 磯村 正 久冨 光一 西見 優 平野 顕夫 川良 武美 諌本 義雄 大野 兼市 林田 信彦 松添 慎一 小須賀 健一 大石 喜六
- 出版者
- 一般社団法人 日本人工臓器学会
- 雑誌
- 人工臓器 (ISSN:03000818)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.717-719, 1992-04-15 (Released:2011-10-07)
- 参考文献数
- 7
最近1年間に施行された冠動脈バイパス術のうち、術前自己採血が不可能であった24例を対象とし、術中セルセーバーのみ使用したもの(C群n=9)、ヘモコンセントレーターのみ用いたもの(H群n=6)、および、両者の併用例(M群n=9)に分類し、術後出血、同種血輸血量の検討を行った。各群間の年齢、体外循環時間(ECC)には有意差は認めなかった。自己血回収量はC群620±176ml;H群530±148ml;M群779±287mlであり、M群が他の2群に比べ有意に増加していた。術後12時間の胸腔ドレーン出血量をみると、C群720±363ml、H群372±159ml、M群413±167mlと、C群で有意に出血量の増加を認めた。今回検討した開心術に際しての自己血回収法の中では、ECC前後の出血はセルセーバーで、人工心肺残留血はヘモコンセントレーターで濃縮返血した群で、自己血回収量が最も多く、セルセーバー単独使用群に比べ、術後の出血量は有意に少ないため、最も有用な方法であると考えられた。
- 著者
- 今津 芳恵 松野 俊夫 村上 正人 林 葉子 杉山 匡
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.263-270, 2016
心療内科に通院中の患者233名を対象に, ストレス反応を測定するPublic Health Research Foundationストレスチェックリスト・ショートフォーム (以下, PHRF-SCL〔SF〕) と自己成長エゴグラム (以下, SGE) を実施し, その関連を検討した. SGEの得点のクラスター分析から, 「A高位Wタイプ」, 「A低位Mタイプ」, 「FC低位Vタイプ」, 「NP高位 ‘ヘ’ タイプ」が抽出された. それぞれについて, PHRF-SCL (SF) の下位尺度ごとに偏差値を算出し, 一元配置分散分析により平均の差を検討した. その結果, 「FC低位Vタイプ」はストレス反応が他のタイプより高く, 「NP高位 ‘ヘ’ タイプ」は他のタイプより低かった. PHRF-SCL (SF) とエゴグラムとの関連が認められ, その関連性は先行研究と一致するものであり, PHRF-SCL (SF) の構成概念妥当性の一端が検証された.
1 0 0 0 リポ蛋白の酸化変性と血管内皮の信号応答に関する研究
動脈硬化症の初期変化をもたらす一つのきっかけは、低比重リポ蛋白(LDL)がラジカル種の攻撃で酸化変性を受け、生理的な代謝が行われなくなることにあると考えられている。しかし、具体的にLDLのどのような構造変化が血管内皮に対して異常信号として作用するのかについては、不明のままとなっている。本研究では、以下の成果をあげることができた。1.アポBの糖鎖構造と易酸化性との関係について調べた.その結果native LDLと酸化LDLで糖鎖構造に違いは認められなかったが、ある切断酵素を作用させたときにだけ、易酸化性が有意に上昇するという現象を認めた。この結果から、アポB上のある種の糖鎖が酸化防御に関わっていることが推測された。2.LDLの酸化によって生じるアポBのフラグメント解析を試みた。ところが種々のフラグメントのアミノ酸配列をホモロジー検索したところ、アポB以外のさまざまなたんぱく質が非特異的に結合していることが分かった。3.酸化LDLを血管内皮細胞に作用させ、VCAM-1のmRNAの変化を調べるという実験系の検討に入った。まず内皮細胞にIL-1を、濃度と時間を変えながら作用させ、VCAM-1のmRNAが発現する最適条件を検討した。さらにVCAM-1アンチセンスを用いたハイブリダイゼーションで、当該バンドが安定して確認できる条件を探った。その結果、IL-1および精製した酸化LDLを内皮細胞に作用させると、VCAM-1のmRNAが明らかに増加する事実を確認することができた。4.酸化によってLDLにどのような構造変化が起きるのかを確かめるべく、アポBの立体構造を解析する研究にも着手することができた。その結果、アポBの膜内でαヘリックスの束を作っている領域が5つあることを確認できた。これは、従来の生化学的な分析結果ともよく一致しており、方法の正しさが証明できたものと考えている。
はじめに レビー小体病(Lewy body disease;LBD)はパーキンソン病(Parkinson's disease;PD),レビー小体型認知症(dementia with Lewy body disease;DLB),パーキンソン病認知症(dementia with PD;PDD),レビー小体嚥下障害(Lewy body dysphagia)を総括した臨床概念で,剖検によって偶然にレビー小体関連病理が発見されたものは偶発レビー小体病(incidental Lewy body disease;iLBD)と呼ばれる。これに加え,運動症状や認知症のない精神症状群,すなわちisolated psychosis(孤立性精神病)は1998年にLennox13)によってpure psychiatric presentation(純粋精神症状:PPP)と呼ばれた。つまりPPPは機能性精神病のように経過するLBDと考えられる。 このPPPは新しく定義された臨床事実でも臨床概念でもない。うつ病で経過した患者にパーキンソン症状が加わり,PDのうつ病であったと分かることは珍しいことではない。LBDでは幻視,意識変動,うつ病,せん妄,レム睡眠行動異常,妄想性誤認,幻聴など精神症状または非運動症状が多く,これらの症状と運動症状が下位疾患ごとに重なり合っているために21),精神症状からLBD下位疾患を診断することは難しい。このためにLBDでPPPの疾患概念が使われることはなかった。PDと認知症については1年ルールがあるが,認知症以外の症状についてはこのような取り決めはない。LBDは精神症状が多様で豊富な神経疾患であり精神症状からの診断が難しいが,心筋meta-iodobenzylguanidine(MIBG)検査やドパミントランスポーターのスキャンなど診断マーカーが近年進歩を遂げ,運動症状や認知症のないLBD,すなわちPPP,を診断できるようになったので,自験例を集めて検討した。
- 著者
- 佐藤 真央 井上 裕太 溝脇 一輝 小林 大純 松尾 怜 外山 太一郎 日比野 友亮
- 出版者
- 一般社団法人 日本魚類学会
- 雑誌
- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.17-22, 2021
<p>Twelve specimens (71.5–89.9 mm standard length) of the genus <i>Lutjanus</i> (Lutjanidae), collected from Ishigaki-jima Island, Ryukyu Archipelago, southern Japan, were identified as <i>Lutjanus biguttatus</i> (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1830), being characterized by the following combination of characters: dorsal fin XI, 12; anal fin III, 8; pectoral rays 15–16; body depth 3.5–3.8 in standard length; preorbital depth 10.8– 16.3 in head length; tongue smooth, without patch of fine granular teeth; a dark longitudinal band from snout to caudal fin base; and two white spots above the lateral line. Dentition of the premaxilla and dentary, including several canine-like (one being long and curved) and many small conical teeth, is illustrated. The collected specimens were determined to be juveniles, due to their coloration matching that of juveniles previously described, in addition to their small body size. Although the coloration of <i>L. biguttatus</i> is similar to that of <i>L. vitta</i> during the juvenile stage, the latter species is distinguished by greater body and preorbital depths. The specimens of the former had been caught in a significantly localized area (in ca. 4 m depth) over several days, indicating the likelihood of their having been schooling, as observed in previous studies of the species. <i>Lutjanus biguttatus</i> is distributed in the Indo-western Pacific, from the Maldives to the Solomon Islands, but had not previously been recorded from Japanese waters. The new standard Japanese name "Futahoshi-fuedai", given in reference to the two white spots above the lateral line in the collected specimens, is proposed.</p>
1 0 0 0 IR 近代中国への自由・権利概念の移植
- 著者
- 林 来梵 松井 直之
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 北大法学論集 (ISSN:03855953)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.270-245, 2018-07-31
1 0 0 0 IR 星野先生を悼む
- 著者
- 林 幸一
- 出版者
- 広島大学マネジメント学会
- 雑誌
- 広島大学マネジメント研究 (ISSN:13464086)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.10-11, 2020-03-26
- 著者
- 薫 一帆 井上 茂 高宮 朋子 町田 征己 小田切 優子 福島 教照 菊池 宏幸 天笠 志保 林 俊夫 齋藤 玲子
- 出版者
- 日本運動疫学会
- 雑誌
- 運動疫学研究 (ISSN:13475827)
- 巻号頁・発行日
- 2021
<B>目的</B>:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行下に運動を実施するには,運動時にも感染症予防対策が必須である。しかし,運動時の個人の感染予防行動に関する研究は乏しい。本研究の目的は,主に自宅外で運動する運動習慣者における運動時の感染予防行動の実態を明らかにすることである。<BR><B>方法</B>:インターネット調査を用いた記述疫学研究を実施した。2020年2月に初回調査を実施した関東在住日本人2400名のうち,同年6月,7月に実施した追跡調査に回答した2149名において,運動場所,運動種目,運動時感染予防行動8項目を尋ね,運動場所や運動種目毎の感染予防行動の実施割合を算出した。<BR><B>結果</B>:運動習慣者は636名(29.6%),このうち自宅外で運動する者は431名(67.8%)であった。8項目中,運動を「体調が悪い時には行わない」は,屋内で運動する者で83.3%,屋外で91.5%であった。運動場所,運動種目によらず,「運動後は手を洗う」の実施割合が高く,「運動中のマスクやネックゲーターなどの着用」が低かった。「人との距離を保つ」は,むしろ屋外より屋内で低く,室内球技や武道等実施者で低い割合を示した。<BR><B>結論</B>:本研究の結果より,体調不良時の運動自粛の徹底,屋内運動実施時の飛沫感染予防策の実施等の課題が明らかになった。感染流行が長期化する中,運動時の感染予防行動について今後も普及啓発の必要がある。