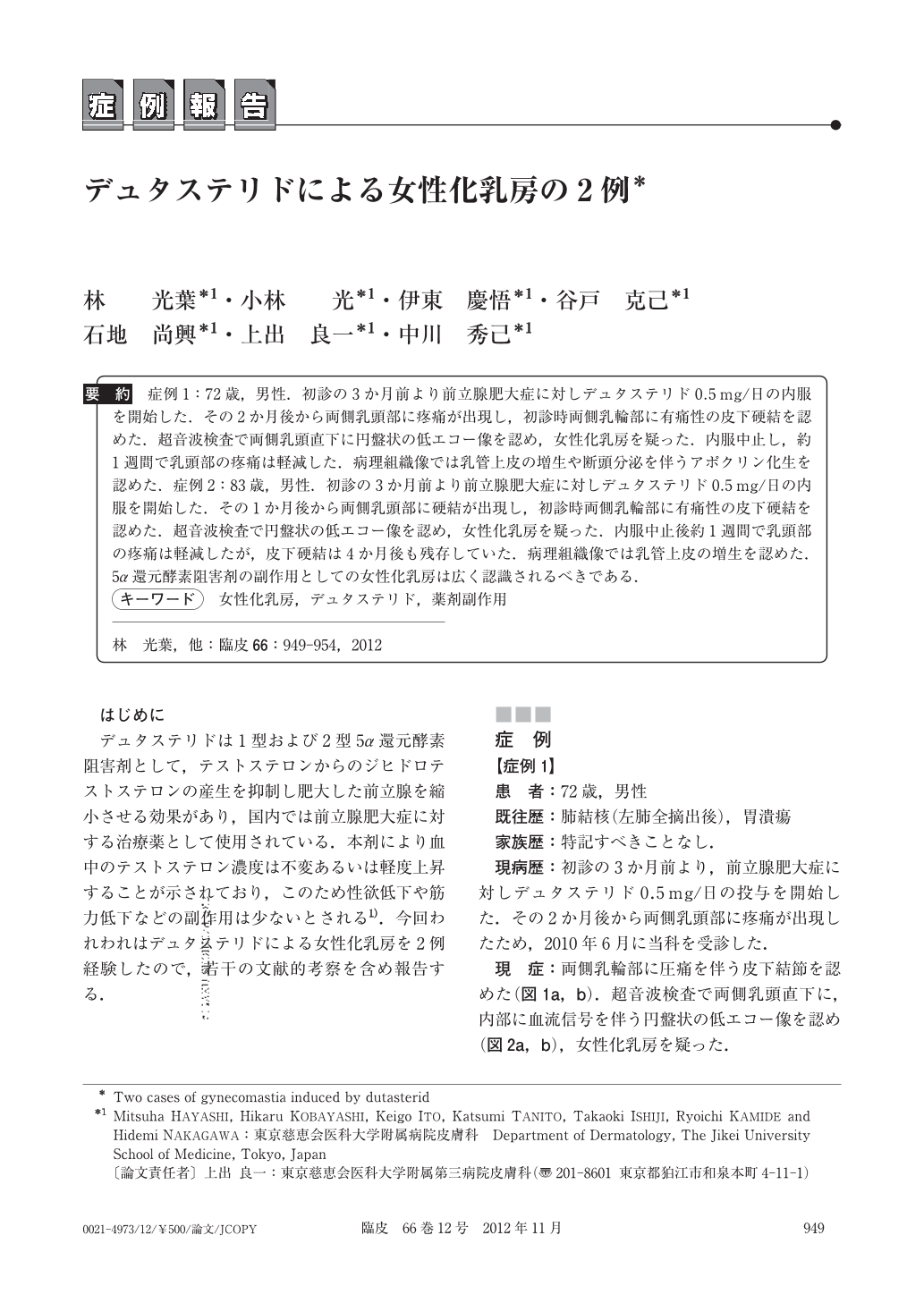1 0 0 0 IR DNAマーカーによるウメの遺伝的多様性解析
1 0 0 0 病期別に見た慢性閉塞性肺疾患患者のパーソナリティの比較検討
- 著者
- 中川 明仁 堀江 淳 江越 正次朗 松永 由理子 金子 秀雄 高橋 浩一郎 林 真一郎
- 出版者
- 日本ヘルスプロモーション理学療法学会
- 雑誌
- ヘルスプロモーション理学療法研究 (ISSN:21863741)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.1-5, 2019
<p>慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary disease; COPD)患者の心理特性について,病期の違いという観点から検討した。COPD 患者38名を対象とし,エゴグラムを用いてパーソナリティを評価して,Ⅰ期群とⅡ期群の差異について比較検討した。その結果,Ⅱ期群はⅠ期群と比べてFC(Free Child)が有意に低い値となり,病期が進行すると感情の表出性が乏しくなることが示唆された。また,病期を統合してCOPD 患者全体のパーソナリティを検討した結果,CP(Critical Parent)とNP(Nurturing Parent)が同程度に最高値となり,続いてA(Adult)とFC が同程度の値となり,AC(Adapted Child)が最も低い値を示した。COPD 患者のパーソナリティの特徴として,頑固さや自己への甘さが強まり,周囲の意見やアドバイスへの傾聴の姿勢を示しにくいことが示唆された。</p>
1 0 0 0 OA 取り巻く問題点 (併存症・二次障害)
- 著者
- 林 隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経学会
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:00290831)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3, pp.203-206, 2015 (Released:2015-11-20)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
学習の障害に起因する行動特徴は学校現場で支援の対象というよりも否定的な評価を受ける対象となっている可能性がある. 一般集団では, 読みに障害があっても, そのことが直接的に情緒の発達に強く影響を及ぼすことがないことが示唆された. 読み障害の中でも不登校を主訴とする児は読み障害の程度は軽いが, 抑うつ度が高く特有の支援ニーズをもつ可能性が示唆された. 不登校を示す読み障害児のWISCの特徴は他の指数に比べて, 処理速度が高いことで, 言えばできるが, 自分では行動できないことが状況から, 教員からは怠け・やる気がないと捉えられ, 支援ではなく強い指導を受ける可能性が高く, これが不登校の引き金になっている可能性がある.
1 0 0 0 OA カプサイシンの抗酸化活性部位の特定に関する研究 速度論および分子軌道計算からのアプローチ
- 著者
- 岡田 洋二 首藤 亜紀 丘島 晴雄 吉澤 清良 大澤亜 貴子 紅林 佑介 大瀧 純一
- 出版者
- 杏林医学会
- 雑誌
- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.4, pp.107-114, 2013 (Released:2013-01-29)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
唐辛子の辛味成分であるカプサイシン(capsaicin,CAP)の抗酸化活性部位を特定することを目的に,CAPの主要骨格であるグアヤコール構造を有する3種化合物の抗酸化活性( kinh) を速度論的に比較検討した。また,CAP分子表面上の静電ポテンシャルエネルギーの最大値(maximam potential energy,MPE)を分子軌道計算で求めて同様に検討した。速度論的に求めたグアヤコール誘導体のk inh値は4.4×10 3 ~ 1.2×10 4 M-1sec -1で,CAPでは5.6×10 3 M-1sec -1とほぼ同じ値であった。また,グアヤコール骨格を持たずCAPのacetamide部位を有するN -benzylacetamideには抗酸化活性が全く認められなかったことから,CAPの抗酸化活性を有する部位はグアヤコール骨格部分のフェノール性水酸基であることが推測された。この結果は,CAP分子表面上のMPEを分子軌道法に基づいた計算の結果からも確認することができた。以上,速度論的研究と分子軌道法に基づいた計算結果より,CAPの抗酸化活性部位はそのフェノール性水酸基であることが強く示唆された。
1 0 0 0 Varchsyn(5) : 論理多段化手法
1 0 0 0 OA 生体膜脂質ドメインの構成とダイナミクスの分子解析
生体膜に於いて脂質はランダムに配列しているのではなく、脂質二重層の内層と外層の脂質組成は異なり、内層のみ、外層のみをとっても特定の脂質がドメインを形成している。しかし生体膜における脂質の詳細な分布状態はほとんど明らかになっていない。私たちは特定の脂質、あるいは脂質複合体や脂質構造体に特異的に結合するプローブを開発するとともに、それらのプローブを用い、超高解像蛍光顕微鏡、免疫電子顕微鏡法等さまざまな顕微鏡手法を用いて、脂質ラフトをはじめとする脂質ドメインの超微細構造を解析し、また細胞分裂や細胞接着等や種々の病態における脂質ドメインの動態を併せて観測することにより脂質ドメインの機能の解明を試みた。
- 著者
- 林 瞬介
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス = The reference (ISSN:00342912)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.4, pp.97-119, 2021-04
1 0 0 0 OA 肺洗浄液中複数の腫瘍マーカーが高値を示した肺胞蛋白症の1例
- 著者
- 中島 正光 玉田 貞夫 吉田 耕一郎 杉村 悟 沖本 二郎 二木 芳人 真鍋 俊明 副島 林造
- 出版者
- The Japanese Respiratory Society
- 雑誌
- 日本胸部疾患学会雑誌 (ISSN:03011542)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.11, pp.1109-1114, 1994-11-25 (Released:2010-02-23)
- 参考文献数
- 20
症例は39歳, 男性. 労作時呼吸困難, 胸部X線上異常陰影にて当科に紹介入院となった. 入院後経気管支肺生検にて肺胞蛋白症と診断し, 現在までに2回の全身麻酔下左肺洗浄を施行し, 軽快退院している. 今回再度肺胞蛋白症の増悪がみられたため入院となった. 血清中のCEAが高値であったため他の腫瘍マーカーの測定を行い, 血清中のCA153, TPAの高値を認めた. さらに肺洗浄液中の腫瘍マーカーの測定を行い, CEA, CA19-9, CA125, CA15-3, CA50, SLX, SCC, TPAが血清正常値以上を示した. 血清中高値の腫瘍マーカー全て肺洗浄後減少傾向を示した. そこで, 高値を示した腫瘍マーカーの産生部位を検索する目的で経気管支肺生検組織の免疫染色を行った. 肺胞上皮にCEA, CA15-3, SLXが陽性を示し, これらはII型肺胞上皮を含む肺胞上皮より産生されていることが示唆された. 本症の肺洗浄液中でCEAが高値を示すことは知られているが, その他の腫瘍マーカーについての検討は少なく興味ある症例と考えられた.
1 0 0 0 乾癬の生物学的製剤治療に対する結核対策実態の多施設共同調査
- 著者
- 金子 栄 山口 道也 日野 亮介 澤田 雄宇 中村 元信 大山 文悟 大畑 千佳 米倉 健太郎 林 宏明 柳瀬 哲至 松阪 由紀 鶴田 紀子 杉田 和成 菊池 智子 三苫 千景 中原 剛士 古江 増隆 岡崎 布佐子 小池 雄太 今福 信一 西日本炎症性皮膚疾患研究会 伊藤 宏太郎 山口 和記 宮城 拓也 高橋 健造 東 裕子 森実 真 野村 隼人
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.131, no.6, pp.1525-1532, 2021
<p>乾癬治療における生物学的製剤使用時の結核スクリーニングの現状について西日本の18施設を調査した.事前の検査ではinterferon gamma release assay(IGRA)が全施設で行われ,画像検査はCTが15施設,胸部レントゲンが3施設であった.フォローアップでは検査の結果や画像所見により頻度が異なっていた.全患者1,117例のうち,IGRA陽性で抗結核薬を投与されていた例は64例,IGRA陰性で抗結核薬を投与されていた例は103例であり,副作用を認めた患者は23例15%であった.これらの適切な検査と治療により,結核の発生頻度が低く抑えられていると考えられた.</p>
1 0 0 0 OA 自然閉塞した椎骨動脈解離から2年後に対側の椎骨動脈が解離により破裂を来した1例
- 著者
- 小守林 靖一 久保 慶高 幸治 孝裕 西川 泰正 小川 彰 小笠原 邦昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.4, pp.291-294, 2013-07-25 (Released:2013-07-25)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
要旨:44歳,男性.頭全体の痛みを自覚し独歩受診.精査上くも膜下出血や脳梗塞は認めなかったが,左椎骨動脈解離を認め,2カ月おきに画像追跡を行い,半年後に左椎骨動脈の閉塞を確認した.なお,反対側の右椎骨動脈には異常所見は認めなかった.その後も画像追跡を行ったが,両側椎骨動脈には変化がなかった.最終画像追跡から2カ月後,左椎骨動脈閉塞から25カ月後に突然くも膜下出血を来した.右椎骨動脈-後下小脳動脈分岐部より近位側に紡錘状動脈瘤を認め,出血源と診断した.血行再建を伴った根治手術を企図したが,肺炎を合併したため待機手術の方針となった.2週間後に再出血を来し,死亡した.これまでの報告では,一側の椎骨動脈解離の自然閉塞または治療による閉塞後に対側の椎骨動脈解離によるくも膜下出血を来す期間は,14日以内であったが,本症例のように2年以上の長期経過後でも反対側椎骨動脈に解離が出現し,出血することがありうる.
1 0 0 0 IR 厩橋能舞台の建築経緯
- 著者
- 林 和利
- 出版者
- 名古屋女子大学
- 雑誌
- 名古屋女子大学紀要. 家政・自然編, 人文・社会編 (ISSN:21857962)
- 巻号頁・発行日
- no.63, pp.448-442, 2017-03
1 0 0 0 OA JAK2遺伝子変異の関与が疑われた非硬変性門脈血栓症に伴う肝外門脈閉塞症の1例
- 著者
- 石橋 啓如 足立 清太郎 片倉 芳樹 吹田 洋將 糸林 詠 横須賀 收
- 出版者
- 一般社団法人 日本肝臓学会
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.170-175, 2014-03-20 (Released:2014-04-07)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 1
症例は48歳の男性.5年前の健診で食道静脈瘤(LmF2CbRC0Lg-)を指摘され,精査にて悪性腫瘍や肝硬変症の合併を認めず,門脈本幹部血栓,肝門部海綿状血管増生,脾腫が確認され,非硬変性門脈血栓症に伴う肝外門脈閉塞症と診断された.5年の経過で門脈血栓,食道胃静脈瘤(LsF3CbRC2LgcF2)は増悪し,予防的に内視鏡的硬化療法を施行した.慢性骨髄増殖性疾患を疑い施行した骨髄生検では慢性骨髄増殖性疾患の合併は否定的であったが,血液検査にてJanus activating kinase 2のV617F遺伝子変異(JAK2変異)が確認されたことから,JAK2変異が門脈血栓症に関与したと考えられた.本症例では5年の経過中,脾腫に比して血小板数が正常域値内に保たれていた.明らかな基礎疾患が指摘されない門脈血栓症に伴う肝外門脈閉塞症ではJAK2変異が存在する可能性について考慮する必要がある.
1 0 0 0 デュタステリドによる女性化乳房の2例
要約 症例1:72歳,男性.初診の3か月前より前立腺肥大症に対しデュタステリド0.5mg/日の内服を開始した.その2か月後から両側乳頭部に疼痛が出現し,初診時両側乳輪部に有痛性の皮下硬結を認めた.超音波検査で両側乳頭直下に円盤状の低エコー像を認め,女性化乳房を疑った.内服中止し,約1週間で乳頭部の疼痛は軽減した.病理組織像では乳管上皮の増生や断頭分泌を伴うアポクリン化生を認めた.症例2:83歳,男性.初診の3か月前より前立腺肥大症に対しデュタステリド0.5mg/日の内服を開始した.その1か月後から両側乳頭部に硬結が出現し,初診時両側乳輪部に有痛性の皮下硬結を認めた.超音波検査で円盤状の低エコー像を認め,女性化乳房を疑った.内服中止後約1週間で乳頭部の疼痛は軽減したが,皮下硬結は4か月後も残存していた.病理組織像では乳管上皮の増生を認めた.5α還元酵素阻害剤の副作用としての女性化乳房は広く認識されるべきである.
1 0 0 0 OA フェロモンと繁殖
- 著者
- 林 進
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.1_11-16, 1986 (Released:2008-10-01)
1 0 0 0 OA 日本における知覚・行動地理学の回顧と展望
- 著者
- 若林 芳樹
- 出版者
- 一般社団法人 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.266-281, 2009 (Released:2018-01-10)
- 参考文献数
- 95
- 被引用文献数
- 2
The annual review of human geographical studies in Japan published in the Japanese Journal of Human Geography (Jimbun Chiri) has included a section on perceptual and behavioral geography since 1982. Nevertheless, the editorial board of the journal decided to remove this section in 2008. There is no doubt that this decision was made because of the need to re-examine the classification of the sections in this article, and was affected by the recent reorganization of this discipline. However, it is too early to say that perceptual and behavioral geography has lost its productivity and attraction. The aim of this paper is to review the advancements in perceptual and behavioral geography in retrospect and to evaluate the prospects for research in this field in Japan in comparison with the trends in English-speaking countries.To elucidate the place of perceptual and behavioral geography in Japanese geography and the changes over the years, the author analyzed the literature in Bibliographies on Japanese Geographical Research, the fields of interest of Japanese geographers, and the change in the tone of the articles published in the annual review of the above journal. The analysis revealed that perceptual and behavioral geography in Japan has not lost its productivity and still attracts the attention of more than a few young geographers; however, the number of researchers specializing in this field remains few. As the studies in this field tend to overlap with other branches of geography, and since the polarization between perceptual and behavioral studies has not yet been reconciled, the unity of this field of research has become lost. As a result, this field is marginalized in human geography.While this trend in perceptual and behavioral geography observed in Japan is similar to that observed in UK, perceptual and behavioral geography in the USA enjoys a more optimistic outlook, since the specialty group of EPBG, which has made close connections with GIS and cartography, remains active there. After 2000, new trends in perceptual and behavioral geography have been observed in Japan. A notable one is the interdisciplinary collaboration with related fields (e. g., psychology and information science). In addition, there has been an increase in the number of studies focusing on special segments of the population, such as the disabled, foreigners, children, the elderly, and women; these studies are more concerned with specificity rather than generality, since they take into consideration the geographic context of environmental perception and spatial behavior. These studies aim at solving actual problems and are applicable to public policy and urban planning. Recently, studies on spatial cognition have also contributed significantly to GIS and cartography.
1 0 0 0 OA 熟練者・未熟練者におけるインステップキック動作解析
- 著者
- 中村 康雄 齊藤 稔 林 豊彦 江原 義弘
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム (ISSN:13487116)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.53-64, 2010 (Released:2017-02-15)
- 参考文献数
- 12
サッカーは, キック動作を基本とした主に足でボールをコントロールするスポーツである. ボールを自在に操る蹴り脚は, 熟練者であるほど巧みな動きをする. そのため, 多くの先行研究では, 足のみを対象としてキック動作の定量的な測定・解析が行われてきた. しかし, キック動作は全身運動である. キック動作をさらに理解するためには, 足だけでなく, 蹴り脚の動作の要となる腰部の運動についても同時に測定し, 定量的に評価する必要がある. 本研究は, インステップキック動作を対象とし運動学・動力学解析することと, 熟練者と未熟練者の腰部の運動の違いを定量的に評価することを目的とした. キック動作はモーションキャプチャ・システムを用いて測定した. 熟練者と未熟練者の運動を評価した結果から, 腰部は, 上体の急激な屈曲運動の補助, 下肢へのエネルギー伝達, 姿勢の安定の3つの役割があると考えられた.
1 0 0 0 古墳時代木棺の用材選択に関する研究
- 著者
- 岡林 孝作
- 出版者
- 奈良県立橿原考古学研究所
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2003
本研究では、遺物論的視点に立った古墳時代木棺研究の一つの試みとして、その製作材料である木材の樹種に注目した検討をおこなった。具体的には、古墳等から出土した遺存木棺材の木材科学的な樹種同定作業を進め、資料を蓄積するとともに、木材科学的な同定により樹種が判明した出土木棺材の調査例を全国的に集成し、用材選択の地域性・階層性と時期的変化を分析した。資料収集の結果、全国で165例の樹種同定例を集成した。針葉樹が91%、広葉樹が9%で、針葉樹が圧倒的に多い。なかでもコウヤマキの使用が突出しており、全体の51%を占めるが、その分布域が近畿地方を中心として西は岡山県から東は愛知県にかけての太平洋側の地域にほぼ限定されることが顕著な顕著な地域的傾向として認められる。その他の樹種としては、スギ、ヒノキがやや多く、カヤ、サワラと続くが、コウヤマキにみられるような明確な使用の選択性は認められない。近畿地方を中心とした地域では、前期〜中期にはコウヤマキの使用率が90%に近い高率を示す。コウヤマキの使用率は後期になると80%程度になり、6世紀末〜7世紀初頭頃を境にして選択的な使用はみられなくなる。この状況の要因は、コウヤマキ材の大量消費による資源の枯渇であったと考えられる。後期におけるコウヤマキ材の不足状態は、木棺自体の小型化や、部材の軽薄化、細長い板の接ぎ合わせ行為などから裏付けられる。コウヤマキ材の選択的使用地域の枠組みが古墳時代を通じて変化せず、その使用のあり方に一定の階層性も反映していることから、古墳時代にはコウヤマキ材を供給する何らかの木材移送システムが存在していた可能性が高い。また、6〜7世紀にはコウヤマキの自生しない朝鮮半島南部の百済王陵へ棺材としてのコウヤマキ材の供給もおこなわれており、そうしたシステムへの王権の関与を示唆する事実として興味深い。
1 0 0 0 OA 前十字靱帯の力学特性
- 著者
- 林 和彦 白崎 芳夫 池田 洋教 立石 哲也 下條 仁士 宮永 豊
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バイオレオロジー学会
- 雑誌
- 日本バイオレオロジー学会誌 (ISSN:09134778)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.26-32, 2003-06-30 (Released:2012-09-24)
- 参考文献数
- 12
The mechanical properties of the anterior cruciate ligament (ACL) were investigated. The method of a versatile clamp was designed to holding the femur-ACL-tibia complex (FATC). Twelve porcine FACT specimens were tested at angle 30° and the parallel direction of the ACL. The static tensile and stress relaxation tests were performed with an Instron-type universal testing machine. Differences in stress-strain behavior at the two (slow and fast) deformation rates. The ACL AM (anteromedial) bundle exhibited significant distribution of the deformation at the two deformation rates. Good agreement is obtained using Y. C. Fung's QLV (quasi-linear viscoelastic) theory relationship between theoretical and experimental data.