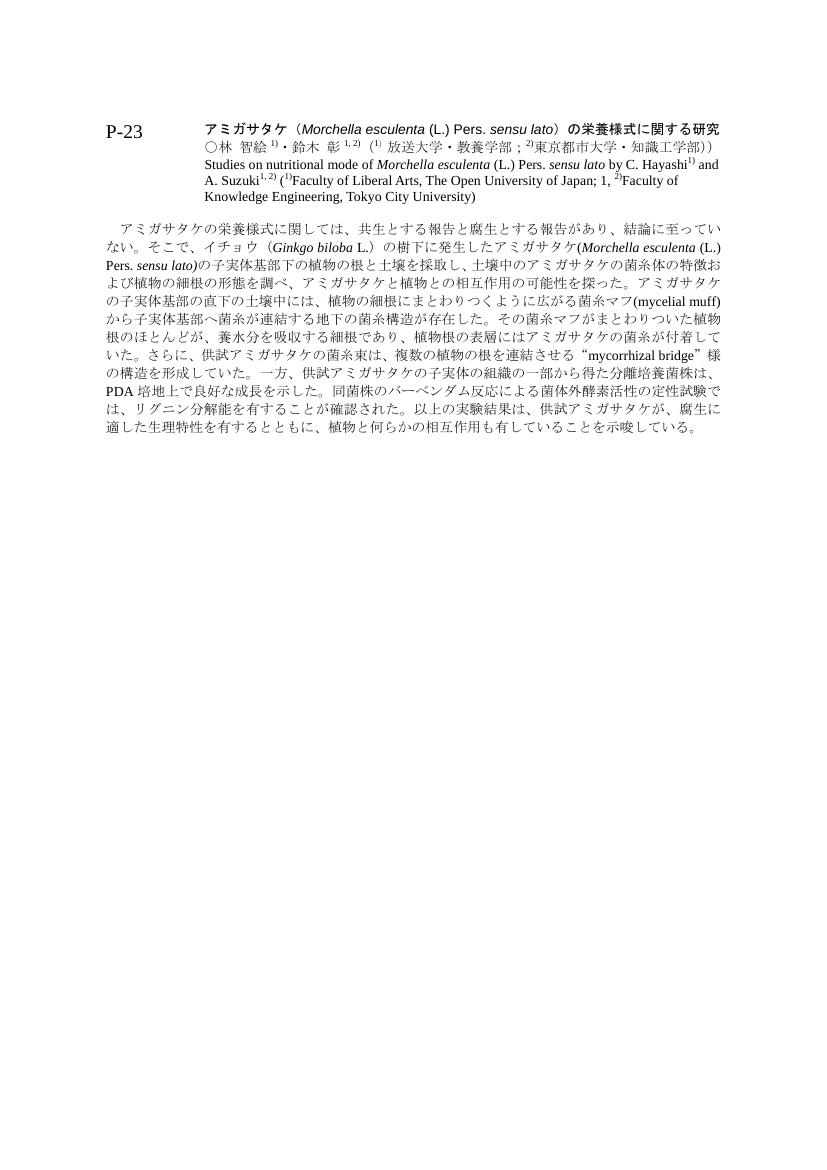- 著者
- 八木 龍平 林 吉郎
- 出版者
- 多文化関係学会
- 雑誌
- 多文化関係学 (ISSN:13495178)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.1-15, 2006
本研究の目的は、林(1999, 2001)が提唱した6眼モデルの主体眼・客体眼マインドセットを測定する心理テストを開発し、その信頼性と妥当性を検証することである。まず異文化体験の豊富な13名が行ったブレーン・ストーミングの結果を基に、我々は129項目の質問項目候補を作成した。そして異文化コミュニケーション専門家グループが個々の項目内容を精査した結果に基づいて、我々は40項目から成る暫定版テストを作成した。暫定版テストを656名に実施して因子分析を行った結果、自己準拠性尺度6項目(a=.73)、自己主張性尺度3項目(a=.62)、客体依存性尺度3項目(a=.64)、グループ準拠性尺度6項目(a=.70)、主体境界柔軟性尺度6項目(a=.70)から成る5下位尺度24項目の主体・客体準拠性および主体・客体境界管理テストが構成された。本テスト及び類似する他の尺度を293名に実施し、相関分析を行った結果、本テストは構成概念妥当性と再検査信頼性があることを確認した。
1 0 0 0 IR 北茨城市平潟町における漁業地域の構造変容
- 著者
- 市川 康夫 横山 貴史 杉野 弘明 水野 卓磨 橋本 暁子 木村 昌司 田林 明 ICHIKAWA Yasuo YOKOYAMA Takafumi SUGINO Hiroaki MIZUSHlMA Takuma HASHIMOTO Akiko KIMURA Masashi TABAYASHI Akira
- 出版者
- 筑波大学人文地理学・地誌学研究会
- 雑誌
- 地域研究年報 (ISSN:18800254)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.1-11,13-37, 2012
1 0 0 0 IR 孤独死報道の歴史
- 著者
- 小辻 寿規 小林 宗之
- 出版者
- 立命館大学大学院先端総合学術研究科
- 雑誌
- Core Ethics : コア・エシックス = Core Ethics : コア・エシックス (ISSN:18800467)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.121-130, 2011
1 0 0 0 水道給水栓から発見されたユスリカ幼虫
- 著者
- 田中 伸久 小林 貞 田中 英文 佐々 学 萱原 伊智郎 山口 安宣 林 治稔 小澤 邦寿
- 出版者
- 日本ペストロジー学会
- 雑誌
- ペストロジー学会誌 (ISSN:09167382)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.1-5, 2004
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
群馬県内において,ユスリカ幼虫が上水道給水栓から発見される苦情事例が発生した.ユスリカは,ヨシムラツヤユスリカおよびハモンユスリカ属の幼虫であり,これらは浄水場内でも確認されたことから,浄水場内のユスリカ幼虫が給水栓に達したものと推測された.また,前塩素濃度を上げる,凝集剤 (PAC) を多めに入れる,濾過機の逆洗回数を増やす,清掃を行うなどの積極的かつ厳重な管理によって,このような事例は防ぎうることが示唆された.
1 0 0 0 観光写真調査法で地域の魅力を再発見する
- 著者
- 林 幸史
- 出版者
- 一般社団法人 交通科学研究会
- 雑誌
- 交通科学 (ISSN:02881985)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.18-23, 2020
本稿では,魅力ある観光地域づくりのための調査手法として,観光写真調査法が有益であることを述べた.観光写真調査法(TPM)は,従来の魅力調査では,捉えることが困難であった感性や直観を魅力評価に反映させた手法であり,個人が観光地に対して抱く集合的・個別的イメージ(魅力)および,個々の観光資源に付与された価値を把握することができる.TPMの実施手続きを解説するとともに,奈良をフィールドとしたTPMの実践例を紹介した.最後に,着地型のコミュニティ・ツーリズムでの観光振興におけるTPMの応用可能性について議論した.
1 0 0 0 OA 縦隔内甲状腺腫を合併した巨大胸腺脂肪腫の1例
- 著者
- 坂口 昌幸 新宮 聖士 春日 好雄 小林 信や 天野 純 保坂 典子 野村 節夫
- 出版者
- Japan Surgical Association
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.12, pp.3021-3026, 1998-12-25 (Released:2009-01-22)
- 参考文献数
- 52
症例は45歳女性.検診で前頸部腫瘤を指摘され,縦隔内甲状腺腫と診断された.この時に胸部X線で右横隔膜の挙上を指摘され, CT, MRIにて右肺下面と横隔膜との間に巨大な腫瘤を認め,右肺中葉を圧排していた. CT値より脂肪腫,胸腺脂肪腫が疑われた.これらの腫瘍を摘出した.縦隔内甲状腺腫は256g,縦隔内巨大腫瘤は2,000gで,病理組織学的にはそれぞれ腺腫様甲状腺腫,胸腺脂肪腫と診断された.縦隔内甲状腺腫を合併した胸腺脂肪腫は極めて稀で,われわれが検索しえた限りでは,本症例1例のみであった.
1 0 0 0 中国甘粛新出土木簡選
- 著者
- 西林昭一編著 「中国甘粛新出土木簡選」編集委員会
- 出版者
- 毎日新聞社
- 巻号頁・発行日
- 1994
1 0 0 0 OA 単細胞・多細胞生物進化の熱力学的解明
1 0 0 0 IR カラオケ利用料金の支払い場面における自閉性障害生徒の援助行動の指導
- 著者
- 若林 上総 加藤 哲文
- 出版者
- 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科
- 雑誌
- 教育実践学論集 = Journal for the science of schooling (ISSN:13455184)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.11-21, 2015-03
- 著者
- 新井 雅信 中津 雅美 袖山 信幸 三條 伸夫 三谷 雅人 小林 一成 織茂 智之 芝 紀代子
- 出版者
- 日本電気泳動学会
- 雑誌
- 生物物理化学 (ISSN:00319082)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.243-248, 1994
著者らはα<sub>1</sub>-antichymotrypsin (ACT) の糖鎖の違いが疾患特異的に存在するか否かを検討する目的で, 交差親和免疫電気泳動法 (CIAE) に着目した. CIAEは一次元, 二次元とも支持体に1%アガロース, 親和性リガンドにはコンカナバリンA (Con A) を用いた. 基礎的検討から一次元ゲルのCon A濃度は0.1%, 二次元ゲルの抗ACT抗体濃度は0.3%, 染色法は4-methoxy-1-naphthol 法が最も優れていることが判明した. 数例の対照群, アルツハイマー型痴呆 (DAT) 患者, パーキンソン病 (PD) 患者の血清, 髄液を本法に適用した. いずれのサンプルも類似した4本より構成されるピークが認められたので, 最も陰極側のピークからACT1~4と名づけた. 血清ACT4は対照群に比べ, PD, DATでは増加傾向を示し, 髄液ACT1, ACT4では対照群に比べDATで低下傾向を示した. 本法は蛋白濃度の低い体液の糖蛋白の検討に有用と思われた.
1 0 0 0 IR 書評 義江明子著『古代王権論 : 神話・歴史感覚・ジェンダー』
- 著者
- 小林 昌二
- 出版者
- 帝京大学文学部史学科
- 雑誌
- 帝京史学 (ISSN:09114645)
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.213-229, 2012-02
- 著者
- 倉渕 隆 鳥海 吉弘 平野 剛 遠藤 智行 栗林 知広 小峯 裕己
- 出版者
- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会
- 雑誌
- 空気調和・衛生工学会 論文集 (ISSN:0385275X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.117, pp.1-10, 2006-12-05 (Released:2017-09-05)
- 参考文献数
- 19
建築基準法の改正に伴い,居室には原則として機械換気設備の設置が義務付けられることとなったが,現状では地域性や建物性能に対応した換気システムの適切な選択方法が整備されていない状況にある。本研究では,住宅に設置される各種常時換気設備について,外界気象条件や建物気密性能による問題点と改善対策を解明することを目的とし,戸建住宅を対象とした年間に渡る換気シミュレーションによる検討を実施した。その結果,第1種換気設備-本体給排気では建物気密性能によらず良好な換気充足度の評価を得ることができるが,第1種換気設備-居室給排気および第2種換気設備-居室給気では2階居室の空気汚染が問題になること,第3種換気設備-水周り排気では2階の新鮮外気の給気量不足が問題になることなどを明らかにし,考えられる改善対策の効果について検討した。
- 著者
- 林 智絵 鈴木 彰
- 出版者
- 日本菌学会
- 雑誌
- 日本菌学会大会講演要旨集 日本菌学会第62回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.90, 2018 (Released:2019-04-17)
1 0 0 0 麦麹のフェノール性物質について
- 著者
- 栗林 義宏
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.12, pp.549-552, 1967
- 被引用文献数
- 1
(1) 麦麹抽出液のフェノール性物質の検出に1次元ペーパークロマトグラフィーを行なった。展開溶剤としてベンゼン:エタノール:2-ブタノール:N-アンモニア(30:30:30:10v/v)系がバニリン酸,フェルラ酸,バニリンの分離にすぐれていることを見出した。<BR>(2) 麦麹のフェノール性物質として従来未知のバニリン酸,フェルラ酸およびバニリンの存在を証明した。<BR>(3) 麦麹のくり香ようのにおいは,これらフェノール性物質が一因子と考えた。
- 著者
- 高林 晴夫 北川 道弘 関沢 明彦 Purwosunu Yuditiya 千葉 博 伊川 和美 末岡 宗廣
- 出版者
- 日本産科婦人科学会
- 雑誌
- 日本産科婦人科學會雜誌
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, 2008
1 0 0 0 OA 地方史を通してみた旧長六橋の評価について
- 著者
- 戸塚 誠司 小林 一郎
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木史研究 (ISSN:09167293)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.25-36, 1997-06-05 (Released:2010-06-15)
- 参考文献数
- 39
Kato Kiyomasa became the Load of Higo (northern half of Kumamoto prefecture) in 1588 and the development of Kumamoto city began from that period. Choroku bridge was constructed under the direction of Kato Kiyomasa and it is believed to be the first bridge over the Shirakawa river which runs across the Kumamoto city from east to west. Because of swift-moving waters of the Shirakawa during the rainy season, this wooden bridge was demolished and reconstructed repeatedly. From the second half of Meiji era, people wished eagerly for a strong steel bridge against the flood and the former Choroku bridge was realized in 1927 as the largest steel tied-arch of Japan.This paper describes the design concept of the former Choroku bridge. The contextual meaning of the bridge site is discussed based on the research of documents and local news papers about the successive Choroku bridges and citezen's activities for the realization of the steel bridge. It is concluded that the understanding of regional sociological history as well as technological history are very important criteria for the evaluation for civil engineering structures
- 著者
- 橋場 貴史 清水 康史 橋本 茂樹 疋島 千裕 渡邉 奈津希 小林 尚史
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, pp.CcOF2080, 2011
【目的】一般的に肩関節周囲炎は自然放置していれば治癒すると認識されているが、その病態や病因は多岐にわたり、炎症の終息が遅れ、拘縮を引き起こし長期化するケースも少なくない。病期によって症状が異なるため、患者自身における疾患への理解と時期を見極めた適切な処方は重要である。このような肩関節周囲炎に対しての治療は第一に保存療法が選択されるが、その保存療法の期間に関連する要因を報告したものは散見する。<BR>柴田らは五十肩(凍結肩)を屈曲135°以下と定義しているが、今回は五十肩までの可動域制限を来たしていない肩関節周囲炎患者における保存療法に影響を与える要因を罹患肢の違いや発症からの期間、そして初診時の肩関節可動域(以下ROM)の状態から検討することである。<BR>【方法】対象は平成21年4月から平成22年10月までに当院で肩関節周囲炎と診断され、初診時の屈曲可動域(他動運動)は140°以上であり、保存療法を施行し経過を追えた34名34肩(男性16名、女性18名、利き手側24名、非利き手側10名、平均年齢57.9±12.3歳)であった。保存療法の内訳は、内服+関節注射+運動療法16名、関節注射+運動療法5名、内服+運動療法9名、運動療法のみ4名であった。<BR>収集したデータの項目は、罹患期間、保存療法期間、初診時の肩関節可動域(ROM)とした。期間の設定は、発症から保存療法開始までの期間を以下、罹患期間とした。また、保存療法を開始し、日常生活での疼痛およびROM等の肩関節機能改善が認められ、その時点から約2~4週間の間その症状が安定し、医師の判断で保存療法が終了となった期間を以下、保存療法期間とした。ROMデータは初診時、他動的に測定された肩関節屈曲、外転、下垂位外旋、外転位外旋、外転位内旋のデータを用いた。<BR>【説明と同意】初診時においてデータ収集の目的、使用用途、プライバシーの保護等を説明し、同意が得られた患者を対象とした。<BR>【データ処理】罹患期間、初診時ROM、保存療法期間の平均値を算出した。また罹患期間及び保存療法期間のデータおいて90日未満の患者をA群、90日以上180日未満の患者をB群、180日以上をC群とそれぞれ群分けを行った。<BR>【データ解析】1.罹患肢側おける保存療法期間を比較する為に対応のないt-検定を用い、検討した。2.罹患期間の違うA、B、C群と保存療法期間の関係をpeasonの相関係数で検討した。3.保存療法期間のちがうA、B、C群のROM(肩関節屈曲、外転、下垂位外旋、外転位外旋、外転位内旋)を一元配置分散分析で比較し、多重比較はscheffeを用いて保存療法期間との関連を検討した。各々の有意水準は5%未満とした。<BR>【結果】今回対象者の罹患期間日数は161.4±157日、保存療法期間は116.1±70.4日であった。罹患肢側おける保存療法期間は、利き手側は112.9±59.6日、非利き手側は123.8±94.8日であった。これらの比較において有意な差は認められなかった。罹患期間と保存療法期間の関係は、A群(n=11)r=0.71 p<0.05で相関を認めたが、B群(n=11)r=0.14、とC群(n=12) r=-0.1は相関が認められなかった。保存療法期間のちがうA、B、C群のROMの比較においては外転位内旋の項目のみ有意にA群が高い値を示した。<BR>【考察】肩関節周囲炎と診断され、初診時屈曲可動域が140°以上の対象者において罹患肢の違いや罹患期間、ROMの状態が保存療法期間に関連しているかを検討した。本研究からは罹患肢の違いによる影響は認められないが、罹患期間が90日未満で早期に保存療法を開始すれば保存療法期間が短くなり、保存療法期間が短いものは外転位内旋可動域が良好であったことが解った。このことから早期に診断を受け、外転位内旋可動域が良好時から保存療法を開始すれば早期に機能改善、治癒に導くことが出来るのではと考えられた。<BR>【理学療法学研究としての意義】本研究は肩関節周囲炎の原因究明などには役立つ内容ではないが、早期に適切な診断、治療を受けることが症状の重篤化、長期化を予防する上で重要であることが解った。また予後予測や評価・治療及び患者へのインフォームドコンセントなどの一助になり、今回の結果は有用な情報となりうると考える。<BR>