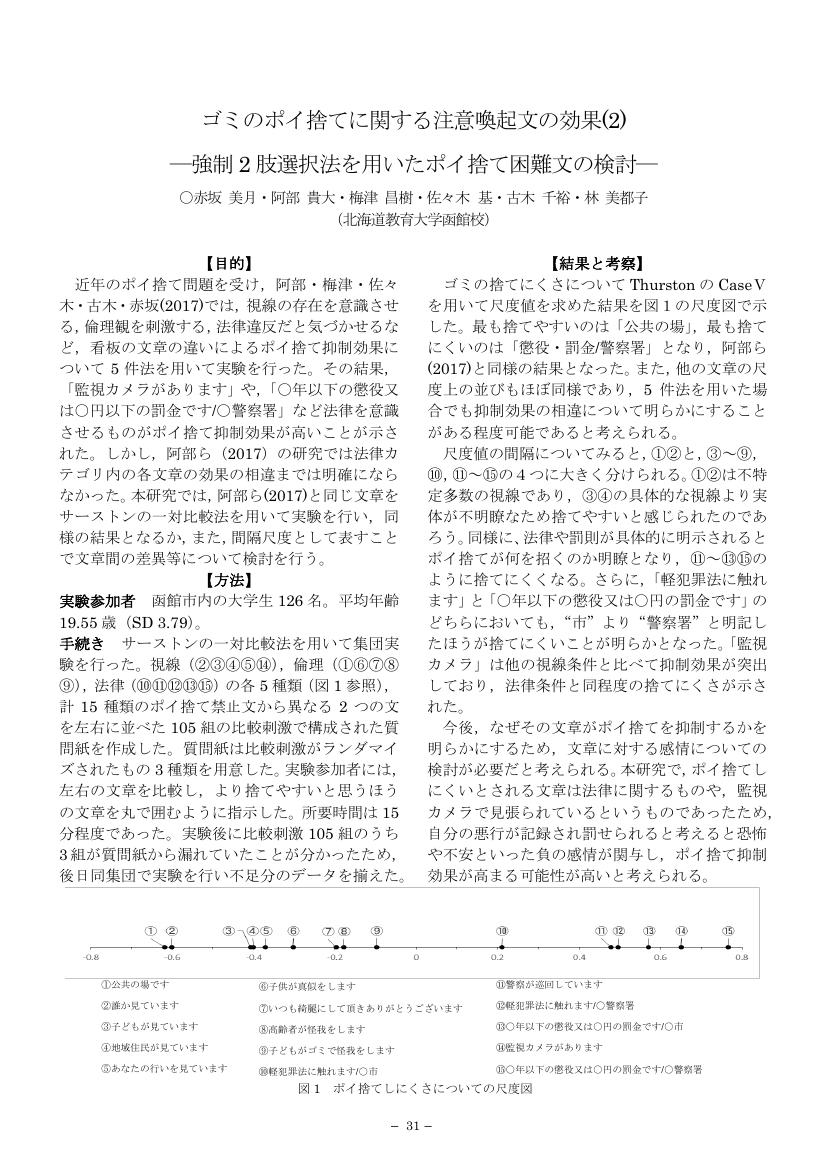- 著者
- 木村 昭夫 五十嵐 英夫 潮田 弘 奥住 捷子 小林 寛伊 大塚 敏文
- 出版者
- 一般社団法人 日本感染症学会
- 雑誌
- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.223-230, 1993
- 被引用文献数
- 7 3
全国国立大学付属病院より分離収集された黄色ブドウ球菌430株を, コアグラーゼ型別に加えてエンテロトキシン (SE) 並びにToxic Shock Syndrome Toxin-1 (TSST-1) 産生性をマーカーとして疫学的に細分し, これらの疫学マーカーと10種抗菌剤に対する感受性の関連性について調査した. 全黄色ブドウ球菌はVCMに感受性であった。OFLXには, コァグラーゼII型-SEA+SEC+TSST-1産生株は高度耐性傾向を示したが, 他の株では約半数が感受性であった. FMOXに対して, コアグラーゼIV型-SEA産生株では感受性菌が78%に認められた。しかし, コアグラーゼII型-SEA+SEC+TSST-1産生株には, 感受性菌は存在しなかった. IPMに対して, コアグラーゼIV型-SEA産生株, コアグラービIII型-毒素非産生株およびコアグラーゼII型-毒素非産生株においては, 50%以上の感受性菌が認められた。しかし, コアグラービII型-SEC+TSST-1産生株およびコアグラーゼII型-SEA+SEC+TSST-1産生株では耐性化が進んでいた。MINOに対して, コアグラーゼIII型-毒素非産生株およびコアグラーゼII型-毒素非産生株は良好な感受性を示した。しかし, コアグラービII型-SEC+TSST-1産生株およびコアグラーゼIV型-SEA産生株では中間的な感受性を示し, コアグラーゼII型-SEA+SEC+TSST-1産生株では感受性が著しく低かった。STに対して, コアグラーゼIV型-SEA産生株は耐性化が進行していたが, 他の株は良好な感受性を示した。
1 0 0 0 IR 支援職のオリエンタリズム的思考 : 『発達障害がある人のナラティヴを聴く』を読む
- 著者
- 林 桂生 Hayashi Keisei ハヤシ ケイセイ
- 出版者
- 大阪大学言語文化学会
- 雑誌
- 大阪大学言語文化学 = Journal of language and culture (ISSN:09181504)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.17-29, 2017
論文
1 0 0 0 OA 8. 原子力利用
- 著者
- 中杉 秀夫 林 昇一郎 渡辺 喜亮 中杉 秀夫 船矢 敏朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本エネルギー学会
- 雑誌
- 燃料協会誌 (ISSN:03693775)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.8, pp.643-668, 1982-08-20 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 21
1 0 0 0 OA 主観的健康感とその要因についての検討: 生活形態と健康維持への意識との関連
- 著者
- 栁澤 節子 小林 千世 山口 大輔 上原 文恵 吉田 真菜 鈴木 風花 松永 保子
- 出版者
- 信州公衆衛生学会
- 雑誌
- 信州公衆衛生雑誌 (ISSN:18822312)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.107-113, 2018-03
本研究の目的は、主観的健康感と生活形態、健康維持への意識、および地域社会活動との関連を検討することであった。2015 年7 月にM 市内の総合球戯場でゲートにいた成人と、2016 年9 月から10 月にM市内の商業施設の成人の来店者とS 大学医学部主催の健康講座に来た成人の参加者を調査対象者とした。調査内容は対象者の属性、主観的健康感、生活形態、直接スポーツ観戦の有無などであり、無記名式質問紙調査を実施した。分析は、主観的健康感について「主観的健康感高群」と「主観的健康感低群」に分けて、それらを従属変数とし、「地域活動に関する事柄」、「生活習慣に関する事柄」、「健康維持に関する意識」、「直接スポーツ観戦の有無」を独立変数として、多重ロジスティック回帰分析を行った。その結果、「夢中になれるもの」(OR=3.41、95% CI=1.270─9.167)、「規則正しい生活」(OR=2.64、95% CI=1.251─5.585)、「直接スポーツ観戦」(OR=2.584、95% CI=1.158─5.766)が、主観的健康感を高める要因であった。これらのことから、人生において、夢中になれるものがあることや、規則正しい生活を送ること、直接スポーツを観戦することが、主観的健康感に大きな影響を与えていることが分かった。また、直接スポーツを観戦することや、直接スポーツをすること以外にも、スポーツに関わる、あるいは携わることが、健康に対する意識を高め、健康の保持増進に影響を与えることが推察された。したがって、スポーツができない高齢者や患者においても、スポーツを観戦することで、主観的健康感が高まり、人生における楽しみや生きがいにつながり、「近隣の人との交流」、「地域での活動に参加する」などの社会的活動やその役割、意識をも高め、主観的健康感も高まると考えられた。今後、健康寿命の延伸に向けた健康づくりのためには、今回明らかになった主観的健康感を高めるような要因が充実する介入や支援ができる体制を作り上げることが重要であると考えられた。
1 0 0 0 OA 腹臥位での脊椎手術後に重症急性膵炎を発症した一例
- 著者
- 浦上 淳 平林 葉子 富山 恭行 河瀬 智哉 吉田 浩司 岡 保夫 平井 敏弘 角田 司
- 出版者
- 一般社団法人 日本膵臓学会
- 雑誌
- 膵臓 (ISSN:09130071)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.38-44, 2012 (Released:2012-03-21)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1 1
症例は76歳女性で糖尿病,慢性膵炎の既往がある.第12胸椎の圧迫骨折のため脊椎短縮術,後方固定,後側方固定術を施行された.腹臥位で,手術時間6時間20分であった.麻酔覚醒後から腹痛が出現し,術後1日目も腹痛は強く,膵酵素,WBC,CRPの上昇を認め,予後因子スコア5点で重症急性膵炎と診断.造影CTでは膵頭部の腫大および膵頭部内の造影不良域を認め,右腎下極以遠までの滲出液貯留を認めたため,造影CT grade 2と診断.蛋白分解酵素阻害薬・抗菌薬膵局所動注療法などの治療を行った.術後16日目の造影CTでは膵頭部の造影不領域が増大し,右後腹膜膿瘍も増大した.十二指腸の壁構造は消失し,十二指腸壁の壊死と考えられた.術後18日目に膵頭十二指腸切除術(PD)を行った.手術では十二指腸は広範に壊死に陥り,後腹膜膿瘍を形成していた.術後は縫合不全など大きな合併症はなく,PD術後101日に退院した.
1 0 0 0 OA ハイデガーと生物学 : 機械論・生気論・進化論
- 著者
- 小林 睦
- 出版者
- 岩手大学人文社会科学部
- 雑誌
- Artes liberales (ISSN:03854183)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, pp.1-16, 2008-07-07
本稿の目的は,ハイデガーにおける「生命」概念を理解するために,彼の思索と生物学との関係を整理・検討してみることにある1)。これまで,ハイデガーと生の哲学との関係については多くの議論がなされてきたが,彼の哲学と生物学との関わりについては,あまり語られることがなかったように思われるからである。 そのためには,ハイデガーがその著作や講義録で行なっている,必ずしも多いとは言えない生物学への言及を手がかりに,彼が当時の生物学によって提案されていた主張をどのように評価あるいは批判していたのか,また,彼がその生物学からどのような影響を受けていたのか,を明らかにする必要がある。 哲学者としてのハイデガーは,アリストテレス研究から出発して,その思索の途を歩み始めた。このことを考慮するならば,彼の生命観を理解するためには,アリストテレスの「生(ζω´η)」概念から引き継いだものを無視することはできない。周知の通り,アリストテレスの生命論は,歴史的に見て,「生気論」の古典的かつ代表的な形態であるとみなされている。 「生気論(Vitalism)」とは,生命現象には物質には還元できない本質(生気)が伴っており,環境に適応するための合目的性は生命そのものがもつ自律性にもとづく,とする立場である。それは,「機械論(Mechanism)」のような,生命現象がそれを構成する物質的な諸要素が組み合わされることによって生じ,物理−化学的な諸要素に還元することができる,と主張する立場とは真っ向から対立する。生命の本性をめぐる解釈の歴史は,こうした生気論と機械論とが互いにその正当性を主張しあう論争の歴史であったと言うことができよう。 アリストテレスの場合,生命における可能態(δ´υναμις)としての質料を,現実態(εʼντελ´εχεια,εʼν´εργεια)へともたらすものが,形相としての「魂(ψυχη´, anima)」である。魂の定義は多義的であるが,その本義は,〈生きる〉という活動─栄養摂取,運動,感覚,思考─の原理として規定されており,植物・動物・人間などの違いに応じて,魂はその生命活動を具現化する形相にほかならない,とされる2)。 こうした思想を熟知していたハイデガーは,アリストテレスと同じく何らかの「生気論」に与するのだろうか。それとも,同時代の生物学において有力であった「機械論」的な発想に理解を示すのだろうか。あるいは,そのいずれとも異なる第三の生命観を主張するのだろうか。 以上のような問題意識にもとづいて,本稿ではまず,(1)ハイデガーによる生命への問いが何を意味するのかを整理する。次に,(2)ハイデガーが機械論的な生命観に対してどのような態度をとっていたのかを確認する。さらに,彼が「生物学における本質的な二歩」を踏み出したとみなす二人の生物学者──ハンス・ドリーシュとヤーコプ・ヨハン・フォン・ユクスキュル──について,(3)ドリーシュの新生気論に対するハイデガーの評価,および,(4)ユクスキュルの環世界論とハイデガーとの関係,をそれぞれ検討する。その上で,(5)生気論と機械論に対するハイデガーの批判を振り返りつつ,動物本性にかんするハイデガーによる意味規定を分析する。最後に,(6)ハイデガーにおける反進化論的な態度が何に由来するのかを考察し,その思想的な特徴を確認した上で,本稿を閉じることにしたい。
1 0 0 0 成田国際空港の航空機事故に対する災害医療体制の再構築
- 著者
- 益子 一樹 松本 尚 本村 友一 平林 篤志 斎藤 伸行 八木 貴典 原 義明
- 出版者
- 日本航空医療学会
- 雑誌
- 日本航空医療学会雑誌 = Journal of Japanese Society for Aeromedical Services (ISSN:1346129X)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.9-14, 2017-08
- 著者
- 小林 比出代
- 出版者
- 全国大学書写書道教育学会
- 雑誌
- 書写書道教育研究
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.41-47, 2017-03
1 0 0 0 OA 横浜F・マリノスが地域に与える定量・定性効果に関する研究
- 著者
- 町田 優作 林 啓人 田村 浩哉 柚木 友哉 居城 琢
- 出版者
- 横浜国立大学 地域実践教育研究センター
- 雑誌
- 横浜国立大学地域実践教育研究センター地域課題実習・地域研究報 2018年度
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, pp.150-154, 2018
1 0 0 0 21295 超高層免震構造の開発と適用 : その1 全体概要
- 著者
- 村井 信義 内山 義英 山本 雅史 吉岡 宏和 佐野 友治 芳沢 利和 鈴木 重信 倉林 浩 白井 武樹
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集. B-2, 構造II, 振動, 原子力プラント (ISSN:13414461)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, pp.589-590, 1998-07-30
1 0 0 0 OA 学童保育施設における児童の栄養状態を反映したおやつ提供のあり方の検討
- 著者
- 吉村 弘太 小林 ゆき子 青井 渉 木戸 康博 桑波田 雅士
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養士会
- 雑誌
- 日本栄養士会雑誌 (ISSN:00136492)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.31-38, 2021 (Released:2021-01-01)
- 参考文献数
- 29
学童期の児童にとって、おやつは補食としての役割を担う。しかし、学童保育施設の運営指針ではおやつの具体的な内容や栄養価については提言されておらず、空腹感を和らげる目的でしかとらえられていない。本研究では、学童保育施設を利用する児童の栄養状態と習慣的な食事摂取量を調査し、施設におけるおやつ提供のあり方について検証を試みた。K市に所在する15の学童保育施設を利用する児童を対象に、小学生・中学生・高校生のための簡易型自記式食事歴法質問票を用いた食事調査を実施し、有効回答を得られた293人(有効回答率38.6%)を解析対象とした。その結果、①京都府平均と比較して痩身傾向と肥満傾向の割合が高い、②脂質と食塩の摂取量において食事摂取基準を逸脱した者の割合が高い、③低学年と比較して中学年または高学年でカルシウムや鉄等の栄養素が摂取不足の傾向にあることが明らかとなった。現状提供されているおやつ内容ではこれらの課題は解消されないこと、施設でのおやつ提供の内容再考と児童の成長に合わせた栄養価の確保が必要であることが示唆された。
- 著者
- 秋山 英也 吉田 典弘 西川 通則 飯村 靖文 小林 駿介
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会技術報告 (ISSN:03864227)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.53, pp.1-6, 1995
- 参考文献数
- 8
Magnetically aligned nematic liquid crystai (NLC) cells were prepared using three kinds of non-rubbed polyimides (Pls) having different surface tension (polarity) as alignment films. The effects of the degree of polarity of PI on LC alignment were studied in terms of the observation of the texture and the isotropic to nematic (I-N) phase transition and the polar anchoring energy measurement. On the I-N phase transition first nematic phase appeared in the bulk for cells with PI having moderate and low degree of polarity, while it appeared from the surfaces for a cell with PI having a high polarity.
1 0 0 0 OA 地域住民におけるヘルスリテラシーと高血圧・糖尿病・脂質異常症の関連:横断研究
- 著者
- 木村 宣哉 小林 道
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.12, pp.871-880, 2020-12-15 (Released:2020-12-31)
- 参考文献数
- 34
目的 地域から層化無作為抽出した集団において,相互作用的・批判的ヘルスリテラシー(CCHL,Communicative and Critical Health Literacy)と高血圧・糖尿病・脂質異常症の関連を横断的に明らかにすることを目的とした。方法 2018年7~8月,北海道江別市の3,000人(20~75歳未満)を対象に自記式質問紙調査を実施した。江別市は大きく3地区に分かれており,参加者は各地区から1,000人を層化無作為抽出した。調査票は,市の職員によって配付・回収が行われた。調査終了後,市から匿名化されたデータを受け取り,分析を実施した。解析に当たって,結果が返送された1,630人から調査票のCCHLの項目が未記入の8人,疾患の有無の項目が未記入の43人を除外し,男性692人と女性887人でそれぞれ解析を行った。CCHLは,疾患および生活習慣等の要因の傾向性を観察するために四分位で群分けした。高血圧,糖尿病,脂質異常症の有無を目的変数とし,CCHLを説明変数とした。年代,世帯構成,配偶者,最終学歴,仕事の有無,肥満区分,定期的な運動,喫煙,朝食欠食を調整変数として,男女別に多重ロジスティック回帰分析を行った。結果 全体のCCHLスコアは3.58±0.67(平均値±標準偏差)だった。単変量回帰の結果では,CCHLスコアの第一分位群を参照群とした場合に第四分位群で,男性の高血圧の割合が有意に低下した(OR=0.49; 95%CI: 0.28-0.84)。一方で,調整変数を含めた多重ロジスティック回帰の結果では,男性の高血圧の調整済みオッズ比は0.62(95%CI: 0.32-1.22)となった。CCHLと疾患の関連について,男女ともすべての項目で有意差は認められなかった。結論 男性では,CCHLが高いほど高血圧の有病率が有意に低い傾向が認められたが,多変量解析による調整後では関連性が弱まり,その他の疾患についても関連は認められなかった。HLと生活習慣病の関連をより明確にするためには,縦断研究による検討を実施する必要がある。
1 0 0 0 歯科診療アシストスーツの開発と機能評価
- 著者
- 石井 信之 木庭 大槻 許 多 佐藤 イテヒョン 清水 千晶 田中 俊 林田 優太郎 菅原 美咲 水野 潤造 武藤 徳子 鈴木 二郎 室町 幸一郎 下島 かおり 藤巻 龍治 宇都宮 舞衣 山田 寛子
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会
- 雑誌
- 日本歯科保存学雑誌 (ISSN:03872343)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.38-43, 2020
<p> 目的 : 現在では, 歯科用実体顕微鏡や拡大鏡を使用した拡大視野下の長時間にわたる精密歯科診療が求められ, 歯科医師や歯科衛生士の正確な手技への支援や肉体的負担を軽減できる歯科診療支援システムの開発が必要とされている. 本研究は歯科診療アシストスーツを開発することで, 歯科診療の精密性向上, 診療成功率の向上, および歯科医師や歯科衛生士の肉体的負担軽減を目的とする.</p><p> 材料と方法 : 歯科診療アシストスーツの上腕負担軽減効果を解析するために, 表面筋電図による解析と定量評価機能を有した臨床シミュレーション装置を使用した臼歯部窩洞形成を実施した.</p><p> 結果 : 歯科診療アシストスーツを作動することで, 上腕二頭筋および上腕三頭筋の平均振幅値はいずれも有意に減少し, 上腕の負担軽減効果が認められた. 臼歯部窩洞形成の客観的総合評価は, 歯科診療アシストスーツ作動前と比較して作動後に有意な高得点を示した.</p><p> 結論 : 本研究で開発した歯科診療アシストスーツは, 上腕二頭筋と上腕三頭筋の緊張を軽減することによって, 診療精度の向上と長時間診療における術者の負担軽減を可能にする装置であることが示された.</p>
1 0 0 0 OA 森山花鈴『自殺対策の政治学』
- 著者
- 小林 悠太
- 出版者
- 日本行政学会
- 雑誌
- 年報行政研究 (ISSN:05481570)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.127-130, 2019 (Released:2020-09-17)
1 0 0 0 OA 四肢切断者と幻肢 (多肢欠損者について)
1 0 0 0 OA 焼きリンゴにおける多糖類の分解と組織の崩壊
- 著者
- 渕上 倫子 治部 祐里 小宮山 展子 林 真愉美 〓田 寛子 横畑 直子 松浦 康
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.11, pp.871-879, 2008 (Released:2010-07-29)
- 参考文献数
- 16
焼きリンゴの軟化とペクチンあるいは多糖類の分解との関係について検討した.焼きリンゴを160℃~190℃において60分間加熱して調製したとき, ペクチンと多糖類の水溶性画分は生リンゴのそれらに比べて増加した.一方, ペクチンと多糖類のシュウ酸塩可溶性画分は生リンゴのそれに比べて減少した.このように, 焼きリンゴの組織の軟化は不溶性ペクチンと不溶性多糖類が可溶性になることによって起こるものと考えられる.ゲル濾過やDEAE-トヨパールクロマトグラフィーの結果によれば,ペクチンと多糖類は低分子化しており,これらの低分子化は主として高温下, 弱酸性の条件においてリンゴ酸の作用による加水分解によるものであり,β-脱離反応による影響は少ないことを明らかにした.
1 0 0 0 OA 非線形最適化問題を解くための数値解法の研究およびその実装
- 著者
- 矢部 博 成島 康史 M. Al-Baali 五十嵐 夢生 稲葉 洋介 大谷 亮介 小笠原 英穂 加藤 惇志 小林 宏 菅澤 清久 中谷 啓 中村 渉 中山 舜民 林 俊介 原田 耕平 平野 達也 柳田 健人 山下 浩 山本 哲生 渡邉 遊
- 出版者
- 東京理科大学
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2013-04-01
大規模な無制約最適化問題に対する3項共役勾配法ならびに微分不可能な関数を含む非線形方程式系に対する共役勾配法について新しい解法を提案し、その大域的収束性を示した。また、無制約最適化問題を解くための準ニュートン法に関してメモリーレス準ニュートン法および目的関数値のみを利用する準ニュートン・パターンサーチ法も研究した。制約付き最適化問題に対して実行可能方向を生成する新しい非厳密逐次二次制約二次計画法を提案しその大域的収束性・超1次収束性を示した。さらに、画像処理などの応用分野で扱うトレース比最適化問題に対する新しい解法も提案した。以上の提案解法について数値実験を行って、実用的な有効性を検証した。