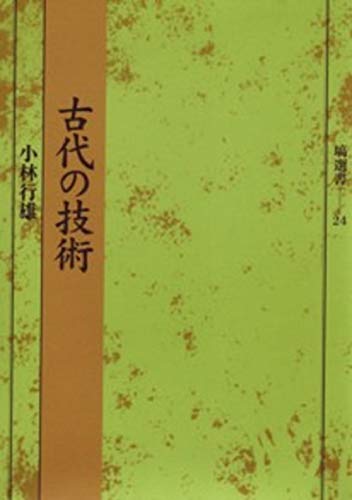- 著者
- 林 典雄 浅野 昭裕 青木 隆明
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, pp.CaOI1021, 2011
【目的】肘関節周辺外傷後生じる伸展制限に対する運動療法では、特に終末伸展域の改善には難渋することが多い。その要因について筆者らは、上腕筋の冠状面上での筋膜内における筋束の内側移動、上腕骨滑車を頂点とした遠位筋線維の背側へのkinkig、加えて長橈側手根伸筋の筋膜内後方移動、上腕骨小頭と前面の関節包と長橈側手根伸筋のmusculo-capsular junctionでの拘縮要因などについて、超音波観察を通した結果を報告してきた。一方、肘伸展制限は前方組織にのみ由来するわけではなく、肘伸展に伴う後方部痛の発生により可動域が制限される症例もまれではない。このような肘終末伸展に伴う後方部痛は、関節内骨折後の整復不良例や肘頭に発生した骨棘や遊離体が原因となる骨性インピンジメントを除けば、後方関節包の周辺組織の瘢痕や関節包内に存在する脂肪体に何らかの原因を求めていくのが妥当と考えられる。本研究の目的は、後方インピンジメント発生の好発域である30°屈曲位からの終末伸展運動における肘後方脂肪体の動態について検討し、運動療法へとつながるデータを提供することにある。<BR>【方法】肘関節に既往を有しない健常成人男性ボランティア10名の左肘10肘を対象とした。肘後方脂肪体の描出にはesaote社製デジタル超音波画像診断装置MyLab25を使用した。プローブは12Mhzリニアプローブを用いた。方法は、被験者を測定台上に腹臥位となり、左肩関節を90°外転位で前腕を台より出し、肘30°屈曲位で他動的に保持した。その後徐々に肘を伸展し、15°屈曲時、完全伸展時で後方脂肪体の動態を記録した。<BR> 画像の描出はプローブにゲルパッドを装着して行った。上腕骨後縁が画面上水平となるように肘頭窩中央でプローベを固定すると、上腕骨後縁、肘頭窩、上腕骨滑車、後方関節包、後方脂肪体、上腕三頭筋が画面上に同定される。その後、上腕骨後縁から肘頭窩へと移行する部分で水平線Aと垂線Bを引き、水平線Aより上方に位置する脂肪体と垂線Bより近位に位置する脂肪体それぞれの面積を計測し、前者を背側移動量、後者を近位移動量とした。脂肪体面積の計測はMyLab25に内蔵されている計測パッケージのtrace area機能を使用した。統計処理は一元配置の分散分析ならびにTukeyの多重比較検定を行い有意水準は5%とした。<BR>【説明と同意】なお本研究の実施にあたっては、本学倫理委員会への申請、承認を得て実施し、各被験者には研究の趣旨を十分に説明し書面にて同意を得た。<BR>【結果】背側移動量は30°屈曲時平均26.7±10.5mm2 、15°屈曲時平均42.2±16.1mm2 、完全伸展時平均59.7±15.5mm2であった。完全伸展時の脂肪体背側移動は、30°屈曲時、15°屈曲時に対し有意であった。30°屈曲時と15°屈曲時との間には有意差はなかった。近位移動量は30°屈曲時平均5.4±2.9mm2 、15°屈曲時平均11.9±8.4mm2 、完全伸展時平均20.6±10.8mm2 であった。完全伸展時の脂肪体近位移動は、30°屈曲時に対し有意であった。30°屈曲時と15°屈曲時、15°屈曲時と完全伸展時との間には有意差はなかった。<BR>【考察】本研究で観察した後方脂肪体は滑膜の外側で関節包の内側に存在する。肘後方関節包を裏打ちする形で存在するこの脂肪体は、超音波で容易に観察可能であり、薄い関節包の動態を想像する際に、伸展運動に伴う脂肪体の機能的な変形を捉えることで、間接的に後方関節包の動きを推察することが可能である。今回の結果より後方脂肪体は、肘の伸展に伴い肘頭に押し出されるように機能的に形態を変形させながら、より背側、近位へ移動することが明らかとなった。この脂肪体の移動は併せて関節包を背側近位へと押し出す結果となり、後方関節包のインピンジメントを回避していると考えられた。我々は以前に後方関節包には上腕三頭筋内側頭由来の線維が関節筋として付着し、肘伸展に伴う挟み込みを防ぐと報告したが、後方脂肪体の機能的変形も寄与している可能性が示唆された。投球に伴う肘後方部痛症例や関節鏡視下に遊離体などを切除した後の症例で伸展時の後方部痛を訴える例では、後方脂肪体の腫脹像や伸展に伴うインピンジメント像をエコー上で観察可能であり、肘後方インピンジメントの一つの病態として認識すべきものと考えられた。<BR>【理学療法学研究としての意義】実際の運動療法技術においては、後方関節包自体の柔軟性はもちろん、肘頭窩近位へ付着する関節包の癒着予防が脂肪体移動を許容する上で重要であり、内側頭を含めた上腕骨からの引き離し操作も拘縮治療を展開するうえでポイントとなる技術と考えられる。
- 著者
- 小林 祐太 中井 雄一朗 木勢 峰之 矢口 悦子 米田 香 古河 浩 寺岡 彩那 山﨑 敦
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.Ab0658, 2012
【はじめに、目的】 股関節疾患患者において、バランス能力低下により立位や歩行での動揺の増大がよくみられる。不安定板上立位での姿勢制御の反復練習にて、より高い姿勢制御能力が獲得される可能性があるとした報告はあるものの、立位や歩行にどのように影響するかの報告は少ない。そこで本研究では、股関節疾患患者に対し不安定な支持面での立位バランス練習にて、実施前後での即時的な重心動揺や歩行の変化について検討する。【方法】 対象者は当院整形外科受診の前期股関節症1名と、変性疾患・外傷により手術治療 (人工股関節全置換術2名、ハンソンピン1名、γ-nail1名)を施行した4名を対象とした。性別は、男性3名、女性2名、年齢67.5±9.1歳とした。立位バランス練習には、株式会社LPNのハーフストレッチポール(以下HSP)を使用した。HSPは平面側を床側にして、規定した幅(身長×0.40÷2)で横向きに並ぶように前後に1つずつ設置した。その上に片脚ずつ均等な荷重で乗せて歩隔は肩幅として立位をとり、5秒保持した後に、15秒休息をとった。次に脚を前後逆にして同様に行い、これを1セットとして、計5セット行った。この運動前後に、小型三次元加速度計(ユニメック社)を第3腰椎の高さに固定し、自由歩行の加速度を計測した。また、フットスイッチを踵部に装着して踵接地を同定した。サンプリング周波数は200Hzとし、アナログ解析ソフトWAS(ユニメック社)にて9Hzのローパスフィルターで処理し、二乗平方根値を歩行速度の二乗値で除した値(以下RMS)を加え前後・側方・垂直成分にて解析した。さらに、定常歩行から得られた患側踵接地からの1歩行周期の加速度波形に対して自己相関係数(以下ACC)の前後・側方・垂直成分を算出した。また、患側上後腸骨棘、大転子、大腿骨外側上顆の3点にマーカーをつけ、加速度測定時の歩行をデジタルカメラで撮影し、ICpro-2DdA(ヒューテック株式会社)にて歩行時の3点間の角度を算出した。この結果を静止立位時と比較して、患側立脚後期の股関節最大伸展角度を算出した。さらに、重心動揺計(ユニメック社)を使用し、運動前後の重心動揺を計測した。開眼・自然立位にて20秒間の測定を行った。指標として、前後・側方方向単位軌跡長を用いた。各々の値は2回の測定結果の平均値を用い、その結果を基に中央値と四分位範囲で表し運動前後を比較した。統計処理にはPASW Statistics 18を用いてWilcoxon signed-rank testを行い、5%未満を統計学的有意とした。【倫理的配慮、説明と同意】 ヘルシンキ宣言に基づき、対象者には本研究の目的、内容、個人情報取り扱いについて口頭および書面にて説明し、同意書への署名により同意を得た。また、本研究は当院倫理委員会の承諾を得て行った。【結果】 各項目は運動前→運動後の順に中央値(四分位範囲)で示す。RMSは前後成分0.15(0.08)→0.16(0.17)、側方成分0.14(0.07)→0.14(0.07)、垂直成分0.22(0.12)→0.12(0.12)であったが、有意差は見られなかった。ACCは前後成分0.85(0.15)→0.88(0.07)、側方成分0.67(0.28)→0.76(0.11)、垂直成分0.66(0.17)→0.89(0.11)と3方向において増加が見られ、側方成分には有意な増加が見られた。 重心動揺は前後方向単位軌跡長(mm/s)が9.55 (3.30)→6.70 (4.35)、側方方向単位軌跡長(mm/s)が4.45 (1.85)→4.60 (1.25)と前後は減少が見られ、側方は増加が見られたが有意差は見られなかった。股関節伸展角度(°)は-0.72(2.75)→-5.24(5.76) と有意な減少が見られた。【考察】 不安定な支持面での立位姿勢保持には、効果的に足関節トルクを用いることができず、股関節による制御が行われるといった報告がみられる。今回HSP上で不安定な立位状況を設定することで、股関節による制御が促通されることを仮説として本研究を実施した。今回の結果から、股関節での制御が促通され、歩行時の側方の規則性において有意に改善させた可能性が示唆される。側方の姿勢制御は、足関節に対して股関節が優位とされていることから上記の結果に繋がったと推察される。一方、歩行時の前後方向への動揺性の増加は、立脚後期の股関節伸展角度減少による推進力低下を体幹などで代償した結果、前後方向の動揺性の増加に起因したのではないかと考えられる。今後は、運動時中の筋電図測定なども行い、姿勢制御戦略に影響を与えている因子を検討していく必要がある。【理学療法学研究としての意義】 本研究の運動が、即時効果として立位や歩行時に影響を与えることが確認できた。不安定な支持面で姿勢制御戦略を促通させることは、股関節疾患患者の歩行効率の改善に有効であることが示唆される。
1 0 0 0 「大東亜共栄圏」の文化史的研究
1 0 0 0 風語解析
- 著者
- 土佐林 義雄
- 出版者
- 日本気象学会
- 雑誌
- 天気 (ISSN:05460921)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.3, pp.79-85, 1954-07
1 0 0 0 アイヌ文身文様の構成
- 著者
- 土佐林 義雄
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:00215023)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.4, pp.382-388, 1949
- 著者
- 土佐林 義雄
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:00215023)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.3, pp.286-299, 1952
Kuwa or grave-posts of the Ainu are considered by the Ainu themselves to be sticks for the dead. Their possible origin from the hoe (kuwa in Japanese) was also once suggested. But there is nothing in their forms, varying from village to village, which can support such a view. Nor can there be any influence of Christianity in their. T or Y forms and X signs upon them. The author, analyzing not only their forms, but also the way in which strings are bound around them, came to the conclusion that the Ainu gravepost represents a part of the arrow-trap amakpo erected originally to avert evil spirits. In the folkbelief of the East, a magical power to subdue evil spirits is attributed to tightly-bound strings. A further proof is offered by the Ainu word ku wa (bow). In the northeastern district of Honshu, Japan, we find also the custom of erecting a bow on the grave. The author assumes that the custom probably originated in Korea or China.
- 著者
- 堀口 俊一 寺本 敬子 西尾 久英 林 千代
- 出版者
- 公益財団法人大原記念労働科学研究所
- 雑誌
- 労働科学 (ISSN:0022443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.4, pp.130-142, 2012 (Released:2014-03-25)
- 参考文献数
- 46
我が国において,1895(明治28)年に「所謂脳膜炎」と称される乳幼児の疾病が報告されて以来,その原因が母親の用いる白粉中の鉛による中毒であることが1923(大正12)年京都大学小児科教授平井毓太郎によって明らかにされた。以来,小児科学領域において,該疾患に対する研究報告が堰を切ったように発表された。本稿では,前報及び前々報に続き,1927(昭和2)年以降,鉛白使用化粧品に対する規制が明文化された1930(昭和5)年までの4年間に「児科雑誌」に発表された該疾患に関する諸論文,学会発表等83編を内容別に分類し,今回はそのうち総説,症例,臨床所見,診療,病理・剖検の各項目について取り上げて論考した。(写真3)
1 0 0 0 IR 連合国戦争犯罪政策の形成 -連合国戦争犯罪委員会と英米(下)-
- 著者
- 林 博史
- 出版者
- 関東学院大学経済学部教養学会
- 雑誌
- 自然人間社会 (ISSN:0918807X)
- 巻号頁・発行日
- no.37, pp.51-77,
本稿では連合国の戦争犯罪政策の形成過程について、連合国戦争犯罪委員会に焦点をあて、同時に連合国の中小国の動向、役割に注意し、かつイギリスとアメリカ政府の動向を合わせて分析する。枢軸国による残虐行為に対してどのように対処するのかという問題を扱うために連合国戦争犯罪委員会が設置された。委員会は従来の戦争犯罪概念を超える事態に対処すべく法的理論的に検討をすすめ、国際法廷によって犯罪者を処罰する方針を示した。だがそれはイギリスの反対で潰された。その一方、委員会の議論は米陸軍内で継承されアメリカのイニシアティブにより主要戦犯を国際法廷で裁く方式が取り入れられていった。委員会における議論はその後に定式化される「人道に対する罪」や「平和に対する罪」に繋がるものであり、理論的にも一定の役割を果たすことになった。だが当初の国際協調的な方向から米主導型に変化し、そのことが戦犯裁判のあり方に大きな問題を残すことになった。
1 0 0 0 OA 大学博物館の現状と未来
- 著者
- 林 良博
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.18-23, 2007-02-01 (Released:2012-02-15)
1 0 0 0 焼酎原料用サツマイモ : 品種開発の変遷と今後の展望
- 著者
- 小林 晃
- 出版者
- 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, no.2, pp.71-78, 2019-02
サツマイモは日本全国で栽培されており,平成29年全国の作付面積は,前年に比べ400ha(1%)減少した3万5600ha,生産量は前年に比べ5万3600トン減少した80万7100トンである。サツマイモの主な用途としては,市場販売用,でん粉原料用,焼酎原料用,加工食品用があるが,平成27年においては生産量全体の25%,約20万トンのサツマイモが焼酎原料として消費されている。また,焼酎メーカーが多く所在する宮崎県および鹿児島県では,焼酎原料用途の消費比率が高く,宮崎県産および鹿児島県産サツマイモのそれぞれ66%(5.6万トン),48%(14.3万トン)が焼酎原料として使われており,南九州における焼酎原料用サツマイモは農業生産においても,また,地域経済においても重要な品目となっている。国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研究センター都城研究拠点サツマイモ育種グループ(所在地 宮崎県都城市)では,これまでに様々なサツマイモの品種開発を行ってきたが,ここでは,焼酎原料用サツマイモを中心に,品種開発の変遷と今後の展望について紹介する。
1 0 0 0 OA 権威主義・保守主義・革新主義
- 著者
- 小林 久高
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.4, pp.392-405,478, 1989-03-31 (Released:2010-05-07)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1 1
権威主義の基本概念は、弱者に対する攻撃を意味する権威主義的攻撃と強者に対する服従を意味する権威主義的服従の結合にある。アドルノ、ロキーチ、アイゼンクの研究を検討すると、この権威主義の基本的な意味と保守主義とが密接に関係していることがわかる。この事実を説明するために、一つの図式が提出される。この図式は、概念的な観点から、権威主義と保守主義の密接な結合を明らかにしたものである。次に、シルズのいう左翼権威主義の問題が検討される。そこでは、左翼の位置する体制の違いを考慮する必要性、体制に対する態度と党派に対する態度の違いを考慮する必要性、態度とパーソナリティのレベルの違いを考慮する必要性が述べられ、自由主義・資本主義体制内の左翼は、過激主義的ではあるが、右翼に比べて権威主義的ではないという指摘がなされる。
1 0 0 0 OA フケ症に対するミコナゾール硝酸塩配合リンスの有用性の検討
- 著者
- 清 佳浩 小林 めぐみ 早出 恵里
- 出版者
- 日本医真菌学会
- 雑誌
- Medical Mycology Journal (ISSN:21856486)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.229-237, 2011 (Released:2011-08-31)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2 3
フケ症を対象に,ミコナゾール硝酸塩配合シャンプー(COF)にミコナゾール硝酸塩配合リンス(COFRM)を併用した際のCOFRMの有用性について,リンス基剤(COFR)併用群を対照とした二重盲検比較試験により検討した.その結果,両群間で有効性に差はみられなかったが,いずれの群でも約80%の症例で改善効果が認められた.また,瘙痒については,試験開始2週後で統計学的有意差は認められなかったが,COFR併用群に比べCOFRM併用群の方が高い改善率を示した.また洗髪頻度によって効果に違いがみられたCOFR併用群に対し,COFRM併用群は洗髪頻度に依らず効果がほぼ同等であったことが示された.この事からシャンプーのみならずリンスにもミコナゾール硝酸塩を配合することにより,洗髪間隔に係わらず有効濃度が維持され,その結果Malassezia属真菌の増殖を妨げ,より確実かつ早期に効果が現れるものと考えた. 以上のことから,COFRMはCOFと併用することで,短期間で効果を実感でき,その結果患者のコンプライアンス向上に寄与する有用なリンス剤であると考えられた.
1 0 0 0 OA 景気循環および所得税・法人税の減税効果再現のためのABMモデル条件
- 著者
- 高島 幸成 荻林 成章
- 出版者
- 一般社団法人 経営情報学会
- 雑誌
- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2014年秋季全国研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.177-180, 2014 (Released:2015-01-30)
景気循環およびGDPに及ぼす減税の影響を再現するためのモデル条件について一連の計算機実験により検討した。その結果、景気循環を再現するための必要条件は投資に際しての信用創造がモデルに内包されていること、またGDPに及ぼす所得税減税効果再現のための必要条件は政府による非効率な支出がモデルに内包されていること、GDPに及ぼす法人税減税効果再現のための必要条件は政府による非効率な支出に加えて、減税による利益剰余金を支出するメカニズム(経営者報酬、設備投資における自己資金使用)が内包されていること、であることがわかった。このことは特定のマクロ現象を再現するために必要不可欠なモデル構造が存在することを示している。
- 著者
- 設楽 仁 高岸 憲二 下山 大輔 石綿 翔 高澤 英嗣 一ノ瀬 剛 山本 敦史 小林 勉
- 出版者
- 日本肩関節学会
- 雑誌
- 肩関節 (ISSN:09104461)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.755-759, 2013
<B>Background:</B> There are many studies about the relationship between brain functional changes and chronic pain such as CRPS, fibromyalgia, osteoarthritis of the knee and chronic back pain.<BR>However there is no study about the relationship between brain functional changes and shoulder disease. The purpose of this study is to clarify the brain functional changes regarding to shoulder pain using functional magnetic resonance image (fMRI) in rotator cuff tear (RCT) patients.<BR><B>Methods:</B> Nine healthy volunteers and 9 RCT patients participated in this study. Brain activation was examined by fMRI technique (3 Tesra-MRI). We applied an active shoulder motion task and a motor imagery task during fMRI.<BR><B>Results:</B> In the active shoulder motion task, there was significant activation in the right premotor cortex, right primary somatosensory cortex, right superior parietal lobule, bilateral prefrontal cortices, right intraparietal sulcus, anterior cingulate cortex, left lingual gyrus and left cerebellum in RCT group compared to normal group.<BR>In the motor imagery task, there were brain activities in the left prefrontal cortex and supplementary motor area which was related to the pain matrix despite the absence of feeling pain in RCT group compared to normal group. <BR><B>Conclusion:</B> The current study reveals that RCT can cause reorganization of the central nervous system, suggesting that such an injury might be regarded as a neurophysiologic dysfunction, not a simple peripheral musculoskeletal injury. This study is the first evidence that the pain with RCT is related to the brain functional change.
- 著者
- 山本 昌樹 林 省吾 鈴木 雅人 木全 健太郎 浅本 憲 中野 隆
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, pp.48100444, 2013
【はじめに】上腕筋は,上腕骨前面下半部に単一の筋頭を有するとされるが,Gray’s Anatomy(2005)においては「2 〜3 部からなる変異が見られる」と記載されている.一方,Leonello et al.(2007)は,「上腕筋は,全例において浅頭と深頭の2 頭を有する」と報告している.我々は,第16 回臨床解剖研究会(2012)において,上腕筋が3 頭から構成されることを明らかにするとともに,肘関節屈曲拘縮との関連について報告した.今回,これら3 頭の形態的特徴と機能について考察する.【対象および方法】愛知医科大学医学部において,研究用に供された解剖実習体15 体24 肢を対象とした.上肢を剥皮後,上腕二頭筋,腕橈骨筋,長・短橈側手根伸筋を展開した.上腕筋を起始部より分離して筋頭を同定し,筋頭の走行や配列を詳細に観察した.【倫理的配慮,説明と同意】本研究は,死体解剖保存法に基づいて実施し,生前に本人の同意により篤志献体団体に入会し研究・教育に供された解剖実習体を使用した.観察は,愛知医科大学医学部解剖学講座教授の指導の下に行った.【結果】全肢において,上腕筋は,三角筋後部線維から連続する筋頭(以下,外側頭),三角筋の前方の集合腱から連続する筋頭(以下,中間頭),上腕骨前面から起始する筋頭(以下,内側頭)に区分することができた.外側頭は,上腕骨の近位外側から遠位中央に向かって斜めに,かつ,浅層を走行して腱になり,尺骨粗面の遠位部に停止していた.中間頭は,最も薄く細い筋束であり,内側頭の浅層を外側頭と平行して走行し,遠位部は内側頭に合流していた.内側頭は,最も深層を走行し,停止部付近においても幅広く厚い筋腹から成り,短い腱を介して尺骨粗面の近位内側部に停止していた.これら3 頭は,上腕中央部においては,外側から内側へ順に配列していた.しかし肘関節部においては,外側頭と中間頭は浅層に,内側頭は深層に配列していた.また,内側頭の縦断面を観察すると,一部の線維が肘関節包前面に付着する例が存在した.これらの例において肘関節を他動的に屈曲させると,内側頭とともに関節包の前面が浮き上がる様子が観察された.【考察】上腕筋を構成する3 頭は,内側から外側へ配列しているだけではなく,各頭が特徴的な走行や形態を呈するため,それぞれ異なる機能を有することが推測される.上腕筋外側頭は上腕骨の近位外側から遠位中央へ,一方の上腕二頭筋は近位内側から遠位中央へ斜走する.そのため肘関節屈曲時,上腕筋外側頭は前腕近位部を外上方へ,一方の上腕二頭筋は内上方へ牽引すると考えられる.すなわち肘関節屈曲時,外側頭と上腕二頭筋は共同で,前腕軸の調整を行うと考えられる.また外側頭は,3 頭の中で最も遠位に停止し,肘関節屈曲における最大のレバーアームを有するため,肘関節屈曲における最大の力源になることが示唆される.さらに,外側頭は三角筋後部線維から連続するため,三角筋の収縮によって,作用効率が変化する可能性がある.換言すれば,外側頭の作用効率を高めるためには,三角筋後部線維を収縮させた上で肘関節屈曲を行うことが有効であると思われる.内側頭は,肘関節部において深層を走行し,幅広く厚い筋腹を有する.したがって,肘関節屈曲時に収縮して筋の厚みが増すことによって,外側頭のレバーアームを維持または延長し,その作用効率を高める機能を有すると考えられる.また,肩関節の腱板が上腕骨頭を肩甲骨へ引き寄せる作用と同様に,内側頭は,尺骨滑車切痕を上腕骨滑車に引き寄せ,肘関節の安定性向上に寄与すると考えられる.さらに,内側頭が関節包前面に付着する例があることから,肘関節運動に伴う関節包の緊張度を調節する機能が示唆される.換言すれば,内側頭の機能不全によって,関節包前面のインピンジメントや肘関節屈曲拘縮が惹起される可能性が推測される.中間頭は,最も薄く細いため,その機能的意義は小さいと思われる.しかし,上腕中央部においては外側頭と並走し,遠位部においては内側頭に合流することから,外側頭と内側頭の機能を連携する,文字通り'中間的な’役割を担うと考えられる.上腕筋は,3頭を有することによって,肘関節屈曲における前腕軸の調整,作用効率の向上,肘関節包の緊張度の調節など複合的な機能を担うと考えられる.また,肘関節屈曲に関しては,主として外側頭が機能することが示唆される.【理学療法学研究としての意義】根拠に基づく理学療法を行うためには,とくに筋骨格系に関する機能解剖学的かつ病態生理学的な研究が不可欠である.本研究は,上腕筋の筋頭構成を詳細に観察し,肘関節運動に対する関与について考察を加えたものであり,肘関節拘縮の病態理解や治療の発展にも寄与すると考える.
1 0 0 0 OA 醤油の新しい機能性
- 著者
- 古林 万木夫
- 出版者
- 日本食生活学会
- 雑誌
- 日本食生活学会誌 (ISSN:13469770)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.4, pp.304-309, 2007 (Released:2007-05-02)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1 1
Soy sauce is a traditional fermented seasoning of East Asian countries and is available throughout the world. In Japanese soy sauce (shoyu), soybeans and wheat are the two main raw materials, used in almost the same quantity. Proteins of the raw materials are completely degraded into peptides and amino acids by microbial proteolytic enzymes after fermentation, and no allergens of the raw materials are present in soy sauce. In contrast, polysaccharides originating from the cell wall of soybeans are resistant to enzymatic hydrolyses. These polysaccharides are present in soy sauce even after fermentation and termed shoyu polysaccharides (SPS). Soy sauce generally contains about 1% (w/v) SPS and SPS exhibit potent antiallergic activities in vitro and in vivo. Furthermore, an oral supplementation of SPS is an effective intervention for patients with allergic rhinitis in two double-blind placebo-controlled clinical studies. In conclusion, soy sauce would be a potentially promising seasoning for the treatment of allergic diseases through food because of its hypoallergenicity and antiallergic activity.
1 0 0 0 外傷性頚部症候群により発生した頚胸椎移行部障害の運動療法について
- 著者
- 赤羽根 良和 永田 敏貢 齊藤 正佳 服部 潤 栗林 純
- 出版者
- 東海北陸理学療法学術大会
- 雑誌
- 東海北陸理学療法学術大会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.28, 2012
<b>【目的】 </b>外傷性頚部症候群(WAD)とは、交通外傷後の包括した臨床症状を意味し、我々はこれまでに、頭頚部移行部障害に対する運動療法の有効性について報告してきた。<br> 今回、WAD後に頚胸椎移行部障害(CTD)を呈した症例に対し、当院で実施している運動療法を行った結果、良好な経過が得られたので、その方法論について紹介する。<br> 尚、本研究は患者に対して十分な説明と了解を得た上で実施した。<br><b>【対象】 </b>2009年4月から2012年4月までに、交通外傷により頚(C)・胸椎(T)を損傷し、当院を受診した症例のうち、対象の選定を全て満たした20例(男性16例、女性4例、年齢39.6±13.4歳)を対象とした。<br> 対象の選定は、①臨床症状の主体は頚背部痛であること②頚部の伸展時痛を認めること③両肩関節の拳上時痛を認めること④C7/T1を徒手で固定すると、頸椎の伸展時痛や両肩関節の拳上時痛が消失すること⑤C7/T1の椎間関節に圧痛を認めること⑥第1肋骨(R1)に圧痛を認めること⑦消炎鎮痛剤の投与や物理療法を実施するも3ヶ月以上明らかな変化を認めないことである。これらを全て満した場合をCTDと判断した。<br><b>【方法】 </b>運動療法は患者を側臥位にさせて実施した。<br> 椎間関節に対する治療は、PTの一方の手でC7棘突起を固定し、他方の手でT1棘突起を把持する。そこから他方の手でT1を尾側方向に滑らせ、椎間関節を離解する。つづいて、深層筋群を収縮することでT1を頭側方向に滑らせ、椎間関節を閉塞する。この操作を繰り返し行うことで、椎間関節の可動域を増大させていく。<br> R1に対する治療は、PTの一方の手で患者の肩関節を拳上させる。他方の手で、中斜角筋と前鋸筋が結合するR1を尾側に押し込みながら各筋のIb抑制を行う。この操作を片方ずつ実施する。R1に圧痛が消失することを目的に実施する。<br><b>【結果】 </b>椎間関節の圧痛が消失した推移は、4週以内が13名、8週以内が20名、12週以内が20名であった。R1の圧痛が消失した推移は、4週以内が12名、8週以内が18名、12週以内が20名であった。頸椎の伸展時痛が完全に消失した推移は、4週以内が10名、8週以内が16名、12週以内が20名であった。<br><b>【考察】 </b>WADでは、頚背部痛を呈することが多く、3ヶ月以上持続すると、慢性化することも少なくない。<br> 生理学的に、頚部の屈曲運動は上位頸椎が主体であるが、伸展運動は頚椎間のみならず、可動域の少ない頚胸椎移行部間でも生じる。また、両肩関節の拳上時には頚胸椎移行部での屈曲運動とR1の拳上運動が生じる。そのため、CTDを呈すると、これらの一連の運動は制限され、疼痛が誘発される。その一方で、C7/T間を徒手で固定すると、これらの疼痛は消失する。この検査はCTDを見極めるための重要な所見であり、また、椎間関節の圧痛も、そこに病態が潜んでいるのか判断するに有効である。<br> 運動療法の目的は、椎間関節の滑り運動の誘導と、R1に付着する筋の柔軟性を獲得することである。これにより、CTDとR1の生理的な連結運動が再獲得できたことが、症状消失に至ったと考えられる。<br><b>【結論】 </b>WADでは頚背部痛を呈することが多く、その中の一つの病態であるCTDは、我々の実施している運動療法が有効と考えられた。
- 著者
- 影山 隆之 河島 美枝子 小林 敏生
- 出版者
- 大分県立看護科学大学
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2002
勤労者のコーピング特性を評価するための既存の質問紙にはさまざまの問題があった。これらを参考に、職域健診や健康教育場面で使いやすい6尺度20項目からなる新しい簡易質問紙を試作した。これを勤労者集団に適用しては信頼性と妥当性を確認する作業を、数回繰り返した。最終的に、18項目からなるコーピング特性簡易評価尺度(BSCP)を完成した。BSCPの下位尺度(積極的問題解決、解決のための相談、気分転換、視点の転換、他者への情動発散、回避と抑制)には十分な内的一貫性と構成概念妥当性が認められ、また因子構造妥当性に男女差がないことも確かめられた。さらに、職業性ストレスや抑うつとBSCP下位尺度との間には中程度の相関があることや、職業性ストレスと抑うつとの関連をコーピング特性が媒介していることも認められ、職業性ストレス過程モデルとの理論的一致が確認された。BSCPを用いた研究の結果、コーピング特性は、喫煙・飲酒習慣・自殺に関する態度などと関連している可能性がある他、病院看護師の喫煙行動が交替制勤務に伴う眠気に対する対処行動の一種である可能性も示唆された。BSCPの再現性の検討、および大集団における標準化の作業は研究期間中に終了できなかったが、近日中に実行する準備を進めている。BSCPは、職業性ストレスに起因するストレインの予測、勤労者の健康問題関連行動・態度の関連要因分析、職場の「ストレスマネジメント研修」の教材などとして、実用的なツールであることが示唆された。