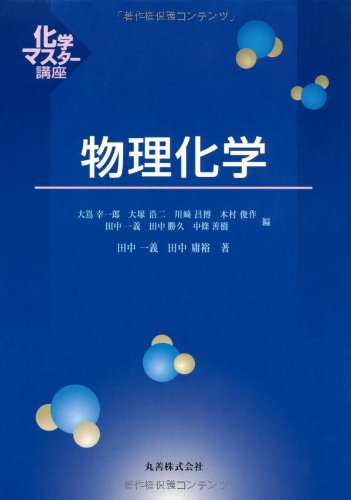1 0 0 0 OA 特許調査業務を改善する特許読解支援システム-特許情報と技術者を近づけるための技術-
- 著者
- 田中 一成 池田 紀子
- 雑誌
- デジタルプラクティス (ISSN:21884390)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.4, pp.378-385, 2016-10-15
特許は企業活動にとって欠かすことのできない財産であり,開発した技術の資産化と資金調達を含む経営判断においても重要である.特許を生み出したり,活用したりするためには特許調査を行う必要があり,その過程で特許文書を読むという作業は避けて通れない.一方で特許文書には独特の読みにくさがあり特許文書を読み解く作業が負担になってしまう.特に特許文書の独特の書き方に不慣れな技術者にとっては深刻な問題である.本稿では,特許文書を読むノウハウを機能として作り込むことによって,特許文書を読む作業を支援するシステムを構築したので報告する.さらに,化学分野に特化した特許読解支援システムの応用を通してさまざまな情報を統合し利活用する可能性について述べる.
- 著者
- 北沢 祐介 寺門 晋 市川 創 前田 和宏 日野 雄太 田中 一伸
- 出版者
- トヨタ自動車技術管理部 ; 1991-
- 雑誌
- Toyota technical review = トヨタ・テクニカル・レビュー (ISSN:09167501)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, pp.71-77, 2016-04
1 0 0 0 OA 気管支喘息 II
- 著者
- 高橋 昭三 可部 順三郎 後藤 和弘 青木 秀夫 萩原 修 栗原 正英 徳島 真彦 須永 吉信 黒沢 元博 根本 俊和 笛木 隆三 小林 節雄 溝部 政史 浦田 誓夫 渡辺 東 阿部 ゆかり 真野 健次 伊藤 幸治 宮本 昭正 岡山 道子 畑岡 勲 井上 洋西 滝島 任 田口 治 飛田 渉 野上 裕子 中島 明雄 池田 賢次 藤田 博司 明瀬 加典 多田 利彦 金森 一紀 魚谷 浩平 高倉 文嗣 岡藤 和博 松田 保 我妻 千鶴 山岸 雅彦 平井 英幸 鈴木 明 成島 道昭 田中 一正 戸野塚 博 金重 博司 国枝 武文 中神 和清 里見 智正 鈴木 一 野口 英世 坂本 裕二 浅井 貞宏 渡辺 尚 林田 正文 原 耕平 谷口 正実 安田 和雅 谷口 ひとみ 菊池 範行 源馬 均 岡野 昌彦 秋山 仁一郎 早川 啓史 本田 和徳 佐藤 篤彦 伊藤 光保 馬場 研二 本多 康希 高木 健三 佐竹 辰夫 富田 忠雄 大川 健太郎 山崎 公世 奥村 二郎 土井 幸雄 岸上 直子 久保 裕一 南部 泰孝 大石 光雄 津谷 泰夫 中島 重徳 宮本 康文 佐野 靖之
- 出版者
- 社団法人 日本呼吸器学会
- 雑誌
- 日本胸部疾患学会雑誌 (ISSN:03011542)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.Supplement, pp.263-270, 1986-03-10 (Released:2010-02-23)
1 0 0 0 玉璽の行方 : 「正統性」の相克
- 著者
- 田中 一輝
- 出版者
- 立命館東洋史學會
- 雑誌
- 立命館東洋史學 (ISSN:13451073)
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.47-75, 2015
1 0 0 0 IR 玉璽の行方 : 「正統性」の相克
- 著者
- 田中 一輝
- 出版者
- 立命館東洋史學會
- 雑誌
- 立命館東洋史學 (ISSN:13451073)
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.47-75, 2015
1 0 0 0 OA RicketyBench:がたつきで人の気配を再現するベンチの開発
- 著者
- 加藤 良治 田中 一晶 中西 英之
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, 2014
人と人とのインタラクションでは相手の気配を感じることができる.そのような人の気配を人工的に生み出すことが本研究の目的である.我々は,人が隣に座った際の座面の振動を再現するベンチと,遠隔地にいる対話相手の姿をユーザの隣に合成して提示する鏡面映像とを組み合わせた遠隔対話システムを開発した.このシステムを用いて,対話相手の身体動作による物理的な作用の再現が気配として感じられる可能性があることを確認した.
1 0 0 0 OA インドネシア編 インドネシアのツーリズム政策
- 著者
- 田中 一郎
- 出版者
- 亜細亜大学
- 雑誌
- ホスピタリティ・マネジメント (ISSN:21850402)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.105-119, 2014
1 0 0 0 OA 骨巨細胞腫の多発肺転移にdenosumabが著効した1例
- 著者
- 田中 一広 前原 博樹 當銘 保則 上原 史成 金谷 文則
- 出版者
- 西日本整形・災害外科学会
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.328-330, 2016-03-25 (Released:2016-05-16)
- 参考文献数
- 5
初回術後多発肺転移と複数回局所再発を来し治療に難渋した右肘頭骨巨細胞腫にdenosumabが著効した1例を報告する.【症例】18歳,女性.右肘頭骨腫瘍にて当科紹介され,単純X線像,切開生検にて骨巨細胞腫の診断に至った.骨腫瘍掻爬,アルコール処理,自家腸骨移植施行後4ヵ月で肺転移を認め化学療法施行,zoledronateを投与した.術後9ヵ月で局所再発し再手術施行するも,計3度再発を来した.転移性肺腫瘍は徐々に増加,増大し初回手術後4年2ヵ月より肺炎,血胸を来すようになりdenosumabを投与開始した所,転移性病変は縮小し症状改善した.10ヵ月投与後に一旦休薬したが,再度転移性病変が増大したため投与を再開した.以降転移性病変は縮小傾向であり,現在術後6年2ヵ月経過している.
1 0 0 0 OA 遠隔対話用ロボットの頷きの自動化とモーションチューリングテストによる検証
- 著者
- 大嶋 悠司 田中 一晶 中西 英之 石黒 浩
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, 2012
本研究では,遠隔対話用ロボットの動きから,対話相手が人であると信じられる度合いを測る方法として,モーションチューリングテストを提案する.これは,操作者の身体動作を再現するロボットを通して対話を行い,そのロボットの動きが操作者のものか自動的な作り物であるかを判断する方法である.このモーションチューリングテストを用いて,ロボットの頷きが人の動きであると信じさせる要因を明らかにする実験を行った.
1 0 0 0 自律・遠隔操作の曖昧化によるロボット操作者との対話感覚の創出
- 著者
- 田中 一晶 山下 直美 中西 英之 石黒 浩
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.1108-1115, 2016-04-15
ヒューマノイドロボットの遠隔操作と自律操作の本質的な違いは遠隔地にいる操作者の存在の有無と考えることができる.この存在の有無をユーザがどのように判断しているのかはいまだよく分かっていない.その判断のメカニズムを明らかにすることによって,自律ロボットとの対話を人との対話のように感じさせることが本研究の目的である.被験者が遠隔操作状態と自律状態のロボットとそれぞれ対話する実験を行った.その結果,自律状態のロボットとの対話における操作者の存在感は,遠隔操作状態であると“信じて”同じロボットと対話した事前の経験に基づいて判断されることが分かった.自律状態での対話の質が事前の経験での対話の質と乖離していると操作者の存在感は低下してしまうが,事前の対話において自律システムが操作者を装ってユーザと対話し,両状態を曖昧化することで,操作者の存在感を効果的に生み出すことができた.
1 0 0 0 物理化学
- 著者
- 田中一義 田中庸裕著 大嶌幸一郎 [ほか] 編
- 出版者
- 丸善
- 巻号頁・発行日
- 2010
- 著者
- 塩崎 恭平 田中 一晶 中西 英之
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.1-4, 2013
1 0 0 0 オオヒメグモの越冬戦略を凍死と餓死の危険性から読み解く
クモのSCPを決定する要因として、餌虫が保持する氷核活性物質の関与が示唆されている(Tanaka 2001)。この点を明らかにするため、氷核活性バクテリアをもちいた操作実験をおこなった。氷核活性バクテリアを摂食した虫をクモに与えたところ、体組織の凍結開始温度である過冷却点(SCP)が上昇したのに対し、バクテリアを摂食していない虫を食べたクモのSCPは低いまま保たれた。このことは、氷核物質が摂食を通して餌虫から捕食者に伝わり、そのSCPに影響をおよぼすことを意味している(投稿中)。本種の凍結回避戦略を理解するうえで、この餌虫由来の氷核活性物質の同定は不可欠であろう。オオヒメグモは休眠という特殊な生理状態で冬を越す。休眠の誘導にともない、貯蔵栄養物質である脂質の蓄積が起きるか否かについて検討した。材料としては、冷温帯個体群(札幌)と亜熱帯個体群(沖縄)を用いた。両者ともに、休眠誘導にともなってTGの蓄積がおきた。このことは、(1)冷温帯でも亜熱帯でも、脂質が越冬時の主要な貯蔵栄養であること、(2)亜熱帯であっても冬季に飢餓の危険性が存在している可能性、を示唆している。貯蔵栄養をじゅうぶんに蓄えたクモは長期の絶食が可能であり、結果として捕食を介した氷核物質のとりこみを回避できる可能性がある。この点を明らかにするために、野外越冬個体の脂質含量とSCPの関連を調べた。まだ、解析は終わっていないが、暖温帯個体群(福岡、宮崎)では両者の間に弱い相関が見出された。飢えた個体は、冬のあいだも積極的に捕食するので、結果としてSCPが高まるのだろう。日本各地で越冬個体の捕食頻度を調査した。捕食頻度は南で高く、北で低かった。この傾向は、越冬個体のSCPの地理的傾向と一致していた。今後、冬季に活動する虫たちが氷核物質を保持しているか否かについての検討が必要だろう。
1 0 0 0 中国古石炭層中の天然フラーレン調査
天然フラーレンC_<60>の存否は未だに定かでない。KT層、PT層など燃焼煤を含むとされる黒色古地層あるいは隕石クレーター中の岩石から抽出される炭素質中に存在するとされるC_<60>濃度は概ね0.1ppm以下で、技術的に確証を取るのは困難である。唯一高濃度に存在し、複数の分析手段を併用して確実な結果が得られたのは中国雲南省一平浪炭鉱産出の石炭であるが、情報が不正確で炭層が特定できず、追加試料は全てネガティブであったために、現地採取を行って確認を行うのが本研究費の目的であった。研究費支給期間中に地質学者を帯同して中国を3回訪問し、一平浪炭鉱のみならず中国各地から石炭サンプルを採取した。一平浪近くの隕石クレーターにも足を伸ばした。また南アフリカに存在するマグマ貫入炭層、世界最大最古の隕石クレーターにも赴いて試料を採集した。その結果以下の結果が得られた。(1)一平浪炭鉱石炭試料のみが0.3%のC_<60>/C_<70>を含み、同試料は共存異常成分として煤と酷似した構造をもつ黒鉛型ナノ炭素粒子、鉄銅硫酸塩ほか一点の未記載鉱物(おそらく高温高圧変態)を含む。またフラーレンは石炭表面に存在する、(2)他の石炭試料に関するフラーレン分析結果は悉くネガティブ。この結果から自然界で発生する衝撃波によるフラーレン生成説が浮上した。しかし、中国の炭鉱に立ち入ることが出来ず、また坑内地図も閲覧が自由にならないので、採取場所の特定は依然として不可能であった。研究期間終了後も粘り強く交渉を続け、漸く最近に至って中国煤炭勘査局が全山から系統的サンプリングを行い、採取した試料を入手することに成功した。時間飛行型質量分光器による予備分析の結果C_<60>が検出され、現在高速液体クロマトグラフによる定量分析中であり、間もなくC_<60>産出場所の正確な位置が特定できる見込みである。
- 著者
- 田中 一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.118-119, 2004
- 参考文献数
- 2
<p></p>
- 著者
- 礒崎 真英 小西 信幸 黒木 誠 野村 保明 田中 一久
- 出版者
- 園芸学会
- 雑誌
- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.4, pp.354-363, 2004-07-15
- 被引用文献数
- 5 10
慣行的なかけ流し方式のロックウールシステム(慣行区)と、我々が開発した培養液をできる限り栽培系外への廃棄量を減らすロックウールシステム(改良区)を用いて、トマト'ハウス桃太郎'の9段穫り栽培を行った。改良区の栽培系外への廃液量は慣行区の9.8%で、大幅に廃液量が削減された。各成分の廃棄量も著しく削減され、削減率はNO3-N 93%、P 99%、K 98%、Ca 87%、Mg 89%、NH4-N 99%であった。改良区の茎長、茎重、葉重および収量は慣行区のそれらと差異がなかったが、茎径は慣行区よりやや細くなり、3果房より上位の果房の平均果実収穫日が3-7日遅れた。改良区では、培地中のCa、Mg、S、Bは、慣行区より2-3倍高い濃度で推移したのに対して、Pは栽培全期間を通して、Kは栽培前半において、それぞれ慣行区より低い濃度で推移した。このPおよびK濃度の低下が茎径が細くなり果実収穫日が遅れた要因の一つであると考えられるので、給液の最適PおよびK濃度についてはさらに検討する必要がある。また、Na濃度は、慣行区では20mg・lier-1前後で推移したのに対して、改良区では栽培後半から次第に上昇し、栽培終了時には135mg・lier-1に達した。今後、改良ロックウールシステムでのトマトの生育・果実収量と原水のNa濃度との関係について明らかにする必要がある。
1 0 0 0 西晋恵帝期の政治における賈后と詔
- 著者
- 田中 一輝
- 出版者
- 史学研究会
- 雑誌
- 史林 (ISSN:03869369)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.6, pp.817-846, 2011-11
- 著者
- 田中 一平 渡邉 清司 中南 秀将 我妻 ちひろ 野口 雅久
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.134, no.11, pp.1219-1225, 2014 (Released:2014-11-01)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1 2
Recently, the procedure for surgical hand hygiene has been switching to a two-stage method and hand-rubbing method from the traditional hand-scrubbing method. Both the two-stage and hand-rubbing methods use alcohol-based hand-rubbing after hand washing. The former requires 5 min of antiseptic hand washing, and the latter 1 min of nonantiseptic hand washing. For a prolonged bactericidal effect in terms of surgical hand hygiene, chlorhexidine gluconate (CHG) has been noted due to its residual activity. However, no detailed study comparing the disinfection efficacy and prolonged effects according to different contents of CHG and the usage of alcohol-based hand-rubbing has been conducted. The glove juice method is able to evaluate disinfection efficacy and prolonged effects of the disinfectants more accurately because it can collect not only transitory bacteria but also normal inhabitants on hands. In the present study, we examined the disinfection efficacy and prolonged effects on alcohol-based hand-rubbing containing CHG by six hand-rubbing methods and three two-stage methods using the glove juice method. In both methods, 3 mL (one pump dispenser push volume) alcohol-based hand-rubbing solution containing 1% (w/v) CHG showed the highest disinfection efficacy and prolonged effects, and no significant difference was found between the hand-rubbing and two-stage methods. In the two methods of hand hygiene, the hand-rubbing method was able to save time and cost. Therefore, the data strongly suggest that the hand-rubbing method using a one pump dispenser push volume of alcohol-based hand-rubbing solution containing 1% (w/v) CHG is suitable for surgical hand hygiene.
1 0 0 0 IR 膀胱摘出により救命しえた気腫性膀胱炎の1例
- 著者
- 田中 一志 武中 篤 楠田 雄司 原口 貴弘 山中 望
- 出版者
- 泌尿器科紀要刊行会
- 雑誌
- 泌尿器科紀要 (ISSN:00181994)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.12, pp.741-744, 2002-12
- 被引用文献数
- 5 7
80歳女.肉眼的血尿,嘔吐が出現し,膀胱鏡で全周性に粘膜の発赤,出血と気泡の形成を認めた.高度の炎症所見,高血糖,脱水を認め,補液,セフォゾプラン投与,レギュラーインシュリンを行った.その後全身倦怠感が増悪し,血液ガス所見で代謝性アシドーシスを認め,意識レベルが低下した.CTで膀胱壁内に著明なガス像を認め,緊急膀胱摘出及び尿管皮膚瘻造設術を行った.膀胱粘膜は全周にわたり暗赤色,浮腫状に変性しており,尿培養及び組織表面の細菌培養でEscherichia coliを認めた.病理所見で,粘膜の上皮細胞はほぼ壊死となって脱落しており,粘膜から粘膜下組織にかけて出血,壊死性の像を認めた.又,粘膜下組織には発生したガスによる著明な大小の腔隙を認めた.術後経過良好で,退院し糖尿病外来治療となったA 80-year-old female with insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) visited our hospital on November 24, 1999, because of nausea, vomiting and macrohematuria. Cystoscopy demonstrated a diffuse hyperemic mucosa and gas-filled vesicles in the submucosa. Despite treatment with antibiotics, infection was not controlled and metabolic acidosis was increased. Simple cystectomy and ureterocutaneostomy were performed. Histological examination showed whole mucosal necrosis and vacuolation with aerogenesis in the submucosa and muscle layer of the bladder. Urine and mucosal surface cultures revealed Escherichia coli infection. After operation, the general condition was improved. Thirty six cases of emphysematous cystitis have been reported in Japan including this case. Successful treatment with cystectomy under the life threatening condition was reported for the first time.