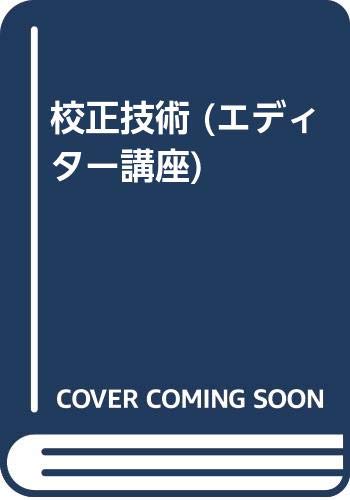1 0 0 0 OA 遠隔地にあるBluetooth機器間のシームレス接続手法の実装と検証
- 著者
- 津田一磨 鈴木秀和 旭健作 渡邊晃
- 雑誌
- 第76回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, no.1, pp.405-406, 2014-03-11
Bluetoothに代表される近距離無線通信技術の発達により,ホームオートメーションの普及が期待されている.今後,宅内にある近距離無線通信機器を外出先から操作したいという要求が高まると考えられる.しかし,このような機器には通信可能範囲に制限があり,外出先から直接操作することができない.筆者らは,Bluetooth機器のハードウェアとソフトウェアの間で交換されるコマンド等をインターネット経由で転送することにより,遠隔地のBluetooth機器へ接続する手法を提案している.この手法によると,ユーザはBluetooth機器の位置を意識することなく,一般のBluetoothアプリケーションを用いてシームレスに接続することができる.本稿では,提案手法をLinux PCへ実装し,動作検証を行った結果を報告する.外出先の操作端末が遠隔地にあるBluetooth機器の検出が可能であることを確認した.
- 著者
- 鈴木 比奈子
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.6, pp.250-255, 2019-06-01 (Released:2019-06-01)
「災害年表マップ」は歴史時代から1600年分,約6万件の日本全国の過去の自然災害事例を災害発生年ごとにWeb地図上で閲覧するアプリケーションである。簡便に過去の災害事例の閲覧を可能にするために取り組んだ。本マップは防災科研が整備する災害事例データベースを利用している。本データベースは日本全国の地域防災計画の過去の災害事例を抽出し,災害の概要が把握できることを目的としたものであり,GISデータとして整備をしている。APIを用いて,他のアプリケーションとのマッシュアップが可能である。災害年表マップを通して,災害事例が掲載される資料へのアクセスや地域の災害発生状況の把握による防災力の向上を目指している。
- 著者
- 佐藤 良夫 川野 昭憲 鈴木 幸治
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会全国大会講演予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.353-354, 1989
1 0 0 0 OA 益田勝実教科書編集の歩み(<特集><豊かさ>の中の文学教育)
- 著者
- 鈴木 醇爾
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.8, pp.44-56, 1991-08-10 (Released:2017-08-01)
この文章では、益田勝実さんが、高校国語教科書の編集者としてすごした三〇年の歩みをたどっている。総合国語時代から、現代国語時代、その前後一〇年ずつと、三時期にわけて、益田さんが発掘したすぐれた教材を紹介すると共に、その教材群がどのような国語科教育を生みだすかにも言及した。戦後の文学教育の中で、最もすぐれた達成であると論者は考えている。
- 著者
- 中村 雅美 青戸 勇太 森山 健 前田 俊二 鈴木 寛 堀江 聖岳
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会学術講演会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, pp.650-651, 2018
<p>高速道路での逆走は、死亡事故につながる可能性が高い非常に危険な事案である。高齢化の進展といった社会状況のもと、逆走事故の発生件数は依然として多い状況にあり、逆走対策の必要性は高い。我々は、一般物体検出手法であるSingle Shot MultiBox Detectorと動きを捉えるOptical Flowを組み合わせた逆走検知手法を提案してきた。本報告では、提案手法の車両検知精度の評価結果について述べる。</p>
- 著者
- 森山 健 青戸 勇太 前田 俊二 鈴木 寛 堀江 聖岳
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会学術講演会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, pp.652-653, 2018
<p>現代の車社会において,衝突防止や駐車支援など車両への安全対策や運転支援技術の搭載が加速されている.特に地方においては,車なしの生活を送ることは不可能に近く,事故を未然に防ぐことは,難しい状況にある.本研究は,逆走事故に焦点を当て,逆走車両の識別を目的とするものであり,本報告では、一般物体検出手法であるSingle Shot MultiBox Detectorと動きを捉えるOptical Flowを組み合わせた逆走検知手法を提案する。</p>
1 0 0 0 IR 「武家故実」にみる服制論
- 著者
- 鈴木 直恵
- 出版者
- 文化女子大学研究紀要編集委員会
- 雑誌
- 文化女子大学研究紀要 (ISSN:02868059)
- 巻号頁・発行日
- no.18, pp.p49-56, 1987-01
1 0 0 0 校正技術
- 著者
- 鈴木兼吉 [ほか] 執筆・編集
- 出版者
- 日本エディタースクール出版部
- 巻号頁・発行日
- 1972
1 0 0 0 『都名所図会』を用いた京都市街地の古水環境の復元
- 著者
- 河野 忠 鈴木 康久
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, 2013
1780(安永9)年に出版された『都名所図会』は,日本で最初の名所図会といわれている。その中には当時の京都が文字による情報だけでなく,挿絵や鳥瞰図として写実的に描かれており,現在の観光ガイドブック的な存在として製本が間に合わないほどの売れ行きとなった。また,1787(天明7)年には,その続編となる『拾遺名所図会』が出版された。その中には名水の記述も多く,全部で150程度を数えることが出来る。1985年当時の環境庁が日本名水百選を発表したが,『都名所図会』に登場する名水は,さながら18世紀京都における名水百選といっても過言ではないだろう。これらの名水は現在どの様な状況に於かれているのだろう,という素朴な疑問から本研究を開始し,京都中の名水を対象に人文科学的および自然科学的な調査を実施した。『都名所図会』に登場する名水の分布は主に京都市街地に集中しているが,北は鞍馬山以北,南は奈良との境にまで及んでいる。多くの名水でその場所は特定できるものの,正確な場所が不明な名水も少なくない。しかし,それはほぼ市街地中央部から南西部に限られている。また,この地域の名水は,石碑のみのものや,新しく掘られたものが少なくないことが分かった。水質および同位体の分析結果から,京都盆地の地下水の水質は,井戸深度に依存するというよりも,地域によって特徴付けられていることが示された。盆地一帯の地下水は概ねCa-HCO3型を示しているが,地域によって(Na+Ca)-HCO3型やNa-Cl型,Na-HCO3型の水質組成を示す地点も見られた。京都盆地には複数の帯水層があることが確認されているが,盆地の地質は砂礫層が厚く堆積しているため,涵養された水は比較的速く浸透する。鴨川近辺の地下水は河川水が混合し,その影響が現れていると考えられる。また,北部山地の湧水では,石灰岩地域の影響を受けてCa-HCO3型の水質組成を示していた。一方,堀川周辺の地下水は井戸深度が比較的浅く,相対的にNO3-濃度が高くなっている箇所もあり,人間活動の影響を受けていると考えられる。名水の現状は,都市化や地下鉄開業などの影響もあって,鴨川以西,地下鉄東西線以南の地域はほぼ涸渇状態となっている。当時の地下水位が数m程度と推定されるものの,現在は50m前後,深いもので100mにも低下している。酒造メーカーの集中する伏見や宇治でも同様で,すべての井戸は新たに再掘削したものであり,宇治の八名水と言われた湧水群は,宇治上神社の「桐原水」のみが細々と湧出を見る程度である。東山以東や京都市街地以外の名水は,比較的当時の状態を保っていると考えられ,水質汚染もほとんど見られない。それに対して市街地にある名水は,西陣や伏見御香宮神社の「御香水」で,硝酸イオンが各々27.6,17.5mg/l検出された。また,近年の都市化や地下鉄開業による地下水環境への影響が名水の存在に大きな影を落としていることも判明した。その一方で,現存する多くの名水は,様々な伝説伝承を語り継ぎ,京都の水文化を物語る重要な文化財となっていることも明らかとなった。本研究は,平成21-23年度科研費補助金(基盤研究C)「『名所図会』を用いた京都盆地における水環境の復元」(研究代表者:河野 忠)の一部を使用した。
1 0 0 0 表面プラズモン共鳴センサーの光学測定原理
1 0 0 0 土石流の構成則に基づいた粒子法モデルの構築と堆積過程への適用
- 著者
- 鈴木 拓郎 堀田 紀文
- 出版者
- 公益社団法人 砂防学会
- 雑誌
- 砂防学会誌 (ISSN:02868385)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.13-24, 2015
<p>The shallow water equations are generally used for numerical simulation of debris flows. In this method, the distributions of the flow velocity <i>u </i>and sediment concentration <i>c </i>are vertically averaged. Therefore, the calculation may be inaccurate when the upper and lower layers have different flow directions, as with countergradient flows. We propose a numerical simulation method for calculating the vertical distributions of <i>u </i>and <i>c </i>in debris flows. Our method is based on the moving particle semi-implicit (MPS) method, which was originally used for incompressible viscous fluid flows with free surfaces. Some modifications are necessary to adapt the method for debris flows. We introduce the constitutive equations of Egashira et al. to the MPS method. In Egashira's equations, debris flows are treated as a continuum. Thus, the proportion of gravel in a debris flow is expressed using the variable <i>c</i>. Similarly, each particle has an associated <i>c </i>value in our modified MPS method. In Egashira's sediment concentration equations, the equilibrium vertical distribution of <i>c </i>is obtained by integrating the rate of change of <i>c </i>in the vertical direction from the riverbed. In our method, <i>c </i>values spread among nearby particles, in order to reduce the difference between the equilibrium rate of change <i>c </i>and the actual rate of change of <i>c</i>. Numerical simulations of debris flow are performed. In the equilibrium condition, there is good agreement with the vertical distributions of <i>u </i>and <i>c </i>and those derived from the constitutive equations. In the condition where the riverbed gradient becomes less steep, there is good agreement with experimental results with a very short relaxation time, including those involving the formation of a convex upward deposition shape in the initial deposition process. Results for the initial deposition process are not produced with existing simulation methods that are based on the assumption of local equilibrium of average sediment concentration. However, simulations with a very short relaxation time show that local equilibrium is established as well as in existing methods. This indicates that the assumption of local equilibrium of sediment concentration is correct, and that because it evaluates the local equilibrium of each particle, our model can yield good results.</p>
- 著者
- 鈴木 克洋 中村 文彦 大塚 慈雨 正井 克俊 伊藤 勇太 杉浦 裕太 杉本 麻樹
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会
- 雑誌
- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.379-389, 2017
<p>The head-mounted displays (HMD) allow people to enjoy immersive VR experience. A virtual avatar can be the representative of a user in the virtual environment. However, the expression of the virtual avatar with a HMD user is constrained. A major problem of wearing an HMD is that a large portion of one's face is occluded, making facial recognition difficult in an HMD-based virtual environment. To overcome this problem, we propose a facial expression mapping technology using retro-reflective photoelectric sensors. The sensors attached inside the HMD measures the distance between sensors and a face. The distance values of five basic facial expressions (Neutral, Happy, Angry, Surprised, and Sad) are used for training the neural network to estimate the facial expression of a user. Our system can also reproduce facial expression change in real-time through an existing avatar by using regression.</p>
1 0 0 0 OA S-netを用いた海域総合解析
- 著者
- 内田 直希 東 龍介 石上 朗 岡田 知己 高木 涼太 豊国 源知 海野 徳仁 太田 雄策 佐藤 真樹子 鈴木 秀市 高橋 秀暢 立岩 和也 趙 大鵬 中山 貴史 長谷川 昭 日野 亮太 平原 聡 松澤 暢 吉田 圭佑
- 出版者
- 日本地球惑星科学連合
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2019年大会
- 巻号頁・発行日
- 2019-03-14
沈み込み帯研究のフロンティアである前弧の海域下において,防災科学技術研究所は新たに日本海溝海底地震津波観測網(S-net)を構築した.S-netは東北日本の太平洋側の海岸から約200kmの範囲を海溝直交方向に約30km,海溝平行方向に50-60km間隔でカバーする150点の海底観測点からなり,その速度と加速度の連続データが,2018年10月より2016年8月に遡って公開された.観測空白域に設置されたこの観測網は,沈み込み帯の構造およびダイナミクスの解明に風穴をあける可能性がある.本発表ではこの新しいデータを用いた最初の研究を紹介する.まず,海底の速度計・加速度計の3軸の方向を,加速度計による重力加速度および遠地地震波形の振動軌跡を用いて推定した.その結果,2つの地震に伴って1°以上のケーブル軸周りの回転が推定されたが,それ以外には大きな時間変化は見られないことがわかった.また,センサーの方位は,5-10°の精度で推定できた.さらに得られた軸方向を用い,東西・南北・上下方向の波形を作成した(高木・他,本大会).海底観測に基づく震源決定で重要となる浅部の堆積層についての研究では,PS変換波を用いた推定により,ほとんどの観測点で,350-400mの厚さに相当する1.3 – 1.4 秒のPS-P 時間が観測された.ただし,千島-日本海溝の会合部海側と根室沖の海溝陸側では,さらに堆積層が厚い可能性がある(東・他,本大会).また,雑微動を用いた相関解析でも10秒以下の周期で1.5 km/s と0.3 km/sの2つの群速度で伝播するレイリー波が見られ,それぞれ堆積層と海水層にエネルギーを持つモードと推定された(高木・他,本大会).さらに,近地地震波形の読み取りによっても,堆積層およびプレート構造の影響を明らかにすることができた.1次元および3次元速度構造から期待される走時との比較により,それぞれ陸域の地震の海溝海側での観測で3秒程度(岡田・他,本大会),海域の地震で場所により2秒程度(豊国・他,本大会)の走時残差が見られた.これらは,震源決定や地震波トモグラフィーの際の観測点補正などとして用いることができる(岡田・他,本大会; 豊国・他,本大会).もう少し深い上盤の速度構造もS-netのデータにより明らかとなった.遠地地震の表面波の到達時間の差を用いた位相速度推定では,20-50sの周期について3.6-3.9km/sの位相速度を得ることができた.これはRayleigh波の位相速度として妥当な値である.また,得られた位相速度の空間分布は,宮城県・福島県沖の領域で周りに比べて高速度を示した(石上・高木,本大会).この高速度は,S-netを用いた近地地震の地震波トモグラフィーからも推定されている.また,このトモグラフィーでは,S-netの利用により海溝に近い場所までの速度構造がよく求まることが示された(豊国・他,本大会).雑微動解析によっても,周期30秒程度の長周期まで観測点間を伝播するレイリー波およびラブ波を抽出することができた.これらも地殻構造の推定に用いることができる(高木・他,本大会).また,海域の前弧上盤の構造についてはS-net 観測点を用いたS波スプリッティング解析によって速度異方性の特徴が明らかになった.プレート境界地震を用いた解析から,速いS波の振動方向は,海溝と平行な方向を向く傾向があり,マントルウエッジの鉱物の選択配向や上盤地殻のクラックの向きを表している可能性がある(内田・他,本大会).プレート境界においては,繰り返し地震がS-net速度波形によっても抽出できることが示された.プレート境界でのスロースリップの検出やプレート境界の位置推定に役立つ可能性がある(内田・他,本大会).さらに,S-net加速度計のデータの中には,潮汐と思われる変動が観測されるものもあり,プレート境界におけるスロースリップによる傾斜変動を捉えられる可能性があるかもしれない(高木・他,本大会).以上のように,東北日本の前弧海洋底における連続観測について,そのデータの特性が明らかになるとともに,浅部から深部にわたる沈み込み帯の構造や変動についての新たな知見が得られつつある.これらの研究は技術的にも内容的にもお互いに密接に関わっており,総合的な解析の推進がさらなるデータ活用につながると考えられる. 謝辞:S-netの構築・データ蓄積および公開に携わられた皆様に感謝いたします.
1 0 0 0 小児の歯肉のメラニン色素沈着に関する研究
- 著者
- 三浦 梢 大谷 聡子 鈴木 淳司 海原 康孝 光畑 智恵子 小西 有希子 河村 誠 香西 克之
- 出版者
- 一般財団法人 日本小児歯科学会
- 雑誌
- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.11-19, 2011-03-25
- 参考文献数
- 17
近年,小児の歯肉のメラニン色素沈着は受動喫煙が関係しているとの報告が多くある。しかし受動喫煙環境下にない小児の歯肉にもメラニン色素がみられることがあり,これについて検討を行った報告はあまりない。そこで,小児の歯肉のメラニン色素沈着の要因となる可能性のある項目ついて研究した。3~11 歳の日本人小児50 名を対象に,歯肉のメラニン色素沈着を,沈着濃さと沈着範囲の2 項目で判定した。沈着濃さは「ない」「極めて薄い」「薄い」「濃い」の4 段階で,沈着範囲はHedin の分類を参考に「0」色素沈着を認めない,「1」1~2 箇所の独立した沈着を認める,「2」3 箇所以上の独立した沈着を認める,「3」色素沈着が帯状をなし左右で独立している,「4」色素沈着が帯状をなし左右で連続している,の5 段階で評価した。調査項目は口呼吸,上顎前歯部歯肉の腫脹,笑った時の上顎歯肉の露出,皮膚の色,日焼け,頭髪の色,唾液中のコチニン濃度,同居者の喫煙状況(同居者の現在および過去における喫煙,喫煙年数あるいは禁煙後の経過年数,喫煙場所,タバコの銘柄,日平均の喫煙本数,同居者以外からの受動喫煙の可能性),偏食,年齢である。これらの項目とメラニン色素沈着との関係を統計学的に分析した結果,「沈着濃さ」に対し日焼け,喫煙者との同居年数,頭髪の色,口呼吸,年齢が,「沈着範囲」に対し日焼け,喫煙者との同居年数,頭髪の色がそれぞれ正に相関した。
1 0 0 0 OA 腸管出血性大腸菌(O-157)感染による急性脳症を発症した24歳女性例
- 著者
- 鈴木 優也 福島 隆男 岩澤 貴宏 中村 元 七澤 繁樹 牧野 邦比古
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.5, pp.274-278, 2019 (Released:2019-05-28)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2
O-157による溶血性尿毒素症候群(hemolytic uremic syndrome; HUS),急性脳症は小児に好発し成人での発症は稀である.今回成人女性で急性脳症を発症し後遺症なく回復した1例を経験した.症例は24歳女性.腹痛,下痢で発症し,便からO-157と志賀毒素が検出された.第6病日にHUS,第11病日に急性脳症を発症した.一時人工呼吸管理となったが,ステロイドパルス療法,血漿交換療法(plasma exchange; PE)を行い第53病日に後遺症なく退院した.成人女性は男性よりも志賀毒素の受容体となるGb3の発現率が高く高リスクと考えられる.治療としては炎症性サイトカインを抑制するステロイドパルス療法とPEの有効性が示唆され,積極的に施行を考慮すべきと考える.
1 0 0 0 OA 血液製剤管理システムの構築と評価
- 著者
- 鈴木 正彦 荒井 千春 手塚 春樹 中澤 美科 田中 睦子 河野 健治 花輪 剛久 中島 新一郎
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.6, pp.623-629, 2002-12-10 (Released:2011-03-04)
- 参考文献数
- 7
Regarding the management of blood preparations, since September 1995 the Ministry of Heath, Labour and Welfare has had to make and/or to keep documentary records such as the product name, date of dispensing, the patient's name and lot number and so on. At Yamanashi Medical University Hospital, to cope with deleterious accidents caused by blood preparations, we developed a new system for the management of blood preparations. This system consists of a printing system for confirmation labels for blood prescriptions and a computerized management system concerning the medication. In this study, the effect of this new management system on the rational use of blood preparations was evaluated. Compared with the former system, the time required to dispense blood preparations decreased from about 500 to 170 seconds per case. Furthermore, based on a questionnaire to medical doctors and/or nurses, it appeared that this system could reduce the time required to manage blood preparations and improve the rational use of injectable drugs.
1 0 0 0 OA 医薬品市販後に追加される重大な副作用の現状
- 著者
- 小林 大介 久津間 信明 中山 惠 鵜近 篤史 鈴木 暢之 佐次田 優子 遠藤 敏成 上田 秀雄 沼尻 幸彦 駒田 富佐夫 齋藤 侑也 森本 雍憲
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.6, pp.571-575, 2002-12-10 (Released:2011-03-04)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 2 1
When a novel additional adverse effect is reported for a marketed medicine, the medical information leaflet has to be revised to inform physicians and pharmacists of this. Pharmacists are responsible for informing patients of early warning symptoms to avoid the subsequent appearance of severe adverse effects. However, at present, patients may suffer from severe adverse events because such symptoms may remain unrecognized until the medicine is on the market. As a result, investigations to predict and prevent novel additional adverse effects of medicines are required. In this study, we investigated a novel additional adverse effect classified as a pharmacological effect based on the drug safety update (DSU). As a result, skin disorders including toxic epidermal necrolysis and Stevens Johnson syndrome, and pseudomembranous colitis have become evident as additional adverse effects of antibiotics, with a high incidence. In addition, neuroleptic malignant syndrome and aplastic anemia have also been reported as adverse effects of central nervous system agents.Therefore, it is important to provide patients with information about the early warning symptoms related to such adverse effects, even though such adverse effects are not contained in the patient information leaflet.
- 著者
- 鈴木 真一
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.11, pp.674-677, 2003
- 参考文献数
- 2
和歌山県下における亜ヒ酸を用いた無差別殺人事件は多くの一般市民を巻き込む未曾有のものであった。その後,類似の異物・毒物混入事件が全国で多発し,社会不安を惹起した。この事件解決のために,ほとんどの分析化学的手法や機器が用いられ,司法側から要求されるハードルをひとつひとつ超えていき,最後にはメガサイエンスの最先端施設であるSPring-8も事件の解決に寄与した。
1 0 0 0 OA 被服による自己呈示に関する研究
- 著者
- 鈴木 理紗 神山 進
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.11, pp.652-665, 2003-11-25 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 18
本研究の目的は, 「被服によって呈示したい自己」および「自己呈示に係わる被服行動」の内容を大学生のような若者に関して明らかにすること, そして, 性別や心理的変数が「被服によって呈示したい自己」の内容, 「自己呈示に係わる被服行動」の内容に及ぼす影響を探索することであった.得られた結果は, 以下のようであった.1) 15項目の「被服によって呈示したい自己」の内容, および56項目の「自己呈示に係わる被服行動」の内容が明らかになった.2) 因子分析の結果, 「被服によって呈示したい自己」に3つの成分, 「自己呈示に係わる被服行動」には6つの成分が明らかになった.3) 性別, セルフ・モニタリング高低別, 他者意識高低別によって, これらの呈示したい自己や被服行動に相違のあることが確認できた.
1 0 0 0 ブルーチーズにおける結晶と脂肪酸の分布および差異
目的: ブルーチーズには、複屈折性を示す結晶状の構造が、タンパク質の基質および脂肪球に存在する。カビの増殖した部位と結晶の分布状態および結晶構造に脂肪酸が係わるかを確かめるために、この実験を行った。<BR>材料: ロックフォール、ブルーデコース、スティルトンおよびゴルゴンゾーラを用いた。組織化学的方法によりカビと脂肪酸を染色して、カビと脂肪酸の分布を調べた。結晶の分布を偏光装置を用いて調べた。<BR>結果: これらのブルーチーズでは、多くの脂肪は複屈折性を示す結晶性の構造物が脂肪内にあった。また、タンパク質の基質に複屈折性を示す結晶が存在した。基質に分布する複屈折性を示す小さい結晶は、スティルトンが最も多く、次にロックフォールで、ブルーデコース、ゴルゴンゾーラの順に少なかった。これらのブルーチーズには、大きな結晶の集積および不定形をした結晶の塊が、カビが増殖した部位およびその近くに分布していた。大きな結晶の塊は、ロックフォールで多く、ブルーデコースおよびゴルゴンゾーラで少なく、スティルトンでは非常に少なかった。基質に分布する結晶および脂肪の一部は、脂肪酸の染色に染まり、脂肪酸が存在した。脂肪酸は結晶を構成する一成分となっていた。染色された部位の大きさと染色の強さによる脂肪酸の分布は、スティルトンで最も多く、ロックフォール、ブルーデコース、ゴルゴンゾーラの順に少なかった。