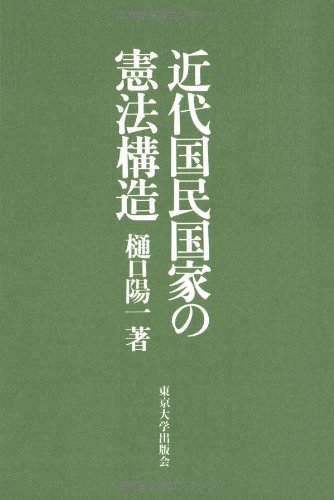1 0 0 0 OA 戦後沖縄のキビ作農業の展開
- 著者
- 有本 信昭
- 出版者
- 東北大学農学部農業経営学研究室
- 雑誌
- 農業経済研究報告 (ISSN:02886855)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.87-102, 1976-04
1 0 0 0 OA 人類發達の經路及雌雄の間に存する淘汰
- 著者
- ダーウィン チャールス 田中 茂穂
- 出版者
- The Anthropological Society of Nippon
- 雑誌
- 東京人類學會雜誌 (ISSN:18847641)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.258, pp.495-514, 1907-09-20 (Released:2010-06-28)
1 0 0 0 OA 竜巻とその親雲の流体力学
- 著者
- 新野 宏
- 出版者
- 社団法人 日本流体力学会
- 雑誌
- 日本流体力学会誌「ながれ」 (ISSN:02863154)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.105-118, 2000-04-30 (Released:2011-03-07)
- 参考文献数
- 44
1 0 0 0 OA 牡鹿半島周辺海域におけるサクラマス成魚の食性
- 著者
- 木曾 克裕
- 出版者
- Japanese Society for Aquaculture Science
- 雑誌
- 水産増殖 (ISSN:03714217)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.4, pp.521-528, 1994-12-20 (Released:2010-03-09)
- 参考文献数
- 25
1983年4月から1989年3月にかけて牡鹿半島周辺海域で漁獲されたサクラマス成魚の胃内容物を観察した。胃内容物組成を月別および尾叉長階級別に整理して個体数法, 重量法, 出現頻度法の3方法で表示し, これらの総合評価の一つの方法であるIRI (Index of Relative Importance) も併用して解析した。成魚の主な食物は大型プランクトンのニホンウミノミやツノナシオキアミ, 魚類のイカナゴ, カタクチイワシ, スケトウダラ稚魚, マイワシなどであった。重量と出現頻度では季節を問わず, 魚類が最も多く, 特にイカナゴは3~6月に卓越した。個体数では4月および5月にはニホンウミノミが多かった。大型個体と小型個体の食物を比較すると大型個体のほうが魚類への依存度が強く, 大型プランクトンへの依存の度合が低かった。サクラマス幼魚の食物と比較すると, 幼魚も成魚もイカナゴとニホンウミノミを主な食物としていたが, 成魚が摂っている動物の方が大型であった。そのほかの餌生物では, 成魚が外洋性の比較的大型の魚類とツノナシオキアミ, 幼魚が汽水性の魚類やThysanoessa longipes, カニ類幼生, ヨコエビ類などを摂っており, 両者の大きさに基づく捕食能力と微小棲息場所が異なることを示唆していた。
1 0 0 0 OA 干し椎茸の水もどし加熱加工における香気成分ならびに香気生成関連物質の変化
- 著者
- 佐々木 弘子 酒井 登美子 青柳 康夫 菅原 竜幸
- 出版者
- Japanese Society for Food Science and Technology
- 雑誌
- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.107-112, 1993-02-15 (Released:2010-01-20)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 3 3
干し椎茸の水もどしおよび加熱加工におけるγ-GT活性,香り物質であるレンチオニン量の変化について検討を加えた. (1) 干し椎茸の水もどし後のγ-GT活性の変化は,温度が高温であるほど,減少が著しく,加熱過程中においては,加熱5分後にほぼ完全に失活していた. (2) 干し椎茸のレンチオニン量は,水もどし直後では浸漬温度が高いもの程多く,低温のもの程少なかった.また10分加熱後のレンチオニンの増加の割合は水もどし温度が高いもの程小さく,低温のもの程大きかった.20分加熱時ではレンチオニンは急激に減少したが,5℃で水もどしをしたものには比較的残存していた.40分加熱時ではレンチオニンはほとんど残存していなかった.
1 0 0 0 OA サイトカインプロファイル解析─何がわかるのか?どんな時にオーダーするのか?─
- 著者
- 清水 正樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児腎臓病学会
- 雑誌
- 日本小児腎臓病学会雑誌 (ISSN:09152245)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.86-94, 2019 (Released:2019-11-22)
- 参考文献数
- 31
生体内においてサイトカインは,細胞の増殖,分化,遊走,代謝など多彩な機能的役割を有し,生体の恒常性が保たれるように炎症を制御する役割を果たしている.小児の炎症性疾患では,過剰な免疫応答によりサイトカインネットワークによる生体の恒常性維持機構が破綻し,様々な炎症性サイトカインの産生が異常に亢進することにより,重症化病態が引き起こされると考えられている.したがって複数のサイトカインを同時に測定するサイトカインプロファイル解析は,患者の免疫応答,炎症病態を反映する,様々な小児の炎症性疾患の病態理解,病勢および重症度評価,そして臨床症状の類似した疾患の鑑別に非常に有用な検査法である.今後さらに幅広く臨床へ応用されることが期待される.
1 0 0 0 OA 職種別の器械出し業務の現状と手術患者の安全のための状況判断とアセスメントの研究
看護師以外の職種が手術の器械出し業務を行っているがその職種の違いによる器械出し業務の実態は明確にされていない。本研究の目的は、職種別の器械出し業務の現状と器械出し時の状況判断とアセスメントを明らかにする。全国の器械出し業務従事者に,郵送法にて器械出し業務に関する質問紙調査を実施した。質問紙の回収は629人。235人が看護師以外の職種も器械出しをしていると回答し,医師81名,臨床工学技士81名,医療器材を取り扱う業者5名などであった。その理由は,看護師不足が最も多かった。看護師以外の職種は看護師と同じように器械出し業務を実施していることが明らかとなった。
1 0 0 0 OA 改良型キトサンナノ繊維管による胸腔内自律神経機能再生に関する実験的臨床的研究
1 0 0 0 OA P-2-01 重症心身障害児(者)看護ケアにフィジカルアセスメント研修がもたらした効果
- 著者
- 一色 努 合田 英子 造々 晶子 蜂谷 直樹 越智 るり子
- 出版者
- 日本重症心身障害学会
- 雑誌
- 日本重症心身障害学会誌 (ISSN:13431439)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.425, 2019 (Released:2021-10-30)
はじめに 重症心身障害児(者)(以下、重症児(者))は意思疎通が困難なことが多く、その時々に必要なケアを看護師の判断に委ねることが少なくない。看護師は自分の頭で考え必要な看護ケアを判断し実践する。このような中、看護師の五感を使ったフィジカルアセスメント能力の向上は重症児(者)の看護ケアに効果があると考え、Z施設ではT大学の協力を得てフィジカルアセスメント研修を年2回行い今年で3年が経過した。その取り組みについて報告する。 方法 T大学病院研修センターにおいてプログラミングシミュレーション人形を使用し、重症児(者)が起こしやすい病態を、2事例設定しシミュレーション研修を行う。 研修は2人1組で行いシミュレーション8分、ディブリーフィング10分を行い、1回の研修参加者3組6名とした。 過去3年間、この研修に参加した32名の看護師にアンケート調査を行い、研修に参加したことで自身の看護ケアにどのような影響をもたらしたか、聞き取りを行った。 結果 何が起こり何を考え何を行ったか言語化することで、看護ケアに根拠と自信が持てるようになった。他者が看護ケアの根拠を伝えてくれることで、看護ケアを多角的に考えることが出来るようになった。自分に足りないところ、気付けなかったところが気付けるようになったという効果が聞き取りできた。 考察 研修参加者は2人1組で実践を行うことで、今何が起きているのかお互いに考えを述べケアを行うことで自分の頭の中の考えだけでなく相手の考えを聞くこができた。また3組それぞれの実践を見学することで、アプローチの方法が自分と異なることもあるということを知ることができたと考える。 申告すべきCOIはない。
1 0 0 0 OA 所得税法における給与所得該当性の判断メルクマール―従属性要件と非独立性要件―
- 著者
- 酒井 克彦
- 出版者
- 中央ロー・ジャーナル編集委員会
- 雑誌
- 中央ロー・ジャーナル (ISSN:13496239)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.83-102, 2017-06-30
Much litigation has taken place on the scope of salary income. The Decisions reflect two patterns. One pattern involves consideration of labor. The other involves consideration of the employee's position. Matters of labor, by themselves, are insufficient to resolve the question. Employee status also is a crucial factor. As to that, one important factor is whether the worker is subordinate to the company or-alternatively-is not independent of the company. The former focuses on working conditions; the latter is concerned with who bears risks and expenses.
1 0 0 0 OA 日本人中高生の男女が想起する重要な自伝的記憶の特徴
- 著者
- 川﨑 采香 上原 泉
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 認知心理学研究 (ISSN:13487264)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.25-40, 2020-08-31 (Released:2020-09-24)
- 参考文献数
- 45
自伝的記憶とは自分史の一部をなすような,過去の個人的な出来事の記憶であり,そのあり方や語られ方に文化差や性差,発達差がみられる可能性が指摘されているが,日本人の思春期を対象とした研究はほぼ行われておらず,その自伝的記憶の内容や発達的特徴は不明である.本研究では,日本人中高生に重要な自伝的な出来事を想起するようにもとめ,その内容と経験時の年齢,伴う感情などを調べた.まず,中高生男女が想起した内容をカテゴリーに分類した結果,カテゴリーは概ね共通し,学校に関する出来事(入学,卒業,部活動など)が多く含まれた.一部の出来事カテゴリーにおいて,中高差や男女差がみられた.また,中学生は12歳,高校生は15歳に経験した出来事をほかの年齢よりも多く想起することが示された.感情別に見ると,これらの時期に想起量の山がみられたのはポジティブ感情もしくは両方(ポジティブとネガティブが混ざっている)感情を伴う出来事のみであった.日本の中高生の自伝的記憶の特徴について,発達差や性差も含めて考察した.
- 著者
- 石井 正樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.6, pp.270-271, 2012-06-20 (Released:2017-06-30)
- 被引用文献数
- 1
夏の暑い環境をより快適に過ごすために,冷涼感性や,皮膚からの汗をすばやく吸って,そして急速に乾燥させる吸汗速乾性を有する衣料は,近年夏物衣料としては必須アイテムになりつつある。本稿では人体から発生する水蒸気や汗の移動により,人体をより快適な状態に保つことを目的とした衣服における繊維素材の実例を紹介する。
- 著者
- 臺 美佐子 峰松 健夫 小川 佳宏 高西 裕子 須釜 淳子 真田 弘美
- 出版者
- Japanese Society of Wound, Ostomy and Continense Management
- 雑誌
- 日本創傷・オストミー・失禁管理学会誌 (ISSN:1884233X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.10-17, 2021 (Released:2021-03-31)
- 参考文献数
- 15
目的:弾性ストッキングは主要なリンパ浮腫管理方法である。しかし、高温多湿な夏季には、装着継続のモチベーション維持に困難感を生じさせる。そこでわれわれは、この問題を解決すべくキシリトール加工したキュプラ繊維を用いた接触冷感弾性ストッキングを開発した。本研究の目的は、プロトタイプによる下肢リンパ浮腫患者への接触温冷感の効果および安全性を検証することである。 方法:本研究は前後比較試験で、下肢リンパ浮腫患者をリクルートし、対象者は介入前(従来型)と介入後(接触冷感弾性ストッキング)を各1日自宅で装着して過ごした。アウトカムは、主観的な接触温冷感としてASHAREスコアである7 点法スケール質問紙に、装着直後と脱着時に回答した。その後、電話にて皮膚トラブルと浮腫状態についてインタビューし回答を得た。 結果:分析対象となった者は下肢リンパ浮腫患者の女性13 名で、接触冷感弾性ストッキングによる有害事象が発生した者はいなかった。接触温冷感の評価では、11 名が装着直後では介入前より介入後のほうが冷たいと感じ、中央値+1(やや温かい)から-1(やや冷たい)へ有意に減少した(P=0.002)。一方、脱着時には両グループに前後で有意な差は見られなかった(P=0.133)。また、皮膚トラブルや浮腫増悪の生じた者はいなかった。 結論:キシリトール加工したキュプラ繊維を用いた接触冷感弾性ストッキングは、下肢リンパ浮腫患者に対して皮膚トラブルや浮腫悪化なく接触冷感を感じさせる可能性があると示唆された。
- 著者
- Masamichi ENDO Shunya HANAKITA Soichi OYA
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- NMC Case Report Journal (ISSN:21884226)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.73-76, 2022-12-31 (Released:2022-04-21)
- 参考文献数
- 8
There are various causes of ventriculoperitoneal shunt (VPS) failures. Patients who receive shunt placement during childhood need follow-up for decades as they grow, especially in the early periods of life. Herein, we report a rare case of mechanical shunt obstruction in a pediatric patient in whom a cramped burr hole and skull growth compressed the tube and obstructed cerebrospinal fluid flow. A 6-year-old girl presented to our hospital with nausea and headache. She was born preterm and developed intraventricular hemorrhage followed by VPS placement for hydrocephalus; thereafter, she had no need for shunt revision until this admission. After careful evaluation of the patency of the shunt system, the presence of tube stenosis was suspected at the site of the shunt tube penetrating the burr hole of the skull. During the operation to revise the shunt tube, a compressed tube was observed at the exit from the skull. After enlarging the narrowed burr hole and reconstructing the proximal catheter, her symptoms immediately improved. Previously, only one case of shunt malfunction due to tube compression from bone growth has been reported in a pediatric patient with osteopetrosis. To the best of our knowledge, such a condition has never been described in pediatric patients with no metabolic bone disease. Although it is rare, obstruction at the exit from the skull due to bone growth should be included in differential diagnoses for young patients during a long follow-up after VPS.
- 著者
- Hiroyasu INOUE Masahiro OOMURA Yusuke NISHIKAWA Mitsuhito MASE Noriyuki MATSUKAWA
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- NMC Case Report Journal (ISSN:21884226)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.49-53, 2022-12-31 (Released:2022-04-01)
- 参考文献数
- 11
Internal carotid artery occlusion rarely recanalizes spontaneously. Awareness of signs of recanalization is important, as it may necessitate changing the treatment strategy. We report a case of new cortical infarction outside the border zone, which led to the realization of internal carotid artery recanalization and revascularization.A 76-year-old woman presented with mild dysarthria. Magnetic resonance imaging showed cerebral infarction in the left-hemispheric border zone and occlusion of the internal carotid artery origin. Cerebral angiography performed showed complete occlusion of the internal carotid artery origin and intracranial collateral blood flow from the external carotid artery through the ophthalmic artery. She was diagnosed with infarction due to a hemodynamic mechanism caused by internal carotid artery occlusion and was treated with supplemental fluids and antithrombotic drugs. Four days after hospitalization, the right paralysis worsened and a new cerebral infarction was observed in the cortex, outside the border zone. This infarction appeared to be embolic rather than hemodynamic; thus, we suspected recanalization of the internal carotid artery. The patient underwent emergency cerebral angiography again, which revealed slight recanalization. Thus, emergency revascularization and carotid artery stenting were performed. New cortical infarcts outside the border zone in patients with complete internal carotid artery occlusion is an important finding, suggesting spontaneous recanalization of the occluded internal carotid artery.
1 0 0 0 近代国民国家の憲法構造
1 0 0 0 OA Frontal Horn Cystsの1例
- 著者
- 三宅 進 宮村 能子
- 出版者
- 岡山医学会
- 雑誌
- 岡山医学会雑誌 (ISSN:00301558)
- 巻号頁・発行日
- vol.124, no.3, pp.239-241, 2012-12-03 (Released:2013-01-04)
- 参考文献数
- 5
We herein report a case of bilateral frontal horn cysts. The infant was delivered with a low birth weight (1,710g) at 31 weeks, 0 days by emergency Cesarean section. She was severely asphyxiated and exhibited respiratory distress syndrome. Surfactant was administered, and mechanical ventilation was required until 21 days of age. Brain computed tomography (CT) at 45 days of age revealed bilateral cysts adjacent to the frontal horns of the lateral ventricles. Her growth and development were normal. At 1 and a half- years of age, she underwent brain CT again and the above-mentioned cystic abnormality had disappeared. No dilatation or irregularity of the lateral ventricles was found. Normal development and transient abnormal cystic findings in brain CT suggested a diagnosis of frontal horn cysts. Frontal horn cysts should be considered as the causes of cystic lesions of the brain.
1 0 0 0 OA 心的トラウマと精神医学
- 著者
- 金 吉晴
- 出版者
- 一般社団法人 国立医療学会
- 雑誌
- 医療 (ISSN:00211699)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.231-236, 2003-04-20 (Released:2011-10-07)
- 参考文献数
- 12
PTSDをはじめとする心的外傷関連障害が, 広範な社会的な関心の対象となっている. ペルー人質事件以後, 国立精神・神経センターでの委託費研究班が発足し, 平成13年には, 研究班としての対応マニュアルを発行した. PTSDで扱われているトラウマとは, 戦争に匹敵するような体験であり, 生理学的な側面と体験の認知ならびに意味付け的な混乱の両側面がある. 診断に際しては, 出来事の定義, 症状の記述とも, DSM-IVのような基準を参照すべきであり, とくに精神鑑定ではそれが重要である. トラウマからの一般的な回復過程を理解することは重要であり, 直後には一過性の比較的軽度の心身の変調が生じ, 一部がASDとなり, さらに一部がPTSDとなる. 遷延化する例はさらに少ない. 長期的にはアルコール・薬物依存, 自殺をはじめとする社会的な不適応が問題となる. 被害者が有責者であるかのようなスティグマは社会適応を阻害する.