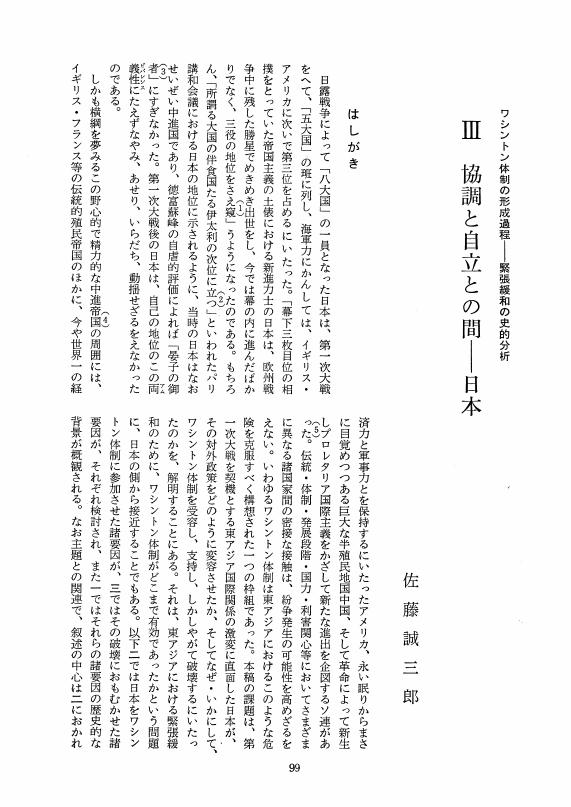- 著者
- 横田 俊平 黒岩 義之
- 出版者
- 一般社団法人 室内環境学会
- 雑誌
- 室内環境 (ISSN:18820395)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.63-73, 2022 (Released:2022-04-01)
- 参考文献数
- 48
全身的な身体症状と登校障害を主訴に受診した学童・生徒28名の臨床症状の特徴を調査した。全身の持続的な骨格筋痛, 関節痛, 種々の頭痛が全例に認められた。睡眠障害と朝の起床困難, 倦怠感・少しの動作で感じる疲労感, 食後の胃部痛・胃もたれ, 反復性の下痢と便秘, 通常の室内環境レベルでの光・音・匂いに対する感覚過敏とそれに伴う嘔気・頭痛を認めた。登校時に体調が悪化する例では眩暈, 動悸・息苦しさ, 頭痛, 腹痛等の訴えが多かった。理学的診察では全例に身体諸筋のこわばりと圧痛を認め, 線維筋痛症18圧痛点が陽性であった。血液検査では病巣を特定できる異常所見は得られなかった。これらの所見は若年性線維筋痛症に類似し, 登校障害児には若年性線維筋痛症の未診断例が含まれる可能性がある。自律神経症状, 疼痛・感覚過敏症状, 情動症状をコアとする視床下部性ストレス不耐・疲労症候群の病像が浮き彫りになり, 概日リズムの制御破綻, エネルギー代謝系の機能不全, 内的・外的環境ストレスに対する環境過敏とストレス不耐がある。線維筋痛症成人例でPositron-Emission Tomography(PET)で, 視床とその周囲にミクログリア由来の炎症が確認されており, 登校障害児においても視床-視床下部-辺縁系に病的プロセスが推察された。健常児では全く問題とならないレベルの室内環境等の身体的ストレスや心理的ストレスが登校障害児では顕著な環境過敏・ストレス不耐と易疲労性を起こし, 不登校の原因と推察された。
1 0 0 0 遺伝子導入によるヒトおよびサルの細胞におけるアスコルビン酸の合成
- 著者
- 錦見 盛光 河合 敏秀
- 出版者
- (財)応用生化学研究所
- 雑誌
- 一般研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 1990
ヒトやサルはビタミンCを生合成することができないため、このビタミンを食物より摂取せねばならない。その原因がビタミンC合成経路で働くグロノラクトン酸化酵素(GLO)の欠損にあることが分っているので、これらの動物の細胞へGLOのミニ遺伝子を導入しGLOの発現を試みた。ラット肝臓GLOのcDNAを発現ベクタ-pSVLの後期プロモ-タ-と後期ポリA付加部位の間へ挿入した構築体を作製した。これをアフリカミドリザルの腎臓由来のCOSー1細胞へリン酸カルシウム共沈殿法で導入し、抗ラットGLOウサギ抗血清を用い免疫組織化学的方法で細胞を染色したところ、5ー10%の細胞でGLOタンパク質が発現されていることが分った。発現されたGLOタンパク質が酵素活性を持つことを高速液体クロマトグラフィ-用いるGLO活性測定法により確認した。さらに、COSー1細胞で発現されたGLOがラット肝臓のGLOと同じ分子量を有することをウエスタンブロット法で明らかにするとともに、ミクロソ-ム画分に局在することを細胞分画法で調べた。また、恒常的にラットGLOをヒト由来のHeLa細胞で発現させるため、マウスMoloney白血病ウイルスのLTRとバクテリアのネオマイシン耐性遺伝子をpBR322へ組み込んだベクタ-(N2)のXhoIサイトへ、SV40の前期プロ-モ-タ-の下流へラットGLOのcDNAをつないで連結した。得られた構築体をHeLa細胞にリン酸カルシウム共沈殿法によりトランスフェクトしG418に耐性を示す細胞を得た。その細胞がGLOを発現することを免疫組織学化的に染色して確認した。現在、GLO活性を発現するようなクロ-ンを得る試みを行っている。
1 0 0 0 OA テクノロジーの進歩と社会的分断の時代におけるデモクラシーと教育 -米国の経験とこれから-
- 著者
- 古田 雄一 間篠 剛留 石嶺 ちづる 岸本 智典 福野 裕美 原田 早春
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項 (ISSN:2433071X)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, pp.87-88, 2021-08-16 (Released:2021-10-22)
- 著者
- 三杉 圭子 Keiko MISUGI
- 出版者
- 神戸女学院大学研究所
- 雑誌
- 神戸女学院大学論集 (ISSN:03891658)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.137-152, 2015-12
第一次世界大戦は近代的兵器を導入した列強国による史上初の総力戦であった。ジョン・ドス・パソス(John Dos Passos 1896-1970)はこの大戦下に成人したいわゆる「失われた世代」の一員である。ひとつ前の世代が戦争に名誉や男らしさの具現を見出したのとは対照的に、彼らはこの不毛な大量殺戮の前に、いかなる幻想を抱くこともできなかった。ドス・パソスは『U.S.A.』三部作の第二部『1919』(1932)において、自らの世代にとっての戦争の再定義を行っている。ドス・パソスは『1919』において、第26代大統領セオドア・ローズヴェルト(Theodore Roosevelt 1858-1919)の伝記的スケッチを「幸せな戦士」("The Happy Warrior")と銘打ち、その戦争観を鋭く風刺している。彼はまず、戦争をめぐるローズヴェルトのロマンティシズムを誇張することでその独善性を揶揄する。そして、米西戦争における好戦的愛国主義者ローズヴェルトと、第一次世界大戦における語り手の体験を並置することで、ローズヴェルトの戦争観が近代戦争においていかに無効であるかを強調している。さらに彼は、ローズヴェルトとの対比において、無名戦士の伝記を「アメリカ人の遺体」と題し、20世紀の戦争の本質を描いている。つまり、モダニティの負の先鋒としての戦争は、個人の固有性を無化し、人間の生を否定するものに他ならない。ドス・パソスは『1919』においてローズヴェルトの戦争観を厳しく批判することで、戦争をめぐるロマンティズムを徹底的に糾弾し、「幸せなアマチュア戦士」の時代は終わり、誰もが「無名の戦士」とならざるを得ない新しい時代の戦争観を提示したのである。World War Ⅰwas the first modern war of advanced technology fought among the world powers. John Dos Passos (1896-1970) is one of the Lost Generation writers who is defined by coming of age during WWI. His experiences of the war allowed for no illusion about warfare being an arena for valor, glory, and manly achievement, as the previous generation conceived. Dos Passos in 1919(1932) reconfigures the meaning of war for his generation. Dos Passos's sarcastic representation of Theodore Roosevelt(1858-1919) in "The Happy Warrior" section of 1919 serves as the focus of this paper and illustrates how Dos Passos reassesses his conceptualization of war. "The Happy Warrior" is a strong statement against America's older generation who could afford to romanticize war and make their entire life a battlefield to prove their honor and manliness. Furthermore, Dos Passos's contrast between the jingoistic Rough Rider and the "gentlemen volunteers" of the ambulance corps in WWI represented in The Camera Eye (32) discloses the failure of the morale of the ex-volunteer cavalry leader in the modern world. The greatest irony is revealed in the author's contrast between the happy amateur warrior and the unknown soldier in "The Body of an American," as the nameless Everyman illustrates deprivation of individuality in the name of war. By investigating how Dos Passos deromanticizes war through his critique of Theodore Roosevelt in the context of WWI, we are able to clarify the nature of modern war as the writer saw it-that Roosevelt, the faded war hero, failed to discern.
1 0 0 0 OA 張城尚歯会
- 著者
- 内藤, 東甫
- 出版者
- 加藤茂助[ほか1名]
1 0 0 0 OA 性同一性障害当事者が抱える困難と困難を乗り越える要因
- 著者
- 福本 美樹
- 出版者
- 日本学校メンタルヘルス学会
- 雑誌
- 学校メンタルヘルス (ISSN:13445944)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.164-172, 2016 (Released:2021-04-08)
- 参考文献数
- 20
【問題と目的】1990年代後半より,性同一性障害に対する社会的な受容が高まってきているように見える。しかし,性同一性障害当事者が社会的・心理的に様々な困難を抱えているという報告もあり,性同一性障害当事者がいまだ大きな心理的ストレスを抱えている現状が推測される。そこで本研究では,性同一性障害当事者への支援方法を考察するために,性同一性障害当事者が抱える困難と困難を乗り越える要因を明らかにすることを目的とした。【方法】性同一性障害当事者3名に対し,半構造化面接で,これまで経験してきた心理社会的困難と,そうした困難への対応状況あるいは方法を聞き取った。面接で得たデータをもとに,複線径路・等至性モデル(TEM)により分析した。【結果】困難として,自分の望む服装や持ち物を志向しても周囲に受け入れてもらえなかったこと,性に対する違和感を周囲に言えないこと,第二次性徴,学校や職場の制服や性役割の強要,就労できないことなどがあった。困難への対応状況あるいは方法としては,自分の性に対する違和感を言わないことにより周囲の批判を避けること,体の変化や制服の着用・外部からの性役割の強要を受け入れること,性同一性障害当事者の仲間を得ること,性に対する知識を得ること,家族や友人からの受容などがあった。【考察】性同一性障害当事者が困難を乗り越える際に必要である要因として,①性の多様性に関しての知識理解②性に違和感をもつ仲間たちとのつながり③家族や親しい友人からの受容④学校の受け入れ態勢の整備⑤職場の理解,が明確になった。特に④と⑤については,学校や職場での性別二元論に基づく男女別の振り分けに苦しむ当事者の状況が明らかになった。今後は,学校や職場における性の多様性についての理解と意識改革が必要であるとともに,なぜ学校や社会が性に違和感をもつ人たちを受け入れることができないのかという,性同一性障害当事者を取り巻く環境側の要因を研究していくことが必要と考えられる。
1 0 0 0 OA Concept Study of HTV-R (HTV-Return)
- 著者
- Yusuke SUZUKI Takane IMADA
- 出版者
- THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES
- 雑誌
- TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, AEROSPACE TECHNOLOGY JAPAN (ISSN:18840485)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.ists29, pp.Tg_11-Tg_19, 2014 (Released:2014-12-26)
Japan contributes essential services to space experiments and enables human activities included as part of the international partnership of the ISS program by utilizing the HTVs (Kounotori). As the next step toword on-orbit service, JAXA has commenced technical research into cargo return from orbit. The HTV was used in research as the base design and a return vehicle was added to enhance performance. The combined vehicle is called the "HTV-R". HTV-R enables JAXA to recover various samples of experiments conducted on the ISS and equips a new return vehicle called as "HRV (HTV Return Vehicle)" for the enhanced function. The HRV will fly autonomously and conduct lifting re-entry into the atmosphere by controlling the attitude and trajectory to a predefined splashdown point. Now two types of vehicle concepts are being investigated. One uses an HTV as the base system for orbital flight and minimizes the initial cost of HTV-R program, and the other integrates the HTV components into a new vehicle, optimizing the on-orbit functions to minimize the recurring cost.
1 0 0 0 OA 50c/s単相交流による鉄道電化
- 著者
- 矢山 康夫
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.795, pp.1514-1517, 1954-12-01 (Released:2008-11-20)
1 0 0 0 OA 協調と自立との間-日本
- 著者
- 佐藤 誠三郎
- 出版者
- JAPANESE POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.99-144, 1970-05-30 (Released:2009-12-21)
1 0 0 0 OA 自傷行為による舌潰瘍形成を認めた2例
- 著者
- 今村 知代
- 出版者
- Japanese Society of Psychosomatic Dentistry
- 雑誌
- 日本歯科心身医学会雑誌 (ISSN:09136681)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.89-95, 2002-12-25 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 22
We recently treated two patients with tongue laceration and tongue ulcers due to automutilation.Case 1: A 7-year-old male visited us with the chief complaint of ulceration of the tongue. He had experienced repeated episodes of tongue ulceration since the age of about five. We applied a mandibular splint and advised the family to modify the family environment. Automutilation of the tongue decreased 4 months after the beginning of the intervention, and the lesion became treatable.Case 2: A 21-year-old male with tongue ulceration visited us with the chief complaint of acute weight loss associated with food intake disorder. His past history included autism and mental retardation. We explained the relationship between the habit of automutilation and psychogenic factors to the family and obtained their understanding and cooperation in treating the disease. The ulcers healed on day 14, and food intake disorder disappeared with the recovery of body weight.
1 0 0 0 OA 金属に彩りを添える伝統工芸着色法
- 著者
- 北田 正弘 桐野 文良
- 出版者
- 公益社団法人 日本表面科学会
- 雑誌
- 表面科学 (ISSN:03885321)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.4, pp.226-230, 2005-04-10 (Released:2007-12-21)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
Traditional coloring techniques used in Japanese metal crafts, such as niiro and iroage, are explained. In niiro for copper-gold alloys, a Cu2O layer in which gold particles are dispersed is formed on the alloy surface. This gold alloy is colored through absorption and reflection of light by gold particles in the layer. Besides coloring, this layer functions to prevent corrosion. In iroage for gold-silver alloys, silver dissolves selectively by heating after a chemical is applied on the metal surface. As a gold-rich layer is formed on the gold-silver alloy surface, the gold color is produced.
1 0 0 0 OA 巨大なタンパク質やバイオナノ粒子の拡散係数の測定方法
- 著者
- 濱地 正嵩 吉本 則子 山本 修一
- 出版者
- 一般社団法人 日本食品工学会
- 雑誌
- 日本食品工学会誌 (ISSN:13457942)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.4, pp.187-191, 2017-12-15 (Released:2017-12-29)
- 参考文献数
- 17
拡散係数(分子拡散係数あるいは相互拡散係数)Dmは,クロマトグラフィーや乾燥などさまざまな分離操作・装置の設計に必要な重要な物性値である.また,物質の大きさを知るための重要な情報でもある.拡散係数の測定のために,さまざまな方法が開発され使用されているが,とくに分子量の大きいタンパク質やDNA,さらにはバイオナノ粒子のDmは,ほとんど報告されていない.本研究では,タンパク質および修飾タンパク質(PEG化タンパク質)のDmを比較的簡単な測定操作と装置が簡便である細管内層流速度分布を利用したTaylor法と動的光散乱法で測定した.どちらの方法でもほぼ同じDm値を得ることができた.ただし,それぞれの方法には特徴と問題点があるので,よく理解して相補的な方法として使用することが望ましい.
1 0 0 0 OA モーリス・ドッブ ──欧米マルクス派の政治経済学──
- 著者
- 塚本 恭章
- 出版者
- 愛知大学経済学会
- 雑誌
- 愛知大学経済論集 (ISSN:09165681)
- 巻号頁・発行日
- no.206, pp.1-34, 2018-03-15
1 0 0 0 OA 障がいのある留学生のためのサポートシステム構築を目指して
- 著者
- 木谷 真紀子
- 出版者
- 同志社大学学習支援・教育開発センター
- 雑誌
- 同志社大学学習支援・教育開発センター年報 = Doshisha University annual report of Center for Learning Support and Faculty Development
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.20-32, 2017-06-30
2016年度春学期、本学日本語・日本文化教育センターに車椅子を使用する学生が在籍していた。日本語を理解せず、生活や学習環境にも慣れていない留学生が、日本語を母語とする学生とは異なる支援を必要としていることは想像に難くない。短い留学生活の中で、学習成果を感じられる環境を調えるためにはどのようなサポートをすべきなのだろうか。今後、障がいのある留学生を受け入れるためのシステムの構築について提案したい。
1 0 0 0 OA 不等式の図形的証明 初等幾何を中心にして
- 著者
- 仁平 政一
- 出版者
- 公益社団法人 日本数学教育学会
- 雑誌
- 日本数学教育学会誌 (ISSN:0021471X)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.7, pp.45, 1991 (Released:2021-04-01)
1 0 0 0 OA 加工タピオカ澱粉の種類がわらび餅の物性および官能評価に及ぼす影響
- 著者
- 古谷 彰子 大西 峰子 三星 沙織 米山 陽子 平尾 和子
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成29年度大会(一社)日本調理科学会
- 巻号頁・発行日
- pp.31, 2017 (Released:2017-08-31)
【目的】ワラビの根から抽出されるワラビ澱粉は、高価で保存性も悪い。わらび餅の調製に用いるわらび粉の市販品には安価な甘藷澱粉やクズ澱粉が混合されているもタピオカ澱粉を利用したものが多い。しかし、これらの澱粉は安価であるという利点はあるものの、ワラビ澱粉で調製した本わらび餅とは食味・食感がかなり異なっていた。本報告では、加工タピオカ澱粉を用いて、本わらび餅に近い食感のわらび餅の調製法を検討した。【方法】澱粉は、未加工タピオカ澱粉(NT)、リン酸架橋タピオカ澱粉(P)、Pの酵素処理澱粉(PE)、アセチルリン酸タピオカ澱粉(AP)、APの酵素処理澱粉(APE)の5種(グリコ栄養食品(株))とし、上白糖(三井製糖)と蒸留水を用いてわらび餅を調製した。加水量は各澱粉の水分量を求めて調整した。またシェッフェの単純格子計画法を用い、NTと2種の加工タピオカ澱粉(PE、APE)を3成分として配合割合の異なる9つの格子点を設定した。物性測定はクリープメータ((株)山電)、官能評価は本わらび餅を対照として、つり合い不完備型ブロック計画法を用いて行った。【結果】官能評価の嗜好では、PEとAPEを用いたものが総合評価の項目で有意に好まれたが、どちらも本わらび餅の食感とは異なっていた。そこで、シェッフェの単純格子計画法を用いて3種澱粉(NT、PEおよびAPE)の配合割合の影響を検討したところ、格子点⑦のNT:PE:APE=1:1:1の配合割合のわらび餅が本わらび餅に最も近い物性値を示した。官能評価の特性評価においても、弾力と口どけの項目で有意にあると評価された。嗜好においても、本わらび餅と同様に「好き」「非常に好き」と評価され、有意に好まれた。
1 0 0 0 OA 〈論文〉GIS による札幌市におけるコンビニエンスストアの空間的自己相関分析
- 著者
- 角野 浩
- 出版者
- 近畿大学経済学会
- 雑誌
- 生駒経済論叢 = Ikoma Journal of Economics (ISSN:24333085)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.37-62, 2019-11-30
[要旨]本研究では,札幌市におけるコンビニエンスストアの立地条件について,GIS を用いて空間的自己相関分析を行う。Global Moran’s I は,地域内のコンビニ店舗数と人口との空間的自己相関の有無を示すことができ,そして Getis-Ord Gi*は,ホットスポットあるいはコールドスポットを特定することができる。したがって,これらの相関関係からコンビニ各社の出店立地の特徴を明らかにする。[Abstract] In this research, Spatial Autocorrelation analysis is performed using GIS for the location of convenience stores in Sapporo. GIS enables the presence or absence of spatial autocorrelation between the number of convenience stores in an area and the population, and identifies Hot Spots or Cold Spots, employing both Spatial Autocorrelation(Global Moran’s I)and Hot Spot Analysis(Getis-Ord Gi*). Therefore, the characteristics of the opening locations of convenience stores are clarified from these correlations.
1 0 0 0 OA 「遠野の曲り家」の絵について
- 著者
- 樋口 敬二
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.55, 1998-01-01 (Released:2009-12-21)