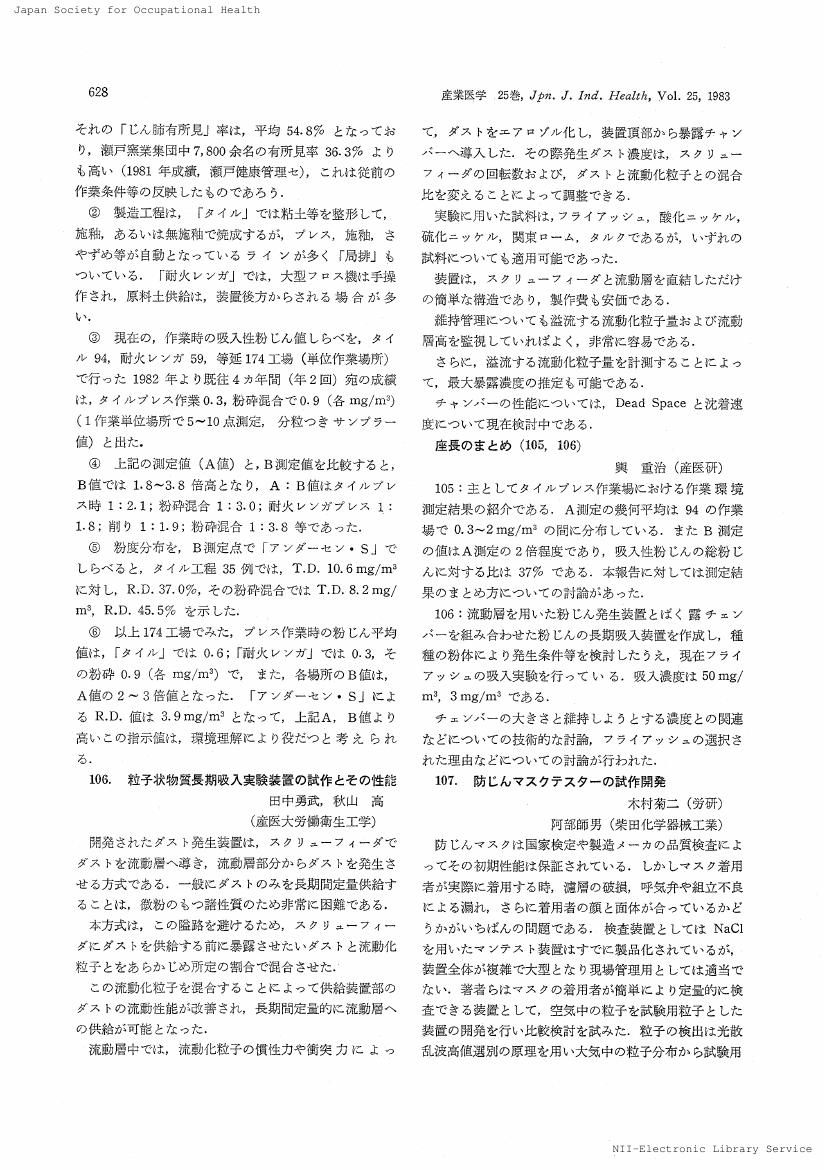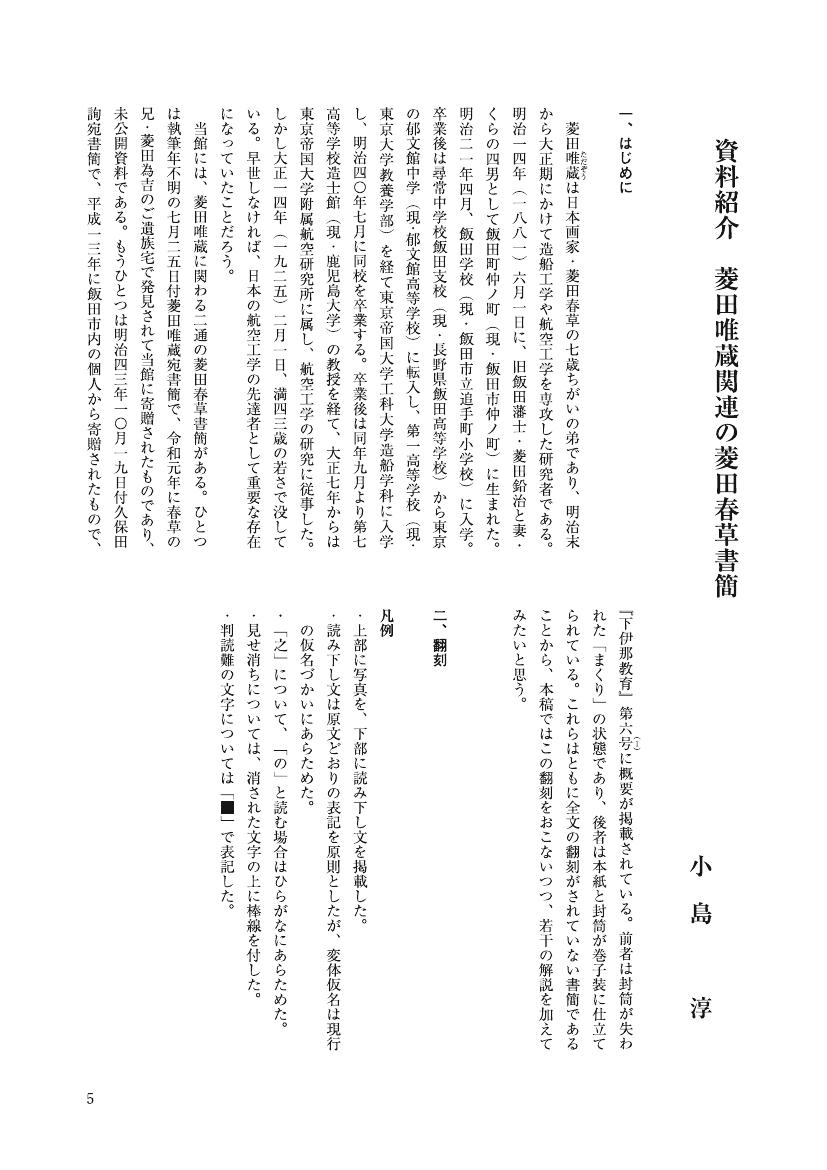1 0 0 0 OA 不良緒の探索理論
- 著者
- 嶋崎 昭典 川久保 八郎 高橋 修
- 出版者
- The Japanese Society of Sericultural Science
- 雑誌
- 日本蚕糸学雑誌 (ISSN:00372455)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.83-87, 1975-04-28 (Released:2010-07-01)
- 参考文献数
- 3
接緒回数の分布について, 以下に示すような, いくつかの結果がえられた。注目した緒内で空接緒を含む接緒回数の変化を示す確率をP(Z=k) とおくと, これは一般にP(Z=k)=a1p(a0+a1q)kで示される。ここにpは有効接緒効率 (比率) でqは1-pである。a1は取り出し効率 (比率) でa0は1-a1である。またkは有効接緒が生じるまで繰かえされる接緒数である。さらに, 接緒効率(1-λ), λ=a1pの分布f(λ) は,f(λ)=(α+β+1)!λα(1-λ)β/α!β!で与えられる。ここにαとβは分布のパラメータであり, λの平均値は (α+1)/(α+β+2) で, 分散は (α+1)(β+1)/(α+β+2)2(α+β+3) である。これらのことから, 工場におけるすべての接緒現象の分布P(U=k) は,P(U=k)=(α+β+1)!(α+k)!(β+1)/α!(α+β+k+2)!で与えられた。ここにα, βとkはf(λ)での定義と同じであり, Uは接緒回数を示す確率分布である。ゆえにUの平均値は (α+1)/β, 分散は (α+1)(β+1)(α+β+1)/β2(β-1) となる。
1 0 0 0 OA 東京都心及びその周辺における事務所立地の動向に関する実証的研究
- 著者
- 渡辺 康 小川 剛志 石川 允
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.517-522, 1994-10-25 (Released:2019-02-01)
- 参考文献数
- 3
THIS STUDY INVESTIGATES THE CAUSES OF BUSINESS AND COMMERCIAL AGGLOMERATION IN THE CENTRAL AREA OF TOKYO, ANALYZING THE DENSITY OF THE EMPLOYEES BY CHOMOKU FROM 1978 TO 1991. THE EXPANSIONS OF THE AGGLOMERATION TOOK PLACE IN THE CENTRAL AREA OF TOKYO AND ITS ADJUSTABLE AREA, THE ADJUSTABLE AREA OF THE SUBCENTERS, THE SUBCENTERS. TAKADANOBABA AREA MARUNOUTI AREA, ARONG ARTERY ROADS FROM THE CENTER TO THE SUBCENTERS. SHIBA. SHIBAURA, 00SAKI. GOTANDA.
1 0 0 0 OA コーヒーブレーク
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.4, pp.270-271, 2021-04-01 (Released:2021-05-01)
1 0 0 0 OA Association between the five-factor model of personality and work engagement: a meta-analysis
- 著者
- Toshiki FUKUZAKI Noboru IWATA
- 出版者
- National Institute of Occupational Safety and Health
- 雑誌
- Industrial Health (ISSN:00198366)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.154-163, 2021-10-15 (Released:2022-04-01)
- 被引用文献数
- 8
The purposes of this meta-analysis were (1) to examine the associations between work engagement (WE) and the personality dimensions of five-factor model and (2) to determine how much variance in WE is explained by these five factors. We performed a database search for studies related to personality traits and WE, and 36 papers that reported correlation coefficients were selected for the meta-analysis. After correcting for publication bias using the trim-and-fill method, conscientiousness had the strongest association with WE (ρ=0.41), followed by extraversion and openness to experience (0.38), neuroticism (−0.36), and agreeableness (0.27). Moreover, 30% of the WE variance could be explained by the five-factor model (R2=0.33, 95%CI=0.26–0.49) according to a path analysis using the weighted average correlation for unreliability. This proportion was higher than that from a previous meta-analysis of job satisfaction and job performance and was lower than that of personality and WE. Thus, to enhance WE, it is necessary to evaluate both the personality and the psychosocial work environment in detail.
1 0 0 0 梅雨前線帯の南下に伴って対馬海峡で発生した気象津波に関する解析
- 著者
- 田中 健路
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集B2(海岸工学) (ISSN:18842399)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.I_386-I_390, 2011
On 15 July 2009, a meteotsunami occurred at Tsushima Strait and with the flood damage at Sasuna community area in the west of Tsushima Island. This study analyzed the meteorological conditions in relation to the meteotsunami event. The baiu front system moved south from Korean Peninsula to the north Kyushu and San-in area in the morning of 15 July, accompanied with the strong cold downdraft. The pressure disturbance occurred by the acoustic gravity mode 100-120 km west from Tsushima Island in the middle of the strait, where the surface moist air from the southwest was lifted by cold downdraft. The cycle of the pressure disturbances were around 10 minutes, which is nearly same as the eigenoscillation of the small bays of the Tsushima.
- 著者
- 山下 裕作
- 出版者
- 地域農林経済学会
- 雑誌
- 農林業問題研究 (ISSN:03888525)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.18-26, 2022-03-25 (Released:2022-03-31)
- 参考文献数
- 1
Japanese folklore is said to be a young discipline constructed by agricultural politician Kunio Yanagita. However, its content is a new national studies (新国学), a history of the common people, and an agricultural policy for the well-being of people. Each has a variety of origins. The research methodology of Japanese folklore is really simple, as it is expressed as “walking, seeing, listening”, but it is the accumulation of the experience of folklore scholars so far. It is very useful in discovering the hidden value of rural areas. In this report, we discuss the usefulness of folk research based on the case of regional resource survey in rural Indonesia.
1 0 0 0 OA 精神科病棟入院患者の現状と理学療法の効果
- 著者
- 石橋 雄介 西田 宗幹 山田 和政
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.4, pp.509-513, 2017 (Released:2017-08-20)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
〔目的〕身体合併症を呈した精神科病棟入院患者を対象に,生活機能と精神機能に対する理学療法(PT)の有効性を検証した.〔対象と方法〕身体合併症に対してPTを実施した精神科病棟入院患者を対象に,理学療法開始時と終了時のBarthel IndexスコアおよびGlobal Assessment of Functioningスコアをカルテより収集した.〔結果〕両スコアともPT終了時で有意に高得点であった.〔結語〕身体合併症を呈した精神科入院患者に対するPTは,生活機能のみならず精神機能の改善も期待できることが示唆された.
1 0 0 0 OA ブレイクスルーを生み出す次世代アクチュエータ研究
- 著者
- 樋口 俊郎 鈴森 康一 横田 眞一 黒澤 実 服部 正 則次 俊郎 黒澤 実 服部 正 則次 俊郎 横田 眞一 吉田 和弘 山本 晃生 神田 岳文
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 特定領域研究
- 巻号頁・発行日
- 2004
本研究課題は,特定領域「ブレイクスルーを生み出す次世代アクチュエータ研究」の総括班としての活動に関するものである.この特定領域は,新しい高性能アクチュエータの実現が,社会の様々な局面において今後ますます重要となることを鑑みて活動を開始したものであり,これまで異なる分野で個別に研究されてきたアクチュエータ研究者に共通の活動の場を与えることなどをめざし,平成16年度より平成20年度まで5年間にわたり研究活動を実施してきた.特定領域しての主な研究活動は平成20年度をもって終了しているが,本年度は,これまでの5年間にわたる研究成果をとりまとめ広く公表することを目的として総括班活動を実施した.本年度の中心となった活動は,一連の成果を英文の書籍として出版することであった,特定領域で活動した研究者らにより執筆された原稿をとりまとめ,世界的に著名な出版社であるSpringer社より,Next-generation actuators leading breakthroughsと題する総ページ数438ページに及ぶ英文書籍として2010年1月に出版した.また,2010年1月には,この英文書籍の一般への配布をかねて,この特定領域最後のシンポジウムとなる,3rd International Symposium on Next Generation Actuators Leadin Breakthroughsを東京工業大学大岡山キャンパスにて開催した.シンポジウムでは,出版した書籍の内容に即して,各研究者が研究成果の発表を行った.
1 0 0 0 出かせぎ
- 著者
- 秋田魁新報社政治部 編
- 出版者
- 秋田魁新報社
- 巻号頁・発行日
- 1965
1 0 0 0 OA 正安の伊勢神宮神領興行法と公武関係
- 著者
- 海津 一朗
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.9, pp.1623-1649,1711-, 1992-09-20 (Released:2017-11-29)
This paper is a an empirical study of the law that shows to recover the Ise Shrine Estate Recovery Act (Shiryo kogyo-ho), which the Warrior Government at Kamakura (Bakufu in the East) proclaimed in 1285 and 1301. In early 1285 A.D. (koan 8) the Bakufu ordered local warriors and tradesimen (kotunin) on the states of the Ise Shrine to return their holdings to its original owners, the Shinto priests of the Ise Shrine. The author has found seven judicial precedents of this law in the diaries of court nobles like the Kanchu-ki. These precedents ranged from Ise province to the Kanto area. Because this act applied not only to Bakufu vassels (gokenin) and rear vassels (buke-hikan), their tenure rights, under the fueki-ho and nenki-ho being annulled, but also Kyoto-based hikan groups, who subsequently litigated the Ise Shrine priests. As a result, the Court in Kyoto ordered the Bakufu to repeal the act. At the close of 1286 A.D., the Warrior Government repealed the act of 1285 and reestablished relations with Kyoto. But in l301 the year the (Mongols) navy occupied koshiki-zima Island, as soon as Halley's comet appeared, the Bakufu proclaimed another recovery act for the estates of the Ise Shrine. The Bakufu sent a mission to the Court in Kyoto, to discuss how to defend against the Mongol invaders. The Bakufu's proclamation was one part of their strategy. According to the act, Shinto priests of Ise Shrine were allowed to turn local warriors and tradesmen out of Shrine territory by force. The estates of the Shrine were unified by its leaders, especially the Gegu Shrine priests. In short a concentration of the Shrine power was developing. After all, Bakufu's law, wishing to recover the Estate of the Shrine play an important role to constract "Ichien-ryo", under the policy agreement between East Government (Kamakura Bakufu) and West Government (Kyoto Court). In addition our previous studies said the first law which had played the role to construct "Ichien-ryo" was the law (1312 A.D.) allowing 5 shrines in kyusyu province to recover their Estase.
1 0 0 0 OA 腰部・体幹機能の臨床的評価とアスレティックトレーニング
- 著者
- 成田 崇矢
- 出版者
- 一般社団法人 日本アスレティックトレーニング学会
- 雑誌
- 日本アスレティックトレーニング学会誌 (ISSN:24326623)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.13-17, 2019-10-31 (Released:2019-12-24)
- 参考文献数
- 21
There is no clinical evaluation of lumbar and trunk functions that can reveal all the trunk functions in one evaluation. Therefor you have to understand the clinical evaluations assessment of lumbar and trunk functions of athletes. This paper introduced clinical evaluations of lumbar and trunk functions. The contents are movement evaluation (active movement, thoracic alignment evaluation during extension), spinal segmental mobility, trunk function evaluation (Manual Muscle Test), trunk endurance, Sharmann core stability test, and motor control. When used clinically, it is important to understand the pathology of low back pain of the athlete and evaluate the dysfunction. In addition, if medical rehabilitation is insufficient, the next stage of athletic training often does not proceed as expected. So it is recommended to improve the function of the trunk at the stage of medical rehabilitation.
1 0 0 0 OA 旧民法と明治民法 (三)
1 0 0 0 OA コロナ禍におけるメンタルヘルスの実態と科学的根拠に基づく対策の必要性
- 著者
- 國井 泰人
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.11, pp.11_40-11_46, 2021-11-01 (Released:2022-03-25)
- 参考文献数
- 20
私たちが現在直面しているCOVID-19流行による社会的混乱は、人々の日常生活や社会経済活動に広範な影響を及しており、今なお収束が見えない現状にある。日本でも、この長期にわたるストレスへの暴露や急速な景気の悪化に伴う失業などの経済問題により、うつ病、適応障害、アルコール関連障害などの精神疾患の発症や悪化及び自殺者数の増加、子どもの精神発達への影響などが懸念されており、メンタルヘルスの問題は極めて深刻である。このメンタルヘルス危機に対しては従来の精神医療の体制や方法論では対応が困難であり、いわゆる「With/Postコロナ」の社会におけるニューノーマルなメンタルヘルス対策が必要である。本稿では、コロナ禍のメンタルヘルスの実態を世界各国の研究報告を交え報告し、脳科学やAI技術などの先端技術を活用した科学的根拠に基づくメンタルヘルス対策を提案する。
1 0 0 0 OA 慢性期統合失調症患者に対する音楽療法介入の研究(博士論文紹介)
- 著者
- 浅野 雅子
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.6, pp.352, 2014-06-01 (Released:2017-06-02)
1 0 0 0 OA 3.ワクチン接種の課題と今後の展望
- 著者
- 松本 哲哉
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.27-33, 2022-01-25 (Released:2022-03-08)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
新型コロナウイルス感染症に対して,ワクチンを用いた対策は重要な役割を担っていることは言うまでも無い.国内でも積極的に接種が進められた結果,高齢者の重症化予防や感染者数の低下など一定の効果が得られており,接種率も世界のトップレベルに至っている.その一方で,抗体価の低下やブレイクスルー感染,3回目接種など新たな課題も生じており,今後の収束に向けて,さらに工夫を行いながら対策を講じていく必要がある.
1 0 0 0 OA 大腸菌の加圧耐性に及ぼす諸条件の影響
- 著者
- 里見 正隆 山口 敏季 奥積 昌世 藤井 建夫
- 出版者
- Japanese Society for Food Hygiene and Safety
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.29-34_1, 1995-02-05 (Released:2009-12-11)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 7 9
大腸菌の培養条件 (増殖段階, 培養温度, 培地) 及び加圧条件 (温度, pH, 浸透圧) の変化が加圧耐性に及ぼす影響について検討した. 大腸菌に対する圧力の効果は1,500atm 以上でみられ, 特に, 1,800から2,000atmの加圧で生残率が急激に減少した. 生育時の培地及び酸素の有無と耐圧性の間に相関はみられなかったが, 増殖段階が進むにつれ大きく耐圧性を獲得した. また, 44°培養で得られた菌体の耐圧性は低かった. 加圧時のpHは耐圧性に大きな影響を与えなかったが, 加圧時の温度は44°で生残率が減少した. また, 浸透圧が高いほど生残率が高く, 損傷及び細胞内物質の漏えいも少なかった.
1 0 0 0 OA 106. 粒子状物質長期吸入実験装置の試作とその性能 (粉塵・じん肺)
- 著者
- 田中 勇武 秋山 高
- 出版者
- 社団法人 日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業医学 (ISSN:00471879)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.7, pp.628, 1983-12-20 (Released:2018-12-30)
1 0 0 0 OA 大学生の発達障害の特性をもつ人との交流行動に関する自己効力感に影響を及ぼす要因の検討
- 著者
- 杉本 由衣 武井 祐子 池内 由子 寺嵜 正治
- 出版者
- 岡山心理学会事務局
- 雑誌
- 岡山心理学会 大会発表論文集 岡山心理学会第69回大会発表論文集 (ISSN:24357146)
- 巻号頁・発行日
- pp.29-30, 2022 (Released:2022-03-31)
- 著者
- 筆内 美砂 カッティング 美紀 秦 喜美恵 筒井 久美子 平井 達也
- 出版者
- 日本リメディアル教育学会
- 雑誌
- リメディアル教育研究 (ISSN:18810470)
- 巻号頁・発行日
- pp.2022.03.11.01, (Released:2022-04-01)
- 参考文献数
- 15
本稿は,立命館アジア太平洋大学(APU)で開講する初年次向け多文化間共修科目について,対面とオンラインを併用した同時双方向型ハイブリッド型授業(ハイフレックス型)の授業実践例を報告し,その教育実践の成果と課題を明らかにする。当該科目は,文化的・言語的背景が異なる学生が混ざってプロジェクトを実施するPBL (Project Based Learning)型授業であり,学部生のティーチングアシスタントを活用したユニークな授業である。全受講生対象の授業評価アンケートの分析結果から,2019年度の対面型と比べて,2020年度のハイブリッド型授業はすべての項目の評価が上がった。とりわけ「学生の学び」「アクティブラーニング」「教員の姿勢・関わり,授業設計」が該当する。これらの結果を踏まえて,ハイブリッド型による多文化間共修授業を活かすために重要な「教育的仕掛け」を考察する。
1 0 0 0 OA 資料紹介 菱田唯蔵関連の菱田春草書簡
- 著者
- 小島 淳
- 出版者
- 飯田市美術博物館
- 雑誌
- 飯田市美術博物館 研究紀要 (ISSN:13412086)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.5-11, 2021 (Released:2021-05-07)