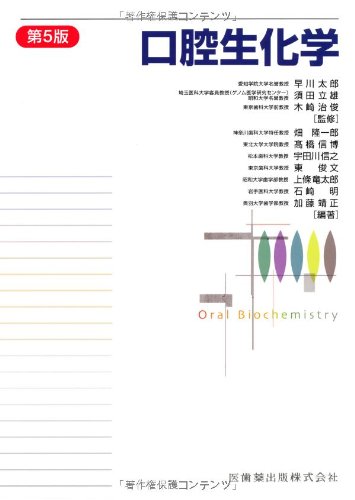- 著者
- 弓 貞子 竹内 登美子 若佐 柳子 桑子 嘉美 片桐 美智子
- 出版者
- 順天堂大学
- 雑誌
- 順天堂医療短期大学紀要 (ISSN:09156933)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.35-42, 1993-03-25
この研究は平成3年に行った表記テーマの研究を土台に行ったものである。研究その1の成果に基づき43名の学生に,改良した実習記録用紙を使用させ,学習効果を測定した。又,記述内容の評価には,教員・学生の双方が使用できる同一の評価用紙を作成した。2つの仮説を基に結果を導き出し,次のような結論を得た。1)情報収集部分の学習の良否が,患者の把握や,看護計画の内容の良さを決定するという事が,仮説検定の理論によっても明かになった。2)改良した実習記録用紙の情報部分では,9割の学生が,必要とする内容を記載できていたので,この様式は学習上有効であるといえる。但し,3)に挙げた注意が必要である。3)教員の評価と学生の自己評価の比較では,7割(14項目)に差が無く,3割(6項目)に有意な差が見られた。差のあった項目のうち4項目は情報部分であり,情報が記入されていても,その意味を理解しているとは限らず,指導上注意が必要である。4)合格ラインに達していなかった項目は,「検査及びその結果」・「予測される問題点」の2つであった。今後特に,指導上の工夫が必要である。
- 著者
- 横溝 賢 赤澤 智津子 澤 孝治 吉田 和裕
- 出版者
- 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究作品集 (ISSN:13418475)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.18, pp.44-49, 2013-03-30
千葉市のバス事業会社・ビィー・トランセホールディングス株式会社の依頼で千葉工業大学のデザイン専攻の学生と、神田外語大学の語学専攻の学生らが共同してバスのラッピングデザインをするワークショップ(以下、WS) が実施された。WSはデザインの非専門家を含むチームでデザインを進めることから、専門知識を必要とせず、参加者全員が同じ立場でデザインを思考するためのフレームワークが必要であると考え、「円集知マップ」を考案し、本WSで実践的活用を試みた。円集知とは「円環に集約された個々人の知識」を意味する造語である。この円集知マップを活用した結果、各チームは個々人のバスの経験と知識(以下、経験知)を統合したマップをチームのビジョンとして共有し、独自のデザイン解を導き出すことができた。本稿では、円集知マップ考案の経緯を呈示し、実践的活用を通してその有効性について考察する。
2 0 0 0 OA 粥の調理に関する研究 : 国産米と輸入米を用いた粥の特性
- 著者
- 江間 章子 貝沼 やす子
- 出版者
- 社団法人日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.29-36, 1996-01-15
- 被引用文献数
- 9
We studied for rice gruel mixtures containing several different ratios of rice (3 bu kayu, 5 bu kayu, 7bu kayu, Zenkayu) with regard to their physical properties and digestibility, and we also conducted sensory tests. We compared two brands, i. e. Thai rice and Japanese "Koshihikari." The following is a summary of the results: 1) After cooking, Thai rice grains gained more weight than "Koshihikari" and had a higher degree of swelling. Rice gruel with a low ratio of rice had a bigger weight increase and a higher degree of swelling. All of the rice gruels absorbed some degree of water and swelled when left for some period of time after cooking. 2) The hardness and adhesiveness of cooked rice were higher in the rice gruel with a high ratio of rice. A remarkable difference between Thai rice and "Koshihikari" was seen in adhesiveness. In the case of "Zenkayu," Thai rice had a higher adhesiveness, and in the case of the other ratios of rice gruel, "Koshihikari" had a higher adhesiveness. 3) Changes in the degree of swelling, hardness, and adhesiveness were seen when the temperature fell to 60℃ after cooking. 4) α-Amylase produced more reducing sugar in Thai rice and gruels with a high ratio of rice. 5) In sensory tests on appearance and ease of swallowing, "5 bu kayu" showed fewer difference with Thai rice and "Koshihikari" than "Zenkayu." Concerning the smoothness and adhesiveness, when both "Zenkayu" and "5 bu kayu" showed distinct difference between Thai rice and "Koshihikari." The panellists preferred "Koshihikari" on the whole. 6) Observing the surface of the cooked rice, it was noticed that Thai rice was rough, while "Koshihikari" was smooth, which corresponds with the result of the sensory tests.
2 0 0 0 韓国伝統医学文献と日中韓の相互伝播
- 著者
- 真柳 誠
- 出版者
- 九州大学韓国言語文化研究会
- 雑誌
- 韓国言語文化研究 (ISSN:13485997)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.41-48, 2004-04
2 0 0 0 OA 中国の人口政策
- 著者
- 若林 敬子
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.59-69, 1986-05-30
中国の人口政策,第1の人口の量をめぐる政策は,晩婚,晩産,少生,稀(出産間隔をあけること)である。今世紀末人口を12億にとどめる目標を目指して,いわゆる"1人っ子政策"が進められ,計画外第2子の出産,多子(第3子以上)率の根絶が当面の課題となっている。1984年春以降,第2子出産の条件が"緩和・拡大"され,1985年9月の第7次5カ年計画および「2000年の中国と就業」研究小組では,2000年の人口を12.5億人前後という"修正"がなされている。第2は,優生をめぐる問題であり,いとこ同士の結婚・ハンセン氏病患者の結婚を禁止している(80年婚姻法)。第3は,農業余剰労働力が今世紀末までは2.5億人以上にもおよぶとされ,"離農不離郷"(離農はしたが離村せず)の新しいタイプの労働者を誕生させつつある。第4は,人口高齢化と年金改革等の問題である。年金・賃金・福祉をトータルに把握し,全国的なあるべき社会保障制度の検討が初められだした。以上のように,本小稿は,中国の最近の人口政策を量,質,移動・分布,高齢化の視点から検討し,かつ各省市の計画出産条例の内容を紹介する。
- 著者
- 藁谷 至誠 久保田 英之 橋本 弥古武 原田 倫孝 小松 正佳 関口 浩司 酒井 憲司
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集. D-1, 環境工学I, 室内音響・音環境, 騒音・固体音, 環境振動, 光・色, 給排水・水環境, 都市設備・環境管理, 環境心理生理, 環境設計, 電磁環境 (ISSN:13414496)
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, pp.261-262, 2010-07-20
2 0 0 0 OA 研究会に行こう!
- 著者
- 中西 功
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.3, pp.274-275, 2014-01-01 (Released:2014-01-01)
- 著者
- Yagi Takeshi Chan Alberto Tanimoto Naoto HARIU Takeo ITOH Mitsutaka
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. IN, 情報ネットワーク (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, no.116, pp.37-42, 2010-07-01
In recent years, web-based applications have gained popularity due to the emergence of the trends such as netbooks and cloud computing. This popularity, along with the emphasis on personalization, has lead to the development of many web applications developed by many people. Due to negligence in secure coding, many of these web applications contain vulnerabilities. This has attracted the attention of attackers who want to exploit these security vulnerabilities to hack the web applications. Malicious users who may illicitly use these web applications and the data contained in their databases pose a constant threat. Therefore, it is necessary to protect these web applications as well as the servers on which they run. In order to effectively protect the web applications, a method of monitoring and analyzing attack is necessary in addition to the conventional intrusion detection systems. Honeypots are highly versatile security tools with various applications to internet security. They are computing resources where their value lies in the information they capture while being probed, attacked, or compromised. In this paper, we will discuss the investigation and evaluation of two web honeypots-the High Interaction Honeypot Analysis Tool and the DShield Web Honeypot as well as our proposal for a hybrid honeypot based on the results.
2 0 0 0 穿刺吸引細胞診で診断しえた良性脂肪芽腫の1例
- 著者
- 和田 匡代 高橋 保 植田 庄介 一圓 美穂 宮崎 恵利子 松浦 喜美夫 森木 利昭
- 出版者
- 特定非営利活動法人日本臨床細胞学会
- 雑誌
- 日本臨床細胞学会雑誌 (ISSN:03871193)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.5, pp.537-540, 1998-09-22
- 被引用文献数
- 2
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンピュータ (ISSN:02854619)
- 巻号頁・発行日
- no.860, pp.86-88, 2014-05-15
一つめは旧式のファイアウオールを使い続け、適切な機能強化をしていなかったことだ。はとバスは2009〜2010年にファイアウオールを導入したが、「物理層やネットワーク層を狙った攻撃を防げるもので、アプリケーション層には対応していなかった」(はとバス経…
- 著者
- 梅野 健 行田 悦資 寺井 秀明 高 明慧
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報プロフェッショナルシンポジウム予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, pp.39-43, 2007
一般の著作物・コンテンツをインターネットで流通するためには、その著作物・コンテンツの著作権者とユーザー双方に満足する仕組みが不可欠であるが、現在著作権があるコンテンツの流通を促す完全な仕組み(ソフトインフラ)が無い状況である。本発表は、日本では独立行政法人情報通信研究機構が提供する標準時を用いた新しいタイムスタンプの仕組みと、2次元バーコードを用いたPKIであるcipheron.netを用いて、絶対的な厳密性を持つコンテンツ配信をする仕組みを提案する。この仕組みにより、決められた時間までは、視聴(復号化)できるが、その時間を過ぎるとコンテンツは暗号化された状態であり、更にその時点で視聴(復号化)しようとすると、コンテンツが自動消滅することにより、コンテンツ著作権管理ができる。この基準となる時刻を標準時とすることにより、そのコンテンツ管理が絶対性(厳密)に行われることになる。更に、コンテンツの2次流通を促す、カオス理論に基づく2次流通価格決定理論を提案する。
2 0 0 0 IR 『イキガミ』を読む--死生の物語の構築と読解に関する試論
- 著者
- 山崎 浩司
- 出版者
- 東京大学グローバルCOEプログラム「死生学の展開と組織化」
- 雑誌
- 死生学研究 (ISSN:18826024)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.304-279, 2008-03
2 0 0 0 OA 常識は覆るのか?! : 光触媒反応における酸素の還元機構
- 著者
- 大谷 文章 阿部 竜
- 出版者
- 化学同人
- 雑誌
- 化学 (ISSN:04511964)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.9, pp.19-23, 2008-09
2 0 0 0 OA 韓国教会にみるキリスト教と伝統文化
- 著者
- 秀村 研二
- 出版者
- 国際基督教大学
- 雑誌
- 国際基督教大学学報. II-B, 社会科学ジャーナル (ISSN:04542134)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.147-170, 1990-03-31
2 0 0 0 IR LMS(Moodle)を利用した多読の可能性 : 多読後のフォーラム投稿文を中心に
- 著者
- 原田 照子
- 出版者
- 桜美林大学言語教育研究所
- 雑誌
- 桜美林言語教育論叢 (ISSN:18800610)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.109-125, 2015
2 0 0 0 OA 人工心臓の新しい自動制御理論
- 著者
- 高木 啓之 岡本 晃〓 高松 幹夫 佐藤 元美 高木 登志子
- 出版者
- 一般社団法人 日本人工臓器学会
- 雑誌
- 人工臓器 (ISSN:03000818)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.1041-1044, 1988-06-15 (Released:2011-10-07)
- 参考文献数
- 4
Single chamberの空気駆動のポンプの圧排、膨満をセンサーの電位レベルできめ、電磁弁と連動させると、パンビングは自走する。その際のsystole, diastoleを計測してS/Dを求め、あらかじめプログラムに与えたS/Dの目標値に近づく様に空気圧を調整するという方式の全自動制御システムを開発した。このシステム下のパンピングは、preload(流入量)とafterloadに自動的に対応し、流入量が同一ならばafterloadが変化してもoutputは同じで、逆に流入量が変化すればafterloadが同一でも、システムがきめる空気圧は異り、outputは異った。このS/Dの目標値は各deviceで異るから、あらかじめ模式回路で計測してきめる必要がある。
2 0 0 0 OA 南部北上山地, 世田米地域の古生層について
- 著者
- 斎藤 靖二
- 出版者
- 東北大学
- 雑誌
- 東北大學理學部地質學古生物學教室研究邦文報告 (ISSN:00824658)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, pp.55-67, 1966-03-30
The Paleozoic System distributed in the Setamai district, southern Kitakami massif, is classified on the ba-5is of rock facies as follows; Toyoma Formation Permian Kanokura Formation Sakamotozawa Formation ~Unconformity~ Nagaiwa Formation Onimaru Formation Carboniferous ~Unconformity~ Odaira Formation Arisu Formation Orikabe Formation The Orikabe, Arisu, and Odaira Formations are composed chiefly of "schalstein" and black slate. The acidic to andesitic pyroclastics intercalated in the Orikabe Formation indicate the former existence of volcanic activities. The Arisu Formation and the lower part of the Odaira Formation are composed mostly of andesitic pyroclastics, which decrease in thickness upwards to the middle part of the Odaira Formation. This shows that intense volcanism was periodic during deposition of those formations. The formations other than mentioned above do not show such intense volcanic activity. The Paleozoic System of this area is folded and faulted into blocks and thus their structures are complicated. The Hizume-Kesennuma tectonic line which extends in NNW-SSE direction is situated in the western part of the area and the eastern margin is defined by the grandodiorite which metamorphosed the sedimentaries in contact ther with. The most striking feature of the geology of this district is the structural differences between the Carboniferous and the Permian Systems. This unconformity was discovered by Minato (1942) at the base of the Permian Sakamotozawa Formation in the Setamai district who said that it represents the "Setamai folding" of thee Late Carboniferous. The folding axes of the Carboniferous System trend nearly N-S, whereas that of the Permian System is generally NNW-SSE in direction, being parallel with the Hizume-Kesennuma tectonic line. The Permian System is distributed in the northeastern, southeastern and central parts of the district and along the tectonic line. In the central part, in general, the Permian strata form a large-syncline, with NNW-SSE trend plunging to the south and parallel with the tectonic line. On the other hand the Carboniferous System which is restricted in distribution to the eastern side of the tectonic line, is developed on the outerside of the large-syncline. In the east of Komata it occurs in the Permian System as a block uplifted by faulting. The Orikabe Formation is distributed along the western wing of the syncline extending from Orikabe to Okuhinotsuchi in north to south direction though it is separated into several blocks by faults. The Arisu Formation is developed on the outerside of the Orikabe Formation which follows the syncline. The Odaira Formation is distributed generally farther to the outerside than the lower formations though it is directly overlain with unconformity by the Sakamotozawa Formation at the west of Mt. Odaira, and is bordered by the Onimaru Formation on its outerside. Concerning the Carboniferous System it seems that each of the formations is developed on the westward and eastward sides of the central part of the area in ascending order, and all of them are covered with unconformity by the Permian Sakamotozawa Formation. Furthermore, the Carboniferous System sometimes develops a large-anticline and gently dipping fluted homoclines, features which cannot be seen in the intensely folded Permian System. It seems that these evidences reflect not only the lithofacies but also the geologic structures of the Carboniferous System before the deposition of the Sakamotozawa Formation. The differences of the geologic structures between the Carboniferous and the Permian Systems, as mentioned above, are the results of the "Shizu folding" and the "Setamal folding" of Minato (1942). Therefore it is supposed that a large-anticline with axis of nearly N-S trend might have been formed and denuded in the Setamai district before the deposition of the Sakamotozawa Formation. The geological structures must have been fairly complicated, but concerning the details more precise investigation must be undertaken.
2 0 0 0 口腔生化学
- 著者
- 畑隆一郎 [ほか] 編著
- 出版者
- 医歯薬出版
- 巻号頁・発行日
- 2011