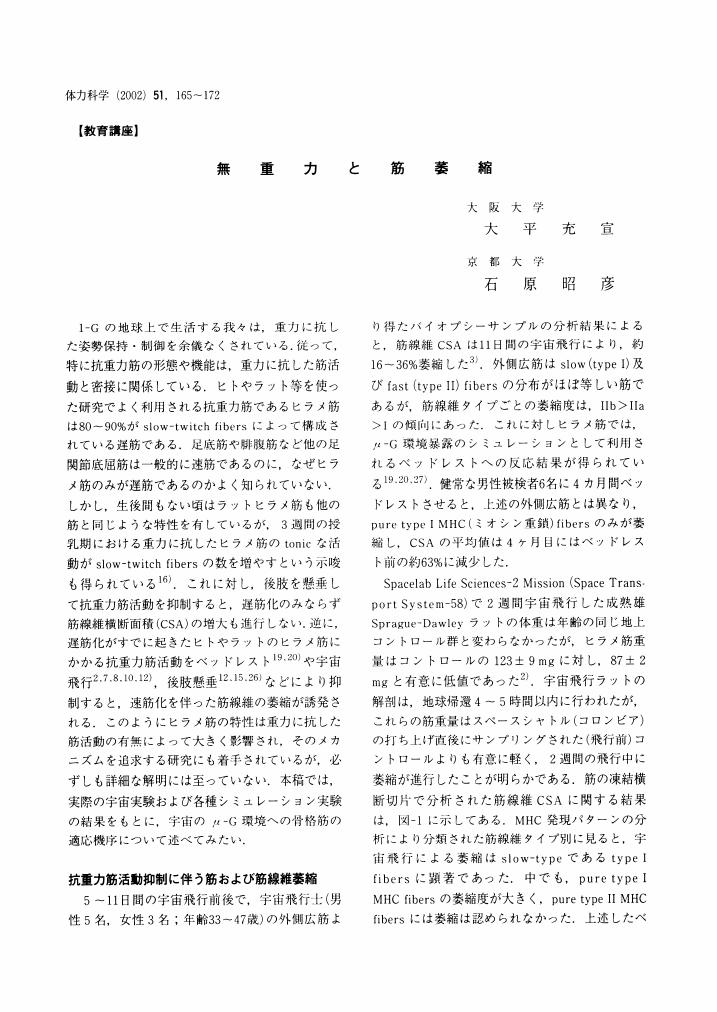- 著者
- 福田 和子 金城 繁徳 尾和 博 貴家 仁志
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会総合大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.1995, 1995-03-27
これまでいくつかの2次元適応フィルタ(ADF)が報告されてきたが、特に演算量が問題となっている。例えば、2次元LMS法を用いても、サンプル当りの演算量はO(N^2)である。演算量の問題を克服するためには、ADFの並列化が不可欠である。そこで本報告では、2次元DFT周波数サンプリングフィルタ(FSF)バンクを用いた並列ADFを提案する。提案する2次元ADFは、並列構造であるうえに、FFTを用いることで演算量も大幅に低減される特長を持つ。
2 0 0 0 OA 茨城県石岡市周辺の特徴的な食材と食事について
- 著者
- 荒田 玲子 渡辺 敦子
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成26年度(一社)日本調理科学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.42, 2014 (Released:2014-10-02)
【目的】日本調理科学会・平成24~25年度特別研究における聞き書き調査の中で、茨城県石岡市とその周辺地域における昭和20~30年代の食生活の様子、その地域で作られた食材、当時の物流の中で入手可能な食材による料理に注目して、石岡地域の食生活の特徴【目的】平成24~25年度日本調理科学会特別研究における聞き書き調査の中で、茨城県石岡市とその周辺地域における昭和20~30年代の食生活の様子、その地域で作られた食材、当時の物流の中で入手可能な食材による料理に注目して、石岡地域の食生活の特徴を知ることを目的とする。【方法】旧石岡市と八郷地区の食生活改善普及員を対象とし、複数回の直接面談法により調査を行う。調査の前に予め、「当時の食生活の様子」、「次世代に伝えたい家庭料理と地域を代表する行事食・日常食」、「地域の行事食とその料理にまつわる思い出や蘊蓄」についてのアンケートを自由記述形式にて行い、回答内容に従って面談する方法をとった。調査者は、石岡市内に35年以上居住する、59~75歳の女性(食生活改善普及員石岡地区役員)9名とした。【結果】特徴的食材・料理としては、貝地の高菜栽培と高菜漬、地域の店で現在も入手できる海藻用羹を使用した「海藻羊羹」、正月などハレの日に作られる「矢羽の羊羹」、「ばらっぱもち」、「たがねもち」などの餅類があげられた。栃木や茨城県西部の郷土食「すみつかれ」と同名の「酢みつかれ」は、鮭頭は入らないが、大豆や石岡産の落花生が入り、大根は鬼おろしでおろして作られる酢の物であった。正月の「昆布巻き」は、霞ヶ浦に近いこともあり、鮒やワカサギなどの淡水魚を昆布で巻いて作られていた。山間の八郷地区と平野の広がる石岡地区、近くに河川や霞ヶ浦を臨み、山や川や大地の恵みを利用した食生活が営まれていたことがわかった。。
2 0 0 0 OA 2字の漢語の読みにおけるリズムの乱れ : ある台湾出身者の場合
- 著者
- 北村 よう
- 出版者
- 東海大学
- 雑誌
- 東海大学紀要. 留学生教育センター (ISSN:03892255)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.49-60, 1999
- 著者
- 野本 豊和 八木 伸也 アーリップ クトゥルク 曽田 一雄 橋本 英二 谷口 雅樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本表面科学会
- 雑誌
- 表面科学講演大会講演要旨集 第25回表面科学講演大会
- 巻号頁・発行日
- pp.118, 2005 (Released:2005-11-14)
Ar+スパッタ後、分子を吸着させる前の金属基板加熱温度を制御し、表面粗さを変化させた。任意の加熱温度での表面粗さを原子間力顕微鏡 (AFM)で測定し、90 Kにおける(CH3)2Sの吸着反応及び構造をX線光電子分光(XPS)及び吸収端近傍X線吸収微細構造(NEXAFS)を用いて調べたところ、吸着種及び構造に基板表面粗さに依存した変化が得られた。
2 0 0 0 OA 疲労強度に及ぼす表面粗さの影響の定量的評価 : 粗さの深さとピッチの影響
- 著者
- 村上 敬宜 高橋 宏治 山下 晃生
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 A編 (ISSN:03875008)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.612, pp.1612-1619, 1997-08-25 (Released:2008-02-21)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 10 43
In order to investigate the effect of surface roughness on fatigue strength, fatigue tests for a medium carbon steel, which was annealed and free of residual stress (HV≅170) and quenched and tempered (HV≅650). were carried out. To simulate the actual surface roughness, extremely shallow periodical notches with a constant pitch but irregular depth were introduced. The equivalent defect size √(area)R for roughness was defined to evaluate the effect of irregularly shaped roughness using the √(area) parameter model. The fatigue limits of the annealed medium carbon steel specimens with artificial surface roughness are much higher than those of the specimen with a single notch because of the interference effect of notches. The fatigue limits predicted by the √(area) parameter model are in good agreement with the experimental results.
2 0 0 0 IR 第二次世界大戦前後の日本における台湾出身者の定住化の一過程 : ライフコースの視点から
- 著者
- 黄 嘉?h
- 出版者
- 神戸大学文学部 海港都市研究センター
- 雑誌
- 海港都市研究
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.129-141, 2008-03
2 0 0 0 OA 2項目自尊感情尺度を用いた状態自尊感情の測定
- 著者
- 箕浦 有希久 成田 健一
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.151-153, 2016-11-01 (Released:2016-09-13)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 2
This paper reports the development and validation of a state self-esteem scale based on the Two-Item Self-Esteem Scale (TISE). Participants completed the state self-esteem scale in hypothetical scenarios. The criterion-related validity was confirmed owing to the significantly higher TISE score in a positive situation than in a negative situation for both achievement and affiliation scenarios. The concurrent validity was confirmed by the positive correlations between the TISE and a modified state Rosenberg self-esteem scale. The internal consistency of the TISE was also confirmed. Results showed that the TISE was a useful tool in assessing state self-esteem.
2 0 0 0 OA 北陸地方における都市のイメージとその地域的背景
- 著者
- 伊藤 悟
- 出版者
- 一般社団法人 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.4, pp.353-371, 1994-08-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 3 2
The purpose of this study is to clarify the image and its regional background of cities in the Hokuriku District, Central Japan. The methodological framework consists of three preparatory questionnaire surveys, semantic differential (SD) method combined with direct factor analysis, and step-wise multiple regression analysis.Through the preparatory surveys, 18 municipalities (shi) were selected for the analysis as well-known Hokuriku cites in the Niigata, Toyama, Ishikawa and Fukui Prefectures, and 12 pairs of bipolar adjective words were gathered as the rating scales of the image evaluation in the questionnaire of the SD method. Undergraduate students of Kanazawa University located in Kanazawa-shi, Ishikawa Prefecture are the subject for the SD questionnaire, as well as the three preparatory ones.In order to extract the dimension of the city image, the evaluation data derived from the SD questionnaire was subjected to the factor analysis by the direct method, which does not standardize the data and thus starts with the cross-product matrix. Step-wise regression analysis was also utilized for searching the regional characteristics for the backgrounds of the image dimensions in the Hokuriku cities.As a result, three image dimensions were obtained. The first can be interpreted as 'yearning' for city since it is concerned with the adjectives 'urban' and 'lively'. Commercial activity and population size affect this dimension. In the Hokuriku cities, the most desired cities are Niigata-shi and Kanazawa-shi, where commercial activities have been highly concentrated and the population are largest.The second dimension is interpreted as psychological distance, or imaginary 'separation' for city. Real distance to a city increases this separation, and the population size of the city decreases it. The third is 'hesitation', which arises for far distant and industrial or transportation cities. On the other hand, the hesitation is less for Kanazawa-shi, the nearest city for the students, and Wajima-shi and Kaga-shi, which are tourist and spa resort places.
2 0 0 0 BTレジン
- 著者
- 綾野 怜 岳 杜夫 永井 俊一
- 出版者
- Japan Thermosetting Plastics Industry Association
- 雑誌
- 熱硬化性樹脂 (ISSN:03884384)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.23-36, 1984
BTレジンは1974年三菱瓦斯化学で発明された新しい耐熱性付加重合型熱硬化性樹脂であり, その成分は西独バイエル社が発明したトリアジン成分と, ビスマレイミド成分からなる。そして, 熱重合反応により合成されるBTレジンは, 分子内にイミド環を有するポリイミド樹脂の一種に分類される。このレジンは高耐熱で高摩耗性, 低誘電特性や耐マイグレーション性などの電気特性を有し, 且つすぐれた成形性, 作業性, 反応性及び低毒性などの特性を併せもつ極めてユニークな実用性の高い高性能材料である。このような諸特性が国内をはじめ海外に於いて高く評価され, 電子機器用プリント配線材料, 航空機用構造材料, 重電機器用絶縁材料, 粉体塗料, 成形材料, 電子部品用保護コーティング材など広範囲な分野で実用化が進められている。<BR>本稿では機能性材料の原料としてのシアネート基の反応性, BTレジンの製法, BTレジンの特性とその用途開発の現況について概説する。
2 0 0 0 音楽的知覚に関する研究 (V) : 音楽刺激に対する共感覚的反応
- 著者
- 古矢 千雪 Furuya Chiyuki フルヤ チユキ
- 出版者
- 広島文化女子短期大学
- 雑誌
- 広島文化女子短期大学紀要 (ISSN:09137068)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.61-66, 1983-09-30
This study is a continuation of the last study to investigate the synesthetic response to the musical stimulus. The subjects were 67 students of music course in Exp.1 and 20 students selected by the preliminary research, in Exp.2. They were indicated to answer their sense experiences in hearing music and noted not to take the attitude of judgement or association. Questions: 1. Do your body move or you feel your body move? 2. Do you experience the physiological change, for example, heart beat fast? If so, discribe. 3. Do you see or feel to see light? 4. Do you see or feel to see color? 5. Do you smell or feel to smell anything? 6. Do you touch or feel to touch anything? 7. Do you taste or feel to taste anything? The example of the answer: a. No, I don't., b. Yes, I feel slightly to-., c. Yes, I feel fairy to- ., d. Yes, I seem to actually-., e. Yes, I actually see (touch, smell, etc.). If you feel or actually do, discribe the contents. The stimulus was the same as Exp.2 in the last study, the first phrases of the Respighi's Pini di Roma. The main results were as follows: In Exp.1, the 25 subjects felt body move or actually moved, 12 felt their physiological change, 38 felt light, 25 felt color and 6 felt touch. The appearance of responses was similar as Exp. 2 in the last study. In Exp. 2, the synesthetic responses, colorhearing, were appeard in 3 subjects. They answerd, "I don't look the thing colored but feel the color vividly, like as see that acutually in mind". There was the color-hearing, in some cases, I think, formed by conditioning in childhood.
- 著者
- 薄田 拓磨 村尾 修 杉安 和也 薬袋 奈美子
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集 (ISSN:18839363)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, pp.441-442, 2015-09-04
2 0 0 0 アカネズミにおける頭骨の異常例
- 著者
- 柳川 定春
- 出版者
- THE MAMMAL SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- 哺乳動物学雑誌: The Journal of the Mammalogical Society of Japan (ISSN:05460670)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.5, pp.187-188, 1972
Mammals in Hawaii, P.Quentin Tomich著, 238ページ, Bishop Museum, 1969<BR>著者はハワイ島のホノカにあるハワイ州立防疫調査研究所に勤務する獣類の研究者で, おもにネズミ, マングースの生態を調べている。この著書にはクジラ, イルカを含めた44種が45枚の写真とともに述べられ, ハワイ群島の地図が1葉ついている。<BR>この群島の陸上にすむ獣類のほとんどは輸入して放されたか, 船から侵入したものであるが, その渡来について各種類ごとに正確な年代をあげ, 現在の生息状況, 被害などについて詳しく述べてあるのでこの群島の獣類相と, 輸入獣類の生物相にあたえた影響を知るのに有益である。とくに, 1883年9月30日にハワイ島のヒロで72頭のマングースがネズミの天敵として放たれたが, いまでは全群島にすみつき, ネズミ駆除の効果はあがらずかえって砂糖キビを食べたり, ニワトリを襲ったりして産業に大きな害をあたえるにいった経過などが文献をあげて説明されている。全般としてハワイ群島の獣類を知るのにこのうえもない本である。<BR>(Bishop Museum, Honolulu, Hawaii発行, 定価5ドル) 。
2 0 0 0 OA 電位地図からみた聴性脳幹反応の第1波の極性について
- 著者
- 白石 君男 加藤 寿彦 曽田 豊二
- 出版者
- 日本聴覚医学会
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.5, pp.317-318, 1982 (Released:2010-04-30)
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 経済成長と二酸化炭素排出量削減は両立するか : デカップリング概念を用いた国際比較
- 著者
- 高井 亨
- 出版者
- 京都大学経済学会
- 雑誌
- 經濟論叢 (ISSN:00130273)
- 巻号頁・発行日
- vol.184, no.2, pp.71-88, 2010-04
2 0 0 0 8014 公営住宅の家賃滞納問題(建築経済・住宅問題)
- 著者
- 平山 洋介
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会近畿支部研究報告集. 計画系 (ISSN:13456652)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.741-744, 1988-05-01
2 0 0 0 OA 無重力と筋萎縮
- 著者
- 大平 充宣 石原 昭彦
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.165-171, 2002-02-01 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 28
- 著者
- 橋本 康二
- 出版者
- 一般社団法人日本科学教育学会
- 雑誌
- 年会論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.131-134, 1989-08-05
2 0 0 0 磁性箔付加ケーブルの伝送損失に関する検討
- 著者
- 柳谷 真由美 森 敏則
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. EMCJ, 環境電磁工学
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.286, pp.41-46, 1997-09-26
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 2
電気ケーブルからの放射ノイズの低減を狙いとして高透磁率・高損失な金属磁性箔を付加したケーブルを作製した. 磁性箔を付加することによってケーブルに生じる伝送損失の測定を行なった. その結果, 心線の外側に直接磁性箔を巻いた時の伝送損失は周波数の増加とともに増え, 300MHzにおいて最高11dB/3m となったが, アルミテープを磁性箔と心線の間に巻くことによって, 通常の磁性箔無しのシールドケーブルと同等の伝送損失となることが分かった. また, 磁性箔だけでは外側の心線と内側の心線の伝送損失の差が大きくなるが, アルミテープを心線と磁性箔との間に巻くことで心線位置による差が小さくなることも分かった. この原因としては, 心線近傍の磁界がアルミテープの渦電流損失によって弱められるため, 磁性箔がケーブル心線に付加するインピーダンスが小さくなることが影響していることを示した. また, 高透磁率・低抵抗率の磁箔を使用した場合は, 1層目の磁性体により渦電流損失・反射が起こるため, ケーブルに多重に巻き付けても伝送損失増加に対する影響は大きくないことを明らかにした.
- 著者
- 冨山 芳幸 高橋 大輔 林 大輔
- 出版者
- 社団法人日本気象学会
- 雑誌
- 大会講演予講集
- 巻号頁・発行日
- vol.108, 2015-09-30
- 著者
- 小澤 考人
- 出版者
- 「現代社会理論研究」編集委員会事務局
- 雑誌
- 現代社会理論研究 (ISSN:09197710)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.378-390, 2004