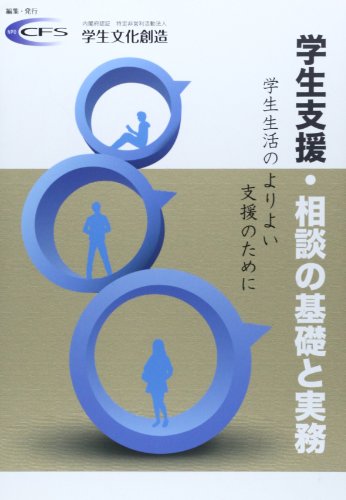2 0 0 0 据置シール鉛畜電池(MST形)の開発状況
- 著者
- 三浦 朝比古 武政 有彦 向谷 一郎 吉山 行男 福田 政寛
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. CPM, 電子部品・材料 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.537, pp.29-34, 2000-01-14
通信ネットワークシステムにおけるバックアップ用電源として、長寿命で新構造の据置シール鉛畜電池MST形を1997年に開発し、さらに大幅に質量を減らした軽量化据置シール鉛畜電池MST形を199年に開発した。電池特性は10時間率の定格容量と15年のトリクル寿命という通信用として十分な性能を有している。また、100 Ah, 1500Ah容量の単電池を直列あるいは並列接続して、1000〜6000Ah容量までの組電池に対応することができる。その上、単電池横置きのユニット構造であり、設置床面積を低減したコンパクトな組電池構造になっている。
2 0 0 0 一般廃棄物の処理工程での事故事例とその解析
- 著者
- 若倉 正英 岡 泰資 三橋 孝太郎 橋本 孝一 泊瀬川 孚 宮川 孝
- 出版者
- Japan Society of Material Cycles and Waste Management
- 雑誌
- 廃棄物学会誌 (ISSN:09170855)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.4, pp.337-343, 1998-05-30
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
一般廃棄物では収集運搬, 処理過程で少なからぬ事故が発生している。一般廃棄物を取り扱う工程での安全を担保するためには, 危険性の実態を把握することが重要である。廃棄物処理管理技術者協議会では厚生省の協力の下に, 平成4年から8年の間に一般廃棄物処理施設で発生した事故に関するアンケート調査を行い興味のある結果を得た。5年間で400件近くの事故が報告され, その中には32名の死亡者と198名の負傷者が含まれ, 被害額1, 000万円以上の物損事故は30件以上発生した。<BR>カセットボンベなどに起因する火災, 爆発事故が多発し大きな施設破壊と時には人身事故を引き起こしていた。また, 施設の老朽化や処理対象廃棄物の増加, 作業マニュアルの整備の不足は種々な労災事故の原因となっていた。さらに, 新規な処理技術の開発や処理対象物質の多様化が進んで, 混触による中毒や異常反応に伴う爆発など, 事故の形態がこれまで以上に複雑化してくる可能性が示唆された。
2 0 0 0 狂犬病特に其の流行状態の立體的考察に就て
- 著者
- 池上 幸健
- 出版者
- The Japanese Association for Infectious Diseases
- 雑誌
- 日本傳染病學會雜誌 (ISSN:00214817)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.6, pp.561-567, 1927
- 著者
- Han Duksu
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コミュニケーション (ISSN:09107215)
- 巻号頁・発行日
- no.596, pp.72-75, 2013-09-01
続いてネイティブアプリ用の開発環境である「Tizen Native IDE」も見ていこう。こちらもEclipseがベースになっており(写真2)、Tizen Web IDEとよく似ており、操作感もほとんど変わらない。 Webアプリ向けIDEと同様に、ネイティブアプリ向けIDEでもウィザード形式で…
- 著者
- 下田 元 佐藤 実 城戸 幹太 猪狩 俊郎 岩月 尚文
- 出版者
- The Japanese Society of Reanimatology
- 雑誌
- 蘇生 (ISSN:02884348)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.18-21, 2004-02-20
- 被引用文献数
- 2
術前の内科的心循環器系機能評価で特に異常を認めない患者の顎口腔再建術中に, 発作性に心室性頻拍が発生し心室細動に移行した。胸骨圧迫心マッサージを継続しながら電気的除細動を繰り返したが奏功しなかった。リドカイン, エピネフリン, アトロピンなどの薬剤併用にも反応せず蘇生し得なかった。病理解剖学的診断の結果, 特に右室に著明な菲薄化・拡張を認め拡張型心筋症の病態を呈していた。潜在していた心筋障害が, 薬剤・DCショックに反応性を示さなかった致死性不整脈発生の原因と考えられた。<BR>潜在性の病的心筋に対する内科的評価の限界を痛感させられ、無症候性症例の術前のリスク評価方法が当面する課題であると思われた。
2 0 0 0 光ポンピング原子磁気センサ
- 著者
- 小林 哲生
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会誌 (ISSN:13405551)
- 巻号頁・発行日
- vol.136, no.1, pp.26-29, 2016-01-01 (Released:2016-01-01)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
1.はじめに 光ポンピング法により生成したアルカリ金属原子のスピン偏極を用いて極微弱な磁界の計測を可能とするのが光ポンピング原子磁気センサ (Optically pumped atomic magnetometer:OPAM) である(1)(2)。光ポンピング法とは,近接した二つのエネルギー準位における電子の占拠数
2 0 0 0 OA 設計を通じた持続可能社会実現への貢献
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.8, pp.893-894, 2007 (Released:2009-11-25)
2 0 0 0 OA ヂゴマ退治 : 探偵奇談
2 0 0 0 OA 速読について
- 著者
- 小田切 隆
- 出版者
- 早稲田大学語学教育研究所
- 雑誌
- ILT NEWS (ISSN:02863545)
- 巻号頁・発行日
- vol.61号, pp.47-59, 1976-07
2 0 0 0 OA 若年男性に発症した後腹膜原発絨毛癌肺転移の一剖検例
- 著者
- 佐々木 結花 山岸 文雄 鈴木 公典 宮澤 裕 杉戸 一寿 河端 美則
- 出版者
- 日本肺癌学会
- 雑誌
- 肺癌 (ISSN:03869628)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.7, pp.1065-1069, 1993-12-20
- 被引用文献数
- 3
肺転移にて発見された後腹膜原発絨毛癌の一例を経験したので報告する.症例は24歳男性.主訴は血痰で, 精査目的にて当院に入院した.胸部エックス線所見上, 両側肺野に多発した結節影および両側胸水を認めた.外性器に異常所見は認められなかった.腹部CT写真にて後腹膜に腫瘤を認め, 泌尿器科にて腎腫瘍が疑われたが, 検査拒否にて組織型を決定できず, 呼吸状態が急激に増悪し, 呼吸不全にて死亡した.剖検にて, 両側肺を多発した腫瘤がしめ, また, 後腹膜に腫瘤が存在し, その一部は下大静脈壁内腔に浸潤していた.同腫瘤, 肺転移巣の両者の病理組織より, 絨毛癌の診断が得られ, 免疫組織学的検索で胞体がhCG陽性であることが確認された.生殖器には原発巣は認めず, 後腹膜原発絨毛癌と考えられ, きわめて稀な症例と考えられ報告した.
2 0 0 0 日本初の自衛隊ヘリコプターによる組織的救急救護搬送
- 著者
- 滝口 雅博
- 出版者
- 日本航空医療学会
- 雑誌
- 日本航空医療学会雑誌 (ISSN:1346129X)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.3-6, 2014-08
- 著者
- Noriko Yamaguchi Sayaka Okahashi Priscila Yukari Sewo Sampaio Toshiko Futaki
- 出版者
- 社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- Asian Journal of Occupational Therapy (ISSN:13473476)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.53-60, 2016 (Released:2016-09-07)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1
Aim: To clarify the characteristics of desktop dual tasks that cause dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) activation. Methods: Subjects (29 young adults and 22 middle-aged adults) performed three different combinations of dual tasks composed of a pencil and paper task (copying numbers or calculation) and a hand-shape changing task (in response to visual hints or self judgment). We measured brain activation using near-infrared spectroscopy. Results: Right DLPFC activation was significantly higher for the simplest dual task than the complex dual task with the younger group, whereas there was no significant difference between tasks with the middle-aged group. Task performance was higher in the younger group than the middle-aged group, whereas there was no difference in brain activation between the two age groups. Conclusion: A dual task including two of each task performed automatically could be used for training frontal lobe functions, and the difficulty level should be adjusted depending on age.
2 0 0 0 OA オープンアクセスとオープンサイエンスの最近の動向: ビジョンと喫緊の課題
- 著者
- 林 和弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本表面科学会
- 雑誌
- 表面科学 (ISSN:03885321)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.6, pp.258-262, 2016-06-10 (Released:2016-06-21)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1 1
Author introduces a vision and current issues of Open Access and Open Science with some backgrounds. Both are hot policy issues all over the world and getting recognized among researchers gradually. Towards new paradigm and a platform for next generation of scientific research activities and publishing systems, learned societies and its members, with other various stakeholders, should reframe their strategy with redefining of their mission.
2 0 0 0 OA 1961∼1976の福岡市周辺における放射性降下じんによる食品汚染
- 著者
- 森重 敏子 石西 伸 長 哲二
- 出版者
- 日本衛生学会
- 雑誌
- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.3, pp.434-441, 1977-08-30 (Released:2009-02-17)
- 参考文献数
- 19
The contamination and the pollution of foodstuffs by radioactive fallout have been investigated since 1961 in Fukuoka city and its suburban area. The results obtained were as follows.1) Recently, the degree of the contamination of greens by radioactive fallout which fell on the leaves decreased to one thousandth in the early stage of the investigation (1961-1962). In the period of the investigation, the remarkable increase of the radioactivity of fallout was observed within a week after the Chinese nuclear bomb explosion in the atmosphere (1st, 2nd, 5th, 12th, 13th, and 15th). The radioactivity was 2 to 300 times higher than the usual level.2) The radioactivity was not remarkable in vegetables which were washed with soap, but it decreased gradually year by year. The increase of the radioactivity was also observed a few days after the atmospheric nuclear explosion.3) In milk, there were no remarkable yearly decreases of the radioactivity from the beginning of the investigation, but the seasonal variations of the radioactivity, such as higher in April and May, were observed.4) The radioactivity in diets based on the standard food production in Japan was the highest in 1967. It decreased gradually from 1967 to 1971 and after that the remarkable variation of the activity was not observed.5) 137Cs contamination of foodstuffs has been observed quantitatively by the method of gamma spectrometry, while sometimes 95Zr-95Nb, 103Ru, and 131I were also detected from the specimens obtained immediately after the nuclear explosions.
2 0 0 0 学生支援・相談の基礎と実務 : 学生生活のよりよい支援のために
2 0 0 0 OA 随想 宇宙からは国境は見えません
2 0 0 0 OA 高校野球指導における新しい打者評価法の開発
- 著者
- 朝西 知徳
- 出版者
- 社団法人日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会号
- 巻号頁・発行日
- no.48, 1997-08-29
2 0 0 0 OA 空に浮かぶ鉄がカッコイイ!(ボクたちの夢・ロマン, 私の鉄・夢ロマン)
- 出版者
- 社団法人日本鉄鋼協会
- 雑誌
- 鐵と鋼 : 日本鐡鋼協會々誌 (ISSN:00211575)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.4, pp.N184-N185, 1995-04-01
2 0 0 0 IR 日本の民事執行制度の歴史及び近時の民事執行法改正について
- 著者
- 三谷 忠之
- 出版者
- 香川大学法学会
- 雑誌
- 香川法学 (ISSN:02869705)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.169-188, 2014-03
2 0 0 0 A statistical study on seismicity patterns of intraplate earthquakes in the Japanese Islands.
- 著者
- 市川 政治
- 出版者
- 気象庁気象研究所
- 雑誌
- Papers in Meteorology and Geophysics (ISSN:0031126X)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.91-134, 1986
- 被引用文献数
- 5
地震予知研究のため、地震をはじめとして各種の観測網が整備され、データが急速に蓄積されつつある。その結果、地震の前駆現象は単純なものでないことが明らかとなってきた。大きな地震の前駆的異常現象として、前震、バースト、群発地震、地震空白域、地震活動の静穏化、発震機構の変化、その他が認められている。しかし、これらの現象は大きな地震の前に必らず出現するものでなく、また、出現したからといって必らずしも大きな地震が発生するものでもないらしい。さらに、これらの現象の発生には地域性があるとされている。<br> 大地震の前駆的異常現象について、これまで多くの研究がなされているが、これらの研究における異常検出の基準は必ずしも同じではなく、また、各種の異常を総合的に調べた事例は少ない。そこで、1926-1983年までに主として日本内陸に発生した深さ30km以浅で規模M5以上の地震を対象にして、同一判定基準で、かつ、できるかぎり客観的に各種の地震学的前駆現象の検出を行った。これらの現象検出はM5以上の地震について、また、検出のために使用した地震のMは、データの均質性を保つために3.5以上とした。このほかに、これらM5以上の地震発生と活断層、地質断層や歴史地震との関連も調査した。<br> 地震発生と検出した各種現象との関連性を統計数理研究所の坂元らの開発したプログラムCATDAPにより解析したところ、大きな地震に最も強い関連のあるものは、地震空白域、ついで、バースト、また、地震空白域と前震、バースト、地震活動静穏化現象との組合せも、大きな地震の発生と強い関連性を持つという結果が得られた。さらに、活断層や歴史地震は大きな地震の発生とは独立であるという結果も得られた。歴史地震と大きな地震の発生が独立であるという結果は、内陸浅発地震の再来周期の長さから妥当なように考えられる。<br> さらに、地震発生のパターンには顕著な地域性が認められた。<br> 以上の諸結果に基づいて、内陸浅発の大きな地震発生の長/中期的予測のために有効と考えられる地震学的前駆現象の検出手法を検討してみた。