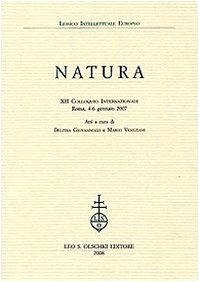2 0 0 0 二重像からの画像分離再構成法
- 著者
- 近藤 浩
- 出版者
- 一般社団法人映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会誌 (ISSN:03866831)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.301-304, 1990-03-20
二重像からそれぞれの画像を分離, 再構成する新しい方法を示す.観測画像が二重像となっているとき, 各々の原画像パワースペクトルと1つの原画像フーリエ変換位相との間に成立する唯一の関係式を導く.これにより得られた位相から画像再構成を行い, 二重像の分離を行う.シミュレーション例は, 二重像の分離が完全に行われることを示している.
2 0 0 0 OA 全てのヲは格助詞か
- 著者
- 中尾 有岐 ナカオ ユウキ Nakao Yuki
- 出版者
- 大阪大学世界言語研究センター
- 雑誌
- 大阪大学世界言語研究センター論集 (ISSN:18835139)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.75-88, 2012-03-08
- 著者
- 片山 昇
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.324-333, 2007
相利共生とは、相互に関係する生物種が互いに相手から利益を受ける関係であり、あらゆる生態系にみられる。しかし、相利共生は状況に応じて変化し、時として解消される。相利共生は多様な生物種を生み出してきた大きな要因であるため、相利共生の動態を解明することは生態学や進化学の重要な課題となってきた。アリとアブラムシの関係は、アブラムシが甘露を提供するかわりに、アリがアブラムシの天敵を排除するという、良く知られた相利共生の一つである。しかし、アリ-アブラムシの関係は生態的あるいは進化的に変化しやすく、相利から片利、さらには敵対にいたるまで多様な形態が存在する。このようなアリ-アブラムシ系における関係の変異の創出や相利共生の維持機構について、これまでの研究ではアブラムシがアリに随伴されることに対するコストと利益を考慮した最適化理論が用いられてきたが、その範疇に収まらない例が多い。一方で、(1)アブラムシの内部共生細菌は宿主の形質を変化させる、(2)アリは局所的な昆虫の群集構造を決める、ということが明らかにされてきた。そこで本稿では、アリ-アブラムシ系を複数の生物が関わる相互作用として捉え直し、相利共生の動態について議論する。特に、(1)アリ-アブラムシ-内部共生細菌による複合共生系の存在と、(2)アリ-アブラムシの相利共生とアブラムシ天敵の群集動態とのフィードバックについて仮説を提唱する。
- 著者
- 田邉 昇
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経メディカル (ISSN:03851699)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.175-177, 2008-03
東京女子医大で患者が死亡した医療事故の裁判で、医師が無罪を言い渡されました。その判決を報じたニュース番組の内容が名誉棄損に当たるとして、医師は弁護士を立てずに本人訴訟でテレビ局を訴え、勝訴しました。
2 0 0 0 121Y06 「エンピツまわし」の研究 : 伝播の条件
- 著者
- 石井 隆憲
- 出版者
- 社団法人日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会号
- 巻号頁・発行日
- no.41, 1990-09-10
2 0 0 0 OA 対話交渉シミュレータの機能と活用事例
- 著者
- 岩成 英一 小島 一秀 イワナリ エイイチ コジマ カズヒデ Iwanari Eiichi Kojima Kazuhide
- 出版者
- 大阪大学世界言語研究センター
- 雑誌
- 大阪大学世界言語研究センター論集 (ISSN:18835139)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.195-209, 2012-03-08
2 0 0 0 ジャンヌ退場 : 火刑でない最後があるとしたら?
- 著者
- 李 春美
- 出版者
- プール学院大学
- 雑誌
- プール学院大学研究紀要 (ISSN:13426028)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.93-98, 2002-12
2 0 0 0 本棚を通した体験共有コミュニケーション支援システム
- 著者
- 三木 可奈子 角 康之 西田 豊明
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.99, pp.55-62, 2007-09-28
- 被引用文献数
- 3
本稿では本棚周辺での人の会話や行為といった体験を研究室のメンバで共有することによるコミュニケーション支援を行う本棚システムを提案する.日常生活において積み重ねられる体験はアウェアネスやコモンセンス,ノウハウのような暗黙知を伝えるのに効果的であり,本人だけでなくその場にいなかった第三者にとっても有用な情報となりうる.特に本棚前での何気ない人の振る舞いや会話には興味や知識が見て取れる.本研究では研究室の中で共有されるべき体験の一部として会話や振る舞いを捕らえるシステムを提案する.また,本から得られる既存の書誌情報や,体験者のプロファイルにより,取得した体験シーンのデータとそれに関わる本や人に緩い紐付けを与える.そして,蓄えられた体験シーンのデータや周辺情報を利用者の状況に合わせて再利用し,'本棚にまつわる体験'を豊かにする.This paper proposes a bookshelf system to facilitate communication among research group members based on shared experiences around the bookshelves. Our daily experiences such as collaborative works and chats in research laboratories are effective to share tacit knowledge, e.g., awareness, commonsense, and know-how, etc. Especially, our behavior and conversation in front of bookshelves imply personal interests and knowledge. This paper proposes a system that captures our conversations and behaviors as tractable parts of our experiences shared in the laboratories. The captured experience scene data are linked to relevant books and other members by bibliographic information of selected book and users' profiles. Also, the accumulated data and associated information are reused to enrich other members' "bookshelf experiences" according to their situation.
2 0 0 0 高度技術社会の裏側 (<特集>私のおすすめ本)
- 著者
- 久須美 雅昭
- 出版者
- 社団法人情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.7, pp.315-317, 1995-07-01
- 著者
- 早瀬 伸子
- 出版者
- 北海道教育大学
- 雑誌
- 情緒障害教育研究紀要 (ISSN:0287914X)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.85-92, 1987-03-15
財団法人ふきのとう文庫は,障害をもつ子どもたちが本の楽しさと出会えるようにと願い,日本で最初の障害をもつ子どもも利用できる私立児童図書館を開設し,絵本を製作し,貸し出しをしているユニークなボランティア団体である。最初に,その設立理念と歴史的経過,活動内容について記述し,今後の発展のための課題をいくつか示した。次に,活動の一つである障害児のための布の絵本の使用実態を調査し,さらに,布の絵本を手指運動機能の発達段階と認知思考機能の発達段階に対応させて分類し,障害児の遊具としての有効性について考察した。障害児の遊具としての布の絵本は,その色や形が,軽度の精神発達遅滞児の興味・関心を誘発し,マジックテープやスナップ・ボタンなどの操作により手指運動機能を向上させ,色・形・数字の認知弁別能力を育成する。
- 著者
- Frank Anders 七邊 信重
- 出版者
- 日本デジタルゲーム学会
- 雑誌
- デジタルゲーム学研究 (ISSN:18820913)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.126-136, 2008
2 0 0 0 波羅夷罪の成立史的考察
- 著者
- 佐々木 閑
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.347-339, 2011
2 0 0 0 OA 生活科における異年齢交流活動の意味 : 幼小連携の視点から
- 著者
- 藤江 康彦
- 出版者
- 関西大学
- 雑誌
- 關西大學文學論集 (ISSN:04214706)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.85-110, 2007-01
2 0 0 0 IR 「つながり」と「交流」 : 幼小連携をめぐる幼稚園と小学校の意識の違いから
- 著者
- a cura di Delfina Giovannozzi e Marco Veneziani
- 出版者
- L. Olschki
- 巻号頁・発行日
- 2008
2 0 0 0 OA 幼小接続期におけるカリキュラムの開発
- 著者
- 善野 八千子
- 出版者
- 奈良文化女子短期大学
- 雑誌
- 紀要 (ISSN:02862867)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.49-67, 2010-11-01
- 著者
- 河崎 道夫 権部 良子 浅田 美知子 藤本 尚 井本 賢治 吉田 京子
- 出版者
- 三重大学
- 雑誌
- 三重大学教育学部附属教育実践総合センター紀要 (ISSN:13466542)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.9-16, 2005-03
- 被引用文献数
- 1
本研究会(幼小連携接続問題研究協議会)は、幼小連携問題について、(1)児童間交流と教員間交流、(2)教育課程の再編、(3)養成課程の改革を三つの課題として取り組んでいる。これまでは(1)全体の取り組みの計画を構造化するとともに、児童間交流の問題を中心とした実践的研究を報告してきた。今回は、(1)3年間にわたり継続的に児童間交流を進めてきた実践の成果と課題を総括すること、(2)2年目となる教育課程の改訂への取り組みの中間報告と今後の展望をまとめた。
2 0 0 0 OA 少年と死 : かれらは無罪か有罪か
- 著者
- 鬼塚 雅子
- 出版者
- 埼玉女子短期大学
- 雑誌
- 埼玉女子短期大学研究紀要 (ISSN:09157484)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.189-217, 1999-03-01
英国の作家Walter de la Mareの3つの短編小説について論じる。3編とも主人公は10歳ぐらいの少年で、孤独な家庭環境の中で育ち、ある日突然、身近な人の死に出会う。少年たちはそれぞれの死-自殺、他殺、事故死-にどう関わっているのか、かれらに罪はあるのかないのか、かれらは死というものをどのようにとらえているのか。こうした疑問点について、少年たちの心理状態を分析しながら考察する。また、なぜde la Mareが幼い子どもを一人で死に直面させたのか、その真意を探る。
- 著者
- 門林 理恵子 西本 一志 角 康之 間瀬 健二
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, pp.980-989, 1999-03-15
- 被引用文献数
- 4
博物館の展示は 学芸員の専門知識や関心の体系的表現であるが ある視点からの構造化の一実現例であり しかも一方的に見学者に提示される. このため 様々な興味や知識を持つ見学者の知的欲求をつねに満たすことは難しい. そこで本論文では 学芸員と見学者を仲介し 博物館展示の意味的関連に基づく構造を見学者ごとに個人化する手法を提案する. 本手法では 展示物などに付与される説明文を キーワードを基に統計処理することで 展示物間の関連に基づく構造を2次元空間に可視化する. まず元の展示の構造を示す展示空間を構成し 次に見学者の興味に基づく興味空間を作る. 最後に両者を融合して個人化空間を作成する. 個人化空間に可視化された展示の構造は 学芸員の視点からの関連を保持しつつ 同時に見学者の視点を反映したものとなる. こうすることにより 既存の 見学者の立場を中心とした個人化手法における 展示が断片化して関連が失われ かえって理解が困難になるという問題を回避することができる. これらの空間を用いることで 同じ展示を見学者ごとに個人化することが可能となる. さらに これらの空間が学芸員へもフィードバックされることにより 学芸員自身が展示についての新たな視点を獲得できるが これは従来の博物館の展示や既存の個人化手法では困難であったものである. 本論文では 本手法の詳細とその実施例 さらに評価についても述べる.Museum exhibitions are thought to be well organized representations of the expert knowledge of curators, but they are just one example of structures of knowledge among many possibilities, given to museum visitors in a one-sided way. Therefore, traditional museum exhibitions can hardly meet the vast requirements of general visitors who possess a variety of interests. In this paper, we propose a method for personalizing the semantic structure of museum exhibitions by mediating curators and visitors. The semantic relations of displays are visualized as a two-dimensional spatial structure based on the viewpoints of the curators and visitors separately, and then together. The structures reflect the interests of the visitors, while maintaining the knowledge of the curators. We disucuss the detail of the method and show an example of personalization. Evaluation results through a subjective experiment is also given.