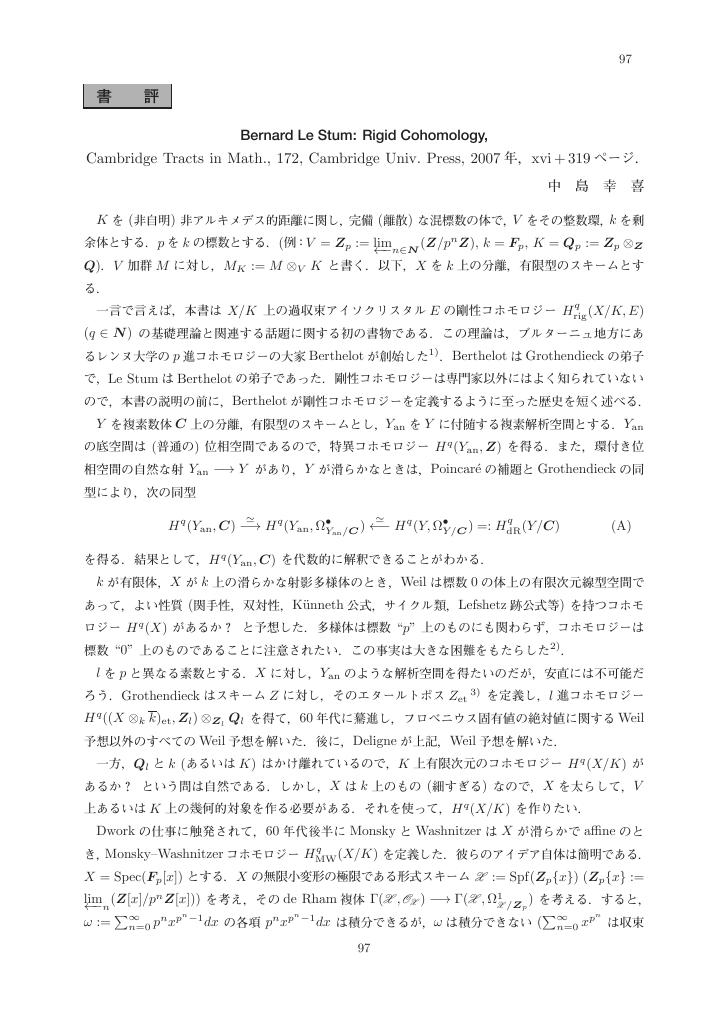- 著者
- 中島 幸喜
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.97-101, 2012-01-26 (Released:2016-07-20)
- 参考文献数
- 10
1 0 0 0 OA “ゾミア”におけるプロテスタント伝道
- 著者
- 福本 勝清
- 出版者
- 明治大学教養論集刊行会
- 雑誌
- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)
- 巻号頁・発行日
- vol.522, pp.37-79, 2017-01-31
1 0 0 0 OA 水素結合(<特集>化学の基本概念)
- 著者
- 坪井 正道
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.5, pp.322-325, 1994-05-20 (Released:2017-07-11)
「はってはがしてまたはれる」これはポスト・イットという付箋紙の宣伝文句であるが, 水素結合は化学の世界でこれに似た挙動にあずかっている。生物が遺伝情報を保存し, 複写し, 発現する過程, われわれの舌が砂糖の甘味を感じるメカニズム, などに多かれ少なかれ水素結合が関与している。水素結合を切るのに必要なエネルギーは20kJ/mole程度にすぎない。これは化学結合の結合エネルギーに比べて圧倒的に低い。たとえば, 水分子H_2OのO-Hを切るエネルギー490kJ/moleの25分の1である。したがってこれは常温で温和な条件下で進行する反応に重要な役割をもつ。以下どんな所にどのような水素結合があるのか当たってみよう。
1 0 0 0 OA 平安貴族衣装の衵 ―男性着用について―
- 著者
- 鹿野 美由紀
- 出版者
- 大妻女子大学人間生活文化研究所
- 雑誌
- 人間生活文化研究 (ISSN:21871930)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, no.25, pp.314-318, 2015-01-01 (Released:2020-03-14)
- 参考文献数
- 1
平安貴族女性の正装である裳唐衣装束は袴,単,袿,表着,唐衣,裳などから構成されている.その中で今回は,袿と衵の着用について着用実態の若干の整理と用例の分析を行った. 袿と衵を辞書で確認すると区別は,袿は裾の長いもので女性用のものとし,衵は裾の短いもので男性や幼童用のものとされている.しかし王朝物語を確認すると,袿の着用者にも男性はおり,同様に衵の着用者にも女性は見られる.また被物として使われることが多く,これは男女ともに贈られていた.また有職故実書で書かれていた説明も矛盾しているものも多く,実際の形状・着用について不明なことが多い.そのことを受けてか,現代の辞典類や注釈書類類の説明も曖昧なところが多くなっている.この研究の目的は,文学作品と古記録における用例の分析を行って,「衵」の着用実態の若干の整理と検討をしていくことである. なお,今回は特に男性の着用について検討を行う.そのため,童と僧侶の着用の用例は除いた.
1 0 0 0 OA 台湾におけるスクーター利用実態調査と普及要因の考察
- 著者
- 高 瑞禎 釜池 光夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.29-38, 2004-05-31 (Released:2017-07-19)
- 参考文献数
- 23
台湾は何故、スクーターが特異に普及していているのであろうか。本研究の目的は、台湾におけるスクーターの利用実態を明らかにし、その要因を考察することにある。はじめに、スクーターの推移に関する文献調査を行い、産業保護政策が大きな影響を与えたことが明らかになった。さらに、使用状況の観察・インタビュー調査を行い、普及要因と思われる項目を整理した。この要因項目をベースに、台湾の代表的都市である高雄市において利用実態調査を実施した。アンケートデータおよび各要因項目間の関係性を分析し、考察を行った。その結果、国民所得の増加、通勤労働者の急増を背景とする人の生活の変化、スクーターの軽便性、経済性などの製品特性、公共交通機関の衰退、約10kmを範囲とする都市の地理条件、温暖な気象など環境要素が主な普及の要因であることがわかった。台湾は、「ひと-もの-環境」に係わる要因の相乗効果から発展、普及したことがあきらかとなった。
1 0 0 0 間接強制の弾力的活用と内在的限界ー独・日・韓の発展的比較法研究ー
本研究は、学術的独自性として、韓国においても紛争解決手段として多用されている間接強制に焦点をあて、日本においてその理論的背景についての分析がなされていない現状から、韓国における間接強制の弾力的活用をめぐる法改正議論について検証をする。あわせて、本研究の創造性として、韓国の理論的状況の対比を通じて日本民事執行法上の間接強制が帯びている独自の可能性について、姉妹法たる韓国法との比較法的見地から理論的・実証的意義を再確認し、ドイツ・日本・韓国の比較民事手続法的考察をし、アジア法からヨーロッパ法への法の環流を促す新たな可能性をみいだす。
- 著者
- 坂口 弘訓 須藤 靖明 沢田 順弘 吉川 慎
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 火山 (ISSN:04534360)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.5, pp.143-149, 2008-10-31 (Released:2017-03-20)
- 参考文献数
- 14
Aso Volcano is one of the active volcanoes in Japan. Seismic wave associated with volcanic activity had been recorded by Wiechert seismograph at Aso Volcanological Laboratory, Kyoto University from 1928 to 2000. Some records of volcanic tremors related to large-scale explosive events had been already analyzed, however, many events were not yet examined. In this study, the previous volcanic activities with explosion are re-examined and classified into the following four types based on the seismographic record: (A) The amplitude of tremor was small prior to an explosion. After the explosion, the amplitude of tremor increased; (B) A phreatic explosion suddenly took place without any precursory signal. The tremor amplitude was less than 3μm before the phreatic explosion, and then decreased to be less than 0.5μm after the explosion; (C) An explosion occurred after decreasing in amplitude of volcanic tremor. After explosion, volcanic activity had been increasing; (D) The volcanic tremor was increasing and changed into continuous tremors. An explosion occurs among continuous tremor. In Nakadake crater, types C and D are major types of volcanic activity after 1963. The above classification could be an important criteria for the prediction of eruption at Aso Volcano.
1 0 0 0 OA 規制緩和と利益団体政治の変容 ―タクシー規制緩和における言説政治―
- 著者
- 秋吉 貴雄
- 出版者
- 日本政治学会
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.2_110-2_133, 2012 (Released:2016-02-24)
- 参考文献数
- 38
This chapter analyzes the change of political strategy of interest groups in the process of deregulation. Since 1980s, in Japan, the problem of government regulation has been argued and deregulation has been done in several industries by government committees under the direct control of Prime Minister. This deregulation has affected the political environment of interest groups. First, according to the change of the style of regulation, the relationship between interest groups and regulatory agencies has changed. Second, the arena of regulatory policymaking has transferred from regulatory agencies to government committee. And we found that these changes have increased the importance of discourse for interest groups, and they have changed their political strategy. To examine these changes, we analyze the process of deregulation and reregulation in taxi industry from the viewpoints of discourse. First, in the process of deregulation, the discourse to claim the merit of competition had the power to persuade the public, and also formed the discursive coalition to promote the reform. Second, in the process of reregulation, the discourse to claim the negative effect of deregulation, especially on the decline of salary of taxi drivers, had changed the problem recognition of public on deregulation, and also could form the another discursive coalition from several actors.
1 0 0 0 OA 比較認知科学は擬人主義とどうつきあうべきか
- 著者
- 後藤 和宏
- 出版者
- 日本動物心理学会
- 雑誌
- 動物心理学研究 (ISSN:09168419)
- 巻号頁・発行日
- pp.62.1.8, (Released:2012-07-06)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 3 1
Anthropomorphim is an enduring controversy in comparative cognition. Some studies in comparative cognition search for human-like behavior as evidence for evolutionary continuity of mental processes as Darwin encouraged. Others eschew interpreting observed behaviors in terms of anthropomorphic mental processes. Even in the former cases, students of comparative cognition often use the predictions by associative learning or reinforcement learning as killjoy explanations to examine the existence of complex cognitive processes shared between humans and other species. In the present paper, I reviewed some of such challenges, including my own, to show how anthropomorphic questions can be studied scientifically. I also reviewed other studies in which the killjoy explanations were inappropriately applied. Misuses of the killjoy explanations are typically revealed by showing human adults behave differently from the experimenters anthropomorphic predictions.
1 0 0 0 OA 従来の「うどん伝来説」の謎 : 武蔵野うどんの視点から
- 著者
- 小島 和男 KOJIMA Kazuo
- 出版者
- 朝日大学大学院経営学研究科
- 雑誌
- 朝日大学大学院経営学研究科紀要 = Bulletin of Graduate School of Business Administration, Asahi University (ISSN:13460544)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.35-40, 2021-03-31
- 著者
- 下畑 享良
- 出版者
- 日本神経治療学会
- 雑誌
- 神経治療学 (ISSN:09168443)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.3-6, 2023 (Released:2023-04-20)
- 参考文献数
- 14
This editorial describes new MDS criteria for multiple system atrophy (MSA). The criteria aim to improve the accuracy of the diagnosis of MSA and to increase diagnostic accuracy in the early stages of the disease leading to increased patient enrollment in clinical trials. The criteria provide detailed definitions of diagnostic findings in a lexicon, which should be reviewed during the interview and diagnosis. The criteria define four levels of diagnostic certainty. The newly created “possible prodromal MSA” is a research category with low specificity, but it is expected to be used to establish future diagnostic biomarkers to catch patients in the earliest stages of the disease.
1 0 0 0 OA 子どもの外見がその子の能力評価に及ぼす影響
- 著者
- 戸田 弘二 芳賀 信太朗 川村 遼 大滝 幸佳 館山 莉奈
- 出版者
- 北海道教育大学
- 雑誌
- 北海道教育大学紀要. 教育科学編 (ISSN:13442554)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.277-289, 2012-02
1 0 0 0 OA ガルカネズマブの投与により登校や運動が再開できた中学生の一例
- 著者
- 田中 敏博
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床薬理学会
- 雑誌
- 日本臨床薬理学会学術総会抄録集 第42回日本臨床薬理学会学術総会 (ISSN:24365580)
- 巻号頁・発行日
- pp.1-LBS-5, 2021 (Released:2022-04-14)
【はじめに】ガルカネズマブ(商品名:エムガルティ)は、片頭痛に関連すると考えられているカルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)に特異的に結合し、CGRPの受容体への結合を阻害するよう設計された新規作用機序のモノクローナル抗体である。片頭痛の予防を適応として2018年9月、米国において承認を取得し、本邦でも2021年4月に発売となった。【症例】15歳男児、中学3年生【既往歴】特記事項なし【家族歴】母、片頭痛【現病歴】以前より天候の影響を受けるなどして頭痛を訴えることがあり、登校できないこともあった。当科を受診し、頭痛対策としてアセトアミノフェンやロキソプロフェン、片頭痛としてバルプロ酸、起立性調節障害としてミドドリン等を順次服用したが、効果を認めなかった。中学3年生になり、春先は登校できていたが梅雨時期に入って状態が悪化。頭痛が続き、登校も運動もできなくなって、精神的な落ち込みが顕著となった。本人および保護者と相談し、ガルカネズマブを投与することとし、7月末に初回の2本を投与した。【経過】投与後数日して頭痛の軽減を自覚した。日々の調子がよくなり、自発的に身体を動かす意欲が出てきて、食欲も増進した。8月末、9月末と1本ずつ投与し、2学期からは登校ができてサッカーの練習にも参加、体育祭にも出場した。【結語】年長児の従来の治療薬に抵抗性の片頭痛に対して、ガルカネズマブの投与は選択肢となり得る。ただし、特に小児における長期的な有効性と安全性の評価に留意していかなくてはならない。
- 著者
- 川中 豪
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アジア経済 (ISSN:00022942)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.11, pp.57-59, 2011-11-15 (Released:2022-09-15)
1 0 0 0 OA 動画を用いた階段昇降に対する介助方法の指導が復学支援に寄与した進行癌対麻痺患児の一例
- 著者
- 深田 亮 浅野 由美 中田 光政 葛田 衣重 水流添 秀行 村田 淳 田口 奈津子
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.6, pp.380-384, 2018 (Released:2018-12-20)
- 参考文献数
- 8
【目的】進行癌に重度の対麻痺を伴った症例に対し,理学療法と動画を用いた介助方法の指導を行い,復学を達成したので報告する。【対象と方法】症例は毎日,中学校に通うことを楽しみにしていた10 代前半の男性。局所再発腫瘍の胸椎浸潤による対麻痺となり,腫瘍部分摘出術が施行された。階段昇降が復学を達成するために重要であったため,中学校の教員宛に動画を用いて介助指導を行った。また,復学を達成するために医療者カンファレンスに加え,教員を交えて復学カンファレンスを実施した。復学後も理学療法士と教員が積極的に情報を共有し学校行事に参加できるように多職種でアドバイスを行った。【結果】教員介助の下,安全に階段昇降を達成し,学校行事にも参加できた。【結語】動画を用いた介助指導,病棟スタッフとのカンファレンスによる目標設定,さらに復学後も教員と情報共有をしたことで,患児の希望に沿った復学を達成できた。
- 著者
- 黒須 俊夫
- 出版者
- 群馬大学社会情報学部
- 雑誌
- 群馬大学社会情報学部研究論集 (ISSN:13468812)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.169-223, 2000-03-31
1 0 0 0 OA 2. 社会的入院を必要とする要介護認定透析患者の医療連携
- 著者
- 前田 兼徳 今田 真里 辻 敏子 林 敏明 前田 由紀
- 出版者
- 一般社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.3, pp.219-222, 2012-03-28 (Released:2012-04-13)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA 表情の筋電図解析による人間の表情反応に関する研究
- 著者
- 小越 康宏 小越 咲子 武澤 友広 三橋 美典
- 出版者
- Japan Society of Kansei Engineering
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)
- 巻号頁・発行日
- pp.TJSKE-D-17-00012, (Released:2018-02-15)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1 5
We have been developing training systems using engineering technologies including voice processing, image processing, and electromyogram measurements, among others, for people with communication difficulties including those with developmental disorders. These training systems are designed to improve their communication skills, and they included voice training for improving the clarity of the voice and emotional expressions, and training in making facial expressions for expressing emotions, among others. Facial expressions play an important role in smooth communication by conveying one's intentions. Moreover, it is necessary to have the skills of synchronizing one's facial expressions with that of others especially when feeling empathy for another person. Skills of synchronizing facial expressions include skills of recognizing others' facial expressions and those of creating one's own facial expressions. We have conducted investigations based on the perspective that when conducting training related to facial expression synchronization it is important to examine abilities for both recognizing and creating facial expressions. This paper describes indices of facial expression synchronization skills developed by us. In an experiment conducted by Otte et al., happy and angry faces were shown to participants as stimuli and they were required to respond with happy or angry faces respectively. It was indicated that the response time differed depending on combinations of facial expressions used in the stimulus and the response. We assessed the response time to an expressionless face as the baseline response time. Then, we defined the effect of generating shorter response times than the baseline when stimulus and response facial expressions were consistent, as a promoting effect, and the effect of generating longer response times when stimulus and response facial expressions were inconsistent, as an inhibitory effect. Furthermore, the time differences from the baseline were defined as indices of the degree of promotion and the degree of inhibition. The results of investigating promoting and inhibitory effects are reported.
1 0 0 0 OA 和歌山大学図書館におけるシバンムシ被害とその対策について
- 著者
- 橋本 唯子 山中 節子 藤井 亜希子
- 出版者
- 国公私立大学図書館協力委員会
- 雑誌
- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, pp.2109, 2021-08-31 (Released:2021-09-16)
平成27年5月に和歌山大学図書館において発生したシバンムシによる虫害について, 発生から緊急対応・燻蒸処理とその後の点検などといった実施項目の概略を示し,以後虫害を防ぐための対策として研修・環境整備・殺虫およびクリーニング作業などを進めてきた経緯を紹介する。成果として職員の意識向上・資料保存環境の改善があげられると同時に, 記録の不足・消毒用エタノールなど必要物品の不足などの課題についてまとめ, 被災時に図書資料をどのように救出すべきか, 意識を共有する意義について言及する。