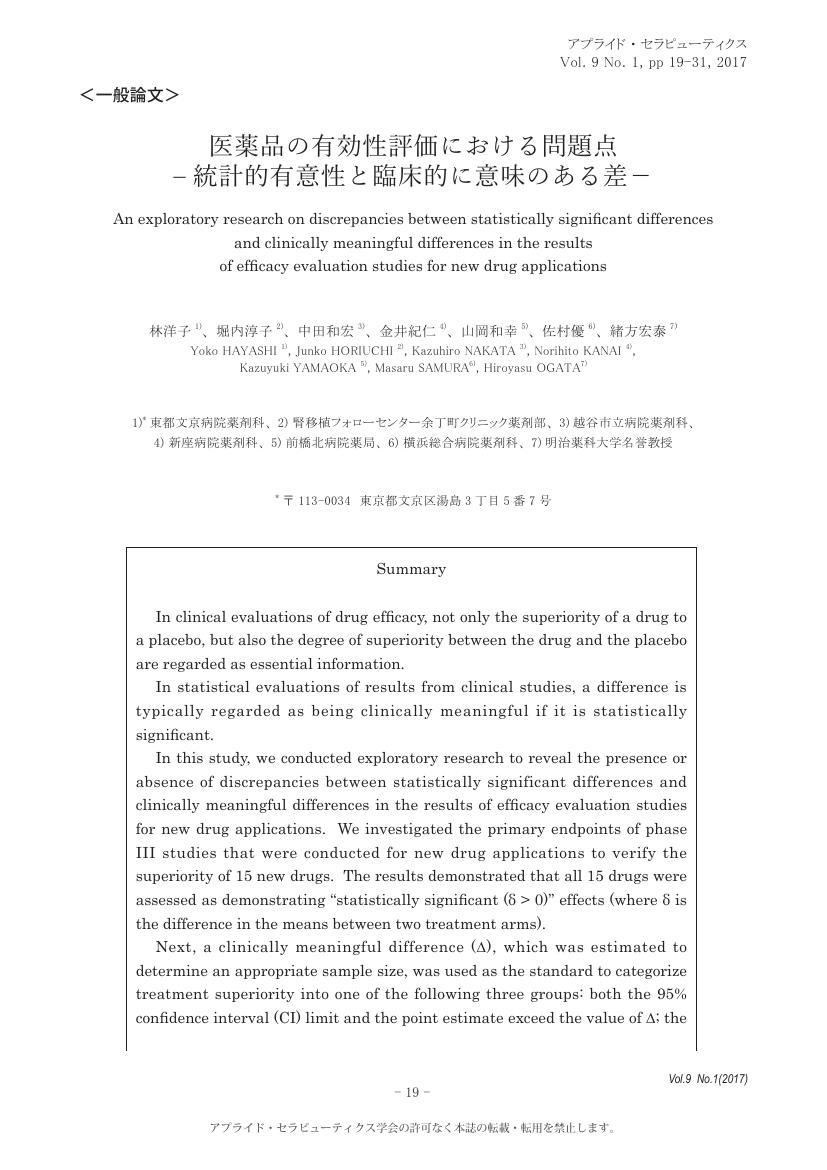- 著者
- 蒲原 聖可
- 出版者
- ファンクショナルフード学会
- 雑誌
- Functional Food Research (ISSN:24323357)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.34-42, 2022-09-12 (Released:2023-01-26)
- 参考文献数
- 22
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策として,ウイルスへの暴露機会を減らす予防策が実践されており,ワクチン接種も進められている.一方,ヒトの側でのウイルス感染への抵抗性を高める対策も重要である.つまり,生体防御機構の維持・亢進による感染防御策,抗炎症や抗凝固といった作用による軽症者の重症化予防である.具体的には,適切な食事あるいはサプリメントの適正使用により,ビタミンやミネラル,その他の機能性食品成分を摂取することがCOVID-19 対策のもう一つの柱となる.これらは,後遺症対策としても重要である.機能性食品成分には,抗ウイルス作用や免疫賦活作用,抗炎症作用などを有する成分が知られており,ウイルス性呼吸器感染症の予防や重症度軽減作用が報告されてきた.すでに,ビタミンC,ビタミンD,亜鉛,クルクミン,コエンザイムQ10(CoQ10),ラクトフェリンなどでは,COVID-19 の罹患リスクや重症化リスクを抑制することが示されている.ワクチン接種による集団免疫獲得などにより,COVID-19 のパンデミックは収束に向かうと期待される.一方,COVID-19 変異株への懸念や,新興感染症の周期的・局地的な流行は,今後も継続 する.したがって,COVID-19 も含めた新興感染症対策として,セルフケアおよび補完療法での機能性食品成分の利活用が重要である.本稿では,COVID-19 の感染予防および重症化予防の視点から,機能性食品成分のエビデンスを概説した.
1 0 0 0 OA 医薬品の有効性評価における問題点 統計的有意性と臨床的に意味のある差
- 出版者
- 日本アプライド・セラピューティクス(実践薬物治療)学会
- 雑誌
- アプライド・セラピューティクス (ISSN:18844278)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.19-31, 2017 (Released:2020-11-30)
1 0 0 0 OA 歯科医師による閉塞性睡眠時無呼吸の早期発見
- 著者
- 對木 悟 幸塚 裕也 福田 竜弥 飯島 毅彦
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本睡眠歯科学会
- 雑誌
- 睡眠口腔医学 (ISSN:21886695)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.25-32, 2023 (Released:2023-03-18)
- 参考文献数
- 26
Some key features including both anatomical (i.e., craniofacial) and non-anatomical factors are involved in the pathogenesis and development of obstructive sleep apnea (OSA). Since craniofacial factors are visible whereas non-anatomical factors routinely require laborious studies and complicated equipment for quantitative evaluation, dentists may be able to detect OSA by understanding the background craniofacial characteristics of OSA. Obese individuals with excessive soft tissue inside the oral cavity do not necessarily develop OSA if the jaw size is large relative to the amount of soft tissue. Conversely, an obese patient is highly likely to have OSA when the jaw size is not sufficiently large relative to the tongue size, a phenomenon called “oropharyngeal crowding.” This review highlights the anatomical balance theory to account for the underlying mechanisms of oropharyngeal crowding in OSA.
- 著者
- 餅原 尚子 松田 英里 成願 めぐみ 久木﨑 利香 有留 香織 永田 純子 坂元 真紀 前原 加奈 松元 理恵子 久留 一郎
- 雑誌
- 鹿児島純心女子大学大学院人間科学研究科紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.44-54, 2007-03-31
災害の体験によって直接の被災者だけでなく,救援者も大きな影響を受ける。海外での先行研究と同じく,わが国の救援者においても心的外傷性ストレス症状(post‐traumatic stress reaction)の割合が高いことが明らかになっている。救援者は災害現場に出場し,被災者と同じような体験をすることによるストレスを受けることになる。一方,職業的救援者であるがゆえに一般的な被災者とは別のストレス(災害出場を忌避できない。彼らには社会的な期待が大きい)に加え,特有の義務感,責任感や弱音を吐きにくい組織的風土が加わる。まして,箝口令が敷かれているとなおさらである。本研究では,消防職員,海上保安官,警察官,救急救命士が直面するCIS(Critical Incident Stress:惨事ストレス), PTSD(Posttraumatic Stress Disorder:外傷後ストレス障害)の現状について分析し,ストレスの特徴を明らかにすることを目的とした。アンケート調査を実施し,そのうち消防職員356名,海上保安官80名,警察官854名,救急救命士200名の有効回答を得ることができた。CISついては,海上保安官や警察官よりも消防職員や救急救命士に高く認められた。さらに,警察官より消防職員や救急救命士が, PTSDの症状を呈しやすいことが明らかになった。
1 0 0 0 OA ヨウ化物イオン光分解による気相ヨウ素生成の各パラメータ依存性の実験的決定
気相ヨウ素分子が大気中に放出されるとヨウ素エアロゾル生成を引き起こす。この気相ヨウ素分子の大気中への生成の新たな過程として,海洋中のヨウ化物イオンの光分解が一つの候補として考えられる。しかし、この生成過程が大気環境に与える影響の評価は未だ行えていない。本研究では,この過程による気相ヨウ素分子生成量の水素イオン指数,溶存酸素量,ヨウ化物イオン濃度など海洋条件における各パラメータ依存性について高感度分光測定法を用いた実験的決定の研究を行った。その結果を用い、この過程が実際の大気環境へ与える影響力についてのモデル計算を行い評価した。
1 0 0 0 OA 超伝導研究の隆盛と今後
- 著者
- 黒木 和彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.6, pp.372-373, 2019-06-05 (Released:2019-10-25)
- 参考文献数
- 2
特別企画「平成の飛跡」 Part 2. 物理学の新展開超伝導研究の隆盛と今後
1 0 0 0 OA 典籤考
- 著者
- 越智 重明
- 出版者
- 東洋史研究会
- 雑誌
- 東洋史研究 (ISSN:03869059)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.6, pp.465-475, 1955-03-30
Some historians are of the opinion that the tien-ch'iens, ministers despatched from the Nan-chao Government were, so to speak, the overlords to the imperial local ministers and that whereby the Government was successful to consolidate a centralized state. But the more detailed study of the contemporary documents makes it clear that the tien-ce'iens' authorities were more limited than ever suggested--that is, their powers were originated from the commission of duty to supervise the local ministers independent directly upon the emperors. and these ministers alone; other ministers were out of the rule of the tien-ch'ien.
- 著者
- Han Soo CHANG Fumiya SANO Takatoshi SORIMACHI
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)
- 巻号頁・発行日
- pp.2022-0330, (Released:2023-07-25)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
Surgery on spinal tumors becomes challenging when the tumor is ventral to the spinal cord. Conventionally, we approach it posteriorly through bilateral laminectomy and rotate the cord after sectioning the dentate ligament and nerve roots. However, manipulating the cord can be hazardous, and a long bilateral laminectomy can be invasive. Meanwhile, a narrow operative field and a limited lateral viewing angle in a unilateral approach constrained the surgeon. To overcome these problems, we previously reported a technique of modified unilateral approach where we incised the skin and the fascia horizontally and placed a pair of retractors longitudinally.The current article reports our experience applying this approach in 15 patients with ventrally located spinal tumors. The approach was performed on 10 schwannomas, 2 meningiomas, and 3 others. We evaluated paraspinal muscle atrophy on postoperative magnetic resonance imaging.The modified unilateral approach provided an excellent surgical field for removing ventrally located tumors. Gross total removal was achieved in 11 patients (92% of benign tumors). No neurological complications occurred except for one case of transient weakness. We encountered no wound-related late complications such as pain or deformity. The reduction of the cross-sectional area of the paraspinal muscles on the approach side (compared to the nonapproach side) was 0.93 (95% confidence interval: 0.72-1.06), indicating 7% atrophy (statistically nonsignificant, p = 0.48).We believe this simple technique can be useful for removing spinal tumors located ventral to the spinal cord.
1 0 0 0 OA 現代インド・英国のカーストとダリト運動をめぐるグローバル化の重層的展開
本研究はグローバル化の趨勢が指摘されるインドにおいて、急速に変貌しつつあるカーストとダリト運動の動態を検討すると同時に、英国のダリト移民にも注目することで、人びとのカースト意識やダリト運動の展開に与える影響を検討した。バールミーキ・コミュニティを事例として、インドで1990年代以降から試みられてきた公益訴訟という手法を活用して自コミュニティの権利や不平等を訴える動きを分析した。さらにバーミンガムのバールミーキ移民に着目し、ライフヒストリー、カースト差別の経験、カースト別の宗教・社会活動を検討することにより、英国のカースト問題や国境を越えた運動のネットワーク形成の可能性と課題を明らかにした。
1 0 0 0 OA 林邑楽に就いて
- 著者
- 津田 左右吉
- 出版者
- 東洋文庫
- 雑誌
- 東洋学報 = The Toyo Gakuho
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.257-272, 1916-05
1 0 0 0 OA 漁協によるサンゴ再生の取り組み〜沖縄県恩納村での事例〜
- 著者
- 比嘉 義視 新里 宙也 座安 佑奈 長田 智史 久保 弘文
- 出版者
- 日本サンゴ礁学会
- 雑誌
- 日本サンゴ礁学会誌 (ISSN:13451421)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.119-128, 2017 (Released:2018-04-20)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 6 8
恩納村漁協では,サンゴ礁保全に積極的に取り組むため,1998年から養殖やサンゴの植え付けにより親サンゴを育て,これら親サンゴが産卵することでサンゴ礁の自然再生を助ける「サンゴの海を育む活動」を行ってきた。この活動の一環として,砂礫底に打ち込んだ鉄筋の上や棚上でサンゴを育成する「サンゴひび建て式養殖」と呼ばれる方法を行っている。養殖しているサンゴは,2017年3月末現在で約24,000群体,養殖している種類は11科15属54種である。サンゴ養殖の効果として,一年間の養殖群体の産卵数が約57億,産卵後2日後の幼生数は約27億が供給されると期待される。また,養殖サンゴに棲み込む魚は,スズメダイ科Pomacentridae魚類を中心として約33種,約67万個体と推定された。養殖しているウスエダミドリイシAcropora tenuis 163群体の遺伝子型を調べたところ,これらは81群体由来であることが判明した。2016年夏季には,高水温により恩納村地先でも大規模な白化現象が見られたが,養殖サンゴの生存率は,養殖場周辺に植付けたサンゴや天然サンゴの生存率と比較して高かった。サンゴひび建て式養殖で大規模にサンゴを育成することは,サンゴ礁再生の一助になるものと期待できる結果となった。
1 0 0 0 OA 使用前自主検査における試験方法の最新動向
- 著者
- 三枝 晃
- 出版者
- 一般社団法人 電気設備学会
- 雑誌
- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.5, pp.331-334, 2015-05-10 (Released:2015-05-13)
- 参考文献数
- 1
1 0 0 0 OA 脳炎脳症の原因究明に役立つショットガンメタゲノム解析
- 著者
- 﨑山 佑介
- 出版者
- 日本神経感染症学会
- 雑誌
- NEUROINFECTION (ISSN:13482718)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.16, 2023 (Released:2023-07-21)
- 参考文献数
- 24
【要旨】次世代シーケンサーを活用したショットガンメタゲノム解析とはサンプル内に含まれる細菌や真菌、ウイルス、原虫などの病原体ゲノムをわずか1 つのアッセイで網羅的に検出できる革新的なゲノム診断技術である。わずかなサンプル量から病原体ゲノムを検出できるため、生検脳や脳脊髄液を対象にした本解析は、脳炎や髄膜炎の感染症スクリーニングとして役立つ。一方で、高コストであり、偽陽性や偽陰性の問題もある。
1 0 0 0 OA 専業非常勤講師という問題 ―大学教員の非正規化の進展とその影響―
- 著者
- 上林 陽治
- 出版者
- 社会政策学会
- 雑誌
- 社会政策 (ISSN:18831850)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.73-84, 2021-03-30 (Released:2023-03-30)
- 参考文献数
- 18
大学の非常勤講師のみで生計を立てるいわゆる専業非常勤講師は,1995年を境に大学教員における割合を高め,1998年には4万5370人(延べ数)だったものが2016年には9万3145人(延べ数)へと倍増し大学教員の3分の1を占めるに至った。これら専業非常勤講師は,週8コマ程度を受け持たない限り,年収300万円にも届かない高学歴ワーキングプアである。 増大の原因は,1991年から始まった大学院重点化計画による博士課程修了者の増加に見合う正規教員等の職が用意されなかったことにあるが,この問題が放置されたのは,正規「専務教員」が大学院重点化政策の過程で大学院へと移行し,少なくなった学士課程の「専務教員」の隙間を埋めるべく高学歴ワーキングプア層の専業非常勤講師が活用されていったことである。 すなわち大学経営は1990年代以降に政策的に生み出された高学歴ワーキングプアの専業非常勤講師を活用することで成り立っているのである。
1 0 0 0 OA 北海道立北方民族博物館が所蔵する池上二良氏の調査・研究ノート(引照付きリスト)
- 著者
- 山田 祥子
- 出版者
- 北海道立北方民族博物館
- 雑誌
- 北海道立北方民族博物館研究紀要 (ISSN:09183159)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.085-115, 2022-03-25 (Released:2022-07-01)
Prof. IKEGAMI Jirō (Professor Emeritus, Hokkaido University; 1920-2011) is a linguist who conducted extensive studies on northern languages from the 1940s to the 2000s. He made remarkable contributions especially to the study of the Tungusic languages. Many of his published works are descriptive studies on Manchu and Uilta (formerly known as Orok) among the Tungusic languages. Hokkaido Museum of Northern Peoples has a collection of Prof. IKEGAMI's former library materials, donated by his bereaved family. This collection is called Ikegami Bunko. The present article provides a list of all 158 notebooks in the Ikegami Bunko that he used in his research and studies. In cases where the contents are related to Prof. IKEGAMI's publications, the references have been added so that they can be checked against them. This is the first step in making the contents of Prof. IKEGAMI's notebooks widely known, and it aims to provide clues for those who are interested to access the notebooks in future. It is hoped that further information will be added through future research and studies.
1 0 0 0 自動改札データを活用した鉄道利用者の通勤行動の変化の実態把握
- 著者
- 橋本 真基 日比野 直彦 森地 茂
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.7, pp.22-00182, 2023 (Released:2023-07-20)
- 参考文献数
- 19
働き方改革の推進,新型コロナウイルス感染症拡大を背景に,テレワークが急速に進展し,通勤行動が大きく変化した.この行動変化を把握することは,今後の鉄道サービスを検討する上では重要であるものの,実行動に基づく定量的な分析は少なく,実態が明らかにされていない.そこで,本研究では,筆者らの先行研究を踏まえ,自動改札データを用い,鉄道利用者の通勤行動の変化を分析する.コロナの影響により,対象路線をほぼ毎日利用していた約86万人のうち,約8万人が在宅テレワークに,約8万人が利用頻度を大きく減少させたことを明らかにした.また,OD別の変化,通勤頻度と定期券利用の関係,性・年齢階層別の変化,出発時間帯の変化,定期券保有と立ち寄り行動との関係等についても定量的に明らかにしている.
1 0 0 0 OA 上部消化管内視鏡後の耳下腺部・頸部の腫脹について
- 著者
- 白井 保之 木下 善博 幸本 達矢 川野 道隆 中村 綾子 大石 俊之 原田 克則 吉田 智治
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.10, pp.2293-2297, 2020 (Released:2020-10-20)
- 参考文献数
- 11
上部消化管内視鏡検査後に両側または片側の耳下腺部から頸部の腫脹が認められることがまれにある.われわれが経験した7例は1例が両側性,6例は左側の発症であった.いずれも経口内視鏡後の発症で,6例は無鎮静であり,DBERCP(Double balloon ERCP)後の1例は鎮静下での内視鏡であった.2例は以前にも同様の腫脹の経験があった.6例は疼痛なく,1例は腫脹部の軽度の疼痛があった.6例は約1時間で改善したが,1例は消失まで半日程度かかった.単純X線検査を施行した2例で空気の貯留は見られず,CTを施行した1例より耳下腺部の腫脹と診断した.上部消化管内視鏡後に一過性に起こる耳下腺部・頸部の腫脹自体は無害であり自然に改善するが,本疾患の知識は内視鏡医にとって重要であると考え報告する.
1 0 0 0 『土佐日記』を対象とする「用」と「美」の風景の関係性に関する研究
- 著者
- 神山 藍
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.7, pp.22-00070, 2023 (Released:2023-07-20)
- 参考文献数
- 58
本研究では『土佐日記』を対象として,楫取が航海のために捉える風景を用の風景とし,紀貫之が和歌を詠むために捉える風景を美の風景として,それぞれの風景に対する認識を探り,用の風景と美の風景の関係性を探った.その結果,用と美の風景は,ほぼ同時に同空間の環境下であっても確認できるが,有する知識によって異なる風景として認識される.この時,一方が他方を認識することは難しい関係にあり,美的な立場から用の風景を捉える場合,多くの用の風景が見過されることが指摘できる.また,美の風景として享受されても,その本来の姿や意味とは異なって表現されることがあるという事実は,美的な立場から用の風景を辿ることの難しさを示すと言える.
1 0 0 0 OA ABSの迷路から抜け出す方法:アクセスと利益配分の遵守を成功させた3つのケース
- 著者
- Ballarin Francesco Lola Alyssa Marie Irawan Ardika Dani Chouangthavy Bounsanong 菊地 波輝
- 出版者
- Entomological Society of Japan
- 雑誌
- 昆蟲.ニューシリーズ (ISSN:13438794)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.149-156, 2023-06-25 (Released:2023-06-28)
- 参考文献数
- 6
Nearly a decade after its entry into force, the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing (ABS) continues to pose challenges for academics. The diversity of local regulations and the complexity of procedures can make it difficult for researchers to understand how to properly comply with the protocol when working with samples collected in signatory countries. To address this issue, the ABS Support Team at the Makino Herbarium, Tokyo Metropolitan University aims to assist Japanese researchers in navigating ABS procedures during their studies. In this article, we present three cases of successful ABS compliance involving animal and plant samples from strictly regulated countries in Southeast Asia. For each example, we provide detailed information on the procedures followed, the required documents, and the government ministries and departments involved. These examples serve as practical guidance for researchers, helping them better understand the structure and complexity of the ABS procedures and providing advice on how to successfully navigate them.