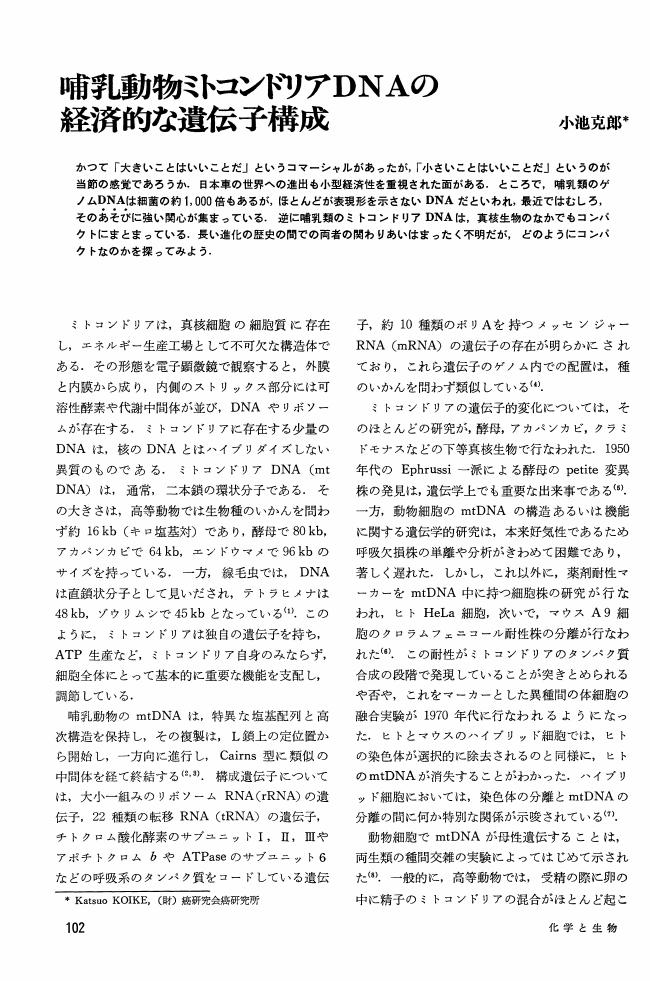- 著者
- Minkyeong Kim Tae Young Lee Byeong Seong Kang Woon Jung Kwon Soyeoun Lim Gyeong Min Park Minseo Bang
- 出版者
- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine
- 雑誌
- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)
- 巻号頁・発行日
- pp.mp.2022-0144, (Released:2023-05-13)
- 参考文献数
- 29
Purpose: Although diffusion-weighted imaging (DWI) with ultra-high b-values is reported to be advantageous in the detection of some tumors, its applicability is not yet known in biliary malignancy. Therefore, this study aimed to evaluate the impact of measured b = 1400 s/mm2 (M1400) and calculated b = 1400 s/mm2 (C1400) DWI on image quality and quality of lesion discernibility using a modern 3T MR system compared to conventional b = 800 s/mm2 DWI (M800).Methods: We evaluated 56 patients who had pathologically proven biliary malignancy. All the patients underwent preoperative or baseline 3T MRI using DWI (b = 50, 400, 800, and 1400 s/mm2). The calculated DWI was obtained using a conventional DWI set (b = 50, 400, and 800). The tumor-to-bile contrast ratio (CR) and tumor SNR were compared between the different DWI images. Likert scores were given on a 5-point scale to assess the overall image quality, overall artifacts, ghost artifacts, misregistration artifacts, margin sharpness, and lesion discernibility. Repeated-measures analysis of variance with post hoc analyses was used for statistical evaluations.Results: The CR of the tumor-to-bile was significantly higher in both M1400 and C1400 than in M800 (Pa < 0.01). SNRs were significantly higher in M800, followed by C1400 and M1400 (Pa < 0.01). Lesion discernibility was significantly improved for M1400, followed by C1400 and M800 for both readers (Pa < 0.01).Conclusion: Using a 3T MRI, both measured and calculated DWI with an ultra-high b-value offer superior lesion discernibility for biliary malignancy compared to the conventional DWI.
1 0 0 0 OA 小笠原諸島の土壌動物相の研究(2015年調査)
- 著者
- 島野 智之 蛭田 眞平 富川 光 布村 昇 寺山 守 平野 幸彦 馬場 友希 西川 勝 鶴崎 展巨 佐藤 英文
- 出版者
- 首都大学東京小笠原研究委員会
- 雑誌
- 小笠原研究年報 (ISSN:03879844)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.137-144, 2018-07-31
小笠原諸島のうち、弟島3地点、父島8地点、母島6地点、合計17地点から、192個体あまりの土壌節足動物が得られた。同定の結果37種と判別され、このうち、学名が確定したりあるいは未記載種でも種レベルで同定が行われたりしたものは、26種であった。特筆すべきは、グンバイウデカニムシCheilidium aokii Sato, 1984の2例目の記録、アシジロヒラフシアリTechnomyrmex brunneus Forel, 1895の弟島からの初記録、また、アサヒヒメグモEuryopis perpusilla Ono, 2011も母島初記録であった。外来種であるホソワラジムシPorcellionides pruinosus(Brandt, 1833)は、父島と母島から見いだされた。
1 0 0 0 OA 哺乳動物ミトコンドリアDNAの経済的な遺伝子構成
- 著者
- 小池 克郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.102-113, 1983-02-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 26
1 0 0 0 OA 断層を横切るシールドトンネルの断面方向の地震応答特性
- 著者
- 大保 直人 古谷 俊 高松 健
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 地震工学研究発表会講演論文集 (ISSN:18848435)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.609-612, 1999 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 6
地形・地盤急変部を横切る地下構造物の地震時挙動の解明は、地下構造物の耐震設計にいて重要な課題である。近年、シールドトンネルが断層を横断して施工される事例も多くなり、耐震設計を行う上で地震時挙動の把握の必要性が議論されつつある。本論文では、武山断層を欄新して施工された共同溝 (シールドトンネル) のトンネル軸方向で観測された地震波と解析結果の報告に引き続き、トンネル断面方向の地震波の解析と解析モデルを作成し、断層から10m-20m離れた位置でのトンネル断面方向の地震時挙動を解明、さらにトンネル断面方向の応答性状を明らかにした。
1 0 0 0 OA 3次元弾性波動論に基づいた山岳トンネルの地震被害メカニズムに関する考察
- 著者
- 保田 尚俊 塚田 和彦 朝倉 俊弘
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集F1(トンネル工学) (ISSN:21856575)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.1-14, 2014 (Released:2014-01-20)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1 1
山岳トンネルの地震被害メカニズムを理解するための基礎として,調和振動の平面波がトンネル軸に対して斜めに入射した場合の円形トンネルの変形挙動を3次元弾性波動論に基づいて解析した.地震波で想定される周波数範囲では,トンネル横断方向の挙動は地盤と覆工の相対的な剛性の比で決まり,入射波の波長の影響をほとんど受けないが,トンネル縦断方向の挙動は剛性比に加え,入射波のトンネル軸方向に生じる見かけの波長の影響を受ける.そのため,トンネル横断面内に変位成分を持つS波だけでなく,トンネル軸を含む縦断面内に変位成分を持つS波でも被害が生じる可能性があることが明らかとなった.また,実際の被害においてもトンネル軸を含む縦断面内に変位成分を持つS波が被害要因の一つと考えられる事例のあることが確認された.
1 0 0 0 OA 危険なデータマイニング —リターン予測とオーバーフィッティング—
- 著者
- 内山 朋規 瀧澤 秀明 菊川 匡
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, no.BI-008, pp.11, 2018-01-20 (Released:2022-02-25)
資産価格のプレミアム(期待リターン)は時系列に変動し,リターンが予測可能であることは現在のファイナンスにおける標準的な考え方である.実務においては投資パフォーマンスの向上のために,学術研究においてはプレミアムの特徴を解明するために,ファクター(予測変数)によってリターンを予測する分析が精力的に行われてきた.しかし,統計的にこれを検出することは容易でないため,より有意な実証的証拠を得ようとデータマイニングを行うと,実際には無意味であるにもかかわらず有意に見えてしまうというオーバーフィッティング(過剰適合)を引き起こす.特に近年では,ビッグデータとして多様なデータを低コストで扱えるようになり,また,工学的な側面から機械学習への注目度が増している.これらは予測精度の向上に貢献する可能性がある一方で,オーバーフィッティングの可能性をより高めてしまう. オーバーフィッティングは,予測対象の標本数が有限であるにもかかわらず,変数選択に自由度があることから生じる.通常の単一検定の基準ではなく,多重検定であることを考慮して有意性を評価する必要がある.従来の資産価格理論の実証では,この影響が軽視されてきた.本研究では,変数選択の自由度だけでなく,モデル選択の自由度,言い換えれば,モデルマイニングの問題も含めて扱う.この結果,時系列におけるリターンの予測可能性を対象に,オーバーフィッティングの影響が大きいことを実証的に示す.変数選択やモデル選択に伴う多重検定を考慮すると,t値の分布は大幅に上方にシフトし,有意水準の臨界値は極めて高くなる.本研究の結果は,ファイナンスの学術的枠組みにオーバーフィッティングの問題を体系的に取り込む必要があることを示唆している.
- 著者
- 佐々木 享
- 出版者
- 日本産業教育学会
- 雑誌
- 産業教育学研究 (ISSN:13405926)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.20-26, 2000-07-31 (Released:2017-07-18)
- 著者
- 森脇 由美子 Moriwaki Yumiko
- 出版者
- 三重大学人文学部文化学科
- 雑誌
- 人文論叢 : 三重大学人文学部文化学科研究紀要 = Jinbun Ronso: Bulletin of the Faculty of Humanities, Law and Economics (ISSN:02897253)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.65-73, 2021-03-31
19世紀にアメリカで大流行した大衆芸能ブラックフェイス・ミンストレルは、音楽、ダンス、寸劇の要素が合わさっていることから、文学、音楽やダンス研究、歴史学と多方面から研究が行われている。ブラックフェイス・ミンストレルに見られる黒人文化の借用や差別的内容、その影響力などは多くの研究者の関心を集めてきた。とりわけ1990 年代以降は、ホワイトネスの研究者たちが移民労働者たちの「白人性」の構築過程を探るための手掛かりとしてこれを取り上げたため、その人種意識が国民化や国民文化などと結びつけて論じられることが多かった。しかし近年では、このようなナショナル・ヒストリーを超え、大西洋史的視座から捉える研究も見られるようになった。これまでの研究を振り返るとともに最新の研究を紹介し、ブラックフェイス・ミンストレル研究の今後の方向性を展望する。
1 0 0 0 OA 教育と福祉の連携――ポスト成長時代の社会構想とケア――
- 著者
- 広井 良典
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.4, pp.102-105, 2018-02-28 (Released:2018-06-22)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA デザイン思考に関する研究の変遷 ─ネットワーク分析を用いた文献研究
- 著者
- 長尾 幸郎 大井 美喜江
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.3, pp.3_41-3_50, 2023-01-31 (Released:2023-02-15)
- 参考文献数
- 27
研究目的は、デザイン思考(Design Thinking)に関して学術分野でこれまでどのような研究テーマが展開されてきたかの変遷を時系列で分析し、全体像を捉えることにある。Web of Scienceに収録された学術論文の書誌情報を対象に、ネットワーク分析を用いてクラスタリングを行い、1,986本の論文から16のクラスターおよび各クラスターの中心論文を特定しながら考察を深めた。論文は3分野に分かれる。第一は理論体系化研究である。1991年から2003年までの主要な研究は工業デザインのデザインプロセスに関する理論研究であった。その後も研究が継続的に行われ今日ではデザイン思考によるプロジェクトの評価についての研究もおこなわれるようになってきている。第二に、教育分野への活用を試みる研究が2004年から始まった。2015年以降はより幅広い分野で創造性を育むためにデザイン思考の研究が活発に行われている。第三に、ビジネス分野への活用が2004年から始まり、様々な業種での研究が拡がり最も論文数の多い分野となっている。今日では組織研究、医療業界関連の研究が急増し、サステナビリティ、政策立案へ適用する動きも論文数はまだ少ないが徐々に増加してきている。
- 著者
- Sanyu Ge Ling Zha Tomotaka Sobue Tetsuhisa Kitamura Junko Ishihara Motoki Iwasaki Manami Inoue Taiki Yamaji Shoichiro Tsugane Norie Sawada
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- pp.JE20220235, (Released:2023-05-06)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 1
Background: Many epidemiological studies have investigated dietary intake of antioxidant vitamins in relation to prostate cancer risk in Western countries, but the results are inconsistent. However, few studies have reported this relationship in Asian countries.Methods: We investigated the association between intake of vitamins, including lycopene, α-carotene, β-carotene, vitamin C, vitamin E, with prostate cancer risk in the Japan Public Health Center-based Prospective (JPHC) study. 40,720 men without history of cancer finished the food frequency questionnaire (FFQ) and were included in the study. Hazard ratios (HRs) and 95% confidence intervals (CIs) of prostate cancer risk were calculated according to the quintiles of energy-adjusted intake of vitamins using Cox models.Results: After an average of 15.2 years (617,599 person-years in total) of follow-up, 1,386 cases of prostate cancer were identified, including 944 localized cases and 340 advanced cases. No associations were observed in consumption of antioxidant vitamins, including α-carotene, β-carotene, vitamin C, and vitamin E, and prostate cancer risk. Although higher lycopene intake was associated with increased risk of prostate cancer (HR for the highest versus the lowest, 1.24; 95% CI, 1.04–1.47; P for trend=0.01), there was a null association of lycopene intake with risk of prostate cancer detected by subjective symptoms (HR, 1.12; 95% CI, 0.79–1.58; P for trend=0.11).Conclusions: Our study suggested no association between antioxidant intake of vitamins and prostate cancer risk.
1 0 0 0 OA 前期高齢者が骨粗鬆症治療を継続した要因
- 著者
- 松井 宏樹 平田 弘美
- 出版者
- 日本健康医学会
- 雑誌
- 日本健康医学会雑誌 (ISSN:13430025)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.4, pp.414-422, 2023-01-30 (Released:2023-05-01)
- 参考文献数
- 19
本研究は,前期高齢者が骨粗鬆症治療を継続した要因を明らかにすることを目的とし,骨粗鬆症治療を1年以上継続している前期高齢者を対象に,「今までどのように骨粗鬆症治療を継続してきたのか」について半構造化インタビューを行い,質的記述的に分析を行った。その結果,前期高齢者が骨粗鬆症治療を継続した要因として,『骨粗鬆症に伴う問題を自分にも降りかかることとして認識する』,『骨折予防に対する意識の高まり』,『独自の方法で治療を工夫する』,『骨粗鬆症治療に対する前向きな気持ち』,『自分なりの目標を持つ』,『周囲の人による支え』が抽出された。前期高齢者が骨粗鬆症治療を継続するために看護師ができる支援として,骨粗鬆症患者が気軽に相談できるような働きかけを行うこと,骨粗鬆症による合併症や日常生活への影響を患者がイメージできるように支援すること,治療開始から半年以上経過した患者に対しては特に,治療効果を自覚できるように支援することが必要であると考えられた。
1 0 0 0 OA 脳卒中既往者における主観的疲労の有訴率
- 著者
- 原田 和宏 齋藤 圭介 津田 陽一郎 井上 優 佐藤 ゆかり 香川 幸次郎
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.34 Suppl. No.2 (第42回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.B0742, 2007 (Released:2007-05-09)
【目的】中枢神経疾患に伴う易疲労(rapid fatigability)は臨床的に重要な症候であり、客観的評価と併せて主観的疲労の程度と質についても検討がなされている。脳血管障害(以下、脳卒中)既往者も疲労に悩まされることは理解されており、国外のレビューでは疲労の有訴率が発症1年前後から3~4割になり、機能的な予後に悪影響を及ぼすと指摘されている。有訴率の算出はうつ気分の者を除外した対象を用いて行われ、脳卒中既往者は対照群の2倍以上の有訴率となることが報告されている。脳卒中後の中枢性疲労や末梢性疲労に関する研究の中で、本邦では主観的疲労の実態資料が依然少ない。本研究は、脳卒中既往者における主観的疲労の実態を把握するために、地域高齢者の調査結果を基に疲労の有訴率について検討することを目的とした。【方法】調査対象は中国地方にある1町の住民で入院・入所中を除く65歳以上の在宅高齢者全員2,212名であった。調査は心身機能や活動状況を内容とし、2005年12月に留置方式で行った。当該調査は岡山県立大学倫理委員会にて了承され、対象には同意を得た。回収された1,864票から基本属性、ADL状況、関連質問の有効回答が確認できた者のうち、いつもうつ気分であるとした者を除外した1,229名を集計対象とした。主観的疲労はスエーデン脳卒中登録Risk-Strokeに従い、「日頃、しんどいと感じますか(4件法)」等で評価した。脳卒中既往者は「脳卒中既往の有無」と「加療中の病気」の質問から選定した。有訴率はクロス集計一元表にて求め、統計処理は多項確率の同時信頼区間に従い95%信頼区間(以下、95%CI)を推定後、脳卒中既往者以外の者と比較した。また脳卒中既往者において主観的疲労との関連変数を検討した。【結果】脳卒中既往者として選定できた者は51名(男性78.4%)で平均76.5歳、対照群と仮定したそれ以外の者は1,178名(同40.6%)で平均74.9歳であった。ADL状況では要介助者は脳卒中既往者の35.2%、対照群の11.8%であった。疲労の有訴率は脳卒中既往者が37.3%(95%CI: 22.0-53.4)で、対照群の16.0%(同: 13.6-18.5)と比し2.3倍高く、統計的に割合の差が認められた。脳卒中後にそれまでよりも早く疲れを感じるようになったとする回答者は67.4%(同: 48.4-81.9)であった。脳卒中既往者の主観的疲労と属性・ADLとの関連は認めなかった。【考察】今回は高齢者に限定された資料であったが、脳卒中既往者の疲労の特徴は有訴率において北欧での地域ベースの調査結果と類似し、対照群の2倍以上で、その程度は属性等との関連が少ないという知見に整合した。この結果から脳卒中後の易疲労は看過できないことが再認識され、障害の評価として重要でないかと考えられた。
- 著者
- Yuki MORI Tomokazu HOKADA Tomoharu MIYAMOTO Takeshi IKEDA
- 出版者
- Japan Association of Mineralogical Sciences
- 雑誌
- Journal of Mineralogical and Petrological Sciences (ISSN:13456296)
- 巻号頁・発行日
- pp.221124, (Released:2023-05-15)
- 被引用文献数
- 2
We determined the metamorphic age and pressure–temperature conditions recorded in a sillimanite-garnet-bearing pelitic gneiss from Niban-nishi Rock, which is part of Niban Rock, on the Prince Olav Coast, eastern Dronning Maud Land, East Antarctica. Niban-nishi Rock is recognized as a component of the Lützow-Holm Complex (LHC), which is characterized by metamorphic age of 600–520 Ma and metamorphic grade of amphibolite to granulite facies. Electron microprobe U–Th–Pb monazite dating of the examined gneiss revealed that, unlike the typical exposures of the LHC, Niban-nishi Rock experienced Tonian metamorphism at 940.1 ± 9.8 Ma (2σ level), and is thus more similar to the neighboring exposures of Cape Hinode and Akebono Rock. Small numbers of younger monazite ages of 827–531 Ma were also detected, and some of which might relate to the metamorphism of the LHC. Phase equilibrium modeling and geothermobarometry indicate metamorphic conditions of 690–730 °C/0.38–0.68 GPa and 620–670 °C/0.42–0.60 GPa for peak and retrograde stages, respectively. The obtained peak temperature is lower than that of typical exposures in transitional- and granulite-facies zones of the LHC, such as Akarui Point and Skallen. Metamorphic features of Niban-nishi Rock, such as the upper amphibolite-facies condition and occurrences of garnet with retrograde zoning and sillimanite in the matrix, differ from those of Cape Hinode and Akebono Rock, with the former belonging to granulite facies and the latter showing kyanite in the matrix and garnet with growth zoning. Investigating Niban-nishi Rock is key in revealing the tectonic relation between the LHC and Cape Hinode (the Hinode Block). Further field surveys are required to reveal the metamorphic variations and the relations among exposures on the Prince Olav Coast.
- 著者
- Koichi SAKAI
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences (ISSN:09168508)
- 巻号頁・発行日
- vol.E103-A, no.1, pp.226-230, 2020-01-01
- 被引用文献数
- 8
Promoting the use of public transport (PT) is considered to be an effective way to reduce the number of passenger cars. The concept of Mobility-as-a-Service (MaaS), which began in Europe and is now spreading rapidly around the world, is expected to help to improve the convenience of PT on the viewpoint of users, using the latest information communication technology and Internet of Things technologies. This paper outlines the concept of MaaS in Europe and the efforts made at the policy level. It also focuses on the development of MaaS from the viewpoint of promoting the use of PT in Japan.
1 0 0 0 OA 飲酒後の吸収相における呼気中アルコール動態モデルの検討
飲酒実験では、呼気採取直後では口腔内等に残留するアルコール(Alc)が多いが、時間経過にしたがって吸収過程に伴って上昇した循環中(血中)Alcが呼気中へ排泄される分が増加するため、呼気中Alc濃度(BrAC)は指数関数的に減少した後、10~20分程度の時点で増加に転じる挙動を示した。一方、洗口実験では、BrACは採取直後から指数関数的に減少して10~20分程度で十分に低下した。両実験のBrAC値の差をとった曲線は、血中Alc動態における吸収相を考慮したモデル式に合うと考えられた。今後も引き続きデータの集積を継続し、完了次第、ALDH2遺伝子型を考慮した動態モデルの検討を行う予定である。
1 0 0 0 OA 脳科学で観る演劇の「もう一つの舞台」
- 著者
- 田中 昌司
- 出版者
- 日本演劇学会
- 雑誌
- 演劇学論集 日本演劇学会紀要 (ISSN:13482815)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, pp.21-40, 2022-06-15 (Released:2022-06-22)
1 0 0 0 OA ヴィクトリア朝期に於ける衣服の色と顔色をめぐる諸問題
- 著者
- 坂井 妙子
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.19-24, 2009 (Released:2011-05-25)
- 参考文献数
- 29
In this essay, I explore the reasons why Victorian women anxiously wanted their garments to be "suitable for their complexions." In the Victorian period, "good complexions" not only meant fair skin that was fine in texture, they also signified the purity, fineness, and gaiety of the women to whom they belonged. In other words, good complexions were vouchers for good characters. This judgment was sanctified by the popular belief that good complexions were "a gift of Nature," and therefore a true exposure of one's purity in mind. The same belief demoralized people having different complexions. Reddened and flushed faces, blotches, freckles, even tiny black spots and oily skin were categorized as bad complexions. Such dichotomy idealized fair skin, while unreasonably denunciated all other types. Furthermore, women with bad complexions were labeled as immoral, because it was firmly believed that bad complexions were the result of indulgence, intemperateness, and vanity. They were stamped on the face as indelible badges of such sins. Cosmetics were also severely criticized, since they were incompatible with the ideal of "a gift of Nature." Under social and moral pressures, women had to find a means to improve their complexions. One of only a few socially acceptable options was to select the right colors for their garments.