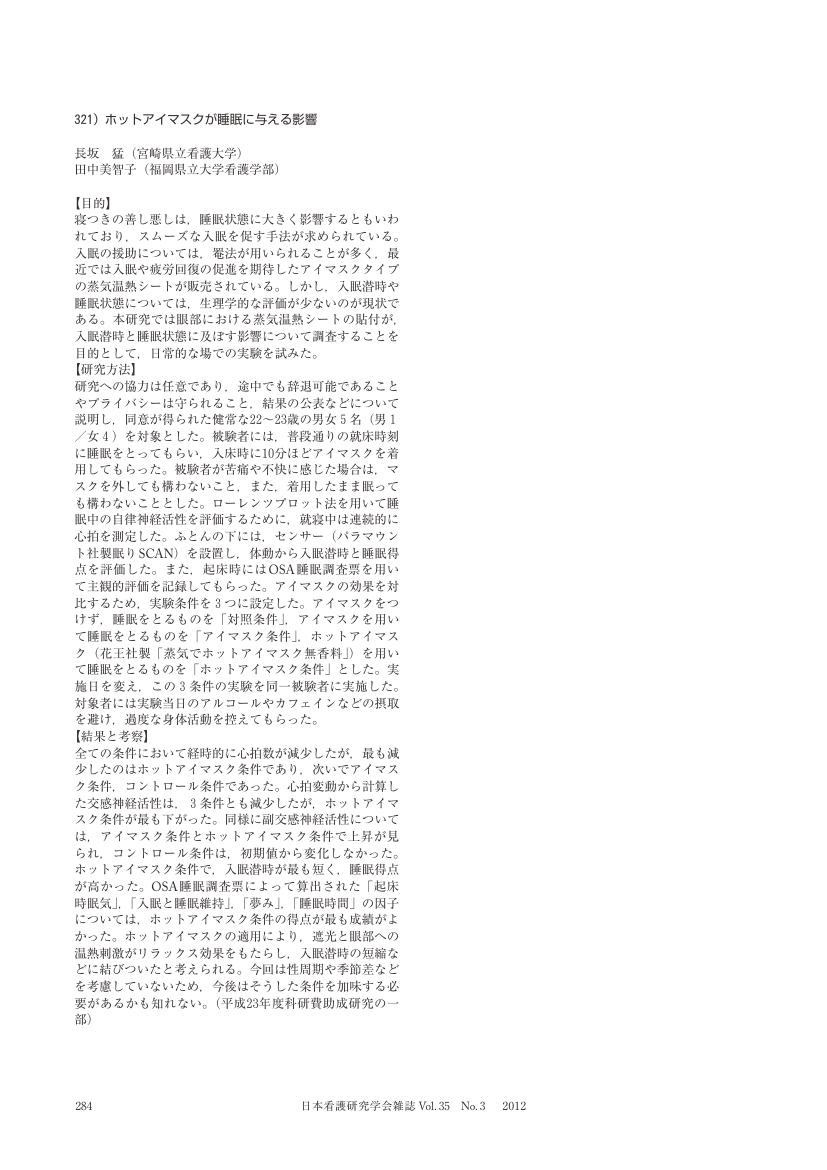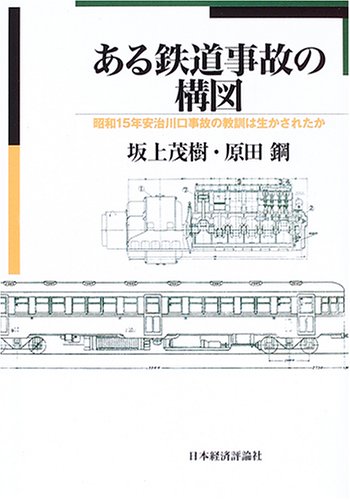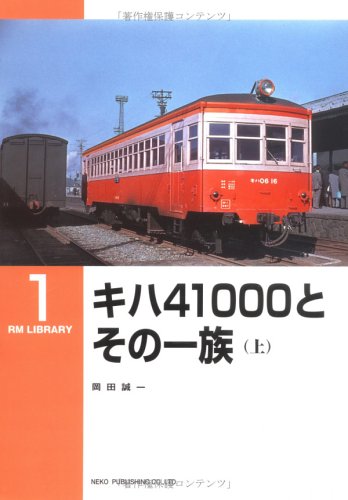1 0 0 0 OA 総説 ダンス/ムーブメント・セラピーによるストレスケア効果の可能性
- 著者
- 渡辺 明日香
- 出版者
- 北海道大学大学院
- 雑誌
- 北海道大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13457543)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, pp.207-220, 2003-02
1 0 0 0 OA 大都市の「草の根保守」は変わったのか ―「大阪維新の会」の地域政治の社会学―
- 著者
- 丸山 真央
- 出版者
- 関西社会学会
- 雑誌
- フォーラム現代社会学 (ISSN:13474057)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.52-65, 2021 (Released:2022-07-08)
- 参考文献数
- 32
本稿では、2010年代を通じて大阪府・市政で大きな影響力をもった「大阪維新の会」を素材に、2010年代の地方政治の構造変化の一端を明らかにする。戦後日本の保守政治の支持基盤のひとつに、都市部では町内会があり、自営業者層を中心に担われるさまは「草の根保守主義」と呼ばれてきた。町内会をはじめ、かつて政治的に力をもった中間集団は、政党にせよ政治家後援会にせよ、近年、凝集力の低下が指摘されている。のみならず、ポピュリズム研究で指摘されるように、ポピュリスト政治家は、こうした中間集団を回避して、マス・メディアやソーシャル・メディアを活用して有権者から直接支持を調達する政治コミュニケーションを展開している。維新の大阪市政でも、既存の町内会が「政治マシーン」と批判され、補助金制度の改革や新たな地域住民組織の設立が進められた。我々の調査によると、そうした地域住民組織政策のもとで、これまで「草の根保守」層の中核を形成してきた町内会の担い手層の一部が、維新支持者に鞍替えしつつある。しかしそれはまだ多数でなく、またその支持も必ずしも堅いものではない。維新は、中間集団に統合されない流動的な無組織層の支持を獲得する一方で、既成の保守政党を支えてきた固定層である「草の根保守」の制度的基盤を破壊して、「中抜きの構造」と呼ばれるような地方政治の新たな構造を生みだしてきた。2010年代の地方政治は、そうした新たな構造の上で展開してきたといえるが、同時に、そうした構造が孕むデモクラシーの課題も浮き彫りにしてきたと考えられる。
1 0 0 0 OA 科学論文とは : 若き研究者のための論文迅速評価法
- 著者
- Donald M. BRUNETTE 八重垣 健
- 出版者
- 一般社団法人 口腔衛生学会
- 雑誌
- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.5, pp.536-543, 2011-10-30 (Released:2018-04-06)
- 参考文献数
- 3
論文を読むあるいは作成するための,論文の価値判断の指針を解説した.論文の構成要素には,まず「読者(あなた)」が最上位にあり,そしてタイトル・著者・掲載雑誌の位置づけ,要旨(抄録),はじめに,研究方法と材料,結果,考察,結論などの因子がある.そのうえで,読者側からは「読者の印象に残る重要な情報」,そして「読者が個人的に学んだ明確で重要な情報」などの因子がある.読者は,その論文に,どの程度興味を持つことができるか,そして読む価値があるかを,判断しなければならない.そこで,要旨を注意深く読み,「読者が,論文を読む目的」を見つけることが必要となる.「タイトル・著者・掲載雑誌の位置づけ」では,論文に重要な新情報が記載されている可能性や,掲載雑誌のランクなどがわかる.要旨にはいくつかの構成要素があり,要旨を読み,「問題点や新知見」を見つけて論文を続けて読む理由とする.「はじめに」では,探求的で仮説に基づいた研究か否か判定し,研究方法と材料では,読者が実験結果の有効性を確かめ,実験を再現するのに十分な情報を得ることができる.結果では結論の基礎となるデータを十分に知り,考察では「論理のある確固とした結論」にしようとの著者の意図を知ることもできる.一方,「はじめに」で記載された仮説の答えを「結論」で明確に知ることができる.
1 0 0 0 OA 高次元類体論から見た数論幾何学
1 0 0 0 OA 321)ホットアイマスクが睡眠に与える影響
- 著者
- 長坂 猛 田中 美智子
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護研究学会
- 雑誌
- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.3, pp.3_284, 2012-06-07 (Released:2019-02-15)
- 著者
- 波戸 謙太 金堀 哲也 蔭山 雅洋 八木 快 谷川 聡 川村 卓
- 出版者
- 日本コーチング学会
- 雑誌
- コーチング学研究 (ISSN:21851646)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.159-176, 2023-03-20 (Released:2023-03-31)
- 参考文献数
- 44
This study delineates the common characteristics of pitching motion in professional baseball players (Top and Minor groups) by focusing on their upper body. With an aim to gain insight into the development of athletic abilities, the pitching motion of the Top group was compared with the Minor group, resulting in the clarification of upper limb issues in the Minor group and amateur pitchers. The subjects were 47 pitchers belonging to the Nippon Professional Baseball (NPB). The experiment was a fastball pitch with maximum effort. The analyzed trial was the highest ball velocity (average ball velocity 38.9 ± 1.8 m/s). Post-analysis, the following commonalities and differences were identified. (1) There is a commonality in the sizeable external rotation of the shoulder joint during MER (Maximum External Rotation), which is considered a factor in pitching speed compared to amateur pitchers. However, after evaluating the professional baseball pitchers, it was suggested that this movement had a low influence on the ball velocity. (2) There was a commonality in the movements in which the maximum shoulder horizontal adduction angular velocity was more significant than the upper trunk angular velocity. (3) However, in terms of differences among professional baseball pitchers, the Top group pitchers had a greater horizontal adduction angular velocity of the shoulder joint during MER and a more significant extension angular velocity of the elbow joint during REL (Ball Release) by suppressing the forward tilt angular velocity of the trunk during MER.
1 0 0 0 OA 海洋酸性化がサンゴ礁域の石灰化生物に及ぼす影響
- 著者
- 諏訪 僚太 中村 崇 井口 亮 中村 雅子 守田 昌哉 加藤 亜記 藤田 和彦 井上 麻タ理 酒井 一彦 鈴木 淳 小池 勲夫 白山 義久 野尻 幸宏
- 出版者
- 日本海洋学会
- 雑誌
- 海の研究 (ISSN:09168362)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.21-40, 2010-01-05 (Released:2022-03-31)
- 参考文献数
- 103
産業革命以降の二酸化炭素(CO2)排出量の増加は,地球規模での様々な気候変動を引き起こし,夏季の異常高海水温は,サンゴ白化現象を引き起こすことでサンゴ礁生態系に悪影響を及ぼしたことが知られている。加えて,増加した大気中CO2が海水に溶け込み,酸として働くことで生じる海洋酸性化もまた,サンゴ礁生態系にとって大きな脅威であることが認識されつつある。本総説では,海洋酸性化が起こる仕組みと共に,海洋酸性化がサンゴ礁域の石灰化生物に与える影響についてのこれまでの知見を概説する。特に,サンゴ礁の主要な石灰化生物である造礁サンゴや紅藻サンゴモ,有孔虫に関しては,その石灰化機構を解説すると共に,海洋酸性化が及ぼす影響について調べた様々な研究例を取り上げる。また,これまでの研究から見えてきた海洋酸性化の生物への影響評価実験を行う上で注意すべき事項,そして今後必要となる研究の方向性についても述べたい。
1 0 0 0 OA 『大学の物理教育』に期待する
- 著者
- 伊達 宗行
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 大学の物理教育 (ISSN:1340993X)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.1, pp.2, 1994-12-05 (Released:2018-04-14)
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 中村 邦子 田中 早苗 武本 歩未 大塚 美智子
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.12, pp.849-863, 2020-12-25 (Released:2020-12-25)
- 参考文献数
- 6
JIS 衣料サイズの改正から20 年以上が経過し,日本人成人の人体寸法データベース2014−2016 に基づく改正について検討されている.JIS 衣料サイズは新しく制定されたISO 8559-3 に対応する必要がある.本研究では,日本人の人体寸法の推定を行い,ISO 8559-3 に対応するサイズ別人体寸法表を作成することを目的とする.日本人の人体寸法データベース2014−2016 の女性1633 名の人体計測結果を利用して,1633 名全体とDROP による体型分類別3 グループ,年齢層を25 歳未満, 25 歳~40 歳,40 歳~55 歳,55 歳以上の4 グループ,計8 グループについて分析した.身長,乳頭位胸囲,胴囲,腰囲,体重の計測項目から,重回帰分析に用いる変数の組み合わせを検討し,上半身にフィットする説明変数は,身長と乳頭位胸囲の2 変数が適当であることを確認した.重回帰分析により回帰係数の推計を行い,算出した定数と係数からDROP による体型分類別と年齢層別のサイズ別人体寸法表を作成した.さらに,胴囲,腰囲,体重を加えた5 変数のサイズ別人体寸法表を作成した.数値モデルにより,現代日本人の体型を幅広く推定することが可能である.また,人体寸法の推定により算出した,項目間のインターバルはパターンメーキング,グレーディング,フィット性の評価などに活用できると考える.
- 著者
- Kazuya Nagasawa Hidekazu Suzuki
- 出版者
- Carcinological Society of Japan
- 雑誌
- Crustacean Research (ISSN:02873478)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.49-54, 2023-04-04 (Released:2023-04-04)
- 参考文献数
- 9
Markevitchielinus anchoratus Titar, 1975 is reported based on an adult female from the floor of the buccal cavity of a sea raven Hemitripterus villosus (Pallas, 1814) caught in Onagawa Bay, an inlet of the Northwestern Pacific Ocean, Miyagi Prefecture, northern Japan. The female specimen is briefly described. The female inserted its head with a pair of large, lateral processes and the anterior part of an elongate neck into the tissues of the buccal cavity floor. The present collection of M. anchoratus represents the third occurrence record of the species and extends its distributional range from Kunashiri and Shikotan islands, east of Hokkaido, to Onagawa Bay off Honshu, the largest main island of Japan. The species is specific to the sea raven and may be a subarctic species.
1 0 0 0 OA タンパク質のモジュール構造と分子進化
- 著者
- 郷 通子
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.6, pp.283-288, 1992-11-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 27
Soluble proteins consist of one to several globular functional domains. A globular domain is decomposed into several modules. Module is a sub-structure within a globular domain and it has a compact conformation consisting of a contiguous sequence of 10 to 40 amino acid residues. Close correlation of module boundaries with intron positions implies that a gene encoding a globular functional domain was created by joining exons in early evolution. Some introns seem to be deleted on different lineages in evolutionary time scale.
- 著者
- Daichi Watanuki Akiko Tamakoshi Takashi Kimura Toshiaki Asakura Masayuki Saijo
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- pp.JE20220359, (Released:2023-04-08)
- 参考文献数
- 26
Background: For therapeutic efficacy, molnupiravir and nirmatrelvir-ritonavir must be started to treat patients within 5 days of disease onset to treat patients with COVID-19. However, some patients spend more than 5 days from disease onset before reporting to the Public Health Office. This study aimed to clarify the characteristics of patients with reporting delay.Methods: This study included data from 12,399 patients with COVID-19 who reported to the Public Health Office from March 3rd, 2021 to June 30th, 2021. Patients were stratified into “linked” (n=7,814) and “unlinked” (n=4,585) cases depending on whether they were linked to other patients. A long reporting delay was defined as the difference between the onset and reporting dates of 5 days or more. Univariate and multivariate analyses were performed using log-binomial regression to identify factors related to long reporting delay, and prevalence ratios with corresponding 95% confidence intervals were calculated.Results: The proportion of long reporting delay was 24.4% (1904/7814) and 29.3% (1344/4585) in linked and unlinked cases, respectively. Risks of long reporting delay among linked cases were living alone and onset on the day with a higher 7-day daily average confirmed cases or onset on weekends; whereas, risks for unlinked cases were age over 65 years, without occupation and living alone.Conclusion: Our results suggest the necessity to establish a Public Health Office system that is less susceptible to the rapid increase in the number of patients, promotes educational activities for people with fewer social connections, and improves access to health care.
1 0 0 0 金毘羅庶民信仰資料集
- 著者
- 日本観光文化研究所編
- 出版者
- 金刀比羅宮社務所
- 巻号頁・発行日
- 1982
1 0 0 0 犬におけるワクチン接種後アレルギー反応に関する研究
これまでの研究により、犬におけるワクチン接種後アレルギー反応の原因アレルゲンは、ワクチン中に含まれる牛胎子血清(FCS)であることが明らかとなっている。本年度は、FCS中においてアレルゲンとなり得るタンパク質成分を解析した。【方法】ワクチン接種後にアレルギー反応を起こし、ワクチンおよびFCSに対するIgE抗体を有する16頭の犬の血清を用いた。ワクチンおよびFCSに対するIgE抗体はELISA法により検出し、次いでこれら犬の血清IgE抗体と反応するFCS中のタンパク質成分を、抗犬IgE抗体を用いたイムノブロット法によって解析した。【結果】ワクチン接種後、16頭中2頭がアナフィラキシーと考えられる呼吸器・循環器症状を起こし、14頭が顔面浮腫などの皮膚症状を起こしていた。これらアレルギー反応は、ワクチン接種後数分から20時間に認められていたが、即時型および非即時型反応のいずれを起こした場合にもワクチンおよびFCSに対するIgE抗体が検出された。FCS成分中アレルゲンのイムノブロット解析においては、ワクチン接種後アレルギー反応を起こした犬の血清IgE抗体が認識するさまざまな分子量のタンパク質が検出された。なかでも、16頭中14頭の犬の血清が約66kDaのタンパク質に対し反応していた。分子量からこのタンパク質が牛血清アルブミン(BSA)であることを疑い、精製BSAに対する血清中IgE抗体の反応性を検討したところ、16頭中4頭のみにおいて精製BSAに対するIgE抗体が検出された。【考察】BSAその他、複数の血清タンパク質がFCS中のアレルゲンとなっていることが明らかとなった。アレルギー反応の少ないワクチンを製造するためには、ワクチン成分からのFCSおよびBSAの除去が必要であるものと考えられた。
- 著者
- 津田 尭哉 山本 真一郎 相河 聡 畠山 賢一
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 B (ISSN:13444697)
- 巻号頁・発行日
- vol.J106-B, no.4, pp.260-263, 2023-04-01
近年,大電力機器用電磁遮へい材の要求が増している.本研究では,一面を開口面とした金属きょう体内に送信コイルを配置し,きょう体から漏洩する近傍磁界について検討した.また,電磁遮へい効果を向上できる穴あき金属板について検討した.
1 0 0 0 OA 経済的利益の経営管理上の有用性―価値創造額の測定をめぐる考察―
- 著者
- 安酸 建二
- 出版者
- 日本管理会計学会
- 雑誌
- 管理会計学 : ⽇本管理会計学会誌 : 経営管理のための総合雑誌 (ISSN:09187863)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.19-39, 2008-02-15 (Released:2019-03-31)
企業の価値創造を明示的な企業目標とする考え方が,広く普及しつつある.これに伴い,企業価値の創造を導く経営活動・経営努力に対して測定可能な目標を与えると同時に,価値創造のプロセスをモニターし,評価するための期間業績指標の開発に大きな関心が向けられている.特に,注目されている期間業績指標は,資本コストを控除した後の経済的利益である.経済的利益の有用性は,しばしば企業価値の理論モデルであるフリー・キャッシュフロー割引モデルとの整合性から説明されるが,経済的利益そのものが何を測定し,どのような情報を生み出しているのかについては十分に明らかにされていない.そこで,本稿では,経済的利益によって生み出される情報を明確にし,経営管理上の経済的利益の有用性を明らかにする.
1 0 0 0 OA 江戸川乱歩と映画的想像力 ―「火星の運河」を中心に―
- 著者
- 韓 程善
- 出版者
- 日本比較文学会
- 雑誌
- 比較文学 (ISSN:04408039)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.110-123, 2006-03-31 (Released:2017-06-17)
The aim of this study is to analyze the impact that cinematic representative techniques had on Edogawa Rampo’s novels. Hitherto, critics tended to recognize the link between Rampo’s no\els and cinema merely because many of Rampo’s works were made into films. However, there has been little focused discourse on what specific effects cinema had on Rampo’s novels and how cinematic expression integrated into his literary style. I begin by describing the process in which cinema developed into an independent art form in the 1920s by conducting an investigation of a number of cinema houses that were newly established during this period. Through an analysis of articles written by literati in Japan during the 1920s I also show how rapid development in cinema influenced contemporary literary circles. Just as many writers were influenced by cinema, Rampo was also strongly drawn to cinema even before he became a writer; this study also reviews Rampo’s unpublished paper which reveals his unique inclination toward cinema that is an important clue to the effective interpretation of his novels. In order to support my argument, I proceed to reinterpret Rampo’s short novel, “Canal on Mars” by investigating the specific influences of cinematic expression that are evident in this short novel. Specifically, I show how “Canal on Mars” integrates the technique of the silent film into its text. I also prove how Rampo attempted to create cinematic expressions into his literary text by using the style of “prose poem.” For instance, Rampo effectively used metaphors in order to express physical “forms” which translated the cinema’s visual expressions into vivid literary representations. In the 1920s, when cinema emerged as a new art form in Japan, literary scholars began to recognize this new type of media as a source from which to experiment and develop new forms of literary expressions. Thus, adopting cinematic expressions into linguistic works became a characteristic phenomenon during this period. In conclusion, I argue that not only does the link between Rampo’s novels and films need to be studied further in order to nurture a more profound understanding of Rampo’s novels but by doing so it also provides an alternative method for examining the artistic interaction between literature and cinema in the 1920s.
1 0 0 0 OA 卵白・卵黄および全卵の起泡性と泡の安定性に関する研究
- 著者
- 柴山 キヨ子 片岡 美智子 光明院 智子
- 出版者
- 高知女子大学
- 雑誌
- 高知女子大学紀要 自然科学編 = THE BULLETIN OF KOCHI WOMEN'S UNIVERSITY Series of Natural Sciences (ISSN:04522486)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.11-15, 1995-03-25
1 0 0 0 キハ41000とその一族
- 著者
- 岡田誠一著
- 出版者
- ネコ・パブリッシング
- 巻号頁・発行日
- 1999