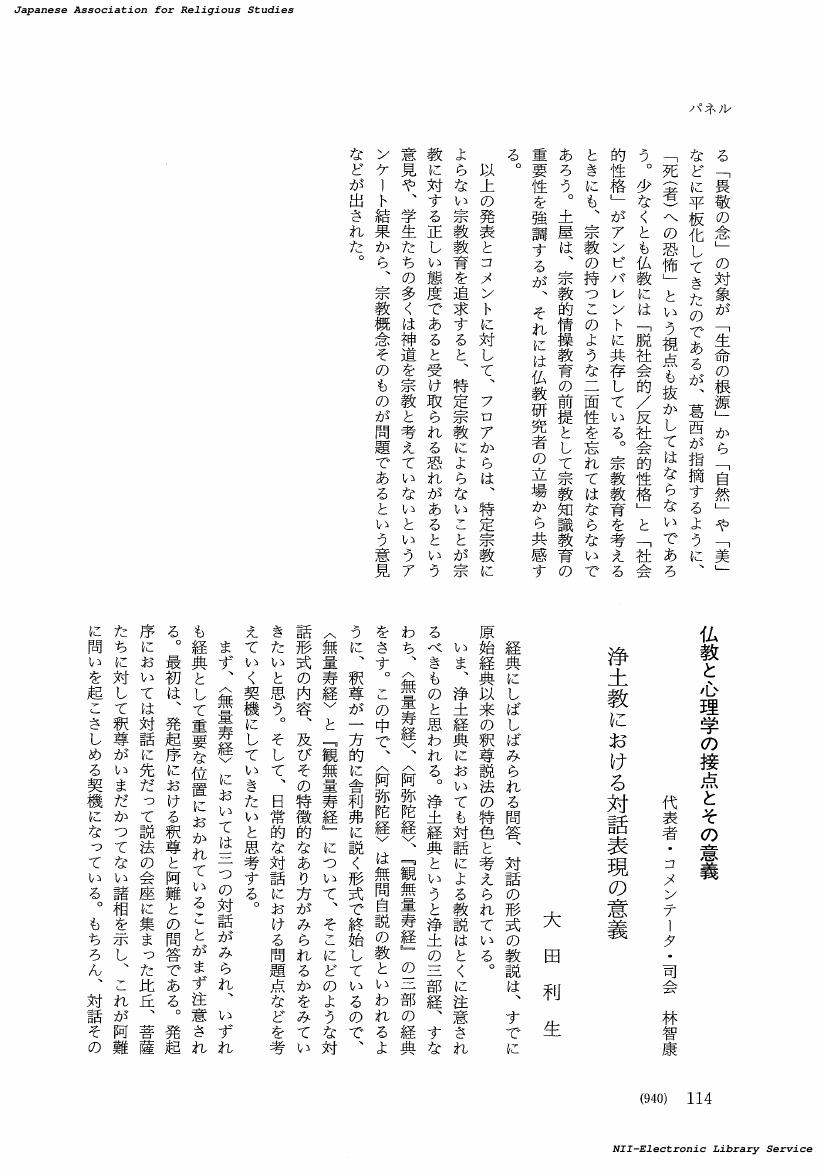1 0 0 0 OA 主成分分析に基づく優れた長距離ランナーの運動学的特徴とleg stiffnessの関係
- 著者
- 村澤 智啓 小林 吉之 小関 道彦
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.176-184, 2022 (Released:2023-03-03)
- 参考文献数
- 29
ランニング中の大きな leg stiffnessは優れた長距離走パフォーマンスに関連づけられるが,大きな leg stiffnessに関連づけられる運動学的特徴は十分明らかにされていない.そこで本研究では, 14名の優れた長距離ランナーを含む 28名の実験参加者の,ランニングにおける運動学的変数に対し主成分分析を行い,優れた長距離ランナーの運動学的特徴を記述する主成分と leg stiffnessの間の関係を調べた.その結果,第 1主成分のみが優れた長距離ランナー群で有意に大きく( p ‹ 0.01),かつ leg stiffnessと有意に相関する( r = 0.77, p ‹ 0.01)ことが明らかになった.この主成分は,立脚期における,小さな骨盤下降変位や小さい膝関節の屈曲運動範囲など,大きな leg stiffnessに関係する HRの運動学的特徴を記述していた.
- 著者
- 井手 広康
- 雑誌
- 研究報告コンピュータと教育(CE) (ISSN:21888930)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023-CE-169, no.20, pp.1-6, 2023-03-04
本研究では,「情報Ⅰ」のプログラミング教育にマイコンボードの micro:bit を用いて授業実践を行った.さらに,令和 3 年度に実施したプログラミング教育と結果を比較し,マイコンボードを用いたプログラミング教育の学習効果について検証した.ARCS 評価シートと事後アンケートを比較した結果から,マイコンボードの micro:bit を用いたプログラミング教育が,「情報Ⅰ」の教科書に使用されている四つのプログラミング言語(Python,JavaScript,VBA,Scratch)による授業実践と,同等あるいはそれ以上の学習効果が期待できることがわかった.他のプログラミング言語とは異なり,実際に手元で操作できるマイコンボードを用いたことで,生徒の興味・関心を効果的に引き出せたことが大きな要因であると推測する.
1 0 0 0 OA ランニング中の足部アーチ変化および足底荷重分布パターンの定量化
- 著者
- 木内 聖 平野 智也 角田 直也 船渡 和男
- 出版者
- 公益財団法人 石本記念デサントスポーツ科学振興財団
- 雑誌
- デサントスポーツ科学 (ISSN:02855739)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.184-191, 2023-02-22 (Released:2023-03-09)
- 参考文献数
- 9
ランニングにおける足部内側縦アーチの変化および足底荷重を定量化することを目的とした.足底圧分析機 (Novel GmbH®,100Hz),モーションキャプチャシステム (Oxford,100Hz),フォースプレート (Kistler,1KHz) を同期し,足底を解剖学的計測点に基づいて5つに分割した.参加者8名が2.78m/sの速度でランニングを行った.内側縦アーチ角度は第一中足骨遠位端,舟状骨,踵骨側面のなす角度,中足趾節関節角度は,母趾末節骨近位端,第一中足骨遠位端および近位端のなす角度として算出した.足底荷重は,接地とともに後足部および前足部外側の荷重がみられ,蹴り出し時には前足部に荷重がシフトし,内側縦アーチ角度が最大の変化量を示した.その後,中足趾節関節背屈に伴い前方向の地面反力が増加する傾向がみられた.内側縦アーチは,足部接地中,足底荷重を吸収するための柔軟な構造から,蹴り出し時に中足趾節関節を背屈させることで剛性を高め,前足部で蹴り出すことで前方への推進力を生み出していると推察される.
1 0 0 0 認知症高齢者の嚥下障害
- 著者
- 野原 幹司
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.1-10, 2023-01-25 (Released:2023-03-08)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
これまでの摂食嚥下リハビリテーション(嚥下リハ)は,主に脳卒中回復期を対象に機能回復を目指した嚥下訓練が行われてきた.しかし,認知症は進行性疾患であるため機能回復を目指すのは難しく,指示が通らないため訓練の適応も困難である.したがって,認知症高齢者の嚥下リハは,今ある機能を生かした食支援の考え方が重要となる.認知症高齢者の食支援を行っていくにあたりポイントとなるのは認知症を一括りにせず,原因疾患に基づいたケアを心がけることである.アルツハイマー型認知症は食行動の障害が主であり,食べない,食事を途中でやめてしまう,といった症状がみられる.肺炎の原因となるような誤嚥がみられるようになるのは重度に進行してからである.レビー小体型認知症は,他の認知症と比べて比較的早期から身体機能の障害がみられ,誤嚥も早期からみられる.誤嚥したものを喀出する力も弱く誤嚥性肺炎のリスクが高い認知症である.抗精神病薬による薬剤性嚥下障害が多いのも大きな特徴である.血管性認知症は多彩な症状を示すが,最も多いとされる皮質下血管性認知症においては,大脳基底核が障害されるため錐体外路症状を呈し,レビー小体型認知症と似た嚥下障害を示す.麻痺などの身体症状が軽度であっても誤嚥がみられるため臨床経過に注意を要する.前頭側頭型認知症は前頭葉症状のため,嗜好の変化,過食といった症状が目立つが,その症状改善のために介入を試みてもうまくいかないことが多い.窒息や重度誤嚥がないのであれば介入せずに症状を受け入れた方がよい.認知症の原因疾患に基づいた食支援を提供するには,医師による認知症の原因疾患の診断が重要である.加えて,医師が他職種や患者家族に原因疾患ごとの特徴や食支援のポイントを説明できるようになるとケアの質は格段に上がる.認知症高齢者の嚥下障害臨床において医師の果たす役割は大きい.
1 0 0 0 OA 黒塚古墳から藤ノ木古墳へ至る古墳時代における染織文化財の総合的研究
本研究では古墳時代における繊維製品の材料学的・構造的研究方法の基礎的研究を行い、ヤマトにおける古墳時代繊維製品の具体的な変遷の把握を試みた。考古学および文化財科学における新たな価値を生み出す研究を大きな目標として研究を進めた。本研究では、ラミノグラフィおよびX線CTと呼ばれる非破壊調査法により非破壊的に織物の構造調査が可能であること、光音響赤外分光分析が非破壊的に素材を知る手段として有効であることが確認できた。考古学的には新沢千塚古墳群から出土した染織文化財を例として、統計分析をおこない織密度や織物の種類や古墳の墳形、規模との相関について研究した。
1 0 0 0 OA 観光客の地震・津波の危険性と避難行動の認識
- 著者
- 照本 清峰
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.30-40, 2020-04-25 (Released:2020-04-25)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1
観光地の地震・津波の対応体制を検討するためには、観光客の認識を踏まえておく必要がある。そこで本研究では、観光客の地震・津波の危険性と津波避難行動の認識を示すとともに、それらの関係性を明らかにすることを目的とする。調査対象地域は、和歌山県白浜町における白良浜周辺地域であり、来訪している観光客グループを対象としている。分析結果より、観光客の属性別において認識の差異がみられる項目があること、自動車避難の選択の規定要因として、来訪手段が自動車であることとともに、想定する避難場所やまちなかにいることが規定要因になっていること、観光客の地震・津波の危険性の認識と津波避難行動の認識の関連性は低いこと、等が明らかになった。分析結果をもとにして、観光地の津波避難時の課題と対策のあり方について、情報提供と避難誘導体制に着目して検討した。
1 0 0 0 OA 水素と水素化合物の金属相探索
- 著者
- 阿部 和多加
- 出版者
- 日本高圧力学会
- 雑誌
- 高圧力の科学と技術 (ISSN:0917639X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.4, pp.281-290, 2018 (Released:2018-12-28)
- 参考文献数
- 56
The idea of looking for metallic states in hydrides rather than in pure hydrogen has remarkably increased the options for attaining the high-temperature superconductivity predicted by Ashcroft in 1968. This article presents a few viewpoints which might serve as a practical guide to searching new metallic hydrides which possess high superconducting transition temperatures. According to the Goldhammer-Herzfeld criterion, it is important to pay attention to unstable compounds at one atmospheric pressure because they can be good metals at high pressures. It is also helpful to make use of possible structural similarities of hydrides between the diagonally adjacent elements in the periodic table in order to control insulator-to-metal transition. The effects of anharmonic proton zero-point energy on stable structures are also discussed by applying the self-consistent harmonic approximation to solid hydrogen.
1 0 0 0 OA 主婦を問い始めた女性たち:田中喜美子および和田好子のライフヒストリー
- 著者
- 池松 玲子
- 出版者
- 東京女子大学現代教養学部国際社会学科社会学専攻紀要編集委員会
- 雑誌
- 東京女子大学社会学年報 (ISSN:21876401)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.19-35, 2017-03-02
高度経済成長期には,性別役割分業を元に主婦は戦後の女性の一般的なライフスタイルとして定着したが,1970 年代に第二波フェミニズムの影響が広がるにつれ,生き難さを感じる女性たちによって主婦という生き方が問題として捉えられるようになった.本稿では,高度経済成長期に実際に主婦として生き,育児終了期からは投稿誌『わいふ』を発行して,主婦に自由な言論空間を提供する活動を実践してきた田中喜美子および和田好子に着目し,両名のライフヒストリーの分析を通して,主婦という生き方に疑問をもち始めた女性たちについて考察した.
1 0 0 0 OA 主婦と近代的個人:投稿誌『わいふ』における主婦論争の分析
- 著者
- 池松 玲子
- 出版者
- 東京女子大学現代教養学部国際社会学科社会学専攻紀要編集委員会
- 雑誌
- 東京女子大学社会学年報 (ISSN:21876401)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.17-34, 2018-03-02
戦後日本社会では,第二波フェミニズムにおける主婦を問題として問うという流れの 中で,家族の中に埋没していた女性たちが近代的個人としての自己に目覚めていくプロセスがあった.主婦であることの意味をめぐっては多様なメディアでの積極的な議論があり,そうした議論は社会的に注目され女性たちに影響を与えてもきた.本稿は識者等ではなく主婦自身の主張で構成される投稿誌『わいふ』の主婦論争に着目し,主婦という生き方と近代的個人としての自己をめぐり何が語られたかを明らかにすると共に,こうした論争を可能にしたメディアとしての同誌について考察した.
1 0 0 0 OA EATがスギ花粉症咽頭症状に有効であった一例
- 著者
- 西 憲祐 西 隆四郎 木村 翔一 西 総一郎 田中 宏明 山野 貴史
- 出版者
- 日本口腔・咽頭科学会
- 雑誌
- 口腔・咽頭科 (ISSN:09175105)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.37-42, 2022 (Released:2022-07-15)
- 参考文献数
- 18
アレルギー性鼻炎は日本において最も頻度が高いアレルギー性疾患の一つである.特にスギ花粉症患者は人口の約40%が罹患しており,重要な治療標的である.アレルギー性鼻炎はしばしば上咽頭のかゆみなどの咽頭症状を誘発する.慢性上咽頭炎に対して上咽頭擦過療法(Epipharyngeal Abrasive Therapy:EAT)が有効であるという報告が多数されており,後鼻漏,咽頭違和感,慢性咳嗽,頭痛といった典型的な症状以外にもアレルギー性疾患に有効であると報告されている.しかしながらEATがアレルギー性疾患に有効とされる機序に関しては不明な点が残されている.今回我々はEATがスギ花粉による上咽頭アレルギーに対して有効であった一例を報告するとともに,病理組織学的所見からその機序に関して考察した.症例は34歳男性でスギ花粉飛散時期に上咽頭の掻痒感を自覚していた.本患者に継続的にEATを施行することで,スギ花粉による上咽頭アレルギーを抑制する事が出来た.更に,この効果発現機序に関しては,EATによる繊毛上皮の扁平上皮化生と粘膜上皮直下の線維性間質の出現によるものと考えられた.
1 0 0 0 OA 2)間質性肺炎の多様性と重要性~診断のコツと専門医紹介のタイミング~
- 著者
- 小倉 高志
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.3, pp.403-409, 2018-03-10 (Released:2019-03-10)
- 参考文献数
- 11
1 0 0 0 OA 教科書の索引の用語に着目した情報Iと他教科との関係
- 著者
- 赤澤 紀子 赤池 英夫 柴田 雄登 角田 博保 中山 泰一
- 出版者
- 情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告. コンピュータと教育(CE) (ISSN:21888930)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023-CE-169, no.16, pp.1-7, 2023-03-04
共通教科情報科は,2003 年に「情報 A」,「情報 B」,「情報 C」の選択必履修から始まり「社会と情報」と「情報の科学」の選択必履修を経て,2022 年に「情報Ⅰ」(必履修 2 単位)と,2023 年「情報Ⅱ」(選択 2 単位)となった.これまで,情報の科学的理解に重きを置いた科目「情報 B」「情報の科学」が設置されていたが,他の科目と比べ履修の割合が少なかった.しかし「情報Ⅰ」は高校生全員が履修するため,これから「情報」を履修するすべての高校生が情報の科学的理解に重きを置いた学習を進めることになる.共通教科情報科は,小・中・高等学校の各教科等の指導を通じて行われる情報教育の中核の教科の一つであり,隣接する中学校技術・家庭科や,高等学校の他の教科と連携することで,より効果的な学習ができると考える.そこで,本研究では,教科書の索引の用語の着目して「情報Ⅰ」と数学,中学校技術・家庭科の用語の比較を行い,科目間の関係について調査分析を行い,高等学校の科目間の関連,中学校と高等学校のつながりについて述べる.
- 著者
- 細内 信孝 東海林 伸篤
- 出版者
- 公益社団法人 都市住宅学会
- 雑誌
- 都市住宅学 (ISSN:13418157)
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, no.69, pp.40-48, 2010 (Released:2017-06-29)
- 参考文献数
- 11
1 0 0 0 OA 象肉が食えないバカピグミーの象猟人
- 著者
- 佐藤 弘明
- 出版者
- 浜松医科大学
- 雑誌
- 浜松医科大学紀要. 一般教育 (ISSN:09140174)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.19-30, 1993-03-31
Food restriction on elephants among the Baka, a hunter-gatherer group in northwestern Congo, was described, and its social function was also discussed. The Baka hunt and snare various forest animals ranging from rats to elephants, mainly aiming at duikers and primates. Elephants are rarely hunted. Once killed, however, an elephant could bring enormous amount of meat to many people. Nevertheless, the Baka elephant hunter and his senior close relatives don't eat any portion of the huge game, because if they eat the meat of an elephant killed by the hunter, he is believed to be incapable of catching any elephant as game thereafter. Besides elephants, there are many kinds of game which certain people should avoid eating. The game includes "anomalous", "unusual", or valueless game for food, which the previous studies on food taboos have so far considered to be susceptible to avoidance. On the other hand, an elephant is not "anomalous", "unusual", or valueless. Unlike the elephant hunter and his senior relatives, most of those who are required to avoid the game are the people at momentous stages of life such as pregnant women, new-born babies, etc. These differences suggest that the above custom of food restriction on elephants has different meanings from the ones interpreted in the previous studies concerning food taboos. I think that this custom is part of the leveling mechanism of the Baka society. Although experienced Baka elephant hunters are held in esteem, they don't have social or political power. It is possible that sharing such an enormous amount of meat as an elephant has makes receivers feel a psychological burden and helps centralize prestige on givers. But, there is not such centralization of prestige in the Baka society. I consider that it is partly because elephant hunters control themselves and partly because they can have no right to the meat under the above custom and therefore meat receivers do not need to feel obliged to the hunters. The egalitarian society of the Baka could be maintained by the leveling mechanisim including thorough sharing, the restrained attitude of elephant hunters, food restriction on elephants and so on.
- 著者
- 大田 利生
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.4, pp.940-941, 2009-03-30 (Released:2017-07-14)
1 0 0 0 OA ブレイン・マシン・インターフェイス操作能力の個人差メカニズム
- 著者
- 笠原 和美 DaSalla Charles 本田 学 花川 隆
- 出版者
- 公益社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.Annual57, no.Abstract, pp.S279_1, 2019 (Released:2019-12-27)
ブレイン・マシン・インターフェイス(BMI)は、読み取った脳活動から機械を動かすことで、病気や怪我により失われた機能を代替する技術として注目されている。しかし、BMIの操作能力には個人差があり、上手く使いこなせないケースも多い。本研究は、運動想像に伴うμ波脱同期を用いた脳波BMIの操作能力を計測し、脳構造・機能との関係を明らかにした。健常者30名を対象とし、自身の手のタッピング動作を想像するように指示した。μ波脱同期の強度をオンラインで計算し、カーソルの制御信号として利用した。カーソルの操作能力を変数として、大脳皮質密度との相関を脳構造MRIにより調べた。さらに、脳機能MRIと脳波BMIの同時計測を用い、操作能力の差がある被験者間の脳機能連絡の違いを調べた。その結果、高い操作能力を有する被験者ほど運動想像に関係する補足運動野の皮質体積が大きく、運動野-基底核の運動ネットワークを利用していた。一方、操作能力の低い被験者は、背側前頭前野や前部帯状回など認知的なネットワークを利用していた。本研究で得られた知見を基に、高い操作性を有するBMIの開発が可能と考えられる。
1 0 0 0 風景の俯瞰から自然との一致へ--花袋「生」改稿をめぐって
- 著者
- 小堀 洋平
- 出版者
- 早稲田大学国文学会
- 雑誌
- 国文学研究 (ISSN:03898636)
- 巻号頁・発行日
- vol.162, pp.24-34, 2010-10
- 著者
- Akiyuki Uzawa Masahiro Mori Yuta Iwai Hiroki Masuda Satoshi Kuwabara
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.18, pp.2785-2787, 2022-09-15 (Released:2022-09-15)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 4
Satralizumab, a monoclonal antibody against interleukin-6 receptors, has been approved for the treatment of neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD). Several reports have described the effectiveness of satralizumab against neuropathic pain in patients with NMOSD, but its effects on painful tonic seizures have not yet been reported. We herein report a Japanese woman with anti-aquaporin-4 antibody-positive NMOSD whose painful tonic seizures completely resolved after six months of satralizumab treatment. In conclusion, interleukin-6 blocking may be effective against painful tonic seizures. This effect may be due to suppression of microglial activation and the resultant neuronal hyperexcitability.