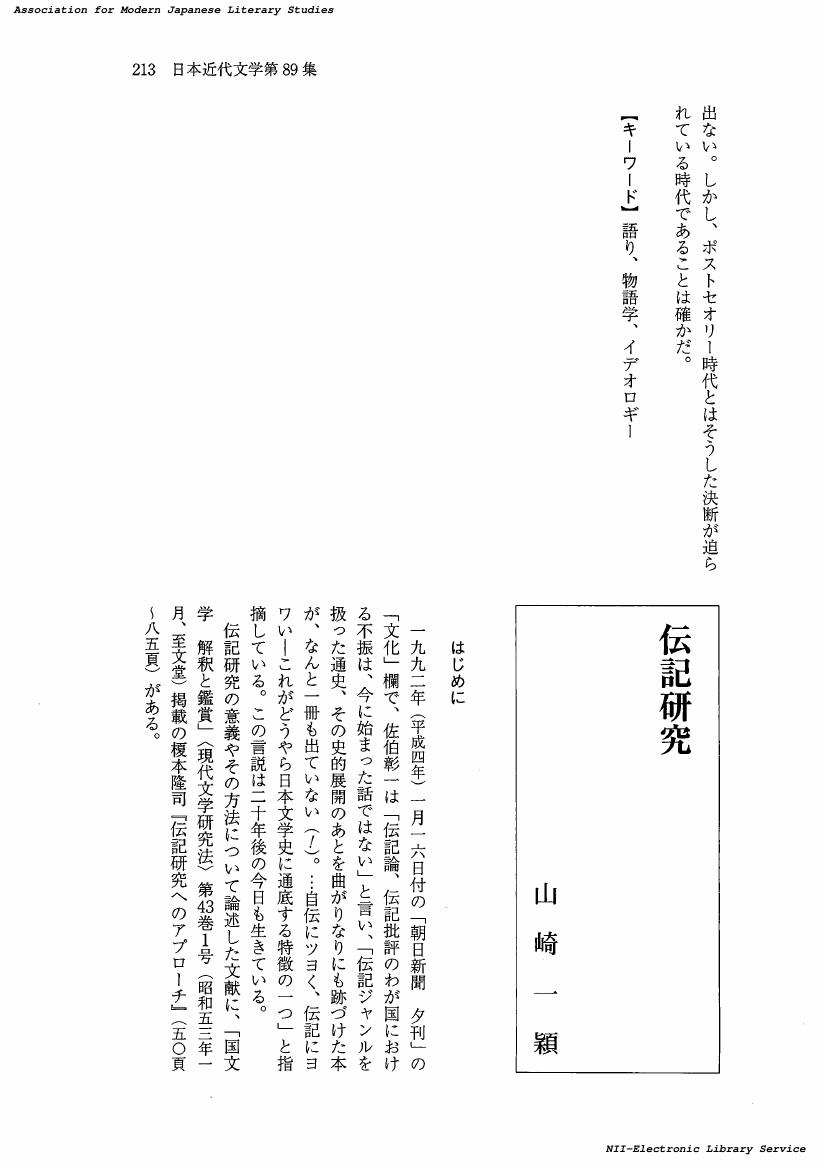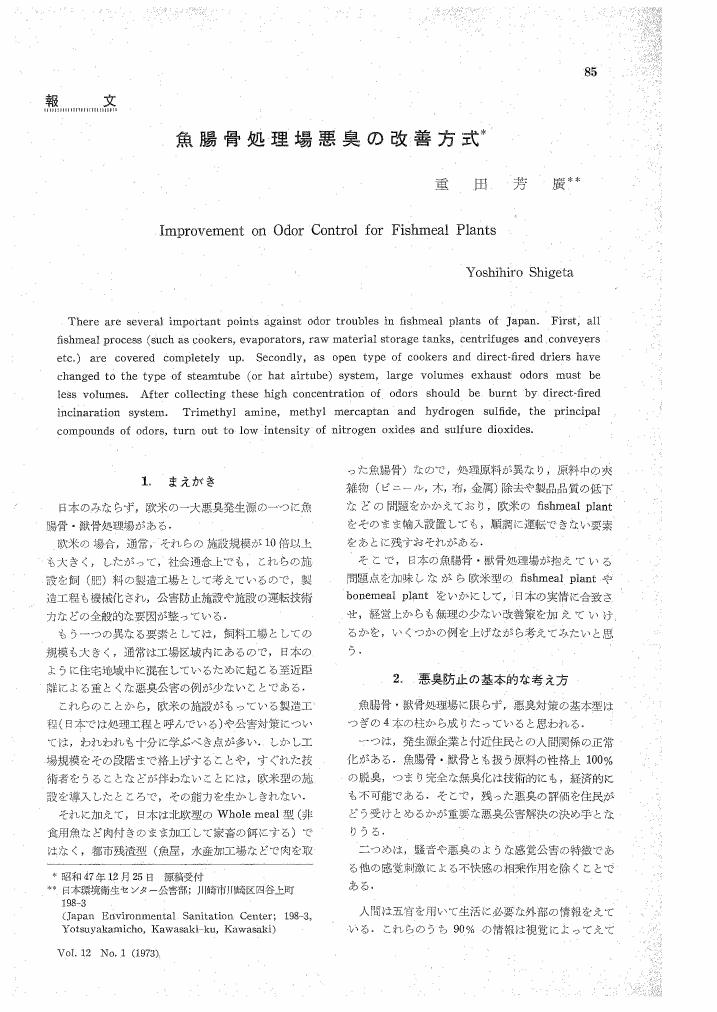1 0 0 0 OA 伝記研究(<フォーラム>方法論の現在I)
- 著者
- 山崎 一穎
- 出版者
- 日本近代文学会
- 雑誌
- 日本近代文学 (ISSN:05493749)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, pp.213-217, 2013-11-15 (Released:2017-06-01)
1 0 0 0 OA 名所江戸百景 深川洲崎十万坪
- 著者
- 森 義信
- 雑誌
- 大妻女子大学紀要. 社会情報系, 社会情報学研究 = Otsuma journal of social information studies
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.75-105, 2012
1 0 0 0 OA 修飾語句を伴わない「第1 文型」について
- 著者
- 滝沢 直宏
- 出版者
- 立命館大学国際言語文化研究所
- 雑誌
- 立命館言語文化研究 (ISSN:09157816)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.243-254, 2021-11
1 0 0 0 OA iPS細胞および脱細胞化・再細胞化技術を用いた子宮再構築
ラットiPS細胞を購入し,レンチウィルスベクターにてGFP遺伝子およびluciferase遺伝子を導入した.FACSにてGFP陽性細胞を分取し,GFP陽性ラットiPS細胞のクローニングに成功した.GFP陽性ラットiPS細胞を免疫不全マウスに皮下移植し,in vivo imaging systemを用いた細胞発光の追跡が可能であることを確認した.さらに,6週間後の奇形腫形成を確認した.ラットiPS細胞を,各分化段階に応じて培養液中の各種増殖因子の組成を変えながら培養した.リアルタイムPCRにて,ラットiPS細胞が中胚葉を経てミュラー管系統に分化していることが示唆された.
1 0 0 0 OA 重症感染症の軽快とともに自然寛解が得られた急性骨髄性白血病の2例
- 著者
- 高塚 祥芝 宇都宮 與 川畑 久 竹内 昇吾 牧野 虎彦 中原 勝志 下高原 茂巳 魚住 公治 花田 修一 有馬 暉勝
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.4, pp.707-709, 1999-04-10 (Released:2008-06-12)
- 参考文献数
- 6
症例1は, 63歳,男性.汎血球減少と右下腿の重症峰窩織炎で入院.骨髄像では芽球が78%を占めAML (M0)と診断.症例2は, 47歳,男性.発熱と白血球増加で入院.骨髄は,低形成で芽球32%,好酸球24%認AML (M4Eo)と診断.入院時肛門周囲膿瘍を併発していた. 2例とも感染症の治療を優先して抗生剤での治療中にAMLの自然寛解を得た. AMLの自然寛解は稀であり貴重な症例と思われ報告した.
1 0 0 0 OA 弥生時代の年代測定
- 著者
- 今村 峯雄 Mineo IMAMURA イマムラ ミネオ
- 出版者
- 総合研究大学院大学教育交流センター
- 雑誌
- 総研大ジャーナル = Sokendai journal
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.37-39, 2004-03-25
1 0 0 0 OA Effects of geological differences on rainfall–runoff characteristics based on field measurements
- 著者
- Jun Inaoka Ken’ichirou Kosugi Naoya Masaoka Tetsushi Itokazu Kimihito Nakamura Masamitsu Fujimoto
- 出版者
- Japan Society of Hydrology and Water Resources (JSHWR) / Japanese Association of Groundwater Hydrology (JAGH) / Japanese Association of Hydrological Sciences (JAHS) / Japanese Society of Physical Hydrology (JSPH)
- 雑誌
- Hydrological Research Letters (ISSN:18823416)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.4, pp.80-86, 2022 (Released:2022-11-25)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
Previous studies have proven that rainfall–runoff characteristics in headwater catchments are affected by many factors, including topography, geology, and vegetation. However, only a few studies have explained the geological effects on rainfall–runoff characteristics based on observations from various catchments. In this study, we conducted runoff observations in 19 headwater catchments in two forests with different geological characteristics; based on these observations, we further conducted direct runoff and hydrograph recessions analyses. The runoff characteristics of the catchments were significantly affected by their local geological settings. Some catchments did not follow average trends, especially catchments with large baseflows, because of the effects of geological structures, such as dips and strikes in sedimentary-rocks and joints in granite. These catchments were likely to have wetter riparian zones, thereby facilitating direct flow, even in the case of reduced rainfall.
1 0 0 0 OA 魚腸骨処理場悪臭の改善方式
- 著者
- 重田 芳廣
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.85-91, 1973-02-15 (Released:2018-08-02)
1 0 0 0 OA 霊長類動物を用いた子宮同種移植モデルの確立および免疫応答の解明と社会的基盤の構築
MHC(主要組織適合遺伝子複合体)統御カニクイザルを用いて子宮同種移植モデルを作製し、血液型一致のMHCミスマッチ間および半ハプロ一致間における移植子宮の生着を比較した。カニクイザルにおける子宮においては拒絶反応をきたしやすく、抗原性が高いことが示された。また、半ハプロ一致間におけるカニクイザルペア間における子宮移植後に妊娠出産に世界で初めて成功した。日本産科婦人科学会、日本移植学会に子宮移植に関する見解を求める要望書を提出し、日本医学会で子宮移植に関する検討委員会が設立され、国内での臨床応用の可能性について議論が行われている。
1 0 0 0 OA テンジクダイ科の新分類体系にもとづく亜科・族・属の標準和名の提唱
- 著者
- 馬渕 浩司 林 公義 Thomas H. Fraser
- 出版者
- 一般社団法人 日本魚類学会
- 雑誌
- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.29-49, 2015-04-25 (Released:2017-08-10)
- 参考文献数
- 57
- 被引用文献数
- 3
A recent revision of the systematics of the family Apogonidae recognized four (two being new), 14 tribes (all new) and 38 genera, one of which was new. Apogon or Rhabdamia, Apogonichthyoides, Nectamia sensu stricto Zoramia. All apogonid subfamilies, tribes and genera occurring in Japanese waters are given fixed standard Japanese names. Based on the rules operationally proposed twenty-five new standard Japanese names were given to three subfamilies, 13 tribes Japanese name (at generic level for , subfamily and tribe level taxa, and a specific level for genera) being designated Additionally, a new standard Japanese Senou-hikari-ishimochi, was proposed for a Japanese species, Siphamia senoui,
1 0 0 0 OA 野生アライグマProcyon lotorにみられた疥癬の1例
- 著者
- 佐鹿 万里子 森田 達志 的場 洋平 岡本 実 谷山 弘行 猪熊 壽 浅川 満彦
- 出版者
- 日本野生動物医学会
- 雑誌
- 日本野生動物医学会誌 (ISSN:13426133)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.125-128, 2009 (Released:2018-05-04)
- 参考文献数
- 16
2005年2月,北海道北広島市にて腰部から尾部にかけ著しい脱毛と痂皮を形成したアライグマProcyon lotor雄幼獣一個体が捕獲され,当該病変部から多数の小型ダニ類が検出された。形態および2nd internal transcribed spacer(ITS-2)の塩基配列から,これらのダニ類はSarcoptes scabieiと同定された。本症例は日本産アライグマのS.scabieiによる疥癬の初報告となった。
1 0 0 0 OA 『大岡昇平のキリスト教』
- 著者
- 竹田 純郎 Sumio Takeda
- 出版者
- 金城学院大学
- 雑誌
- 金城学院大学論集. 人文科学編 = Treatises and studies by the Faculty of Kinjo Gakuin College (ISSN:04538862)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.49-63, 2012
1 0 0 0 OA 新型コロナワクチンの接種が在留外国人に対する態度に及ぼす影響:行動免疫システムの観点から
- 著者
- 田戸岡 好香 石井 国雄 樋口 収
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- pp.si5-3, (Released:2022-10-08)
- 参考文献数
- 23
感染症脅威は行動免疫システムにより外国人に対する偏見を生じさせるが,Huang et al.(2011)によればワクチン接種をすることでそうした偏見を低減できることが示されている。本研究では新型コロナワクチンの接種が在留外国人に対する態度に及ぼす影響を検討した。高齢者のワクチン接種が始まる前に,外国人に対する態度をベースラインとして測定する事前調査を行った。その後,全国的にワクチン接種が進んだ段階で,事後調査を行い,感染嫌悪の個人差,ワクチンの接種状況,ワクチンの有効性認知,外国人に対する態度を測定した。調査の結果(n=520),行動免疫システムの想定と一致して,ワクチン接種が完了していない状態では,感染嫌悪が低い場合よりも高い場合に,外国人に対する不寛容な態度が見られた。しかし,ワクチン接種を完了すると,感染嫌悪による影響が弱まっていた。なお,こうしたワクチンの接種が外国人態度に及ぼす影響は,特にコロナワクチンの有効性を高く認知している場合に顕著であった。考察では新型コロナのパンデミック下においてワクチン接種によって偏見が低減することの示唆について議論した。
1 0 0 0 OA 現実検討能力が欠けている患者へ個人SSTを試みて
- 著者
- 遠藤 恵理子
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会学術総会抄録集 第56回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)
- 巻号頁・発行日
- pp.60, 2007 (Released:2007-12-01)
統合失調症で開放病棟に入院中のA氏は入院6年目であるが陽性症状(妄想、滅裂思考など)と認知機能の低下があり、看護師や他患と時々トラブルを起こす事がある。A氏の心に中には「退院したい」という想いがあり、それを相手に上手く伝えられない事がトラブルに至る原因と考えられる。 A氏は人付き合いが苦手である事を自覚しており、ある時看護師にSST(社会生活技能訓練)を希望してきた。SSTはA氏にとって生活技能の改善が見られ退院へ向けての最初のステップにする為、その効果を見る事を目的に関わりをもった。個人SSTによる効果はアプローチの前後に精神科リハビリテーション行動評価尺度(REHAB以下リハブとする)で評価をした。 A氏は看護師に「いつからSSTをやるのですか」と積極的に声を掛けてきて意欲が感じられたが、訓練中は話が反れ、修正してもまた反れてしまう繰り返しが多く、進めていくのは困難であった。これは認知機能の障害が強く表れていたと考えられる。看護師の問題として話の反れた場合の軌道修正が上手く対応出来ず効果的なSSTにならない場合もあった。出来る時にはA氏にメモをとって貰いロールプレイを行って、宿題を出してみたが実践するのは難しく、A氏が自信をつけて貰える様褒めながら関わりをもったが般化する事は難しかった。A氏が訴えてきた場合には傾聴しつつ正の強化を与えていった。リハブの結果では「ことばの技能」は変化が無かったが「ことばのわかりやすさ」においては障害があるという方向から普通状態になった。以前はA氏の質問を一度に聞き取れず聞き返すと易怒的になり待つ事も出来ずにいたが個人SSTを実施するようになってからは易怒的になる事は少なくなり、看護師がすぐに対応出来ない場合、理由を話すと待つことが出来るようになった。個人SSTをする事はA氏にとってストレスがかかる事であったと思われるが看護師がじっくりと落ち着いて関わりをもった事がA氏にとって良い刺激になり心地良い程度のストレスになっていたのかも知れない。 「セルフケア」は変化が無く「社会生活の技能」に関しては普通状態から障害がある方向へと悪くなっている。担当看護師とA氏で小遣い管理などについて話し合い、その場ではA氏は理解出来て決めた計画を毎日継続していくのは困難であり、現実検討能力の低さや認知・学習障害(融通の利かなさ)が現れていた。状況によって分り易く説明し、決めた事を継続出来るよう関わりをもつ事が必要である。 A氏とに関わりから患者の訴えを傾聴し、共感的態度を示し信頼関係を築く事が改めて大切であると感じ_丸1_患者と共に入院生活のあり方や看護計画(患者目標)を話し合い、援助する事が大切である _丸2_看護師は患者の持っている能力の可能性を信じ継続した援助をしていく事が重要である事を学んだ。
1 0 0 0 OA 長岡安平の官歴を中心とした経歴区分による設計業績の変遷について
- 著者
- 浦﨑 真一
- 出版者
- 公益社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.5, pp.407-412, 2014 (Released:2015-05-22)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 3 5
Consideration of Yasuhei Nagaoka’s design achievements clarifies the relationship between the designer’s employment position, the places where he carried out his work, and the number of designs by classifying the different phases of his career. His career is classified and his employment positions clarified by arranging his design achievements according to the places where he carried out his design work during specific periods of time. This classification indicates that he had almost no achievements during the more than 20 years he was employed at the Tokyo prefectural government office. When he became part of the professional staff of the Tokyo City office, the classification reveals that he designed for many places. His achievements for Akita in his later years as a member of staff at the Tokyo prefectural office greatly influenced this thing. The quantity of the park design of each place decreased when Nagaoka resigned from the Tokyo City office. He was continually involved with the design of many personal gardens, but his achievements in the suburbs of Tokyo came to account for most. In addition to his park designs, he designed the personal gardens of distant places as well. However, it is predicted that this reduced the number of his garden designs of distant places, as is evident in the decreasing number of his park design projects.
1 0 0 0 OA 長岡安平の公園設計書にみる着眼点の傾向と設計思想
- 著者
- 浦﨑 真一
- 出版者
- 公益社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.5, pp.413-418, 2015 (Released:2015-12-22)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1 2
This study clarifies Yasuhei Nagaoka’s design concepts by examining specifications for six of his parks. It compares the parks by extracting the focus of the design policy and instructions and classifying both the instructions and the intentions for those instructions. Instructions were able to be classified into seven types, and intentions for instructions were able to be classified into eight types. These analyses clarified the idea that Nagaoka regarded how visitors would use the park as the most important consideration while respecting the natural landforms and view. He also took into consideration the scenic beauty and convenience as well as making artificial elements inconspicuous, if possible, when designing park facilities. The importance of enjoying scenery or using park facilities changes the design specifications, depending on the location and history of the park. The comparison of specifications for six parks enabled a cross-sectional and concrete verification. This study provides a new understanding of Nagaoka’s thoughts about park design.
1 0 0 0 OA 腰椎手術後疼痛症候群に対する後仙腸靱帯ブロックの効果に関する後方視的検討
- 著者
- 松本 園子 光畑 裕正
- 出版者
- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会
- 雑誌
- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.4, pp.318-324, 2017-10-25 (Released:2017-11-08)
- 参考文献数
- 14
腰椎手術後に再度腰痛・下肢痛が出現する腰椎手術後疼痛症候群(failed back surgery syndrome:FBSS)の治療には苦慮することが多い.今回当院外来でFBSS患者での難治性腰下肢痛に対する後仙腸靱帯ブロックの有効性を検討した.2010年4月~2016年3月の6年間に当科に初回受診したFBSS患者64症例のうち,仙腸関節関連痛と認められた55症例について後仙腸靱帯ブロック後の数値評価スケール(numerical rating scale:NRS)の経時的変化,罹患期間,罹患部位,下肢痛の有無などについて検討した.初診時FBSSと診断した64例中,仙腸関節関連痛と認められた55症例について後仙腸靱帯ブロックのみで痛みが軽減した症例は85.5%(47/55)であった.罹患期間は中央値18カ月で,腰痛だけでなく下肢痛を伴う症例が68.1%(32/47)であった.NRSは経時的に有意に低下した.1回のブロックで50%以上のNRS改善を示した症例は53.2%(25/47)であった.後仙腸靱帯ブロックはFBSSの治療に対して有意に疼痛を軽減し,診断的ブロックとしても治療としても有効であり,FBSSには少なくない割合で仙腸関節関連痛が含まれていた.