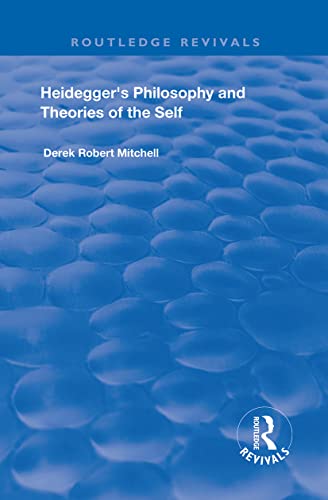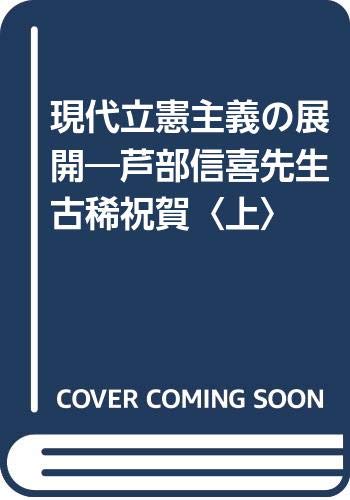1 0 0 0 OA プロセスフィードバックが動機づけに与える影響 —制御焦点を調整変数として—
- 著者
- 外山 美樹 湯 立 長峯 聖人 三和 秀平 相川 充
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.321-332, 2017 (Released:2018-02-21)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 10 8
本研究の目的は, ポジティブなプロセスフィードバック(以下, PosiProFB)とネガティブなプロセスフィードバック(以下, NegaProFB)が受け手の動機づけに与える影響において, 制御焦点が調整変数となりうるのかどうかを検討することであった。実験参加者は大学生64名であった。本研究の結果より, プロセスフィードバックが受け手の動機づけに及ぼす影響は, 制御焦点によって異なることが示された。促進焦点の状況が活性化された場合には, NegaProFBよりもPosiProFBが与えられた方が次の課題への努力が高く, 課題への興味が向上することが示された。一方で, 防止焦点の状況が活性化された場合には, 逆に, PosiProFBよりもNegaProFBが与えられた方が次の課題への努力が高く, 課題への興味が向上することが示された。また, 自由時間中の課題従事の有無においては, 制御焦点およびフィードバックの影響が見られなかった。獲得の在・不在に焦点が当てられている促進焦点は, PosiProFBが与えられた時に制御適合が生じる一方, 損失の在・不在に焦点が当てられている防止焦点は, NegaProFBが与えられた時に制御適合が生じ, その結果, 動機づけ(次の課題への努力, 課題への興味)が高まるものと考えられる。
1 0 0 0 鉄道工場
- 著者
- 交通資料社
- 出版者
- レールウエー・システム・リサーチ
- 巻号頁・発行日
- vol.12(4), no.127, 1961-04
- 著者
- Derek Robert Mitchell
- 出版者
- Routledge
- 巻号頁・発行日
- 2021
1 0 0 0 OA SHとSSの生化学
- 著者
- 高木 俊夫
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.5, pp.332-342, 1977-05-01 (Released:2010-04-23)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 1
Various organic compounds containing SH and/or SS are found in organisms, and are playing important roles to maintain life. In this review, the nature of the groups and their reactions of biological importance are described surrounding following topics : evolution of hydrogen sulfide from boiled egg, disulfide interchange, stereostructure of disulfide group, thioester linkage and its biological significance, role of acyl carrier protein, and metallothionein.
1 0 0 0 OA 探訪記 齋藤實展~その人と時代~
- 著者
- 堀内寛雄
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 参考書誌研究 (ISSN:18849997)
- 巻号頁・発行日
- no.58, 2003-03-25
1 0 0 0 OA 社会的フレイルの指標に関する文献レビューと内容的妥当性の検証
- 著者
- 阿部 紀之 井手 一茂 渡邉 良太 辻 大士 斉藤 雅茂 近藤 克則
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.24-35, 2021-01-25 (Released:2021-02-25)
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 1
目的:社会的フレイルはリスク因子として重要だが,評価法が統一されていない.本研究の目的は専門家の評価による内容的妥当性のある社会的フレイルの要素を明らかにすることである.方法:PubMedで検索し入手した社会的フレイル関連26論文から抽出した要素のうち,7名中5名以上の評価者が4条件(負のアウトカム予知因子,可逆性,加齢変化,客観性)を満たすと評価した要素を抽出し分類した.結果:4条件を満たす要素は経済的状況(①経済的困難),居住形態(②独居),社会的サポート(③生活サポート者の有無,④社会的サポート授受),社会的ネットワーク(⑤誰かと話す機会,⑥友人に会いに行く,⑦家族や近隣者との接触),社会的活動・参加(⑧外出頻度,⑨社会交流,⑩社会活動,⑪社会との接触)の5分類11要素が抽出された.結論:先行研究で用いられている社会的フレイル22要素のうち,内容的妥当性が示唆された要素は11要素であった.
1 0 0 0 OA 外国人学習者の日本語アクセント・イントネーション習得(第二言語習得,<特集>音声の獲得)
- 著者
- 鮎澤 孝子
- 出版者
- 日本音声学会
- 雑誌
- 音声研究 (ISSN:13428675)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.47-58, 2003-08-30 (Released:2017-08-31)
This paper reviews research papers published since 1990 on the acquisition of the Tokyo accent and intonation by foreign learners of Japanese. Intonation studies examined in this paper were mainly focused on the acquisition of sentence final pitch patterns for interrogative sentences in Japanese. As for accent acquisition studies, both production and perception studies were analyzed. With the surprising improvements of computer technology in recent years, it is expected that a great amount of progress could be done in research on the acquisition of accent and intonation in the future.
- 著者
- 鈴木 明 山名 善之
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.759, pp.1271-1277, 2019 (Released:2019-05-30)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1 1
Le Corbusier’s Modulor is a theory of dimension and scale for architects. The Modulor replaced the dimensional standards, principles of Purism, and tracés régulateurs used in achieving the “machine aesthetic” advocated by Le Corbusier during the 1920s, and it brought harmony to both the interior and exterior of buildings such as the postwar Unité d’Habitation in Marseille, the Cabanon, and works of religious architecture. Why does the Modulor’s human figure raise its left arm? Despite the wide dissemination of this distinctive posture and physique, what role the human figure played in the Modulor research, and what it brings to the theory, remains unknown. The human figure in the Modulor is not merely a diagram or explanation of the theory, but also at the heart of the theory. In this paper, by tracing mutual adjustments between theory and bodily expression (part and posture) at each stage of the formation of the theory, we argue that there was a deliberate transition in graphic representation. Next, the freedom of behavior attained by the Modulor's “arm-raising body” in comparison with the “mechanical body” of modern aesthetics, mathematicians and architects, was a criticism of the efficiency of diagrammatic representations of the human body. The standards that motivated the Modulor research arose from the modern knowledge that supported mass production and allowed its distribution across languages and national boundaries. It is shared by Le Corbusier's advocacy of “machines for living” and his artistic movement Purism, as well as modern art in general, including the Bauhaus and other architectural movements. But under the “total warfare” policy of the Nazi regime in Germany, Neufert-based standards were adopted not only in ordinary mass housing, but also for maximum efficiency in the planning of concentration camps, and for forced labor by national prisoners of war. The expression of the body in the Modulor made diverse and free behavior possible through a relaxation of the whole body. The posture of raising the right arm indicates the height of the space unavailable for labor/production. Such a posture is irrelevant to functionalist thinking and efficiency-oriented human understanding. However, for architects it is an everyday attitude, a posture that confirms the height of the ceiling. With this posture the Modulor critiqued the mechanical body, including the Neufert body, and discovered a free space that cannot be grasped by spatial concepts and may be considered a meaningful space. The purpose of this paper is to use these issues to clarify the function and role of the human figure in the formation of the theory of the Modulor.
1 0 0 0 現代立憲主義の展開 : 芦部信喜先生古稀祝賀
- 著者
- 樋口陽一 高橋和之編集代表
- 出版者
- 有斐閣
- 巻号頁・発行日
- 1993
1 0 0 0 OA わかるとは
1 0 0 0 OA 罫線・升目と幼児文字の書字パターン
- 著者
- 高橋 敏之
- 出版者
- 日本教科教育学会
- 雑誌
- 日本教科教育学会誌 (ISSN:02880334)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.4, pp.17-26, 1998-03-25 (Released:2018-05-08)
文字の習得は,小学校に就学してから国語科教育において体系的に指導されるようになる。これに対して描画活動は,通常1歳前後にスクリブルから自発的に始まる。しかし,writingもdrawingも平面における描出行為であり,起源は同じである。例えばギリシャ人は,グラフオという言葉で両者を一括していたと言われている。それが,絵,絵文字,文字という歴史が示すように,文字と絵はそれぞれの専門性が徐々に進み,現在では別個の物として扱われ,認識されている。したがって,文字を書く(write)ことは国語教育で指導・研究され,絵を描く(draw)ことは美術教育で指導・研究されるのが,現在は常識になっている。本研究は,幼児が正しい文字記号を習得する前段階に創作する前文字図形を対象にしている。この「幼児文字」が,国語教育と美術教育の間を埋める重要な手がかりを与えると考える。本論では,罫線・升目と幼児文字の関連性を考察した。
1 0 0 0 ホテルマン必携 : 近代経営下のホテル業務の詳解
1 0 0 0 OA 国際聯盟日支紛争調査委員会報告書
1 0 0 0 渋沢栄一伝記資料
- 著者
- 竜門社 編
- 出版者
- 渋沢栄一伝記資料刊行会
- 巻号頁・発行日
- vol.第45巻 (社会公共事業尽瘁並ニ実業界後援時代 第16), 1962