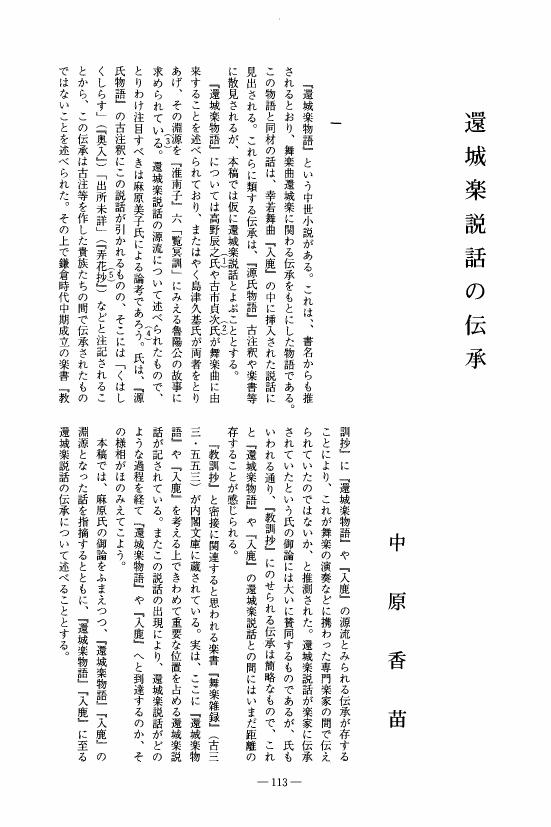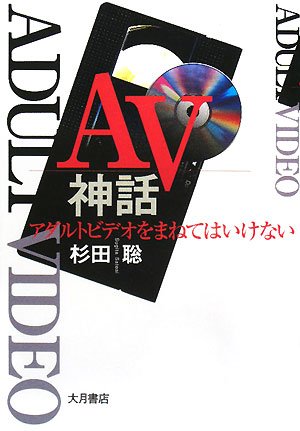- 著者
- Yusaku MORITA Koji KANDABASHI Shigeyuki KAJIKI Hiroyuki SAITO Go MUTO Takahiro TABUCHI
- 出版者
- National Institute of Occupational Safety and Health
- 雑誌
- Industrial Health (ISSN:00198366)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.4, pp.360-370, 2022-05-11 (Released:2022-08-01)
- 被引用文献数
- 2
This study evaluated the relationship between occupational injury risk and gig work, which included the exchange of labor for money between individuals or companies via digital platforms. As Japan has experienced a severe economic decline during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, an increasing number of individuals have engaged in gig work. While few studies have evaluated occupational risks in gig work, several traffic accidents associated with food delivery gig work have been reported in the mass media. In this study, 18,317 individuals completed an internet survey that collected information pertaining to their involvement in gig work and experience of related occupational injuries; data regarding several confounding factors were also recorded. Multiple logistic regression analysis showed that workers involved in gig work had a greater risk of any minor occupational injuries (odds ratio, 3.68; 95% confidence interval, 3.02–4.49) and activity-limiting injuries (odds ratio, 9.11; 95% confidence interval, 7.03–11.8) than those not involved in gig work, after adjusting for age, sex, household income, lifestyle factors, and work-related factors. The results of this study indicate that gig workers are exposed to greater occupational hazards during the COVID-19 pandemic. Additional studies are warranted to clarify the causal mechanism for this relationship.
- 著者
- Hyeon-Mi Park Nobukazu Nakasato Teiji Tominaga
- 出版者
- Tohoku University Medical Press
- 雑誌
- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)
- 巻号頁・発行日
- vol.226, no.3, pp.207-211, 2012 (Released:2012-02-21)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 17 22
The insula, one of the five cerebral lobes of the brain, is located deep within the brain and lies mainly beneath the temporal lobe. Insular epilepsy can be easily confused and misdiagnosed as temporal lobe epilepsy (TLE) because of the similar clinical symptoms and scalp electroencephalography (EEG) findings due to the insula location and neuronal connections with the temporal lobe. Magnetoencephalography (MEG) has higher sensitivity and spatial resolution than scalp EEG, and thus can often identify epileptic discharges not revealed by scalp EEG. Simultaneous scalp EEG and MEG were performed to detect and localize epileptic discharges in two patients known to have insular epilepsy associated with cavernous angioma in the insula. Epileptic discharges were detected as abnormal spikes in the EEG and MEG findings. In Patient 1, the sources of all MEG spikes detected simultaneously by EEG and MEG (E/M-spikes) were localized in the anterior temporal lobe, similar to TLE. In contrast, the sources of all MEG spikes detected only by MEG (M-spikes) were adjacent to the insular lesion. In Patient 2, the sources of all MEG spikes detected simultaneously by EEG and MEG (E/M-spikes) were localized in the anterior temporal lobe. These findings indicate that MEG allows us to detect insular activity that is undetectable by scalp EEG. In conclusion, simultaneous EEG and MEG are helpful for detecting spikes and obtaining additional information about the epileptic origin and propagation in patients with insular epilepsy.
1 0 0 0 OA 呼吸器リハビリテーションでのオンライン診療の可能性
- 著者
- 長谷川 高志
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.185-189, 2022-04-28 (Released:2022-04-28)
- 参考文献数
- 7
1990年代半ばから遠隔医療の実用化が進み,専門医が他の医師を支援する遠隔画像診断,遠隔から患者を診察するオンライン診療や遠隔モニタリングなどが発展した.Doctor to Doctor(DtoD)形態の遠隔画像診断では診療画像等の共有により専門医の指導を行い,医師偏在地域でも高度な診療が可能になる.オンライン診療などのDoctor to Patient(DtoP)形態で,テレビ電話による診察や心臓ペースメーカー等のデバイスの遠隔モニタリングで慢性疾患患者の診療を行う.継続すべき診療からの脱落の抑制,予後改善等の効果がある.医師法や医療法下での適正な診療の実施,診療報酬制度による安定した運営などは整備途上である.ICTならではの新形態の診療手法の出現も考えられ,制度整備の課題は広がっている.呼吸ケアのリハビリテーションには,オンライン診療など遠隔医療のみ可能な「持続のための診療手法」が有効であり,推進には医療技術の定量的な評価の確立が重要である.
1 0 0 0 OA <資料>青木ケ原樹海における自殺未遂について:予備調査
- 著者
- 高橋 祥友
- 出版者
- 山梨医科大学医学会
- 雑誌
- 山梨医科大学雑誌 = 山梨医科大学雑誌 (ISSN:09120025)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.23-28, 1986
青木ケ原樹海は,自殺が多発する地域として有名であるが,これまでその詳細についての報告はなかった。昭和57年から59年の3年間における同地域での自殺未遂116例につき,山梨県警察富士吉田警察署の資料を基に情報を収集し分析することにより,同地域における現在の危機介入の実態を把握し,その改善に役立てる目的で今回の調査を実施した。青木ケ原樹海での自殺未遂について幾つかの特徴が見出されたが,そのなかでも特に次の点が注目された。1) 自殺既遂者数から推定される自殺未遂者数に比し,実際に保護下におかれる自殺未遂者数が極めて低い。2) 自殺未遂者中の男女比は2.9対1と一般に言われている傾向とは逆転していた。3) 他者に対する敵意の表出に乏しく自己の消滅や静かな死を望む傾向がみられた。4) 現時点における危機介入はほとんどが警察の手にゆだねられており,短時間のうちに家族のもとへ自殺未遂者を戻すことに終わっており,精神医学的介入は皆無に近かった。自殺未遂者が,将来既遂に終わる危険は,一般人口に比べてはるかに高く,現在までの警察主体の危機介入に加えて,今後積極的な精神医学的介入が必要と考える。
1 0 0 0 OA 化粧水の使い心地に関する官能値と物性値との関係性
- 著者
- 武井 秀仁 齋竹 隆貴 高橋 正人
- 出版者
- 日本感性工学会
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.215-223, 2022 (Released:2022-04-28)
- 参考文献数
- 10
When performing sensory evaluation, it is necessary to consider not only using a lot of time and cost but also human factors such as stress of subjects. This study focused on solution viscoelasticity and peel force. In order to link above properties with sensory values, we performed sensory evaluation for subjects to various samples with different properties. The obtained sensory values were averaged to exclude influences of individual differences, and the correlation between the obtained sensory values and measured properties was investigated. As the results, high correlation was obtained between sensory properties about “moist”, “refresh”, “smooth”, and “sticky”. Also, high correlation was obtained between sensory properties about “sticky” and “skin familiarity” and the maximum value of peel force measured during 50 cycles of measurements. Therefore, when evaluating skin feeling of skin toner, it may be possible to substitute skin feelings to the evaluation of solution viscoelasticity and maximum peel force.
- 著者
- 松本 悠貴 内村 直尚 石田 哲也 豊増 功次 久篠 奈苗 森 美穂子 森松 嘉孝 星子 美智子 石竹 達也
- 出版者
- 公益社団法人 日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.5, pp.128-140, 2014 (Released:2014-10-18)
- 参考文献数
- 55
- 被引用文献数
- 6 6
目的:ピッツバーグ睡眠質問票(PSQI)に代表される睡眠尺度の多くは,実際の睡眠時間や日中の眠気といった量的問題や,睡眠の維持・導入といった質的問題を捉えてある.それらに加えて,24時間型社会となった今日では起床時刻・就寝時刻といった位相の問題まで視野に入れていく必要があり,かつ睡眠の位相・質・量のいずれに問題があるのかを把握するためには各々に測定・評価しなければならない.そこで我々は位相・質・量の3つの睡眠関連問題について測定する3次元型睡眠尺度(3 Dimentional Sleep Scale; 3DSS)の日勤者版を開発した.本研究はその信頼性・妥当性を検証することを目的とする.対象と方法:対象は製造業およびサービス業に従事する日勤労働者635名(男性461名,女性174名)で,平均年齢は40.5歳であった.質問紙は全17項目から成り,事前研究結果および専門家との討議を参考に睡眠の位相・質・量に関する質問を設定した.回答偏向分析後,探索的および確認的因子分析を行った.信頼性はクロンバックα信頼性係数を算出して求め,尺度の得点化・上位-下位分析を行った.仮説検定ではPSQIおよびSDSより位相・質・量それぞれに関連した項目を抜粋し,3DSSの各尺度得点との相関をみて収束的妥当性および弁別的妥当性の検証を行った.また,PSQIの総合点と3DSSの各尺度得点との相関についても検証を行った.結果:回答偏向分析にて回答に大きな偏りはみられなかった.探索的因子分析の結果2項目が削除されたが3つ因子が抽出され,位相に関する質問5項目,質に関する質問5項目,量に関する質問5項目の計15項目となり,確認的因子分析においても15項目モデルの方が適合度が高かった.α 信頼性係数は下位尺度毎では位相 = 0.685,質 = 0.768,量 = 0.717であった.仮説検定では,収束的妥当性については仮説がすべて採択された.弁別的妥当性については新尺度および既存尺度の質尺度と量尺度の間で仮説をやや上回る相関がみられていた.PSQIの総合点と3DSSの各尺度得点との相関についてもすべて仮説が採択された.考察:本研究において,我々の開発した3次元型睡眠尺度(3DSS)の日勤者版について,日勤労働者を対象として使用するにあたり,必要と考えられる信頼性・妥当性が示された.今後さらに対象者数を増やし調査を重ねることで尺度の標準化およびカットオフ値の設定を行っていきたい.
1 0 0 0 OA ケニア西部におけるガンビエハマダラカ繁殖場所の物理化学的特性
- 著者
- 都野 展子 石田 幸恵 矢吹 彬憲
- 出版者
- 日本衛生動物学会
- 雑誌
- 日本衛生動物学会全国大会要旨抄録集 第63回日本衛生動物学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.47, 2011 (Released:2014-12-26)
サハラ以南アフリカで主要なマラリア媒介蚊である2種Anopheles gambiae とAn. arabiensisの幼虫繁殖場所の生産性を決める環境要因は何かについて近年研究が進められている.従来よりこの2種の幼虫繁殖場所の特徴は、短命な浅い水溜りであることが認識され報告されてきていたが、Tunoら(2006)は緑藻類(特にRhopalosolensp.)が幼虫の餌として重要であることを示した.本研究は、Anopheles gambiaeとAn.arabiensisの2種の幼虫の生息する水体に発生する他の生物群集を評価しながら、その水体の特徴、とりわけ藻類とその水体の物理化学的特徴を評価し、生物的・無生物的な環境変量と幼虫個体数の関係を解明することを目的として、本研究を行った.方法:ケニア西部の水溜りから、水を採集し、動物群集・生産者である藻類群集・水体サイズ・陽イオン成分・陰イオン成分・酸素同位体比δ18Oなど物理化学的な特徴を調査した.結果:調査に費やした2008年と2009年で水溜りの性質はかなり異なっていた.2008年は水溜りが出来るのを見ながら採水を進め、2009年は乾いていく水溜りからの採水となった.δ18O値の性質や実用性を検証した結果,δ18O値は降雨以外に、水体の個性(形状・土壌の質・水の供給源)に影響されているとわかった.ガンビエ幼虫に関係するさまざまな環境要因は水の古さによって大きく異なった.2008年の新しく出来た水溜りのみ、卵に乾燥耐性がある種が見られ、2009年の長期間存在していた水溜りでは、甲虫目や半翅目など比較的成長に時間がかかる種が多く存在していた.考察:ガンビエ幼虫密度と環境要因の結果では、生産者との関係として、水の古さにより幼虫密度と重要な藻類は異なっていたが、Rhopalosolen sp.は両年で重要性が証明された.ガンビエ密度は新しい水体では生産性の高い水体にニッチの近い生物種と同時に発生すると考えられた.古い長期間存在する水体では捕食圧が重要であったことが示唆された.
1 0 0 0 OA 唐朝雲南経営史の研究(其三) : 雲南経営の挫折
- 著者
- 藤沢 義美
- 出版者
- 岩手大学学芸学部
- 雑誌
- 岩手大学学芸学部研究年報
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.23-34, 1958-08
1 0 0 0 OA 磁歪材料を用いた振動発電とアクチュエータの実用化,現状と展望
- 著者
- 上野 敏幸
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.4, pp.305-308, 2013-04-05 (Released:2013-10-05)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 3 4
1 0 0 0 OA 還城楽説話の伝承
- 著者
- 中原 香苗
- 出版者
- 中世文学会
- 雑誌
- 中世文学 (ISSN:05782376)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.113-122, 1996 (Released:2018-02-09)
1 0 0 0 OA 世代間所得移動と階層帰属意識の趨勢分析
- 著者
- コン アラン
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.1, pp.2-18, 2021 (Released:2022-06-30)
- 参考文献数
- 32
本研究は,世代間所得移動が階層帰属意識に対してもつ影響を1955年から2015年までのSSM調査(社会階層と社会移動全国調査)データを用いて,時系列的に検証したものである.世代間所得移動の測定には,父親の所得を推定する方法を用いた.検証にあたり,本研究では,①現在の階層的地位のみが階層帰属意識を決定するという「絶対地位仮説」,②上昇(下降)移動は相対的満足感(剝奪感)を与え,階層帰属意識を高める(低める)という「相対地位仮説」,③上昇(下降)移動しても,過去の低い(高い)階層的地位の影響が残るため,階層帰属意識を低める(高める)という「慣性仮説」の3つの仮説を提示し,データを用いて検討した.分析の結果,1975年においては世代間所得移動は階層帰属意識に対して正の影響力をもつが,1985年になるとその影響力を失い,2015年,再び統計的に有意な負の影響力をもつことがわかった.この結果,1975年においては「相対地位仮説」,1985年から2005年においては「絶対地位仮説」,2015年においては「慣性仮説」と合致する結果となった.本研究により,世代間所得移動は階層帰属意識に影響しており,その影響力と方向は時代により変化していることが明らかとなった.
1 0 0 0 OA 中国の耐震基準により設計されたRC純ラーメン建物の耐震性評価
1 0 0 0 現代の出版人五十人集
- 出版者
- 出版ニュース社
- 巻号頁・発行日
- 1956
- 著者
- Chanasak Hathaiareerug Suthida Somnam Wipoo Kumnerddee Chanwit Phongamwong
- 出版者
- The Japanese Association of Rehabilitation Medicine
- 雑誌
- Progress in Rehabilitation Medicine (ISSN:24321354)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.20220037, 2022 (Released:2022-07-22)
- 参考文献数
- 28
Objectives: This study aimed to evaluate the diagnostic properties for carpal tunnel syndrome (CTS) of the median-to-ulnar cross-sectional area ratio (MUR) and the median-to-superficial radial cross-sectional area ratio (MRR).Methods: A case–control study was conducted. A physiatrist, blinded to the CTS status of the subjects, assessed the cross-sectional area of the median nerve (CSA-m), MUR, and MRR at the distal wrist crease for the CTS and control groups. The relationship of CSA-m, MUR, and MRR with CTS severity was tested using Spearman’s correlation. The overall diagnostic accuracy was determined using the area under the receiver operating characteristic curve (AUC). The cut-off values to diagnose CTS were chosen to achieve similar values for sensitivity and specificity.Results: There were 32 hands in the CTS group and 33 hands in the control group. The correlations of CSA-m, MUR, and MRR with CTS severity were 0.66, 0.56, and 0.34, respectively. The AUCs of CSA-m, MUR, and MRR were 0.86 (95%CI: 0.77–0.95), 0.79 (0.69–0.90), and 0.69 (0.56–0.82), respectively. The cut-off values of CSA-m, MUR, and MRR were 12 mm2 (sensitivity, 81.3%; specificity, 81.8%), 2.6 (sensitivity, 68.8%; specificity, 69.7%), and 10 (sensitivity, 65.6%; specificity, 63.6%), respectively.Conclusions : MUR and MRR had acceptable diagnostic abilities but did not show superiority over CSA-m for CTS diagnosis.
1 0 0 0 OA 脳と精巣の機能ネットワークの解明
生殖細胞である精子形成のメカニズムに関して不明な点が多く残されている。本研究では、カルシウムが精子形成を制御する可能性を検討するために、イメージングや光遺伝学などの細胞活動操作技術を応用し、脳活動を操作したときの精巣細胞のカルシウム活動をリアルタイムで観察・操作できるin vivo実験系の開発を目指した。成果として、マウス精巣においてin vivoカルシウムイメージング法を新規に開発し、in vivoで細胞のカルシウム活動を1細胞レベルかつ多色でイメージングすることが可能となった。また精巣においてカルシウム活動を駆動しうる分子を見出し、カルシウム活動が精子形成に関与する可能性を見出した。
1 0 0 0 OA 人工光型植物工場における赤青LEDと蛍光灯使用時の植物成長および消費電力の評価
- 著者
- 大竹 範子 米田 正 鈴木 廣志
- 出版者
- 日本生物環境工学会
- 雑誌
- 植物環境工学 (ISSN:18802028)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.213-218, 2015-12-01 (Released:2015-12-01)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 11 7
植物工場のリーフレタス生産における赤青LED交互連続照射法(SHIGYOTM法)の生育促進効果および照射時間の効果を評価した.一般的な明暗周期(明期16時間,暗期8時間)だけでなく,24時間連続照射の対照区(赤青LED同時照射区,蛍光灯照射区)と比較しても,同じ栽培期間あたりのSHIGYO法区の可食部生体重が有意に大となり,生育が促進されることがわかった.さらにSHIGYO法では収穫サイズになるまでの生育日数短縮効果により年間栽培回数を増大できる.LEDと蛍光灯の消費電力の比較から,植物栽培においてLEDを使用すると1株あたりの消費電力量が低いことがわかった.これらの結果は,今後より効率的な植物工場運営に貢献できるものと期待される.
1 0 0 0 OA 地球温暖化問題を考える(その3) : 太陽活動の変化にともなう気候変動
- 著者
- 秋山 雅彦
- 出版者
- 地学団体研究会
- 雑誌
- 地学教育と科学運動 (ISSN:03893766)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, pp.33-42, 2009-07-23 (Released:2018-03-29)
- 参考文献数
- 38
1 0 0 0 AV神話 : アダルトビデオをまねてはいけない
1 0 0 0 OA 四日市製紙専用鉄道の吊橋-富士橋の再評価
- 著者
- 森 陽子 望月 清 樋口 輝久 馬場 俊介
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木史研究論文集 (ISSN:13495712)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.45-57, 2004-06-15 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 50
Fuji-bashi, completed in 1915 over the Fuji River in Sizuoka Prefecture, is probably the longest span suspension bridge as well as only one railway suspension bridge in Japan before the World War II. However it's existence has been forgotten for a long time. The reason of oblivion will be as follows; that is, it was constructed by a private paper-manufacturing company, and it was used only four years until it was destructed in the stormy night with intent to save disaster. The purpose of this paper is to regain its reputation, and try to emphasize that Fuji-bashi is one of the important structures in the history of civil engineering of the modernized era in Japan. The paper contains lots of original data concerning its construction.