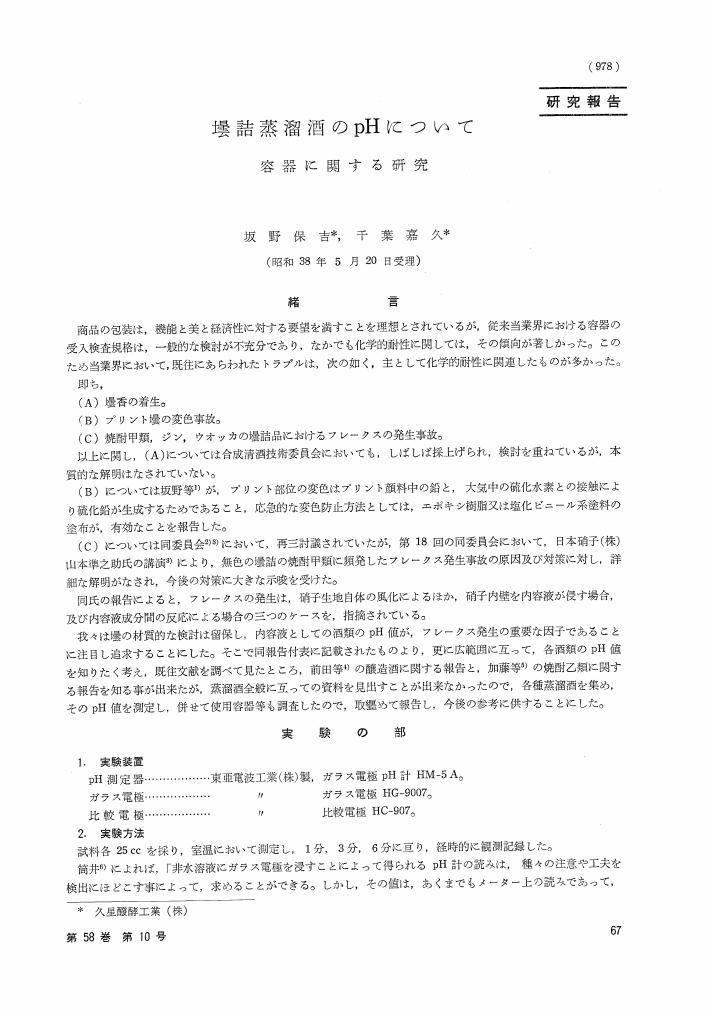8 0 0 0 OA P1-34 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: ME/CFS)におけるB細胞異常の解析
- 著者
- 小野 紘彦 佐藤 和貴郎 中村 雅一 山村 隆
- 出版者
- 日本臨床免疫学会
- 雑誌
- 日本臨床免疫学会会誌 (ISSN:09114300)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.4, pp.306b, 2017 (Released:2017-11-25)
【背景】筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)は著しい疲労に加え,認知機能障害や睡眠障害など様々な神経症状が生じる深刻な慢性疾患である.近年ノルウェーからリツキシマブによるB細胞除去療法の有効性が報告されたが,ME/CFSにおける末梢血リンパ球についての知見は乏しく,なぜB細胞除去療法が治療効果を発揮するか不明である.【目的】ME/CFS患者の末梢血中のB細胞異常を明らかにする.【方法】対象はカナダ基準およびInternational consensus criteriaを共に満たす患者40人と年齢,性別をマッチさせた健常者20人とした.末梢血から末梢血単核球細胞を分離し,B細胞受容体(BCR)レパトア解析とフローサイトメーターを用いたB細胞サブセット頻度及び機能分子発現の解析を行った.【結果】BCRレパトア解析では患者群において多様性指数であるNormalized shannon indexとクローナリティーの指数であるDE50が低い傾向があり,多様性の減少およびクローナリティーの増加がみられた.リンパ球サブセット解析では,患者群と健常者群で比較すると,B細胞では患者群においてplasmablastが低下し(p = 0.04),一部の患者でCD80の発現が亢進していた.【結論】ME/CFSの末梢血においてB細胞の異常が認められた.免疫異常とME/CFSの病態との関わりについてさらなる研究が必要である.
- 著者
- 前田 亮介
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, no.9, pp.1560-1569, 2011-09-20 (Released:2017-12-01)
8 0 0 0 OA 1950~60年代のテレビ・ドキュメンタリーが描いた朝鮮のイメージ
- 著者
- 丁 智恵
- 出版者
- 日本メディア学会
- 雑誌
- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, pp.111-131, 2013-01-31 (Released:2017-10-06)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
This research examines how the image of the Other excluded from "national memory" was represented in Japanese television documentaries of the 1950s and 1960s as well as clarifies how intellectuals, journalists, and filmmakers had to resist the contradiction and incoherence of linking "public memory" with "national memory." After World War II, Japan's political, economic and social systems, which had maintained continuity before and during the war, were shaken substantially. Japanese recognition of their role in the war as promoted by the American General Headquarters lacked awareness of the perspective of the Asian nations Japan colonized. Nevertheless, critical television documentaries were made one after another during this time. This paper first examines how Asia's political, economic, and social history as well as changes in the skills and techniques necessary for making television programs influenced the representation of Korea in television documentaries. It then examines the changes in said representation by analyzing program images and interviewing the directors of several television documentary programs. First is Nihon no Sugao: Nihon no Naka no Chosen [The Real Japan: Korea in Japan] (1959: NHK), which was the first television documentary after the end of the war to focus on Koreans in Japan (Zainichi). Second is Daitokai no Ama [Women Divers in the Big City] (1965: Asahi Broadcast), which was made by Japan's first Korean television director. Finally, some documentary programs which portray Korean soldiers who were mobilized as part of the Japanese Army during the war are studied, including Wasurerareta Kogun [Forgotten Imperial Soldiers] (1963: Nihon Broadcast) , directed by Nagisa Oshima. Based on the findings of this study, I concluded that few documentary programs focused on Korea in the early days of television in Japan; however, those that did exist expressed some signs of responsibility for Japanese imperialism and colonialism in Korea.
8 0 0 0 OA 欧米主要国の議会による情報機関の監視
8 0 0 0 OA 統計数学と制御数学 モスクワとレニングラード
- 著者
- 北川 敏男
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.17-22, 1967-04-01 (Released:2008-12-25)
8 0 0 0 OA モノアミントランスポーターの薬理学
- 著者
- 土肥 敏博 北山 滋雄 熊谷 圭 橋本 亘 森田 克也
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, no.5, pp.315-326, 2002 (Released:2003-01-28)
- 参考文献数
- 55
- 被引用文献数
- 6 6
神経終末から放出されたノルエピネフリン(NE),ドパミン(DA)およびセロトニン(5-HT)は,それぞれに固有の細胞膜トランスポーター(NET,DAT,SERT)によりシナプス間隙から速やかに除去されて神経伝達が終息される.さらにこれらのモノアミンはシナプス小胞トランスポーター(VMAT)によりシナプス小胞内に輸送·貯蔵され再利用される.NET,DAT,SERTはNa+,Cl−依存性神経伝達物質トランスポーター遺伝子ファミリーに,VMATはH+依存性トランスポーター遺伝子ファミリーに属する.また選択的RNAスプライシングにより生じるアイソフォームが存在するものもある.NET,DAT,SERTは細胞膜を12回貫通し,細胞内にN末端とC末端が存在する分子構造を有すると予想される.近年,トランスポーターの発現は種々の調節機構により誘導性に制御されていると考えられるようになった.例えば,kinase/phosphataseの活性化によりその輸送活性あるいは発現が修飾され,トランスポータータンパク質あるいは相互作用するタンパク質のリン酸化による調節が考えられている.また,トランスポーターの発現は神経伝達物質それ自身の輸送活性に応じて調節されることやアンフェタミンなどの輸送基質あるいはコカインなどの取り込み阻害薬による薬物性にも調節されることが示唆されている.NET,DAT,SERTは抗うつ薬を始め種々の薬物の標的分子であることから,うつ病を始めとする様々な中枢神経疾患との関わりが調べられてきた.近年,遺伝子の解析からもその関連性が示唆されてきている.これまで抗うつ薬は必ずしも理論に基づき開発されたものばかりではなかったが,これらトランスポーターのcDNAを用いた発現系により,これまで検証できなかった多くの問題が分子レベルで詳細に検討されるようになった.その結果,多くの精神作用薬のプロフィールが明らかになったばかりでなく,より優れた,理論的に裏打ちされた多様な化学構造の新規治療薬の開発が可能となった.
8 0 0 0 OA A・グラムシにおける規律と「ヘゲモニー」
- 著者
- 金山 準
- 出版者
- 北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院
- 雑誌
- 国際広報メディア・観光学ジャーナル
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.25-44, 2009-09-01
The aim of this article is to reconsider the relation between bios (the cultural and social life) and zoe (the biological life), dealing with the political thoughts of Antonio Gramsci. As is well known, his major interest is the cultural power ruling in the civil society. The notion of "hegemony" has had a great influence over the social sciences of the 20th century. But he also devotes a large part of the Prison Notebooks to researching the changes of the biological life in the industrial society (drinking, sexual instinct, etc.). I will reexamine the relation between these two major regions of his thoughts as a form of "individualization".
- 著者
- Rintaro Yokoyama Koichi Haraguchi Kazumi Ogane Seiichiro Imataka Yuki Nakamura Noriaki Hanyu Nobuki Matsuura Kazuyoshi Watanabe Takeo Itou
- 出版者
- The Japanese Society for Neuroendovascular Therapy
- 雑誌
- Journal of Neuroendovascular Therapy (ISSN:18824072)
- 巻号頁・発行日
- pp.cr.2023-0050, (Released:2023-09-30)
- 参考文献数
- 19
Objective: We report a case of near-occlusion of the common carotid bifurcation caused by a giant free-floating thrombus (FFT) successfully treated with mechanical thrombectomy using a large dual-layer stent retriever.Case Presentation: A 51-year-old man presented to our hospital with dysarthria, right hemiparalysis, and paresthesia. MRI revealed an acute infarction of the left cortical watershed zone, and MRA revealed decreased signals in the left common carotid bifurcation. Carotid ultrasonography demonstrated a giant FFT in the left common carotid bifurcation. Angiography revealed a giant thrombus extending from the left common carotid artery (CCA) to the internal carotid artery (ICA) and the external carotid artery. As direct aspiration from both a balloon-guided catheter (BGC) and an aspiration catheter (AC) was ineffective, we deployed a large dual-layer stent retriever from the ICA to the CCA with an AC-connected aspiration pump and retrieved it under manual aspiration through the BGC. The giant thrombus was successfully removed, and complete recanalization was achieved without distal embolisms.Conclusion: Although there is no established treatment for giant thrombi in the carotid artery, mechanical thrombectomy using a large dual-layer stent retriever may be an effective treatment option.
8 0 0 0 OA 国家による監視と日本社会 エドワード・スノーデンが教えてくれたこと
- 著者
- 村田 潔 折戸 洋子 福田 康典
- 出版者
- 一般社団法人 経営情報学会
- 雑誌
- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2017年秋季全国研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.317-320, 2017 (Released:2017-11-30)
2013年6月からエドワード・スノーデンとその協力者によって行われた,米国の情報機関NSAによる無差別大量監視に関する内部告発が社会に与えた影響について,筆者らは2014年10月~11月に, 日本を含む8か国における,大学生を対象としたアンケート調査ならびに聞取り調査を行った。この国際比較研究の結果,「国家による監視」に対する社会的態度において,日本は調査を行った国の中で特異な存在であることが明らかになった。本研究報告ではこの調査結果に基づき,高度情報化が進む日本社会における「国家による監視」に対する人々の態度の特徴を示し,それがプライバシー保護や個人の自由と自律,民主主義のあり方などに対して持つ意味を明らかにする。
8 0 0 0 OA ピアジェ発達段階論の意義と射程
- 著者
- 中垣 啓
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.369-380, 2011-12-20 (Released:2017-07-27)
- 被引用文献数
- 1
本論文の目的は,ピアジェの発達段階論の紹介と解説を通して,認知発達において発達段階を設定することの意義と射程とを明らかにすることであった。まず,ピアジェの知能の発達段階は主体の判断,推論を規定する実在的枠組みである知的操作の発達に基づいて設定されたものであり,知的操作は順序性,統合性,全体構造,構造化,均衡化という5つの段階基準を満たす,認知機能の中でも特権的な領域であることを指摘した。次に,形式的操作期の知的新しさがこの時期の知的操作の全体構造から如何に説明されるか,具体的操作期の全体構造から形式的操作期の全体構造が如何に構築されるかを明らかにすることを通して,形式的操作の全体構造がもつ心理的意味を探った。最後に,ピアジェ発達段階論の意義と射程を理解する一助として,発達心理学の古典的問題である発達の連続性・不連続性の問題,最近の認知発達理論の一大潮流である理論説が提起する認知発達の領域固有性・領域普遍性の問題,そしてこの特集号の編集責任者から提起された形式的操作期の一般性・普遍性の問題を議論した。
8 0 0 0 OA 消費者心理の落し穴 ―催眠商法の誘導テクニック (1) ―
- 著者
- 中谷内 一也
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.66-70, 1993-02-25 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 11
8 0 0 0 OA 昆虫による皮膚炎
- 著者
- 夏秋 優
- 出版者
- 一般社団法人 日本昆虫学会
- 雑誌
- 昆蟲.ニューシリーズ (ISSN:13438794)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.2-11, 2020-03-25 (Released:2021-10-21)
- 参考文献数
- 12
昆虫による皮膚炎は,昆虫由来の毒成分や唾液腺成分に対する刺激性炎症反応,あるいはアレルギー性炎症反応によって生じる.本稿では有害昆虫の中で,刺咬性昆虫であるハチ類やアリ類,サシガメ類,吸血性昆虫であるカ類,ブユ類,ヌカカ類,アブ類,ノミ類,トコジラミ,そして接触性昆虫である毛虫類,甲虫類について概説した.そしてこれら有害昆虫による皮膚炎の治療や予防対策についても述べた.
8 0 0 0 OA 2011 年東北沖超巨大地震が明らかにした超巨大地震の多様性
- 著者
- 小山 順二 都筑 基博 蓬田 清 吉澤 和範
- 出版者
- 北海道大学大学院理学研究院
- 雑誌
- 北海道大学地球物理学研究報告 (ISSN:04393503)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, pp.129-146, 2013-03-19
2011 年3 月11 日マグニチュード9.0 の超巨大地震が東北地方太平洋沿岸をおそった.この地震は過去千年以上にわたる日本付近で発生したどの地震よりも大きな津波を励起し,地震動災害ばかりではなく歴史に残る甚大な津波災害を発生させた.従来,このような超巨大地震が日本付近で発生することは,地震学的に想定されてこなかった.我々は,この超巨大地震の発生を考えるうえで,今まで見過ごされてきた超巨大地震の発生場には二つの異なった特徴があることに気が付いた.それはAlong-dip Double Segmentation(ADDS)とAlong-strike Single Segmentation(ASSS)という異なった地震活動である.我々はこの考えに基づき,世界中で発生した超巨大地震を調べなおし,超巨大地震の発生場を,地震活動の特徴(ADDS/ASSS),地震メカニズム,破壊様式,沈み込み帯の形状,上盤プレートの性質や背弧海盆の活動といった性質から,明らかにする.
8 0 0 0 OA 日本学術会議の「2017年声明」を考える : 歴史的視点から
- 著者
- 杉山 滋郎
- 巻号頁・発行日
- pp.1-37, 2017-07-24
8 0 0 0 OA M10 地震の発生条件:2011 年東北沖地震の新しい知見から
- 著者
- 蓬田 清
- 出版者
- 北海道大学大学院理学研究院
- 雑誌
- 北海道大学地球物理学研究報告 (ISSN:04393503)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, pp.111-128, 2013-03-19
After the 2011 Tohoku-Oki earthquake, the immediate threat of megathrust earthquakes in and around Japan has been suddenly advocated by some researchers. One even points out the possibility of a larger event than ever, an event of Magnitude 10. In this study, we discuss whether an event of M10 will be realistic or not, from not only statistical aspects of earthquake occurrence or macroscopic scaling laws of seismic sources in a conventional manner(e.g., fault size, the amount of slips)but also the diversity of megathrust earthquakes that was revealed after the occurrence of the 2011 Tohoku-Oki earthquake. From a simple extrapolation of seismicity and macroscopic scaling laws, one event of M10 occurs every 500 years all over the world, with its fault length, width and average slip to be 1,200 km, 600 km and 50 m, respectively. The width may not exceed 200 km very much because of the limitation of an elastic region of a plate boundary in a subduction zone. We therefore need either of (1) average slip as large as 100 m or (2) fault length of more than 1,500 km for a possible M10 event. The average slip may be able to exceed 100 m, considering an area of very large shallow slips associated with the 2011 Tohoku-Oki earthquake, but we must take care that this is possible only for an event of the along-dip double segmentation. This type of events is, however, generally adjacent to segments of weak plate coupling with small coseismic slips. In contrast, an event of the conventional along-dip single segmentation may extend its fault into many adjacent segments. A drawback in this case is that the average slip may not exceed 50 m unless there are several segments of very strong plate coupling, resulting in co-seismic slips lager than those with usual events repeating in each segnent. Although a very large strong shallow segment of the double segmentation is a candidate of am M10 event, we cannot find any clear evidence of such a region from the present spatial seismic pattern in the world. The subduction zone in south Chile is the best candidate from its apparent strong plate coupling although it may not occur for a while due to the nearly complete strain release associated with the 1960 earthquake. We consider a very large event will be impossible even if a large portion of subduction zones breaks in the Aleutian trench because of the existence of several segments of weak plate coupling with slow events or aseismic slips in this trench.
8 0 0 0 OA APG 分類体系と植物の進化 横浜国立大学教育学部
- 著者
- 倉田 薫子
- 出版者
- 公益財団法人 地球環境戦略研究機関 国際生態学センター
- 雑誌
- 生態環境研究 (ISSN:13404776)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.53-66, 2020-06-30 (Released:2021-07-22)
- 参考文献数
- 20
8 0 0 0 OA 壜詰蒸溜酒のpHについて 容器に関する研究
- 著者
- 坂野 保吉 千葉 嘉久
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.10, pp.978-981, 1963-10-15 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 7
8 0 0 0 IR 日本語助数詞の範囲 : 名詞と助数詞の連続性
- 著者
- 田中 佑
- 出版者
- 筑波大学大学院博士課程文芸・言語研究科応用言語学コース
- 雑誌
- 筑波応用言語学研究 (ISSN:13424823)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.117-126, 2012
8 0 0 0 OA 3.慢性炎症性脱髄性ポリニューロパチーの診断と治療
- 著者
- 久堀 保 梶 龍兒
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.4, pp.623-628, 1998-04-10 (Released:2008-06-12)
- 参考文献数
- 5
慢性炎症性脱髄性ポリニューロパチーは慢性の経過をとる運動知覚性ニューロパチーの一群で,近位部優位の末梢神経系有髄線維の障害による.診断は,臨床的・病理学的所見や脳脊髄液所見より行われるが,特に電気生理学的所見が重要である.治療は,副腎皮質ステロイドホルモン療法, azathioprine・cyclophosphamideなどの免疫抑制療法,血漿分離療法が一般的であるが,最近免疫グロブリン療法が注目されている.