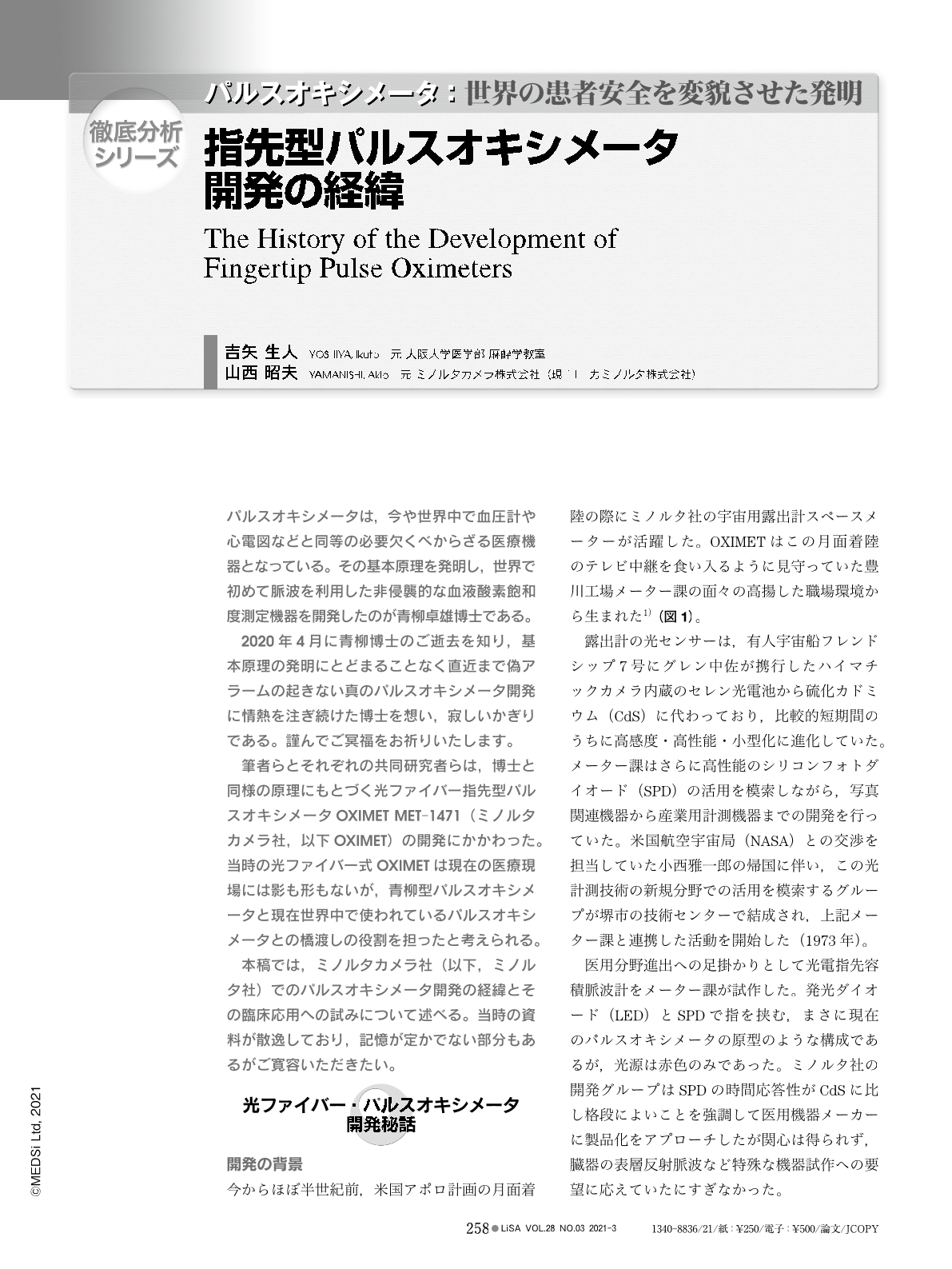1 0 0 0 OA ドライビングシミュレータを用いた トラックの隊列走行に対する一般車両の受容性の評価
- 著者
- 杉町 敏之 橋本 怜 須田 義大
- 出版者
- 公益社団法人 自動車技術会
- 雑誌
- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.5, pp.1121-1126, 2017 (Released:2018-05-15)
- 参考文献数
- 3
現在,高速道路の様な限定された交通環境下において一般車との混在での隊列走行システムの実運用が検討されている.従来存在しなかった短い車間距離で隊列を組む大型トラックの車群が一般車に対して悪影響を与える可能性がある.そのため,ドライビングシミュレータを用いて大型トラックの隊列走行の一般車に対する受容性の評価を行う.
1 0 0 0 IR 張愛玲の映画シナリオ--『不了情』と『太太萬歳』
- 著者
- 白井 啓介 SHIRAI Keisuke
- 出版者
- 中国文化学会(筑波大学文芸言語学系内)
- 雑誌
- 中国文化 (ISSN:02896648)
- 巻号頁・発行日
- no.60, pp.46-59, 2002
1 0 0 0 OA 旅するマトリョーシカ 移動するおみやげのルーツとルート
- 著者
- 鈴木 涼太郎
- 出版者
- 観光学術学会
- 雑誌
- 観光学評論 (ISSN:21876649)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.153-168, 2018 (Released:2020-09-30)
本稿は、ロシアを代表する民芸品として観光客に人気のおみやげマトリョーシカを事例に、観光みやげにかかわる人やモノの移動の連関について考察するものである。これまでの観光研究では、おみやげは当該の観光地で生産されていることが前提とされ、訪れた観光客が自らのホームへとそれを持ち帰る過程や、おみやげになることによって生じる意味や形態の変化に主たる焦点が当てられてきた。しかし実際に観光地で販売されているおみやげの多くは、必ずしも地域固有のものであるとは限らず、生産のプロセスにおいて時間的にも空間的にも様々な越境を経てその場所へとたどり着いた商品であることも少なくない。またおみやげをその「本来の姿」との対比で論じることで、観光という移動のために生産されたモノを規定する論理については十分な検討が行われてこなかった。その結果既存の研究では、おみやげをめぐる複数の移動の経路や、異なる社会的文脈においておみやげが経験する意味や価値の変化の在り方をとらえきれていなかったと考えられる。 それに対して本研究では、マトリョーシカというおみやげを観光客が持ち帰る前の「本来の姿」、いわばそのルーツとの対比で論じるのではなく、マトリョーシカが過去100年余りの時間の中で経験してきた、幕末の日本から20世紀初頭のロシアやフランス、さらに現代の中国やベトナム、マレーシア、そして再び日本へと至る世界規模での一連の移動のルートを素描することを試みた。そこから明らかになったのは、おみやげは観光客の移動のみに付随する現象ではなく、より広範な人やモノ、イメージの移動のネットワークにおける移動の途上で、絶えずその形態や意味を再構成させながら存在するモノだということである。そしておみやげが経験する一連の移動をめぐる考察は、真正なモノ/ニセモノ、ローカルなモノ/グローバルなモノ、商品/非商品といった区分がゆらぐ過程の分析となるのである。
1 0 0 0 レーザー加速度場における時空の歪みとウンルー効果
- 著者
- 矢野 将寛 Zhidkov Alexei 兒玉 了祐
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会講演概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.71, pp.630, 2016
<p>パワーレーザーとX線自由電子レーザーが時空と真空の物理を開拓する。ウンルーによれば等加速度運動する粒子の時空がゆがみ、真空の状態が変化する。その結果、その粒子は真空中が粒子に満たされていると感じるウンルー効果が生じる。本研究ではレーザー航跡場によって加速運動する電子によるX線トムソン散乱によってこの効果の実証を提案した。高繰り返し率により十分な結果が得られるはずである。</p>
1 0 0 0 OA リレー講義:フィールドワーク入門「人類学とフィールドワーク」講義録
- 著者
- タブレロ フランシスコ ハビエル
- 出版者
- 愛知大学国際コミュニケーション学会
- 雑誌
- 文明21 = Civilization 21 (ISSN:13444220)
- 巻号頁・発行日
- no.35, pp.43-51, 2015-12
1 0 0 0 OA 2 朝鮮人の非協力と接種率
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 植民地帝国日本における支配と地域社会 = The Rule and the Local Society in the Japanese Colonial Empire (ISSN:09152822)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.63-66, 2013-03-18
- 著者
- 国立研究開発法人科学技術振興機構
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- JSTnews (ISSN:13496085)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, no.6, pp.3-7, 2015
私たちの生活を支える時計が、新たな進化を遂げた。2014年初頭、東京大学の香取秀俊教授らが開発した「光格子時計」が、これまでの原子時計をはるかに上回る精度を実現したのだ。その精度はなんと「160億年に1秒しか狂わない」というもの。超高精度の時計の出現によって、私たちの「時間」は、どのように変化するのだろうか?
1 0 0 0 九州地方における弥生人骨の地域的特性に関する人類学的研究
形質人類学的側面から九州地方から出土している弥生人骨の地域的特性に関する研究を遂行した。調査対象人骨は長崎大学に保管されている資料を用い、縄文時代と同様に漁労・採集に生活基盤をおいていた西北九州地域の弥生人骨、南九州離島群出土の弥生相当期人骨と大陸からの渡来系と考えられる北部九州地域の弥生人骨について骨計測、頭蓋小変異観察を行い、次の結果を得た。1.西北九州及び南九州離島弥生人の計測的特徴(1)西北九州弥生人は、北部九州弥生人と比較して脳頭蓋がやや小さく、特に高径が小さい。頭型は西北九州弥生人の方がやや短頭に傾く。顔面頭蓋では幅径はほぼ同じであるが、顔高、上顔高の高径にはかなりの差が見られ、北部九州弥生人よりも著しい低顔傾向を示す。また、西北九州弥生人の顔面は平坦ではなく、立体的である。(2)南九州の弥生相当期人は、大局的には西北九州弥生人と同類で縄文系の弥生人と考えられるが、頭型が短頭に傾くことと顔面の平坦性がやや強い点で西北九州弥生人とは違いが見られる。(3)各遺跡ごとでの男性の平均推定身長値は、北部九州弥生人が162cm以上あるのに対し、西北九州及び南九州弥生人は160cm以下であり低身長である。2.西北九州及び南九州弥生入の頭蓋形態小変異形質の特徴(1)西北九州弥生人の出現頻度は、北部九州弥生人と比較して眼窩上孔が低頻度で出現し、逆に舌下神経管二分、翼棘孔、頬骨後裂、横後頭縫合残存は高頻度で出現する。この傾向は縄文人に酷似している。(2)南九州弥生人の出現傾向は西北九州弥生人に類似するが、舌下神経管二分と顎舌骨筋神経管が低頻度である点でこれと異なる。(3)外耳道骨腫は、西北九州及び南九州弥生人に高率で出現しており、形質のみならず生活様式が北部九州地域の弥生人と異なっていたことが示唆された。
- 著者
- 駿河 昌樹 Masaki Suruga
- 雑誌
- 中央学院大学法学論叢 = The Chuo-Gakuin University Review of Faculty of Law (ISSN:09164022)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.379-413, 2016-03-01
1 0 0 0 OA 免疫システムのメカニズムを用いた感情の計算モデル
- 著者
- 小野 哲雄 佐藤 理史
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.3, pp.3_48-3_65, 1995 (Released:2008-10-03)
- 参考文献数
- 15
We propose a computational model of emotion using the mechanism of the immune system. This model is inspired by the observation that emotion is similar to the immune system, in that each is a result of a self-defense system that is capable of adapting to the environment.The main component of this model is a body, in which many cells undergo Brownian Motion. Each cell has energy and characteristics that correspond to one of the five ego states in transactional analysis(Berne, 1964). The cells' state as a whole is its emotional state. Some cells are activated when antigens invade the body, and they work to sweep away those antigens. This process changes the emotional state.We implemented this model, and the results of experiments indicate that the model has the following two characteristics, which other models have not been able to achieve:(1) Emotional states change continuously.(2) Emotional states change in response to stimuli (antigens) according to the state at that moment and its past changes.We implemented a dialogue system using this model and found that the system can imitate human dialogues.
- 著者
- 松田 淳 和才 克己 谷藤 鉄也 佐宗 章弘 安部 隆士
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 東海支部総会講演会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.457-458, 2008
1 0 0 0 OA <論文>韓国仮面劇と日本伎楽の比較研究
- 著者
- 村上 祥子 Murakami Yasuko
- 出版者
- 筑波大学比較民俗研究会
- 雑誌
- 比較民俗研究 : for Asian folklore studies (ISSN:09157468)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.86-123, 1991-03-31
1 0 0 0 IR 飛翔する 《笛吹き童子》--芸能神義経の誕生
- 著者
- 中村 一基
- 出版者
- 岩手大学語文学会
- 雑誌
- 岩大語文 (ISSN:09191127)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.1-8, 2007
義経と弁慶の五条大橋での対決場面に相当するほどの、わくわくする対決場面が他にあるだろうか。千本の太刀を集めることを目標として、京の町を徘徊する僧兵姿の弁慶が、五条大橋で千本目に当たる黄金の太刀を帯びた女装の笛吹き童子牛若丸に遭遇、太刀をめぐって闘いを行ない、牛若丸の圧倒的な強さの前に降り、主従の約束をするという、《義経伝説》の中でも最も親しまれた場面である。現在、この場面を描いた多くの絵(挿絵・浮世絵が大半)が残っているが、七つ道具を背負った弁慶の大薙刀が振り下ろされ、牛若丸が軽やかに飛翔してそれをかわしている構図が、その絵の定番の構図である。本稿では、飛翔する《笛吹き童子》に象徴される芸能神義経誕生の神話にこだわってみたい。
1 0 0 0 OA 1.血糖変動と血管病リスク
- 著者
- 西村 理明
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.4, pp.922-930, 2013 (Released:2014-04-10)
- 参考文献数
- 18
現在,糖尿病患者における血糖コントロール指標として,主にHbA1cが用いられている.しかし,HbA1cを指標とした介入試験において,心血管疾患の発症予防に成功した研究は皆無である.HbA1cだけでは把握できない血糖変動の是正を含めた血糖コントロールを行う必要があるのではなかろうか.近年,血糖変動の把握を可能とする機器が登場し,血糖変動と心血管関連エンドポイントとの関連を示す報告がまだ少数ではあるが登場してきた.
1 0 0 0 「自立」再考—互助・助け合う“自立”の大切さ
はじめに 「自立」の定義は,「他の助けや支配なしに自分一人の力だけで物事を行うこと.ひとりだち.独立」である. しかしながら,東京大学先端科学技術研究センター准教授の熊谷晋一郎氏は「自立とは依存先を増やすこと」と述べている.熊谷氏は車いすで移動をしている.東日本大震災時には職場のエレベーターが止まり,建物の外に出られなくなった経験をした.健常者はエレベーターが動かなくなっても,階段や避難梯子等,階下に降りる手段がいくつかあり選択できる.それは,頼れる手段や依存できるものが複数あるということとなる.「“自立”を支えているのは依存する物や人,場が沢山あること」というわけである.初めてこの言葉を聞いたときに目からうろこが落ちたとともに,自立を支援していく者として大きな間違いを犯していたのではないかと自身の作業療法人生を振り返ったことを覚えている. そもそも「自立」には,身体的・精神的・職業的・経済的等の自立があり,それと対比するように「依存的自立」という言葉がある.たとえば,他人の助けを借りて5分で衣服を着替えて外出する人と,自分だけでは着替えに2時間かかるため,外出できない人とを比較すると,前者のほうが自立度が高いという考えである. この「依存的自立」は,その人自身の能力や考え,自己決定を尊重した自立のかたちであり,その人らしさをつくり上げる土台,価値観になるものである.熊谷氏にはそういった土台が根づいているのであろう.
1 0 0 0 OA EPA及びDHAの代謝と機能
- 著者
- 鈴木 平光 和田 俊
- 出版者
- Japan Oil Chemists' Society
- 雑誌
- 油化学 (ISSN:18842003)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.10, pp.781-787, 1988-10-20 (Released:2009-11-10)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 1 2
Since it has been reported that dietary intakes of fish oil link to reduced rates of cardiovascular and inflammatory diseases in Greenland Eskimos, many studies have focused on the role of icosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) in the modulation of lipid metabolism. By the way, the number of patients with disease peculiar to the aged, such as senile dementia, has tended to increase in recent years. Studies specifically concerned with the modification of nervous system and the control of aging by EPA and DHA are now noteworthy.In this review, we have described recent studies in the following areas: metabolism of EPA and DHA, cardiovascular system, anti-inflammatory action, brain and retina, and aging.
1 0 0 0 OA 東日本大震災被災者・避難者の健康増進
- 著者
- 本谷 亮
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.68-74, 2013 (Released:2013-10-31)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 8
東日本大震災の被災者・避難者の多くは、心身両面においてさまざまな健康問題を抱えている。健康問題の例としては、PTSD症状の出現、抑うつ、不安、焦燥、怒りの増加、睡眠障害、血圧上昇、アルコール依存症、生活習慣病、あるなどがあげられる。震災がもたらしたこのような健康問題は、震災直後の急性期のみならず、中長期においても大きな問題となっており、被災者に対する継続的なアプローチが必要である。今回の震災では、津波や原発事故のために、強制的に避難をせざるをえず、震災後、住環境が大きく変化した者も多い。動かないことで全身の心身機能が低下する“生活不活発病(廃用症候群)”も、避難している高齢者を中心に散見され、心身の健康問題の悪循環を生んでいる。加えて被災三県の中でも放射線の影響が懸念されている福島県では、住民の屋外活動の減少や食品摂取の過剰制限など、放射線不安が要因で引き起こされている健康問題への対応も課題の一つとなっている。被災者・避難者の抱える健康問題に関しては、ハイリスク者の早期発見、早期支援を行うことが重要である。また、ハイリスク者や対応困難者に対しては、医師、看護師、保健師、心理士など多職種がチームとなって連携したアプローチをすることが不可欠であり、支援に臨床心理学的視点や行動医学的視点が必要となることもある。そして、被災者・避難者の健康増進を考える際には、個々人に対するアプローチに加えて、地域やコミュニティーに対するアプローチも非常に重要であり、いかに地域やコミュニティーを取り込んだアプローチができるかが長期におよぶ被災者・避難者の健康増進のカギとなる。
- 著者
- 吉矢 生人 山西 昭夫
- 出版者
- メディカル・サイエンス・インターナショナル
- 巻号頁・発行日
- pp.258-261, 2021-03-01
パルスオキシメータは,今や世界中で血圧計や心電図などと同等の必要欠くべからざる医療機器となっている。その基本原理を発明し,世界で初めて脈波を利用した非侵襲的な血液酸素飽和度測定機器を開発したのが青柳卓雄博士である。 2020年4月に青柳博士のご逝去を知り,基本原理の発明にとどまることなく直近まで偽アラームの起きない真のパルスオキシメータ開発に情熱を注ぎ続けた博士を想い,寂しいかぎりである。謹んでご冥福をお祈りいたします。 筆者らとそれぞれの共同研究者らは,博士と同様の原理にもとづく光ファイバー指先型パルスオキシメータOXIMET MET-1471(ミノルタカメラ社,以下OXIMET)の開発にかかわった。当時の光ファイバー式OXIMETは現在の医療現場には影も形もないが,青柳型パルスオキシメータと現在世界中で使われているパルスオキシメータとの橋渡しの役割を担ったと考えられる。 本稿では,ミノルタカメラ社(以下,ミノルタ社)でのパルスオキシメータ開発の経緯とその臨床応用への試みについて述べる。当時の資料が散逸しており,記憶が定かでない部分もあるがご寛容いただきたい。
1 0 0 0 OA 巻頭言
- 著者
- 宮坂 勝之
- 出版者
- メディカル・サイエンス・インターナショナル
- 巻号頁・発行日
- pp.237, 2021-03-01