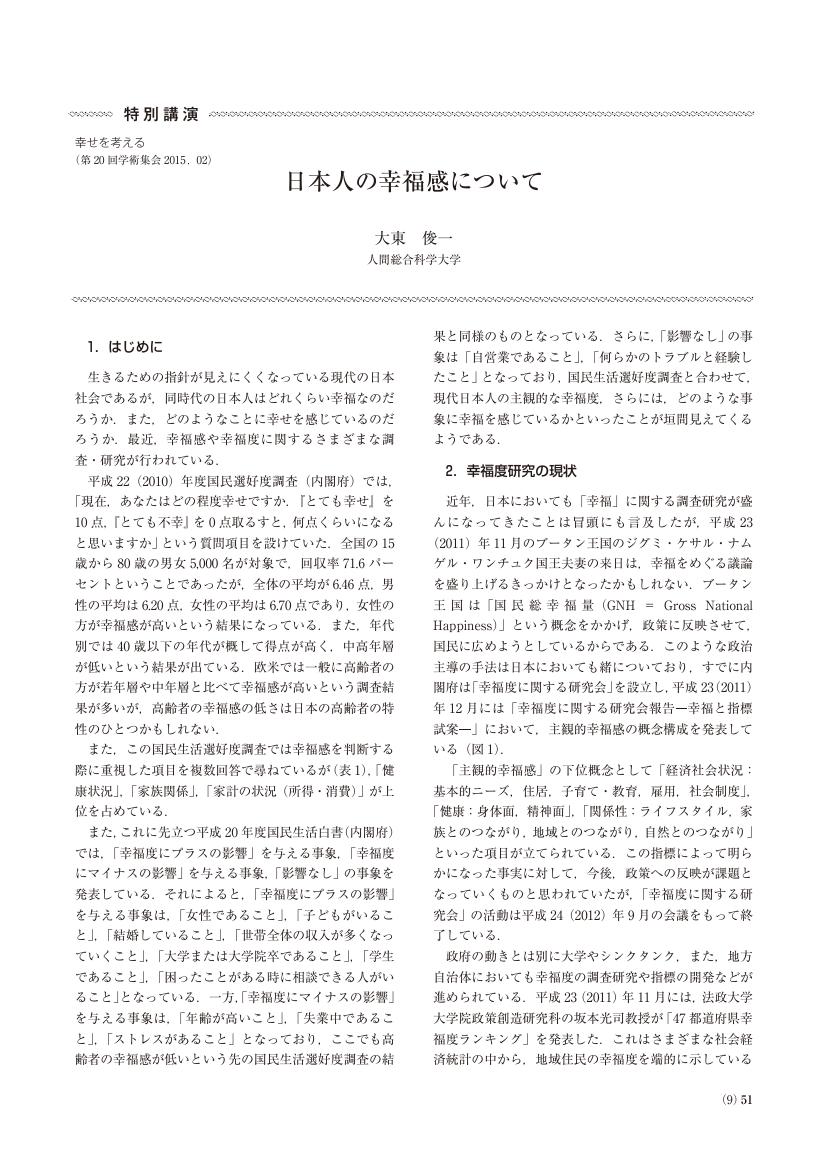- 著者
- 中村 肇
- 出版者
- 一般社団法人 社会情報学会
- 雑誌
- 社会情報学 (ISSN:21872775)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.15-30, 2019-06-30 (Released:2019-07-10)
- 参考文献数
- 22
メディアが透明な媒介としてわれわれの生活世界を侵食する際に立ち現れる身体性の剥奪という問題は如何にして記述できるのだろうか。本論考は,その些か巨大すぎる問いに,ネオ・サイバネティクスと総称される思想的潮流の一端を担う「基礎情報学」の観点から,社会美学における「共通美」の概念を手がかりに考察する。より具体的には,昨今のSNS文化における加工写真=〈新しいテクノ画像〉が,被写体の身体性が剥奪されているにもかからず広く受容されている状況に対して,基礎情報学の心的システムの議論やヴィレム・フルッサーのメディア理論,さらにはマイケル・ポラニーの暗黙知などの諸概念に依拠しつつ,理論的な検討を加える。主観的な知から出発したわれわれの心的システムが,二人称的な対話を通じて共振しながらコミュニケーションの発展過程として描出されていく一方で,それが社会システムへと転化し,安定状態へと達した結果,逆に個人の美的価値から身体性=視覚ディスプレイ上から立ちのぼるある種の生々しさを剥奪させていく様態を,階層的自律コミュニケーション・システムHACS(Hierarchical Autonomous Communication System)モデルから捉え直す。
- 著者
- 森本 宏 菊川 義宣 村上 尚史
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.146, no.4, pp.225-232, 2015 (Released:2015-12-10)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
尋常性ざ瘡は,脂腺性毛包での毛包漏斗部の角化異常に伴う閉塞およびPropionibacterium acnes(P. acnes)などの細菌増殖による炎症惹起を含め,多因子が絡み合って発症する疾患とされる.過酸化ベンゾイルは,分解に伴い生じるフリーラジカルが,尋常性ざ瘡の病態に関与するP. acnesなどの細菌の細胞膜構造などを障害することで抗菌作用を発揮すると考えられる.また,角層中コルネオデスモソームの構成タンパク変性に基づいて,角質細胞間の結合を弛めて角層剥離促進をもたらすと示唆される.これらの薬理学的機序により,過酸化ベンゾイルは細菌増殖を抑制し,毛包内に貯留した皮脂放出を促すことで尋常性ざ瘡を改善する.尋常性ざ瘡患者を対象とした国内臨床試験において,過酸化ベンゾイルゲル2.5%を1日1回,12週間塗布することにより,治療開始2週後からプラセボに対し有意な炎症性および非炎症性皮疹数の減少を示した.また長期投与試験により,52週後まで皮疹数減少が維持されることを確認した.さらに,被験者に認められた副作用はおもに適用部位である皮膚に発現したもので,多くは軽度の事象であり,いずれも無治療あるいは薬物治療で回復した.本剤は,52週間塗布することによりP. acnesの抗菌薬感受性を低下させることなく,かつ抗菌薬感受性に関わらず皮疹改善効果に影響は認められなかった.さらに,本剤塗布後,過酸化ベンゾイルは安息香酸および馬尿酸に代謝され,尿中に排泄された.以上から,過酸化ベンゾイルゲル2.5%は,尋常性ざ瘡治療において忍容性が高く持続的な治療効果が得られる薬剤であり,海外と同様に本邦での標準的な治療薬の一つとして期待が持てる.
- 著者
- 川本 諒 五條堀 眞由美 柴崎 翔 松吉 佐季 鈴木 総史 平井 一孝 植田 浩章 金澤 智恵 高見澤 俊樹 宮崎 真至
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会
- 雑誌
- 日本歯科保存学雑誌 (ISSN:03872343)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.5, pp.402-409, 2016 (Released:2016-10-31)
- 参考文献数
- 24
目的 : 歯科疾患の予防という概念の普及に伴って, 機械的歯面清掃 (PMTC) を行う機会が増加している. その際に用いられるPMTCペーストは, さまざまな製品が市販されているものの, プラーク除去効果あるいは歯質に対する影響については不明な点が多い. そこで, PMTCペーストの使用がエナメル質および歯冠修復物の表面性状とプラーク除去効果に及ぼす影響について検討した. 材料と方法 : 疑似エナメル質としてステンレス板 (SUS304), コンポジットレジン試片としてFiltek Supreme Ultra (3M ESPE), 金銀パラジウム合金試片としてキャストウェルM. C. 金12% (ジーシー) を用い, それぞれ通法に従って10×10×1mmの平板に調整したものをPMTC用試片とした. これらの試片に対し, 等速コントラアングルに歯面清掃ブラシを装着し, PMTCペースト0.1gを用い, 回転数2,000rpm, 荷重250 gfの条件で, 15秒間PMTCを行った. なお, 供試したPMTCペーストは, クリンプロクリーニングペーストPMTC用 (CP, 3M ESPE), コンクールクリーニングジェル (CJ, ウェルテック), メルサージュレギュラー (MR, 松風), メルサージュファイン (MF, 松風) およびメルサージュプラス (MP, 松風) の合計5製品とした. PMTC終了後の試片について, その表面をレーザー走査顕微鏡を用いて観察するとともに付属のソフトウェアによって表面粗さRa (μm) を求めた. また, 表面に塗布した人工プラークの残存面積 (mm2) を計測することによって, 人工プラーク除去率を算出した. 成績 : PMTC後のステンレス, コンポジットレジンおよび金銀パラジウム合金試片の表面粗さは, 用いたPMTCペーストによって異なる傾向を示した. 特に, CJ, MRおよびMFはBaselineと比較してPMTC後の表面粗さが増加し, MRはほかの製品と比較して有意に高いRa値を示した. 一方, CPにおいては, コンポジットレジンおよび金銀パラジウム合金でPMTC後の表面粗さが増加したが, ステンレス板においては変化が認められなかった. また, プラーク除去率についても使用した製品によって異なる傾向を示した. 結論 : エナメル質, コンポジットレジンおよび金銀パラジウム合金のPMTC後の表面粗さの変化ならびにプラーク除去率は, 用いたPMTCペーストによって異なるものであり, 配合されている研磨粒子の成分や粒径によるものであったことが示された.
3 0 0 0 OA 植民地教育とマレー民族意識の形成
- 著者
- 左右田 直規
- 出版者
- Japan Society for Southeast Asian Studies
- 雑誌
- 東南アジア -歴史と文化- (ISSN:03869040)
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, no.34, pp.3-39, 2005-05-30 (Released:2010-02-25)
- 参考文献数
- 42
This paper intends to examine the interplay between the official construction of “Malayness” in colonial educational policy and the formation of Malay ethno-national identity in British Malaya. For this purpose, it uses as its case study the Sultan Idris Training College (SITC), a Malay teacher training college that was established in Tanjung Malim, Perak, in 1922.The SITC played an important role in the reproduction of ethnic, class, and gender relations in British Malaya. As in the case of the Malay College, Kuala Kangsar (MCKK), the SITC was a residential school, modeled on public schools in England, in which the college authorities aimed to have total control over the students' studies, their extra-curricular activities (sports, cultural and recreational activities, military training and scouting), and their lives in the student dormitories called “houses.” Unlike the aristocratic MCKK, however, the SITC was designed to train Malay rural male teachers so that they would be able to educate Malay village boys to be “intelligent peasants.”SITC-graduated teachers were expected to become local agents of the British colonial authorities for the inculcation of desirable values among rural Malay children. The formal curriculum for the SITC was Malay-centered and ruralbiased, with an emphasis on the Malay language and the history and the geography of the “Malay world, ” as well as on practical education such as gardening, basketry, carpentry, etc. Furthermore, it was also male-biased when compared with the curriculum for the Malay Women's Training College (MWTC), which stressed domestic science for Malay girls.Though the SITC was a product of British colonial education policy, it left enough room for its teachers and students to utilize their shared experiences and to reorganize their acquired knowledge in order to construct Malay ethnonational identity. The SITC had some well-known Malay teachers and a European Principal all of whom were active in propagating Malay nationalist sentiments.SITC students could obtain knowledge on Malaya, the “Malay world” and other parts of the world not only during regular classes, but also from daily communication with their teachers and college mates, as well as from various kinds of reading materials such as books, magazines, and newspapers. Some of the students secretly participated in political activities. As a result of this local appropriation of colonial education, the SITC produced a number of Malayeducated nationalist intellectuals. This was not what British colonizers originally intended or wanted to be the product of the educational system that they had imposed.
3 0 0 0 OA 45年で日本人はどう変わったか(1) 第10回「日本人の意識」調査から
- 著者
- 荒牧 央
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.5, pp.2-37, 2019 (Released:2019-06-20)
NHKは1973年から5年ごとに「日本人の意識」調査を行い、同じ質問・同じ方法で調査を繰り返すことによって、社会や経済、政治、生活など、人びとの幅広い意識を長期的に追跡している。その最新の調査結果から、結婚観、婚前交渉、女性の職業、女の子の教育など、家庭・男女関係についての結果を紹介する。家庭・男女関係は、「日本人の意識」調査の中で最も変化の大きい領域である。その変化の特徴として以下のようなことがあげられる。①全体として、男女の平等や個人の自由を認める方向へ意識が変化している。②増えるものは増え続け、減るものは減り続けるというように、同じ方向に変化している項目が多い。③世代交代によって変化している質問もあれば、時代の影響を大きく受けている質問もある。家庭・男女関係についての考え方は45年間で大きく変わったが、2000年頃からは変化が小さくなった質問も見られる。
3 0 0 0 OA タッチモニタを用いたマウスにおける視覚弁別の訓練手続き
- 著者
- 後藤 和宏 幡地 祐哉
- 出版者
- THE JAPANESE SOCIETY FOR ANIMAL PSYCHOLOGY
- 雑誌
- 動物心理学研究 (ISSN:09168419)
- 巻号頁・発行日
- pp.70.1.2, (Released:2020-06-23)
- 参考文献数
- 23
Automated touchscreen-based tasks are increasingly being used to explore a broad range of issues in learning and behavior in mice. Researchers usually report how they train mice before acquiring a target task concisely, and shaping protocols at this stage are typically flexible. In this report, we described a training protocol, developed in our laboratory, for mice acquiring a simultaneous discrimination performance using visual stimuli. C57BL/6N mice were first given magazine training. Nosepoke responses were then authoshaped and maintained on a continuous reinforcement schedule. Self-start response was then introduced in order to measure response time to complete each trial. The stimulus position was also varied across trials. We finally examined the contrast discrimination performance. Mice were tested with four different contrast ratios. Target stimuli were white and black targets and the brightness of distractors had values between targets and background. All mice successfully went through all training stages, confirming that this training protocol is promising for shaping appropriate discriminative behaviors in mice.
3 0 0 0 OA 薬事法改正の見直しで問われる,適正な医薬品販売の在り方~薬害被害者の立場から~
- 著者
- 増山 ゆかり
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬剤学会
- 雑誌
- 薬剤学 (ISSN:03727629)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.4, pp.247-250, 2009 (Released:2019-03-31)
- 著者
- 歌川 史哲 指田 勝男 上松 佐知子 髙津 翔平
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.123, no.11, pp.969-976, 2017-11-15 (Released:2018-02-23)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
The Neogene Chikura Group, which is widely exposed in the southeastern part of Minamiboso City, Chiba Prefecture, Japan, is made up of a thick sequence of marine sedimentary rocks deposited in a middle to upper bathyal environment. The group comprises (in ascending order) the Shirahama, Shiramazu, Mera and Hata formations. The upper Pliocene Shirahama Formation is composed mainly of red-brown volcaniclastic sandstone and the Nojimazaki Conglomerate Member. This member comprises volcaniclastic conglomerate with granules to boulders of basalt and andesite, and is characterized by pebbles of andesite, basalt, granodiorite, gabbro, sandstone, siltstone, greenish tuff, and chert. We obtained Anisian and Ladinian (Middle Triassic) radiolarians from chert pebbles, and Bajocian to Callovian (Middle Jurassic) radiolarians from a siliceous siltstone pebble. These Mesozoic pebbles were probably derived from a Mesozoic accretionary complex (present-day Kanto District) in the northwestern part of Boso Peninsula.
- 著者
- Akihiko ITO Kazuhito ICHII
- 出版者
- The Society of Agricultural Meteorology of Japan
- 雑誌
- 農業気象 (ISSN:00218588)
- 巻号頁・発行日
- pp.D-20-00024, (Released:2020-12-25)
- 参考文献数
- 178
- 被引用文献数
- 3
A wide variety of models have been developed and used in studies of land-atmosphere interactions and the carbon cycle, with aims of data integration, sensitivity analysis, interpolation, and extrapolation. This review summarizes the achievements of model studies conducted in Asia, a focal region in the changing Earth system, especially collaborative works with the regional flux measurement network, AsiaFlux. Process-based biogeochemical models have been developed to simulate the carbon cycle, and their accuracy has been verified by comparing with carbon dioxide flux data. The development and use of data-driven (statistical and machine learning) models has further enhanced the utilization of field survey and satellite remote sensing data. Model intercomparison studies were also conducted by using the AsiaFlux dataset for uncertainty analyses and benchmarking. Other types of models, such as cropland models and trace gas emission models, are also briefly reviewed here. Finally, we discuss the present status and remaining issues in data-model integration, regional synthesis, and future projection with the models.
3 0 0 0 OA 日本列島の自然放射線レベル
- 著者
- 古川 雅英
- 出版者
- Tokyo Geographical Society
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.7, pp.868-877, 1993-12-25 (Released:2009-11-12)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 15 12
Extensive field survey on natural radiation was conducted from 1967 to 1991 over Japan Islands. The average level of the islands was found to be 79.7 nGy/h. In general, Southwest Japan has higher level compared with the Northeast one. From the data obtained at 1304 sites of the survey, a contour map of natural radiation level in the islands was made by simple interpolations, and a geological interpretation on the distribution of the level was done by comparing the contour map with geological information. The islands were divided into four areas according to whether the level is higher or lower than the average level. The boundaries between these areas were found almost exactly coincide with major geo-tectonic lines. This feature suggests that natural radiation level is controlled mainly by distribution of granitic and volcanic rocks.
3 0 0 0 OA 情報環境におけるテクノ依存症傾向のうつ傾向に及ぼす影響に関する研究
- 著者
- 坂部 創一 山崎 秀夫
- 出版者
- 一般社団法人 環境情報科学センター
- 雑誌
- 環境情報科学論文集 Vol.26(第26回環境情報科学学術研究論文発表会)
- 巻号頁・発行日
- pp.143-148, 2012 (Released:2014-09-20)
- 参考文献数
- 14
うつ傾向に対する,情報環境におけるテクノ依存症傾向と学生生活の一般的ストレスの影響度を比較することを主目的に,情報系大学生を対象に調査し,共分散構造分析で検証した。その結果,テクノ依存症傾向が高まることでうつ傾向をかなり悪化させることが検証され,インターネット利用目的により影響度が異なることも示された。また,一般的ストレスよりもテクノ依存症傾向の悪影響の方が倍以上高いことが検証された。このことから,情報化社会におけるうつ傾向の予防策として,テクノ依存症の回避と現実逃避目的のインターネットの利用を控えることの重要性が示唆された。
3 0 0 0 OA めまいリハビリテーションの段階的治療戦略.
- 著者
- 山中 敏彰
- 出版者
- 一般社団法人 日本めまい平衡医学会
- 雑誌
- Equilibrium Research (ISSN:03855716)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.4, pp.219-227, 2016-08-31 (Released:2016-10-01)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1 1
Some patients with uncompensated vestibular hypofunction present with a long history of persistent severe problems in posture and mobility that are intractable to any treatment. We examined whether graded vestibular balance rehabilitation would alleviate the dizziness and balance problems, and increase the safety and independence of patients with chronic balance disorders following unilateral vestibular loss. The stepwise treatment program for vestibular balance rehabilitation developed at our clinic consists of vestibular adaptation training (Step 1), sensory reweighing training (Step 2), and vestibular substitution training (Step 3). This rehabilitation program is intended at promoting the central vestibular adaptation process, altering the vestibular, visual and somatosensory inputs, and encouraging the use of the sensory substitution system with a human (brain)-machine interface as a substitute for the diminished vestibular input, for transmitting information about the patient's head position to the tongue. Clinical trials were performed to investigate the degree to which the stepwise multimodal approach might be effective for chronic balance disorder in subjects with unilateral decompensated vestibular loss. Some interventions for rehabilitation were selected and customized for each patient in accordance with the level of their compensation for postural control and sensory dependence. Improvements in the balance performance were noted in 64.4% of all the subjects after the Step 1 training. Of the 31 subjects (35.6%) who failed to improve with the step 1 program, 14 (45.2%) showed improvements after the Step 2 training. All of the subjects who failed to show improvement after the Step 1 and 2 training programs showed pronounced improvements after the Step 3 training. These results suggest that programmatic stepwise multimodal approach to vestibular rehabilitation yields beneficial effect in patients with balance disorder secondary to vestibular decompensation.
- 著者
- 喜山 克彦 岡山 知世 志田 直樹 内山 友香理 永田 勝太郎 志和 悟子 大槻 千佳 雨宮 久仁子
- 出版者
- 公益財団法人 国際全人医療研究所
- 雑誌
- 全人的医療 (ISSN:13417150)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.29-40, 2020-01-25 (Released:2020-07-02)
- 参考文献数
- 6
筋痛性脳症/慢性疲労症候群(ME/CFS)は,原因不明の慢性で深刻な疲労,広範な痛み,睡眠障害に多彩な症状を呈する疾患である.【症例】14歳女性,ME/CFS,全身のアロディニア,両手指,両足趾の屈曲拘縮.日常生活活動(ADL)は機能自立度評価(FIM)で51/126点を認めた.【経過】補法による治療に加え,理学療法士(PT)によるリハビリテーションを行った.【結果】ME/CFSの症状およびADL(FIM 110/126点)は改善した.【考察】ME/CFS患者の活動性レベルは約50%以上の低下を来す.ある患者はひきこもりや寝たきりとなる.労作後の消耗や疲労感はME/CFSの最も顕著な特徴であり,診断基準にもかかわらず,患者たちはしばしば不適切な運動を処方される.本症例は,補法および患者の持つ資源の活用,担当PTによる適切なリハビリテーションによりADLが改善したと考えている.
3 0 0 0 OA 三角表象の話
- 著者
- 井本 英一
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- オリエント (ISSN:00305219)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.83-96, 1992-09-30 (Released:2010-03-12)
3 0 0 0 OA ストレスと睡眠・情動障害:神経ステロイド・アロプレグナノロン系の関与
- 著者
- 松本 欣三 Alessandro Guidotti Erminio Costa
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.126, no.2, pp.107-112, 2005 (Released:2005-10-01)
- 参考文献数
- 29
精神的緊張をはじめ,様々な心理的ストレスがうつや不安などの情動障害や,不眠などの睡眠障害の要因にもなるが,ストレスによりそれらが発症するメカニズムはまだ十分には解明されていない.近年,多くの臨床および前臨床研究から,神経ステロイドと呼ばれる一連のステロイドのうち,特にallopregnanolone(ALLO)等のγ-アミノ酪酸A(GABAA)受容体作動性神経ステロイドの量的変動と種々の精神障害の病態生理やその改善との関連性が明らかになりつつある.我々は雄性マウスを長期間隔離飼育し,一種の社会心理的ストレス(隔離飼育ストレス)を負荷したときの行動変化を指標に,ストレスで誘導される脳機能変化を薬理学的に研究している.隔離飼育マウスでは対照となる群居飼育動物と比較して鎮静催眠薬ペントバルビタール(PB)誘発の睡眠時間が短くなっており,この原因の一つに脳内ALLO量の減少によるGABAA受容体機能の低下があることを示した.また脳内ALLO量の低下は隔離飼育雄性マウスに特徴的に現れる攻撃性亢進にも関与し,選択的セロトニン再取り込み阻害薬フルオキセチンは脳内ALLOレベルを回復させることにより攻撃性を抑制することを示唆した.PB誘発睡眠を指標に検討したALLOをはじめとする脳内物質の多くは睡眠調節にも関わることから,脳内ALLO系のダウンレギュレーションを介したGABAA受容体機能の低下もストレス誘発の睡眠障害の一因であろうと推察された.また攻撃性のような情動行動変化にも脳内ALLOの量的変動が関与する可能性が高いことから,今後,脳内ALLO系を標的とした向精神薬の開発も期待される.
3 0 0 0 OA 視覚障害者の植物の嗜好に関する研究
3 0 0 0 OA 近代日本の教科書における富士山の象徴性
- 著者
- 阿部 一
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.238-249, 1992-03-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2
The symbolic landscapes of a nation are important clues to the human-landscape relation, which is an aspect of the relationship between the people and their environment. Mt. Fuji was long the typical symbolic landscape of modern Japan, as can be seen in textbooks for use in elementary schools. I examined the symbolism of Mt. Fuji in textbooks to suggest tendencies in the relationships between Japanese and their environment. The results are as follows: 1) Mt. Fuji appeared in the primary school textbooks from Meiji Era until 1945. The mountain was presented as the sublimest mountain in Japan through textbooks for reading, drawing, and singing, whose contents were inter connected. Consequently, children learned a certain image of Mt. Fuji. 2) Mt. Fuji was praised as the sublimest mountain of Japan in order to make children sympathize with the sentiments of Japanese adults, who were supposed to admire Mt. Fuji. At the same time, children were taught that the national sentiment was focused on the image of Mt. Fuji. 3) The relation between the nation and school children as illustrated in teaching materials concerning Mt. Fuji is shown graphically in Fig. 5. The materials formalized the appearance of Mt. Fuji and formed a specific image of it. Children learned the materials and internalized a certain image of the mountain. The image validated the content of the materials and suggested the national sentiment. Through this process of learning, children came to obscurely understand the concept of a national sentiment. 4) The national sentiment of Japan that was used as a unifying concept was a Vague idea escaping logical grasp; therefore the education inevitably stressed impressions rather than logic. Mt. Fuji was seen to be the best material for that kind of education. 5) The relation between Mt. Fuji and the national sentiment seems to have been sustained by an “intentionality to legitimacy”. The national sentiment was supposed to have legitimacy, although the foundation of that legitimacy was not shown. On the other hand, Mt. Fuji was given legitimacy through the formalization of its appearance. Therefore, Mt. Fuji was chosen as the image of legitimacy to suggest the content of the national sentiment.
3 0 0 0 OA 日本人の幸福感について
- 著者
- 大東 俊一
- 出版者
- 日本心身健康科学会
- 雑誌
- 心身健康科学 (ISSN:18826881)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.51-55, 2015-09-01 (Released:2015-09-15)
- 被引用文献数
- 7
3 0 0 0 OA イエネコによる絶滅危惧種アカコッコの捕獲:御蔵島における撮影事例
- 著者
- 徳吉 美国 岡 奈理子 亘 悠哉
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.237-241, 2020 (Released:2020-08-04)
- 参考文献数
- 22
イエネコFelis silvestris catusによる在来種の捕食は生物多様性保全における大きな問題である.特に島嶼における鳥類への影響は大きいとされるが,いまだ日本における報告は限られている.伊豆諸島御蔵島において,絶滅危惧種鳥類であるアカコッコTurdus celaenopsの生体1羽を咥えたイエネコを,森林内に設置した自動撮影カメラで初めて記録したので報告する.撮影日は2018年7月24日であり,アカコッコを咥えたイエネコの静止画と,このアカコッコがイエネコに咥えられながら嘴を開閉させる動画が撮影された.これらの映像から判断し,イエネコが他の要因で死んだアカコッコを咥えていたのではなく,イエネコ自身が捕獲したと考えられた.捕獲されたアカコッコは巣立ち前後の雛の特徴を有するため,撮影直前にイエネコがアカコッコの巣内雛もしくは移動能力の低い巣立ち雛を襲ったものと考えられた.アカコッコ以外にもオオミズナギドリCalonectris leucomelasを咥えて運ぶ映像も撮影され,イエネコによる在来鳥類への捕獲リスクの存在が示唆された.今後は,映像記録の蓄積や糞分析などにより,島の在来鳥類へのイエネコの捕殺や捕食の実態の把握が必要である.御蔵島を含め,アカコッコの分布地域には放し飼いや野生化したイエネコが生息している.これらの地域で捕食リスクを低減するために,イエネコの適正飼養や効果的な捕獲対策が求められる.
3 0 0 0 OA 顎関節症の理学療法II
- 著者
- 竹井 仁
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.49-54, 2000 (Released:2007-03-29)
- 参考文献数
- 15
顎関節症の治療は,その原因を明確にした上で実施することが大切である。理学療法の実施にあたっては,顎関節の解剖学や運動学を理解した上で評価が完全になされていることが重要となる。本論文では,欧米諸国の顎関節症の治療理論と実際をふまえながら,顎関節症の理学療法と生活指導について述べる。理学療法としては,物理療法の他に,マイオフェイシャルリリース,軟部組織モビライゼーション,アクティブ・ストレッチ,リラクセーション,下顎下制リリース,関節モビライゼーション,関節包内運動再教育訓練,筋力増強及び協調性訓練などについて概説する。