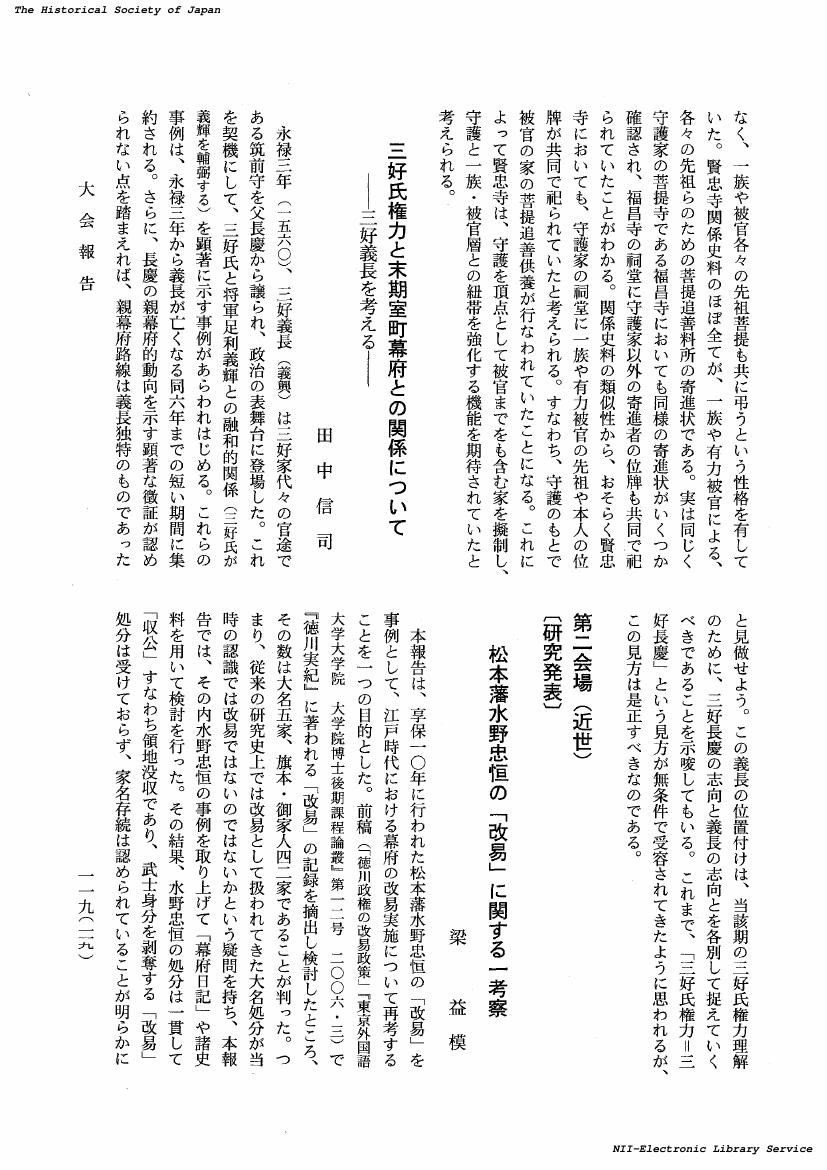- 著者
- 田中 信司
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, no.1, pp.119, 2009-01-20 (Released:2017-12-01)
- 著者
- Jun YASUDA Takahiro YOSHIZAKI Kaori YAMAMOTO Masae YOSHINO Masako OTA Takashi KAWAHARA Akiko KAMEI
- 出版者
- Center for Academic Publications Japan
- 雑誌
- Journal of Nutritional Science and Vitaminology (ISSN:03014800)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.177-183, 2019-04-30 (Released:2019-04-30)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 10
The purpose of the study was to examine the association of the frequencies of milk and dairy product consumption with subjective sleep quality during the training period in Japanese elite athletes. In this cross-sectional study, 682 Japanese elite athletes who were candidates for the 2016 Rio Olympic Games underwent medical evaluations at the medical center of The Japan Institute of Sports Sciences. Self-reported questionnaires were used to collect information on demographics and lifestyle (age, height, weight, sports, presence of milk allergy, smoking and drinking habits), subjective sleep quality (good, normal, or poor), bedtime, waking time, sleep duration, and frequencies of milk and dairy product consumption. Data from 679 athletes (379 men, 300 women) without milk allergy, were analyzed. Based on the frequencies of both milk and dairy product consumption, the athletes were divided into three groups: low (0-2 d/wk), middle (3-5 d/wk), and high (6-7 d/wk). Multiple logistic regression models showed that in comparison with the low milk consumption group, the middle [OR (95% CI): 0.48 (0.26-0.91)] and high groups [0.38 (0.21-0.71)] were significantly associated with a lower risk of decrease in subjective sleep quality (0: good, 1: normal or poor) only in women, after adjusting for possible confounders, such as smoking, drinking habits, and sleep duration. Accordingly, the present study elucidated that a greater frequency of milk consumption was significantly associated with a lower risk of decrease in subjective sleep quality, during training periods in women.
3 0 0 0 OA n-3系多価不飽和脂肪酸の摂取基準の考え方
- 著者
- 江崎 治 佐藤 眞一 窄野 昌信 三宅 吉博 三戸 夏子 梅澤 光政
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会
- 雑誌
- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.123-158, 2006-04-10 (Released:2009-12-10)
- 参考文献数
- 209
- 被引用文献数
- 2 5
日本人のn-3系多価不飽和脂肪酸 (以下n-3系脂肪酸と略す) の摂取基準策定 (2005年版) に用いた論文をエビデンステーブル (表) として提示し, 策定の基本的な考え方を詳しく述べた。n-3系脂肪酸は一定量以下のある摂取量で皮膚炎, 成長障害が認められる必須脂肪酸であるので, 下限の設定 (最低必要量) が必要である。しかし, 報告症例が少なく, 一定量以下のある摂取量を求めることができないため, 摂取量の中央値で表される目安量を用いた。すなわち, 大部分の日本人では皮膚炎は認められていないので, 日本人の各年齢階層における男女別にみたn-3系脂肪酸摂取量の中央値を日本人の大多数で欠乏症状が認められない十分な量と考え, 目安量とした。このように安全幅が広めに設定されているため, 実際の摂取量が目安量より少なくても欠乏症状はあらわれないと思われる。n-3系脂肪酸を多く摂取すると, 虚血性心疾患罹患が少なくなることを示す欧米の報告は多い。しかし, 現在の日本人のn-3系脂肪酸摂取量の中央値は, 欧米人の検討成績の中で, 虚血性心疾患罹患率の最も低い, 最高分位のn-3系脂肪酸摂取量のグループの中央値よりも多い。このため, 日本人のn-3系脂肪酸摂取量の中央値程度を摂取していれば, 虚血性心疾患罹患率を十分低くできると考えられる。そこで, 18歳以上に対し, n-3系脂肪酸摂取量の中央値を, 目標量 (生活習慣病予防を目的とした食事摂取基準の一つ) の下限と設定した。設定された18歳以上の目標量は2.0-2.9g/day以上となる。この値は必須脂肪酸としての目安量と一致するため, 18歳以上については目標量のみの設定となっている。n-3系脂肪酸を多く摂取した場合の弊害についても検討した。出血時間の延長, LDL-コレステロール値の増加が多く報告されているが, 臨床的に問題となる出血例の増加は報告されていないし, 虚血性心疾患罹患率が増加したことを示す報告もない。このため, 今回の策定では, 目標量の上限値設定は行わなかった。しかしながら, 日本人のおもなn-3系脂肪酸摂取源である魚介類には, 水銀, カドニウムなどの重金属, ダイオキシン, PCBなどの環境汚染物質が微量ながら含まれる。食事摂取基準では, 有害物質の摂取量について取り扱っていないため, これらの影響については考慮されていない。この点を補完するために, 本稿では水銀摂取の影響についてエビデンスの収集を行い, 妊婦が魚を摂取する場合の注意点についても言及した。
3 0 0 0 OA 高齢者の嚥下障害の特徴
- 著者
- 大前 由紀雄
- 出版者
- 日本音声言語医学会
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.167-173, 2013 (Released:2013-10-25)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 3
高齢者のQOL向上が求められるなか,嚥下障害を抱えた高齢者の診療を実践する機会が増えている.高齢者の嚥下障害は,さまざまな原因疾患に関連した嚥下動態の異常に応じて発症するが,高齢者の抱える身体的・精神的・社会的要因が複雑に絡み合っている.さらに,加齢に伴うが生理的な嚥下機能の低下がその病態を修飾している.一般的に,高齢者の嚥下機能検査では,嚥下反射の惹起遅延や咽頭残留の増加に伴う喉頭流入・誤嚥,ならびに気道防御反射の低下に伴う喀出低下が高頻度に観察される.こうした異常所見には,加齢に伴う嚥下のメカニズムの変化として,(1)嚥下に関連する筋力低下や構造の変化,(2)嚥下に関連する感覚神経や運動神経の機能低下,(3)嚥下運動を制御する中枢機構の低下,(4)身体機能や精神機能ならびに呼吸機能の低下,が指摘されている.本稿では,嚥下機能検査で観察される異常所見を呈示し,加齢に伴う高齢者の嚥下機能とそのメカニズムを概説し,高齢者の嚥下障害の特徴と高齢化社会に向けての嚥下障害の取り扱いを解説する.
3 0 0 0 OA 1968SNA から1993SNA へ:ある回想
- 著者
- 倉林 義正
- 出版者
- 環太平洋産業連関分析学会
- 雑誌
- 産業連関 (ISSN:13419803)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.3, pp.3-14, 2008-10-31 (Released:2014-10-09)
- 参考文献数
- 26
小論は,かつて筆者が国連本部統計局(UNSO)に在勤し,1993SNA の初期段階における作成作業に携わった経験に基づいて,その作成作業の経過を,当時のSNA をめぐる各国の研究状況に照らして考察した回想の記録である.筆者とSNA の関わりを述べる導入(第1節)に続いて,第2節では,1993SNA を作成するためのさまざまな準備作業とその問題点が,また第3節では,具体的な作成作業の展開とそれに伴う問題点が考察される.結びの第4節では,今後の改定作業との関連で発生すると予想される未解決の問題を指摘する.この小論は,図らずも去る10月18日に急逝した(以下の考察でしばしば登場する)Michael Ward 氏との30年に余る交友の思い出と追悼のために捧げられる.
3 0 0 0 OA 日本と台湾の高等教育におけるデザイン関連学科のカリキュラムの比較
- 著者
- 侯 茉莉 小野 健太 渡邉 誠
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.17-24, 2010-11-30 (Released:2017-06-24)
- 参考文献数
- 14
台湾では戦後早期のデザイン発展およびデザイン教育において、日本からの影響と、米国およびヨーロッパの専門家や学者から多くの協力が得られた。日本の影響のもとに築かれた台湾のデザイン教育が、商工業の発展につれて次第に独自のスタイルを持つようになった。一方、日本でも、ものを作るだけの時代から、更にマーケティング等の視点を取り入れ発展してきた。本論では、100年以上の歴史を経た現在の日本および台湾における高等デザイン教育の状況、また、日本と台湾のデザイン教育の相違を抽出することが目的である。日本の35のデザイン学科および台湾の32のデザイン学科に対し、カリキュラムの調査を行った。具体的には、それぞれのカリキュラムについて、重視されている、あるいは欠けている課程を調べ、数量化理論III類を用いて分析することにより、9つのタイプに分類を行った。それらのタイプと日本、台湾との関係を見ることにより、日本のデザイン教育は多様な要素を含んだ総合的な学問として、台湾のデザイン教育は「ものづくり」ための技術教育を中心に発展してきたことが分かった。
3 0 0 0 OA 農業労働市場の計量経済分析
- 著者
- 加賀爪 優
- 出版者
- 地域農林経済学会
- 雑誌
- 農林業問題研究 (ISSN:03888525)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.124-134, 1976-09-25 (Released:2011-09-05)
- 参考文献数
- 29
3 0 0 0 OA 実験 : その日本的様相
- 著者
- 川崎 謙
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 科学教育研究 (ISSN:03864553)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.2-10, 2001-03-10 (Released:2017-06-30)
- 参考文献数
- 48
- 被引用文献数
- 1
This paper presents a cross-cultural study on concepts of "experiment" between Western Modern Science, i.e., W-M science, and Japanese culture. This study will make it possible to liberate science educators in Japan as well as those in other non-Western nations from a dogma which forces them to accept the universality of W-M scienee. The first step of the study is to establish a viewpoint to relativize the worldview of W-M scienee to that of Japanese culture in a synchronic perspective; in other words, W-M seience is recognized to be a possible alternative in science educatioru. The second is to coin undefined terms that include "experiment". They have no intensions and encompass both intellectual systems concerned. The third is to establish an axiomatic system to illustrate a relation between the undefined terms. The axiom is as follows : In the sphere of [EXPERIlVIBNTJ, [NATURE] is[0BSERVEI)]. In this axiom, each of the undefined terms is written in capital letters and stressed by a pair of brackets. Since undefined terms have no intensions, the respective cultural aspects of both "jikken" and "experiment" can be derived from the axiom. In this process, science educators can be aware of "jikken" incommensurable with "experiment". Within the axiomatic relation as a reference frame for science education research, an epistemological reflection of pupils' and students' culture can be accomplished in science education.
- 著者
- YOSHITAKA NISHIKAWA
- 出版者
- The English Linguistic Society of Japan
- 雑誌
- ENGLISH LINGUISTICS (ISSN:09183701)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.14-31, 1990 (Released:2009-12-24)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 2 8
The aim of this paper is to give evidence for positing Agr Phrase in English from the analysis of Heavy NP Shift. It is shown that Heavy NP Shift has several peculiar properties that cannot be explained naturally under the traditional analysis which presupposes a less articulated clausal structure. I propose a new analysis, which treats Heavy NP Shift as movement to the position which agrees with AgrO. It is claimed that this analysis can provide natural explanations for the problems connected with Heavy NP Shift such as subject-object asymmetry and upward-boundedness. It is also argued that Heavy NP Shift does not license parasitic gaps.
- 著者
- Hirotomo Moriwaki Yu-Shi Tian Norihito Kawashita Tatsuya Takagi
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.5, pp.426-432, 2019-05-01 (Released:2019-05-01)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 3
Quantitative structure–activity relationship (QSAR) techniques, especially those that possess three-dimensional attributes, such as the comparative molecular field analysis (CoMFA), are frequently used in modern-day drug design and other related research domains. However, the requirement for accurate alignment of compounds in CoMFA increases the difficulties encountered in its use. This has led to the development of several techniques—such as VolSurf, Grid-independent descriptors (GRIND), and Anchor-GRIND—which do not require such an alignment. We propose a technique to construct the prediction model that uses molecular interaction field grid potentials as inputs to convolutional neural network. The proposed model has been found to demonstrate higher accuracy compared to the conventional descriptor-based QSAR models as well as Anchor-GRIND techniques. In addition, the method is target independent, and is capable of providing useful information regarding the importance of individual atoms constituting the compounds contained in the chemical dataset used in the proposed analysis. In view of these advantages, the proposed technique is expected to find wide applications in future drug-design operations.
3 0 0 0 OA カクレガニ類の話題 : その後の状況
- 著者
- 小西 光一
- 出版者
- 日本甲殻類学会
- 雑誌
- CANCER (ISSN:09181989)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.31-38, 2010-05-01 (Released:2017-07-05)
- 参考文献数
- 42
3 0 0 0 OA 高大接続改革と教育現場の断層—「善意」の帰結を問う—
- 著者
- 濱中 淳子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.4, pp.411-422, 2016-12-30 (Released:2017-05-26)
- 参考文献数
- 13
高大接続をめぐっては、すでにさまざまな施策が試みられているが、その根底には、ひとつの共通した要素が確認される。関係者たちの「善意」だ。ただ、善意がいつも望ましい施策につながるわけではないのもたしかだろう。本論文は、大学生や高校生に実施した質問紙調査の分析から、むしろこれら施策が中間層にあたる高校生を学習から遠ざけ、大学での充実した学びも難しくさせている様相を実証的に描いたものである。
3 0 0 0 OA スポーツファーマシストによるドーピング防止教育と医薬品管理の効果
- 著者
- 薄井 健介 小室 治孝 月村 泰規 渡辺 雄一 神 雅人 伊藤 千裕 井口 智恵 野島 浩幸 井上 岳 厚田 幸一郎
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.6, pp.338-346, 2013-06-10 (Released:2014-06-10)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 3
We investigated the effectiveness of using a “Sports Pharmacist” to prevent the occurrence of doping in sports.During the first step, we individually interviewed 17 high school softball team athletes and determined their regular and/or occasional use of prescription and OTC medications, herbal agents, vitamins and supplements. A total of 76% of these players were either taking or had access to medications for occasional use that contained prohibited substances. Athletes determined to be using a prohibited compound were sent a written notice that recommended they avoid carelessly taking these banned substances.In the subsequent step, we gave an educational lecture to the entire team on how to avoid doping in sports. Before and after the presentation, we evaluated the effectiveness of the lecture by examining the athletes’ knowledge and awareness of anti-doping in sports. The results indicated a significant difference after the lecture with regard to appropriate knowledge and awareness of anti-doping in sports. This specific awareness continued for at least a month.In summary, medication reviews and one-on-one consultation with athletes in conjunction with a follow-up educational lecture to the team as a group resulted in successfully educating and helping team members avoid doping. In addition, these findings demonstrated the effectiveness of the “Sports Pharmacist” profession in working with athletes to help prevent doping in the future.
3 0 0 0 OA 日本語版感覚ゲート尺度(SGI)の信頼性と妥当性の検討
- 著者
- 信吉 真璃奈 金生 由紀子 松田 なつみ 河野 稔明 野中 舞子 藤尾 未由希 下山 晴彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.89.17314, (Released:2018-09-20)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 2
The purpose of this study was to develop a Japanese version of the Sensory Gating Inventory (SGI; Hetrick, Erickson, & Smith, 2012) and to examine its reliability and validity. SGI measures abnormalities in the quality of sensory input, heightened awareness of background noises, and poor selective attention at the phenomenological level. The questionnaire was completed by 515 university and graduate students. The questionnaire package included 3 scales; 35 items from the Japanese version of SGI, 27 items from the Japanese version of the Highly Sensitive Person Scale (HSPS; Funahashi, 2011), and 25 items from the Japanese version of the Cognitive Failures Questionnaire (CFQ; Yamada, 1991). Confirmatory factor analysis showed that the Japanese SGI had an acceptable level of internal consistency. Cronbach’s alpha was calculated to examine reliability and showed high values. Correlation analyses showed that the Japanese SGI and Japanese HSPS or CFQ were moderately positively correlated. This study suggests that the Japanese SGI is reliable and valid. It can be used to screen for abnormal sensory gating before physiological or behavioral inspection.
- 著者
- 松井 輝昭
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.12, pp.2148, 1992-12-20 (Released:2017-11-29)
3 0 0 0 OA 悪性黒色腫の心臓転移により完全房室ブロックをきたした犬の1例
- 著者
- 田中 茂喜 佐々木 崇文 石黒 奈央 浦野 孝太郎 小山 秀一 木村 勇介 町田 登
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.3, pp.162-166, 2019-03-20 (Released:2019-04-20)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
爪床悪性黒色腫の心臓転移がみられた犬の完全房室ブロック(CAVB)症例について,ブロック発生の形態学的基盤を明らかにすべく,心臓刺激伝導系を中心に詳細な病理学的検索を施した.本例は,死亡する11カ月前に右前肢の第5指に発生した悪性黒色腫の外科的切除術を受けていた.剖検時,心臓の割面では暗褐色〜黒褐色の腫瘍組織が,心筋層内に多発性の増殖病巣を形成していた.病巣部の組織学的検索により,悪性黒色腫の心臓転移と診断された.腫瘍性のメラノサイトは房室接合部領域にも重度に浸潤しており,房室結節は完全に消失していた.この病的機転はヒス束貫通部をも巻き込んでおり,当該部位の伝導系細胞は全長にわたって消失していた.このような房室伝導系病変が,インパルスの房室伝導を遮断したものとみなされた.
3 0 0 0 OA 平成20年代日本の政府当局発行中学生向け放射線教育関連副読本の分析
- 著者
- 平田 昭雄 青戸 優花
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.6, pp.23-28, 2018-03-25 (Released:2018-07-01)
- 参考文献数
- 6
平成20年代日本で文部科学省他の日本国政府当局により発行された3点の中学生向け放射線教育関連副読本の内容を分析し見較べたところ、次のようなことが確認された。すなわち、初代副読本においては原子力発電と放射線関連科学技術が、二代副読本においては放射線の性質と被曝の影響が、三代副読本においては原発事故と放射線被害、被曝、復興が、それぞれ重点的に扱われるという変遷を辿っていた。そして、各副読本の作成、発行に当たっては、国のエネルギー基本計画、2011年3月の原発事故、同事故により生じた被災者の実情、などの社会的情勢が強く影響していたことを認識した。"
3 0 0 0 OA 放射線量を読み解き、人体への健康影響を理解する
- 著者
- 松田 尚樹
- 出版者
- 日本放射線看護学会
- 雑誌
- 日本放射線看護学会誌 (ISSN:21876460)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.24-25, 2019-03-31 (Released:2019-04-12)
- 著者
- 中尾 達馬 村上 達也 数井 みゆき
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- pp.27.3.1, (Released:2018-11-08)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
本研究の目的は,児童用に,アタッチメント不安とアタッチメント回避を測定可能な尺度(児童版ECR-RS)を作成し,その信頼性と妥当性を確認することであった。調査対象は小学4年生から6年生540名(平均年齢10.5歳,男児260名,女児280名)であった。本研究では,まず,児童版ECR-RSが2因子(アタッチメント不安,アタッチメント回避)から構成されているとみなせるかどうかを検討した。次に,児童版ECR-RSの信頼性については,内的整合性と再検査信頼性(5カ月)を確認した。最後に,妥当性については,児童版ECR-RSと理論的な関連性・無関連性が想定される変数(アタッチメントの安定性,全体的自己価値,情動知能,共感性,生活満足度,対人不安傾向,孤独感,友人関係良好度,運動能力評価)との間で検討を行った。これらの結果は,我々の予測をおおむね支持していた。以上の結果から,児童版ECR-RSは,一定の心理測定的属性(信頼性と妥当性)を備えた尺度であることが示唆された。
3 0 0 0 OA 戦後の理科教育改革にみる日本文化に適した科学技術リテラシー教育と社会受容研究
- 著者
- 仲矢 史雄 中山 実 野原 佳代子
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.4, pp.49-52, 2014 (Released:2018-04-07)
- 参考文献数
- 8
科学技術リテラシーの構成概念は、科学技術の基本的な知識と、科学的思考力・批判的能力や科学的態度を包括している。戦後、アメリカ占領軍の強力な指導権のもと作られた我が国最初の学習指導要領・理科編には、その政策の一環として民主主義社会の科学的精神の重要性を説かれている。その結果、旧来の教科書と大きく異なる理科教科書「小学生の科学」が文部省によって編纂された。その内容は、実生活に基づく学習者の自主的な思考を重視する問題解決型であり、また当時最高の紙質 4 色オフセット印刷、1 学年当たりの総ページ数は 300 ページを超えるという質、量ともに破格の内容であった。この教科書は、その後の我が国の理科教育に大きな影響をおよぼしているが、一方で、その後の理科教科書が系統学習型になっており、社会的に受容れず継承されていない要素も多い。本研究では、教育資料として貴重な「小学生の科学」の原資料をデジタルデータ(画像およびテキスト)化し、多面的な研究を行った。