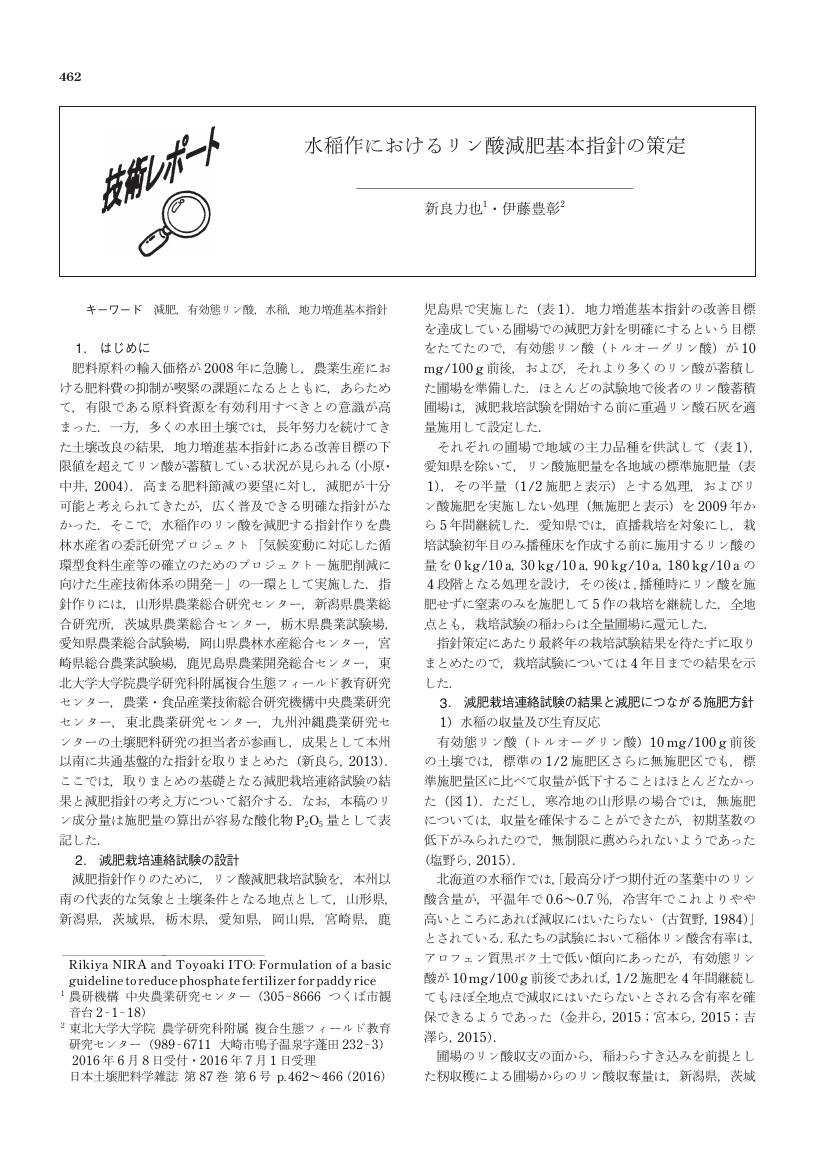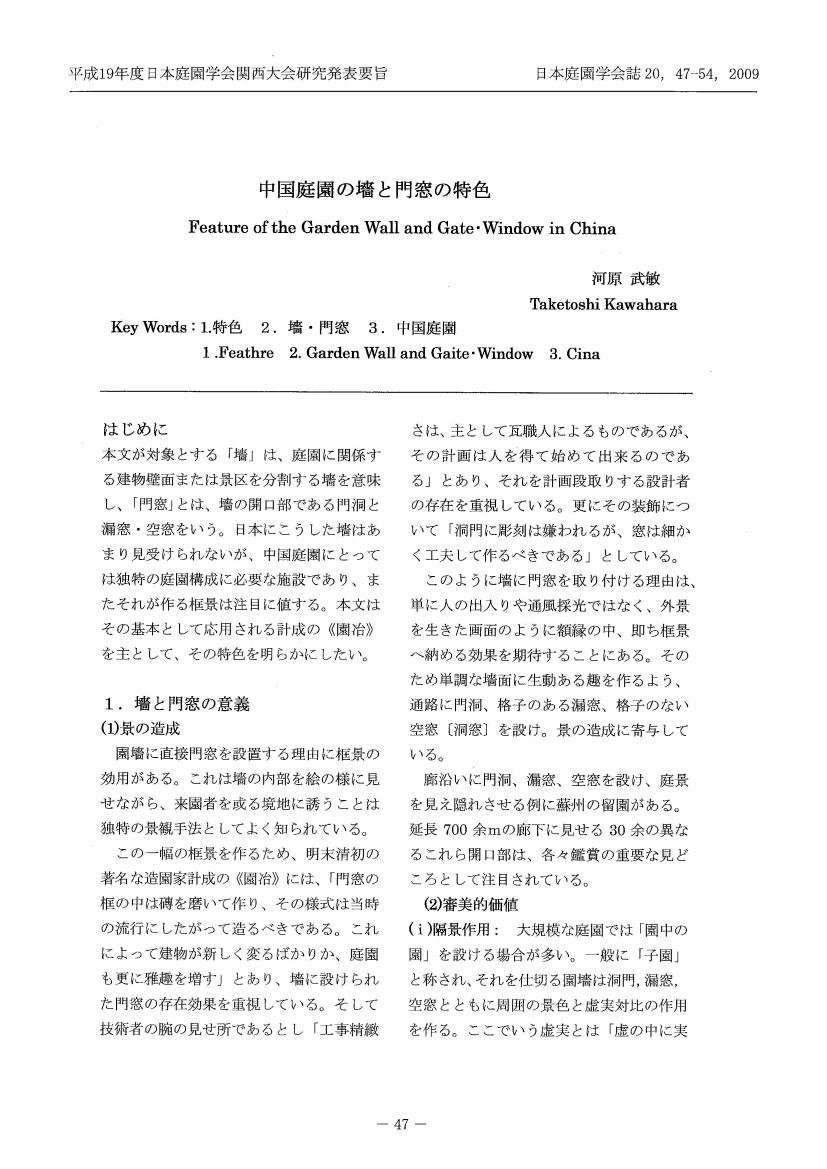24 0 0 0 OA 誤嚥性肺炎の予防と治療
- 著者
- 寺本 信嗣
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.231-235, 2012-10-31 (Released:2016-04-25)
- 参考文献数
- 13
経口摂取困難な高齢者や誤嚥性肺炎を繰り返す高齢者に対する,栄養摂取は重要な課題である.このような高齢者では,経口摂取を一時的に中止し,経管や経静脈的な栄養管理が必要になる.この際,経皮内視鏡的胃瘻増設術percutaneous endoscopic gastrostomy(PEG)は,重要な選択肢の一つである.しかし,PEGは優れた栄養療法であるが,不顕性誤嚥に対する十分な予防策ではない.脳梗塞後の患者で早期に栄養介入を行うことは予後を改善するが,PEGを選択することで肺炎が減るわけではない.したがって,PEGによる栄養療法を導入する場合,平行して肺炎予防策を講じる必要があり,食事を摂っていなくとも,口腔ケア,嚥下リハビリテーションを行い,胃腸の蠕動運動の改善,胃食道逆流の予防などを行うことが大切である.
24 0 0 0 OA 死産・新生児死亡で子どもを亡くした父親の語り
- 著者
- 今村 美代子
- 出版者
- 一般社団法人 日本助産学会
- 雑誌
- 日本助産学会誌 (ISSN:09176357)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.49-60, 2012 (Released:2012-08-31)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 3 2
目 的 死産または新生児死亡により子どもを亡くした父親が,妻の妊娠中から現在までにどのような体験をしてきたのかという語りを記述し,それを通して父親をより深く理解し,求められるケアの示唆を得ることである。対象と方法 死産または新生児死亡で子どもを亡くした6名の父親を対象に半構成的面接を行い,現象学的研究方法を参考に質的記述的に分析した。結 果 父親の体験は,以下の7つに分類された。1. 予期せぬ死に衝撃を受ける:子どもを突然に失ったという,驚きや混乱からもたらされた精神的衝撃,そして,その後に引き続く無力感,空虚感であった。2. 自分の悲しみをこらえ妻の心身を案じる:自分の悲しみよりも先に,心も身体も傷つけられたであろう妻の立場を気遣っていた。3. 辛さを隠し父親·夫としての役割を果たす:自分の辛さを押し隠し,子どもを送り出す為の諸々の手続きを引き受け,父親と夫の両方の役割を果たしていた。4. 社会に傷つけられながら生活を続ける:男性の備え持つ特性により,悲しみは内に抱え込まれたまま表出されず,更に子どもの死を嘆き悲しむことを認めない社会に傷つけられていた。5. 子どもの死因を知りたいと望む:子どもの死に対して何らかの意味付けを行い,死を受容してゆくきっかけとしていた。6. 父親として在り続ける:子どもが誕生する以前からその存在を愛しみ,子どもを亡くした後も父親として在ることに変わりなかった。7. 人間的な成長を遂げる:父親達は悲しみを抱えながらも「自分自身の力で乗り越えた」,死生観が変容した,人生観が変容した,自分の体験を他者に生かして「共有」したいと願った。結 論 死産·新生児死亡によって子どもを亡くした父親は,予期せぬ我が子の死に大きな衝撃を受け,悲しみを押し隠しながらも父親と夫の役割を果たしていた。表面化されない悲しみは社会からも見過ごされ,時に父親自身も気付き得ないほどであったが,亡き子どもの存在を忘れることはなく,父親として在り続けることで人間的な成長を遂げていた。
24 0 0 0 OA 福島県南会津地域に伝わる「麦芽水あめ」の特性
- 著者
- 本間 祐子 角野 猛 真鍋 久
- 出版者
- 日本食生活学会
- 雑誌
- 日本食生活学会誌 (ISSN:13469770)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.106-113, 2011-09-30 (Released:2011-10-27)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
“Malt mizuame (millet jelly)” is a traditional food that has long been produced in the Minamiaizu region of Fukushima Prefecture. In the present study, we investigated the characteristics of the method used in this region for making malt mizuame and the sweet components. Following are our findings: In the Minamiaizu region, the unique customs of ameyobi or ameyobare are associated with malt mizuame;these customs were thought to have developed due to the mild sweetness and functionality of mizuame. During the saccharification process in the making of malt mizuame,steps are taken to maximize the saccharifiability of malt to starch.We identify these processes as an important way to reduce the amount of time required for saccharification.
24 0 0 0 OA 水稲作におけるリン酸減肥基本指針の策定
- 著者
- 新良 力也 伊藤 豊彰
- 出版者
- 一般社団法人 日本土壌肥料学会
- 雑誌
- 日本土壌肥料学雑誌 (ISSN:00290610)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.6, pp.462-466, 2016-12-05 (Released:2017-11-27)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 3
24 0 0 0 OA 多重比較法の実際
- 著者
- 永田 靖
- 出版者
- Japanese Society of Applied Statistics
- 雑誌
- 応用統計学 (ISSN:02850370)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.93-108, 1998-10-30 (Released:2009-06-12)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 7 8
統計的多重比較法の適用において,実務家から寄せられた疑問点を材料にして,「多重比較法に関する誤解・誤用」,「多重比較法を用いる際の注意点」などについて検討する.取り扱う内容は,「分散分析と多重比較法との関係」,「ノンパラメトリック法にっいての誤解と注意」,「Scheffeの方法やDuncanの方法について」,「対照群が複数個ある場合の考え方」,「検出力とサンプルサイズの設計について」,「毒性試験・薬効試験における多重比較法の適用の妥当性」などである.
24 0 0 0 OA 超準解析とはどういうものか
- 著者
- 齋藤 正彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.133-149, 1986-05-09 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 40
24 0 0 0 OA 福島原子力発電所事故時の安定ヨウ素剤に関する薬剤師の経験と今後の課題
- 著者
- 遠藤 きよ子 高橋 まり子 功刀 恵美子 野口 和孝 佐藤 政男
- 出版者
- 日本社会薬学会
- 雑誌
- 社会薬学 (ISSN:09110585)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.43-50, 2014-06-10 (Released:2015-08-11)
- 参考文献数
- 20
The Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant (FDNPP) Accident happened in Fukushima prefecture in March, 2011 and various efforts have been carried out to prevent health damage, including thyroid cancer, caused by radioactive-iodide. In this present report, we tried to discover whether stable-iodide for the prevention against the development of thyroid cancer was properly administered to radioactive-iodide-exposed persons or not. Since pharmacists play an important role in the treatment of stable-iodide, we investigated how the pharmacists in Fukushima contributed to the treatment of stable iodide in the FDNPP accident. In addition, we introduce a new revised method for the treatment of stable iodide published by the Nuclear Regulation Authority, discuss the important role of pharmacists in the Nuclear Power Plant Accident, and propose possible ways of preparation to protect the health of citizens.
24 0 0 0 OA 国際法から見た日本人捕虜のシベリア抑留
- 著者
- 白井 久也
- 出版者
- ロシア・東欧学会
- 雑誌
- ロシア・東欧学会年報 (ISSN:21854645)
- 巻号頁・発行日
- vol.1994, no.23, pp.33-42, 1994 (Released:2010-05-31)
24 0 0 0 OA 放射線被曝問題における批判的科学
- 著者
- 立石 裕二
- 出版者
- 科学社会学会
- 雑誌
- 年報 科学・技術・社会 (ISSN:09199942)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.31-46, 2013-06-30 (Released:2022-09-10)
24 0 0 0 OA CGRP関連抗体による片頭痛の新規治療
- 著者
- 柴田 護
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.10, pp.668-676, 2020 (Released:2020-10-24)
- 参考文献数
- 69
片頭痛の有病率は約10%と報告されている.片頭痛では,数時間持続する拍動性頭痛が悪心・嘔吐や光過敏を随伴して繰り返し起こる.個々の患者のQOLは大きく障害され,社会全体に与える経済的影響も非常に大きい.動物実験や機能画像を用いた臨床研究から,片頭痛は視床下部,大脳皮質,三叉神経系,自律神経系など非常に広範な部位の異常を呈する複雑な神経疾患であることが明らかとなった.従来の片頭痛発作予防治療では,カルシウム拮抗薬や抗てんかん薬などが経験に基づいて用いられてきた.しかし,カルシトニン遺伝子関連ペプチド(calcitonin gene-related peptide; CGRP)が片頭痛病態に深く関与することが明らかとなり,CGRP関連抗体による特異的治療が脚光を浴びている.
24 0 0 0 OA 静岡県引佐町久留女木の棚田における草刈空間の維持管理実態
- 著者
- 小林 成彦 荒井 歩
- 出版者
- 公益社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.5, pp.707-710, 2015 (Released:2015-12-22)
- 参考文献数
- 10
This paper focuses on the stage of annual maintenance of weeding levee slope of terraced paddy fields called Kurumeki-no-tanada, in Inasa-chou, Hamamatsu , Shizuoka prefecture. In this study, we characterize ridges between rice fields and grassy fields as ‘fields for weeding’. First, we survey cultivated paddies and fields for weeding. Secondly we presents some results concerning the relation between the management systems and farmers. Finally, we consider some arrangements for sustainable conservation on these rice terraces. It was concluded that 1. The fields for weeding have been classified into five types, 1) Cultivated paddies of 35 groups has been weeding, 2) Abandoned paddies of 38 groups has been weeding, 3) Abandoned paddies there are not weeded is 21 groups, 4) Grassy fields of 21 groups has been weeding, and 5) Grassy fields there are not weeded is 21 groups. 2. There are four rules for maintenance of fields for weeding, 1) Border division of the management range, 2) Range of duties of restoration, 3) Right to weeding range, and 4) Work support of the mutual help by village residents for large-scale restoration.
24 0 0 0 OA 「就職用自己分析マニュアル」が求める自己とその機能 「自己のテクノロジー」という観点から
- 著者
- 牧野 智和
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.150-167, 2010-09-30 (Released:2012-03-01)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 1
本稿では,大学生の就職活動における自己分析という慣行の定着を,新規大卒採用市場における1つのサブ市場の確立と捉える.このことで,先行研究の欠落点であった,自己分析への関わり方の多様性,送り手と受け手,その影響力の限定性という論点に対応することができる.また本稿では自己分析を,「自己の自己との関係」を通した主体化を行う「自己のテクノロジー」と捉える.このことで他の自己論との比較を可能とし,また先行研究の難点であった定着因の考察を資料内在的に行うことができる.このような観点から,自己分析市場が提供する「自己のテクノロジー」の分析とその機能の考察を行った.分析対象は自己分析をその内容に含む就職対策書,190タイトル計758冊である.自己分析の作業課題の核には,自らの過去の回顧,現在の分析,未来の想像を通して「本当の自分」を抽出する志向がみられる.だがこれは純粋に心理主義的なものではない.自己分析では具体的な職業の導出,内定の獲得に向けた自己の客観化,積極的な自己表現もともに求められるためである.分析を通して,自己分析市場は新規大卒採用市場における不透明性の低減,動機づけの個人的獲得支援・調整,社会問題の個人化という機能を果たしていると考えられた.だが採用状況の悪化によって社会問題の個人化機能が突出するとき,それを可能にする「自己のテクノロジー」への注意が払われなければならない.
24 0 0 0 OA 第15章 ポーランドと東方ロカルノ案 (1934年) に関する小論
- 著者
- 植田 隆子
- 出版者
- 東欧史研究会
- 雑誌
- 東欧史研究 (ISSN:03866904)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.176-189, 1978 (Released:2017-09-28)
24 0 0 0 OA 原爆被爆者の健康管理としての温泉療法
- 著者
- 八田 秋
- 出版者
- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会
- 雑誌
- 日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1-2, pp.23, 1968-12-25 (Released:2010-08-06)
24 0 0 0 OA 日本産淡水海綿の概説および日本産の種について
- 著者
- 益田 芳樹
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.15-22, 2006-02-20 (Released:2018-03-30)
- 参考文献数
- 44
All species of freshwater sponges belong to the suborder Spongillina (Phylum Porifera) and are classified into seven families. Some families (such as Spongillidae comprising about 150 species) are geographically widespread, while others (such as Lubomirskiidae) are endemic to small areas. Spicules exsist in a variety of forms and are most important in the identification and classification of species and higher taxa. Other important key characters for identification are size, form and structure of gemmules, the gemmule coat, and micropyle. Most freshwater sponges produce gemmules, which are resistant bodies and asexual propagules. In Japan, the timing of gemmule production varies among species. Some species are hatched from gemmules in early spring and produce gemmules in early summer when water temperatures have not reached the maxima. Green color of freshwater sponge bodies is caused by the presence of algal symbionts. The algal symbionts are classified into two major groups based on the presence or absence of pyrenoid. In Spongilla lacustris, transfer of symbionts from parents to the next generation has been observed in both sexual and asexual reproduction. The classification of symbionts in several sponge species is currently under investigation using culture and molecular biological methods. Whether host specificity exists in these symbiotic algae is also under investigation. All Japanese species belong to the family Spongillidae. The Japanese species have been classified into 25 species in 11 genera. Recently, Heterorotula multidentata and Trochospongilla pennsylvanica have conspicuously increased in their geographical range in Japan, although they were not recorded before World War II. They may be exotic species introduced by human activity.
24 0 0 0 OA 中国庭園の墻と門窓の特色
24 0 0 0 OA 仙台湾地区における東日本大震災からの海岸防災林復旧の取組み
- 著者
- 村上 卓也
- 出版者
- 一般社団法人 日本治山治水協会
- 雑誌
- 水利科学 (ISSN:00394858)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.6, pp.105-126, 2017-02-01 (Released:2018-03-31)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 2
24 0 0 0 OA 清宮憲法と宮沢憲法 ──日本憲法学における私の二師──
- 著者
- 樋口 陽一
- 出版者
- 日本学士院
- 雑誌
- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.2, pp.103-120, 2021 (Released:2021-02-20)
Propos introductif KIYOMIYA (1898-1989) et MIYAZAWA (1899-1976), les deux disciples représentatifs de MINOBE Tatsukichi (1873-1948), fondateur de la doctrine de constitutionnalisme au Japon I. Dans le année 1920-30 : théories critiques chez Kiyomiya et Miyazawa inspirées, l'un et l'autre, par la théorie pure du droit de Hans Kelsen 1. Ce que signifie la théorie pure du droit : «Reine Rechtslehre ist keine Rechtslehre» ? S'agit-il d'une «rechtsleere Rechtslehre» ? 2. Analyse d'interrogation par Kiyomiya ainsi que par Miyazawa à l'encontre des doctrines qui leur précédaient : les deux articles, parus dans les Mélanges offerts en l'honneur de Minobe (1934), l'un par Kiyomiya sur la possibilité logique de «lex posterior non derogat priori» et l'autre par Miyazawa sur le caractère fictif et idéologique de la notion de «représentation nationale». 3. Suite et développement : die «Grundnorm» non plus comme «vorausgesetzte », mais en tant que droit positif pour Kiyomiya, et le cours inaugural de Miyazawa comme successeur de la chaire de Minobe où il s'identifie, en invoquant Auguste Comte, à la troisième et dernière phase du développement du savoir. 4. Affaire de la doctrine de l'Empreur organe de l'Etat et prise de position de Miyazawa pour la défense de la liberté académique, tout en distinguant la doctrine préscriptive d'avec la théorie descriptive.(View PDF for the rest of the abstract.)
24 0 0 0 OA 天理市における教団と地域住民間の土地利用をめぐる諸相
- 著者
- 石坂 愛
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.299-315, 2016-09-30 (Released:2016-10-11)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
本研究では,都市化と宗教弾圧の歴史の中で発展した新宗教の聖地における教団と地域住民間の土地をめぐる葛藤の実態とその要因を明らかにすることを目的とする.研究方法として,奈良県天理市において進められる天理教教会本部の宗教都市構想の基盤となる八町四方構想に着目し,その計画地をめぐる地域住民と教団の交渉過程と,構想に対する地域住民の意識を追った.その結果,調査対象者の地域住民のうち約90%が天理教信者であるにも関わらず,約45%がこの構想に葛藤を抱いていることがわかった.その要因として,①教団の持つ宗教的イデオロギーと自身の考える教理の不一致があることがわかった.その他の要因として,②地域住民内部での八町四方構想に関する知識共有の薄弱化③教団と土地所有者のみで取り行われる土地・建物の譲渡交渉が考えられる.
- 著者
- Hideo Yasunaga
- 出版者
- Society for Clinical Epidemiology
- 雑誌
- Annals of Clinical Epidemiology (ISSN:24344338)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.33-37, 2020 (Released:2020-04-28)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 9 35
Propensity score is defined as the probability of each individual being assigned to the treatment group. Propensity score analysis has recently become the sine qua non of comparative effectiveness studies using retrospective observational data. The present report provides useful information on how to use propensity score analysis as a tool for estimating treatment effects with observational data, including (i) assumptions for propensity score analysis, (ii) how to estimate propensity scores and evaluate propensity score distribution, and (iii) four methods of using propensity scores to control covariates: matching, adjustment, stratification, and inverse probability of treatment weighting.