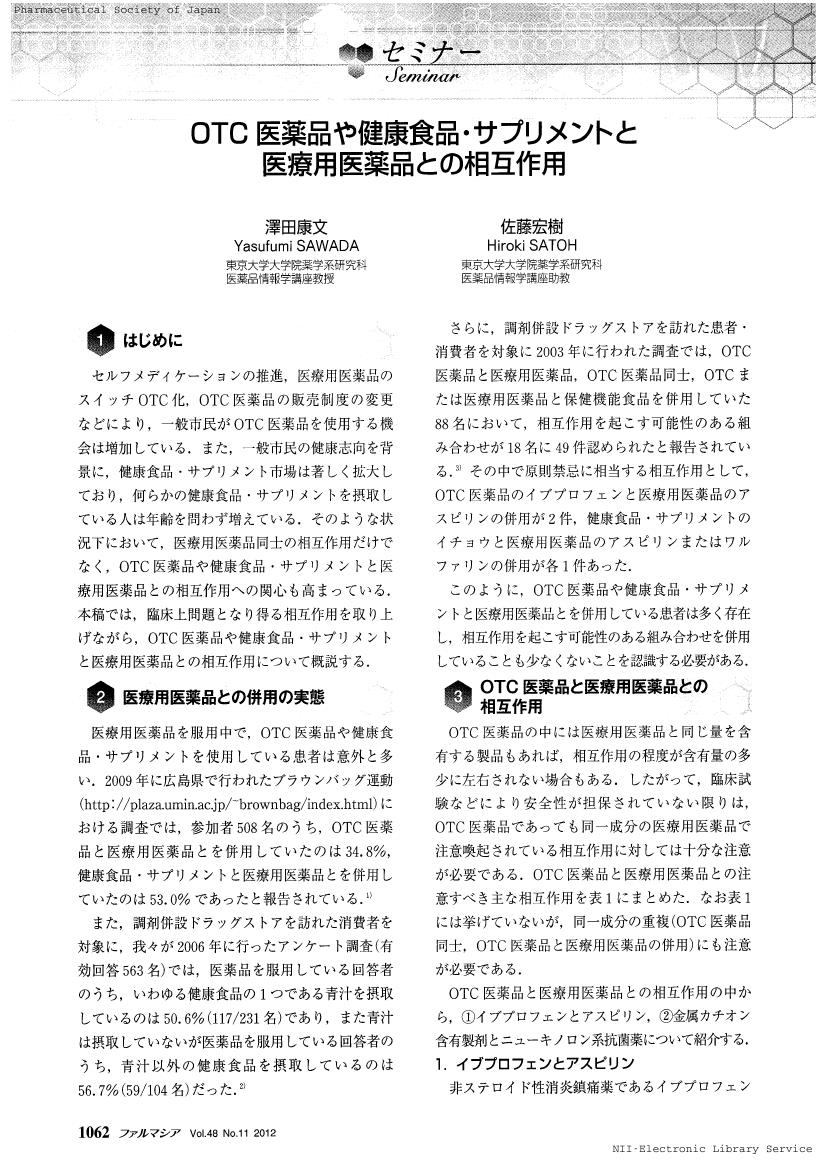1 0 0 0 市民科学と生物多様性情報データベースの関わり
- 著者
- 宮崎 佑介
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.237-246, 2016
新興の学術領域であるCitizen Science(市民科学)の発展は、情報科学技術の発展と不可分の関係にある。生物多様性に関連する分野においても、その可能性はとみに高まっている。本稿では、市民科学に関連する生物多様性情報データベースの現況と課題を、国内外の事例から概観することによって、今後の生物多様性情報データベースを活用した市民科学の在り方を考える。
1 0 0 0 "市民科学"が持つ意義を多様な視点から再考する
- 著者
- 佐々木 宏展 大西 亘 大澤 剛士
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.243-248, 2016
近年の保全生態学において、研究者が非専門家である一般市民と共同で調査等を行う「市民科学」(Citizen Science)は、有効な研究アプローチとして受け入れられつつある。しかし、市民科学は本来、市民が主体の活動であり、成果を研究者らが論文としてまとめることを目的とした活動は、市民科学が持つ意味のごく一部にすぎない。市民科学という言葉が定着しつつある今日、これを短期的な流行で終わらせないために、市民科学における研究者、市民それぞれの役割やあるべき姿について再考することは有意義である。筆者らは、中学校教諭、博物館学芸員、国立研究開発法人研究員という異なった立場から市民科学について議論し、研究論文につながる、つながらないに関係なく、全ての市民科学には意義があり、成功、失敗は存在しないという結論に達した。本稿では、上記の結論に達するまでの議論内容を通し、筆者らの意見を述べたい。
1 0 0 0 調査観測兼清掃船「海輝」「海煌」による八代海の海域環境特性の把握
- 著者
- 只隈 章浩 幸福 辰己 滝川 清 横手 敏弘 奥村 靖浩 小田 勝也 小堀 達
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木学会論文集B3(海洋開発) (ISSN:21854688)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.I_491-I_496, 2015
国土交通省九州地方整備局では,調査観測兼清掃船「海輝」「海煌」を用いて,有明海・八代海の海域環境特性の把握を目的として,水塊構造調査並びに底質・底生生物調査を実施している.2004-2013年度の10ヶ年分の調査結果を整理した結果,八代海では球磨川河口前面海域よりも湾奥の海域の方が表層-下層間の密度差が大きいことが確認された.また,八代海において,底質と底生生物群集のクラスター解析により,それぞれ4つのグループに分類されるが,さらに,これらの組み合わせにより9つのグループに細分類され,複雑な環境特性を持つ海域であることが明らかになった.
1 0 0 0 大都市近郊の住宅地域における生態系管理のための市民科学の活用
- 著者
- 小松 直哉 小堀 洋美 横田 樹広
- 出版者
- 日本景観生態学会
- 雑誌
- 景観生態学 (ISSN:18800092)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.49-60, 2015
- 被引用文献数
- 1
都市の生物多様性の持続的管理のためには,住宅地域も対象とした広域的な生態系管理を行なう必要がある.その実現のためには,地域に居住し,その周辺環境と身近に接している地域住民を対象とした市民科学の導入は有効な手法として挙げられる.市民科学とは,専門家ではない市民や学生がモニタリングやデータ収集だけでなく,主体的に科学的研究プロセスに関わる手法であるが,市民科学を用いた科学研究の成果を広域的な生態系管理に生かしている事例は少ない.そこで本研究では,横浜市都筑区牛久保西地区において,学生および市民が,1)チョウ・トンボを指標とした生物分布調査,2)個人住宅における庭の生物調査,3)大学保全林内のチョウのビオトープの創出と検証,といった生態系のモニタリングと管理を市民科学プログラムとして実践すること,その結果から住宅地域の生態系管理における市民科学の今後の可能性と課題を抽出することを目的とした.チョウ・トンボの生物分布調査では,住宅地域の生物分布を明らかにし,生物分布データベースとして意義のある調査結果を共有した.個人住宅における庭の生物調査では,庭に出現する身近な生物と庭の環境要因との関係性を学生と市民との協働により評価した.また,大学保全林を活用したチョウ誘致のためのビオトープ創生とモニタリングの実践により,ビオトープがチョウ類の生息拠点としての機能を有しているか検証した.これらの市民科学プログラムを活用することによって,住宅地域の生物相ポテンシャルや生物にとっての私有地の緑の重要性などを学生と市民が共有でき,また,住宅地域の生態系管理おける市民科学の有効性が示唆された.牛久保西地区の緑のまちづくり事業では,これらの市民科学プログラムの成果を活用した緑の管理は,官学民の連携により行っている.今後,市民が生態系管理の意義などを理解したうえで独立して調査や管理を行えるような教育プログラムなどの教育的側面を充実させることにより,大都市近郊の住宅地域における生態系管理へ展開していける可能性がある.
- 著者
- 蘆田 裕史
- 出版者
- 青土社
- 雑誌
- ユリイカ (ISSN:13425641)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.14, pp.149-157, 2011-12
- 著者
- 吉中 奎貴 中村 孝 髙久 和明 塩澤 大輝 中井 善一 上杉 健太朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.856, pp.17-00104-17-00104, 2017 (Released:2017-12-25)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 2
The initiation and growth of internal small fatigue cracks with around ten or several dozen μm in Ti-6Al-4V were nondestructively examined by using synchrotron radiation μCT at the large synchrotron radiation facility SPring-8. Lots of grain-sized internal cracks were observed roughly evenly in the observation volume in the specimen; in contrast, only one surface crack was detected. The initiation lives of the internal cracks were widely different for each crack and had no significant correlation with the crack initiation site nor the initial crack size. The internal cracks propagated microstructure-sensitively with several crack deflections, and the growth rates were very small, less than 10-10 m/cycle. The crack growth rates just after facet formations showed large variability and had no apparent relationship with the crack initiation life nor the initial crack size. This variability can likely be attributed to microstructural inhomogeneities around the crack initiation facets. The estimated facet formation rate indicated that most facets formed rapidly compared with the following internal crack growth rate.
1 0 0 0 IR 広島控訴院管内における陪審裁判・資料解題
- 著者
- 広島修道大学「明治期の法と裁判」研究会 緑 大輔 ヒロシマシュウドウダイガク「メイジキノホウトサイバン」ケンキュウカイ ミドリ ダイスケ Research Group of Hiroshima Shudo University for Laws and Justice in the Meiji Era Daisuke MIDORI
- 雑誌
- 修道法学
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.307-321, 2014-02-28
1 0 0 0 OA OTC医薬品や健康食品・サプリメントと医療用医薬品との相互作用
- 著者
- 澤田 康文 佐藤 宏樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.11, pp.1062-1066, 2012-11-01 (Released:2016-12-16)
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1715, pp.124-127, 2013-11-11
同じソーシャルメディアを使った情報発信でも、従来は自社のキャンペーン情報や商品に関連した画像などを公式アカウントで公開し、それが拡散するかどうかはアカウントをフォローする受け手の反応次第だった。 新たな取り組みでは、公式アカウントのフォロ…
1 0 0 0 非接触給電を利用した玩具の提案
- 著者
- 東藤 絵美 吉池 俊貴 馬場 哲晃 串山 久美子
- 雑誌
- 研究報告エンタテインメントコンピューティング(EC)
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, no.11, pp.1-6, 2012-05-07
遊び手が人形を動かさなくとも,ドールハウス内の人形が動いている映像や CM はよく知られている.しかし市販のドールハウス人形は,遊び手が人形を動かす必要がある.本研究では,ドールハウスに人形を置くだけで自動に人形が動くことを目標とし,設計条件として①人形の外観を損ねない/②電池を必要としない/③スイッチで ON・OFF 操作を必要としない,の 3 点を掲げた.設計条件の解決の為に非接触給電技術を用いてプロトタイプ制作を行うことで,より使い勝手のよい人形遊びを提案し,上記の人形設計の条件を満たす人形とドールハウスの土台の制作を実現した.また,本稿では非接触給電を用いた音楽シーケンサタイプのアプリケーションについても提案する.給電デバイスの最適な位置に受電デバイスを置くだけで,電力が供給され,ソレノイドアクチュエータを動かし鉄琴の音板を鳴らすシーケンサタイプの楽器を提案する.We can watch a TV commercial that the doll in a dollhouse is moving automatically. However, in fact, those dolls do not run automatically, so we need to put and move dolls if we want to move those. In this paper, we aim at realizing that the doll itself moves automatically like a TV commercial, when we put dolls on the dollhouse. We impose following three conditions, when we design doll. (1) Not spoil an appearance of a doll (2) Not use a battery (3) Not use an ON-OFF operation. We made the prototype, using "Contactless power transmission" as technology which fulfills the above conditions. Moreover, we propose a music sequencer used contactless power transmission. If we put a receiving device on an electric supply device, electric power will be supplied to it. Then, a solenoid actuator strikes glockenspiel. We can play music using this device.
1 0 0 0 女性外科医支援の現状と課題
- 著者
- 野村 幸世 川瀬 和美 萬谷 京子 明石 定子 神林 智寿子 柴崎 郁子 葉梨 智子 竹下 恵美子 田口 智章 山下 啓子 島田 光生 安藤 久實 池田 正 前田 耕太郎 冨澤 康子
- 出版者
- 日本外科系連合学会
- 雑誌
- 日本外科系連合学会誌 (ISSN:03857883)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.187-195, 2015
日本では外科を選択する医師は減少していますが,日本外科学会に新規入会する女性医師は年々増加しており,2008年新入会の22%が女性でした.ところが,日本の女性の年齢別就労人口をみると,M字カーブを描き,30,40代での離職が目立ち,医師も例外ではありません.この現状を打破するために必要な支援を探るため,日本外科学会女性外科医支援委員会と日本女性外科医会が中心となり,2011年6月下旬~8月末に日本医学会分科会に対し,専門医,認定医制度,評議員,役員,委員会委員,男女共同参画,女性医師支援に関しアンケートを行いました.その結果,多くの学会で女性医師支援の活動は行われつつあることがわかりました.しかし,役員,評議員,委員会委員といった意志決定機構における女性の割合は低いままにとどまっています.あらゆる意思決定機関に女性を参入させることが,女性外科医の活動を,ひいては我が国の外科医療そのものを加速させるのではないかと思われました.
1 0 0 0 4H-SiC非極性面の表面再結合速度の解析
- 著者
- 渡邉 麻友美 射手園 健斗 遠藤 央 菅原 雄介 岡本 淳 柿崎 隆夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, pp.2A2-L05, 2017
<p>In this study, focusing on the sustainability of the environment and health, it has proposed a mobility that human-powered. The proposed system is designed on the "Man-powered robotics", which realizes the intelligent operation by controlling the power to be transmitted to the output shaft in the robot system. Manpower to implement the safety control in mobility to the power source, it puts control to allow prolonged exercise. As a result , to health by increasing the chance of occupant movement. Moreover, by making human power to power, it becomes environmentally friendly mobility. In this paper, the mobility of control is discussed. Specifically, when mobility operates in one dimension, Simulate the torque around the pedal axis. This confirms the effectiveness of control.</p>
1 0 0 0 OA 太平御覽 1000卷目録15卷
- 著者
- (宋) 李昉 等奉敕撰
- 出版者
- 饒世仁等銅活字印
- 巻号頁・発行日
- vol.[40], 1574
- 著者
- 玄侑 宗久 関根 謙
- 出版者
- 三田文学会 ; 1985-
- 雑誌
- 三田文学. [第3期]
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.132, pp.174-189, 2018
1 0 0 0 OA 医療におけるIoTとレギュレーション
- 著者
- 加納 信吾
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 年次学術大会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.464-467, 2017-10-28
一般講演要旨
1 0 0 0 OA 健康・医療分野における日米欧の研究開発課題の比較 : 2型糖尿病を例に
- 著者
- 重茂 浩美 小笠原 敦
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 年次学術大会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.455-459, 2017-10-28
一般講演要旨
1 0 0 0 膵転移,胆嚢転移を認めた腎癌の2例
- 著者
- 寺島 雅典 安部 彦満 菅 一徳 松谷 富美夫 小林 謙太郎 伊藤 進 佐々木 亮孝 菅野 千治 斉藤 和好 冨地 信和
- 出版者
- 一般社団法人日本消化器外科学会
- 雑誌
- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.7, pp.1952-1956, 1990-07-01
- 被引用文献数
- 8