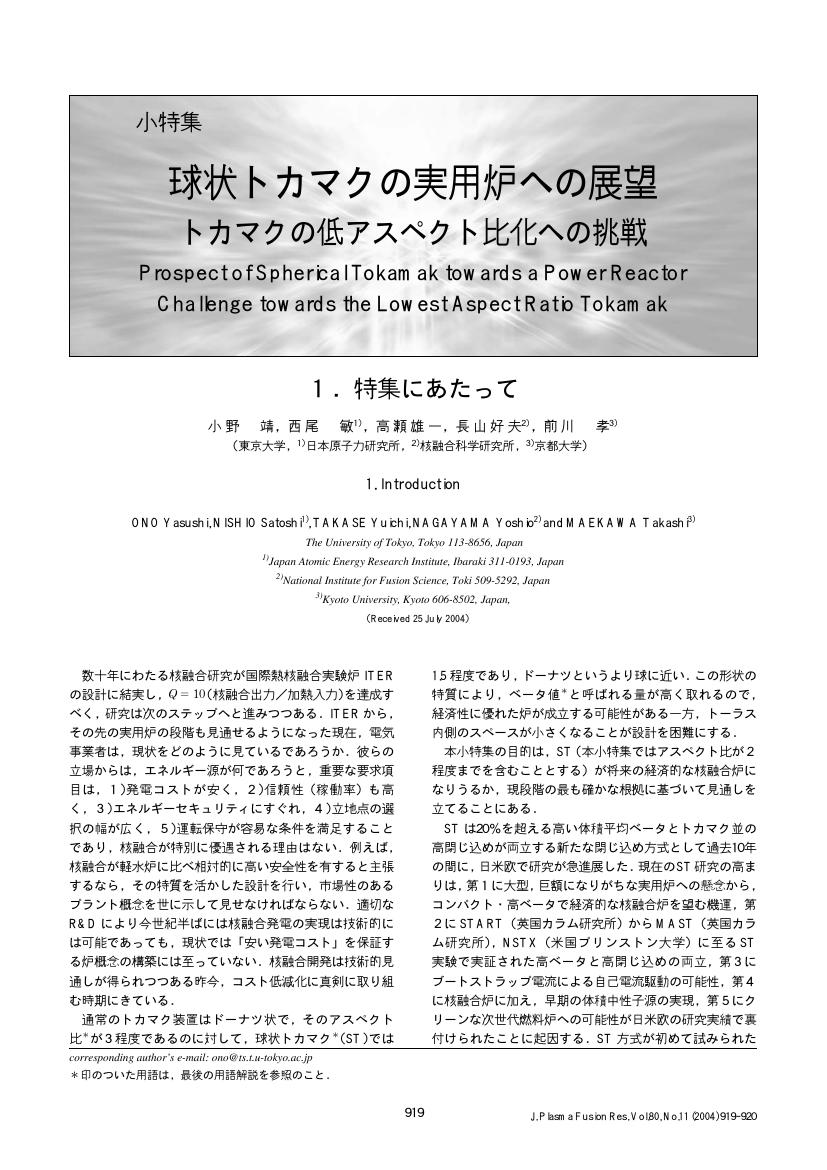2 0 0 0 OA 新型コロナウイルス感染拡大と流言・トイレットペーパー買いだめ 報道のあり方を考える
- 著者
- 福長 秀彦
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.7, pp.2-24, 2020 (Released:2021-04-16)
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中で、トイレットペーパーをめぐる流言と買いだめが如何にして発生したのか、また、両者がどのように関わり合っているのかを検証した。そのうえで、流言と買いだめを的確に抑制する報道のあり方を考察した。検証と考察の結果は以下の通り。 ■「トイレットペーパーが不足する」という流言の発生には、マスク不足、オイルショック、海外の買い占め騒動が心理的要因として作用していた。日本とシンガポールなどで拡散した流言はほぼ同じ内容であり、感染症の流行による国際社会の不安から、流言は国境を越えて拡がった。 ■買いだめの動きは、流言がきっかけとなって各地で散発的に始まり、2月28日に急加速した。急加速を主に促したのは、品切れの様子を伝えたテレビだった。 ■流言を信じて買いだめをした人は少なかった。多くの人は流言を信じていなかったが、「他人は流言を信じて買いだめをしているので、このままでは品物が手に入らなくなる」と思い、買いだめをしていた。そうした心理は品切れとなる店舗が増えるにつれて増幅し、買いだめに拍車をかけた。 ■流言を否定する情報は、店頭から現実にモノが消えているので、説得力を欠いた。買いだめが加速すればするほど、品不足への不安が高じて、流言の打ち消しは効果が逓減した。 ■流言が社会に悪影響を及ぼす群衆行動へとエスカレートする前に、流言の拡散を抑え込まなければならない。
2 0 0 0 OA 説話文学における舞台と内容の関連性―平安時代の都とその周辺を対象に―
- 著者
- 安藤 哲郎
- 出版者
- 一般社団法人 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.41-54, 2008 (Released:2018-01-06)
- 参考文献数
- 37
This paper gives a synoptic view of the distribution of places mentioned in the setsuwa stories compiled in the late Heian and early Kamakura periods (the 12th and first half of the 13th centuries). The author deals with places that were described as the staging areas for various events occurring during the Heian period, in and around Heian-kyo (present-day Kyoto).The author presents a geographical analysis of classical Japanese literature. Existing studies of the field have tended to focus on individual works or authors. In this paper, various stories including similar contents from different compilations are classified and analyzed in temporal and spatial dimensions.The category of setsuwa literature consists of many stories that include miracles and reasoning based on Buddhist teachings. Those stories were collected and resulted in several compilations (setsuwa-shu) in the late Heian and early Kamakura periods. The events told in the stories were distinguished ‘desirable’ from ‘undesirable’ for the people described. Then the locations of the events were plotted on maps of different times during the Heian period.By examining such maps, we can see that the locations of those events were familiar to the inhabitants of Heian-kyo. We can also see that residences and Buddhist temples related to the ruling people of the time were mentioned frequently. This suggests that the events in the stories were told as occurring in reality, reflecting the nature of setsuwa literature.In analyzing the contents of the stories, we can see that undesirable events often occur within the city boundary, whereas desirable events tend to happen in the peripheral zone. This peripheral zone can be associated with Buddhist temples and Shinto shrines which were religious foci for people of that time. Several events were described as having occurred just outside the city boundary, suggesting that the city area was not clearly circumscribed.The author concludes that the locational nature of events mentioned in the setsuwa literature can be considered to reflect the spatial structure of the metropolis of the Heian period. Further research should analyze factual records in diaries written by noblemen for comparative studies with literary materials.
2 0 0 0 OA ユーパーライト(Yooperlite)蛍光の起源
- 著者
- 荻原 成騎
- 出版者
- 宝石学会(日本)
- 雑誌
- 宝石学会(日本)講演会要旨 2019年度 宝石学会(日本)講演論文要旨
- 巻号頁・発行日
- pp.16, 2019 (Released:2019-07-03)
Yooperlite とは、2017 年の夏に Superior 湖の湖岸にて発見された“紫外線蛍光を示す石ころ”である。Yooper とは、発見された場所である Michigan 北部の Upper Peninsula、略して U.P. に由来する。Yooperlite の紫外線によるオレンジの蛍光は、まことに麗しく神秘的であり、パワーストーン愛好者を魅了している。岩石学的には、Syenite の円礫で、蛍光の原因は Sodalite である。蛍光する Sodalite について、特に区別して Hackmanite と呼ぶことがある。Greenland や MontSaint-Hilaire、コラ半島などからの産出が知られるが、いずれも母岩は Syenite である。これらの Hackmanite 蛍光の原因として S や Be が指摘されている。岩石学的には、珍しい石ではない。本研究では、薄片観察に基づき、Sodalite の産状を記載し、XRD による結晶学的特徴付け、EPMA および LA/ICP-MS による主成分/微量成分分析により蛍光の起源を明らかにする。Yooperlite は湖岸に転がる石ころの中でも稀な石であり、現在ではほぼ取り尽されている。そのため現地調査は行っていない。Yooperlite は氷河堆積物中の円礫であるため、礫の母岩である Syenite の産状は見ることはできない。顕微鏡観察に基づく Syenite の特徴は、nepheline を欠くことである。Nepheline については、XRD からも検出されなかった。顕微鏡観察から、Sodalite は matrix を充填しており、もともと nepheline があった場所に置換して分布しているように見える。Sodalite が matrix の Nepheline を置換していると考えると、Sodalite の成因は、単純に Nepheline とアルカリの反応3NaAlSiO4 + NaCl → Na4Al3Si3O12Cl(3Nepheline + NaCl →Sodalite)で説明できる。本研究における Sodarite の分析の結果格子定数 a=8.8594(49)組成 Na3.49Al3.15Si3.07O12Cl1.22発表では、Sodalite 中の蛍光に関与している微量元素組成について言及する。研究で用いた Yooperlite は、Mr.Stone 吉田様から提供された。質問などは ogi@eps.s.u-tokyo.ac.jp まで
2 0 0 0 OA 重症患者における体組成評価の有用性とその限界
- 著者
- 堤 理恵 大藤 純 福永 佳容子 筑後 桃子 瀬部 真由 井内 茉莉奈 堤 保夫 西村 匡司 阪上 浩
- 出版者
- 一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会
- 雑誌
- 日本静脈経腸栄養学会雑誌 (ISSN:21890161)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.803-806, 2016 (Released:2016-06-20)
- 参考文献数
- 12
重症患者における栄養管理の重要性は広く認識されつつある。一方で、侵襲下においては有効な栄養指標や予後指標とされるものはなく、栄養投与量や適切な栄養組成についても議論の余地が大きい。また、その栄養投与の効果をどのように評価するか、モニタリングのポイントをどこにするか、これについても十分な見解がないのが現状である。近年多くの施設で身近に使用されつつある体組成計による体組成の評価は重症患者の栄養評価に有用であろうか?あるいはどのように使いこなせばよいのだろうか?本稿では、体組成評価に着目し、重症患者における有用性と課題について概説したい。
2 0 0 0 OA 独裁国家における中下級エリートの「ゲーミング」としての選挙不正
- 著者
- 豊田 紳
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.88-100, 2018 (Released:2021-07-16)
- 参考文献数
- 36
非民主主義体制(=独裁体制)の政治過程は,秘密のベールに覆われている。そのため,その選挙,殊に選挙不正については,不明な部分が多い。本稿の目的は,独裁体制の選挙不正に新たな光を当てることを通じて,その政治過程の理解に貢献することである。具体的には次の2つを主張する。第1に,独裁体制における選挙不正には,独裁体制内の中下級エリートが独裁者に対して,自らの得票率を誇示するための「ゲーミング」として行うものが存在する。第2に,野党が競争選挙に参加し,監視するようになると,ゲーミングとしての選挙不正は起きづらくなる。2000年の民主化以降,様々なアーカイブ資料やデータが利用可能となったかつての独裁国家メキシコを分析し,これらの仮説の妥当性を検証した。
2 0 0 0 OA 核兵器なき世界に向けて グローバル・ゼロ軍縮会議
- 著者
- 遠藤 哲也
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3, pp.160-163, 2009 (Released:2019-06-17)
- 参考文献数
- 4
核兵器廃絶論は,古くから唯一の被爆国である日本,非同盟諸国,北欧,カナダ,豪,ニュージーランド等の非核兵器国から主張されてきたが,近年,米国から,それもかつて米国の核戦略に直接関与した元政府高官から主張されるようになったことは注目に値する。その議論は以前の核廃絶論が,一般的,情緒的であったのに比べ,冷戦終えん,9.11事件後の安全保障環境の変化を踏まえた核戦略論に基づくもので,かつ廃絶に至る具体的な道筋を提案している。それとともに,廃絶への過程に横たわる多くの政治的,技術的困難を指摘している。世界が核廃絶の途に踏み出すには,まずは米国の決断が必要なこと,核なき世界が米国にとっても世界の安全保障にとっても望ましいことを強論している。この軍縮会議はそういった議論の流れの一つである。
2 0 0 0 OA 皇紀二千六百年記念行事と飯田下伊那
- 著者
- 齊藤 俊江
- 出版者
- 飯田市歴史研究所
- 雑誌
- 飯田市歴史研究所年報 (ISSN:13486721)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.118-130, 2019 (Released:2022-03-12)
2 0 0 0 OA 飯田下伊那の少年農兵隊 戦争末期の食糧増産隊
- 著者
- 原 英章
- 出版者
- 飯田市歴史研究所
- 雑誌
- 飯田市歴史研究所年報 (ISSN:13486721)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.131-156, 2019 (Released:2022-03-12)
2 0 0 0 OA 黙示録,ユートピア,遺産 エルンスト・ブロッホにおける「(第三の)ライヒ」論
- 著者
- 吉田 治代
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文学 (ISSN:24331511)
- 巻号頁・発行日
- vol.154, pp.82-102, 2017-03-25 (Released:2018-03-31)
Ernst Blochs Utopie mit ihrem ‚religiös-marxistischen‘ Impetus ist im späten 20. Jahrhundert in Verruf geraten. Entsprechend der berühmten Interpretation von Karl Löwith, dass das Dritte Evangelium von Joachim von Fiore sowohl als die Dritte Internationale wie auch als das nationalsozialistische „Dritte Reich“ erscheine, haben Kritiker wie K. Vondung und N. Bolz Blochs Geist der Utopie mit dem „apokalyptischen Geist“ und somit dem „philosophischen Extremismus“ identifiziert und – genauso wie Nationalismus / Faschismus – mitverantwortlich für die Katastrophen des 20. Jahrhunderts gemacht. Dass es sich hier um eine voreilige Kritik handelte, lässt Siegfried Kracauers Einschätzung des Blochschen Denkens erkennen. Auch er fand zwar in Blochs Büchern Geist der Utopie (1918) und Thomas Münzer (1921) zunächst das Manifest eines „religiösen Kommunismus“ und kritisierte, dass Bloch die politische Utopie der klassenlosen Gesellschaft mit der apokalyptisch-eschatologischen Erwartung verschränkt habe. Gegen Ende der 1920er Jahren hat Kracauer jedoch eine weitaus differenziertere Sicht entwickelt. Er sieht beim linken Philosophen einen konservativen Zug, indem dieser die Dinge nicht nur „entschleiern“, sondern auch „bewahren“ will. Damit trifft Kracauer genau das Motiv des Buches Erbschaft dieser Zeit (1935). „Zum utopischen Ende stürmen“ einerseits und andererseits „in der Welt verweilen“, „alles Gewollte, Gedachte und Geschaffene einsammeln“ – das gehört bei Bloch zusammen, und Kracauer nennt in den späteren Jahren Blochs Utopie „eine bewahrende“. (View PDF for the rest of the abstract.)
2 0 0 0 OA 球状トカマクの実用炉への展望 -トカマクの低アスペクト比化への挑戦- 1.特集にあたって
- 著者
- 小野 靖 西尾 敏 高瀬 雄一 長山 好夫 前川 孝
- 出版者
- 社団法人 プラズマ・核融合学会
- 雑誌
- プラズマ・核融合学会誌 (ISSN:09187928)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.11, pp.919-920, 2004 (Released:2005-07-14)
2 0 0 0 OA シンギュラリティは近い 世界の課題をテクノロジで克服するには
- 著者
- 牧野 司
- 出版者
- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター
- 雑誌
- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)
- 巻号頁・発行日
- pp.0170222a, (Released:2017-06-20)
人工知能、生命工学、製造技術などのテクノロジが、現在の延長線上では考えられないようなスピードで進化を始める時点を「技術的特異点 (テクノロジカル・シンギュラリティ) と呼ぶ。シンギュラリティに到達すると、あらゆる社会生活およびビジネスに大きな変化が生じると考えられている。「人工知能が人類を滅ぼしてしまうのではないか」という懸念がある一方、「幾何級数的に進化するテクノロジにより、世界の抱えている課題はそのほとんどが解決可能である」という明るい未来予測もある。「テクノロジカル・シンギュラリティ」という言葉を初めて提唱した未来学者レイ・カーツワイル氏は後者の考えで、カリフォルニアのシリコンバレーに「シンギュラリティ大学」を創設した。世界中から優秀な頭脳を集めて世界の問題解決に挑むと同時に「エグゼクティブ・プログラム」などを通じてその考えを全世界に広めようとしている。本講演では、講師が本年7月に米国シンギュラリティ大学・エグゼクティブ・プログラムで学んできた内容をベースに未来はどうなるのか、私たちは何をすべきか等について述べていく。
2 0 0 0 OA 外国人留学生に対する就労許可制度の国際比較
- 著者
- 石井 誠
- 出版者
- 学校法人 須賀学園 宇都宮共和大学 シティライフ学部
- 雑誌
- 宇都宮共和大学 シティライフ学論叢 (ISSN:21895805)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.174-183, 2017 (Released:2018-03-30)
2 0 0 0 OA 衝撃圧縮による鉱物の変形
- 著者
- 森 寛志
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉱物科学会
- 雑誌
- 鉱物学雜誌 (ISSN:04541146)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.153-158, 1990-01-31 (Released:2009-08-11)
- 参考文献数
- 13
Deformation textures (i. e. fracturing, plastic deformation, recrystallization, vitrification, phase transforma-tion, and melting) in naturally and artificially shocked mineral crystals have been reported. The main part of this report is devoted to a description of the shock-induced residual effects in olivine and orthopyroxene crystals recovered from shock experiments by transmission electron microscopic observation. Deformation textures in naturally shocked olivine crystals from some meteorites were also described.
2 0 0 0 OA 地面反力からみた野球のティーバッティング技術
- 著者
- 小田 伸午 森谷 敏夫 田口 貞善 松本 珠希 見正 冨美子
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.255-262, 1991-12-01 (Released:2017-09-27)
- 被引用文献数
- 5 2
The purpose of this study was to investigate tee-batting skills in relation to ground reaction forces. Eithteen batters tried seven swings on the force platform recording three-dimensional kinetic data. A video camera (60 fps) was used to measure ball velocity and swing velocity. The following results were obtnined. 1) A statistically significant correlation was observed between the swing velocity and the swing time. 2 Statistically significant correlations were observed between the swing velocity and the anteroposterior forces during backward swing phase, the mean power calculated from the anteroposterior force during forward swing phase. 3) Statistically significant correlations were obtained betwben the swing velocity, the ball velocity and the mediolateral distance of the CG of the body from the starting position during backward swing phase. 4) The swing velocity and the ball velocity significantly correlated with the mediolateral distance of the CG of the body between the starting phase and the impact phase. 5) Coefficient of variations (cv) of the vertical forces during backward swing phase and the mean power calculated from the vertical force significantly correlated with cv of the swing velocity. CV of the vertical power of the CG of the body significantly correlated with cv of the ball velocity. These findings suggest that the batter should move the body toward the opposite side of the ball and the anterior direction just before the starting phase of the forward swing to obtain the high swing velocity. The result also suggests that the batter should control the vertical movement during backward and forward swing to obtain the high reproducibility of batting.
2 0 0 0 OA ミネト・エル・ベイダ出土新資料の考古学的検討 -埋葬遺構の年代考察を中心に-
- 著者
- 長谷川 敦章
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- オリエント (ISSN:00305219)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.1-27, 2007 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 70
This paper studies a tomb found at Minet el-Beida in 1997. Fortunately, it seems that the tomb was not looted, and many grave goods were intact. These were the first materials recovered from Minet el-Beida since Schaeffer stopped the excavations in 1932, six decades before and have significant value for the archaeological study of the Late Bronze Age in the East Mediterranean world. This study aims to consider how long the tomb was in use by studying the structure of the tomb and the finds in it such as Mycenaean and Cypriote pottery.The tomb was built entirely of ashlars. It has one chamber of rectangular shape and is equipped with ashlar steps and a dromos, a short passage connecting the chamber to the outside. This type of tomb is commonly seen at Ras shamra, Minet el-Beida and Ras ibn Hani, and seems to date from the Late Bronze Age II, that is the 14th to 13th centuries B. C.Twenty-eight pieces of Mycenaean pottery and twenty-nine pieces of Cypriote pottery were recovered from the tomb. The Mycenaean pottery includes stirrup jars, alabastra and piriform jars. The chronological analysis in this paper suggests that most of the Mycenaean pottery dates back to the Late Helladic IIIB, several to the Late Helladic IIIA2, and one to the Late Helladic IIIB to IIIC1. The Cypriote pottery consists of white shaved ware and white slip II ware, which are also called milk bowls. The former are dated to the Late Cypriote IB to IIB and the latter to the Late Cypriote IIC1.In conclusion, it seems that the tomb started being used in the Late Helladic IIIA2 and was abandoned in the Late Helladic IIIB, that is, that it was used for about 165 years, between 1350 B. C. and 1185 B. C.
2 0 0 0 OA 戦後の経済を顧みて
- 著者
- 中村 隆次
- 出版者
- 一般社団法人 溶接学会
- 雑誌
- 溶接学会誌 (ISSN:00214787)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.8, pp.613-615, 1996-12-05 (Released:2011-08-05)
2 0 0 0 OA 明治期「媒酌結婚」の制度化過程
- 著者
- 阪井 裕一郎
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.89-105,177, 2009-10-31 (Released:2015-05-20)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 1
The purpose of this paper is to consider the process whereby marriage, arranged by nakoudo (go-betweens), was institutionalized during the Meiji period. The subject of countless articles, this marital pattern has characterized Japanese marriage. However, it was not “Japanese tradition” but “Samurai tradition.” While Western modernization resulted in the individualization and secularization of marriage, Japanese early modernization institutionalized, paradoxically, arranged marriage based on familism. This marital pattern then began to gain wide acceptance as a “legitimate marital pattern” among the general population. Few studies have addressed the institutionalization process of arranged marriage and go-betweens during the course of modernization. However, it is essential to study the process because there was a strong social norm: marriage without a go-between was not “correct marriage” and love marriages had been sanctioned long since the Meiji era. Given that the Civil Code in Meiji did not prescribe the use of go-betweens, we need to focus rather on ideology, because this norm seemed to be widespread, not by laws but through the press, education and morals. By examining the ideological conflict between Individualism and Familism, discourses of “civilization” by intellectuals, nakoudo marriage as an “invention of tradition,” and nakoudo as respectable or desirable, this paper shows that arranged marriage did not always confront the idea of “liberty” or “love” but was institutionalized in parallel with the popularization of love (marriage). Nakoudo marriage was a marital pattern that overcame contradictions between Familism and Individualism. The nakoudo, rather than restraining individual will or love, functioned as a symbol of the social approval oflove.
- 著者
- 増田 智美 長江 信和 根建 金男
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.123-135, 2002-09-30 (Released:2019-04-06)
本研究では、大学生の怒りに対する認知行動療法(CBT)、すなわちISST(inductive social skills training)の効果と同時に、個人差である怒りの表出傾向が介入効果に相違をもたらすかどうかを検討した。被験者は、怒りの特性が高く、かつ怒りの表出傾向の高い者(AO高者)と怒りの抑制傾向の高い者(AI高者)の計42名であった。 AO高者とAI高者それぞれを、 CBT群と統制(Ctrl)群に割り当て、2つのCBT群には、怒りの行動的反応を標的とするCBTを4週間実施した。その結果、 Ctrl群と比較して、CBT群では、介入直後の怒りの特性だけでなく、敵意や不安においても有意な低減がみられ、その効果は3か月後のフォローアップ時でも維持されていた。また、表出傾向別にみると、怒りの表出傾向が高い被験者のほうが低い被験者よりも効果が著しかった。怒りを表出する傾向の高い被験者には、行動的反応を標的としたCBTが有効であることが判明した。 CBTを施す際に、怒りの表出傾向まで考慮することの意義が示唆された。
2 0 0 0 OA 両側後頭葉病変による大脳性色覚障害の1例
- 著者
- 小松本 悟 大庫 秀樹 五十棲 一男 横塚 仁 奈良 昌治
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.236-240, 1997-06-25 (Released:2009-09-16)
- 参考文献数
- 11
症例は73歳男性で, テレビを見ていたとき突然テレビの画面の色が白黒になった.その後も色彩が判断できず, 視野に映るものは白黒の濃淡で識別していた.相貌失認, 地誌的失見当, 着衣失行等は認めず, 視力は保たれていたが, 軽度の右同名半盲を認めた。色覚検査では以下の如くであった.物体の識別, 認知はすべて白と黒の濃淡でなされるため明度の配列は正確であった.色の命名は黒と白は可能で, 赤は茶色, 黄色は白ということが多く, 他の色は白と黒の濃淡でのみ表現した.頭部MRIでは, 両側後頭葉底面に脳回に沿った出血性梗塞を認め大脳性色覚障害の病巣を考える上で示唆に富む症例と思われた.
2 0 0 0 OA 新生時エストロゲン投与による雌性化雄マウスの膣上皮の不可逆的角質化の誘起
- 著者
- 鈴木 賢英
- 出版者
- 順天堂医学会
- 雑誌
- 順天堂医学 (ISSN:00226769)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.414-420, 1976-12-10 (Released:2014-11-21)
- 参考文献数
- 31
ICR系の妊娠マウスに6mgのcyproterone acetate (CA) を妊娠14日から20日まで皮下注射し, 妊娠20日に帝王切開で仔マウスを取り出し, 雄仔マウスは去勢後他の母親に哺乳させた. これら去勢された雌性化雄マウスを出生当日から10日間ゴマ油のみを皮下注射する群 (第1群), 20μgのエストラジオール-17β (ED) を皮下注射する群 (第2群), そして50μgのEDを皮下注射する群 (第3群) に分けた. 各群の動物は60日令で殺し, 通常の方法でH-E染色して検鏡した. 組織学的観察の結果, 全ての雌性化雄マウスに腔形成が認められたが, 尿道と腔の分離は不完全であった. 第1群の動物の腔上皮は萎縮的な重層立方ないし扁平上皮であった. ところがED処理を行なった第2, 3群では腔上皮の増殖肥厚が見られ, 50μgのED処理を行なった第3群では15匹中2匹の腔前部から会陰の全域にわたって腔上皮が角質化していた. この第3群の残りの大部分の動物では, 腔全域にわたって上皮の著しい肥厚が見られ, 角質化は膣中部から会陰にかけての上皮に認められた. CAの母体投与で得られた雌性化雄マウスの腔は大部分が尿生殖洞由来と考えられているので, 本実験で雌性化雄マウスの膣中・後部で上皮に角質化が見られたことは尿生殖洞由来の細胞がエストロゲン非依存の腔上皮の角質化に関与する可能性が強いと推論された.