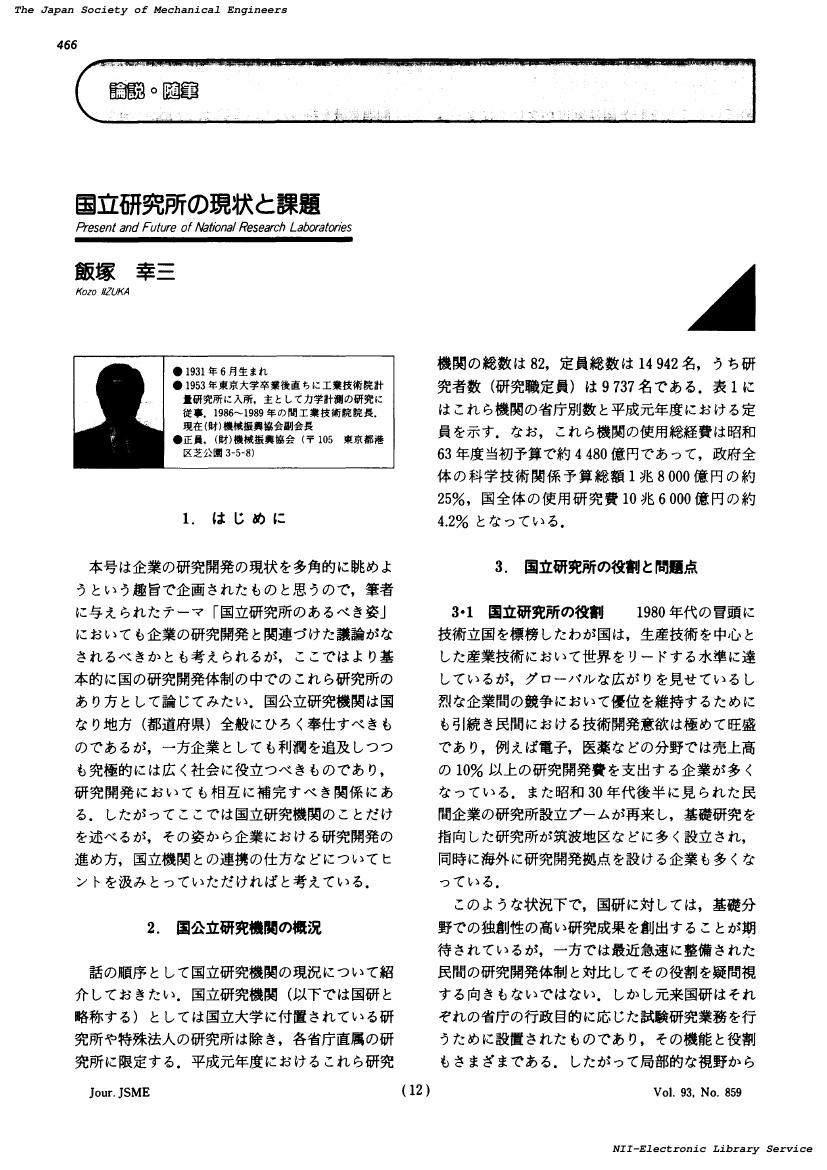2 0 0 0 OA 企業の大学化と大学の企業化 ―オンライン教育をめぐる市場化の嵐―
- 著者
- 吉田 文
- 出版者
- 一般社団法人 CIEC
- 雑誌
- コンピュータ&エデュケーション (ISSN:21862168)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.9-13, 2001-05-31 (Released:2014-12-25)
本稿は、アメリカのオンライン高等教育を市場とみなす近年の動向を、1)私企業と2)既存大学の2つの組織を対象とし、事例にもとづいて検討し、それが高等教育システムに投げ掛けている問題について考察することを目的とする。検討の結果、1)私企業は、オンラインによる営利大学を、設置認可や単位や学位などに関して従来の大学の枠組みの外で設立し、2)既存大学は、大学外部に私企業を設立し、ビジネスとしてオンライン教育を行うという新たな動向が生じていることが明らかになった。そして、それらの新たな動向は、「教育機会の拡大」と「教育で収益をあげる」というまったく異なる考え方がオンライン教育の登場によって両立可能とみなされるようになったことを示しており、それはまた、「大学」とは何かという問題の再考をわれわれに迫っている。
2 0 0 0 OA 重力異常から推定された飛騨山脈下超低密度域の三次元分布
- 著者
- 源内 直美 平松 良浩 河野 芳輝
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 火山 (ISSN:04534360)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.5, pp.411-418, 2002-11-29 (Released:2017-03-20)
- 参考文献数
- 26
A three-dimensional density structure in the shallower crust beneath the Hida Mountains, central Japan, is estimated by using gravity data. We employed seismic velocity structure models both as an initial condition and constraints of gravity structure models. We estimated that an extremely low-density body (density is smaller than 2.1 g/cm3) exists at 4-8 km depth (2 to 6 km below the sea level) beneath Mt. Tateyama (3,015 m) and also along the Hida mountains. Estimated horizontal extent of the body is about 14 km in east to west, about 28 km in north to south directions, respectively, and about 4 km in thickness. The volume of the body is about 1,000 km3. Spatial distribution of the extremely low-density body is well consistent with a low velocity region estimated from studies of seismic tomography.
2 0 0 0 OA イラン暦の諸問題
- 著者
- 井本 英一
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- オリエント (ISSN:00305219)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3-4, pp.69-90,194, 1968 (Released:2010-03-12)
There are three calendars of ancient Iran: the Old Avestan, Young Avestan and Old Persian calendars.Gathic people were aware of the lunar year as well as the solar and settled five important turns of season on the ecliptic while they made them adjust the solar vague year. It is probable that even a Metonic cycle was known to some extent.The young Avestan and the Old Persian calendars are the complex of the solar, lunar and lunisolar calendars.Problems of months of the beginning of the year, the five-day stolen month and the ten-day fravardigan at the end of the year, the Zoroastrian weeks, and the Hamaspathmaedaya feast are illustrated.
2 0 0 0 OA 薪ストーブ燃焼ガスへのFe系触媒の適用に関する基礎的研究
- 著者
- 玉井 康仁
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会大会発表データベース 第124回日本森林学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.785, 2013 (Released:2013-08-20)
はじめに木質バイオマスの家庭系用途として薪ストーブに着目し、熱利用の可能性について調査している。既報1)より、触媒付き薪ストーブを用いても燃焼ガス中COは299~3896ppm、NOxは36~81ppmと比較的高かった。そこで、安価なFe系触媒(群馬県吾妻産FeO(OH))を用いて燃焼ガス中COおよびNOxの低減に関する調査を行った。方法 薪ストーブ内に触媒(粒径1.0mm、85ml、SV値700h-1)を充填した管を挿入し、通常の燃焼状態を維持してCOおよびNOx低減実験を行った。脱硝実験ではNH3水を入れたトレーを燃焼室内に置き、NH3を気化させた。結果 (1)FeO(OH)触媒により2000~10000ppmのCOが500~1000ppm以下に低下した。 (2)気化させたNH3との触媒反応によりNOxも60ppmから10ppm以下に低下した。 今後は触媒の効率の向上を図り、触媒設置位置や圧力損出の把握等、より実用化に向けた検討を行う必要がある。引用文献 (1)占部、玉井他、龍谷大学里山学研究センター、2011年度年次報告書、pp.84-90(2011)
2 0 0 0 OA 国立研究所の現状と課題
- 著者
- 飯塚 幸三
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会誌 (ISSN:24242675)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.859, pp.466-469, 1990-06-05 (Released:2017-06-21)
2 0 0 0 OA コルクからのカビ臭原因物質(ハロアニソール)除去技術
- 著者
- 但馬 良一
- 出版者
- Brewing Society of Japan
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.3, pp.177-184, 2012 (Released:2017-10-24)
- 参考文献数
- 49
ブショネ(bouchonne)と呼ばれるコルクからのカビ臭は,ワインの品質を著しく損なうオフフレーバとして国際的な問題となっている。コルクを使用するワインの20から30本に1本という頻度は,消費者,レストラン等の経済的損失ばかりではなく,嗜好品として大切な「ワインを飲む喜び」を奪うことになる。製造者にとっては,ぶどう栽培や醸造といった自分たちの責任範囲外に品質を損なう要因がありその頻度が高いことは容認できないであろう。しかし,この臭いの原因物質の閾地が極めて低く検査が困難である上,天然素材であるコルクの汚染にばらつきがあり,抜き取り検査だけでは汚染がないことを証明できないため,決定的な解決方法がなかった。筆者らはこの問題に対し早くから研究を進め,高圧水蒸気処理により,カビ臭原因物質を含まないコルクの生産に成功された。
2 0 0 0 OA 注入された微小異物の行方
- 著者
- 倉本 敬二
- 出版者
- 日本静脈経腸栄養学会
- 雑誌
- 静脈経腸栄養 (ISSN:13444980)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.6, pp.1183-1190, 2009 (Released:2009-12-21)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 3
輸液フィルターの必要の是非が論じられてから久しい。不溶性異物による生体への有害反応が証明されているにもかかわらず、本邦臨床においてはコストとの関連を理由に輸液フィルターを使用しないで輸液療法 (栄養・薬物療法) が行われている場合も未だ見受けられる。本稿では不溶性微粒子による注射剤汚染の現実を通して日本薬局方の矛盾点並びに調製された輸液の不溶性微粒子汚染とそれらが静脈内投与された場合の体内分布についての検討結果を踏まえて輸液療法時のリスクマネジメントとしての輸液フィルターの必要性について述べる。
- 著者
- 清家 庸佑 野口 卓也
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.5, pp.548-556, 2020-10-15 (Released:2020-10-15)
- 参考文献数
- 32
要旨:本研究の目的は,ポジティブ作業に根ざした実践(以下,POBP)が高齢者サロン利用者のWell-Being(以下,幸福)に与える効果を予備的に検討することであった.方法は,高齢者サロンの利用者21名を対象に,介入期間は5週間,介入デザインは前後比較試験でPOBPの効果を検討した.効果指標は,改訂版PGCモラールスケール,ポジティブ作業評価などを使用した.解析は,介入効果に影響を与える変量効果を考慮した結果が推定できるよう一般化線形混合モデルで検討した.その結果,POBPはPGCモラールスケール(合計得点)で介入効果を認めた.POBPは,高齢者サロン利用者の幸福の促進に貢献できる可能性を示唆した.
- 著者
- 進藤 浩子 深澤 光晴 飯嶋 哲也 高野 伸一 門倉 信 高橋 英 横田 雄大 廣瀬 純穂 佐藤 公 榎本 信幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.12, pp.2389-2398, 2016 (Released:2016-12-20)
- 参考文献数
- 22
【目的】ベンゾジアゼピンを用いた従来のERCP鎮静ではしばしば脱抑制による体動を認める.安定した鎮静を得られる方法としてドロペリドール,フェンタニル,ケタミンを用いた静脈麻酔による鎮静法の安全性と有効性を評価した.【方法】対象はERCPの鎮静にミダゾラムとペンタゾシンを用いた従来法群42例とドロペリドール,フェンタニル,ケタミン(DFK法)群17例.評価項目は鎮静関連偶発症および鎮静効果とした.【結果】SpO2 90%未満を認めた症例は従来法で4例(10%),DFK法で1例(6%)と有意差は認めなかった.体動により処置継続に支障があった症例は従来法で8例(19%),DFK法で0例とDFK法で良好な鎮静効果を得られる傾向を認めた(p=0.09).鎮静困難ハイリスク症例である飲酒習慣を有する21例では,鎮静不良となる症例はDFK群で有意に少なかった(従来法 50% vs DFK法 0%,p=0.02).【結論】DFK法は従来法と比較して同等な安全性で施行可能であった.飲酒習慣を有する症例ではDKF法の方が有効な鎮静が得られた.
2 0 0 0 OA 無機物質の反応をどう教えるか
- 著者
- 岩田 久道
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.9, pp.436-439, 2017-09-20 (Released:2018-03-01)
- 参考文献数
- 5
無機物質の自発的な変化である酸化還元反応や酸塩基反応は,水を中心として安定物質に落ち着く。熱化学的な安定性のもと,縦軸を酸化数,横軸をpHでおいた物質間の変化を反応式で表す系統図を描くと同時に,外部からエネルギーを必要とする工業的な製法の反応を重ねると自然界・工業界の物質循環が理解できる。
2 0 0 0 OA 文法の一部としての語彙層の是非(<特集>借用語音韻論の諸相)
- 著者
- 立石 浩一
- 出版者
- 日本音声学会
- 雑誌
- 音声研究 (ISSN:13428675)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.34-43, 2002-04-30 (Released:2017-08-31)
Lexical strata as a part of grammar have been assumed to account for various phonotactic (un)markedness in certain groups of lexical items. In particular, the reranking hypothesis of Ito and Mester (1995a,b) and the indexed FAITH hypothesis of Fukazawa (1998) had triggered disputes and discussions among scholars on the fundamental organization of phonological grammar. This article will examine approaches to the sublexicon, and show problems with the aforementioned studies. In particular, the emergence of the unmarked patterns in the marked vocabulary classes presents a serious problem.
- 著者
- 興津 舜也 金光 香保子 浅野 聡
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.66, pp.937-942, 2021-06-20 (Released:2021-06-20)
- 参考文献数
- 14
The report introduces the present condition and problem of descriptions about the treatment of disaster hazard areas in basic guideline for urban renaissance and guideline for city planning. The targets are 4 prefectures in Tokai region. As the result of analysis, it has become clear that treatments of disaster hazard areas were different from each municipality because of directionality about the exclusion of guideline for city planning and kinds of disasters. In the future, not excluded areas need to be considered excluding and if impossible, disaster prevention measures need to be set in location normalization plan.
2 0 0 0 OA GMP 教育訓練の教材としてみた医薬品回収事例
- 著者
- 稲津 邦平
- 出版者
- 一般社団法人日本PDA製薬学会
- 雑誌
- 日本PDA学術誌 GMPとバリデーション (ISSN:13444891)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.52-60, 2007 (Released:2008-06-06)
- 参考文献数
- 12
2 0 0 0 OA DETECTION OF CARRIERS OF TYPHOID BACILLI BY SEWERAGE-TRACING SURVEILLANCE IN MATSUYAMA CITY
- 著者
- 篠原 信之 田中 博 斉藤 健 出口 順子 近藤 玲子 曽田 研二 鈴木 賢
- 出版者
- National Institute of Infectious Diseases, Japanese Journal of Infectious Diseases Editorial Committee
- 雑誌
- Japanese Journal of Medical Science and Biology (ISSN:00215112)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.6, pp.385-392, 1981 (Released:2010-03-19)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 4 5
Since periodical survey of the sewage entering the sewage-farm in Matsuyama City revealed a high incidence of Salmonella typhi of different phage types, attempts were made to trace the upstream reservoir. It was found that S. typhi was drained into a particular manhole at a distance of about 5 km from the sewage-farm. Two members of two families were found to be carriers. Further investigation detected other 25 carriers. The 27 carriers were all pupils of the same primary school. Ten of them showed mild symptoms such as fever, abdominal pain and diarrhea; the remaining 17 were asymptomatic. The phage type of 24 isolates was of Vi degraded approaching phage type A [degraded Vi (A) ] and that of the other three was of type 53. The results coincided with those of the isolates from sewage.
2 0 0 0 OA 御遺告の成立過程について
- 著者
- 武内 孝善
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.607-611, 1995-03-25 (Released:2010-03-09)
2 0 0 0 OA タイ国におけるホテイアオイの堆肥化
- 著者
- 鈴木 正昭 テップンポン マリーワン モラクン ポンレック 五十嵐 孝典
- 出版者
- Japanese Society for Tropical Agriculture
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.55-62, 1982-06-01 (Released:2010-03-19)
- 参考文献数
- 7
タイ国の河川に繁茂するホテイアオイ (Eichhornia cyassipes, Solms) の実用的な堆肥化方法を検討した.すなわち, ホテイアオイ, 野草, 稲わら, 水牛糞などを主な材料とした各種の堆肥を製造し, その性状を経時的に調べて, 品質や熟度等を論じた.得られた結果は以下のように要約される.1.ホテイアオイだけを材料として堆肥を製造すると, 品温は42℃に達しただけであったが, 水牛糞や稲わらを混じて堆肥を製造すると容易に50℃以上の高温を得ることができた.2.ホテイアオイは窒素, リン酸, カリ等の養分に富むため, これを他の資材と混用することにより堆肥の品質が向上した.3.稲わらを堆肥化する場合にホテイアオイを混用すると, 水牛糞や石灰窒素を用いるのと同等の効果を発揮した.4.ホテイアオイは堆肥資材として良好であり, タイ国の農民に勧めうる.また, その適切な製造法について述べた.5. (付録) タイの中央平原と東北部で集めたホテイアオイを比較すると, 前者は後者よりも植物養分の含量が高い傾向を示した.茎葉部と根部について養分含量を比較すると, 茎葉部では窒素, リン酸, カリ, カルシウム, マグネシウム, 銅などが根部よりも高かったが, マンガンや亜鉛は根部の方が高かった.
2 0 0 0 OA 神会の無念について
- 著者
- 瀧瀬 尚純
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.648-650, 2004-03-20 (Released:2010-03-09)
2 0 0 0 OA 分譲マンションの専有部分改修工事における不確定要素の実態
- 著者
- 宇治 康直 秋山 哲一
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.66, pp.1021-1026, 2021-06-20 (Released:2021-06-20)
- 参考文献数
- 5
This research investigates elements of uncertainty (EOU) remaining after demolition work starts, through observation of the design and construction processes of an exclusively-owned dwelling unit of a condominium with a design–bid–build method. Design revision was assumed for designers to deal with EOU as of the construction contract. There was a case where EOU found after the demolition of interior brought design revision and additional construction, which influenced the construction period and cost. It is thinkable that issues caused by EOU found during the construction work increase. A contract needs to be thought for such risks among stakeholders.
2 0 0 0 OA ウェルビーイング研究に基づく家が関連する主観的幸福とその決定要因
- 著者
- 有馬 雄祐
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会環境系論文集 (ISSN:13480685)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.785, pp.680-691, 2021-07-30 (Released:2021-07-30)
- 参考文献数
- 48
Studies about well-being (WB) have been used to build an interdisciplinary research area centered on positive psychology and economics of happiness. WB research is characterized by active use of subjective data about one’s life, called subjective wellbeing (SWB), as indicators of the quality of an individual’s life or their society. SWB has various domains, including ones related to cognitive and emotional well-being, and each has different determinants. For example, life satisfaction, which is the cognitive aspect of SWB, is strongly correlated with income, while emotional well-being has a relatively strong correlation with health and social relationships. There are various theories about SWB’s composition, and the OECD has defined three basic domains of SWB: life evaluation (life satisfaction), emotion (affect, mood), and eudaimonia. Conventional research for assessing residential environments has used “housing satisfaction” as a subjective indicator of housing quality, which belongs to the “cognitive evaluation” domain. However, based on the findings of WB research, it can be inferred that there are diverse subjective domains related to housing quality. Therefore, in the current study, we attempted to construct home-related subjective well-being (HOME-SWB) based on the OECD’s SWB definition: “home satisfaction,” “positive emotions at home,” “negative emotions at home,” and “eudaimonia derived from home.” “Home satisfaction” is the cognitive aspect of HOME-SWB, which is similar to the conventional subjective indicator, housing satisfaction. “Positive emotions at home” includes the frequency of positive emotional experiences at home, such as feeling happy, cheerful, or joyful, while “negative emotions at home” includes the frequency of negative emotional experiences, such as feeling depressed, stressed out, or lonely at home. “Eudaimonia derived from home” indicate to what extent residents obtain experiences of eudaimonic well-being from their homes, such as self-esteem and the sense that life is worth living. The purpose of this study is to investigate the current status of HOME-SWB among 4,000 residents in the Tokyo area and the determinants of each domain of HOME-SWB using ordinary least squares (OLS) regression analysis. Our assessment shows that HOME-SWB is closely related to demographics; for example, the relationship between home satisfaction and age is a U-shaped curve, which is similar to the well-known relationship between life satisfaction and age. Therefore, we conducted OLS regression by controlling demographic variables, including gender, age, and household income, and the results show that each domain of HOME-SWB has unique relationships with them. For example, the size of a house strongly affects home satisfaction but not positive emotions or eudaimonic aspects. Having a nice view from windows or a high level of thermal insulation has a relatively strong effect on emotional HOME-SWB. Proactive ways of living in a home, such as being picky about furniture and the interior of one’s home or frequently redecorating rooms, enhance the eudaimonic aspects, such as self-esteem and optimism. When we use conventional subjective information to measure housing satisfaction as an indicator of housing quality, it is noted that the importance of the housing elements that strongly affect cognitive well-being, such as the size of a house, are overestimated, while the importance of elements that have an impact on the emotional and eudaimonic aspects of HOME-SWB are underestimated. There are various subjective domains related to housing quality; therefore, we can conclude that we must measure various domains of HOME-SWB when assessing home-related well-being based on residents’ subjective information.
2 0 0 0 OA 中性フッ化物の応用がインプラント周囲炎を増悪させる可能性
- 著者
- 吉成 正雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本口腔インプラント学会
- 雑誌
- 日本口腔インプラント学会誌 (ISSN:09146695)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.182-190, 2017-09-30 (Released:2017-11-05)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1
中性フッ化物の応用がチタンインプラントの耐食性に与える影響およびインプラント周囲炎を増悪させる可能性について検討した結果,以下が明らかとなった.①チタンイオンの溶出を引き起こす因子はフッ化物以外にも様々あり,インプラント周囲炎=フッ化物と一義的に限定するのには無理がある.②酸性(pH低)のフッ化物のみがチタンを腐食する.③歯肉縁下および縁上において,持続的なpH低下を支持するエビデンスはない.④急性炎症により生ずるpHの低下はほとんどない.⑤歯肉縁下において溶存酸素濃度が低下してもpHは低下せず腐食の危険性は少ない.⑥チタンへのフッ化物の応用は,抗菌性の付与など,積極的一面も存在する.以上より,中性フッ素化物の応用がチタンを腐食させる可能性が少ないことから,中性フッ化物の応用がインプラント周囲炎を増悪させる可能性はきわめて少ない.