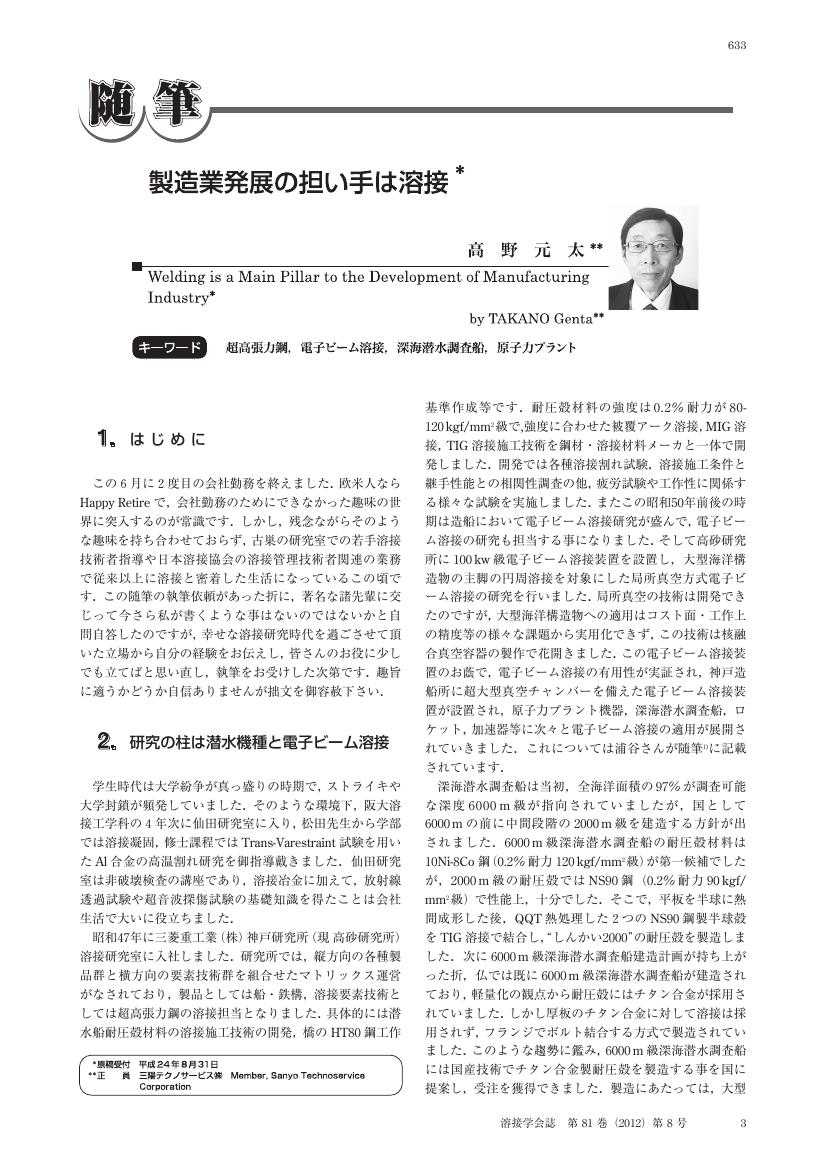3 0 0 0 定印上に宝塔を載せる弥勒如来像の研究
定印上に宝塔を載せる弥勒如来の図像は、善無畏訳の弥勒儀軌等には像容の説明が十分でない。このためか定印弥勒像には、彫刻、絵画、工芸の諸作例にわたっていくつかの異なるかたちが存する。しかし、これら定印弥勒像を密教史と対応させながら図像学的に系統だてて分析した研究は無かった。本研究では、先ずこのタイプの弥勒像が頭髪、着衣、持物等の表現にそれぞれ異なる特徴をそなえていることに着目した。そして、このタイプの弥勒を図像の上から第一類、第二類、第三類に分類した。その結果、第一類から第三類の定印弥勒像制作の背景にはつぎのような事実があるという知見も得た。◎第一類 儀軌の記述に忠実な如来形で古いかたち(例、仁和寺本『弥勒菩薩畫像集』一図等)。螺髪上に宝冠を頂き、衲衣を着し、宝塔を捧ぐ。この如来形は善無畏訳『胎蔵図像』の毘瀘遮那を意識した台密(寺門系)伝来の図像。弥勒即大日の密教思想が反映。◎第二類 宋図様の影響をうけた宝冠毘瀘遮那を意識した如来形と菩薩形の中間的像容(例、『撹禅鈔』一図、快慶作建久三年銘像等)。宝髻上に宝冠を頂き、衲衣を着すという宋仏画の形式をとる。この第二類も弥勒(菩薩)即大日(毘瀘遮那如来)という密教思想を反映。これら第一類、第二類は請来図像をもととしたもので、盲目的にそのかたちを踏襲するという共通した特徴がある。したがって、構図にも変化が乏しい。◎第三類 儀軌にこだわらない菩薩形で新しいかたち。宝髻上に宝冠を頂き、条帛・裙を着け、五輪塔を捧ぐ(和歌山・慈尊院本、高山寺鏡弥勒像等)。この菩薩形は、非善無畏系現図曼荼羅の胎大日を意識。この図像は兜率即密厳=弥勒即大日という東密の深秘釈に基づく。第三類は12世紀末頃わが国で成立し、以後定印弥勒像の主流をなす。第三類は定印弥勒像の日本的展開ともいえ、阿闇梨の意楽が反映され構図等に改変が多い。
3 0 0 0 OA 愛知県紳士録
- 著者
- 小沢有隣 編
- 出版者
- 内外新聞社雑誌縦覧所
- 巻号頁・発行日
- 1914
3 0 0 0 OA 大学生の退学と留年 その発生メカニズムと抑制可能性
- 著者
- 立石 慎治 小方 直幸
- 出版者
- 日本高等教育学会
- 雑誌
- 高等教育研究 (ISSN:24342343)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.123-143, 2016-05-30 (Released:2019-05-13)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 6
本稿の目的は,高等教育の大衆化がもたらす大学生の多様化のうち,特に退学と留年に着目し,その実態と発生のメカニズムを,学部を単位として実証的に検討し,抑制の可能性も視野に入れて考察することであり,その結果明らかになったのは以下の3点である.その結果,以下の3点を明らかにした.第1に,退学と留年を統合的に考察し,4類型に基づく学生の動態の規定要因を析出した.第2に,退学率と留年率の分岐点を探索し,学部がおかれた様々な文脈を考慮しつつ,退学と留年問題に取り組む必要性を,具体的に提示した.第3に,退学と留年に対する教育・学習支援の介入効果を分析する過程で,大学教育の効果研究に用いられる横断的調査の可能性と限界を批判的に検討した.
3 0 0 0 OA 企業における精神障害者への合理的配慮の実際と課題 ~企業人事の立場から~
- 著者
- 境 浩史
- 出版者
- 一般社団法人 日本産業精神保健学会
- 雑誌
- 産業精神保健 (ISSN:13402862)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.79-83, 2023-06-20 (Released:2023-06-20)
民間企業における雇用障害者数は年々増加している.その中でも,精神障害者は他の障害区分よりも増加傾向にあるが,雇用後の定着率は他の障害区分よりも低い傾向にある.一因と考えられるのが精神障害に対する受入れ企業の知識・認識,合理的配慮提供に対する障害者および受入れ企業の理解である.合理的配慮は,当事者から提供者である企業への申し入れを基本に相互の合意形成により提供されるが,実際の運用となると当事者自身や企業の認識・理解が十分でないことが原因で合意形成が成り立たないこともある.その中でも,精神障害者への合理的配慮は個別性が非常に高く,企業としても事例の蓄積も少ないことから過去の事例がそのまま適用されるとは限らないケースが多くある.企業人事担当者の立場から,精神障害者への合理的配慮の実際と課題を中心に考察する.
- 著者
- 金子 雄司 草島 邦夫 宮岡 慎一 中川 貴史
- 出版者
- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会
- 雑誌
- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.75-77, 2023-06-10 (Released:2023-06-24)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 2
医学部低学年に在籍する筆頭著者が,医療機関で多職種業務を実践し,成員となっていく過程を「正統的周辺参加理論」に基づき考察した.学習者と実践共同体の間に互恵的関係が構築される過程で,学習者の学びが促進され,実践共同体の成員として認められた.さらに,実践共同体にも建設的な変化が観察された.本活動は医学生にとって有意義な学習機会であり,転用性の高い活動となりうる.
3 0 0 0 OA 物質における対称性を破って電気と磁気をつなぐ(現代物理のキーワード)
- 著者
- 木村 剛
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.3, pp.144-145, 2016-03-05 (Released:2018-07-20)
- 被引用文献数
- 2
3 0 0 0 OA 富士火山東斜面で2900年前に発生した山体崩壊
- 著者
- 宮地 直道 富樫 茂子 千葉 達朗
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 火山 (ISSN:04534360)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.5, pp.237-248, 2004-10-29 (Released:2017-03-20)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 5
A large-scale collapse occurred at the eastern slope of Fuji volcano about 2900 years ago, based on calibrated 14C age of a wood sample collected in the resulting debris avalanche deposit. The collapsed slide deposit, called “Gotemba debris avalanche deposit” (Goda), is distributed on the eastern foot of the volcano covering an area of more than 53 km2 The source amphitheater is not preserved because it became covered by younger tephra erupted from the summit crater. This avalanche deposit is overlain by the “Gotemba, mudflow deposits” (Gomf) emplaced repeatedly after the avalanche. Some now units of the Goda and Gomf entered pre-existing rivers and were finally emplaced as fluvial deposits. The Goda is composed of debris-avalanche blocks, showing jigsaw cracks, along with smaller blocks ranging from several tens of centimeters up to l m in diameter. The debris-avalanche matrix is a mixture of smaller nieces of blocks and ash-sized materials due to mainly shearing and fragmentation of large blocks. Igneous rocks include fresh and altered gray basaltic lava, weathered tephra including red scoria and white clay. Petrographical and geochemical data indicate that most blocks were derived from the Older Fuji volcano. The volumes of the Goda and Gomf are about l.05km^3 and 0.71km^3 respectively, based on presently available geological and borehole data. Since the blocks of Goda are composed mostly of the products of the Older Fuji volcano and the older stage lavas of Younger Fuji volcano do not extend to the eastern foot of Fuji volcano, a bulge of Older Fuji volcano must have existed in the eastern flank of Fuji volcano preventing the older stage lavas to now to the east. This bulge collapsed in the form of three blocks from the foot of the mountain. The abundance of hydrothermally altered deposits in the Goda and the absence of fresh volcanic products within the Goda suggest its origin as a rupture inside the altered deposits possibly triggered by a large earthquake or phreatic eruption.
3 0 0 0 OA 明治憲政における宮中と府中の関係
- 著者
- 石倉 幸雄 Yukio Ishikura
- 雑誌
- 国際経営・文化研究 = Cross-cultural business and cultural studies (ISSN:13431412)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.17-36, 2016-12-01
After the victory over the feudal powers (Tokugawa Bakuhan Taisei), Meiji Government started its office on January 3rd 1868 declaring the Restoration to the old autocratic Tenno(Monarchical) regime as its political cause, with total abolition of every feudal way and custom. As a matter of course came the reinstatement of the Emperor (Tenno) and the royal family in conformity with its old status.Then the government promulgated the Meiji Constitution on February 11th 1889, and adopted a constitutional form of government under the same political regime. On this changing context the royal family who were entitled to succession to the Emperor were politically marginalized and left behind social interest. Hirobumi Itoh who had worked for Japan three times as the prime minister was much concerned with this peculiar social condition, and made an effort to lift the royal family up to the previous social status considering that the royal family was essential for the balanced and secured development of the Japanese Tenno regime. This dissertation tries to attempt to put light on the process in which the royal family were secured from the political oblivion.
3 0 0 0 アメダスデータを用いた機械学習による定期船の運航予測
- 著者
- 園田 潤 中道 一紗 小岩 晃
- 雑誌
- 2023年度 人工知能学会全国大会(第37回)
- 巻号頁・発行日
- 2023-04-06
3 0 0 0 OA アルフレッド・ジャリにおける知性の原理
- 著者
- 佐原 怜
- 出版者
- 東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻
- 雑誌
- 言語情報科学 (ISSN:13478931)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.221-236, 2012-03-01
L'objectif de cet article est de mettre en lumière le principe de l'intelligence chez Alfred Jarry en s'appuyant sur les discours de psychologues de l'époque et sur ceux de philosophes épistémologiques. Dès les premiers écrits de Jarry, le concept d'atomisme s'impose sous la figure du sable, qui symbolise chez lui les mots, la mémoire et les idées. La psychologie empiriste, qui se propageait largement à l'époque en France, se base sur le concept d'atomisme, et l'associationnisme en fait partie. Selon cette théorie, tous les éléments mentaux s'associent de façon immanente, sans travail sélectif de l'intelligence. L'association des atomes, selon Jarry, tient du hasard. Dans son roman postérieur, la figure d'atome réapparaît, cette fois-ci soumise aux lois physiques. Le héros du roman sort de l'espace-temps afin d'en reconstruire l'unité. Cette action peut s'expliquer au regard de la pensée de Kant, selon laquelle le libre arbitre est rendu possible lorsque le moi transcende le temps et le monde phénoménal. Ainsi c'est dans cette même dimension que l'intelligence selon Jarry peut sélectionner les phénomènes accidentels pour les intégrer à sa création.
- 著者
- 南 庄一郎 中澤 紀子 永吉 美香
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.221-227, 2023-04-15 (Released:2023-04-15)
医療観察法病棟において,統合失調症の対象者に関わる機会を得た.本介入では対象者の「他者との会話がうまくなりたい」という希望に着目し,この実現に向けて作業療法介入プロセスモデルと社会交流評価を用いて関わった結果,対象者の対人交流技能が向上し,コミュニケーションの困難さが軽減した.危機介入モデルが先行する医療観察法医療において,作業療法介入プロセスモデルに基づいた司法精神科作業療法の実践は,対象者の保護要因を見出すことを可能にし,再犯の防止に間接的に作用すると考えられ,社会内再統合モデルに基づく医療観察法医療を推進する可能性があると考えられた.
- 著者
- 佐野 菜緒子 早川 貴行 吉岡 和哉
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.398-406, 2023-06-15 (Released:2023-06-15)
- 参考文献数
- 24
COVID-19感染により重度の呼吸不全に陥り,人工呼吸器離脱後に不安や抑うつ状態を認めたA氏を担当した.作業療法ではA氏にとって価値ある作業に焦点を当て,さらに作業参加に影響する要因をMOHOの視点を参考に分析し介入した.経過中,A氏は再び人工呼吸器管理となったが,床上でのメールや読書など,本人にとって価値ある作業を提供していく中で笑顔が見られ,不安や抑うつの軽減を認めた.重症COVID-19患者に対して,急性期から作業に焦点を当てた介入をすることは作業療法士の重要な役割として示唆された.
3 0 0 0 OA 南極昭和基地で採集した流星塵
- 著者
- 西堀 栄三郎 石崎 正子 Eizaburo NISHIBORI Masako ISHIZAKI
- 出版者
- 国立極地研究所
- 雑誌
- 南極資料 (ISSN:00857289)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.407-410, 1959-07
3 0 0 0 OA 千葉大学で発見されたディズニー・アニメーションのオリジナル画
- 著者
- 小林 裕幸
- 出版者
- 社団法人 日本写真学会
- 雑誌
- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.5, pp.299-307, 2006-10-25 (Released:2011-02-17)
3 0 0 0 OA スジエビの在・不在が動物プランクトン群集と水質に与える影響
- 著者
- 中武 禎典 高村 典子 佐治 あずみ 宇野 晃一
- 出版者
- 応用生態工学会
- 雑誌
- 応用生態工学 (ISSN:13443755)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.11-20, 2011 (Released:2011-10-01)
- 参考文献数
- 48
千葉県成田市北須賀の印旛沼漁業協同組合の敷地に同じように造成された 2 つの植生再生実験池では,一方は沈水植物が再生・繁茂し透明度が高い水界に,他方はアオコが発生し透明度が低い水界になった.後者では前者の 10 倍のスジエビが捕獲された.そこで,実験池内に 8 基の隔離水界を設置し,スジエビの在・不在を操作し,動物プランクトン群集と水質に与える影響を調べた.水質については,実験開始直後からスジエビ在の隔離水界で濁度,懸濁態物質 (SS),全窒素 (TN),全リン (TP),クロロフィル a (Chl. a),および溶存態有機炭素 (DOC) の値が有意に高くなった.ミジンコ類の総密度は,スジエビ在の隔離水界で有意に減少した.逆に,ワムシ類の密度は,有意に増加した.ミジンコ類のうち,大型および遊泳性のミジンコ類 (Daphnia 属,Diaphanosoma 属,Scapholeberis 属)の密度は,スジエビ在の隔離水界で有意に減少したが,小型の底生性ミジンコ類 (Alona 属,Chydorus 属) の密度については,有意差はなかった.ただし,スジエビ在区の栄養塩が実験開始直後に増加したのに比べ,スジエビ不在区でのミジンコ類の密度の増加は,遅めにあらわれた.そのため,スジエビの存在は,まず生物攪拌と栄養塩回帰を促し,その後大型甲殻類動物プランクトンを捕食することによるカスケード効果が加わり水質を悪化させ,浅い湖沼や池のレジームシフトを誘導することが明らかになった.
3 0 0 0 OA 製造業発展の担い手は溶接
- 著者
- 高野 元太
- 出版者
- 一般社団法人 溶接学会
- 雑誌
- 溶接学会誌 (ISSN:00214787)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.8, pp.633-635, 2012 (Released:2015-02-05)
- 参考文献数
- 1
3 0 0 0 OA 人口流動と開発動向からみた広域中心都市・広島の変容
- 著者
- 川瀬 正樹
- 出版者
- The Japan Association of Economic Geography
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.4, pp.291-302, 2018-12-30 (Released:2019-12-30)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
本報告では,1985年以降の広島,特に近年の広島の動向について,人口移動,通勤・通学,商圏調査等の人口流動データの分析に加え,交通網の整備,近年の各施設の開発状況について報告し,広域中心都市・広島の変容について考察した. 1985年以降,広島市の人口は,特に丘陵地を切り崩して住宅開発が行われてきた郊外の区で増加し,周辺県からの転入と大都市圏への転出が大幅に減少した.また,商業面では中心市街地の中心性が2004年以降著しく低下した.代わって郊外のショッピングセンターに客足を奪われ,もはや中心-郊外の対立から郊外同士の競合に変化してきている.広島駅前の再開発エリアでも,オフィスビルではなくタワーマンションが増えており,現段階で業務機能が集積したと言えない. あらゆる観点からみて郊外化が進んできた一方で,広域中心都市としての広島の地位は低下しつつある.支店の統廃合が進んだことなどにより東京一極集中が進む一方で,近年発展を遂げる福岡よりも東京・大阪寄りに位置する広島の「支店経済都市」としての性格は弱まっていると言わざるを得ない.一方で,広島では最近,ホテル建設が増えており,広島の都市としての性格が変容しつつある.今後,広島が広域中心都市としての地位を維持し続けられるかどうかの岐路に立たされていると言える.
3 0 0 0 OA 極域温暖化問題の概観
- 著者
- 山内 恭 Takashi Yamanouchi
- 雑誌
- 南極資料 = Antarctic Record (ISSN:2432079X)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.1-18, 2016-03
今,北極・南極は温暖化しているのだろうか? この質問に答えられるように,解説を試みた.近年の地球温暖化の中で,強い温暖化の現れている地域は北極域と南極半島域である.北極域の温暖化は全球平均の2倍以上の温暖化で,北極海の夏の海氷も著しく減少している.何がこの北極温暖化増幅をもたらしているのか,その原因を探った.一方,南極では,南極半島や西南極で温暖化が激しいのに対し,東南極では温暖化が顕著にはみえない.なぜ,温暖化が抑えられているのであろうか.オゾンホールが関係しているという説を述べる.さらに,北極温暖化の影響で,中緯度に寒冷化が起こる現象がみつけられ,様々な議論を呼んでいる.今後の研究が期待される.
3 0 0 0 OA 浦賀の発展における浦賀ドックの意味
- 著者
- 市村 真実
- 出版者
- 筑波大学歴史・人類学系歴史地理学研究室
- 雑誌
- 歴史地理学調査報告 (ISSN:09152504)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.113-131, 2006-03
3 0 0 0 OA 母趾種子骨障害に対し運動療法が有効であった一症例
- 著者
- 田中 夏樹 岡西 尚人 稲葉 将史 山本 紘之 川本 鮎美 早川 智広 加藤 哲弘 山本 昌樹
- 出版者
- 東海北陸理学療法学術大会
- 雑誌
- 東海北陸理学療法学術大会誌 第24回東海北陸理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.O032, 2008 (Released:2008-12-09)
【はじめに】 母趾種子骨(以下、種子骨)障害に対しては、保存療法が第一選択となるが、そのほとんどが足底挿板による免荷の有効性を報告するものである。今回、足底挿板が処方できない状況であった症例の理学療法を経験した。Dynamic Alignmentを変化させるべく運動療法を行うことで種子骨周囲の運動時痛が消失した。本症例におけるDynamic Alignmentの特徴と理学所見、荷重時における種子骨の疼痛との関係について考察を踏まえ報告する。 【症例紹介】 症例は野球、空手を行っている中学1年の男性である。2年前から両側種子骨周囲に運動時痛を訴え、本年5月に歩行時痛が憎悪したため当院を受診し、理学療法開始となった。 【初診時理学所見】 両側とも種子骨を中心に圧痛を認め、歩行時痛(右>左)を訴えた。歩行時footprintにて両側ともに凹足傾向であった。また、Thomas testが陽性/陽性(右/左)、SLRが50°/50°、大腿直筋短縮テストが10横指/5横指(殿踵部間距離)と股関節周囲筋に伸張性の低下を認めた。足関節背屈可動域は25°/25°であり、両足をそろえたしゃがみ込みでは後方に倒れる状態であった。歩容はmid stance以降、支持脚方向への骨盤回旋が過度に認められた。 【治療内容および経過】 腸腰筋、大腿直筋、hamstringsを中心にstretchingおよびself stretchingの指導を行い、距骨を押し込むためのTapingを指導した。また、3週後からはショパール関節のmobilizationを行った。5週後にはThomas testが両側とも陰性化、SLRが80°/80°、大腿直筋短縮テストが0横指/0横指と改善を認め、歩行時、ランニング時の疼痛が消失し、全力疾走時の疼痛程度が右2/10、左1/10と改善した。 【考察】 hamstringsのtightnessによる易骨盤後傾、重心の後方化に拮抗するため、股関節屈筋群の活動量が増加し、腸腰筋、大腿直筋のtightnessが出現したと推察された。そのため、股関節伸展可動域の低下が生じ、歩行ではmid stance以降に骨盤の支持脚方向への過回旋による代償動作による足角の増加に加え、凹足傾向と足関節背屈可動域の低下によりmid stance~toe offにかけて荷重が足部内側へ急激に移動することで母趾球への荷重が過剰となり歩行時痛が出現していると推察された。そのため、股関節周囲筋のtightnessを除去するとともにショパール関節のmobilization、足関節背屈可動域増加を目的としたtapingを行い、toe off時における母趾球への過剰な荷重を回避することで種子骨への荷重による機械的ストレスの減少を図ることが可能となり、運動時痛が軽減、消失したと考えた。有痛性足部障害といえども、全身の機能障害が関与しているケースもあると考えられ、足底挿板療法以外にも症状改善に足部以外の部位に対するアプローチの有効性が示唆されたものと考える。