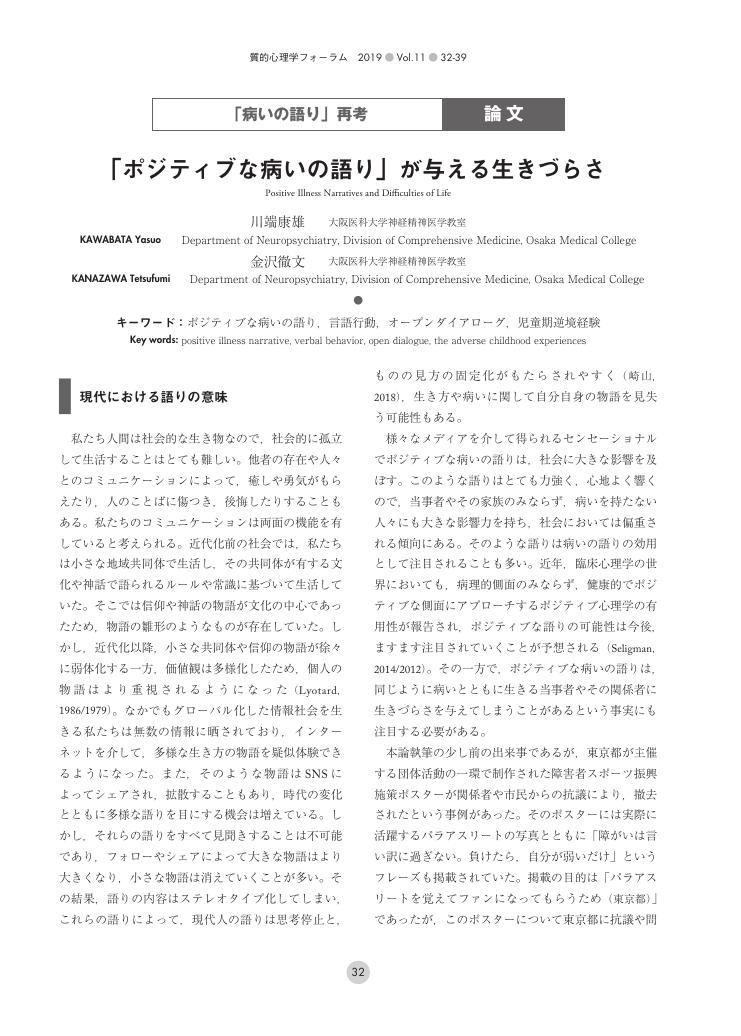3 0 0 0 OA 城館遺構と土地利用の関係からみる城館跡地の市街化の実態 東京都の中世城館を対象として
- 著者
- 安武 覚 饗庭 伸
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.848-854, 2022-10-25 (Released:2022-10-25)
- 参考文献数
- 7
城館跡地の市街化の経緯と現状を踏まえた検討の基礎的な研究として、城館跡地の「境界」と「内部構造」の残存状況と土地利用に注目し、東京都の中世城館を対象とした63事例における城館跡地の市街化の実態を明らかにするものである。「境界」では、城館跡地の外周とその周囲の市街地との関係の分析として、城館跡地の土地利用と立地から境界の構成要素を調査し、航空写真を用いて年代ごとの構成要素の変化とその残存状況を明らかにした。「内部構造」では、堀・曲輪・通路といった城館の構造と内部の土地利用の関係の分析として、本研究では片倉城跡と高幡城跡の2つの事例を取り上げ、都市計画と土地所有の視点から土地利用の動向を明らかにした。
3 0 0 0 OA IV.Parkinson病の認知症治療
- 著者
- 柏原 健一
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.8, pp.1565-1571, 2015-08-10 (Released:2016-08-10)
- 参考文献数
- 10
Parkinson病(Parkinson's disease:PD)に伴う認知症の治療には,抗認知症薬のいずれも有効との報告がある.ドネペジル,リバスチグミンのエビデンスレベルが高い.幻覚・妄想は抗PD薬の減量,中止や抗認知症薬の併用により,改善が期待できる.改善しない場合は非定型抗精神病薬を試用するが,運動障害の悪化や過鎮静に注意する.運動や知的刺激による認知機能障害への効果はエビデンスに乏しいが,障害改善と進行予防が期待できる.
3 0 0 0 IR <論考> ソーシャルワークの視点からみた介護保険制度の変容 (情報社会学部特集号)
- 著者
- 森 詩恵
- 雑誌
- 大阪経大論集 (ISSN:04747909)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.5, pp.67-82, 2014-01-15
3 0 0 0 OA 書評:伊勢田哲治『動物からの倫理学入門』
- 著者
- 江口 聡
- 出版者
- 関西倫理学会
- 雑誌
- 倫理学研究 (ISSN:03877485)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.169, 2009 (Released:2018-03-15)
3 0 0 0 OA 附子の毒力・効力に関する諸問題
3 0 0 0 OA 絶滅危惧水生食虫植物ムジナモの保全に及ぼすセンチュウの影響と対策
- 著者
- 金子 康子
- 出版者
- 埼玉大学総合研究機構
- 雑誌
- 総合研究機構研究プロジェクト研究成果報告書
- 巻号頁・発行日
- vol.第6号(平成19年度), pp.134-135, 2008
3 若手研究及び基礎研究
3 0 0 0 建造環境における微生物叢の特徴と人体に及ぼす影響の理解に向けて
- 著者
- 伊藤 光平
- 出版者
- 一般社団法人 室内環境学会
- 雑誌
- 室内環境 (ISSN:18820395)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.29-42, 2023 (Released:2023-04-01)
- 参考文献数
- 96
- 被引用文献数
- 2
ヒトは用途に応じて複数の建造環境を使い分けながら1日の大半を建造環境内で過ごしている。近年,「建造環境の微生物叢 (MoBE)」の網羅的な解明が進んでいる。建造環境では,屋外環境などの一部やヒト自体が微生物の供給源となり多様な微生物が持ち込まれ,独自の微生物生態系が構築されている。その動態は,季節などの自然要因のみならず,換気,建材,設計手法などの人的要因によっても変化する。本論文では初めに,ヒト,環境,微生物における相互作用や関係によって生じるMoBEの構成要因を説明する。次に,建造環境における薬剤耐性菌の発生プロセスと感染症拡大につながるリスク要因を評価する。さらに,都市化に伴いヒトが多様な微生物に曝露する機会が減少することによって生じる免疫発達への影響など,MoBEが与えるヒトの健康への影響についても議論する。以上の通りMoBEの重要性が明らかになりつつある一方で, 複雑性の高いMoBEから一貫した特徴を検出するためには解決すべき課題が多くある。MoBEの複雑性が高いのは,微生物の発生源が無数に存在し,同時にヒトの活動,建築設計や屋外の土地利用など多様なパラメータが存在するからである。さらに,MoBEを解明するための生物学的実験・解析手法にはいくつかの技術的な制限がある。MoBEを人為的に管理することで健康,快適性,生産性等を向上させるためには,さらなる研究が必要である。
3 0 0 0 OA 無償の画像解析ソフトウェアを用いた運動解析の実用性
- 著者
- 山中 悠紀 水野 智仁 石川 成美 笹倉 祐太 山本 亜衣 石井 禎基
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.4, pp.571-574, 2016 (Released:2016-08-31)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
〔目的〕無償のソフトウェア(フリーウェア)による動作解析の実用性を検討すること.〔対象と方法〕大学生11名(男性5名,女性6名)にデジタルビデオカメラで矢状面から撮影した立ち上がり動画を画像上のマーキング箇所の座標値が取得できるフリーウェアで解析させ,作業時間と自覚的疲労度を評価するとともに,算出した股,膝,足関節角度と2次元動画解析ソフトウェアで求めた角度との差を分析した.〔結果〕115枚の画像解析に要した平均時間は約20分,自覚的疲労度はVASで30.0 mm程度であった.2種類の解析方法で算出した角度の最大値の差は股関節屈曲で0.12±0.25°,膝関節屈曲で0.14±0.30°,足関節背屈で1.02±0.38°であった.〔結語〕フリーウェアによる動作解析法は実用的である.
3 0 0 0 IR 三島由紀夫『愛の渇き』論 : 他者としての情念
- 著者
- 柴田 勝二
- 出版者
- 相愛大学
- 雑誌
- 相愛大学研究論集 = The annual report of researches of Soai University (ISSN:09103538)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.134-116, 1996-03
3 0 0 0 OA ボノボとチンパンジーのロコモーションと生態
- 著者
- 坂巻 哲也
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.181-186, 2014 (Released:2016-04-16)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 2 2
ヒトにもっとも近縁な現生類人猿は,チンパンジーとボノボである.ヒトの直立二足歩行の進化を考えるとき,近縁な現生種の生態を知ることは,ヒトの二足歩行がはじまった起源と,その後に洗練される過程に働いた選択圧を考えるために重要である.この解説では,チンパンジーに比べ研究が遅れているボノボにおもな焦点を当て,両者の生態とロコモーションについて概観する.両者の社会と食物はよく似ている.二足姿勢はボノボの方がきれいに見えるが,これは幼形保有の副産物だろう.ボノボの湿潤林や水辺の利用,より乾燥した地域のボノボの生態は,今後の研究課題である.野生ボノボで観察される二足姿勢とその文脈についての素描も行った.
3 0 0 0 OA 「件」管見
- 著者
- 堀部 功夫
- 出版者
- 同志社大学国文学会
- 雑誌
- 同志社国文学 = Doshisha Kokubungaku (ISSN:03898717)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.216-224, 1994-11
3 0 0 0 OA 実験中の事故を防ぐための安全衛生対策の検討
- 著者
- 引地 力男 松田 忠大
- 出版者
- Japanese Society for Engineering Education
- 雑誌
- 工学教育 (ISSN:13412167)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.6, pp.6_93-6_99, 2007 (Released:2007-12-19)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 2 2
The purpose of this report is to exclude risk factors based on the instance of Hiyari Hatto (near-miss accidents) experienced by school personnel and students and to make the environment in which students can participate safely in the class and extracurricular activities. By means of the risk assessment and KYT (training for predicting dangers, K : Kiken, Y : Yochi, T : Training) , it has been considered how the college should control the students′ experiments. As a result, the students have been able to work on the experiments without affecting the school facilities and the students′ working site, and the number of injuries has decreased.
3 0 0 0 OA 一般化ぷよぷよのより強い計算困難性
- 著者
- 江藤 宏 木谷 裕紀 小野 廣隆
- 雑誌
- ゲームプログラミングワークショップ2021論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, pp.130-137, 2021-11-06
本研究では一般化ぷよぷよの計算複雑度について考える.対象とするのは盤面サイズ,色数に関して一般化した,オフライン型パズルとしてのぷよぷよである.本研究ではこの一般化ぷよぷよにおける 2つの問題を取り上げる.1 つは全消し判定であり,もう一つは連鎖数最大化である.前者に関してはぷよ 2色(おじゃまぷよあり)の設定であっても NP 完全であることが,後者に関してはぷよ 4 色(おじゃまぷよあり)の設定でも NP 困難であることが示されている.特に後者に関しては,詳細な証明は公開されていないがぷよ 3 色(おじゃまぷよあり)の設定で,あるいはぷよ 5 色(おじゃまぷよなし)でも NP 困難であることが指摘されている.本研究ではこれらの結果をいくつかの側面から強化する.我々の結果は以下のとおりである: (1) 連鎖数最大化はぷよ 3 色(おじゃまぷよなし)でも NP 困難,(2) P≠NP の仮定の下で, ぷよ 4 色(おじゃまぷよあり)の連鎖数最大化に対しては近似比の精度保証が入力の多項式以下となるような多項式時間近似アルゴリズムは存在しない, (3) 全消し判定はぷよ 4 色(おじゃまぷよなし)でも NP 完全である.
3 0 0 0 IR 大岡昇平「野火」を〈読む〉--反復と恩寵
- 著者
- 宮坂 覺 Satoru Miyasaka フェリス女学院大学 文学部(教員)
- 出版者
- フェリス女学院大学
- 雑誌
- フェリス女学院大学文学部紀要 (ISSN:09165959)
- 巻号頁・発行日
- no.46, pp.451-477, 2011-03
第12回東北アジアキリスト者文学会議(2009年8月28日、韓国、龍仁市、Ross記念館)においての口頭発表の内容に新たに追記したものフェリス女学院創立140周年記念号
3 0 0 0 OA 特集論文 「ポジティブな病いの語り」が与える生きづらさ
- 著者
- 川端 康雄 金沢 徹文
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学フォーラム (ISSN:18842348)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.32-39, 2019 (Released:2020-04-28)
3 0 0 0 OA 「Slime Hand」における主観的な皮膚伸長距離の同定
3 0 0 0 OA 香りによる快・不快感が心的作業に及ぼす影響
- 著者
- 中野 良樹 畑山 俊輝 菊池 晶夫
- 出版者
- JAPAN SOCIETY FOR RESEARCH ON EMOTIONS
- 雑誌
- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.2, pp.44-54, 1997-03-30 (Released:2009-04-07)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1
This study examined effects of hedonic tones produced by odor stimuli on human mental performance. Thirty subjects were equally assigned to one of three olfactory stimulus groups: a control group with blank air, a Rose and a Ylang-ylang scented air group. From a preliminary study, we selected the latter as an unpleasant odor stimulus. The subjects of a different group received a different olfactory stimulus into a their nostril while they performed an audio-visual dual task. In this task the subjects were required to discriminate the difference in duration of a tone stimulus and to press a right hand key when they found the tone shorter. Engaging in this performance they had to attend to a red light rested in front of them and to press a left hand key when the light was turned off. For this visual performance the subjects of the Ylangylang group improved the detection of the signals in the first odor block. For the auditory performance, however, they made more errors than those of other groups. These results suggested that whiffs of an unpleasant odor would enhance detectability of the visual signal, but inhibit cognitive processes associated with discrimination in the dual task performance.
3 0 0 0 OA クライオ電子顕微鏡単粒子解析の実際~試料調製から画像解析まで~
- 著者
- 橋本 翼 横山 武司 田中 良和
- 出版者
- 日本結晶学会
- 雑誌
- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.89-96, 2021-05-31 (Released:2021-06-05)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
Recent marked development called “Resolution revolution” has made cryo-electron microscopy (Cryo-EM) the third method of structure determination at atomic resolution next to X-ray crystallography and NMR. In this review, actual situation surrounding Cryo-EM including an outline about the workflow from sample preparation to image analysis and differences between Cryo-EM analysis and X-ray crystallography is introduced. We hope that this review is useful for researchers particularly who will start Cryo-EM analysis.
3 0 0 0 IR 過剰な<言葉>の交換--芥川龍之介「歯車」試論
- 著者
- 小澤 純
- 出版者
- 早稲田大学国文学会
- 雑誌
- 国文学研究 (ISSN:03898636)
- 巻号頁・発行日
- vol.147, pp.34-47, 2005-10
- 著者
- 小川 輝繁
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会関東支部ブロック合同講演会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, pp.189-190, 2005-08-25
- 被引用文献数
- 1
日本における煙火事故の年間件数は、製造中が0-3件、消費中が約20件であり、消費中の事故発生件数が製造中に比べてはるかに多い。しかし、製造中に極めて重大な事故が発生している。1992年に茨城県の製造工場で発生した事故では従業員3人が死亡、周辺住民を含む58人が負傷した。また、2003年には鹿児島県の工場で爆発事故が発生し、従業員10人が死亡、周辺住民を含む4名が負傷した。日本の煙火産業の保安について考察した。日本の煙火業者のほとんどは中小企業である。そのため、煙火産業の保安について次のような問題点がある。(1)煙火技術における科学的基礎に基づいた取り組みの不足煙火は業者が代々受け継いできた経験に基づいた技術で製造されている。(2)煙火は手作りで製造されている。煙火職人は爆発危険性物質を手で取り扱っている。(3)ほとんどの煙火業者は経済基盤が弱く、海外から安い製品や半製品が輸入されることが経営を圧迫している。煙火業者の保安のために推進すべき課題は、科学的基礎に基づいた煙火の技術開発と業者の経済基盤の強化である。