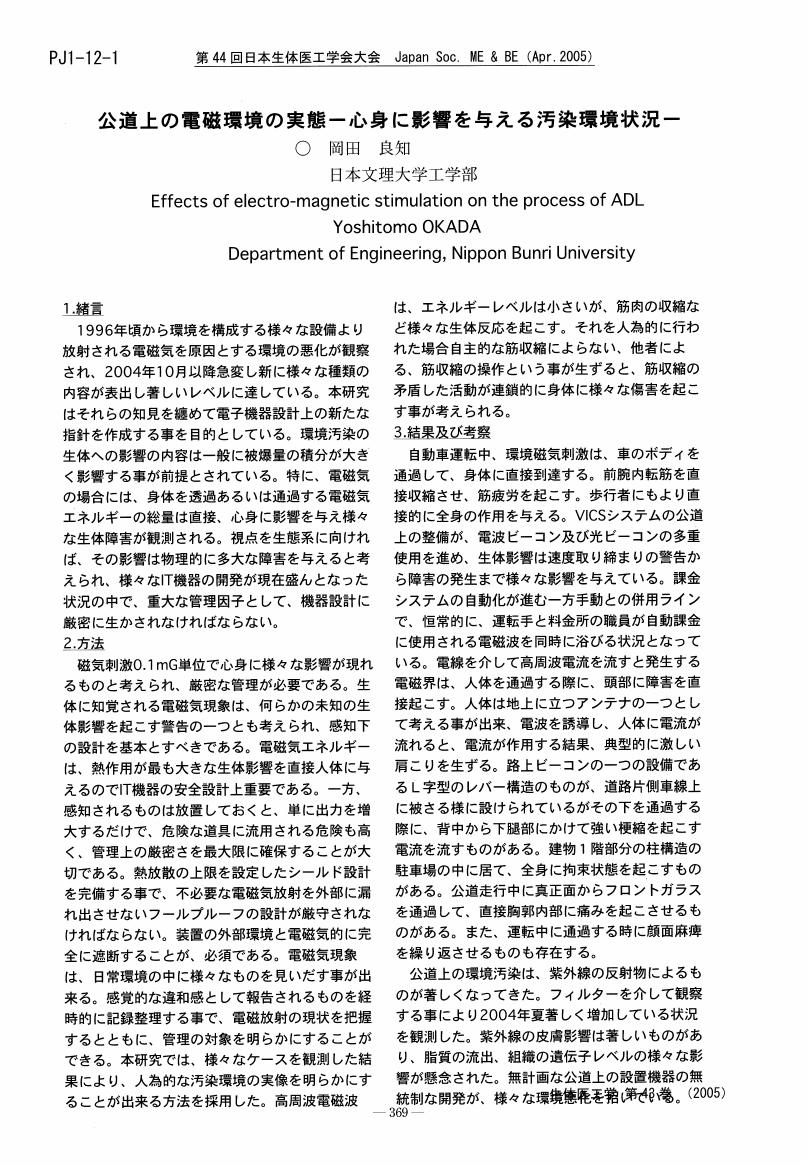105 0 0 0 OA ミュージカルの変異と生存戦略――『マリー・アントワネット』の興行史をめぐって――
- 著者
- 田中 里奈
- 出版者
- 日本演劇学会
- 雑誌
- 演劇学論集 日本演劇学会紀要 (ISSN:13482815)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, pp.1-26, 2020-12-15 (Released:2020-12-26)
In 2006, the musical Marie Antoinette was launched from Tokyo. Before the return to Japan in 2018, this work about the French Revolution was performed in Germany, South Korea, and Hungary.Marie Antoinette was originally intended for the export but did not fully follow the trend of megamusical that globally succeeded with the franchise system since the 1980s. Rather, this musical continued to be dedicated to the specific context of popular theater in each performing venue, as seen in the growing trade of musicals between Continental Europe and East Asia in the last few decades. For meeting actual demands and limitations, all the elements including the text and music were constantly overwritten with the approval of the copyright holders.In the chained variations on the principle of flexible adaptation, the authority of the original product, which is connected to the license business of musicals with enormous initial costs, is diminishing. Instead, companies and institutions that have more or less their own financial resources, e.g. from the public sector or the holding company, played a significant role in the survival of the genre within the various and acceleratedly changing sociocultural environments on the performance.
105 0 0 0 OA シンポジウム
- 出版者
- 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会
- 雑誌
- 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 (ISSN:21869545)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.Supplement1, pp.S69-S77, 2015 (Released:2015-06-02)
104 0 0 0 OA オーストリアにおける地域鉄道の財政支援構造
- 著者
- 宇都宮 浄人
- 出版者
- 日本交通学会
- 雑誌
- 交通学研究 (ISSN:03873137)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, pp.133-140, 2019 (Released:2020-04-27)
- 参考文献数
- 17
日本では採算の合わない地域鉄道の運営に関して公的関与が議論されているが、財政事情等から模索が続いている。一方、地域鉄道の再生を進めるオーストリアをみると、法律上で、連邦と州の役割、インフラと運行サービスの両面に対する財政支援が明確に制度化されていることがわかる。また、オーストリア中部3州の予算書からは、近年道路建設・維持から公共交通関連に予算配分をシフトさせていることも確認できる。オーストリアの連邦と州の関係は、日本の国と県の関係と似通ったところもあり、日本の地域鉄道の再生と今後の運営に、オーストリアの制度や財政支援の方法は参考になるものと思われる。
104 0 0 0 OA たばこの煙のエアロゾル性状
104 0 0 0 OA 論文海賊サイトSci-Hubを巡る動向と日本における利用実態
- 著者
- 大谷 周平 坂東 慶太
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.10, pp.513-519, 2018-10-01 (Released:2018-10-01)
- 被引用文献数
- 5
Sci-Hubとは,6,450万件以上もの学術論文のフルテキスト(全文)を誰もが無料でダウンロードできる論文海賊サイトである。Sci-Hubからダウンロードできる論文には,学術雑誌に掲載された有料論文の約85%が含まれており,Sci-Hubは学術出版社の著作権を侵害する違法サイトである。大学図書館の契約する電子ジャーナル,OAジャーナル,機関リポジトリ,プレプリントサーバーなど法的に問題ない論文サイトが在る中で,世界中から1日に35万件以上の論文がSci-Hubを通じてダウンロードされている。本稿では先ずSci-Hubの概要・仕組み・世界的な動向について述べる。次いで2017年にSci-Hubからダウンロードされた論文のログデータを分析し,国内におけるSci-Hub利用実態の調査結果を報告する。栗山による2016年調査と比較すると,Sci-Hubの利用数やSci-Hubの利用が確認された都市数は増加していた。また,Sci-Hubでダウンロードされているのは有料論文だけではなくOA論文が約20%を占めていること,クッキーの情報から約80%のユーザーは1回のみSci-Hubを利用している状況も明らかになった。
104 0 0 0 OA 北浦の23本の流入河川における魚類の分布パターンと生息環境特性
- 著者
- 大森 健策 諸澤 崇裕 加納 光樹
- 出版者
- アクオス研究所
- 雑誌
- 水生動物 (ISSN:24348643)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023, pp.AA2023-1, 2023-01-05 (Released:2023-01-05)
東日本の海跡湖である北浦(最大深度7 m、面積36 km2)に流入する23本の河川において、2016年4月中旬から5月下旬と9月中旬から10月中旬に魚類の分布パターンと環境変量を調査した。調査期間中に出現した魚類は、計11科33種であった。各河川の種組成データに基づいてクラスター分析を行ったところ、23本の河川は流路延長が長く種数が多いグループと流路延長が短く種数が少ないグループに分けられた。各グループを表徴する複数の絶滅危惧種が存在した。各魚種の出現・非出現と各環境変量との関係を一般化線形混合モデル解析で検討したところ、20種の生息環境特性が把握された。河口からの堰堤の数は水産有用種のワカサギやヌマチチブを含む10種の出現と負の関係がみられ、これらの種では堰堤による遡上阻害が生じている可能性が示唆された。川幅、流速、水際を覆う植生の被度も、多くの魚種の出現の有無と関連付けられた。とくに植生被度は複数の絶滅危惧種の出現と正の相関が認められた。今後、北浦流域において水産有用種や絶滅危惧種を含む在来魚のさまざまな生息環境を適切に保全していくうえで、堰堤への魚道の設置、水辺植生の管理、護岸構造の改良などを含む流入河川再生計画の検討が急務であると考えられた。
104 0 0 0 OA 猫科動物の瞳孔の形態について
- 著者
- 那波 昭義
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳動物学雑誌: The Journal of the Mammalogical Society of Japan (ISSN:05460670)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.3, pp.72-73, 1967-01-25 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 4
- 著者
- 岩見 恭子 小林 さやか 柴田 康行 山崎 剛史 尾崎 清明
- 出版者
- 日本鳥学会
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.63-69, 2015 (Released:2015-04-28)
- 参考文献数
- 19
福島第一原子力発電所の事故によって放出された放射性物質による鳥類の巣の汚染状況を把握するため,2011年に繁殖したツバメの巣を日本全国から採集し,巣材に含まれる放射性セシウム(Cs-134およびCs137)を測定した.全国21都道府県から集められた197巣のうち182巣について測定した結果,1都12県の巣から福島第一原子力発電所由来の放射性セシウムが検出された.福島県内のすべての巣から放射性セシウムが検出され,Cs-134とCs-137の合計の濃度が最も高いものでは90,000 Bq/kgで低いものでは33 Bq/kgであった.巣の放射性セシウム濃度は土壌中の放射性セシウム濃度が高い地域ほど高かったが,地域内で巣のセシウム濃度にはばらつきがみられた.
- 著者
- Hani Al-Abbad Sanaa Madi
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.5, pp.323-331, 2020 (Released:2020-05-01)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 3
[Purpose] To explore the views of clients referred for physical therapy in a tertiary care setting regarding the integration of physical therapy service at primary health care centers. [Participants and Methods] A self-administered questionnaire was distributed to eligible Saudi clients. The questionnaire consisted of three sections including demographic information section; closed-ended section with 6 Likert scale items on the perceptions of potential advantages of physical therapy service at the primary health care level; and open-ended section on potential disadvantages and barriers of implementing physical therapy service. The surveys were described and analyzed quantitatively and qualitatively. [Results] A total of 412 participants were included in the analysis (56.8% females). Participants’ mean age was 35.7 ± 21.9 years; 67.2% were Riyadh city residents; and 38.1% had musculoskeletal conditions. Seventy-five percent responded in support for the availability of physical therapy service at the primary health care level. Demographic characteristics had no effect on the level of support to the service availability. [Conclusion] The results of this survey demonstrated high positive support for the integration of physical therapy service at primary health care centers in Saudi Arabia. However, challenges and barriers identified by the study results require attention when physical therapy services are to be established.
104 0 0 0 OA パルスレーザー推進による静止遷移軌道への単段打ち上げシステムの可能性
- 著者
- 葛山 浩 小紫 公也 荒川 義博
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会論文集 (ISSN:13446460)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.625, pp.63-70, 2006 (Released:2006-03-20)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1 2
An air-breathing pulse laser powered launcher has been proposed as an alternative to conventional chemical launch systems. The trajectory from the ground to a geosynchronous transfer orbit by pulse laser propulsion is calculated by modeling the thrust during pulsejet, ramjet and rocket flight modes, and the launch cost is estimated. The results show that the pulse laser powered launcher can transfer 0.085kg payload per 1MW beam power to a geosynchronous orbit, and the cost becomes quarter of existing systems if one can divide a single launch into 22,500 multiple launches.
104 0 0 0 OA ポスターセッション 電磁界の生体影響
- 出版者
- 公益社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.Supplement1, pp.369-378, 2005-04-25 (Released:2011-09-05)
104 0 0 0 OA EPUB概説:電子出版物とWeb標準
- 著者
- 高瀬 拓史
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.9, pp.618-628, 2014-12-01 (Released:2014-12-01)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 3
EPUBは電子出版物の交換および配信フォーマットの標準である。今日,主要な電子書籍ストアのほとんどは,何らかの形でEPUBを利用している。EPUBの普及を支えた要因には,(1)Web標準をベースにしていること,(2)オープンでロイヤルティーフリーであること,(3)多様な読書環境に対応していること,があげられる。本稿ではEPUBの特徴,データ構造,表現力を紹介し,課題と近年の動向についても触れる。EPUBは電子出版にかかわるさまざまな要件を満たしており,今後も重要なフォーマットであり続ける可能性が高い。
103 0 0 0 OA 変体仮名のこれまでとこれから 情報交換のための標準化
- 著者
- 高田 智和 矢田 勉 斎藤 達哉
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.6, pp.438-446, 2015-09-01 (Released:2015-09-01)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
変体仮名は平仮名の異体字であるが,現代の日常生活ではほとんど用いられていない。しかし,1947年以前には命名に使われ,戸籍など行政実務において変体仮名の文字コード標準化のニーズがある。一方,日本語文字・表記史や日本史学の学術用途においても,変体仮名をコンピューターで扱うニーズがある。そこで,活版印刷やデジタルフォントから集字し,学術情報交換用変体仮名セットを選定した。このセットには,変体仮名の機能的使い分けを表現するため,同字母異体も収録した。行政用途の変体仮名と合わせ,2015年10月にISO/IEC 10646規格への追加提案を予定している。
103 0 0 0 OA Amyotrophic Lateral Sclerosis after Receiving the Human Papilloma Virus Vaccine: A Case Report of a 15-year-old Girl
- 著者
- Ryota Hikiami Hodaka Yamakado Shinsui Tatsumi Takashi Ayaki Yuichiro Hashi Hirofumi Yamashita Nobukatsu Sawamoto Teruyuki Tsuji Makoto Urushitani Ryosuke Takahashi
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.13, pp.1917-1919, 2018-07-01 (Released:2018-07-01)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 7
We herein report a 15-year-old girl who developed rapid progressive muscle weakness soon after the third injection of a bivalent human papilloma virus (HPV) vaccine. Although immunotherapies were performed for possible vaccine-related disorders, she died of respiratory failure 14 months after the onset of the disease. A genetic analysis identified a heterozygous p.P525L mutation of the fused in sarcoma (FUS) gene, and a histopathological analysis was also consistent with FUS-associated amyotrophic lateral sclerosis (ALS) without any evidence of neuroinflammation. We concluded the diagnosis to be FUS-ALS, although we cannot completely rule out the possibility that the vaccination worked as a trigger.
- 著者
- 細野 天智 鵜沢 美穂子 大前 宗之 升本 宙 出川 洋介
- 出版者
- 日本菌学会
- 雑誌
- 日本菌学会会報 (ISSN:00290289)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.77-91, 2021-11-01 (Released:2021-12-28)
- 参考文献数
- 78
Octospora系統(チャワンタケ目,ピロネマキン科)は多数のコケ植物生および少数の非コケ植物生の種からなる系統群である.本系統に含まれる種は主にヨーロッパや北アメリカから報告されているが,日本からの正式な報告は皆無であった.筆者らは盤菌類の調査によって得られた標本の中から,本系統に含まれる以下の4属4種を形態的に同定し,これらの同定結果は核リボソームRNA遺伝子の大サブユニット領域を用いた分子系統解析によっても支持された.Leucoscypha leucotricha (新称 ワタゲシロチャワンタケ)は非コケ植物生で,カバノキ属の樹下より採集された.他の3種はいずれもコケ植物生で,Neottiella albocincta (新称 アラゲタチゴケチャワンタケ)はナミガタタチゴケを,Octospora ithacaensis (新称 ゼニゴケツブチャワンタケ)はゼニゴケを,Octosporopsis erinacea (新称 ケゼニゴケニセチャワンタケ)はケゼニゴケをそれぞれ宿主としていた.いずれも東アジア新産で,O. erinaceaは基準産地のボルネオ島に続く二例目の報告となる.
103 0 0 0 OA 食品照射の海外動向
- 著者
- 久米 民和 等々力 節子
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.7, pp.469-478, 2019-07-15 (Released:2019-07-15)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
食品照射の海外動向について,2017年の実施状況をまとめた。総処理量は中国の550,000トンが最も多く,次いでベトナムの110,000トンであり,世界の食品照射は急速に拡大している。検疫を目的とした新鮮果実・野菜の照射処理では,米国がメキシコなどから31,000トン輸入している。アジア・オセアニア諸国では米国への輸出だけでなく,オーストラリアやベトナムなど地域内での照射農産物の相互の輸出入を展開している。
103 0 0 0 OA 児童の読み困難を支援する電子書籍端末ソフトTouch & Readの開発と導入方法の検討
- 著者
- 高橋 麻衣子 巌淵 守 河野 俊寛 中邑 賢龍
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.3, pp.521-533, 2011 (Released:2012-03-09)
- 参考文献数
- 35
There are some children with reading difficulties in the regular class. They seem to have some problems in their perceptual or cognitive skills involved with reading process. In this study, we developed the multi-media learning support system “Touch & Read” for assisting their reading process. The system can zoom up the text, highlight the line in it, and read out it to present the information auditorily. Introducing this system to the regular class, we investigated the way of the learning support for the children with reading difficulties. Ahead of the introduction, we conducted the test to survey the children's decoding skills and visuoperceptual functions and identified the causes of reading difficulties. We provided the Touch & Read to children for their learning in the regular class, and observed how the children with reading difficulties used the system. As a result, it was suggested that children could use the system to compensate their perceptual or cognitive skills and achieve more efficient learning outcomes.
103 0 0 0 OA インフルエンザ流行による超過死亡の範囲の推定 年間死亡率と季節指数を用いた最小超過死亡の推定モデルの応用
- 著者
- 高橋 美保子
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.8, pp.554-562, 2006 (Released:2014-07-08)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1
目的 わが国におけるインフルエンザ流行による超過死亡を明らかにするための一法として,超過死亡の範囲を推定し,記述すること。方法 1987~2003年の人口動態統計から不慮の事故(ICD-9:E800-E949,ICD-10:V01-X59)を除く総死亡の月別死亡数を得て,年間死亡率と季節指数を用いたモデルを適用し,インフルエンザの流行がない場合の死亡数の期待値と95%範囲(基準範囲)を求めた。実際の死亡数(観察値)と期待値との差から超過死亡の点推定値を求め,観察値と基準範囲限界値(上限値,下限値)との差から超過死亡の範囲を求めた。なお,インフルエンザ流行月は,感染症発生動向調査の結果を考慮しつつ,「インフルエンザ死亡率0.9(人/10万人年)以上の月」とした。結果 超過死亡の点推定値が最も大きかったのは1999年,次いで95年,そして,93年,97年,2000年,および2003年の流行期であった。1999年の超過死亡は約 4 万 9 千人と点推定されたが,その年の超過死亡は約 3 万 7 千人~約 6 万人の範囲とも推定された。同様に,95年の超過死亡は約 3 万 8 千人と点推定されたが,約 2 万 7 千人~約 4 万 8 千人の範囲とも推定された。また,93年,97年,2000年,および2003年の超過死亡の点推定値は,それぞれ約 2 万 1 千人~約 2 万 5 千人のほぼ一定の範囲内にあったが,超過死亡の範囲(最小値,最大値)はそれぞれ,約 1 万 5 千人~約 3 万 6 千人,約 1 万 8 千人~約 3 万 1 千人,約 1 万 4 千人~約 2 万 8 千人,そして約 1 万 1 千人~約 3 万 4 千人と年によって異なることが示された。超過死亡の範囲を比較し,95年の超過死亡が観察期間中で最大であった可能性もあることが分かった。結論 インフルエンザの流行がない場合の死亡数のばらつきの範囲を考慮した上で,その年のインフルエンザの流行によって増加したと考えられる死亡数の範囲(最小値,最大値)を把握することができた。超過死亡の範囲の推定は,インフルエンザによる健康影響を把握する上で,有用な方法の 1 つであると考える。
103 0 0 0 OA 欧州議会は, なぜ従軍慰安婦非難決議を出したか
- 著者
- 羽場 久美子
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.3_79-3_81, 2009-03-01 (Released:2012-02-09)
- 参考文献数
- 3
103 0 0 0 OA Investigating the Chronological Variation of Popular Song Lyrics ThroughLexical Indices
- 著者
- Yuichiro Kobayashi Misaki Amagasa Takafumi Suzuki
- 出版者
- Japanese Association for Digital Humanities
- 雑誌
- Journal of the Japanese Association for Digital Humanities (ISSN:21887276)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.90-107, 2017-09-06 (Released:2017-09-07)
- 参考文献数
- 29
Popular songs can be regarded as a fine representation of modern society andculture. In particular, the lyrics of popular songs are the most importantaspect for understanding the sense of values and linguistic sensitivity in agiven generation and community. The purpose of the present study is toinvestigate the chronological variation of popular Japanese songs usingstylometric techniques. This study draws on the lyrics of 858 songs, whichappeared on the Oricon annual top 20 single hit chart between 1976 and 2015. Thelinguistic features investigated in this study include five different types oflexical indices, namely (a) number of words, (b) parts-of-speech, (c) wordtypes, (d) character types, and (e) vocabulary level. Multiple regressionanalysis was conducted to explore the chronological change in the frequencies oflexical indices. The results showed that the frequencies of word types andcharacter types dramatically changed before and after 1990. Moreover, the usagesof auxiliary verbs as well as lower level vocabulary became more prominent,whereas the frequencies of adjectival nouns and conjunctions decreased. Thefindings suggest that a turning point in cultural trends corresponds with thehistorically significant political and economic events, such as the end of theShowa era and the burst of the bubble economy.