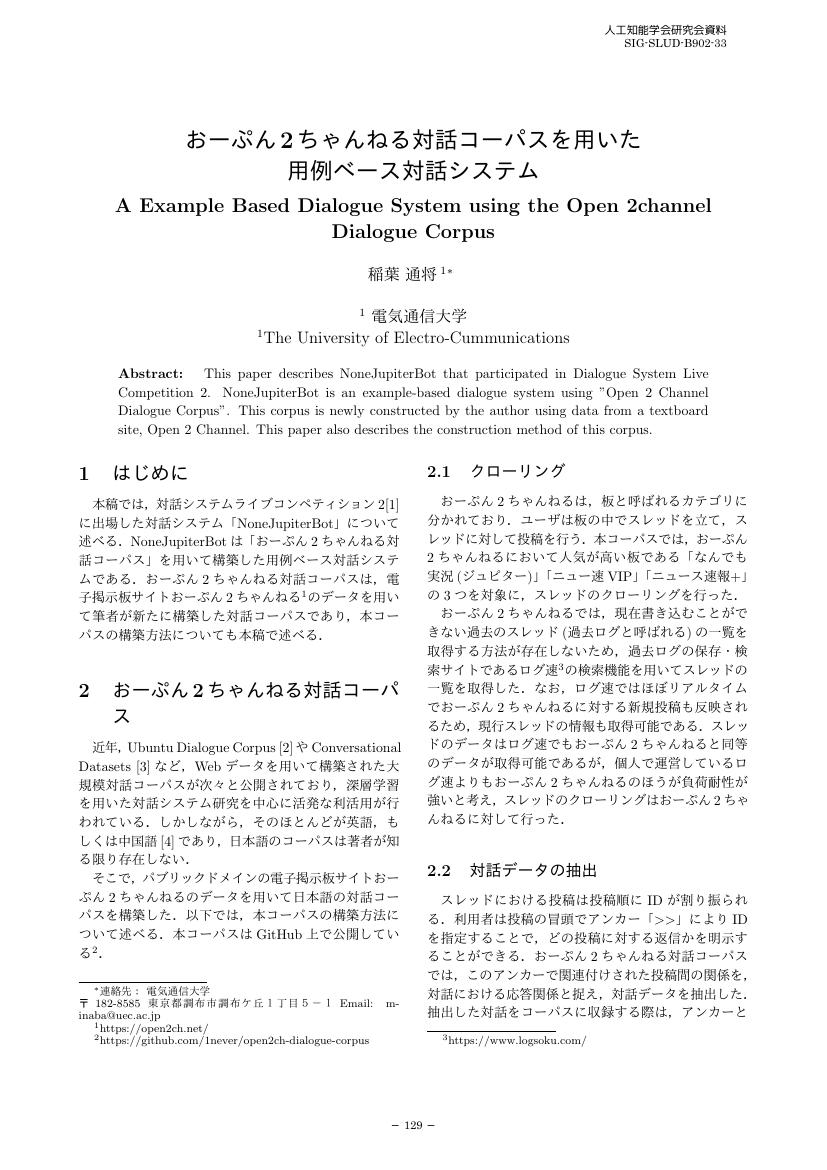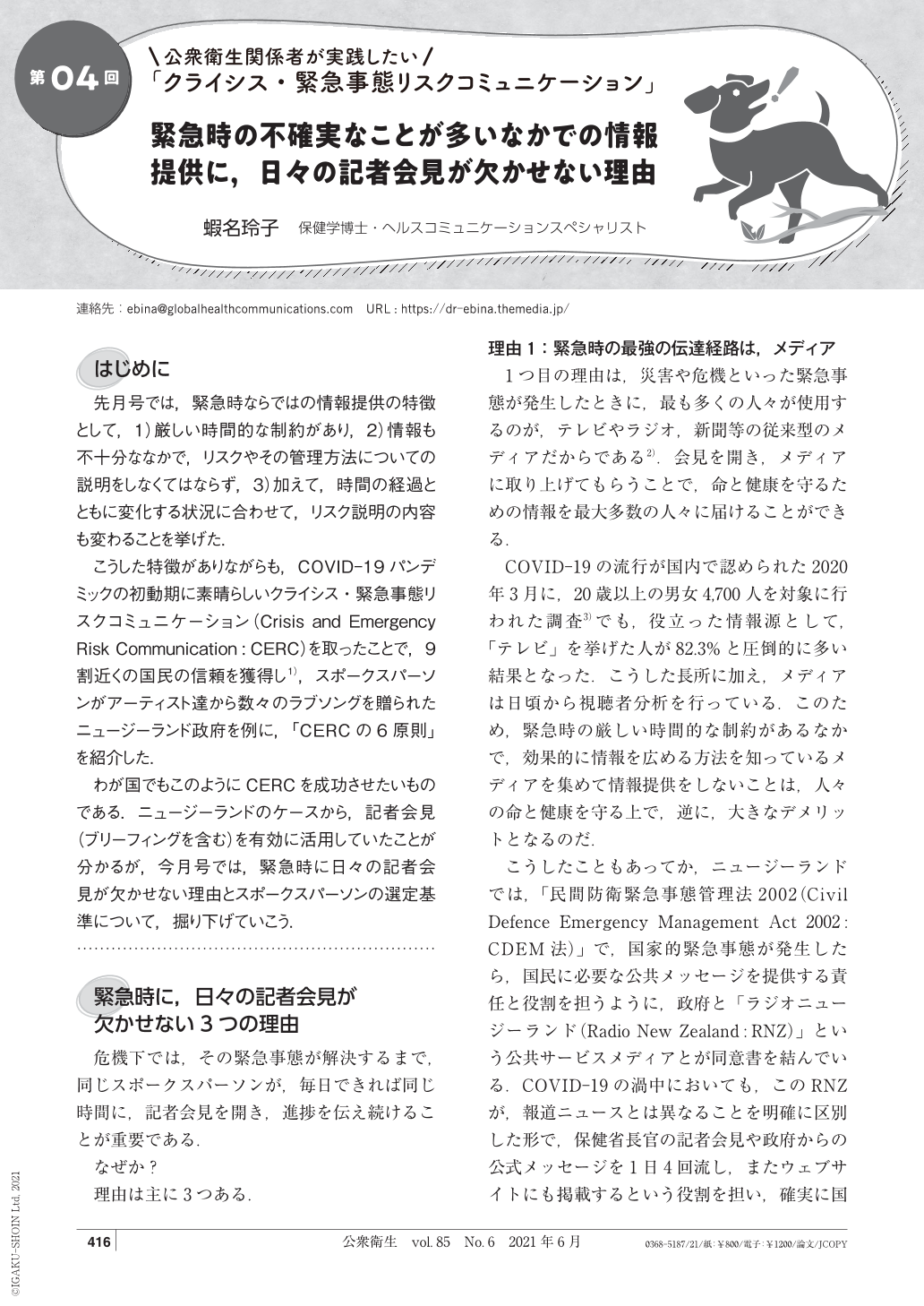3 0 0 0 OA ラドクリフ・ブラウンによる原始宗教の研究
- 著者
- 平敷 令治
- 出版者
- 沖縄大学
- 雑誌
- 沖大論叢 (ISSN:03871630)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.1-24, 1967-03-31
3 0 0 0 IR 障害者施設職員における職務環境の認識に関する研究指導教員 : 自由回答に基づく分析
- 著者
- 中山 慎吾
- 出版者
- 鹿児島国際大学福祉社会学部
- 雑誌
- 鹿児島国際大学福祉社会学部 = カゴシマ コクサイ ダイガク フクシ シャカイ ガクブ (ISSN:13466321)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.13-27, 2019-10-01
Two aspects are considered vital for the accomplishment of the duties of personnel who assist persons with disabilities : the first aspect concerns their work environment, including human relationships and the treatment these personnel receive at their workplace, and the second aspect involves the subjective rewards attained by the facilitators from the work they perform. This paper aims to focus on the former aspect and examines the features pertaining to the perceptions of the personnel regarding their work environment. A qualitative analysis was conducted on the basis of free answers obtainedfrom a questionnaire survey administered to 223 participants facilitating children or persons with disabilities. The results of the evaluation of the descriptions provided by the participants were classified into five core categories. Statements on the work environment and also on matters external to the workplace milieu were included in this analysis. Participants' insights on their work environment were incorporated in the core category, "the workplace and the treatment received in the workplace." This core category also encompassed assertions about the physical and mental burden borne by these personnel. This paper primarily reports on the results of the examination conducted on statements included in this core category. Moreover, the present study additionally evaluated the contents relating to the core category that included the participants' doubts and dissatisfaction with their jobs and their attitudes toward work.
3 0 0 0 OA おーぷん2ちゃんねる対話コーパスを用いた用例ベース対話システム
- 著者
- 稲葉 通将
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会研究会資料 言語・音声理解と対話処理研究会 87回 (2019/12) (ISSN:09185682)
- 巻号頁・発行日
- pp.33, 2019-11-20 (Released:2021-06-28)
3 0 0 0 ライトノベルのトポグラフィ/グラフィティ
- 著者
- 土居 浩 西 訓寿
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.P04-P04, 2008
ライトノベルは《どこを》描写しているのか,ライトノベルは《どこに》存在しているのか.文化現象に対してむしろ「場所・空間フェティシズム」(参照:森正人『大衆音楽史』中公新書,2008)をより徹底化させることで,場所・空間研究の立場から,ライトノベル研究ひいてはポピュラーカルチャー研究に寄与することができないか.この目論見を素描することが,本発表の目的である. ライトノベルは《どこを》描写しているのか,との問いで注目するのは,安藤哲郎(「説話文学における舞台と内容の関連性」人文地理60-1,2008)が「舞台」と呼ぶ対象とほぼ同義である.安藤は「舞台」を「登場人物などに何らかの行動がある場所,由緒や出身地としての説明がある場所」として,院政期に編纂された説話集からその「舞台」を抽出した上でさらに分析軸を加える.本発表も安藤と同様に,登場人物の行動を追いかけることで作品の「舞台」を抽出するが,分析軸については安藤の方法をとらない.それは対象とする作品群の違いに拠る.つまり安藤における説話集と異なり,本発表におけるライトノベルが文学研究の対象としてようやくみなされつつある現状を前提としている. 文学作品を対象とする地理学研究に対して小田匡保は,「地理学研究者が文学を扱う際に,文学研究者の研究史を踏まえ,それに(地理学的観点から)何か新しいことを付け加えるのでなければ,文学の人には相手にされないだろう」(「文学地理学のゆくえ」『駒澤地理』33,1997)と指摘している.すでに10年以上経過した現在においてもなお有効な指摘であることを認め,本発表ではライトノベル研究を踏まえつつ,まずは「文学の人」に相手にされる研究を試みた. ライトノベル研究の現状については,大島丈志(「ライトノベル研究会の現在」日本近代文学78,2008)の整理が参考になる.大島は「ライトノベル市場が拡大し影響力を増す一方で,ライトノベルに関する研究は文学研究の落とし穴のような状況になっている」と指摘した上で,ライトノベル研究会で蓄積された知見を紹介する.そのひとつとして,ライトノベルの成立期におけるTRPG(テーブルトーク・ロールプレイングゲーム)の影響がある.この点に関連し発表者はライトノベル研究会に参加し,ライトノベルが描写する「舞台」について直接に研究会参加者たちと意見交換する中で,「舞台」の時期的変遷が参加者たちにある程度共有されつつも,いまだ実証的検討が試みられていないことに気がついた. ライトノベル研究に場所・空間研究の立場から寄与すべく,本発表ではアスキー・メディアワークス(旧メディアワークス)主宰の小説賞である電撃小説大賞を対象とし,その大賞・金賞受賞作品は《どこを》描写しているのか,作品の「舞台」を抽出し整理を試みた.その結果,90年代の受賞作品と,00年代の受賞作品とでは,その「舞台」の明確な差異が指摘できた.ライトノベルはより《学校を》描写するようになってきており,端的に述べればライトノベルの「舞台」は《学校化》しているのである. 以上は作品内部の分析である.では作品外部はどうか.これに対応する問いが,ライトノベルは《どこに》存在しているのか,である.森前掲書の「重要なキーワード」である「聴衆,音楽産業,商品化,物質化,アイデンティティ,政治,歴史,地理(移動,場所,空間)」は,冒頭の二語を「読者,出版産業」等に置換すればそのままライトノベルの語り口としても適用可能かつ重要なキーワードとなる.とはいえこれらキーワードが示すメタ次元の問いを発する前に,本発表ではベタな実地踏査を試みた結果を報告する.その意味では断片的報告であり,トポグラフィならぬトポグラフィティを名乗る所以でもある.
3 0 0 0 IR 障害者施策の変遷と相談支援・1996 年─ 2000年
- 著者
- 萩原 浩史
- 出版者
- 立命館大学大学院先端総合学術研究科
- 雑誌
- Core Ethics : コア・エシックス = Core Ethics : コア・エシックス (ISSN:18800467)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.179-190, 2014
はじめに 先月号では,緊急時ならではの情報提供の特徴として,1)厳しい時間的な制約があり,2)情報も不十分ななかで,リスクやその管理方法についての説明をしなくてはならず,3)加えて,時間の経過とともに変化する状況に合わせて,リスク説明の内容も変わることを挙げた. こうした特徴がありながらも,COVID-19パンデミックの初動期に素晴らしいクライシス・緊急事態リスクコミュニケーション(Crisis and Emergency Risk Communication:CERC)を取ったことで,9割近くの国民の信頼を獲得し1),スポークスパーソンがアーティスト達から数々のラブソングを贈られたニュージーランド政府を例に,「CERCの6原則」を紹介した. わが国でもこのようにCERCを成功させたいものである.ニュージーランドのケースから,記者会見(ブリーフィングを含む)を有効に活用していたことが分かるが,今月号では,緊急時に日々の記者会見が欠かせない理由とスポークスパーソンの選定基準について,掘り下げていこう.
3 0 0 0 OA 快適さの客観的計測と評価
- 著者
- 吉田 倫幸
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.10, pp.696-701, 2002-10-10 (Released:2009-11-26)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 2
3 0 0 0 OA 首都の特質と首都機能再配置の諸形態
- 著者
- 山口広文
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.627, 2003-04
- 著者
- 村上 龍
- 出版者
- 国士舘大学哲学会
- 雑誌
- 国士館哲学 (ISSN:13432389)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.38-46, 2012-03
3 0 0 0 OA シーティングの基礎 - 車椅子利用者への理学療法-
- 著者
- 廣瀬 秀行
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.4, pp.349-352, 2013-06-20 (Released:2017-07-21)
- 参考文献数
- 17
- 著者
- 須見 洋行
- 出版者
- Brewing Society of Japan
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, no.3, pp.137-146, 2014 (Released:2018-03-06)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 2 1
血液には,血液を凝固させる凝固系と凝固した血液を溶かす線溶系が存在し,そのバランスが大切である。筆者はこれまでに血液の凝固-線溶系について研究を重ね,1980年代に血栓を溶解するナットウキナーゼを発見し,納豆の健康食品としての有効性を裏付けた。本稿では,焼酎香気成分が線溶因子の1つであるt-PAの放出を促進し,血小板凝集を阻害することについてご紹介いただく。これまでに,適量飲酒は心臓疾患や脳梗塞に良いという結果が多くの疫学調査で報告されているが,焼酎香気成分の寄与もあるのではないだろうか。
3 0 0 0 OA 社会科学における理念型とモデル 社会科学の科学方法論再考
- 著者
- 田端 泰子
- 出版者
- 京都橘大学研究紀要編集委員会
- 雑誌
- 京都橘大学研究紀要 = Memoirs of Kyoto Tachibana University (ISSN:18830307)
- 巻号頁・発行日
- no.42, pp.(1)-(19), 2016-02-18
3 0 0 0 性同一性障害をめぐって : 司会のことば
- 著者
- 阿部 輝夫 仲本 政雄
- 雑誌
- 日本性科学会雑誌 = Japan Journal of Sexology
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, 1998-09-30
3 0 0 0 OA 銀舎利考
- 著者
- 菅原 泰典
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.843-839, 1994-03-25 (Released:2010-03-09)
- 著者
- 今井 民子 笹森 建英
- 出版者
- 弘前大学教育学部
- 雑誌
- 弘前大学教育学部紀要 (ISSN:04391713)
- 巻号頁・発行日
- no.66, pp.29-53, 1991-10-31
ヴァイオリン音楽の発展を可能にした背景には,17世紀から18世紀の楽器製作の改良,演奏技術の確立があった。この論文では,先ず楽器製作の変遷を概観する。この時代の演奏技術の確立を把握する上で重要なのは,器楽形式の発展と,一連の技法書の出版,技巧を駆使して葵すカブリスの類の作品の出現である。レオボルト・モーツァルトMozart, Johann GeorgLeopoldやジェミニア一二Geminiani,FrancescoSverioの奏法に関する著書,ロカテッリLocatelli,PietroAntonioのカブリスは重要な役割をはたした。この論文では,彼らによって掲示された技法を具体的に考察する。20世紀,特に1945年以降は,音楽様式,演奏法が画期的な変貌を遂げた。その技法上の特質を明らかにする.これらを踏まえて,音楽文化が新芽し,形成され,さらに発展,変遷していく過程に教育書がどのような役割を果たすのかについても検証する。
3 0 0 0 OA 前近代日本の山村をめぐる三つの視角とその再検討
- 著者
- 米家 泰作
- 出版者
- The Human Geographical Society of Japan
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.6, pp.546-566, 1997-12-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 225
- 被引用文献数
- 1
The purpose of this paper is to re-examine the history of the mountain area in Japan with special reference to differing viewpoints expressed by historians and other scholars such as folklorists, geographers or ethnologists. This difference of viewpoint between historians and other disciplines is notable. The former has mainly concentrated on economic development and the formation of political systems, while the latter have been concerned with systems and the processes of cultural decline. These two approaches are in contrast with each other, but have the potential to complement each other. Consequently, the author surveyed researches on cultural, political and economic points of view to explore more comprehensive schema.A good place to start is to inquire into the genetical approach to mountainous area culture by folklorists, ethnologists and cultural geographers. Some have advanced the hypothesis that subsistence economies such as shifting cultivation, hunting and gathering, which still remain in modern mountain villages, date back to the Jomon period, that is to say, before the time when paddy cultivation developed in Japan. Assuming this hypothesis to be true, it can be said that the mountain people are successors of the Jomon culture, which is supposed to be the base of all Japanese culture.This opinion begs the question how and when the non-paddy cultural system has been carried into modern mountain villages. It is necessary to discuss this on two points. Is the modern inhabitant of the mountain area, who is isolated from the alluvial plain, a descendant of Jomon people? Has the non-paddy cultural system survived only in mountain areas since ancient times?First, some folklorists emphasize that medieval warriors retreated into the mountain area afther defeat. Some historians have studied the governmental forestry system in ancient times, and reclamations expanding toward mountain areas in medieval times. Results of these researches suggest that we must pay more careful attention to the dynamic process of the immigration from low lands to the mountain area and to their relation with the political and economic context.Secondly, recent historical and historico-geographical studies have recognized the importance of dry field and shifting cultivation in the alluvial plain from ancient to medieval times. We can, consequently, presume that the subsistence economies without paddy had developed both in the mountain area and in the plain, but that in early modern times the cultural characteristics in the mountain area presented a clear contrast with the culture concentrating on rice cultivation in the plain.These points lead us to the question how did non-paddy cultures survive at a time when the strong tendency was to concentrate on rice cultivation in Japan? In other words, what was the relationship between the Japanese political and economic system and the people in the mountain area prior to early modern times?This paper also re-examines the works focusing on the peasant revolts in mountain areas in early seventeenth century. Some folklorists and cultural geographers have suggested that these uprisings happened in the process of mountain people being ruled by the unifying political powers based on paddy cultivation in the plains. However, these revolts were not the first contact between them. Other folklorists pointed out that the mountain people were already ruled by a centralized government in ancient times. Some historians have argued about the medieval territory as a manor or a legal unit in western Japan, and pointed out that the medieval political power had a reason to keep estates in the mountain area to supplement rice production with various products of dry field cultivation, shifting cultivation, hunting and gathering. This way of control contrasts with the early modern political system which demanded timber and charcoal from mountain villages.
3 0 0 0 OA H-ⅡBロケット 射点設備の開発
- 著者
- 長田 弘幸 上田 広幸 原 利顕 平野 雅宣 服部 正雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.682, pp.348-352, 2010-11-05 (Released:2019-04-19)
3 0 0 0 OA 吃音症患者に対して身体障害者手帳を記載した 2 例
- 著者
- 菊池 良和
- 出版者
- 耳鼻と臨床会
- 雑誌
- 耳鼻と臨床 (ISSN:04477227)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.2, pp.72-75, 2018-03-20 (Released:2019-04-27)
- 参考文献数
- 6
3 0 0 0 OA 秋田家文書による文祿・慶長初期北國海運の研究(一)
- 著者
- 古田 良一
- 出版者
- 社会経済史学会
- 雑誌
- 社会経済史学 (ISSN:00380113)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.313-344, 1941-06-15 (Released:2017-09-24)