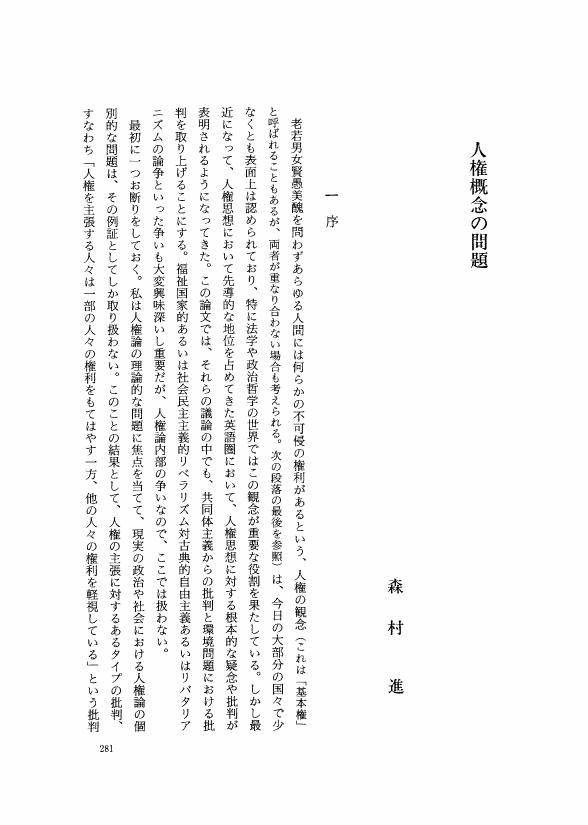2 0 0 0 OA 近世後期洒落本に見る行為指示表現の地域差 ──京・大坂・尾張・江戸の対照──
- 著者
- 森 勇太
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.69-85, 2019-08-01 (Released:2020-02-01)
- 参考文献数
- 21
本稿では,近世後期に見られる洒落本の行為指示表現について,京・大坂・尾張・江戸の4地点の状況を対照し,その地域差について考察した。敬語を用いない形式群を非敬語グループ,敬語オを用いた形式群をオグループ,敬語を用いた形式群を敬語グループとすると,上方は各グループの多様な形式を用いているが,江戸はほとんどが敬語グループであった。尾張は敬語形式の多様性は上方と類似しているが,敬語グループの頻度が高いことは江戸と共通していた。この地域差について,京・大坂では,敬語グループと他の形式,特にオグループを併用することが通常の運用となっているのに対し,江戸では丁寧体を基調とするスタイルにおいて,行為指示表現が「お─なんし」等少数の形式に限定される傾向にあり,中間的な尾張の運用は,心的距離や発話意図によって併用することがあるものの,全体的には敬語グループに偏っており,江戸に近い運用と位置づけられることを述べた。
- 著者
- 中村 和彦
- 雑誌
- 北星学園大学社会福祉学部北星論集 = Hokusei Review, the School of Social Welfare (ISSN:13426958)
- 巻号頁・発行日
- no.58, pp.121-132, 2021-03-15
2 0 0 0 IR 神話の「抹殺」、「抹殺」の歴史 : 『基督抹殺論』と「かのやうに」における近代史学
- 著者
- 堀井 一摩
- 出版者
- 東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻
- 雑誌
- 言語情報科学 (ISSN:13478931)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.283-297, 2014
本稿の目的は、幸徳秋水のキリスト教批評『基督抹殺論』(丙午出版社、1911 年)と森鷗外の短編小説「かのやうに」(『中央公論』1912 年1 月)を、近代史学と皇国史観との歴史的緊張関係の中に位置づけて読み直すことである。草創期の日本近代史学を担った重野安繹や久米邦武等の「抹殺論」と呼ばれる考証史学の実践とこの二つのテクストとのインターテクスト性を浮かび上がらせる作業を通じて、南北朝正閏論争で顕在化した実証史学の弾圧に対して、この二つのテクストがいかにして「抹殺論」を甦らせようとしているかを分析する。その過程で、『基督抹殺論』と「かのやうに」の応答関係とともに、「抹殺論」甦生の試みが閉塞的な同時代に対してもつラディカルな批評性を明らかにした。
2 0 0 0 OA チューリップの自家不和合性の打破に及ぼす開花時期ならびに柱頭切除および高温処理の影響
- 著者
- 岡崎 桂一 村上 欣治
- 出版者
- THE JAPANESE SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE
- 雑誌
- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.405-411, 1992 (Released:2008-05-15)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 3 7
チューリップの自家不和合性を打破する目的で, 促成時期のちがいと自家不和合性の強弱の関係を調査したほか, 柱頭を花柱から切り放し, その切断面に自家花粉を受粉する柱頭切除受粉法および柱頭を40°~50°Cの温湯に浸漬する高温処理を検討した.1.チューリップ5品種を2月から4月にかけて促成栽培と露地栽培を行い自殖したところ, 露地栽培の自然開花時では全品種とも完全な自家不和合性であったが, 促成栽培では5品種中4品種は自殖によって多数の種子が得られた. 促成栽培を行うことによって,自家不和合性が弱まることが示された.2.柱頭切除後の受粉によって, 供試した5品種すべての自家不和合性が部分的に解消され, 1子房当たり8~81個の自殖種子が得られた. 柱頭切除法によって, 極めて効率よくチューリップの自家不和合性が打破されることが明らかになった.3.柱頭を温湯に浸潰する高温処理法により自殖したところ, 供試した3品種のうち1品種で, 50°C, 1分間処理により24花交配中2花, 3分間処理により24花交配中4花結実し, 低率ではあるが自殖種子が得られた.これらの方法は, チューリップの自殖系統育成法として実用的な技術であると推察された.
2 0 0 0 OA 「意味の行為」とは何であったか? J. S. ブルーナーと精神の混乱と修復のダイナミズム
- 著者
- 横山 草介
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学研究 (ISSN:24357065)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.205-225, 2018 (Released:2021-04-12)
本論の目的は,ブルーナーの「意味の行為」論本来の探求の射程を明らかにすることにある。ナラティヴ心理学 の展開におけるブルーナー受容においては,「意味の行為」は専ら物語を介して対象を「意味づける行為」とし て理解されてきた。だが,彼が本来の主張として訴えたのは,人間の意味生成の原理と,その機能の解明という主 題であった。これまでのブルーナー受容は,この論点を不問に処してきた傾向がある。これに対し我々は,ブルー ナーの「意味の行為」論本来の主題の解明に取り組んだ。我々の結論は次の通りである。ブルーナーの主張した 「意味の行為」とは,前提や常識,通例性の破綻として定義される混乱の発生に相対した精神が,その破綻を修復し, 平静を取り戻そうとする「混乱と修復のダイナミズム」の過程として理解することができる。この過程は,何ら かの混乱の発生に伴って生じた,今,この時点においては理解し難い出来事が,いずれ何らかの意味を獲得するこ とによって理解可能になるような「可能性の脈絡希求の行為」として定義することができる。最後に我々は,ブ ルーナーの「意味の行為」論は,心理学の探求による公共的な平和の達成という思想的展望を有することを指摘 した。この展望は特定の文化的脈絡の中で生きる我々が,他者と共に平穏な生活を営んでいくために精神が果た し得るその機能は何か,という問いと結びつくものであることが明らかとなった。
2 0 0 0 OA 人権概念の問題
- 著者
- 森村 進
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1997, pp.281-298, 1998-10-30 (Released:2009-02-12)
- 参考文献数
- 8
2 0 0 0 IR ヨーロッパの古式テニス球戯を訪ねて : イタリアの北部・中部諸州の「ブラッチャレ球戯」
- 著者
- 辻本 義幸
- 出版者
- 神戸松蔭女子学院大学
- 雑誌
- 研究紀要. 人文科学・自然科学篇 (ISSN:13421689)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.21-66, 2001-03-20
- 著者
- 中野 智世
- 出版者
- 障害学会 ; 2005-
- 雑誌
- 障害学研究 (ISSN:18825265)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.186-209, 2020
2 0 0 0 OA 奴隷所有者の妻 : ファニー・ケンブルの『ジョージア日記』を読む
- 著者
- 大井 浩二 Koji Oi
- 雑誌
- 英米文学 (ISSN:04246853)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.240-253, 2011-03-15
- 著者
- 南里 幻香
- 出版者
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会
- 雑誌
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, pp.84-84, 2016
<p>【はじめに】</p><p>重症心身障害者の中には、他者との関わりを好んでいても自己表出の仕方が分からず、受身的になっている症例は少なくない。今回、他者との関わりに対し受身的であった症例が作業療法(以下、OT)で行ったミサンガ作りを通して関わりの段階を踏み、積極的に話せるようになった。その経過に考察を加えて報告する。尚、この報告は本人と保護者および当園の倫理委員会の承諾を得ている。</p><p>【症例紹介】</p><p>30代男性(以下、A氏)。診断名は脳性麻痺(痙直型四肢麻痺)、Pelizaeus-Merzbacher 病。横地の分類A3。絵画語彙発達検査の語彙年齢は5歳2か月。脳性麻痺児手指操作能力分類システム(MACS)Ⅲ。脳性麻痺児粗大運動機能分類システム(GMFCS)レベル5。FIM52点、Barthrl Index 35点。当園に入所されており、余暇時間には趣味である折り紙や塗り絵を行うことが多い。</p><p>【作業療法評価】</p><p>他者と関わることを好んでいるが、自発的な関わりはなく、話したい人をみつめていることが多い。自分の思いや考えは明確に持っているものの、他者から話しかけられると応答の仕方に困り、首を傾げることが多い。食事や排泄等の生活場面に必要な介助も、病棟職員(以下、職員)からの声掛けを待つなど受身的である。OTで作製した作品を職員から褒められることがA氏の自信へとつながっており、自ら作品を披露しようとすることもあるが、どのように関わって良いか分からず披露できない。気づいた職員が「上手にできたね。」と声掛けをするとうなずいて応答するのみである。</p><p>【目的】</p><p>A氏が自信を持っている創作活動をコミュニケーションツールとし、職員へ積極的に話しかけることができる。</p><p>【方法・結果】</p><p>〈第Ⅰ期:職員の声掛けに対し、定型文での返答がみられるようになった時期/1~2ヶ月間〉</p><p>創作活動としてミサンガ作りを行った。A氏が困難な動作を補うためにミサンガ台を作製し、OTで台の取り扱いと声掛けへの返答を練習した。ミサンガ作りは余暇時間に職員の多い病棟ホールで行い、職員とのやり取りが行えるようにした。作る様子を見た職員から「上手だね。」と声を掛けられると、「どうも。」と定型文での返答がみられるようになった。</p><p>〈第Ⅱ期:A氏から職員へ定型文で声掛けができるようになった時期/3~4ヶ月間〉</p><p>ミサンガ屋さんを開き、職員より注文を受け付けてプレゼントをした。OTでは定型文で声掛けをする練習した。職員へ「何色の糸がいいですか?」と好みの糸の色を聞き、注文票に糸の色と氏名を記載してもらい、専用の受付ポストに投函してもらうよう伝えることができるようになった。</p><p>〈第Ⅲ期:A氏から職員へ自由に声掛けができるようになった時期/5~8ヶ月間〉</p><p>糸が絡まるなど修正が必要になった場合には、「糸が絡まっちゃったよ~。」と自ら依頼ができるようになった。また、受身的だった生活場面での介助も積極的に職員へ依頼する様子がみられるようになった。</p><p>【考察】</p><p>今回、他者と関わりを持ちたいが関わり方が分からず応答に困っているA氏に対し、積極性向上を目的にOTを行った。その結果、職員と積極的に話すことができるようになった。その要因として、A氏が唯一自信を持てる創作活動をコミュニケーションツールとして生活に組み込めたこと、さらにミサンガ作りを通して段階を踏んだ関わり方の練習を行ったことがA氏の積極性につながったのではないかと考える。今後もより多くの人との関わりを持ち、A氏の生活の幅がさらに広がることを願っている。</p><p>【倫理的配慮,説明と同意】</p><p>この報告について本人と保護者へ十分に説明を行い、承諾を得ている。また、当園の倫理委員会の承諾を得ている。利益相反に関する事項はない。</p>
2 0 0 0 5115 東京カテドラル大聖堂における自然光による空間演出手法
- 著者
- 鈴木 信宏 伊谷 峰 中澤 王久東
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集. E, 建築計画, 農村計画 (ISSN:09150153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1986, pp.229-230, 1986-07-25
- 著者
- 松井 広志
- 出版者
- 日本マス・コミュニケーション学会
- 雑誌
- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, pp.19-32, 2021
<p>This paper examines video games in order to discuss roles played by media culture during the COVID-19 pandemic. In 2020, people spent a large amount of their time playing communication-oriented games, such as "Animal Crossing: New Horizons," or social multiplayer games on smartphones. This trend is an extension of the casual revolution in video games since the 2000s.</p><p>Notably, however, communication-oriented games during the pandemic also seem to offer alternative means for casual ordinary communication in the abnormal reality imposed by the pandemic. Their popularity is a sign of new roles played by media culture and games.</p>
2 0 0 0 OA あいりん地域に生活の拠点を置く者の栄養学的特性
- 著者
- 田原 遠
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.1, pp.13-23, 2020-02-01 (Released:2020-03-19)
- 参考文献数
- 31
【目的】あいりん地域に生活の拠点を置く者の生活状況,栄養学的特性について明らかにすることを目的とした。【方法】大阪社会医療センター付属病院通院中の患者と高齢者特別清掃事業参加者に対し,半定量食物摂取頻度調査票による栄養調査と身体状況・生活状況調査を行い計255名より完全回答を得た。うち生活困窮度の低い5名を除いた250名(生活保護受給者=生保群とする123名,生活保護未受給者=未受給群とする127名)を対象者とした。対象者が平成26年国民健康・栄養調査における所得の低い集団(低所得群とする)が示している特徴を有しているかどうか,また生活保護受給の有無で対象者の特性に差異が生じるかどうかの検討を行った。【結果】本対象者は残歯20本未満の者が79.2%,喫煙者は58.8%と共に極めて多く,野菜類摂取量は極めて少なかった。両群間の比較では,生保群において仕事をしている者がより少なく,肥満者はより多く,野菜類,果実類,きのこ類,乳類の摂取量はより多かったが,飲酒習慣者の割合や嗜好飲料類の摂取量はより少なかった。【結論】本対象者は低所得群の特徴を有しており,なおかつ低所得群よりもより顕著な傾向を示した。両群間の比較より,生保群においては活動量に見合った摂取量に関する栄養教育が,未受給群においては飲酒に関する教育,外食や中食でも野菜類を摂取できるような栄養教育が必要であると考えられた。
- 著者
- 河村 徳士
- 出版者
- 社会経済史学会
- 雑誌
- 社會經濟史學 (ISSN:00380113)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.2, pp.179-201, 2010-08-25
本稿は,1920年代前半に指摘された小運送料金問題とその対応を検討し,26年6月に実施される合同政策の背景および業界がこれを受容する条件を考察するものである。この時期,荷主や鉄道省は小運送料金の高さを問題とした。それは,第一次大戦期に指摘された高額請求とは,小運送料金の水準自体の引下げを求めた点て異なるものであった。しかし,何らかの合理化策を施さない限り料金低下を実現することは困難な状況にあった。鉄道省は,料金低下には合同政策が必要であると判断し始めていた。一方,業界では,大戦後の需要減退を契機として競争が激化し,不当な手段に訴えた値下げ競争,違法性の強い取引を利用した荷主獲得競争が展開された。こうした不正な競争への関与を余儀なくされつつあった業界では,何らかの競争抑制策が求められていた。合同を通じた運送店数の減少により競争が抑制される効果を期待できる点て,合同政策を受容する条件が形成されていたのである。
- 著者
- 宮崎 和光 吉田 望 森 利枝
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)
- 巻号頁・発行日
- vol.142, no.2, pp.117-128, 2022-02-01 (Released:2022-02-01)
- 参考文献数
- 32
In 2017, it became mandatory for universities in Japan to disclose their policies in degree granting (Diploma Policy: DP, hereafter) that state standards to confer degrees. Meanwhile, since 1991, nomenclature of major fields that appear in diplomas has been the responsibility of individual universities, instead of the national regulation. This study examines whether the former reasonably evokes the latter, given that both of them are deemed to represent the learning outcomes that the graduate has obtained. In order to do so, we compared the ability of humans and that of a deep-learning system (which is based on the Character-level CNN), to match DPs and major fields that are randomly given. In the examination of human ability, which was implemented with a large enough number of participants to obtain statistically significant results, we found there were a certain number of DPs that the majority of people failed to match with major fields. Given this fact, we analyzed such DPs to demonstrate that the deep learning system shows a high success rate in sorting out the DPs that poorly evoke major fields.
- 著者
- 河野 隆志 清水 聖志人 島本 好平 久木留 毅 土屋 裕睦
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.67, pp.242_1-242_1, 2016
<p> 日本レスリング協会では、「インテリジェントレスラーの育成」を理念にアスリートとしてのキャリアと人としてのキャリアの両立(Dual Career)の支援を目指した新たな発掘・育成システムの構築を推進している。本事業の一環にて、カデット世代(U-18)の国内育成プログラムに参加している最も優秀なタレントを選考し、海外育成プログラムへ派遣した。同プログラムにおいては、ライフスキル(以下、LS)の獲得を促すためGROWモデル(Goal・Reality・Options・Will)による個別ミーティングを複数回実施した。2015年度においては、男子フリースタイルのタレント3名をロシア(クラスノヤルスク)、男子グレコローマンスタイルのタレント3名を韓国(釜山)、女子のタレント4名をアメリカ(コロラドスプリングス)へそれぞれ派遣した。本研究ではLS評価尺度を用いて、海外育成プログラムの出発時点と帰国時点のLS獲得レベルを比較することで、GROWモデルを用いた海外育成プログラムがLS獲得に与える影響を検討した。分析の結果、特に「コミュニケーション」(t(9)=1.87、p<.10)と「礼儀・マナー」(t(9)=1.65、p=.13)において、他のLSに比べ平均値の大幅な上昇が見られた。</p>
2 0 0 0 OA 小売店の購買行動における天気の影響 : スーパーマーケットのPOS データを用いた分析
- 著者
- 生田目 崇 須山 憲之
- 出版者
- 専修大学商学研究所
- 雑誌
- 専修大学商学研究所報 (ISSN:13450239)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.8, pp.1-29, 2010-02-26
- 著者
- 久保 樹里
- 出版者
- 日本子ども虐待防止学会 ; 1999-
- 雑誌
- 子どもの虐待とネグレクト = Japanese journal of child abuse and neglect : 日本子ども虐待防止学会学術雑誌 (ISSN:13451839)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.274-281, 2020-12