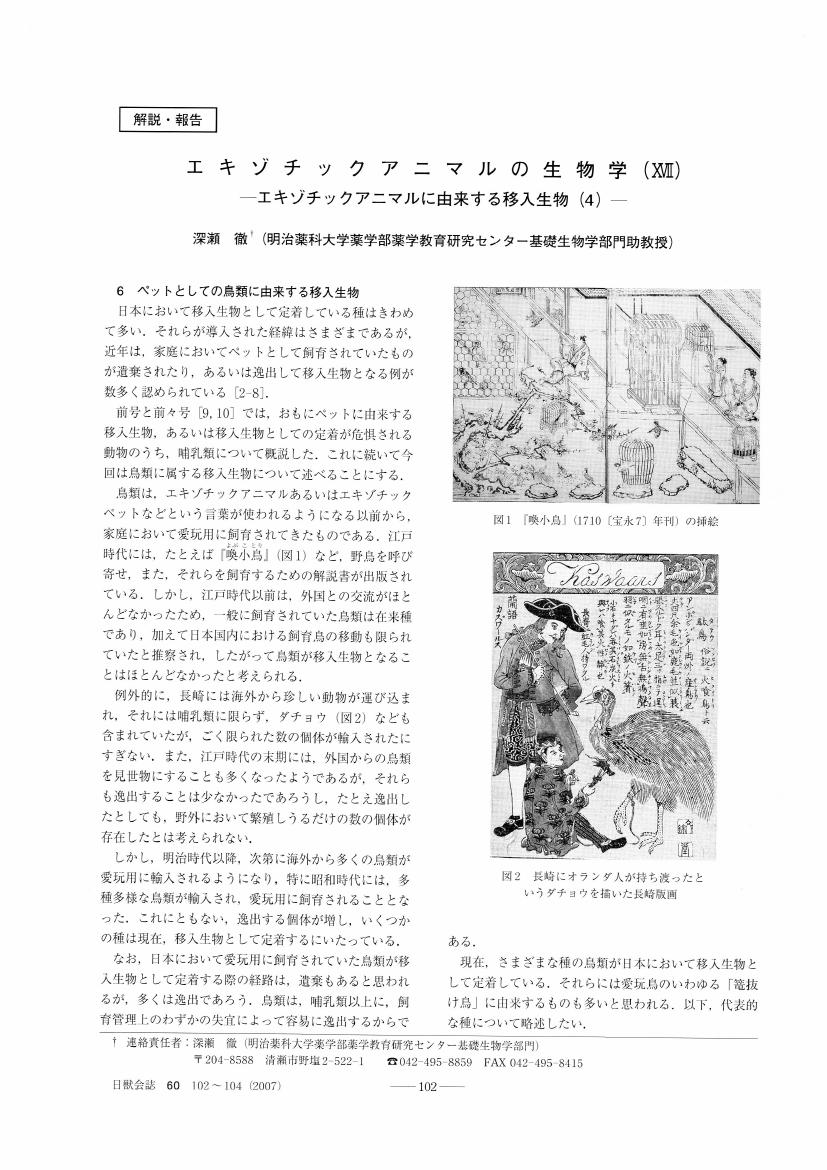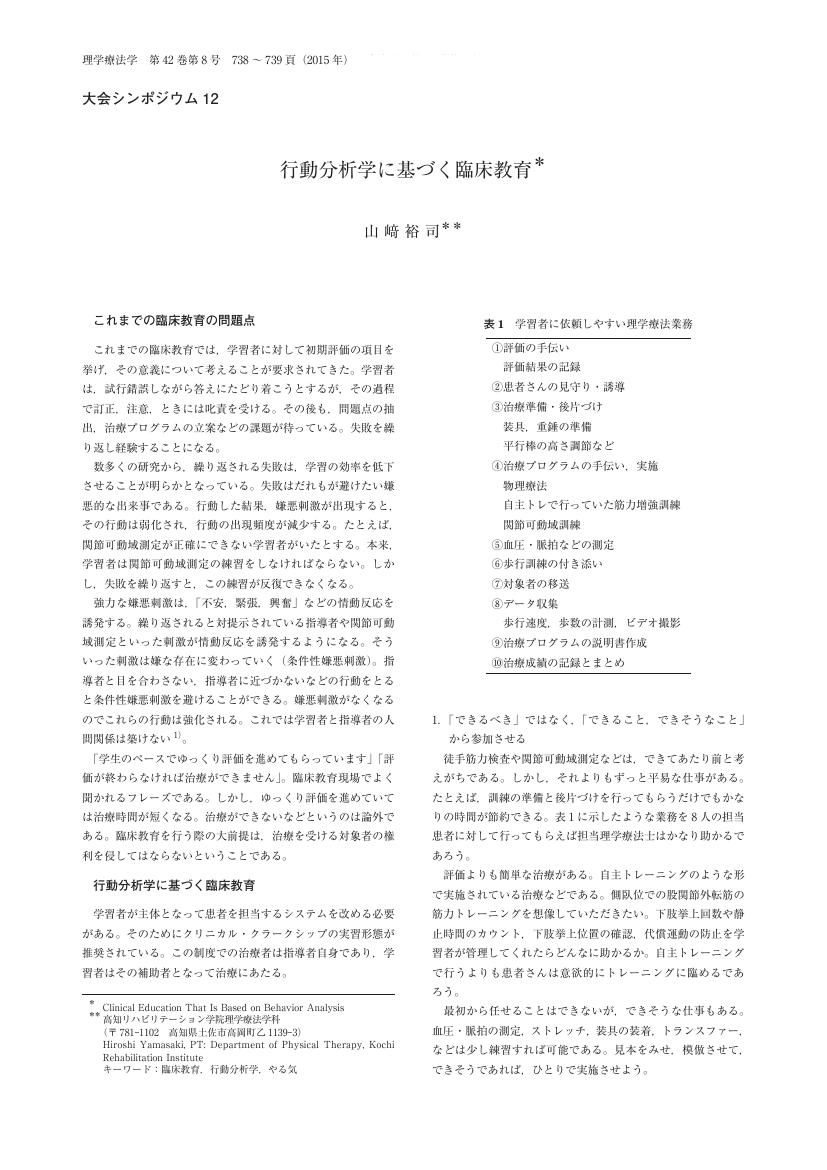1 0 0 0 OA ERCPに起因した後腹膜穿孔の原因と対応
- 著者
- 清水 哲也 水口 義昭 吉岡 正人 松下 晃 金子 恵子 川野 陽一 勝野 暁 神田 知洋 高田 英志 中村 慶春 谷合 信彦 真々田 裕宏 横室 茂樹 内田 英二
- 出版者
- 日本腹部救急医学会
- 雑誌
- 日本腹部救急医学会雑誌 (ISSN:13402242)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.79-85, 2016-01-31 (Released:2016-04-26)
- 参考文献数
- 19
ERCPは胆膵疾患の診断に不可欠な手技となり,ERCPを応用したさまざまな手技が活用されている一方,ERCPの偶発症は重篤化しやすく慎重を要す手技である。ERCP合併症の中でも後腹膜穿孔は死亡率が高く,その診断と対処が重要である。1999年1月から2015年5月までのERCP自験例 4,076例のうちERCPの後腹膜穿孔を10例(0.25%)に認め,その原因と対応を検討した。穿孔部位は,乳頭部3例,胆管3例,膵管2例,十二指腸2例であり,原因は,乳頭部穿孔ではEST,胆管穿孔では砕石処置具の挿入,膵管穿孔ではカテーテル操作,十二指腸穿孔では内視鏡の挿入による損傷であった。後腹膜穿孔を疑う際にはENBDや胃管で減圧しCTで後腹膜穿孔の重症度を確認する。CTで後腹膜に液体貯留を認め,かつ発熱や疼痛のある症例は緊急手術を行う。後腹膜気腫のみ,もしくは少量の液体貯留のみで無症状の症例は保存的加療を行い経時的に疼痛や液体貯留をフォローし,所見の悪化がある際は緊急手術を考慮する。
- 著者
- Peipei Song Jiangjiang He Fen Li Chunlin Jin
- 出版者
- バイオ&ソーシャル・サイエンス推進国際研究交流会
- 雑誌
- Intractable & Rare Diseases Research (ISSN:21863644)
- 巻号頁・発行日
- pp.2017.01003, (Released:2017-02-17)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 18
China is facing the great challenge of treating the world's largest rare disease population, an estimated 16 million patients with rare diseases. One effort offering promise has been a pilot national project that was launched in 2013 and that focused on 20 representative rare diseases. Another government-supported special research program on rare diseases – the "Rare Diseases Clinical Cohort Study" – was launched in December 2016. According to the plan for this research project, the unified National Rare Diseases Registry System of China will be established as of 2020, and a large-scale cohort study will be conducted from 2016 to 2020. The project plans to develop 109 technical standards, to establish and improve 2 national databases of rare diseases – a multi-center clinical database and a biological sample library, and to conduct studies on more than 50,000 registered cases of 50 different rare diseases. More importantly, this study will be combined with the concept of precision medicine. Chinese population-specific basic information on rare diseases, clinical information, and genomic information will be integrated to create a comprehensive predictive model with a follow-up database system and a model to evaluate prognosis. This will provide the evidence for accurate classification, diagnosis, treatment, and estimation of prognosis for rare diseases in China. Numerous challenges including data standardization, protecting patient privacy, big data processing, and interpretation of genetic information still need to be overcome, but research prospects offer great promise.
1 0 0 0 OA エキゾチックアニマルの生物学 (XVII)
- 著者
- 深瀬 徹
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.102-104, 2007-02-20 (Released:2011-06-17)
- 参考文献数
- 10
1 0 0 0 OA ハナヤスリ目の細胞分類学III.
- 著者
- 栗田 子郎 西田 誠
- 出版者
- 公益社団法人 日本植物学会
- 雑誌
- 植物学雑誌 (ISSN:0006808X)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.930, pp.461-473, 1965 (Released:2006-10-31)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 4 7
栗田子郎•西田誠: ハナヤスリ目の細胞分類学III. ハナヤスリ属の染色体数日本産のハナヤスリ属の内, 2種1変種の染色体数を観察した. ヒロバハナヤスリ (O. vulgatum)はn=240である. この染色体数はオランダ産のものと一致する. コヒロバハナヤスリ(O. petiolatum) には4系(細胞学的) があることが知られた. 千葉県の成田, 臼井, 銚子, および栃木県日光産の個体はn=480で胞子形成過程は正常である.千葉県稲毛産の個体はインド, セイロン産のものと同様n=510~520であるが,しばしば減数分裂に異常が起こり, 染色体橋や偽直接分裂が観察された. 千葉県土気と京都黒谷産の個体は正常な減数分裂をしない. 第1分裂中期での染色体数は一定せず450~500の問である. 染色体の大きさはさまざまで, 多価染色体および1価染色体と考えられるものがかなり現われる. 恐らくn=480の個体に由来する Cyto-races の1つであろう. 一方千葉県東金産の個体は土気や京都産の個体と同様に減数分裂が異常であるが, 2, 3の胞子母細胞の第一分裂中期で約700の染色体が数えられた. この内, 約400が2価染色体で残りが1価染色体と推定されるので, 実際に体細胞の染色体数を数えることはできなかったが,多分2n=ca. 1100ぐらいであろう. コハナヤスリ (O. thermale var. nipponicum) でも3っの Cyto-racesが知られた. 1っは東京小金井産のものでn=240である. これは Verma (1957) が報告したものである.一方成田のd群落の個体はすべて2n=480で胞子形成過程は正常であり, 成田のe群落と京都黒谷産の個体は土気や京都産のコヒロハハナヤスリと同様正常な減数分裂はせず2分子や3分子の形成がみられた.後者では染色体数は正確には数えられなかったが, ある母細胞では約460であった. いくつかの多価染色体と思われるものがあり, 恐らくn=480の個体に由来するものであろう.形態学的にみると, コヒロハハナヤスリは特に多型で, 葉身が丸く葉柄が非常に短かい個体, 葉身は細長く葉柄が顕著な個体, および両者の問のさまざまな中間型とがある. しかしこの多型現象と染色体数との間には何らの関連も見出しえなかった.西田 (1959) はハナヤスリ属を2っの亜属, Vulgata と Aitchisonii に分けた. 染色体数をみると後者にはn=240以上の数を持つものが現在のところ知られていない点は注目に値する. Ninan (1958) らはハナヤスリ目の基本染色体数を15だと考えているが筆者達もこの考えに賛成である.ハナヤリ目は非常に特殊化された植物の一群で系統的には現生の他のシダ植物からかなり離れたものと考える.
- 著者
- 石川 徳久 杉谷 広元 李 明杰 松下 寛
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 日本化学会誌 (ISSN:03694577)
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, no.6, pp.399-404, 0001-01-01 (Released:2001-08-31)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1 1
試料溶液のイオン強度調整を必要としない標準液添加法と沈殿反応を利用した陰イオン(または陽イオン)の間接電位差定量を提示する。濃度cxの測定陰イオンBを含む体積Vの試料溶液に,既知濃度crの沈殿剤陽イオンAを含む溶液(反応液)の一定量(Vr)を添加する。このとき,生成した沈殿物の組成をAmBnとすれば,cr≥mcxV/(nVr)の条件を満たす必要がある。この溶液に,Aイオン選択性電極-比較電極対を浸漬したのち,既知濃度cs1のAを含む溶液(標準液1)で滴定し,標準液1の添加体積(vs1)に対する起電力(E1)を測定する(標準液1の最終添加体積をvs10とする)。引き続いて,同一試料溶液をVおよび反応液をVr添加したのち,既知濃度cs2(>cs1)のAを含み,標準液1と同じイオン強度をもつ溶液(標準液2)で再び滴定し,標準液2の添加体積(vs2)に対する起電力(E2)を測定する。この二つの滴定曲線から,vs2=2vs1-vs10を満足するvs1, vs2に対応したE1,E2を読み取れば,Bの濃度cxに関して次式が成立する。y=(ncs1/ncrVr-mcxV)x+gここで,y=10ΔE/S,x=vs1{(cs2/cs1)-y},ΔE=E2-E1, SはAイオン選択性電極の応答勾配,gは定数である。y対xの直線プロットの勾配からcxが決定される。沈殿剤として銀イオンを,指示電極として銀イオン選択性電極を用いて,種々のイオン強度の試料溶液中の1×10-2-5×10-4mol dm-3の濃度範囲のヘキサシアノ鉄(II)酸イオンを,誤差約±1%以下,相対標準偏差1%以下で定量した。
1 0 0 0 OA 特別講演3 「活性酸素は諸刃の剣」
- 著者
- 近藤 元治
- 出版者
- 日本炎症・再生医学会
- 雑誌
- 炎症 (ISSN:03894290)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.4, pp.354-355, 2000-07-10 (Released:2010-04-12)
1 0 0 0 OA 名古屋大学豊田講堂改修工事
- 著者
- 森 堅太郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学 (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.12, pp.12_T1-12_T2, 2010 (Released:2012-03-27)
1 0 0 0 OA 人間関係における問題解決
- 著者
- 北川 公路
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会宮城県理学療法士会
- 雑誌
- 理学療法の歩み (ISSN:09172688)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.6-10, 2009 (Released:2009-02-17)
- 参考文献数
- 3
本稿は平成20年7月に開催された宮城県理学療法士会主催の教育部研修会においておこなった講演会に加筆修正を加えたものである。心理学の行動分析学の立場から演題である「人間関係」について講演を行った。実際に仕事をしていくなかで人間関係における問題は数多く存在する。人間関係などで問題が生じたとき,多くの場合,自分自身や他者に問題の原因を求めようとする。そして原因を自分ではなく他者に帰属させる傾向がある。このようなことをしていても問題は解決しない。具体的に問題解決の方法を探すことが必要である。
1 0 0 0 OA 行動分析学に基づく臨床教育
- 著者
- 山﨑 裕司
- 出版者
- 日本理学療法士学会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.8, pp.738-739, 2015 (Released:2016-01-15)
- 参考文献数
- 1
1 0 0 0 OA 臨床実習学生に質問行動の増加を促したことが能動的な行動変容へ与えた影響について
- 著者
- 由谷 仁 梶原 秀明 宮原 正文 中根 博
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.38 Suppl. No.2 (第46回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.GaOI2055, 2011 (Released:2011-05-26)
【目的】 情意領域の低下、特に「自発性のなさ」が問題となる臨床実習学生(以下、学生とする)の指導は、臨床実習指導者(以下、指導者とする)の心的負担を著しく増加させる。そこで、臨床実習を円滑に遂行するため、指導者にとって負担の少ない指導方法を確立させることは急務であるが、現状は各病院や各指導者の裁量次第で明確な方法は示されていない。当院では臨床実習の位置付けとして、平成21年より「受動的教育」から「能動的教育」へ行動変容させることを最重要課題とし、続いて国家試験の知識を習得することを目的として掲げている。辻下は、行動分析学的アプローチは有効な行動変容法であると述べており、学生に行動変容を促しつつ指導者に負担の少ない指導方法を模索してきた。 今回は、情意領域に問題があると指摘された学生に対し、行動分析学的アプローチを用いた「質問行動の増加」という介入を行い、その効果をシングルケースデザインにより検討し報告する。【方法】 対象は当院での臨床実習にて情意領域の低下が指摘された理学療法士学科最終学年、30代、男性、1名。方法は畑山らの報告を参考にし、実習期間をベースライン期(2週間)、介入期(4週間)、非介入期(2週間)に分け、まずベースライン期終了時にターゲット行動の明確化を図るため中間評価を行った。その際、特に低下がみられ問題とした「自発性のなさ」に対し、「質問行動の増加」をターゲット行動と設定した。 介入期は「質問行動の増加」のため、学生に自ら質問を行い、その内容を質問行動記録表に記載するよう指導した。また、質問のルールとして自分の考えを可能な限り述べることとした。先行刺激は、質問数に応じて臨床実習総合評価の情意領域に関して15回/週以上で「可」、30回/週以上で「良」にすること、質問に関して否定的なコメントはしないこと、必要以上に課題を出さないことを約束した。後続刺激は、質問行動が見られた直後に指導者側から賞賛することを徹底し、週末に学生と1週間分の質問内容を確認した。 非介入期では質問行動記録表への記載は継続させたが、後続刺激は与えなかった。調査内容は質問行動数(自分の考えを述べた質問数/全体の質問数)、臨床実習評価(当院独自、各項目4点満点で良好4点、普通3点、やや劣る2点、劣る1点)とした。なおベースライン期の質問行動数はデイリーノートより作成した。加えて最終週は3日間のみのデータ収集となった。【説明と同意】 学生には本報告の主旨、本データを報告以外に使用しないこと、未同意でも不利益を受けないことなどを実習終了時に説明し、紙面にて同意を得た。【結果】 1週間の平均質問行動数はベースライン期で0/0.5(0%)回、介入期で16.3/32.3(50.4%)回、非介入期で16.3/31.3(52.0%)回であり、介入期で増えた回数を非介入期でも維持できた。臨床実習評価による全領域の平均は、2週後2.6点、4週後2.4点、6週後2.5点、最終2.5点と若干の変化であった。そのうち、情意領域だけの平均は、2週後2.5点、4週後2.6点、6週後2.7点、最終2.8点と改善傾向はみられたが大幅な変化ではなかった。【考察】 ベースライン期ではほとんどなかった質問行動自体は、介入期より増加し非介入期でも継続してみられたため、質問行動自体の定着は図れたと考えられる。しかし、臨床実習評価の平均点数に大幅な変化がなかったことを考慮すると、当院で目的とした能動的な行動変容までは至らなかったと考えられる。これは質問行動数の結果より、先行刺激で与えた30回/週以上で「良」との質問数を若干超えた値が多く、質問行動数自体が目的となっていたためと考えた。臨床実習教育の手引き-第5版-によれば内発的動機づけには知的好奇心が必要で、その知的好奇心は環境に変化を起こせたという有能感あるいは達成感が動機づけに重要となると述べられている。今回、知的好奇心を促せなかったことが、能動的な行動変容まで至らなかった原因ではないかと思われた。今後は、知的好奇心を促すために、人の役に立つという視点で指導方法を模索し、能動的な行動変容を促す方法の確立に取り組んでゆきたい。【理学療法学研究としての意義】 臨床実習教育において自発性のなさが問題となる学生に対し、受動的から能動的への行動変容を起こさせる簡便かつ、有効な指導方法が確立出来れば大変有意義なことである。
1 0 0 0 OA 青化製錬の化学 (4)
- 著者
- 吾妻 潔
- 出版者
- 一般社団法人 資源・素材学会
- 雑誌
- 日本鑛業會誌 (ISSN:03694194)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.763, pp.30-35, 1952-01-25 (Released:2011-07-13)
1 0 0 0 OA 活性炭のできるまで
- 著者
- 江口 良友
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.7, pp.682-685, 1971-07-15 (Released:2011-11-04)
1 0 0 0 OA 抗線維化薬ピルフェニドン(ピレスパ®錠200 mg)の薬理学的特徴と臨床効果
- 著者
- 戸倉 猛 奥 久司 塚本 有記
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.134, no.2, pp.97-104, 2009 (Released:2009-08-12)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 2 3
ピルフェニドンは新規の抗線維化薬である.動物実験では各種線維化疾患モデルで各臓器における明らかな線維化の減少と機能低下の抑制が認められている.ブレオマイシン誘発肺線維症モデルでは,ステロイドであるプレドニゾロンとの比較により,プレドニゾロンは抗炎症作用のみを示したのに対し,本薬は抗炎症作用と抗線維化作用の両方を示した.種々の検討からピルフェニドンは,炎症性サイトカイン(TNF-α,IL-1,IL-6等)の産生抑制と抗炎症性サイトカイン(IL-10)の産生亢進を示し,Th1/2バランスの修正につながるIFN-γの低下の抑制,線維化形成に関与する増殖因子(TGF-β1,b-FGF,PDGF)の産生抑制を示すなど,各種サイトカインおよび増殖因子に対する産生調節作用を有することが示されている.また,線維芽細胞増殖抑制作用やコラーゲン産生抑制作用も有しており,これらの複合的な作用に基づき抗線維化作用を示すと考えられる.本邦において実施された特発性肺線維症(IPF:Idiopathic Pulmonary Fibrosis)患者を対象とした第III相試験の結果,ピルフェニドン投与によりプラセボ群に比べ有意に肺機能検査VC(肺活量)値の悪化を抑制し無増悪生存期間の延長に寄与していたことから,特発性肺線維症の進行を抑制することが示された.一方,本薬投与による特徴的な副作用は,光線過敏症,胃腸障害(食欲不振,食欲減退),γ-GTP上昇等であった.ピルフェニドンが特発性肺線維症患者に対して一定の効果を示したことにより,副作用の発現はプラセボ群に比べ高かったものの,減量・休薬等で副作用をコントロールし治療を継続することで,病態の進行を抑制し生命予後の改善にも寄与することが期待される.
1 0 0 0 OA 「川越まちづくり」の物語描写研究-町並み保存に向けたまちづくり実践とその解釈-
- 著者
- 澤崎 貴則 藤井 聡 羽鳥 剛史 長谷川 大貴
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集F5(土木技術者実践) (ISSN:21856613)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.1-15, 2012 (Released:2012-05-18)
- 参考文献数
- 33
近年,中心市街地の活力低下等が問題となっている中で,町の活気を取り戻すというような事例も見られる.こうした成功事例に着目し,如何にしてその成功が導かれたのかについての一般的知見を得ることは,今後のまちづくりにおいて有益であると考えられる.その知見を得る方法として,これまでは定量的な分析を行う自然科学的な手法が多く用いられてきたが,まちづくりに関わった人々の思いを理解するためには,“物語”を解釈するという解釈学的な方法論を用いることが求められる.本研究では,まちづくりの成功事例として挙げられる埼玉県川越市を対象として,まちづくりの様々な関係者にインタビューを行う.そして,それらを通じて“物語”を構成し,その解釈によって「川越まちづくり」が成功に至った要因を論ずる.
1 0 0 0 OA 本邦宗教分布の研究(神道各派) 附 宗教傳播の地理的制約について
- 著者
- 村上 英雄
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.4, pp.317-341, 1935-04-01 (Released:2008-12-24)
1 0 0 0 OA 味噌嗜好とストレス受容度との関連性について
- 著者
- 河野 昭子 栗山 寛子
- 出版者
- 日本官能評価学会
- 雑誌
- 日本官能評価学会誌 (ISSN:1342906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1-2, pp.30-33, 2008-04-15 (Released:2012-12-28)
- 参考文献数
- 9
We found a significant correlation between people's preference for Japanese miso and their susceptibility to mental and/or physical stress. We selected two kinds of Japanese miso, red miso and white miso. A sensory evaluation based on ANOVA revealed that miso preference significantly correlates to a mental feeling of depression (p=0.026). The feeling of depression among the examinees with a preference for red miso was lower level than that among those who had a preference for white miso. Furthermore, we attempted to classify the degree of depression into 3 levels in order to make a crosstable. Another evaluation (chi-square) on the table showed almost the same results (p=0.041). The results seem to be due to the characteristics of the ingredients of red miso.
- 著者
- Hiroshi Kajihara Mariko Takibata Mark J. Grygier
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- Species Diversity (ISSN:13421670)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.105-110, 2016-11-25 (Released:2017-02-03)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
The freshwater heteronemertean Apatronemertes albimaculosa Wilfert and Gibson, 1974 has previously been reported from Germany, Austria, and the USA. All these records were from aquarium tanks with commercially distributed tropical and/or subtropical water plants; by hiding among their roots, the worms are thought to have been introduced from an unidentified place of origin. We report the occurrence of A. albimaculosa for the first time from Japan, based on specimens found in private home aquaria for guppy breeding, with a total of 18 species of water plants grown for different periods and lengths of time but not all at the same time. Histological examination confirmed the presence of diagnostic features of this species, including a complex precerebral vascular system and hermaphroditism. The partial sequence of the mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I gene (607 bp) of the Japanese material is identical with that of a heteronemertean specimen from a freshwater tank in Madrid, Spain, which had been deposited in the public databases but left unidentified as to its species, genus, or family. Apatronemertes albimaculosa appears unlikely to be able to survive below 10°C for more than about a week, which suggests that its native locality is in the tropics or subtropics, not the temperate zone. The barcoding sequence herein determined will serve in future studies to help locate the natural place of origin.
1 0 0 0 OA 顔文字付きメールが受信者の感情緩和に及ぼす影響
- 著者
- 荒川 歩 竹原 卓真 鈴木 直人
- 出版者
- 日本感情心理学会
- 雑誌
- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.22-29, 2006-03-30 (Released:2010-01-15)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2 1
This research compared the effects of messages with and without emoticons from a familiar friend on the reduction of intensity of emotions, the relationship between changes in emotions, and the impact of emoticons on text messages. In particular, the effect of messages with one of five emoticons { (^_^) (;_;) (>_<) (^_^;) m(_ _)m } and messages with no emoticons, on four emotional scripts, happy, sad, angry, and anxious, were compared. Using their own cell phones, university students (n=33) participated in this study by reporting emotional intensity when they were in each script. They again reported emotional intensity after receiving a text message with emoticons from a familiar friend. Results indicated that (1) messages with emoticons reduced the intensity of the receiver's negative emotions in comparison to messages without emoticons; and (2) when receivers were feeling angry or happy, a significant relationship was found between the impact of emoticons and the reduction in the intensity of emotions, expect when receivers were feeling anxious or sad. Results suggest that appropriate selection from emoticons reduces the intensity of the receiver's negative emotions.
1 0 0 0 OA 気仙沼市舞根地区の津波浸水域におけるトウホクサンショウウオの卵嚢分布の経年変化
- 著者
- 板川 暢 樋口 陽平 一ノ瀬 友博 横山 勝英
- 出版者
- 社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究(オンライン論文集) (ISSN:1883261X)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.37-46, 2017-02-09 (Released:2017-02-24)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 1
This survey monitored the quantity and distribution of egg clutches of Tohoku salamander (Hynobius lichenatus) in the tsunami inundated lowland area from the period 2012 to 2015, looking at the case of Moune district, Kesennuma city, Miyagi prefecture, Japan. After the 2011 Tohoku Earthquake, lowland area almost changed into wetlands by erosion and land subsidence, and seawater ran into a part of the lowland. Lots of egg clutches were found in the whole area in 2012. However several egg clutches deposited in brackish-water were dead. After 2013, the number of egg clutches declined, and the distribution moved inland. The number of egg clutches roughly increased in 2015, indicating the meta-population of Tohoku salamander’s resilience against temporary disturbance caused by the tsunami. Models of relations analyzed between the numbers of egg clutches in each year showed larger population had higher resilience and the numbers of dead egg clutches had negative correlation to the total numbers of egg clutches in late years. Results indicated that the environmental changes after the tsunami had more severe impacts on the population’s survival. However the population of Tohoku salamander had resilience under the natural state. This resilience may be weakened by man-made induced environmental changes and habitat loss from the tsunami recovery and reconstruction works. Hence, the need for conservation and monitoring was suggested.
1 0 0 0 OA リードユーザーが生み出す製品コンセプトは本当に優れているのか?
- 著者
- 秋元 創太 三富 悠紀 井上 剛
- 出版者
- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター
- 雑誌
- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.23-34, 2017-02-17 (Released:2017-02-25)
- 参考文献数
- 13
ユーザーイノベーションに関連する研究は、非常に多岐な分野へと広がっている。それに伴って、ユーザーイノベーションを起こせるような先駆的な顧客、所謂リードユーザーの特定が着目されている。本稿では、①はじめてリードユーザーを特定し、②特定したリードユーザーが考案した製品コンセプトを評価するプロセスを構築し、第三者から高い評価を得ることの二つの貢献をした Urban and von Hippel (1988) の解説と評論を試みる。その上で後続の研究を確認し、リードユーザーによって生み出された製品コンセプトが本当に優れているのかについて疑問を提示していく。