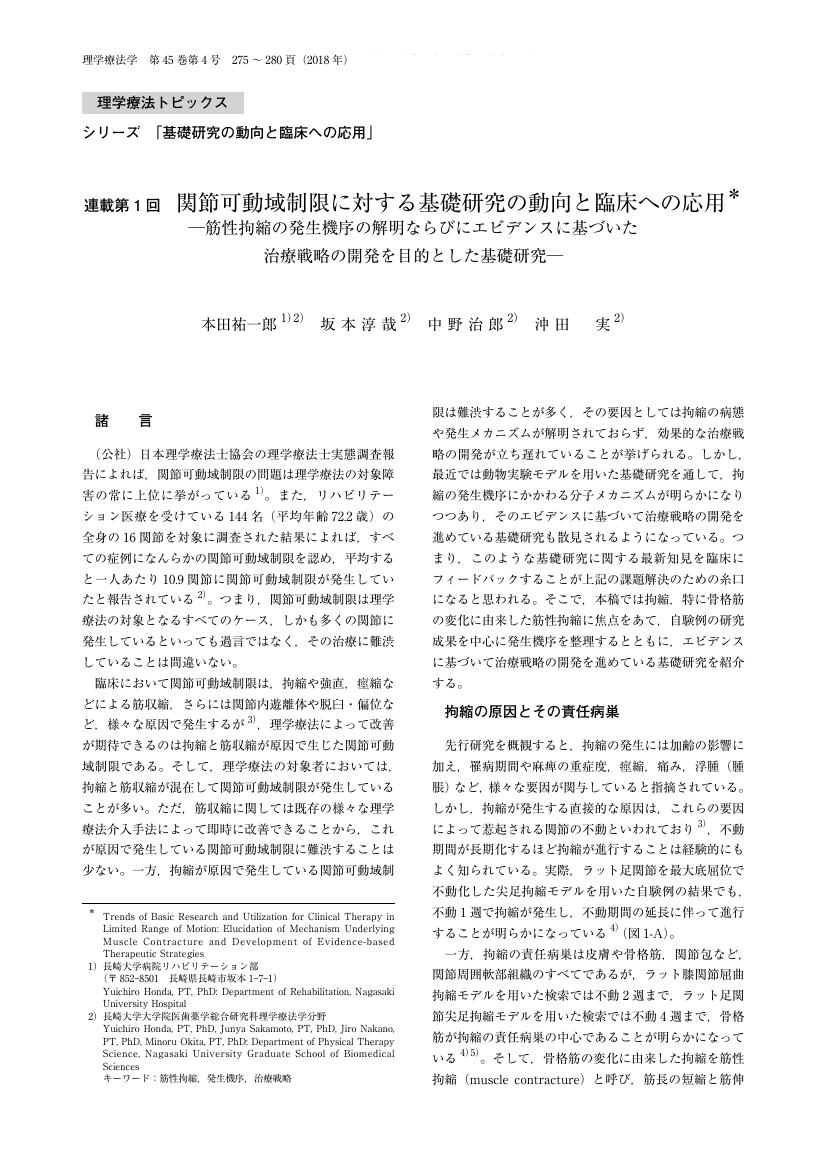- 著者
- 本田 祐一郎 坂本 淳哉 中野 治郎 沖田 実
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.275-280, 2018 (Released:2018-08-20)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 3
31 0 0 0 OA 日本近海の海水温変動と北半球気候変動との共時性
- 著者
- 小泉 格 坂本 竜彦
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, no.3, pp.489-509, 2010-06-25 (Released:2010-08-30)
- 参考文献数
- 113
- 被引用文献数
- 7 8
Annual sea-surface temperatures (SSTs) (°C) were derived from a regression analysis between the ratio of warm- and cold-water diatoms (Td' ratio) in 123 surface sediment samples around the Japanese Islands and measured mean annual SSTs (°C) at the core sites. The cross spectra between the atmospheric residual 14C (‰), and annual SSTs (°C) of cores DGC-6 (Japan Sea) and MD01-2421 (off Kashima), respectively, consist of five dominant periods: 6000, 2400, 1600, 950, and 700 years. The amplitude of fluctuations of annual SSTs (°C) in the millennial time scale during the Holocene after the Younger Dryas is within 6-10°C. Periodic variations of annual SSTs (°C) can be correlated within error to abrupt climatic events reported from different paleoclimatic proxy records in many regions of the Northern Hemisphere. The cooling time of annual SSTs (°C) also corresponds to the triple events of high 14C values in the atmospheric residual 14C records, as well as the Bond events in the North Atlantic.
31 0 0 0 OA 虐待ケースを100件担当するということ : 1児童福祉司からの報告
- 著者
- 坂本 理
- 出版者
- 日本ソーシャルワーク学会
- 雑誌
- ソーシャルワーク学会誌 (ISSN:18843654)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.51-56, 2012-12-31 (Released:2017-10-23)
日本の児童相談所の児童福祉司(SW)の人員配置は,欧米諸国や韓国などと比べ,非常に劣悪なものである.欧米や韓国では虐待についてはSW一人当たり20件前後のケースを担当するが,日本では虐待だけでもその数倍,他の相談と合わせれば,100件以上ものケースを担当することは珍しいことではない.では,児相のSWの1人当たりの担当ケース数が多すぎると,実際どのようなことが現場で起きるのであろうか.筆者はある都市部の児相において,虐待専属のSWとして100ケース以上を担当した経験をもつ.その際,どういった状態に陥ったのか,これまでどこでも報告していない.今回,100件もの虐待ケースを担当した場合,(1)何人の子どもや保護者と実際に会って面接できたのか,(2)それはどの程度の回数であったか,の2点を中心に報告し,虐待を受けた子どもたちに対して,あってはならないレベルの支援体制しか取れていない,この国の現状の一端を報告したい.
31 0 0 0 OA 樹木年輪と歴史資料からみた10世紀の十和田カルデラと白頭山の巨大噴火の絶対年代
- 著者
- 箱崎 真隆 三宅 芙沙 佐野 雅規 木村 勝彦 中村 俊夫 奥野 充 坂本 稔 中塚 武
- 出版者
- 日本地球惑星科学連合
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2019年大会
- 巻号頁・発行日
- 2019-03-14
十和田カルデラ(青森県/秋田県)と白頭山(中国/北朝鮮)は、10世紀に巨大噴火を起こした。その痕跡はTo-aテフラ、B-Tmテフラとして、北日本の地層に明瞭に残されている。この2つの噴火は、それぞれ過去2000年間で日本最大級、世界最大級のものと推定されている(早川・小山1998)。しかしながら、この2つの噴火に関する直接的な文書記録は、周辺国のいずれからも見つかっていない。そのため、その年代は長らく未確定であった。また、年代が未確定であるために、人間社会や地球環境への影響評価も進んでいなかった。近年、白頭山の10世紀噴火の年代は、日本で発見された西暦775年の炭素14濃度急増イベント(Miyake et al. 2012)を年代指標とする「14C-spike matching」と、日本で実用化された「酸素同位体比年輪年代法」により、西暦946年と確定した(Oppenheimer et al. 2017, Hakozaki et al. 2018, 木村ほか 2017)。この年代は、早川・小山(1998)が日本列島と朝鮮半島のごく限られた古文書(「興福寺年代記」や「高麗史」)から読み取った「遠方で起きた大きな噴火」を示唆する記述と一致した。一方、B-Tmの年代が確定したことにより、十和田カルデラ10世紀噴火の年代に疑義が生じた。十和田カルデラ10世紀噴火は、「扶桑略記」における東北地方の噴火を示唆する記述や、ラハールに埋没する建築遺物の年輪年代をもとに西暦915年と推定されてきた。この915年を基準にTo-aとB-Tmの間に挟まる年縞堆積物をカウントし、上手ほか(2010)は白頭山の噴火年代を929年と推定していた。しかし、先のとおりB-Tmの絶対年代は946年であったため、上手ほかの推定から17年のズレがあることが明らかとなった。つまり、十和田カルデラ10世紀噴火は西暦946年から14年を差し引いて西暦932年である可能性が生じた。もし、これが正しいとすれば、扶桑略記の西暦915年の記述は、十和田カルデラ以外の火山で起きた噴火を示唆している可能性がある。最近、宮城県多賀城跡の柵木に、酸素同位体比年輪年代法が適用され、西暦917年の年輪が認められた(斎藤ほか 2018)。この柵は、考古学的調査ではTo-aテフラ(915年)の降灰前に築造されたと考えられてきた(宮城県多賀城跡調査研究所 2018)。その構造材に西暦917年の年輪が認められたことは、To-aテフラの年代と大きく矛盾する。さらにその構造材には樹皮も辺材も残存せず、伐採年は917年よりも後の年代であることが明らかである。本発表では、「14C-spike matching」と「酸素同位体比年輪年代法」という2つの新しい年輪年代法によって、白頭山や多賀城跡の木材の年代がどのようにして決定したのか、十和田カルデラ10世紀噴火の絶対年代の確定に必要な調査とは何かについて示す。
30 0 0 0 OA NPO への参加はなぜ忌避されるのか ―コンジョイント実験による忌避要因の解明
- 著者
- 坂本 治也 秦 正樹 梶原 晶
- 出版者
- 日本政治学会
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.2_303-2_327, 2020 (Released:2021-12-15)
- 参考文献数
- 38
1990年代末以降、日本では特定非営利活動法人 (NPO法人) や一般社団法人などの新たに創設された法人格を有する (広義の) NPOが多数誕生した。組織レベルでみた場合、NPOの活動は明らかに活性化している。にもかかわらず、一般の人々のNPOへの参加は依然としてまったく広まっていない。 なぜ多くの日本人はNPOへの参加を今なお忌避しているのであろうか。どのような要因が参加忌避を引き起こす原因となっているのであろうか。どうすればNPOへの参加をより増やしていくことができるのだろうか。 これらの点を探索的に解明するために、本稿では筆者らが独自に実施したオンライン・サーベイのデータを用いて、コンジョイント実験 (conjoint experiment) を通じてNPOへの参加の規定要因の解明を試みた。 分析の結果、デモなどの政府への抗議活動を行うこと、多額の寄付を集めること、自民党寄りないし立憲民主党寄りの組織であることは、参加忌避に大きな影響を与える要因であることが明らかとなった。つまり、NPOの 「政治性」 やNPOの 「金銭重視」 姿勢が参加忌避をもたらす主要な原因になっていることが本稿の分析から示唆される。
30 0 0 0 OA サーベイ実験の再現可能性と外的妥当性 : オンラインフィールド実験による追検証
- 著者
- 善教 将大 坂本 治也
- 出版者
- 関西大学法学研究所
- 雑誌
- ノモス = Nomos (ISSN:09172599)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.1-15, 2020-06-30
30 0 0 0 IR 鳥取砂丘におけるハンミョウ類の分布・生活史と1種の絶滅
- 著者
- 鶴崎 展巨 川上 大地 太田 嵩士 藤崎 謙人 坂本 千紘
- 出版者
- 鳥取県生物学会
- 雑誌
- 山陰自然史研究 (ISSN:13492535)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.33-44, 2015-03-31
2013年から2014年にかけて鳥取砂丘の全域でハンミョウ類の生息調査をおこない,カワラハンミョウの幼虫の巣穴が砂丘のほぼ全域にみられるのに対し,エリザハンミョウのそれはオアシス周辺の湿り気のある砂泥地表に限定されていることを確認した。1990年代までオアシス周辺で生息が確認されていたハラビロハンミョウは確認できず,鳥取砂丘からは絶滅したと判断される。当地は環境省国立公園の特別保護地区であり,採集は厳密に規制されているのでこの絶滅は1994年からはじまった除草に影響された可能性が強く疑われる。本種の鳥取砂丘内での最終確認は1997年である。カワラハンミョウとエリザハンミョウについてはコドラート調査により,カワラハンミョウは基本的に年1化で1 ~ 2齢の幼虫で越冬,エリザハンミョウも年1化だがすべての齢で越冬していると推定された。巣穴は1年をとおして集中分布でとくに若齢幼虫の多い秋季にはその傾向がめだった。We surveyed distributions and life histories of cicindelid beetles in Tottori Sand Dunes, Tottori Prefecture, Honshu, Japan. Larval nests of Chaetodera laetescripta were widely found in the bare arenaceous ground around vegetation of sandy shore plants in the dunes, while those of Cilindela elisae were limited to the bare silt-mingling arenaceous ground along the stream flowing into the pool called "Oasis". No adults and nests of Calomera angulata (Fabricius, 1798) that had been found up to 1990s around "Oasis"were found. Absence of the records of Calomera angulata from Tottori Sand Dunes after the last observation in 1997 strongly suggests extinction of the species in the area. It is highly suggested that weeding activities that started in 1994 in Tottori Sand Dunes influenced negatively for the occurrence of the species, because Tottori Sand Dunes has been designated as a special protection area of the national parks by the Japan Ministry of Environment and collecting animals and plants and other activities that may influence conservation of the environment are strictly regulated. Chaetodera laetescripta and Cilindela elisae were univoltine and adults appeared from July. Analyses of dispersion pattern of larval nests for the two species showed contagious distribution.
29 0 0 0 OA 児童・生徒(6~15才)の化学物質過敏症様症状に関するアンケート再調査
- 著者
- 永吉 雅人 杉田 収 橋本 明浩 小林 恵子 平澤 則子 飯吉 令枝 曽田 耕一 室岡 耕次 坂本 ちか子
- 出版者
- 一般社団法人 室内環境学会
- 雑誌
- 室内環境 (ISSN:18820395)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.97-103, 2013 (Released:2013-11-25)
- 参考文献数
- 7
上越市立の全小学校(新潟県)児童を対象に,化学物質過敏症(multiple chemical sensitivity: MCS)様症状に関するアンケート調査が2005年7月に実施されている。今回,その調査から5年経過した2010年7月,実態の時間的推移を把握するため,対象を市立の全小中学校の児童・生徒に拡げてアンケートの再調査を実施した。また今回新たに就寝時刻についても合わせて調査した。アンケートの有効回答数は14,024名分(有効回答率84.0%)であった。調査の結果,14,024名の回答児童・生徒中MCS様症状を示す児童・生徒は1,734名(12.4%)であった。今回の調査で主に,次の3つのことが明らかとなった。1. 小学1年生から中学3年生へ学年が進むに伴い,MCS様症状を示す児童・生徒の割合が増加傾向にあった。2. 小学生全体のMCS様症状を示す児童の割合は,今回調査した小学生の方が5年前に比べて大きくなっていた。3. 小学3年生から中学3年生までのMCS様症状を示す児童・生徒はMCS様症状を示していない児童・生徒より就寝時刻が遅かったことが明らかとなった。
29 0 0 0 OA 『分析手帖』と『マルクス=レーニン主義手帖』 1960 年代フランスにおける学知、革命、文学
- 著者
- 坂本 尚志
- 出版者
- 日本フランス語フランス文学会
- 雑誌
- フランス語フランス文学研究 (ISSN:04254929)
- 巻号頁・発行日
- vol.115, pp.255-269, 2019 (Released:2019-10-25)
28 0 0 0 OA 桜花譜
- 著者
- 坂本浩然<坂本浩雪>//筆
- 出版者
- 写
28 0 0 0 鎌倉時代に入ると荘園の増加がとまる
- 著者
- 坂本 賞三
- 出版者
- 広島史学研究会
- 雑誌
- 史学研究 (ISSN:03869342)
- 巻号頁・発行日
- no.253, pp.64-75, 2006-08
27 0 0 0 OA 大腿骨近位端骨折術後運動器リハビリテーションの1日施行単位数の無作為化比較試験
- 著者
- 東 良和 土井 一輝 藤井 裕之 坂本 相哲
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.4-5, pp.277-282, 2014 (Released:2014-05-10)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2 1
目的:高齢者大腿骨近位部骨折の術後リハビリテーション(以下,リハ)施行時間(単位数)とADL機能,医療費について比較検討し,適正リハ時間について検証する.方法:2010 年6 月1 日から2013 年6 月27 日の間に当院で手術,術後リハを施行した222 名に対してCONSORT 2010ガイドラインに基づいた無作為化比較試験(RCT)を6 単位(120 分)と1日2 単位(40 分)施行群間で行い,術後12 週までのADL機能,歩行と医療費について比較検討した.結果:最終的にRCTが完遂できた受傷前独歩患者は,6 単位群29 症例,2 単位群29 症例であった.FIM, Barthel Index,EQ-5D,歩行に関しては両群間で統計学的有意差はなかったが,医療費に関しては,6 単位群で約20 万円高額となった.結論:早期リハを行うことにより,術後2 単位リハで十分な機能回復が獲得でき,医療費の有効利用ができた.
27 0 0 0 OA 踊り念仏の種々相(1) : 空也及び空也系聖について
- 著者
- 坂本 要
- 出版者
- 筑波学院大学
- 雑誌
- 筑波学院大学紀要 (ISSN:18808859)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.69-79, 2015
26 0 0 0 OA [調査研究活動報告] 京都大学所蔵「マリア十五玄義図」の調査
- 著者
- 神庭 信幸 小島 道裕 横島 文夫 坂本 満
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, pp.175-210, 1998-03-31
26 0 0 0 OA 子ども虐待におけるAI 実装:pLSA とベイジアンネットワークを用いた再発事例の検討
- 著者
- 髙岡 昂太 坂本 次郎 北條 大樹 橋本 笑穂 山本 恒雄 北村 光司 櫻井 瑛一 西田 佳史 本村 陽一 K. Takaoka J. Sakamoto D. Hojo E. Hashimoto Yamamoto K. Kitamura E. Sakurai Y. Nishida Y. Motomura
- 雑誌
- SIG-SAI = SIG-SAI
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.5, pp.1-7, 2018-11-22
As the number of reported child abuse cases is increasing, the workload of child welfare social workers is highly escalated. This study aims to find the characteristics of recurrent cases in order to support the social workers. We collected data around the child abuse and neglect from a prefecture database and analyzed it with Probabilistic Latent Semantic Analysis and Bayesian Network modeling. As the result, pLSA showed the four different clusters and Bayesian Network revealed a graphical model about the features of recurrence cases. The Interpretable modeling can be effectively deployed in those child welfare agencies to save children who are suffering from child abuse cases.
25 0 0 0 OA 遺伝子組換え大豆のF344ラットによる104週間摂取試験
- 著者
- 坂本 義光 多田 幸恵 福森 信隆 田山 邦昭 安藤 弘 高橋 博 久保 喜一 長澤 明道 矢野 範男 湯澤 勝廣 小縣 昭夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.4, pp.272-282, 2008-08-30 (Released:2008-09-11)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 12 18
除草剤グリホサート耐性の性質を有する遺伝子組換え大豆(GM大豆)の安全性を確かめる目的で,ラットを用い,GM大豆および非遺伝子組換え大豆(Non-GM大豆)を30%の割合で添加した飼料による104週間摂取試験を行った.また大豆に特異的な作用を観察する目的で,一般飼料(CE-2)を大豆と同様の期間摂取させた.GMおよびNon-GM大豆群とCE-2群間には,検査項目の一部に差が見られたが,GM大豆群の体重,摂餌量,血液学的および血清生化学検査結果,臓器重量には,いずれもNon-GM大豆群と比べて顕著な差は認められなかった.組織学的にもGM大豆に特徴的な非腫瘍性病変や腫瘍性病変の発現や自然発生病変の発現率の増加は認められなかった.GM大豆の性状はNon-GM大豆と顕著な差はなく,飼料に30%まで添加し,104週間摂取させても障害作用はないものと考えられた.
- 著者
- 坂本 佳子
- 出版者
- 日本応用動物昆虫学会
- 雑誌
- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.71-85, 2021-05-25 (Released:2021-06-10)
- 参考文献数
- 171
The ectoparasitic mite, Varroa destructor Anderson and Trueman(Mesostigmata: Varroidae), causes tremendous damage to the beekeeping and pollination industries. These industries rely upon the naïve European honey bee, Apis mellifera L.(Hymenoptera: Apidae), to which the mite has spread from its native host, the Asian honey bee, Apis cerana Fabricius. Researchers around the globe have been building our understanding of the ecology of V. destructor. However, the research has not been regularly reviewed in Japanese, and researchers and beekeepers in Japan have not had access to the most update reports over the past two decades. Here, I review recent developments in the study of the biology and ecology of V. destructor and the resistance of honey bees to the mite in Japanese.
24 0 0 0 OA 音楽幻聴 (楽音性耳鳴) に関する臨床的検討
- 著者
- 御子柴 卓弥 新田 清一 中山 梨絵 鈴木 大介 坂本 耕二 島貫 茉莉江 岡田 峻史 藤田 航 鈴木 法臣 大石 直樹 小川 郁
- 出版者
- 一般社団法人 日本聴覚医学会
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.4, pp.315-325, 2019-08-30 (Released:2019-09-12)
- 参考文献数
- 18
要旨: 音楽幻聴は, 外部からの音刺激がないのに歌や旋律が自然に聞こえる現象であり, 耳鳴患者の中にも稀に存在する。2011年1月から2018年10月までに当科を受診した耳鳴患者のうち, 音楽幻聴を訴えた23例の臨床像を検討した。このうち11例に対し耳鳴について詳細に説明した上で補聴器による音響療法を行い, 治療効果を検討した。音楽幻聴症例は, 高齢者・女性に多く1例を除く全例で感音難聴を認めた。全例で病識が保たれており, 精神神経科疾患の合併を認めなかった。治療後に Tinnitus Handicap Inventory の合計値, 耳鳴の自覚的大きさ・苦痛の Visual Analogue Scale は有意に改善した。本検討から, 精神神経科疾患の合併がなく難聴が主病因の音楽幻聴に対し耳鳴の説明と補聴器による音響療法が有効な治療である可能性が示唆され, 耳鼻咽喉科医が中心となり診療に携わることが望ましいと考えられた。
24 0 0 0 IR 端島(軍艦島)における聞き取り調査及び現地調査
- 著者
- 後藤 惠之輔 森 俊雄 坂本 道徳 小島 隆行
- 出版者
- 長崎大学
- 雑誌
- 長崎大学工学部研究報告 (ISSN:02860902)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.64, pp.57-62, 2005-03
In recent years, the small island nick named as 'Gunkanjima' (formal name "Hashima") located in the southwest of the Nagasaki harbor attracted a lot of attention. Historically Gunkanjima, an island rich of coalmine supported modernization of Japan by supplying invaluable energy. However, abrupt shift in energy use during the 1970s forced the closure of the mines in this island on January 15, 1974. Eventually, since almost thirty years this island became an uninhabited island. But still there are many cultural heritages valuable from scientific standpoint left in the island, including the first Reinforced Concrete Apartment Building in Japan. In this paper, we have summarized the results of the interview with the former residents of this island and also the field survey in "Gunkanjima". This investigative study indicated that, the community structures followed by the residents of this island in those days, can be an ideal model to solve the present social problems arising in Japan. The results of the study also revealed the immense importance of Gunkanjima to be preserved as an industrial heritage, symbolizing the industrial growth of Japan. Hence got sufficient potential to be utilized as a scientific research center for the future generation and which in turn would promote revitalization of the surrounding areas.
23 0 0 0 OA 炊飯における温水浸漬と低温浸漬が米の吸水率に与える影響
- 著者
- 坂本 薫 森井 沙衣子 上田 眞理子
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.193-199, 2015 (Released:2015-07-06)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 3
温水浸漬と低温浸漬が米の吸水率に与える影響について,浸漬水中の固形分を考慮して経時的に検討した。5~50°Cの温度で5~240分間米を浸漬し,米の吸水率を測定したところ,温水浸漬と低温浸漬では,吸水曲線が交差する現象が観察され,平衡状態まで吸水させた場合では,温水浸漬よりも低温浸漬の米の吸水率が高かった。浸漬水中の固形分の量を経時的に測定したところ,40°C,50°Cの温水浸漬では固形分は多く浸漬液中に懸濁していた。そこで固形分を加えた補正吸水率を算出したが,吸水曲線が交差する現象が同様に観察され,平衡状態では温水浸漬よりも低温浸漬の米の吸水率が高かった。