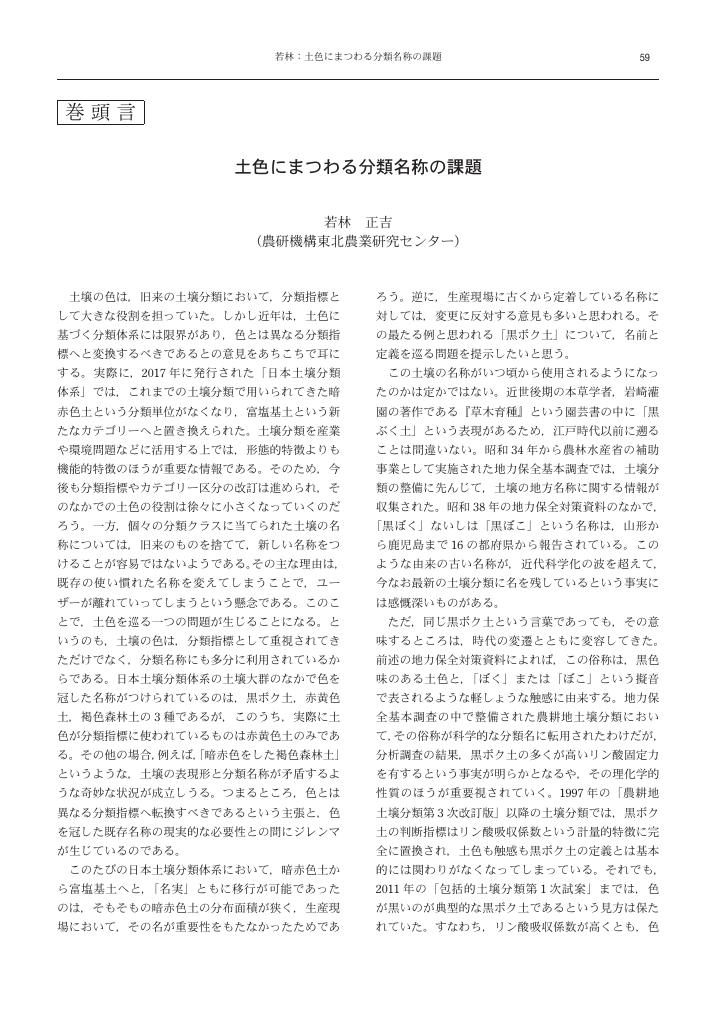- 著者
- 伊谷 充礼 豊福 恒弘 岩井 哲二 林 久美子 山村 理 佐川 淳 市橋 宗篤 大崎 千佐子 前田 弌郎 藤井 輝久
- 出版者
- 社団法人日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科學會雜誌 (ISSN:03895386)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, 1983-04-01
1 0 0 0 食品中酸化防止剤の迅速HPLC法および標準溶液の長期安定性の検討
- 著者
- 見上 葉子 高木 優子 宮川 弘之 山嶋 裕季子 坂牧 成恵 小林 千種
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.12-19, 2022-02-25 (Released:2022-03-10)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 3
食品添加物であるジブチルヒドロキシトルエン(BHT),ブチルヒドロキシアニソール(BHA)およびtert-ブチルヒドロキノン(TBHQ)のHPLC分析条件について検討した.内径2.1 mmのカラムを用い,タイムプログラムを使用し各至適蛍光波長に切り替えることにより,25分間で一斉分析が可能となった.蛍光検出をUV検出と併用することにより選択性が向上し,夾雑ピークの影響を大幅に改善できた.また,ガス供給不足に対応するため,GC-MSによる確認法の代替としてLC-MS/MSによる確認法を作成した.さらに,上記3化合物標準溶液の長期安定性について検討した.その結果,0.1%アスコルビン含有メタノールを用い−20℃の条件で,TBHQは約1年間保存が可能となったが,BHT, BHAは著しく減少する場合があった.BHA, BHT混合標準溶液の場合は,メタノール溶液で4℃,BHA, BHT, TBHQ混合標準溶液は0.1%アスコルビン酸含有メタノール溶液で−20℃としたときいずれも約1年間安定であることを確認した.
It is known that a dolphin swims fast and freely in water. The propulsive performance and the kinetic performance of the dolphin are one of great concern among researchers. We paid attention to the dolphin's tail flukes which has an important role to generate propulsive force. So the experiments on both the propulsive force of the outboard propulsor with the oscillating wing which is similar to the dolphin's tail flukes in shape and the velocity of a small boat equipped with the outboard propulsor were carried out. The propulsive performance of the wing was discussed compared with rectangular wings.
1 0 0 0 ピリドキサール酵素の"同士討ち"を防ぐデアミナーゼRidA
- 著者
- 林 秀行
- 出版者
- 公益社団法人 日本ビタミン学会
- 雑誌
- ビタミン (ISSN:0006386X)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.12, pp.685-690, 2013
1 0 0 0 IR 東日本巨大地震が留学生に与えた影響 : インタビューを通して
本研究は2011年3月11日に起きた東日本巨大地震の留学生への影響を調査したものである。具体的には2011 年3~6月に日本に留学していた(またはしている、しようとしている)学生15人(台湾人13人、韓国と中国大陸人各々1人)に対するインタビューをまとめた。また、直接インタビューしたわけではないが、メール等の形で、地震当時日本にいた引率の先生、そして台湾の日本語学科を卒業後ワーキング・ホリデーで日本に行っている人、あわせて4人(いずれも台湾人)の意見も得た。基本的には日本に留学までした学生はもともと日本のことがかなり好きで、今回の地震が発生する遥か前より留学しようと考えていた者が多い。多くの留学生たちは、何もかもよく見えていた日本で今回起きた地震を、最初は驚き、痛々しく思ったが、心のどこかに蓄えていた日本に対する信頼で、敢えて家族の反対を押し切り自分の夢を追うように留学に踏み切った。それに対して、日本に不信感を抱いた人ももちろんいるが、少数である。
1 0 0 0 OA 道〓の戒律観と大仏建立
- 著者
- 直林 不退
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.538-541, 2002-03-20 (Released:2010-03-09)
- 著者
- 若林 真希 ワカバヤシ マキ Maki Wakabayashi
- 雑誌
- Rikkyo ESD journal
- 巻号頁・発行日
- no.3, 2019-03-01
- 著者
- 川田 綾子 宮腰 由紀子 藤井 宝恵 小林 敏生 松川 寛二 高瀬 美由紀 寺岡 幸子
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護研究学会
- 雑誌
- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.3, pp.3_194, 2009-07-03 (Released:2019-09-30)
1 0 0 0 OA 土色にまつわる分類名称の課題
- 著者
- 若林 正吉
- 出版者
- 日本ペドロジー学会
- 雑誌
- ペドロジスト (ISSN:00314064)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.59-60, 2019 (Released:2020-12-31)
1 0 0 0 機能的バランスからみた小脳性運動失調評価スケールの妥当性について
- 著者
- 小澤 純一 中村 友美 塚谷 桐子 山田 汐里 堀 裕一 小林 義文 高島 浩昭 竹内 ゆかり 宮崎 昌代 田中 和徳 三村 夏代 恩田 めぐみ 杉下 泰明
- 出版者
- 東海北陸理学療法学術大会
- 雑誌
- 東海北陸理学療法学術大会誌
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.159, 2011
【目的】<BR> 脳血管障害,腫瘍,変性疾患などによる小脳障害患者は,その病巣部位により上下肢運動の協調性の欠如,立位・座位・起立歩行障害,姿勢調整障害,眼球運動障害,構音障害などがみられる.近年,新しい小脳性運動失調の評価スケールとしてSchmitz-Hubschらにより,Scale for the Assessment and Rating of Ataxia(以下,SARA)が提唱された.その信頼性について,International Cooperative Ataxia Rating Scale(以下,ICARS)やBarthel index(以下,BI)等との有意な相関が報告されている.<BR> 日本においても,厚生労働省難治性疾患克服研究事業「運動失調に関する調査研究班」において日本語版SARAが作成された.SARAは全8項目(歩行,立位,坐位,言語障害,指追い試験,鼻指試験,手の回内回外運動,踵すね試験)から構成された簡便な評価スケールであり,評価者内,評価者間共に高い信頼性や内的整合性が報告されている.<BR> 今回,SARAと歩行に関連した機能的バランスとの関連性について検証し,理学療法評価法としての信頼性・妥当性について検討した.<BR>【方法】<BR> 対象は,平成21年4月から平成22年3月の間に当院に入院し,理学療法を実施した小脳性運動失調の患者である.認知症および高次機能障害などにより,検査実施に支障のある患者は除外した.また,対象者に対しては,事前に目的や方法等の研究内容について説明し,同意を得た上で行った.<BR> カルテより基本情報(年齢,性別,疾患名等),小脳性運動失調の重症度評価スケールとしてSARAを使用して評価を行った.あわせて,ADL評価としてBI,歩行関連の機能的バランステストとして10m最大歩行速度(以下,10m歩行),Timed up and go test(以下TUGT)と重心動揺解析システムG‐6100(アニマ社製)を使用してつま先接地足踏みテスト(Toe-touch gait test,以下足踏みテスト)を実施した.<BR> 統計処理は,SPSSVer.15.0を使用し,SARAと各評価項目との相関についてはスピアマン順位相関係数により検討した.統計学的有意水準は5%とした.<BR>【結果】<BR> 対象者数は,30名(平均年齢62.7±12.5歳,男性26名,女性4名)であり,小脳梗塞28名,小脳出血2名であった.発症より検査日までの経過期間は28.77 ±27.10日であった.SARAスコアは6.53±2.43点 ,BIは86.83±10.95点,TUGT15.41±4.36sec,10m歩行8.58±2.06secであった.足踏みテストは,総軌跡長:276.43±78.23cm,単位時間軌跡長:27.66±7.84cm/sec,単位面積軌跡長:4.66±1.37cm,外周面積:66.47±31.13cm)cm<SUP>2</SUP>であった.<BR> SARAスコアと各変数間の相関はBIでは弱い相関(r=-0.42)であったが,TUGT(r=0.53)と10m歩行(r=0.57)では比較的強い相関であった.また,足踏みテストの各指標(総軌跡長:r=‐0.26,単位時間軌跡長:r=‐0.25,単位面積軌跡長:r=‐0.1,外周面積:r=‐0.1)との間では,有意な相関は認められなかった.<BR>【考察】<BR> 小脳性運動失調の総合的な評価法として,SARAは半定量的な評価が可能であり,重症度や治療効果の判定に有用なツールである.評価手法も,一般的な神経学的評価手技を用いているため,同一評価者内および評価者間での評価のばらつきが少ないことが報告されている.また,ICARSの評価項目が19項目であるのと比較するとSARAは8項目と少なく,臨床的にも簡便に使用可能な評価尺度といえる.今回,SARAと歩行に関連した機能的バランスとの間で比較的強い相関が認められた事から,基準関連妥当性の一部が確認され,理学療法評価尺度として有用であると考えられた.しかし,BIや足踏みテストについては低い相関しか確認できなかった.BIに関しては,今回の対照群がある程度の立位・歩行が可能な比較的重症度の軽い対象者を多く含んでいたためとも考えられる.足踏みテストについては,各対象者の歩行の際の姿勢調整機構の特徴を足底圧中心のみの評価ではとらえきれないためと考えられた.<BR>【まとめ】<BR> 本研究において,歩行に関連した機能的バランスとSARAとの間で,比較的強い相関が一部確認されたことから,小脳性運動失調患者の重症度把握や理学療法の治療効果の判定等の評価手法として有用であることが示唆された.
1 0 0 0 OA 都心地域からの山なみの見え方についての研究 京都市域の例
- 著者
- 中林 浩
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.613-618, 1990-10-25 (Released:2020-07-01)
THE CITY OF KYOTO HAS DEVELOPED WITHIN A BASIN. SO WE CAN SEE MOUNTAINS EASTWARD, NORTHWARD, AND WESTWARD THROUGH A SERIES OF TRADITIONAL WOODEN HOUSES. THIS KIND OF TOWNSCAPE WHICH CHARACTERIZE DOWNTOWN KYOTO HAS AMUSED THE CITIZENS IN THEIR DAILY LIFE. IT IS FOUND THAT WE CAN GET VIEWS OF MOUNTAINS AT A SOLID ANGLE OF 0.5 TO 3.0 UNITS FROM ORDINARY POINTS IN DOWNTOWN KYOTO. ( 1 UNIT IS DEFINED AS A SOLID ANGLE FORMED BY VERTICAL 1° AND HORIZONTAL 1°.) VIEWS OF MOUNTAINS, PARTICULARLY FROM SMALL STREETS , ARE INTERRUPTED BY TALL BUILDINGS RECENTLY CONSTRUCTED.
1 0 0 0 わが国の宝石学のあゆみ
- 著者
- 林 政彦
- 出版者
- 宝石学会(日本)
- 雑誌
- 宝石学会誌 (ISSN:03855090)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.31-35, 2008
- 参考文献数
- 15
The history of the gemmology in Japan can roughly be divided into three agesas follows. 1) The 1st age: the Tsunashiro Wada (1856-1920) and Satoshi Suzuki hadtaken an active part around 1900. T. Wada wrote the "Hougyokushi (寶玉試)" in 1889. It was the first textbook of the gemmology in Japan. 2) The 2nd age: the gemmology was made well known by Takeo Kume (1887-1958) and so on in around 1960. 3) The 3rd (present) age: after the gemmological society of Japan (GSJ) wasinitiated in 1974. It is common knowledge fact that GSJ contributed to the improvement of thegemology in the world.
- 著者
- 林 政彦
- 出版者
- 宝石学会(日本)
- 雑誌
- 宝石学会誌 (ISSN:03855090)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.64-65, 2004
1 0 0 0 わが国の宝石学のはじまりについて
- 著者
- 林 政彦
- 出版者
- 宝石学会(日本)
- 雑誌
- 宝石学会(日本)講演会要旨
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.6-7, 2003
宝石学会(日本)創立の際の趣意書に、「久米武夫氏の初期的な研究がありながら、日本には宝石学が在存しないという比判が外国の宝石学者からしばしば寄せられたものです。」(1)と書かれているように、宝石学会の設立は当時の時代の要請であった。今からちょうど30年前に発起人たちが集まり、その翌年に宝石学会(日本)が創設され、宝石学(Gemmology)の発展に貢献してきた。その結果、現在のわが国の宝石学のレベルは他の国に肩を並べるようになった。特に、さまざまな最新鋭の分析機器が宝石の鑑別にも利用され、最新知見が得られた結果、宝石学の発展にも寄与した(2)。今回、わが国に宝石学が導入されてきた時期について調べてみたので報告する。
1 0 0 0 OA カレーの調理過程におけるラジカル捕捉活性の変化
- 著者
- 高村 仁知 山口 智子 林 恵理奈 藤本 さつき 的場 輝佳
- 出版者
- 社団法人日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.11, pp.1127-1132, 1999-11-15
- 被引用文献数
- 11
The change in radical-scavenging activity while cooking curry made from spices, vegetables, and meat was analyzed by the 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl-HPLC method. Fifteen kinds of spices generally used in curry all possessed radical-scavenging activity. In particular, the activity of clove, allspice, and cinnamon was extremely high and comparable with that of vegetables. After heating, the radical-scavenging activity of the combination of vegetables and meat increased, while that of mixed spices decreased. Vegetables as well as spices contributed the radical-scavenging activity of curry. In the present research, one serving of curry and rice contained 363 μmol Trolox eq of radical-scavenging activity. The spices contributed approximately 45% of the total radical-scavenging activity of curry and rice.
1 0 0 0 OA ミナミハンドウイルカ (Tursiops aduncus) における餌の消化管通過速度
- 著者
- 高橋 力也 小林 希実 比嘉 克 酒井 麻衣
- 出版者
- Japanese Society of Zoo and Wildlife Medicine
- 雑誌
- 日本野生動物医学会誌 (ISSN:13426133)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.4, pp.143-146, 2021-12-24 (Released:2022-02-28)
- 参考文献数
- 10
本研究は,ミナミハンドウイルカ(Tursiops aduncus) における生理学的知見の蓄積を目的として,餌の消化管通過速度を測定する実験を行った。実験は飼育下のミナミハンドウイルカのオス1頭を対象とし,3日間1日1回行われた。赤色色素を粉のままゼラチン製の薬用カプセルに梱包し,餌のカラフトシシャモの体内に挿入し給餌した。着色餌の給餌後,水中観察窓から連続観察を行った。着色餌の給餌から,初めて糞に赤色が確認されるまでの期間をIPT (Initial Passage Time) と定義した。着色糞は3日間全ての実験で確認された。着色糞が最初に観察されるまでの経過時間(IPT) は平均254 ± 20.4 分(n=3)であった。先行研究における同属のハンドウイルカの平均IPTと比べ近い値となった。本研究により,ミナミハンドウイルカは摂餌から最短で4時間から6時間程度で排泄し,加えて餌が消化管内に20時間以上留まる可能性があることが通常色の糞の観察から示唆された。
1 0 0 0 OA ハロラクトン化反応および関連反応を用いた天然物合成
- 著者
- 小林 進
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.8, pp.745-754, 1983-08-01 (Released:2009-11-13)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 3 4
The reaction of γ, δ- or δ, ε-unsaturated carboxylic acid with halogen afford halolactone in high yield. This halolactonization reaction generally proceeds in a high stereo- and regiospecific manner. This makes the reaction one of the most important procedures for the functionalization of the carbon-carbon double bond.This review provides illustrative examples of the synthesis of natural products where halolactonization reaction plays an important role.Some related reactions are also described.
1 0 0 0 キルギス 誘拐婚の現実
- 著者
- 林 典子
- 出版者
- 日経ナショナルジオグラフィック社
- 雑誌
- National geographic (ISSN:13408399)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.7, pp.110-127,158, 2013-07
1 0 0 0 耐酸化コーティング : 化学ポテンシャルと相互拡散の利用
- 著者
- 林 重成 成田 敏夫
- 出版者
- 公益社団法人 腐食防食学会
- 雑誌
- 材料と環境 : zairyo-to-kankyo (ISSN:09170480)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.11, pp.476-482, 2006-11-15
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 2
近年の熱交換システムでは, 熱効率向上を目的とした運転温度の上昇が求められており, 耐熱材料にはより高温での使用が要求されている。高温対応型の耐熱材料設計の自由度を上げるため, 合金上への耐酸化コーティングの適用は必要不可避となっており, コーティングの重要性はますます増加している。本解説では, 著者らの最近の研究成果を紹介しながら, 次世代の耐酸化コーティングについて議論する。
1 0 0 0 OA レジスタンストレーニングと有酸素性トレーニングを併用した際のトレーニング効果について
- 著者
- 井上 佳和 宮本 謙三 宅間 豊 宮本 祥子 竹林 秀晃 岡部 孝生
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.30 Suppl. No.2 (第38回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.55, 2003 (Released:2004-03-19)
【はじめに】 長年,健康づくりのための運動指針の中で奨励される運動は有酸素性トレーニングであったが,ここ数年,レジスタンストレーニングとの併用が奨励されるようになった。それぞれのトレーニングの方法論や効果についての報告は多い。しかしエネルギー供給系の異なる2種の運動を併用した際のトレーニング効果についての報告は少なく,明確な知見は得られていない。そこで本研究では有酸素性トレーニング単独実施時とレジスタンストレーニングを併用して実施した際のトレーニング効果について検討を行なった。【対象と方法】 対象は運動習慣を持たない成人男性17名とした。この対象者を有酸素性トレーニングのみを実施する群(AT群),レジスタンストレーニングを併用して実施する群(ART群),トレーニングを実施しない群(C群)に分けAT群とART群に対しては週3回,5週間のトレーニングを実施した。内容は有酸素性トレーニングとして50%V(dot)O2max負荷量での自転車エルゴメーター駆動20分,レジスタンストレーニングとして100deg/secの等速性膝伸展運動30回であった。測定項目はPeak V(dot)O2,膝伸展筋力の2項目とし,各群のトレーニング前後の値をt検定にかけることでトレーニングによる効果を判定した。有意水準は5%とした。【結果】 AT群では2項目共に増加したが,有意な増加が認められたのは膝伸展筋力のみであった。ART群ではPeak V(dot)O2,膝伸展筋力共に有意な増加が認められた。C群では,すべてに有意差が認められなかった。【考察】 レジスタンストレーニングによるPeak V(dot)O2の増加は,筋の酸素利用能力の改善に起因すると考えられた。筋の酸素利用能力の改善は,酸素拡散能力と酸素消費能力により規定されるがART群では有酸素性トレーニングによる筋毛細血管の発達が酸素拡散能力を向上させ,レジスタンストレーニングによる速筋内でのFOGへのサブタイプの移行が,ミトコンドリア量と酸化酵素活性を高め,酸素消費能力を向上させたと推察された。今回の結果をふまえると,有酸素的作業能の代表的指標であるPeak V(dot)O2を増加させるためには,有酸素性トレーニングのみならず,レジスタンストレーニングを併せて実施する方が,より大きな効果が期待できる可能性が示唆された。膝伸展筋力については,対象を日常運動習慣を持たない一般成人とした場合,自転車駆動などの運動によっても改善を認めることが明らかとなった。しかしペダル負荷量から考えると,活動が高まる筋線維は遅筋が中心になると考えられることから,速筋線維の活動を高めるレジスタンス運動を加えることで,バランスのとれた筋機能への刺激となり得ると考えられた。